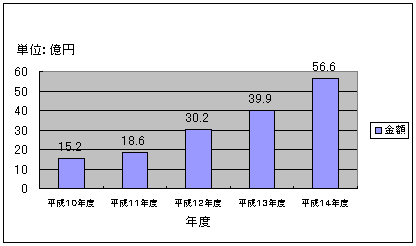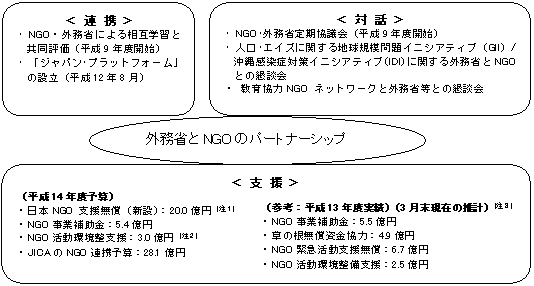第3章 NGO事業補助金制度の概要
3-1 NGO事業補助金制度の歴史と現状NGO事業補助金制度は、ODA事業の一環として、日本のNGOによる途上国での開発協力事業に対する公的資金協力支援として、1989年度に草の根無償資金協力とともに創設された。その背景としては、外務省は、「日本のNGOは、開発途上国に対し開発協力を積極的に推進する十分な意欲を持ちながら、その活動の規模・内容は、欧米諸国の主要NGOに比べ、概して限られたものにならざるを得ない状況にある」「一方、日本のNGOに対する開発途上国からの協力要請は年々増加しており、NGOから、ODAの活用に対する強い要望が出されてきた」と、ホームページ1で説明している。また、他の分析では、創設された背景を、「NGO側からの外務省や政府に対しての財政支援を求める要望2や組織能力的にも自らの組織を向上させたいという要望が強く」、また、「外務省側にも日本を世界一の援助国に押し上げる戦略を進めると同時に、トップに立った後も継続してODAを円滑に実施していくためには、国民の広い支持が絶対必須条件であり、そのために従来の官ベースのODAから民間各層の広い支援を受けた国民参加型ODAへの転換の必要性が高まった」と指摘している3。
NGO団体の数は、1989年末に186団体であったが、1990年代半ばには350団体と約2倍に増加し4、それに対応して、以下の図3-1に示す通り様々なNGO活動への支援策が拡充されてきた。
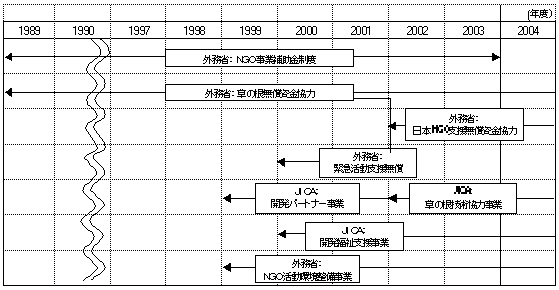
政府側からも政府レベルでの協力においてNGOを活用し、効果的な協力達成のために、NGOの組織強化が試みられた。1990年代後半になると、支援策が内容的に豊富になり、NGOの組織能力強化支援の傾向が強まり、JICAにより「開発パートナー事業(委託事業)」および「開発福祉支援事業」5が開始された。これは、「NGOの組織能力を強化し、積極的に政府のパートナーとして活用しよう」という政府側の意向と「組織能力強化を行いたい」というNGO自身からの意向とが合致した事の現れである。外務省もNGOの活動環境整備を目的として、1999年には「NGO相談員制度」、「NGO専門調査員制度」、「分野別NGO研究会」等を開始した。このようにNGO支援制度は質的に充実されてきた。
同時にNGO支援額においても年々増加し、量的拡充も行われた。2002年度には、支援額は1998年度に比べ3.7倍に上っている(図3-2参照)。近年は、緊急人道災害支援におけるNGOの役割の重要性に注目し、この活動への支援が大幅に拡大している(現在利用可能な外務省、JICAを中心とするNGO支援制度については別添1参照)。 以上のように、NGO体制強化支援の動きが進められてきており、本制度はその一翼を担ってきたといえる。
| 図3-2:我が国NGOに対する支援策(外務省関連)の推移
|
現在も、NGO事業補助金制度はODA事業の一部で、NGOを通じて開発事業を行うものとして、外務省とNGOとのパートナーシップの一つとして位置づけられている。ODAにおける外務省とNGOの関係強化の連携の概要は以下の図3-3の通りであり、(1)「連携」:ODAの政策立案や事業の実施にあたりNGOの人材やノウハウを活用すること、(2)「支援」:NGOによる国際協力活動への資金協力を中心とするもの、(3)「対話」:これらを充実させて行くため不可欠なもの、の3つを柱としている。NGO事業補助金制度は、平成14年度は、年5.4億円の予算で、NGO支援を行うための重要な施策の一つとして位置づけられている。
| 図3-3:外務省とNGOのパートナーシップにおける主な取り組み
|
次に、NGO事業補助金制度の内容については、(1)開発協力事業(1989年度より)、(2)国際ボランティア補償支援制度(1994年度より)、(3)NGO海外研修支援制度(1999年度より)の3つに分類される。各制度の概要は別添1の通りである。本調査の対象は、開発協力事業に限ることとする。
| 開発協力事業とは: 医療、農漁村開発、人材育成など一定分野で本邦NGOが実施する開発協力活動に対し、施設建設費、専門家人件費及び専門家等派遣旅費(あるいは派遣旅費)、資機材設備費など定められた経費について一定割合を補助する制度である。対象となる国は、原則として世銀ガイドラインによるIDA(国際開発協会)適格の所得水準(平成14年度においては2000年の国民一人あたりGNPが1,445ドル以下)の途上国である。対象となる事業は、農漁村開発、人材育成、女性自立支援、保健衛生、医療、地域産業向上、生活環境、環境保全、民間援助物資輸送、地域総合振興、事業促進支援制度である。金額については総事業費の一部(1件当たりの総事業費の2分の1以下、かつ上限1,000万円)を補助することとなっている。 |
NGO事業補助金制度は、NGO関係者の要望や新たなニーズに応える形で、内容的にも、メニュー的にも拡充が図られてきた。例えば、開発協力事業支援の事業内容についても、1989年度の制度創設時には農漁村開発事業などの6つの対象事業分野で始まったが、1994年度には開発協力適正技術移転・普及事業(但し、2000年度に廃止)が加わり、また1995年度には女性自立支援事業が、1996年度には地域総合振興事業が新たに対象事業分野に追加され、拡充が行われた。また、2001年度からは、事業促進支援制度(NGOのキャパシティービルディングを目的とし、NGOの開発協力事業の案件の発掘形成やプロジェクトの評価支援等のための補助制度)も設けられた。また、制度のメニューに関しても、1994年には、国際ボランティア補償支援制度が創設され、1999年度にはNGO海外研修支援制度が創設され、拡充が行われた。
開発協力事業の補助金交付額の実績(予算金額ベース)であるが、1989年度予算1億1千万円からスタートし、1997年度には12億円とピークに達した。補助対象団体も1989年度の15団体23事業であったが、1997年度には116団体224事業にまで拡大した。1997年以降、政府の補助金削減の影響を受け、開発協力事業は、予算規模および採択件数ともに減少をみせた6。1999年度には9億7,600万円、2000年度は6億8400万円(対前年度比マイナス30%)86団体149事業となっている(表3-1参照)。分野的には、医療事業の比率が一貫して高く、毎年3割近くを占めている。1996年度からは対象分野に地域総合振興事業が加わり、医療分野に次いでこの分野の割合が高い。また、日本のNGOの活動地域としてアジアが多いのに対応してか、地理的にはアジアが最も多く7割を占める。
| NGO事業補助金制度 | |||||||||
| (1)開発協力事業 | (2)国際ボランティア補償支援制度 | (3)NGO海外研修支援制度 | |||||||
| 交付 事業数 |
交付 団体数 |
予算額 (千円) |
交付 件数 |
交付 団体数 |
予算額 (千円) |
交付 件数 |
交付 団体数 |
予算額 (千円) |
|
| 1989年度(H1) | 23 | 15 | 110,000 | ||||||
| 1990年度(H2) | 36 | 16 | 220,000 | ||||||
| 1991年度(H3) | 47 | 24 | 280,000 | ||||||
| 1992年度(H4) | 53 | 30 | 340,000 | ||||||
| 1993年度(H5) | 75 | 31 | 340,000 | ||||||
| 1994年度(H6) | 92 | 49 | 540,000 | 15 | 12 | 4,077 | |||
| 1995年度(H7) | 137 | 84 | 760,000 | 14 | 12 | 6,128 | |||
| 1996年度(H8) | 215 | 132 | 1,000,000 | 16 | 14 | 7,830 | |||
| 1997年度(H9) | 224 | 116 | 1,200,000 | 6 | 6 | 2,000 | |||
| 1998年度(H10) | 185 | 111 | 1,151,000 | 5 | 5 | 2,111 | |||
| 1999年度(H11) | 154 | 92 | 976,000 | 2 | 2 | 1,827 | 4 | 4 | 4,089 |
| 2000年度(H12) | 149 | 86 | 684,000 | 10 | 10 | 4,415 | 4 | 4 | 4,425 |
| 合計 | 1,390 | 786 | 7,601,000 | 61 | 68 | 28,388 | 8 | 8 | 8,514 |
現在、日本全国には約400以上のNGOが活動しているといわれるが、NGO事業補助金制度は年間最高では132団体、この3年間は約100前後のNGOに対して、補助金の交付を行ってきた。累計では、平成12年までに786団体、1,390事業に対し、補助金が交付されてきた(表3-1参照)。
開発協力事業の申請件数と交付件数の実態に関しては、平成12年度は申請155件に対して、交付149事業、平成13年度は、申請129件に対して、交付118件であり、申請に対して90%以上の割合で補助金が交付されている。
| 図3-4:NGO事業補助金の推移 |
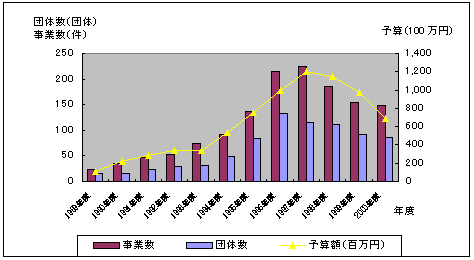 |
| (出所)外務省ホームページより作成。 |
平成12年度の事業補助金制度の交付先は、86団体149事業であった(別添3参照)。参考までに、交付金額の多かったNGO団体の上位10団体は、次の通り。(1)(社)シャンティ国際ボランティア会、(2)日本口唇口蓋裂協会、(3)AMDA、(4)(特非)ワールド・ビジョン・ジャパン、(5)(特非)プロジェクトHOPEジャパン、(6)(特非)JEN、(7)(特非)日本国際ボランティアセンター、(8)(財)オイスカ、(9)砂漠植林ボランティア協会、(10)(特非)地球ボランティア協会、となっている(別添4参照)。交付実績額では全体の平均で、1事業に対して394万円、1団体に対しては649万円の補助金が支払われたことになる(別添3及び4参照)。
交付先NGOの財政基盤は、約15億円の財政規模を持つ、ワールド・ビジョン・ジャパン、約6億円のシャンティ国際ボランティア会から、1,000万円代のNGOと多様であった。また、いずれの団体も1年だけでなく継続してNGO事業補助金の交付を受け、毎年NGO団体の予算に対して、一定の割合をNGO事業補助金の金額に依存している。
このように、NGO事業補助金制度は多くのNGOに利用されているが、既存の諸制度の見直しや整理の一環として2003年度を以って終了予定である。NGO事業補助金制度が終了した後、NGO側にとって、替わりとして最も利用可能な外務省のNGO支援制度は、日本NGO支援無償資金協力7といわれている。(NGO事業補助金制度と日本NGO支援無償資金協力の比較は別添3参照)。
1 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shimin/oda_ngo/shien/hojyokin.html
2 1989年以前、財団法人の資格を持つごく限られた団体のみが利用できたCo-Financing制度(財政支援)を、財団法人格を持たないが成果を出している団体にも広げてほしいというNGO側からの要望があった(杉下恒夫(2000年))。
3 杉下恒夫(2000年)
4 国際協力NGOセンター(JANIC)の調査によると、1980年時点で約50団体だったのが、10年足らずで200団体を越えたとのこと。
5 分野:保健衛生改善、高齢者・障害者・児童等支援、女性自立支援及び地場産業振興支援等。
6 その一方で、「草の根無償資金協力」は1989年度予算3億円から1995年の30億円、1998年度の57億円、1999年度の70億円とその予算規模を急激に拡大している。それに伴い承認件数も1989年度の1,064件から1999年度には約13,000件にまで達している。
7 2002年6月28日、日本NGO支援無償資金協力が発表され、即日受付開始された。この制度は、「草の根無償資金協力」のうち、日本のNGOを対象としてきたものと、日本のNGOに対して行われてきた「NGO緊急活動支援無償」を統合・拡充した内容で、平成14年度の予算額は20億円である。本制度は、(1)開発協力事業支援、(2)セクター連携支援、(3)NGO緊急人道支援無償(旧称「NGO緊急活動支援無償」)の3つから成る。(1)は、「草の根無償資金協力」のうち、日本のNGOを対象として創設されたが、草の根レベルに直接裨益する経済・社会開発プロジェクト(施設建設、資材供与、啓蒙活動など)を対象としている。これは、従来の草の根無償資金協力はハードが中心であったのだが、資機材供与などのハードを中心にすえつつ、研修・専門家派遣などのソフト経費の充実、担当スタッフ人件費等の間接経費を認めるものである。(2)は、日本のNGOが他のNGO(当該国・地域のローカルNGOを除く)や研究機関と連携し、コンソーシアムを組んで、開発協力プロジェクトを実施するものである。主たる契約者は日本のNGOとなり、プロジェクトの実施にあたり、全責任を負うものである。(3)は、緊急人道支援活動に従事するNGOが、より迅速、かつ機動的に活動を立ち上げられるよう支援するためのものである。
また、制度の特徴としては、(1)支援を受けるNGOの法人格取得(2003年度より)、(2)外部専門家による事前審査の実施、(3)適正な会計処理の確保、(4)全採択案件の最終報告書の公表、が挙げられ、NGOの透明性、健全性、説明責任の向上をNGO側に強く要求しているといわれている。