南南協力支援評価調査
第3章 評価結果3.3 効果の検証
本節では、日本の南南協力支援政策の効果について検証する。
3.3.1 政策目標の達成度合い
3.1 理論の節で述べたように、南南協力支援政策は、「(わが国)政府開発援助の効果的実施」を目標として行なわれている。その達成度合いを、ODA中期政策で挙げられている以下の4つの観点を指標として検証した。
(1)新興援助国の育成による援助資源の拡大
(2)域内又は地域間協力の推進
(3)適正技術の移転
(4)ODA経費の削減
<新興援助国の育成による援助資源の拡大>
新興援助国の育成は、南南協力支援の実施による協力実施国政府機関、研修実施機関、第三国専門家および第三国研修の講師の能力の向上度合いから、検証することとした。
協力実施国政府機関に対する効果
「協力実施国政府機関の援助実施能力は、わが国の南南協力支援により向上したか」という観点から、エジプトについては、EFTCA、チュニジアについてはATCTに対して調査を行なった。
日本の南南協力支援案件は、一般的にプロジェクトサイクルマネージメント(PCM)17の考え方に基づき運営、管理されている。エジプトにおける調査では、わが国のこのような運営、管理方法が協力実施国政府機関の参考となり、ひいては援助実施能力の向上につながったか、という観点から検証した。調査の結果、EFTCAは、日本の南南協力支援案件については、PCMの考え方に基づいて案件管理を行なっていたが、この考え方は、日本の南南協力支援案件に限って適用しており、EFTCAが独自に実施している南南協力案件については、従来通りの方法で運営、管理していることが確認された。EFTCA は、アフリカ諸国に対する南南協力の歴史が長く、わが国の南南協力支援を受ける前から年間数千人もの専門家を海外に派遣し、成果を上げていることから、仮に、わが国の政策支援が援助実施能力の向上に効果を与えたとしても、それは極めて限定されたものに過ぎないと想定される。
実施機関に対する効果
第三国研修実施機関へのヒアリング調査から、日本の南南協力支援案件の実施を通して研修事業の管理能力の向上や設備・施設の向上が図られる等のプラスの効果に繋がっていることが確認された。日本の南南協力支援の実施において義務付けとなっているコースレポートの作成は、実施機関の案件管理のためのツールとして役立っている他、担当官によっては、南南協力支援案件以外でも日本の案件管理方法を適用していることも確認された。
協力実施国における講師及び専門家に対する効果
アンケート調査によれば、第三国研修講師および第三国専門家(29名)全員が、わが国の南南協力支援政策に関与したことが彼等自身の能力の向上に役立ったと回答している。その理由をグループディスカッションおよびヒアリング調査で確認したところ、エジプトにおける第三国研修においては、日本人講師18からエジプト人講師に対して技術、知識の移転が行われていることがわかった。ただし、これは全ての研修において確認されたものではなく、傾向としては、建設機材や溶接技術等、技術革新が目覚ましく、日本の最新技術がエジプトにおいて現在も求められている分野の研修に限られている。医療分野や農業分野のように、分野の中で専門が更に細分化されている分野では、日本人講師との専門的知見における接点が限られているため、日本人講師の参画による影響は殆どないという意見が多かった。
また、講師および専門家は、アフリカ諸国からの研修生との交流を通じて、適正技術や地域特有の技術に関する知識を向上させていることも確認された。
さらに、エジプトの例からは、第三国研修の講師を務めたことにより、英語の能力が向上した、また、研修で蓄積された教材を活用して国際的な学会において発表できるようになった等の講師の能力においてプラスの効果が確認された。
<地域間協力の推進>
地域間協力の推進度合いを協力実施国と協力受益国との人的交流の発展の観点から検証した。
エジプトについても図3-9に示す通り、1981年から2002年までにアフリカ諸国より5,930名の研修生を受け入れている他、エジプトからアフリカ諸国に対して7,627名の専門家を派遣していること、エジプトの協力により便益を受けたアフリカ諸国の数が着実に増えていることが確認された。
図3-9 アフリカ諸国からのエジプトにおける研修受講者数及びアフリカ諸国への
エジプト人専門家派遣数(1981年~2002年)
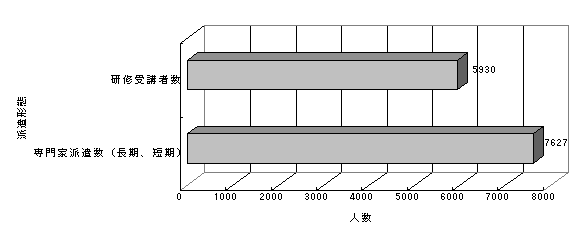
出所:EFTCAの広報資料より作成
エジプト人専門家派遣数(1981年~2002年)
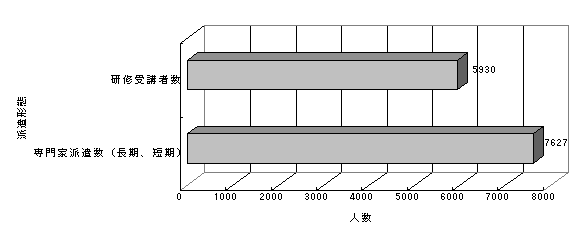
出所:EFTCAの広報資料より作成
図3-10 エジプトの協力により便益を受けたアフリカ諸国の数 (1981-2002)
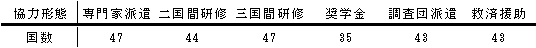
出所:EFTCAの広報資料より作成
出所:EFTCAの広報資料より作成
また、エジプトでは、1981年から2002年までにアフリカ諸国と61件の二国間合意及び31件の三ヶ国間合意がなされた。エジプト外務省によれば、過去5年間のみでも、約30件の貿易、外交に関する署名がアフリカ諸国との間で行なわれている。以上の結果から、日本の南南協力支援政策は、人的資源の交流や外交関係において間接的にプラスの効果を与えていると判断できる。
図3-11 エジプトのアフリカ諸国との技術協力に関する合意(1981-2002)
出所:EFTCAの広報資料より作成
| 二カ国間合意 | 三カ国間合意 |
| 61 | 31 |
チュニジアについてみると、以下の図3-12が示すとおり、チュニジアの国外への専門家派遣人数は増加傾向にあり、その内、アフリカ諸国に対する派遣数についてみると、1998年は37名であったが1999年には約2倍の81名と急増していることがわかる。1999年は、チュニジアがわが国のパートナーシップ・プログラムに署名した年であることから、日本の南南協力支援はチュニジアとアフリカ諸国との人的交流の推進に間接的ではあるが、プラスの効果を与えていると想定される。
図3-12アフリカ諸国へのチュニジア人専門家派遣数の推移
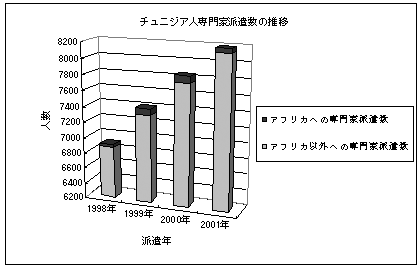
出所:ATCT. Experience Tunisienne en Matiere de Cooperation Technique
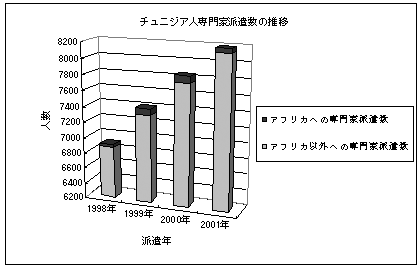
| 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | |
| アフリカ以外への専門家派遣数 | 6871 | 7325 | 7760 | 8141 |
| アフリカへの専門家派遣数 | 37 | 81 | 85 | 54 |
<適正技術の移転>
「自然条件や言語等の類似した地域からの技術移転は、わが国が行なう技術移転より適切である」という観点から、その有効性について、セネガルを事例に協力受益国の立場から検証した。
エジプト及びチュニジアにおいて開催された第三国研修について、セネガルより参加した研修生に対してアンケート調査を行なったところ19、8名中7名の研修生が研修で習得した技術は、彼等の仕事に「非常に役立った」又は「まあまあ役立った」と回答している(図3-13)。
図3-13 第三国研修で習得した技術の母国での貢献度
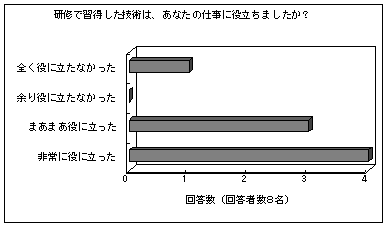
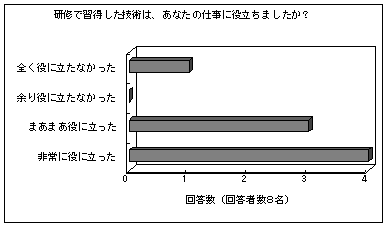
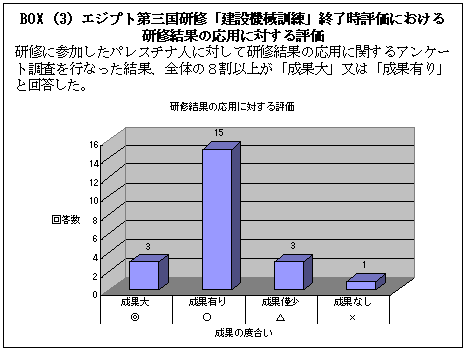
また、研修が分かり易いと感じた理由について、「教材が良かったから」との回答が最も多く、「講師が同じ文化圏の人であったから」や「言語が母国語であるから」という理由を挙げた人は少なかった(図3-14)。しかしながら、アンケート調査の結果に反して、グループディスカッションにおいては、エジプトにおいて第三国研修に参加した研修生より、「講師の英語の能力が低すぎて講議が理解できなかった」、「全ての教材が英語で作成されていたため、理解に苦労した」等、言語に関連した様々な問題点が多く指摘された。研修受講者の中には、協力実施国の大使館がフランス語に訳したGIの翻訳の質が悪く、当人のニーズに全く合わない研修を受講させられた者も見受けられた。
図3-14 研修が分かりやすいと感じた理由
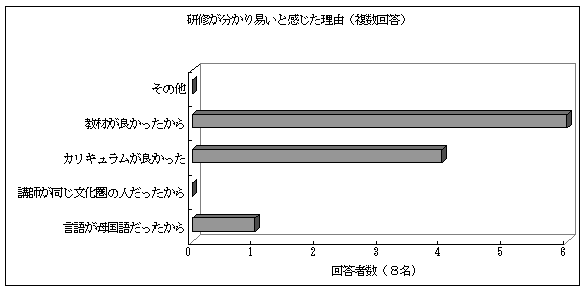
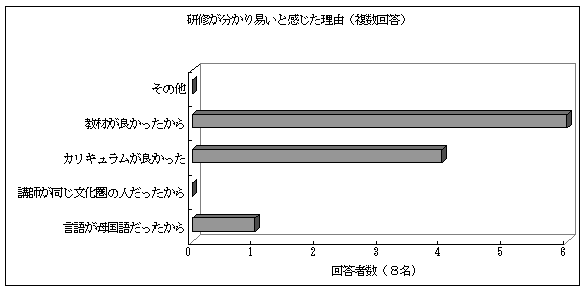
さらに、言語や文化背景が類似していることの影響の度合いは、案件の内容により異なることも確認された。例えば、リプロダクティブヘルスの研修に参加した研修生は、溶接技術や建設機械等の研修に参加した研修生に比べて、研修実施国との言語、文化の共通性を重視していた。その理由として、リプロダクティブヘルスの研修においては、イスラム圏において一般的にタブーとされているこの分野への対応策に関する講義、意見交換等が中心となる場合が多く、協力実施国と協力受益国の文化、言語においての共通性が研修の効果に大きく影響すること等が確認された。
一方、溶接技術や建設機械等の研修は、その大半が機械を使った実地研修であるため、言語の違いは殆ど関係がないことがわかった。このような分野で効果を上げるためには、協力実施国の所有する機材、施設の状況が協力受益国の適用範囲において進んでいることが重要であることがグループディスカッションの結果より分かった。
さらに、農業分野では、自然環境条件の共通性が適正技術の移転において不可欠であることが研修生の発言及び日本人専門家とのヒアリング調査により確認された。

<ODA経費の削減>
南南協力支援政策の下で行なわれている第三国研修および第三国専門家派遣は、日本で行なう研修(本邦研修)や日本人の専門家派遣と比較して実施経費が安価であるという考え方に基づき、経費削減の効果の度合いを第三国研修及び第三国専門家派遣の事例を比較することにより検証した。
第三国研修
表3-1の第三国研修と本邦研修の経費比較表からからわかるように、第三国研修にかかるJICAの経費は、本邦研修の約5分の1である。また、第三国研修における研修生の招待費で最も経費がかかっているのは、アフリカ諸国からエジプトまでの航空運賃(1人当り約12万円)であることがわかる。一方、仮に、マリから研修生1名を日本に招待した場合は、マリのバマコ市から東京までの正規エコノミークラス料金で892,740円(エアーフランスを利用すると仮定)となり、これはエジプトまでの航空運賃の約7倍にあたる。第三国研修の研修費には、この他に、講師への謝礼費(表3-2第三国研修のエジプト人講師と本邦研修の日本人講師への謝礼費の比較を参照)、雇用費(コーディネーター代)、スタディーツアー費、教材費、会合および式典費、印刷費、教科書費などの項目がある。これらの経費は、航空運賃に比べて小さいが、物価の違いから、本邦研修に比べて安価に収まっていることも確認された。
表3-1 第三国研修と本邦研修の経費比較表
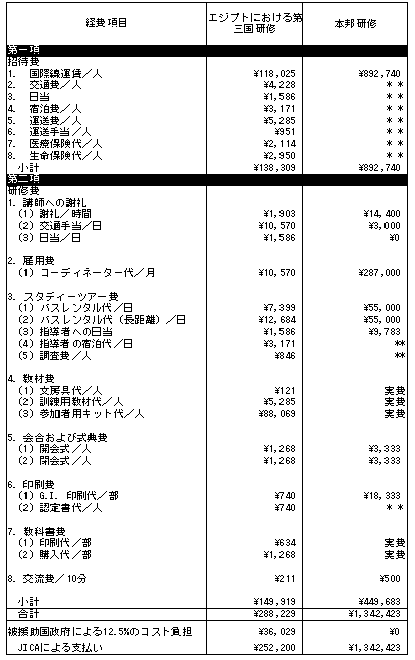
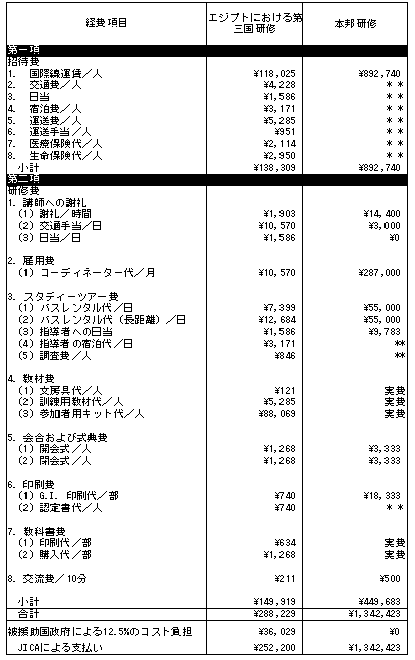
| 出所: | 第三国研修については、アフリカ諸国からの研修生を対象に、エジプトで開催された第三国研修・感染症対策を参考に作成。本邦研修については、マリの研修生を対象に都内で開催された本邦研修・工業プロジェクト評価と中小企業育成セミナーを参考に当センターで作成。*印は情報が不明であることを表す。 |
表3-2 第三国研修のエジプト人講師と本邦研修の日本人講師に対する謝礼費の比較
| 第三国研修 | 本邦研修(日本語の場合) |
| 1時間当たり一律LE.90(約2000円) +日当(約1,600円) |
特号(学長) 12,000円/時間 1号(教授) 9,600円 2号(助教授) 7,300円 3号(講師) 5,900円 4号(助手) 4,700円 |
第三国専門家派遣
表3-3にみるように、第三国専門家派遣と日本人専門家派遣の経費の差は、第三国研修と同様に、赴帰任航空費に大きく表れていることがわかる。具体的には、チュニジアからモーリタニアまでの航空運賃は、約6万円であるのに対して、日本からモーリタニアまでは、約90万円かかる。その他の経費については、ここで比較した事例において大きな違いは見受けられなかった。
表3-3専門家派遣経費の比較(派遣先をモーリタニアと仮定)
| 経費の種類 | 第三国専門家派遣にかかる経費(単価表) (1US$=118円、1US$=1.3215DT)で計算) |
日本人専門家派遣にかかる経費(単価表) |
| 1. 日当 | 3,658 | 3,800 *丙単価適用 |
| 2. 宿泊費 | 11,092 | 11,600 *丙単価適用 |
| 3. 支度費 | 89,798 | 75270 *タイの例を適用 |
| 4. 空港使用税 | 4,018 | - |
| 4. 内国旅費 | 11,092 | 4,140 896,020 |
| 5. 赴帰任航空費 | 56,656 | *エコノミーノーマル |
| 6. 赴帰任日当・宿泊費 | 14,750 | 15,400 |
| 7. 予防接種費 | 1,607 | 実費 |
| 8. 生命保険代 | 5,715 | ** |
| 合計 | \198,386 | \1,002,730 |
| 出所: | チュニジアのモーリタニアに対する第三国専門家派遣経費見積もり及びタイに派遣された日本人専門家(34才)の派遣経費見積もりを参考に作成。なお、日本人専門家については上記経費の他に給与補填があった。 |
3.3.2 間接的・波及的効果
以下において当初予定していない、間接的・波及的効果が確認された。
<日本のプレゼンスの強化>
エジプト又はチュニジアの第三国研修に参加したセネガル人研修生及び彼等の上司に対してアンケート調査を行なったところ、回答者の92%が参加した研修が日本の援助によるものであることを認知していたことが分かった。その理由をグループディスカッション及びヒアリング調査で確認したところ、「研修に日本人講師がいたから」、「教材、修了証書にJICAのマークがあったから」等の意見が挙げられた。また、全員が研修の準備プロセスにおいて、政府窓口機関或いは研修実施機関から本研修が日本の南南協力支援の一環であることについての説明を受けていたことが確認された。エジプトにおける第三国研修の講師および第三国専門家に対するアンケート調査においても、1名を除き全員が、研修参加者又は第三国の受け入れ機関に対して案件が日本の南南協力支援によるものであることについて予め説明をしていたことが確認された。
図3-15 南南協力支援における日本の関与に関する認知度
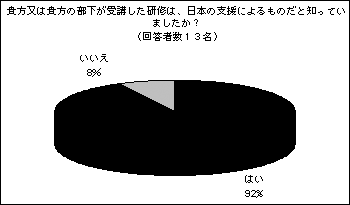
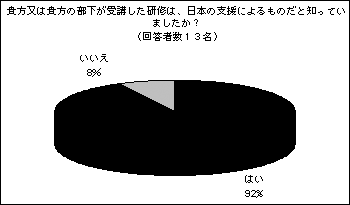
他方、協力実施国では、過去に様々な形でわが国の南南協力支援が現地の報道機関にとりあげられていることが確認された。これらは、協力実施国における日本のプレゼンスを高める役割を果していると判断される。
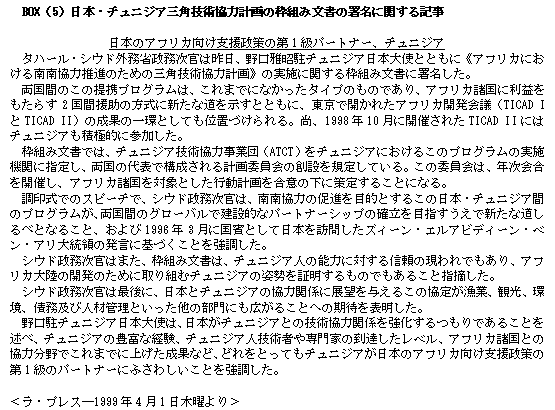
<ネットワークの構築>
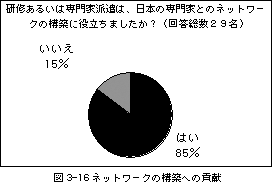 第三国研修講師あるいは第三国専門家に対して行なったアンケート調査によれば、わが国の南南協力支援は、協力受益国の関係者とのネットワーク及び日本人専門家、日本人講師とのネットワークの形成に役立っていることが確認された。協力受益国の関係者とのネットワークの形成については、アンケートの回答者全員が役立ったとしている。また、日本人専門家、日本人講師とのネットワークの形成についても、回答者の大半が役立ったとしていることが確認された。ネットワークの形成方法は、電子メールを用いるケースが多く、内容は、専門分野に関する情報交換やプロジェクト形成に関する相談等様々であった。
第三国研修講師あるいは第三国専門家に対して行なったアンケート調査によれば、わが国の南南協力支援は、協力受益国の関係者とのネットワーク及び日本人専門家、日本人講師とのネットワークの形成に役立っていることが確認された。協力受益国の関係者とのネットワークの形成については、アンケートの回答者全員が役立ったとしている。また、日本人専門家、日本人講師とのネットワークの形成についても、回答者の大半が役立ったとしていることが確認された。ネットワークの形成方法は、電子メールを用いるケースが多く、内容は、専門分野に関する情報交換やプロジェクト形成に関する相談等様々であった。
<技術の再移転>
エジプト又はチュニジアにおける第三国研修に参加したセネガル人研修生に対してアンケート調査を行なったところ、1名を除き全員が職場に戻ってからも研修で移転された技術を同僚に教えていたこと(図3-17)、また、研修生の大多数が研修で習得した技術を職場で活かしていることから、南南協力支援政策の波及効果が認められる。
図3-17 技術の再移転
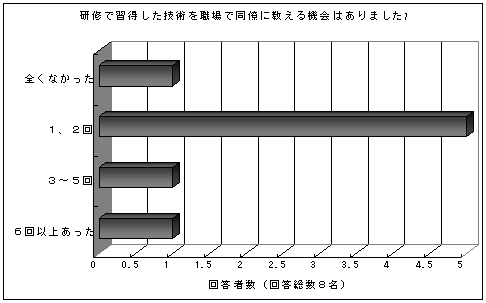
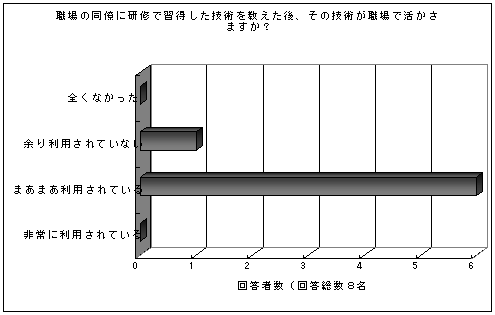
3.3.3 結論・考察
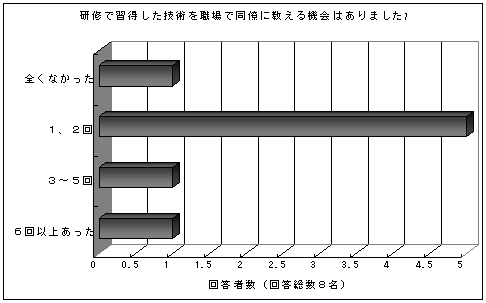
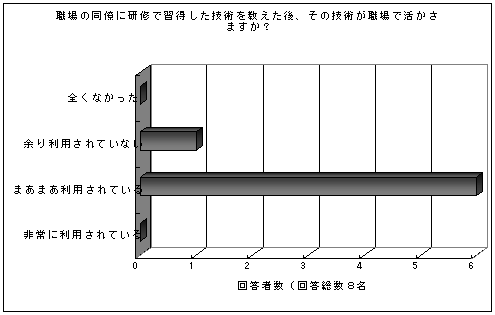
本節では、効果を政策目標の達成度合い及び間接的・波及的効果の観点から検証した。その結果、以下の通り、政策目標の達成度合いについては、新興援助国の育成による援助資源の拡大、地域間協力の推進、適正技術の移転、ODA経費の削減において、各々効果の大きさは異なるものの、プラスの効果が確認された。また、間接的効果として、南南協力支援政策による、日本のプレゼンスの強化、ネットワークの構築、技術の再移転が確認された。これら効果をさらに高めるために、以下について検討される必要がある。
1)新興援助国の育成の対象者の具体化
新興援助国の育成の効果は、協力実施国政府機関に対する効果、実施機関に対する効果、協力実施国の講師及び第三国専門家に対する効果の3つの視点から検証した。その結果、協力実施国政府機関に対する効果については殆ど確認されなかったが、実施機関、協力実施国の講師及び第三国専門家に対する効果はある程度確認された。わが国の南南協力支援政策において、協力実施国政府機関の能力向上を図ることが重要であるならば、協力実施国政府機関が殆ど関わる必要がない既存の政策プロセスの見直し及び目的達成のための具体的な方策を検討する必要がある。
2)地域間協力の推進の目的と戦略の具体化
地域間協力の推進度合いは、協力実施国と協力受益国との人的交流の発展の観点から検証した。エジプトとチュニジアの事例から、南南協力支援により人的資源の交流や外交関係においてプラスの効果が確認されたことから、わが国南南協力支援政策は、北アフリカ地域と他のアフリカ地域との人的交流の推進及び外交関係の強化に多少なりとも寄与していると言える。ただし、わが国南南協力支援は実施案件数が限られていることから、効果の度合いは極めて限られたものであると推測する。
他方、北アフリカ地域と他のアフリカ地域の地域間協力の促進をプラスと捉えるか、マイナスと捉えるかは、その国の捉え方により大きく異なる。セネガルは、北アフリカ地域との協力促進よりも、むしろ西アフリカ地域との協力が重要であると考えている。わが国が南南協力支援を通じて、域内、域外協力の推進を図る際は、協力実施国と協力受益国の両者の政策を十分に理解する必要がある。
3)協力実施国と協力受益国の適切なマッチングの必要性
アンケート調査の結果からは、言語の共通性によるプラスの効果は確認されなかったが、グループディスカッションを通じて、言語は、研修滞在中の日常生活や他の研修参加者との意見交換を円滑に行う上での基礎であること、また、言語の相違は、マイナスの効果をもたらす可能性があることが確認された。さらに、文化の共通性は、分野によりその効果の度合いが異なることも確認された。以上のことから、言語、文化等の共通性、さらに分野の特徴を意識して協力実施国と協力受益国のマッチングが行なわれたわが国の南南協力支援政策については、プラスの効果をもたらしていると結論づけられる。
4)パートナーシップ・プログラムの締結によるわが国のさらなる経費削減
南南協力支援政策の下で行なわれている第三国研修及び第三国専門家派遣の経費を本邦研修及び日本人専門家派遣を比較した結果、南南協力支援政策は、「国際航空運賃」が安くすむことから、わが国のODA経費の削減に直接的なプラスの効果をもたらしていることがわかった。パートナーシップ・プログラムの枠組み文書に署名している国との南南協力支援では、費用分担化の原則により、わが国の費用分担化のさらなる削減につながっている。
5)日本のプレゼンスの向上のための努力
第三国研修における日本人講師の存在やわが国南南協力支援に関する報道が、協力実施国においてわが国援助のプレゼンスを高めていることが確認された。さらに、協力実施国の関係者と日本人専門家、講師、研修生の間でネットワークが形成されていることも確認された。南南協力支援政策においてこれらの位置付けを明確化すれば、政策の効果をさらに高めることができる。
17 プロジェクトの発掘形成から、計画立案、審査、実施、モニタリング、評価とそのフィードバックまでの一連の事業の過程をプロジェクトデザインマトリックス(PDM)と呼ばれるプロジェクト概要表を用いて運営管理する手法。
18 第三国研修には、原則として少なくとも日本人1名が講師として参画している。
19 アンケートは、2000年及び2001年にエジプト又はチュニジアの第三国研修に参加し、ダカール市近郊に在住のセネガル人研修生及び彼等の上司に対して実施した。なお、2000年及び2001年にエジプトの第三国研修に参加したセネガル人研修生は合計7名、チュニジアについては合計3名であった。

