南南協力支援評価調査
第3章 評価結果3.2 プロセスの検証
本節では、わが国の南南協力支援政策のプロセスの「適切性」及び「迅速性」を検証する。
パートナーシップ・プログラムに署名している国と、署名はしていないが協力実施国としてわが国の南南協力支援を受けている国とでは、南南協力支援政策のプロセスが異なっている(以下図3-3参照)。本調査では、パートナーシップ・プログラムに署名している国のプロセスについては、ODA中期政策において南南協力支援に関する方針が明確となった時点から、(1)パートナーシップ・プログラムの文書策定、(2)南南協力支援に関する「行動計画」の策定、(3)南南協力支援案件の形成、(4)南南協力支援案件の実施までの4段階として検証する。一方、パートナーシップ・プログラムに署名していない国のプロセスについては、ODA中期政策において南南協力支援に関する方針が明確となった時点から、(1)南南協力支援案件の形成、(2)南南協力支援案件の実施までの2段階を検証する11。さらに、本評価調査では、プロセスの適切性を、本政策の関係者がプロセスに参加していること、協力実施国の比較優位性が十分に把握されていること、協力受益国のニーズが把握されていること、わが国、協力実施国、協力受益国の三者間の役割が果たされていることをもって判断する。
| 図3-2南南協力支援政策の概念図 | 図3-3プロセスの検証範囲 |
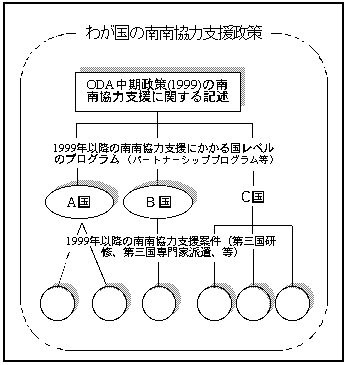 |
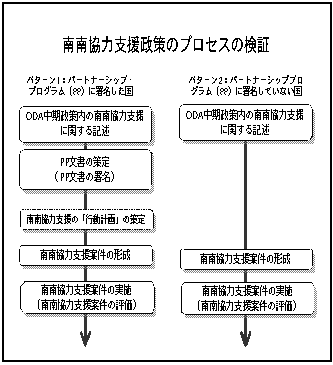 |
3.2.1 パートナーシップ・プログラムに関する枠組み文書の策定プロセスの実態と 適切性
<パートナーシップ・プログラムに関する枠組み文書の特徴>
わが国はこれまでに8ケ国と「パートナーシップ・プログラム」に関する枠組み文書を取り交わしているが、外務省において同枠組み文書の署名国の選定に関する規定や策定に関するガイドラインは特に作成されていない。過去の例から、同枠組み文書の内容について特徴を整理すると、以下の共通点があげられる。
- 過去に事業レベルで行なってきた南南協力の連携をより外交レベルで約束するものであり、法的拘束力を有さない
- 費用分担化を約束している
<わが国とエジプトがパートナーシップ・プログラムの署名に至った背景>
エジプトのアフリカに対する南南協力は、エジプト外務省内にエジプト技術協力基金(Egyptian Fund For Technical Cooperation: EFTCA)が設立された1981年から始まっている。EFTCAは、2002年までに7,625名のエジプト人専門家をアフリカ諸国約47ケ国に派遣し、また、同諸国から約5900名の研修生を受け入れた実績を有している。
EFTCAは業務方針書の中で、エジプトは、中東地域のアラブ人であるという特性に加え、アフリカ大陸に位置する国であるため、アフリカ諸国との関係強化を図ることにコミットしており、アフリカ諸国の生産能力を高める手段として南南協力が有効であるとの考えを明らかにしている。また、開発途上国に最も必要とされているのは人的資源の開発であるとして、アフリカに対する技術協力を推進している。
他方、このようにエジプトがアフリカ支援に重点を置いている背景には、エジプトが、将来的にアフリカに対する輸出を増やしたいという経済政策があるとの見方もある。現在、エジプトの主要輸出先は、米国、EU、アラブ諸国が中心であるが、輸出競争力の観点からアフリカ諸国の市場に対する期待は大きい。エジプトの社会経済開発計画(2002-2007)においても、貿易赤字を解消するために輸出を拡大していくことの重要性が強調されている。
1985年に開始されたわが国のエジプトに対する南南協力支援は、エジプトの既存の対アフリカ援助政策及び外交政策の延長線上に位置づけられてきた。エジプトは、同国の対アフリカ支援政策の枠組みの中で、日本と協力してアフリカ諸国に対し南南協力を行うことは、同地域への援助の拡大につながるものとして有意義であると考え、1998年、「アフリカにおける南南協力推進のための日・エジプト三角技術協力計画(以下パートナーシップ・プログラム)」に署名した。エジプトとしては、今後も、わが国に限らず国際機関や二国間ドナーとの協力関係を図りつつ、アフリカ諸国に対する支援を拡大する方針である。エジプトに対するわが国の南南協力支援の実績を図3-4に示す。
図3-4 エジプトのフローチャート(PDF)
<わが国とチュニジアがパートナーシップ・プログラムの署名に至った背景>
チュニジアでは、1972年、国際協力庁の傘下にチュニジア技術協力事業団(ATCT)が設立され、アラブ、アフリカ諸国を対象に技術協力専門家の派遣を実施してきた。設立当初は教育、医療分野の協力に限られていたが、1980年代には、アラブ、アフリカ諸国からの要請に基づき、電気、通信、情報工学、環境、人材育成、農業、漁業等、多岐にわたる分野に事業内容を拡大し、国際機関や二国間ドナー等からの援助を受けて積極的に南南協力を推進している。
チュニジアは、1998年5月南南協力支援会合(於沖縄)の折、わが国が参加国代表者らに対してパートナーシップ・プログラムの説明とTICADIIへの参加に関する呼びかけを行なったことを受け、これに応える形で「アフリカにおける南南協力推進のための三角技術協力計画の枠組み文書」の策定にかかる検討を開始した。日本側としては、第三国研修においてチュニジア側が一定のコストシェアを行うことを重視しつつ協議を行なった結果、最終的には、2004年度までにチュニジア側が30%負担することを同文書に盛込むことで合意された。また、同枠組み文書の作成と並行し、リプロダクティブヘルス分野の広報教育コミュニケーション(IEC)にかかる第三国研修の計画(事前調査団の派遣等)が進んでいたことも、両国のパートナーシップ・プログラムの署名を後押しした。
パートナーシップ・プログラムの枠組み文書のタイトルにも示されるように、わが国のチュニジアへの南南協力支援は、協力受益国としてアフリカ諸国、特にフランス語圏アフリカ諸国を対象としている。チュニジアは外交政策の中で、サブサハラアフリカ諸国との良好な外交関係を維持することに努力しており、わが国の南南協力支援の方向性は一定の妥当性を示している。一方、同国の外交政策は、マグレブ諸国、地中海、中東地域との外交関係により重点が置かれており、チュニジア側は、わが国の支援による南南協力が、今後、受益国としてマグレブ諸国や中東地域も対象とするよう期待している。
一方、チュニジアでは失業率が15%と高く、経済開発計画10次計画(2002-2006年)においても、雇用対策を最重要課題の一つとし、年平均8万人への雇用機会を創出することを目標に掲げている。チュニジアに駐在する国際機関事務所等の間では、上記の社会背景を抱えるチュニジアにおいて、現地専門家を雇用する南南協力支援は、チュニジア人専門家の雇用機会の裾野を広げることに一役買っていると見るむきもある。
チュニジアは一人あたりのGDPが2,090ドル(WB資料等)で、世銀の定義では「中所得国(middle income country)」に位置づけられており、近年、EUやフランス等、対チュニジア援助における主要ドナーからのODA贈与額が減少傾向12にある。第10次計画では、2002~2006年の間に、第9次計画(1997-2001年)の約2倍(5億米ドル)のODA贈与額が必要とされており、二国間ドナーである日本との関係を維持・拡大するうえで、わが国の南南協力支援は、協力実施国であるチュニジアにとって重要な意味を持つ。
チュニジアに対するわが国の南南協力支援の実績を図3-5に示す。
図3-5 チュニジアのフローチャート(PDF)
<パートナーシップ・プログラムに関する枠組み文書の策定プロセス>
エジプト及びチュニジアのパートナーシップ・プログラムに関する枠組み文書(添付資料8・9を参照)は、いずれもA4サイズで3枚程に纏められたもので、大きくは、(1)プログラムの目的、(2)研修事業に関する事項、(3)専門家派遣に関する事項、(4)年次計画の策定に関する事項の4項目で構成されている。費用分担化に関する事項は、(2)研修事業に関する事項において明記されている。また、いずれの文書も協力受益国をアフリカ諸国に限っている点で共通している。
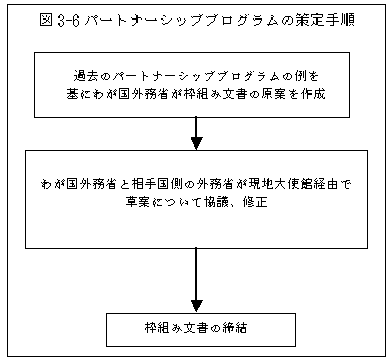 一方、エジプトとチュニジアのパートナーシップ・プログラムは細かい点で相違もみられる。チュニジアの枠組み文章には、「費用分担化に関する事項(負担率を含む)」、「枠組み文書署名後の作業として計画委員会:Planning Committeeの設立」、「枠組み文書の見直し期限に関する事項」の記述があるが、エジプトにはそれらに関する記述がない。チュニジアについては、「研修事業の必要経費は分担して行なうこととし、チュニジアは、費用分担化の割合を1999年度の15%から2004年度までに30%まで徐々に引き上げる努力を行なう」との記述を残している他、枠組み文書の見直しを2004年に設定している。一方、エジプトについては、「研修事業を費用分担で行なう」との方針を示しているものの、数値目標に関する記述はない。エジプトについては、署名日と同日に口上書(Note Verbal)をエジプト外務省から在エジプト日本大使館宛に送付しており、その中に、エジプトの費用分担化は、1999年度に5%で開始し、以降5年以内に15%まで徐々に引き上げることを確認している。
一方、エジプトとチュニジアのパートナーシップ・プログラムは細かい点で相違もみられる。チュニジアの枠組み文章には、「費用分担化に関する事項(負担率を含む)」、「枠組み文書署名後の作業として計画委員会:Planning Committeeの設立」、「枠組み文書の見直し期限に関する事項」の記述があるが、エジプトにはそれらに関する記述がない。チュニジアについては、「研修事業の必要経費は分担して行なうこととし、チュニジアは、費用分担化の割合を1999年度の15%から2004年度までに30%まで徐々に引き上げる努力を行なう」との記述を残している他、枠組み文書の見直しを2004年に設定している。一方、エジプトについては、「研修事業を費用分担で行なう」との方針を示しているものの、数値目標に関する記述はない。エジプトについては、署名日と同日に口上書(Note Verbal)をエジプト外務省から在エジプト日本大使館宛に送付しており、その中に、エジプトの費用分担化は、1999年度に5%で開始し、以降5年以内に15%まで徐々に引き上げることを確認している。これら事例国における枠組み文書は、基本的に過去に署名されたパートナーシップ・プログラムの例を参考にわが国外務省がその原案を作成していた。枠組み文書の内容の決定に際しては、外務省からJICAに対して適宜情報が提供されていたが、あくまでも政策レベルにおける二国間の決定事項として位置付けられていたため、原案の作成に関してJICAや現地の援助窓口機関は大きく関わっていなかったことが確認された。総体的にみて、パートナーシップ・プログラムの枠組み文書の草案に関する相手国政府との協議及び署名は、これまでの実績と信頼のもと上位のレベルでスムーズに行われていたと判断される。
3.2.2 南南協力支援に関する「行動計画」の策定プロセスの実態と適切性
エジプト及びチュニジアのパートナーシップ・プログラム枠組み文書によれば、署名を受けて南南協力支援に関する「行動計画」が策定されることになっている。しかしながら、両国においては、これが行なわれていなかった。
エジプトについてみると、EFTCAは、枠組み文書における行動計画は、毎年JICAに対して提出している年次計画と同一であり、特段新しい行動計画を作る必要性を感じていない。JICAについても、要望調査の際に相手国政府との協議を十分に行なっており、これが行動計画に代用されるものと理解している。
チュニジアについても、パートナーシップ・プログラムの枠組み文書において、政策レベルでの計画委員会(Planning Committee)を組織し年次協議を行うことが記載されているが、これに該当する年次協議は行われていないのが実状である。一方、2000年に「アフリカ三角協力に関するプロジェクト形成調査」ミッションが本邦より派遣され、2001年度には在外プロジェクト形成調査ミッションが組織され受益国であるサブサハラアフリカ諸国に派遣される等、今後のわが国の対チュニジア南南協力支援について協議する機会は提供されている。また、2001年9月頃より、1ヵ月に1回程度、実務レベル13で、南南協力支援について、情報交換やフォローアップを行っている。
3.2.3 南南協力支援案件の形成プロセスの実態と適切性
第三国研修及び第三国専門家派遣の一般的な案件形成プロセス14を以下に示す。
<案件発掘>
第三国研修および第三国専門家派遣案件の発掘は、基本的にJICAが主体となって行なわれる。これまでに発掘された案件の例では、過去にわが国の無償資金協力、プロ技、専門家派遣等が実施された機関/施設を受け入れ先として研修の実施可能性を検討したケース、協力実施国政府や研修実施機関がJICAに提出した研修プロポーザルが基になるケース、第三国研修の研修生から非公式に第三国専門家派遣の要請を受けたケース等、さまざまな形態がみられる。また、必要に応じてプロジェクト形成調査を実施する場合もある。
<要望調査>
発掘された案件は、わが国が協力実施国に対して実施している要望調査において、口上書にて要請され、第三国専門家派遣については口上書と併せて正式な派遣要請書(通称A1フォーム)が提出される。その後JICA在外事務所は、先方政府の要請内容を「要望調査票」にまとめ、JICA本部へ送付する。送付された「要望調査票」およびA1フォームは、JICA本部で検討される。
要望調査は、継続案件についても行なう。第三国研修については、協力受益国、研修対象者、研修内容、研修時期等の見直しを判断することを目的として、また、第三国専門家派遣については、協力受益国、受け入れ機関のニーズ等の見直しを判断することを目的として行なう。
<計画通報>
要望調査の結果を踏まえ、JICA地域部は、次年度計画案を策定し、これを基に外務省と協議を行なう。外務省により承認された計画は、外交ルートを通じて案件実施の前年度末、または当該年度の初めに協力実施国の在外公館に通報され、JICA在外事務所に対してはJICA本部から連絡される。計画通報においては、計画された案件は、「当該年度に実施予定のもの」、「当該年度に調査団を派遣し、実施可能性を検討するもの」、「次年度以降の検討課題とするもの」、「採択案件として取り上げ困難なもの」の4つに分類して示される。継続案件についても基本的に新規案件と同じ手続きが行なわれる。
これに平行して、わが国外務省が、協力受益国に対して通報を行う。継続案件については、わが国外務省が協力受益国の在外公館に対し、割り当て国の希望有無、また、希望する場合は、在外公館から協力受益国政府に対し当該研修の案件名、実施国についての正式な通報を行なう。なお、新規案件については、基本的に協力実施国が、独自の外交チャンネルを通じて協力受益国に対する通報を行なう。
<事前調査>
新規案件の内、「当該年度に実施予定のもの」、「当該年度に調査団を派遣し、実施可能性を検討するもの」については、JICA在外事務所が「事前調査実施指針」に基づき事前調査を行う。第三国研修の事前調査では、以下の事項を確認する。
- 域内研修ニーズの把握 (域内各国における当該分野の人材育成ニーズ、域内各国における予想応募機関等)
- 研修実施体制(実施国における当該分野の技術レベル、予算措置、実施機関の運営能力等)
- 研修計画(協力期間、コース名称、目的、到達目標、カリキュラム、割当国、日本側の技術面での支援の必要性、日本側との費用分担割合、業務分掌等)
<実施協議>
事前調査において合意したミニッツをもとに、JICA本部(地域部)が在外事務所および実施機関と協議の上R/D案を作成し、外務省に提出、承認を得る。外務省からR/D案の最終案が在外公館に送付され、在外事務所はそれに基づき実施協議を行ない、R/Dの署名を行なう。第三国研修については、協力受益国政府、協力実施国政府機関、協力受益国におけるJICA事務所、専門家派遣機関の4者の署名が必要となる。
<案件形成に関するその他の事項>
1998年度以降、第三国研修のプロジェクト形成に関し、次の規則が導入されている。
- 1998年度より新規に開催される第三国研修については、協力実施国との間で費用分担化及びわが国負担の上限額を導入。費用分担化の比率は、無償非対象国は、協力実施国30%、日本70%、無償対象国は、協力実施国15%、日本85%を目指す。日本の負担額は原則1000万円を上限とし、これを超える場合には研修規模の縮小を行なう。
- 1999年度より新規に開催される第三国研修の協力年限は原則として5年迄とし、延長した場合も10年を超えないものとする。
図3-7 案件形成プロセス
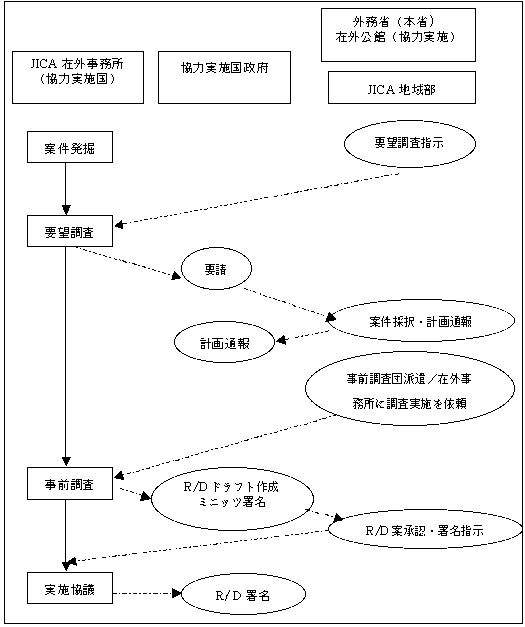
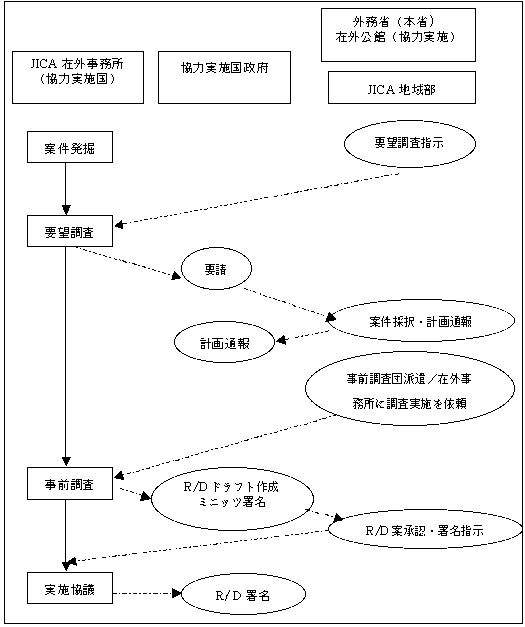
■事例国における実態■
<エジプト>
エジプトにおける南南協力支援案件についても、基本的に上述のプロセスで案件が形成されていることが確認された。JICAエジプト事務所は、1998年から南南協力支援の案件形成を目的とした企画調査員1名を配置し、案件発掘に力を入れている。
案件の発掘についてみると、エジプトでは、わが国の南南協力支援の歴史が長いことから、さまざまな方法で行なわれていた。例えば、第三国研修の「感染症対策(96-98、99-03年度)は、研修実施機関であるスエズ運河大学医学部がイニシアティブをとり、研修案をJICAに提出したことから案件の形成が始まっている。また、「建設機械訓練(94-98, 99-03年度)」は、わが国の無償資金協力で建設された建設機械訓練所の有効的な活用を目指して形成された。
案件の発掘に際しては、エジプト政府側から提案される場合もあるが、エジプト政府側から提案される案件がわが国の援助方針に合っていないケースが多く、結果的にJICAが主体となり行なわれているのが現状である。
協力受益国のニーズの把握については、「事前調査」の際に、在外事務所経由で協力受益国に対するアンケート調査を実施している他、研修参加者からの意見交換も適宜行なわれている。また、本調査で訪問した実施機関の中には、独自の予算を利用して受益国に対して調査団を派遣し、ニーズ調査を実施しているところもあった。
在外プロジェクト形成調査団の派遣は、新規案件の形成に際してのみ行なわれていた。最近の例では、1998年度、2001年度、2002年度に在外プロジェクト形成調査を実施している。1998年度は、JICAの費用分担化でJICA、EFTCA、実施機関の3者で実施、2001年度についてはJICAの費用分担化でJICA及びEFTCAの2者で実施、2002年度はJICAのみで行なわれていた。
2002年度在外プロジェクト形成調査がJICAのみで実施された背景には、同調査において費用分担化の原則が適用されたことが影響している。本調査の対象国は、シリアであったため、エジプト政府の窓口機関は、EFTCAではなく外務省文化局であった。費用分担化の原則に基づくならば、同局にプロジェクト形成調査の費用分担化を求めるべきところであるが、そもそも同局には、EFTCAのような研修実施のための予算がないため、わが国の要請に応えることは不可能であった。JICAとしても文化局及び実施機関の調査費用を負担できず、結果としてJICA在外事務所のみで調査を行なうこととなった。JICA調査団は、協力実施国関係者の不在を補完すべく、実施機関と協力して協力受益国で実施するためのアンケート票を作成する等して、協力受益国におけるニーズの適切な把握に務めていたが、JICA在外事務所関係者からは、協力受益国の関係者と協議する際には、調査団側からの専門的な知識がインプットされることが不可欠であるとの意見が聞かれた。
パートナーシップ・プログラムの署名に基づいて案件実施にかかる費用分担化を行なっているEFTCAにとってもプロジェクト形成における費用分担化は負担が大きいとしてプロジェクト形成調査への参加を躊躇する姿勢を見せていることも確認された。このような状況から、今後、南南協力支援政策においてプロジェクト形成の段階から費用分担化が適用されるようならば、プロジェクト形成は、JICAのみで行なうことになる可能性が高いと判断される。
<チュニジア>
チュニジアでの南南協力支援案件については、主として、過去にわが国が実施した技術協力と関連した形で案件の発掘が行われている。第三国研修「リプロダクティブヘルス分野におけるIEC能力向上」及び「リプロダクティブヘルス分野における視聴覚コミュニケーション」は、わが国のプロジェクト方式技術協力(プロ技)「人口教育促進プロジェクト」(1993-1998年)の終了を受け、同プロジェクトの長期専門家及び国際協力専門員からの強い推薦を受け、わが国が移転した技術をより広範に普及することを目的に計画された。また、第三国研修「廃棄物処理と環境汚染対策」については、同研修の実施機関であるチュニジア国立科学技術研究院・水・環境研究所(INRST)に、かつてJICA個別専門家が派遣されており15、技術指導や機材供与が行われてきた経緯がある。本第三国研修は、同研究所が主催する国際会議に伴い計画され、研修の立案、実施に、上述のJICA個別専門家が果たした役割が大きい。一方、2000年に実施された第三国研修「債務管理セミナー」は、TICADIIのフォローアップ事項として、世銀/IMF、UNDPとの連携で計画、実施された。同研修については、過去のわが国の技術移転の内容と関連性は無い。
第三国専門家派遣「沿岸漁業教育・訓練」では沿岸漁業教育を指導科目とし、チュニジア人専門家がモーリタニアに派遣された。本案件は、チュニジア、モーリタニアのみならず、セネガル、モロッコに派遣されているわが国の個別専門家の非公式の情報交換と、モロッコでの第三国研修(水産分野)の場を機に、モーリタニアのニーズとチュニジアの人的資源がマッチングされ、案件の計画と実現に至った。本案件の形成に、当該国以外のJICA専門家が関わった背景として、これらの諸国に派遣されているJICA専門家が、派遣国の水産資源が地理的理由から類似していることもあり、非公式に国を越えて連絡を取りあい、情報交換を行っていることが挙げられる。また、本案件のモーリタニア側の受入機関は、わが国の無償資金協力(「国立水産海洋技術学校整備計画」)で支援した水産海洋技術学校となっている。
協力受益国のニーズの把握については、2001年、チュニジア人と日本人の専門家で構成された在外プロジェクト形成ミッションが派遣されている。同ミッションは「リプロダクティブヘルス、ジェンダー」と「水産、砂漠化防止、水資源管理」の二つの分野グループに分けられ、前者がニジェール、マリ、ブルキナファソ、後者がセネガル、モーリタニア、モロッコに派遣された。同ミッションの派遣について、JICAが旅費及び調査にかかる諸経費を負担し、チュニジア側は、チュニジア人の人件費を負担した。
<セネガル>
第三国研修案件の形成、実施は、協力実施国におけるJICA事務所と協力実施国政府が主体となって行なわれるため、セネガルの関係者(大使館、JICA在外事務所、関係政府機関)が受益国としてこれに大きく関わることは、原則として無い。
第三国専門家派遣については、水産分野で、セネガルの長期派遣専門家(日本人)がコアとなり、国を越えた個人のネットワークを活用して案件を形成し、セネガルで第三国専門家の受入を行ったケースがみられた。
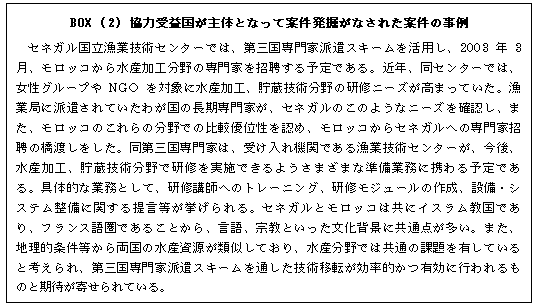
3.2.4 南南協力支援案件の実施プロセスの実態と適切性
第三国研修及び第三国専門家派遣の一般的な案件実施プロセス16を以下に示す。
第三国研修
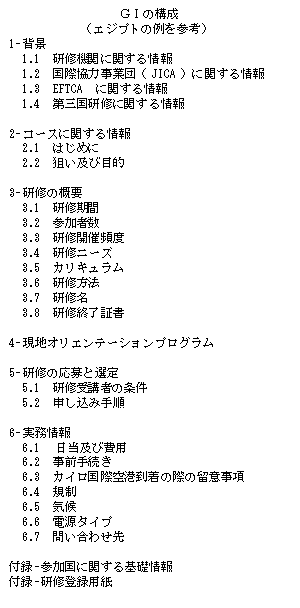 <募集>
<募集>R/Dの署名を受けて、研修実施機関は、コース・インフォーメーション(通称GI)を作成し、協力実施国と協力受益国間の外交ルートを通じて、協力受益国にGIを送付し、参加者の募集を行なう。
基本的に募集は、協力実施国自身がその外交ルートを通じて行なうことになっているが、協力実施国の在外事務所が協力受益国の在外事務所にGIを送付する等して、協力受益国の在外事務所が当該第三国研修の関係省庁に対して応募を促進するよう努めている。
<参加者決定>
研修実施機関は、外交ルートを通じて正式要請があった応募者から参加者を選考し、その結果を外交ルートで通報する。協力実施国の在外事務所は、参加者決定後、参加予定研修員リストを入手し、 JICA地域部に送付する。
<研修基盤整備機材>
実施機関における研修の実施に不可欠な機材の整備が不十分であり、資金不足により実施機関が独自に機材の購入または更新ができない場合は、協力実施国政府の要請を受けて必要機材の供与を検討する。機材の供与計画は、要望調査票に添付する機材要望調査票をもとに、当該年度の実施案件決定後にJICA地域部が策定する。
<コース運営・管理及び評価>
在外事務所は、コース実施にあたり開講式、閉講式、評価会等に積極的に参加するとともに、可能な限り実施中のコースに足を運び、研修実施状況を把握するよう務める。特に評価会では、研修員に対するアンケート調査を行ない、実施機関からのコースレポートを添付してJICA地域部宛に送付する。
<終了時評価調査>
第三国研修については、JICAが終了時評価を行なう。本評価は、原則的に最終年度の前年度(通常4年目)に行なう。評価では、目標達成度を図り、延長の必要性および実施方法のあり方について協力実施国又は実施機関と協議する。また、評価の結果から教訓や提言を引き出し、第三国研修全体のあり方や実施方法改善に努める。
図3-8 実施プロセス
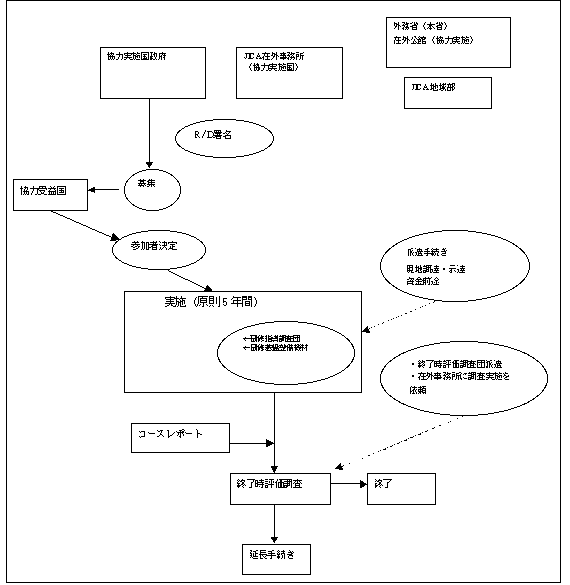
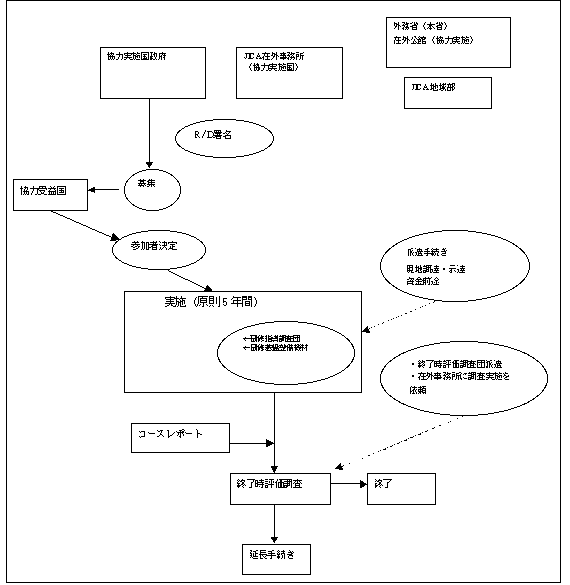
第三国専門家派遣
<派遣通知>
R/Dの締結を受けてJICA在外事務所は、第三国専門家に対して正式な派遣通知を送る。
<派遣準備>
JICA在外事務所は、専門家に対して、派遣国および派遣受け入れ機関に関する情報の提供及び派遣にかかる諸事項の説明を行なう。
<派遣>
協力受益国におけるJICA在外事務所は、必要に応じて第三国専門家の派遣期間中のケアを行なう。
■事例国における実態■
<エジプト>
エジプトにおいても、実施機関が全ての研修案件についてGIを作成している。継続案件については、JICAエジプト事務所と協議しつつGIの見直しを行ない必要に応じてその改訂を行なっている。GIは、一定の共通項目で構成されているが、研修に関する説明等の内容は実施機関によりその深さが異なる。GIは、EFTCA又はその他の政府窓口機関に提出され、外交ルートで協力受益国に送付されている。参加者の応募結果は、外交ルートでエジプトに連絡され、応募者が予定人数を上回る場合には、実施機関が研修生の人選を行なっている。
研修が終了すると、実施機関は、コースレポートを作成し、JICA及び政府窓口機関に提出している。以前はコースレポートの内容が参加者数の増減、研修実施日数等、アウトプットベースの内容に留まっていたがが、JICA事務所が実施機関に対してインパクトの観点を入れるように指示したことを受けて、2002年度からは、実施機関が研修受講者に対して事前、事後の能力テストを行ない、その結果をコースレポートで報告するようになっていることが確認された。これにより、研修を受講した結果、個人の能力がどの程度向上したかについて把握できるようになっている。研修実施期間(R/Dにおける契約期間)が完了した案件については、JICAにより終了時評価が行なわれている。
日本側の規則により、研修の期間は原則5年と決められているが、5年経過後も協力受益国からのニーズが高い案件が殆どである。しかしながら、研修の期間を原則5年とする日本側の方針に基づき、実施機関は、研修名と研修内容を若干変更する形で実質的には研修を延長しているのが現状である。現地調査における実施機関の関係者に対するヒアリングでは、ニーズが高い研修であるにも関わらず、5年を原則として打ち切る日本側の方針を理解できないとする意見が多く聞かれた。
第三国研修の実施にかかる費用分担化については、わが国とEFTCAとの間においては現在まで順調に行われてきているが、約束の15%を達成する来年度以降の費用分担化に関し、EFTCAおよび実施機関の関係者が懸念を抱いていることが確認された。エジプトでは、近年、石油輸出余力の低下や輸入の拡大から、外貨不足が深刻化し、また銀行の不良債権の増大や政府の財政赤字の拡大等により、内貨の流動性も逼迫している。エジプト・ポンドは、2000年の1ドル=3.40ポンドから2003年2月現在までに1ドル=5.5ポンドまで下落している。このような経済状況によりEFTCAの予算に増加が見込まれないことから、来年以降に更にコストシェアのエジプト側の負担率を増やすような方針がとられた場合、エジプト側がこれに対応できない可能性もあり得る。さらに、アフリカ以外の他の地域との南南協力については、枠組み文書の対象外であること、EFTCAのように独自予算を有する窓口機関も限られていることから、費用分担化の条件を満たせる窓口機関を見つけることは更に困難な状況と見受けられる。
他ドナーとの調整に関しては、EFTCAが3年前からノルウエーの援助機関であるノルウェー開発協力庁(NORAD)と家族計画および看護分野において南南協力を開始している。わが国も看護分野における南南協力支援を行っているが、NORADが協力開始前にコンサルタントを派遣し、わが国の南南協力支援について調査を行っているため、研修内容の重複等の問題はこれまでに生じていない。
第三国専門家派遣については、手続き上の問題はみられないものの、専門家より、派遣準備が不十分であるとの意見が多く聞かれた。特に、事前に与えられる派遣先の受け入れ機関に関する情報が少なく、現地に入ってからの調整に時間がかかったケースや受け入れ機関が派遣に関して承知しておらず、現地到着後数日間を受け入れ機関との協議に費やしたケースもあることが確認された。
<チュニジア>
チュニジアで実施される第三国研修は、パートナーシップ・プログラムの枠組み文書に記載されている通り、全ての案件でチュニジア側との費用分担化が行われており、毎年、チュニジア側の負担額も増加している(次ページ囲み参照)。いくつかの案件では、案件の開始当初、R/Dで明記されていた費用分担化の内容とその会計手続きに関しチュニジア側の解釈が異なり、会計手続き上の課題もあったが、現在は、チュニジア側の実施機関が日本の協力スキーム上の会計手続を理解し、案件実施上の問題は解決されている。しかし、今後、チュニジアにおけるわが国の南南協力支援を拡大し、より円滑な実施を図るためには、費用分担化の解釈について共通認識を図り、また、相手国側の会計手続き上の負担を軽減するため、費用分担化の適用範囲、費用項目、会計手続等について、検討する余地があるものと思われる。
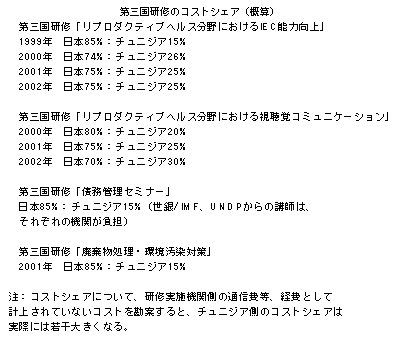
チュニジアでの第三国研修にかかる準備、実施は、前述のマニュアル(35ページ脚註参照)に記載されているように、一般的なプロセスに基づいて行なわれていた。実施の中心的役割を担う研修実施機関は、各々に実施体制を整備しながら効率的な研修の実施に努めている。例えば、国家人口家族公団は、第三国研修の実施にあたり、(1)プログラムの管理運営を所掌する業務委員会(Admin.Committee):及び(2) 教材開発、カリキュラムの開発を所掌する技術委員会(Techinical Committee)を組織している。また、水・環境研究所は、研究所スタッフを (1)プログラム、(2)Techinical Visit、(3)Secretariatの担当に分け、研修の準備、実施に対応している。
パートナーシップ・プログラムの枠組み文書に記載されている通り、チュニジア技術協力事業団(ATCT)が、わが国の対チュニジア南南協力支援の受入窓口として、案件の計画、実施にかかる種々の調整業務を行う役割を担っている。チュニジアでは、援助受入窓口として、借款は国際開発協力省が、技術協力は外務省が担当しているが、ATCTは国際開発協力省の下部組織である。わが国の南南協力支援は技術協力が中心であるが、借款の受入窓口である国際開発協力省の下部組織であるATCTが、わが国の南南協力支援案件の受入窓口の役割を担うことにより、チュニジア側の受入体制に若干の複雑さが認められる。南南協力支援案件は、協力実施国関係諸機関、協力受益国関係諸機関、わが国の援助関係諸機関と、多数の関係者が介在し、種々の調整手続が発生する。わが国の援助関係者は、このような調整手続きに、ATCTが調整役としてより積極的に関わることが、チュニジア側のオーナーシップを高め、円滑に業務を進めるうえで、望ましいと考えている。このため、わが国の南南協力支援の受入について、ATCTを中心としたチュニジア側政府関係機関の役割分担を明確にすることが重要と考えられる。
国際機関及び二国間ドナーとの調整について、チュニジアでは、ドナー間のラウンドテーブルは設けられていない。援助調整はチュニジアの関係機関が個々に取り仕切っており、これまでにわが国の南南協力支援案件が他ドナーの活動と重複する状況は生じていない。例えば、国家人口家族公団は、各ドナーが支援する研修の内容が重複しないよう調整を行っている。このため、同じリプロダクティブヘルス分野の研修でも、UNFPAはプロジェクトマネージメントの研修を、JICAはIECに関する研修を実施しており、役割が明確に分担されている。
案件の評価に関し、2003年度、第三国研修「リプロダクティブヘルス分野におけるIEC能力向上」について、本邦ミッションによる終了時評価が実施される予定である。また、第三国研修「廃棄物処理・環境汚染対策」については、現地コンサルタントを雇用し、在外事務所による終了時評価が行われる予定である。
<セネガル>
セネガルが、協力受益国の立場からわが国の南南協力支援のプロセスに関わるのは、第三国研修への参加者(研修生)の選定についてである。協力実施国の外交ルートを通じて送られたGIは、セネガル外務省政府事務局経済協力局から関係機関(政府機関、NGO等)に配付され、各機関で候補者の選定が行なわれている。その結果を受けて経済協力局は、各関係機関から推薦された候補者リストを再度審査し、最終候補者を選定している。
研修実施国によっては、HIV/AIDS検査や胸部レントゲン写真の結果等、個人の健康状態を選定条件として求める場合があり、個人情報の提示を人々が好まないことや、コストがかかること等の理由から研修への応募人数が少なく、適切な人材を選定することが困難な場合がある。さらに、エジプトのように英語圏での研修の場合、英語のGIが送付されるため、仏語圏のセネガルでは、研修の内容を充分に理解しないまま、研修に応募するケースがあることが確認された。
一方、セネガル政府は、上述のような問題があっても、わが国が支援する第三国研修への参加を求められた場合、その要望に沿って研修生を派遣するよう努めている。ヒアリング調査から、セネガル政府は、日本の南南協力支援案件への受益国としての参加は、その協力案件の内容以上に日本との外交関係の維持の観点から南南協力への参画の意義を認めていることが確認された。
3.2.5 プロセスの迅速性
南南協力支援のプロセスの迅速性を、(1)パートナーシップ・プログラム枠組み文書の策定、(2)南南協力支援に関する行動計画の策定、(3)南南協力支援案件の形成、(4)南南協力支援案件の実施、の4段階で検証した。
パートナーシップ・プログラム枠組み文書の策定は、同文書の外交手段としての位置付けが大きいこと、また、費用分担化等の新しい援助の形態を導入することもあり、策定プロセスに要する時間は二国間の外交行事のタイミング、及び相手国政府の経済事情を勘案しつつ進められている。例えば、エジプトの場合、TICADIIの開催時に署名することを目標として署名の1年前からその準備が進められた。結果的にわが国とエジプトは、予定通りのタイミングでパートナーシップ・プログラムの署名を行なっていることから、同枠組み文書に要した時間は、適切であったと判断される。
案件形成プロセスにおいては、新規案件については、案件発掘に最も時間を要していることが確認された。新規案件が発掘され、要望調査に至るまで、3年以上かかった案件もある。過去の例から、第三国からのニーズにあった案件の発掘及びそれに見合う講師を探すことよりも、研修の運営能力(研修のアレンジ、研修生のための週末のアレンジ等)や予算管理能力に優れた実施機関を探すことに時間を要していた。
案件実施プロセスにおいては、第三国研修の研修生の「募集」に最も時間を費やしていることが確認された。前述の通り、研修生の募集は、協力実施国の外務省が、協力受益国における在外大使館を通じて外務省にGIを送付し、外務省から関係省庁、研究機関等に連絡がいくようになっている。このプロセスに関し、エジプトの多数の実施機関より第三国研修の研修受講者の決定から研修実施までの期間が短すぎるため、研修員の受け入れ準備のための時間が足りないとの意見が聞かれた。協力実施国は、この原因について、協力受益国の外務省が人選に時間をかけ過ぎていることを挙げている。一方、協力受益国であるセネガルの外務省側は、そもそもGIを受け取る時期が遅いため、人選にかかる期間が10日間程度しか与えられていないとして、協力実施国の大使館の対応を問題として指摘している。
3.2.6 結論と考察
本節では、南南協力支援政策プロセスとして、パートナーシップ・プログラム枠組み文書の策定~行動計画の策定~案件形成~案件実施、という4段階のプロセスについて検証した。個々の段階をわが国外務省の過去の事例およびJICAのガイドライン等の一般的なプロセスに照らして検証したところ、実施されなかった「行動計画の策定」を除き、南南協力支援政策のプロセスは、適切な役割分担の下で、適切な手順に従って行なわれていたと評価できる。また、迅速性の観点からも、パートナーシップ・プログラム文書の策定、案件の形成、案件の実施が妥当なタイミングで行なわれていたことから、適切であったと判断できる。
一方、「南南協力支援」政策の観点から、枠組み文書の策定から実施に至るまでの一連のプロセスを総合的に検証したところ、以下について検討される必要がある。
1)パートナーシップ・プログラムに関する継続的な対話の必要性
パートナーシップ・プログラムの策定は、わが国と協力実施国とのこれまでの実績と信頼に基づいて、政策レベルでスムーズに行われたことは前述の通りである。しかし、その後のプロセスにおいて、枠組み文書に記載されている「行動計画の策定」が行なわれていないこと、また、エジプトの例にみられるように費用分担化について今後の方向性の不透明さが懸念されている。さらに、チュニジアの事例でも、費用負担の適用範囲や会計上の手続きに関し共通認識を図る必要性が確認された。これらを踏まえ、対話等を通じて、同プログラムの策定プロセスにおける実務レベルの関係者の関与を高めることで、関係者間でパートナーシップ・プログラムの記述内容に関する共通認識が図られることが望ましい。
2)わが国の南南協力支援における協力受益国関係者との対話を促進する
案件形成及び実施プロセスは、実質的には、協力実施国政府及び協力実施国の日本側関係者の主導で行なわれているのが現状である。しかし、そもそも日本は、協力実施国と協力受益国の協力を支援する立場にあることから、これらが協力実施国関係者の主導のみで行なわれることは理論的に妥当でない。協力受益国政府及び協力受益国の日本側関係者の関与を高めることを目指し、案件形成及び実施プロセスを見直す必要がある。
3)費用分担化の原則による在外プロジェクト形成調査への影響
プロジェクトの実施のみならず在外プロジェクト形成調査においても、協力実施国との費用分担化が求められるようになっている。しかしながら、エジプトの事例に見るように、協力実施国政府側が費用負担できないケースもあり、その結果、JICAのみで在外プロジェクト形成調査を行なう事態が生じていることが確認された。プロジェクト形成調査は、案件形成のプロセスにおいて協力実施国および実施機関が協力受益国の現場を視察し、協力実施国と協力受益国が協議できる唯一の機会であることから、これを日本のみで行なうことは適切とは言えない。
4)南南協力支援のための協力実施国における体制強化の必要性
プロジェクト形成プロセス及び実施プロセスにみるように、南南協力支援政策は、その実施に際してJICA本部、在外事務所をはじめ、協力実施国政府機関、実施機関、協力受益国政府、協力受益国における受け入れ機関等、多くの関係者が関わるため、手続きが複雑であり、且つ膨大な事務的作業を伴う。例えば、本邦研修は、JICA本部、研修実施機関、被援助国政府の主に3者によりアレンジがなされるが、第三国研修は、協力実施国における日本大使館、JICA本部、JICA在外事務所、研修実施機関、協力受益国政府、協力実施国外務省に加え、場合によっては協力受益国における日本大使館、協力受益国JICA在外事務所等もアレンジに関与する。また、本邦研修は日本が実施費用を全額負担しているが、第三国研修ではそれを協力実施国と費用を分担しているため、JICA在外事務所は研修実施機関の作成した見積もり書の費用分担化について、協力実施国の政府(エジプトでは外務省)と協議しなければならない。エジプトでは、南南協力支援を主体的に担当するJICA企画調査員及びローカルコンサルタントによりこれらの業務に対処してきた。チュニジアの事例では、南南協力の窓口機関であるATCTの「調整役」としての役割が明確でないことが指摘されたが、今後同国に対する南南協力支援案件が増えるのであれば、エジプトの例を参考にJICAチュニジア事務所及び協力実施国政府の業務の実施体制及び分担を見直す必要があろう。
尚、参考まで、第三国研修の募集プロセスにおける遅延についても付記する。案件実施プロセスにおいては、第三国研修の研修生の「募集」に最も時間を費やしていることが確認された。上述した通り、研修生の募集は、基本的に協力実施国の外務省の役割であり、業務上、わが国の関与は限られているのが現状であるが、先ずはその原因を明らかにし、わが国としてどのような対応が可能であるか、今後、検討が必要である。
11パートナーシップ・プログラムを署名していない国では、政策協議等の場において南南協力支援に関する話し合いが行なわれている。
12OECD. Geographical Distribution of Financial Flows to AID Recipients
13JICA事務所、ATCT、日本大使館、チュニジア外務省、チュニジア国際開発協力省、また、必要に応じて、第三国研修実施機関や第三国専門家派遣機関が加わる。
14JICA研修事業部が作成中の「在外技術研修業務マニュアル」及びヒアリングを参考としている。
15同研究所には、現在、わが国のシニアボランティアが派遣されている。
16JICA研修事業部が作成中の「在外技術研修業務マニュアル」及びヒアリングを参考としている。

