南南協力支援評価調査
第3章 評価結果国内調査及び現地調査の結果を踏まえ、南南協力支援政策について、以下に政策の背景にある理論、政策実施のプロセス、政策の効果を検証する
3.1 理論の検証
本節では、わが国の南南協力支援政策が、わが国の開発援助の上位政策および協力実施国のニーズに沿って策定されていたかどうかについて検証する。
3.1.1 南南協力支援政策の日本の援助政策との整合性
わが国の南南協力支援は、1972年にタイで実施されていた第2国研修コースにラオスからの研修生の招聘を第一号として、JICAの「第三国専門家派遣」および「第三国集団研修(以下第三国研修)」を通じて行われている。また、1994年から現在までにわが国は、実施協力国8ケ国7と「パートナーシップ・プログラム8」を結び、プログラムレベルでの取り組みも行っている。さらに、わが国は、UNDPの「人造り基金」を通した南南協力支援への協力も行ってきた。
わが国の南南協力に対する取り組みがこれらのプロジェクト、プログラムの取り組みからより政策的に行われるようになったのは、1992年6月閣議により決定されたODA大綱及びこれを受けて1999年8月10日に公表されたODA中期政策の策定に始まる。
ODA大綱は、「1. 基本理念」、「2. 原則」、「3. 重点事項」、「4. 政府開発援助の効果的実施のための方策」、「5. 内外の理解と支持を得る方法」、「6. 実施体制」の6つの項目で構成されている。ODA大綱においては、「南南協力支援」に関する直接的な記述はないものの、「4. 政府開発援助の効果的実施のための方策」において 挙げられている ---(6)開発途上国の発展段階に適した技術移転等に資するため、必要に応じ当該技術に関する技術開発に取り組むとともに、他の開発途上国の有する知識や技術の十分な活用を図るための支援を行う(ODA大綱より抜粋)---がまさしく南南協力支援に該当する記述であると判断される。
ODA中期政策では、IV.援助手法「5.南南協力への支援」において、(1)新興援助国のドナー化支援による援助資源の拡大、(2)地域内協力(の推進への貢献)及び地域間協力の推進への貢献、(3)自然条件や言語等の類似した地域からの適正技術の移転が可能、(4)先進国で実施するよりも実施経費が安価であることを南南協力の利点として掲げた上で、わが国は南南協力を積極的に支援するという明確な方針を打ち出している。
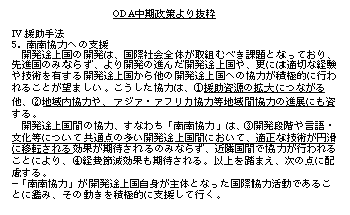
以上を踏まえ、わが国の南南協力支援政策のわが国のODA政策における位置付けを図に表すと、図3-1のようになる。
図3-1わが国ODAにおける南南協力支援の位置付け9
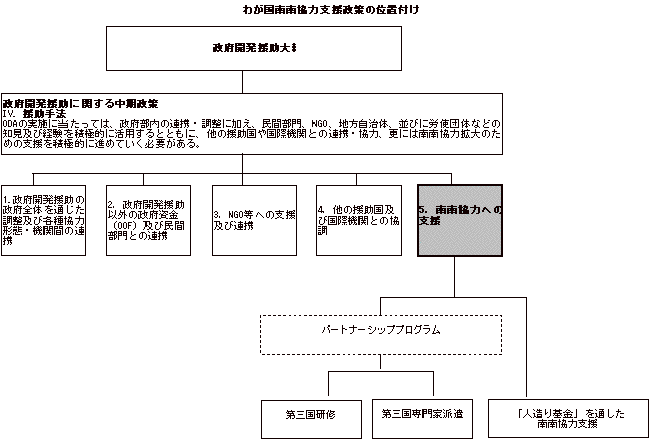
この他、わが国は、1998年10月に開催された第2回アフリカ開発会議10(TICADII)で策定された東京行動計画においてアジア・アフリカ間の南南協力の重要性が言及されたことを受けて、1999年6月に発表された対南アフリカ支援策において、南南協力に関する具体的な以下の施策を掲げている。
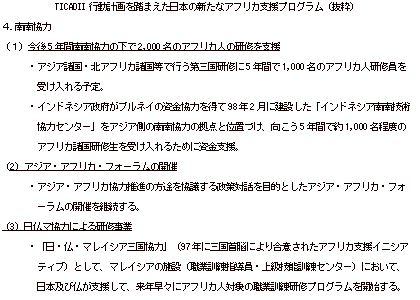
以上のことから、南南協力支援政策は、わが国の上位の援助政策及びわが国が国際的に合意した南南協力の方針に則していると判断される。
3.1.2 南南協力支援政策の協力実施国の要望との整合性
わが国の南南協力支援政策は、協力実施国からの協力が得られることによりその実施が可能となる。2003年2月現在までに8ケ国が、わが国と「パートナーシップ・プログラム」を結び、第三国研修のコース数や費用の分担、専門家の共同派遣等に関する中期的な目標・計画を設定し、南南協力に対して総合的に取り組むことを約束している。また、このような枠組み文書を取り交わしていない国についても、1996年から2000年度までに第三国研修については33ケ国、第三国専門家派遣については12ケ国が協力実施国としての役割を担ってきた。さらに、98年5月に開催された「南南協力支援会合」(外務省/JICA共催)においては、出席したアジア、中南米、アフリカ、中近東の世界各地域の協力実施国15カ国より、南南協力の規模を拡充したいとする強い希望が表明された。これら協力実施国の対応状況からみて、わが国南南協力支援政策が協力実施国に受け入れられているものと判断される。
3.1.3 結論
本節では、南南協力支援政策が日本の政策方針及び協力実施国の要望に整合しているかどうかについて検証した。その結果、わが国の南南協力支援政策は、わが国の上位の援助政策であるODA大綱、ODA中期政策及びTICADII等のわが国が国際的に合意した南南協力の方針に則していること、また、協力実施国の国内政策や外交政策にも則していることから、わが国が今後とも右政策を支援していくことについての理論的整合性が認められる。
7 シンガポール、タイ、エジプト、チュニジア、ブラジル、チリ、アルゼンチン、フィリピン
8 「三角協力枠組み」という名称を用いる場合もあるが、内容が類似しているため、通常「パートナーシップ・プログラム」と呼称している。なお、エジプトは、99年4月のムバラク大統領の訪日時に、首脳レベルで発表された「日本・エジプト共同声明」の中で「日本・エジプト・パートナーシップ・プログラム」を発表しているが、これは上述の「パートナーシップ・プログラム」と異なる内容のものである。 9 パートナーシップ・プログラムが点線で表示されている理由は、2003年3月現在、8ヶ国のみが同プログラムに署名しているため。
9 パートナーシップ・プログラムが点線で表示されている理由は、2003年3月現在、8ヶ国のみが同プログラムに署名しているため。
10 98年10月に第2回アフリカ開発会議(TICADII)は、アフリカ諸国の経済・社会開発や貧困削減と国民の生活水準向上を促すことを目的として、日本、国連(アフリカ及び最貧国特別調整室(OSCAL)及び国連開発計画(UNDP))並びにアフリカのためのグローバル連合(GCA)の共催の下、東京で開催された。80ヶ国、40国際機関、22NGO団体が参加した(そのうち、元首・首脳15名)。

