南南協力支援評価調査
第2章 わが国南南協力支援の実績(1995年?2001年)と特徴2.1 わが国南南協力支援の概要
2.1.1 世界の潮流~南南協力の始まりとこれまでの経緯~
1970年代、北から南への協力関係を補完するため、途上国間で水平協力をしようという動きが高まった。従来、開発途上国の発展には先進国からの資金・技術援助の提供に依存せざるを得ないとの考えが主流だったが、1970年代の石油輸出国機構(OPEC)、新興工業経済地域(NIES)等の出現にみられるように、途上国の多様化が進み、途上国相互間の協力の重要性が認識されるようになった。1972年には、非同盟諸国(NAM)1外相会議において「途上国間経済協力に対する非同盟行動プログラム」が採択され、1974年の国連資源・開発特別総会では、「新国際経済秩序の樹立に関する宣言」が採択された。
このような情勢の変化を受け、1970年代には、国連システムの中で南南協力を支援する枠組みが形成された。国連開発計画(UNDP)は、1974年の国連総会を契機にSpecial Unit for Technical Cooperation among Developing Countries (SU/TCDC)を設置し、1975年に開催された委員会で、南南協力に対する各国政府の関与と技術協力プログラムの実施に関する方針「New Dimension」を採択した。また、1978年、ブエノスアイレスで開催された「途上国間協力に関する国連会議」で「途上国間協力の推進と実施のためのブエノスアイレス行動計画」が採択され、開発途上国間技術協力(Technical Cooperation among Developing Countries: TCDC)の概念が整理された。同行動計画は、「国際機関及び先進諸国は途上国間協力に貢献できるような開発途上国(機関)に対し、財政支援等を与えること」、「途上国間協力を支援するために技術協力に関する政策や手続きを改善すること」等、途上国間技術協力の推進に関し採るべき行動として38項目からなる具体的措置を勧告している。
1970年代の南南協力に関する世界的な潮流を踏まえ、1980年代以降も、南南協力について、活発な議論や活動が展開された。Group of 77 (G77)2は、1981年、途上国間経済協力に関する「カラカス行動計画」を、1997年には、その見直しとなる「サンホセ行動計画」を含む各種南南協力関連の決議・宣言を採択し、南南協力の推進に向けた取り組みを「南」側の集団的自助という観点から積極的に行っている。最近では、2000年4月に、第1回「南サミット」を開催し、グローバリゼーションのもたらす課題に対応するための有効な手段の一つとして南南協力の重要性を強調している。
「南」委員会(The South Commission)3は、1990年の最終会合で「南への挑戦(The Challenge to the South)」を採択し、南の諸国が互いに手を携え、「南」の国と「北」の国との二国間の関係ではなく、集団での働きかけを行うことによって、「北」の諸国が支配する国際経済体制の変革を要求していこうという文脈から、南南協力の必要性を説いた。
UNDPは、ブエノスアイレス国連会議以降も、南南協力の実施を推進する国際機関として、途上国間技術協力に関する活動を積極的に行っている。1996年には「NEW Directions for TCDC」を発表し、国際情勢の変化に併せ新しい南南協力の方向性に関する提案を行っている。また、2001年1月、途上国間技術協力に関する第2次協力枠組み(2001-2003)を採択し、今後この枠組みに基づき南南協力を推進していく予定である。
上記のような南南協力を取り巻く世界的な動向の中で、わが国は、1992年に閣議決定された「政府開発援助大綱(以下ODA大綱)」において、開発途上国が有する知識や技術の十分な活用を図るための支援を行うことがODAの効果的実施の方策であるとの方針を表明した。また、1999年に発表された「政府開発援助に関する中期政策(以下ODA中期政策)」の中では、南南協力支援を有効な援助手法の1つと位置付け、南南協力拡大のための支援を積極的に進めていく必要があると論じている。
2.1.2 南南協力の定義とわが国の協力形態
南南協力は、開発途上国がお互いの優れた開発経験や技術を学習し共有することによって、開発を効果的に進めるための協力形態である。一般に、開発途上国同士の技術協力を指す「開発途上国間技術協力(Technical Cooperation among Developing Countries: TCDC)4」と、政府間経済協力及び民間セクターによる投資・貿易分野の開発途上国間協力を指す「開発途上国間経済協力(Economic Cooperation among Developing Countries: ECDC)5」の2つを含めた概念として使われている。
わが国の南南協力支援は、国際協力事業団(JICA)を通して実施される(1)第三国研修、(2)第三国専門家派遣、が主な協力形態となる他、(3)パートナーシップに基づく支援、(4)UNDPの「人造り基金」を通した支援、(5)国際会議の開催による支援に分類される。JICAは前述の協力スキームの他、カンボジアにおける三角協力プロジェクトや、メキシコでの専門家チーム派遣を通した南南協力の実施体制強化等の協力も展開している。
わが国の南南協力支援は、主に、ODA技術協力の実施機関であるJICAの協力スキームを通して実施されており、その他の協力形態による支援も技術移転を通した人材育成や能力強化を目的に行われる場合が大半である。このため、わが国の開発協力のコンテクストの中で語られる「南南協力」支援は、「開発途上国間技術協力(TCDC)」への支援を意味する場合が多い。
|
BOX(1) アフリカ開発会議(Tokyo International Conference on African Development)
アジア・アフリカ間協力 わが国は、1993年10月に「アフリカ開発会議(TICAD)」、1998年10月に「第2回アフリカ開発会議(TICADII)」を開催した。各会議で採択された「東京宣言」及び、「東京行動計画」の中で、南南協力の一つの具体化として、アジア・アフリカ間の協力推進の重要性が提唱されている。 わが国は、TICADIIで採択された東京行動計画を踏まえ、新たなアフリカ支援プログラム(「TICADII行動計画を踏まえた日本の新たなアフリカ支援プログラム」)を発表した。同プログラムの中で、アジア・アフリカ間の南南協力を推進するため、(1)南南協力支援のもと、5年間で2000名のアフリカの人材に研修の機会を提供する、(2)アジア・アフリカ・フォーラムの開催を継続する、(3) 「日・仏・マレイシア三国協力」6による研修事業を通しアフリカの人材育成に貢献する、ことを表明した。 アジア・アフリカ・フォーラムは、TICADの「東京宣言」を契機に、1994年以降アジア・アフリカ間の協力推進の方途を協議する政策対話を目的とし、わが国と国連等との共催で開催されている。1994年は、インドネシア、バンドンで、第1回フォーラムが開催され、アジア・アフリカ協力の基本原則を提示する「アジア・アフリカ協力のためのバンドン・フレームワーク」が採択された。第2回フォーラムは、1997年、タイ、バンコクで開催され、第1回フォーラム以降の両地域間の協力の現状を踏まえ、より具体的な施策提言となる「バンコク宣言」が採択された。さらに、2000年5月には、TICADIIの「東京行動計画」でアジア・アフリカ間の南南協力の重要性が再確認されたことを受け、第3回アジア・アフリカ・フォーラムがマレーシアで開催された。第3回フォーラムでは、農業セクター及び民間セクターに関し、「能力強化・人造り」と「情報テクノロジー推進」という2つのテーマに沿って、アジア・アフリカ協力促進のための政策対話が行われ、「クアラルンプール・ニュー・ミレニアム・ステートメント」とその別添の勧告が採択された。同フォーラムの中で、わが国は、国連ボランティア(UNV)をアジアからアフリカに派遣するTICAD/UNボランティアプロジェクト、アフリカ諸国のIT開発とアジア・アフリカネットワーク拡充のためのプロジェクトを提唱した。 |
2.2 協力形態別にみたわが国南南協力支援の実績と特徴(1)
~JICA事業を通した南南協力支援~
2.2.1 第三国研修
第三国研修は、開発途上国の中でも比較的開発が進んだ段階にある国を拠点とし、周辺国等から研修員を受入れ、研修を実施し、技術を移転、普及する協力スキームである。1975年、タイの養蚕研究研修センターでラオスの研修員4名を対象に研修を実施したことをきっかけに始まり、現在は、わが国の南南協力支援の中心的な協力形態となっている。
第三国研修には、集団、個別の二つの形態がある。第三国集団研修では、当該技術分野における他の途上国の人員を一同に集めて研修を実施している。第三国個別研修は、主としてJICAが支援するプロジェクトや個別派遣専門家のカウンターパートを対象とし、日本での実施と比較して第三国での研修の方が効率的、効果的であると判断された場合に実施している。
図2-1は、1994年から2001年までの、第三国集団研修のコース数と参加者数の推移を示している。コース数は、1994年度以降、継続して増加傾向にある。参加者数は、2000年度に入り、若干の減少はみられるものの、1998年度以降、毎年2000人代を維持している。
図2-1 第三国集団研修の実績の推移(1994-2001年度)
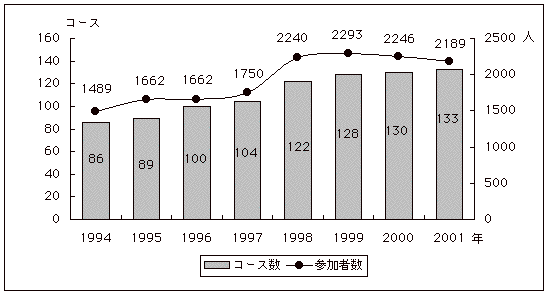
出所:JICA企画・評価部「JICA事業における南南協力支援の概要(暫定)」平成14年10月
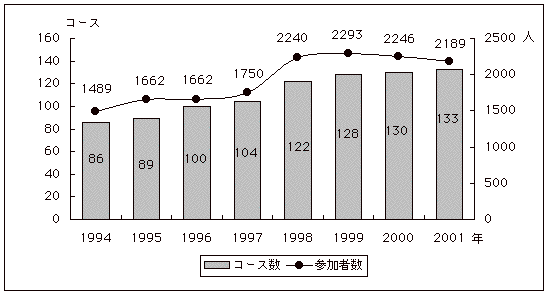
出所:JICA企画・評価部「JICA事業における南南協力支援の概要(暫定)」平成14年10月
図2-2は、第三国集団研修の実施地域のシェアを1990、1995、2000、2001年度で比較している。実施地域の中では、従来より、アセアン地域のシェアが40~50%と大きく、この傾向は近年も変わっていない。また、近年、アフリカ地域で実施される第三国集団研修案件のシェアが増加している。
図2-2 第三国集団研修の実施地域シェアの推移
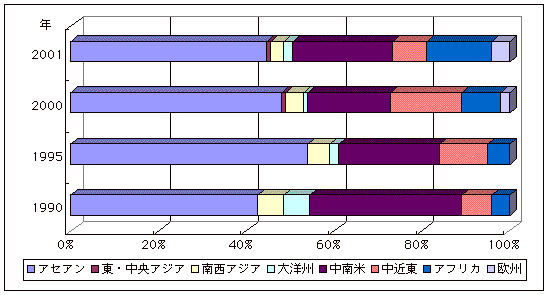
出所:JICA企画・評価部「JICA事業における南南協力支援の概要(暫定)」平成14年10月
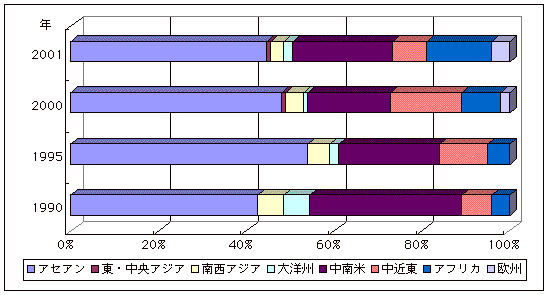
出所:JICA企画・評価部「JICA事業における南南協力支援の概要(暫定)」平成14年10月
図2-3は、第三国集団研修案件の分野別シェアの推移を示している。研修分野の中では、従来から農林水産分野のシェアが大きく、この特徴は続いている。また、近年、公益・公共事業分野が徐々に減少し、商業・観光分野が増加傾向にある。
図2-3 第三国集団研修実施分野の推移
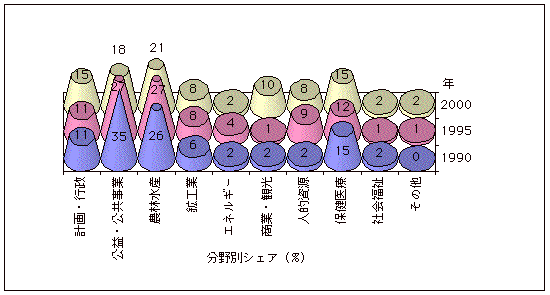
出所:JICA企画・評価部「JICA事業における南南協力支援の概要(暫定)」平成14年10月
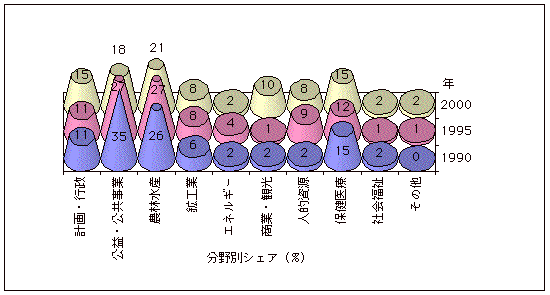
出所:JICA企画・評価部「JICA事業における南南協力支援の概要(暫定)」平成14年10月
2.2.2 第三国専門家派遣
第三国専門家派遣は、南南協力支援の一環として、日本の技術協力を補完・支援、または日本が実施した技術協力の成果を普及・発展することを目的に、開発途上国で、他の途上国の優れた人材を専門家として活用する制度である。1995年度に10名の派遣から開始されたが、以後、派遣者数は年々増加し(図2-4)、2000年度は125人、2001年度は118人を派遣した。
図2-4 第三国専門家派遣人数の推移(1995-2001)

出所:JICA企画・評価部「JICA事業における南南協力支援の概要(暫定)」平成14年10月

出所:JICA企画・評価部「JICA事業における南南協力支援の概要(暫定)」平成14年10月
図2-5は派遣元地域別に、図2-6は派遣受入地域別に、第三国専門家数の推移を示している。近年、中南米地域を派遣元とする第三国専門家が増加している。アジア地域を派遣元とする第三国専門家は、1990年代後半に増加したものの、2000年代に入り、若干減少傾向にある。
第三国専門家の受入は、年によってバラツキはあるものの、1990年代後半からアフリカ地域で増加している。また、中南米地域でも増加傾向にあり、上記派遣元地域の増加傾向に鑑み、中南米地域内の第三国専門家派遣が増加していることがわかる。
図2-5 派遣元地域別第三国専門家数の推移
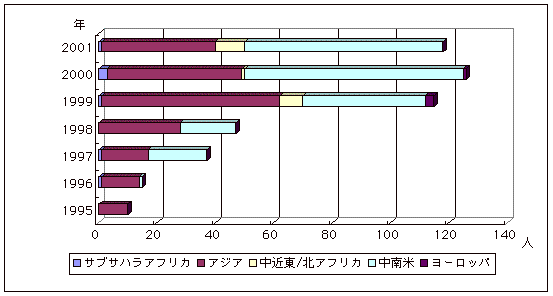
出所:JICA企画・評価部. 第三国専門家実績(1995-2001年度)
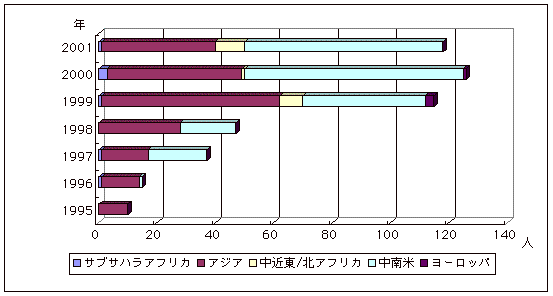
出所:JICA企画・評価部. 第三国専門家実績(1995-2001年度)
図2-6 受入地域別第三国専門家数の推移
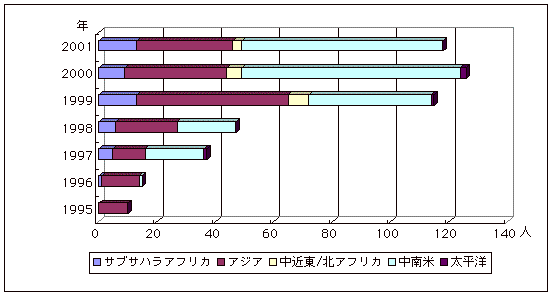
出所:JICA企画・評価部. 第三国専門家実績(1995-2001年度)
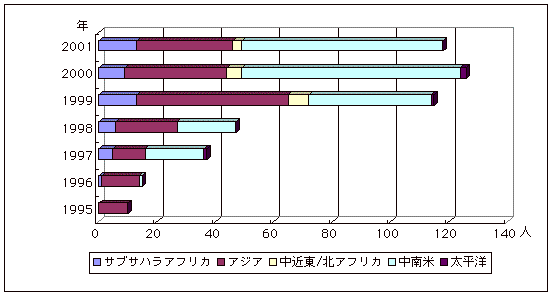
出所:JICA企画・評価部. 第三国専門家実績(1995-2001年度)
2.2.3 その他のJICA事業を通した南南協力支援
(1)三角協力プロジェクト「カンボジア農村開発計画」
「三角協力プロジェクト」は、わが国が他の援助国・援助機関と共同で、途上国における協力事業を実施するものである。わが国は、1992年、カンボジア和平協定後、同国コンポンスプー県及びタケオ県周辺を対象とし、農村基盤整備・農村地域開発による帰還難民等の生活向上を目的に、上記プロジェクトを実施している。
プロジェクト対象地域内に整備した施設を拠点とし、日本人専門家、青年海外協力隊、アセアン諸国の専門家が、農業、生計向上、教育、公衆衛生と多角的なアプローチで農村開発協力活動を実施している。アセアン諸国の専門家派遣については、UNDPの「人造り基金」を活用し、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ等から数名ずつ招聘している。高温多湿という気候や、農村の社会開発に共通項が多いアセアン諸国の専門家の協力により、効果的な技術移転が可能となっている。
(2)メキシコの南南協力実施体制の強化
1988年以来、メキシコ政府は周辺国への専門家派遣等を通した南南協力を積極的に展開してきた。わが国は、メキシコ政府の南南協力の実施体制を強化するため、1997年から協力を開始し、1999年にはメキシコ国際協力庁の組織強化等を目的とした専門家チーム派遣による協力を3年間の計画で開始した。具体的な協力内容として、計画策定、実施、モニタリング・評価と一連のプロジェクト管理に係る制度設計、データベースの構築、PCM手法の導入、関係機関のネットワーク化、国内広報の強化を支援している。また、この協力の過程で、日本とメキシコによる周辺国への三角協力プログラムを立ち上げていくことも視野に入れている。
(3)アフリカ人造り拠点(AICAD)
1998年10月のTICADIIで提唱した構想に基づき、わが国は2000年から「アフリカ人造り拠点(AICAD)」をケニアのジョモ・ケニヤッタ農工大学に設置し、周辺諸国の大学、政府機関、NGO等と連携しながら、アフリカ地域に貢献する研究、人材育成、情報発信を目指す協力を実施している。
1981年に設立された同農工大学は、無償資金協力やプロジェクト方式技術協力等を通し、20年以上にわたりわが国の援助を受けてきた。AICADは、貧困削減等、現在アフリカ諸国が抱える開発課題だけでなく、将来、直面すると想定される課題への対応も含め、(1)研究開発、(2)人材育成、(3)情報発信を行い、国境や属性を越えた拠点づくりを目指している。プロジェクトは2年間の準備フェーズを経て、現在5年間の第2フェーズに入っており、東アフリカ三ヶ国(ケニア、タンザニア、ウガンダ)の参加を得ている。
2.3 協力形態別にみたわが国の南南協力支援の実績と特徴(2)
~パートナーシップ・プログラム、「人造り基金」、国際会議を通した南南協力支援~
2.3.1 パートナーシップ・プログラム
わが国は、南南協力の促進を目指し、特定の南南協力の実施国と共同で周辺の受益国へ協力を行うため、総合的な枠組みを政府間で合意し、枠組み文書の署名を交わすパートナーシップ・プログラム制度を設けている。2002年までに、わが国は、タイ、シンガポール、エジプト、チュニジア、チリ、ブラジル、アルゼンチン、フィリピンの8ヶ国と同プログラムの枠組み文書に合意している(表2-1参照)。
表2-1 パートナーシップ・プログラムと概要
出所:JICA企画・評価部「JICA事業における南南協力支援の概要(暫定)」平成14年10月
| 名称 | 相手国 | 開始年 | 概要 |
| 日本・タイパートナーシップ・プログラム (Japan-Thailand Partnership Programme) | タイ | 1994 | 第三国集団研修を2000年までに15コース、250人に拡大することを目標。現在更新に向けて交渉中。 |
| 21世紀のための日本・シンガポール・パートナーシップ・プログラム(Japan-Singapore Partnership Programme for the 21 Century) | シンガポール | 1997 | 2001年10月に更新。2002年度、17コースの共同研修の他、カンボジアで共同セミナーの実施等を合意。 |
| 日本・エジプト三角技術協力計画(Japan-Egypt Triangular Technical Cooperation Programme for the Promotion of South-South Cooperation in Africa) | エジプト | 1998 | 2002年度の計画では、農業、保健医療分野等6コース、89人の第三国集団研修を実施すると共に14人の第三国専門家をアフリカに派遣予定。 |
| 日本・チュニジア三角技術協力計画 (Japan-Tunisia Triangular Technical Cooperation Programme for the Promotion of South-South Cooperation in Africa) | チュニジア | 1999 | 2002年度は第三国研修3コース、第三国専門家3人の派遣を実施。リプロダクティブヘルス、水産業、環境分野で仏語圏アフリカへの協力を実施中。 |
| 日本・チリパートナーシップ・プログラム (The Japan-Chile Partnership Programme) | チリ | 1999 | 中南米を対象としたニーズ調査、第三国研修、第三国専門家、合同研修等を実施。ボリビアの鉱業、ペルーの養殖等特定テーマに関する協力も推進。 |
| 日本・ブラジルパートナーシップ・プログラム (The Japan-Brazil Partnership Programme) | ブラジル | 2000 | 初期段階ではポルトガル圏アフリカを協力対象とすることで合意。2001年に保健と農業分野で合同研修を開始。 |
| 日本・アルゼンチンパートナーシップ・プログラム(Partnership Programme for Joint Cooperation between Japan and Argentina) | アルゼンチン | 2001 | ニーズ確認のため周辺国に対する合同調査を予定。 |
| 日本・フィリピンパートナーシップ・プログラム (The Japan-Philippines Partnership Programme) | フィリピン | 2002 | 東チモール協力の具体的案件形成のため、日比合同調査団を派遣する予定。 |
2.3.2 UNDPの「人造り基金」を通した南南協力支援
UNDPは、南南協力支援において、国連機関で中心的な役割を担っている。わが国は、UNDP内に設置した「人造り基金(Japan Human Resources Development Fund)」を通して、UNDPが進める南南協力支援に協力している。
わが国は、1986年、途上国の人的資源開発を目的として、UNDPに「人造り基金」を設置し、貧困撲滅、生活手段の確保、環境保全、グッド・ガバナンスの確立、女性の地位向上の5分野を中心に、2001年度までに累計で6,400万ドルを拠出してきた。1996年以降、南南協力を推進するため、毎年、本基金の約半分の使途を南南協力に使途を指定し、途上国の行政機関を中心とした組織の機能強化と個人の能力強化、途上国間で経験を共有するための情報システムの改善と強化、持続可能な人間開発のための事業等を支援している。特に1998年以降、本基金を活用し、TICADIIのフォローアップのため、アジア・アフリカ協力を中心とした南南協力の拡充を図っている。
表2-2 UNDPの人造り基金を通した南南協力支援の分野別承認額(1996-2001)
出所:UNDP. 2001. South-South Cooperation Under the Japanese Human Resources Development Fund 1996-2000
| 分野 | 承認額(米ドル) | % |
| 貧困削減 | 7,337,205 | 45.7 |
| 貿易・投資 | 5,476,344 | 34.1 |
| 援助マネジメント | 2,230,679 | 13.9 |
| マクロ経済政策 | 648,000 | 4.0 |
| 環境 | 349,000 | 2.2 |
| 債務 | - | - |
| 生産・雇用 | - | - |
| その他 | - | - |
| 合計 | 16,042,028 | 100.0 |
表2-2は、「人造り基金」を通した南南協力支援の分野別承認額を、図2-7は、承認額の分野別シェアの推移を示している。協力分野の承認額は、年度によってバラツキがあるが、1996年から2001年までの承認額を合計すると、貧困削減分野での協力が全体の45.7%を占め最も多く、次いで貿易・投資分野の協力が多い(34.1%)ことがわかる。
図2-7 UNDPの人造り基金を通した南南協力支援の分野別承認額の推移(1996-2001)
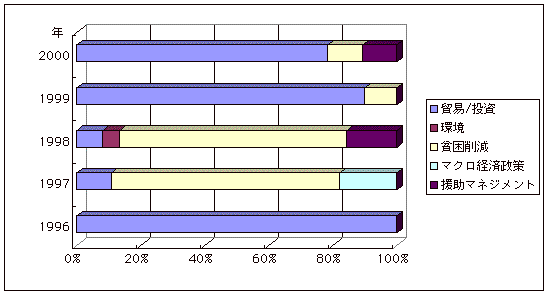
出所:UNDP. 2001. South-South Cooperation Under the Japanese Human Resources Development Fund 1996-2000
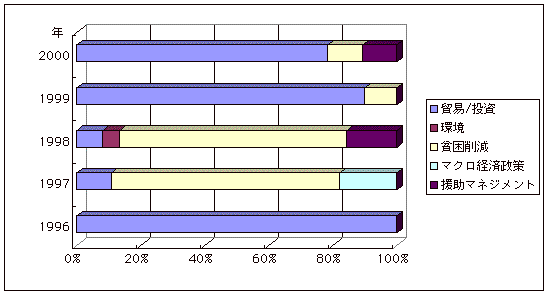
出所:UNDP. 2001. South-South Cooperation Under the Japanese Human Resources Development Fund 1996-2000
図2-8は、「人造り基金」へのわが国の拠出金と、南南協力支援に使途を指定された拠出金の推移を示している。「人造り基金」への拠出金に占める南南協力支援分の割合は、50%前後とほぼ一定であるが、2000年以降、「人造り基金」自体へのわが国の拠出金が減少していることから、これを通した南南協力支援への拠出金額も減少している。
図2-8 UNDPの人造り基金を通した南南協力支援拠出金の推移(1996-2001)
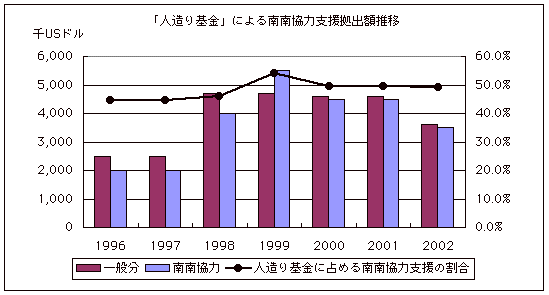
出所:UNDP. 2001. South-South Cooperation Under the Japanese Human Resources Development Fund 1996-2000
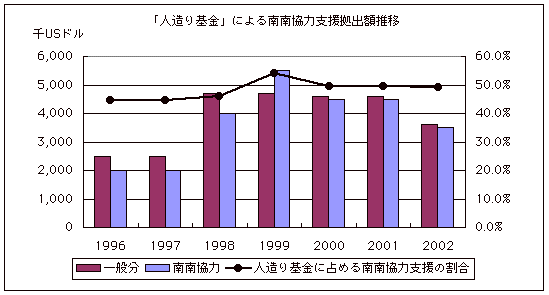
出所:UNDP. 2001. South-South Cooperation Under the Japanese Human Resources Development Fund 1996-2000
2.3.3 国際会議等の開催を通した南南協力支援
(1)南南協力支援会合
わが国は、1998年5月、外務省とJICAの共催により、沖縄で、南南協力支援会合を開催した。本会合は、新興援助国の南南協力における経験・ノウハウの共有を図り、実施面での共通の課題を明らかにし、また南南協力を拡充するために必要な制度・体制のあり方を議論することを目的としており、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、韓国、中国、トルコ、エジプト、チュニジア、ケニア、メキシコ、ブラジル、チリ、アルゼンチン、15ヶ国の参加を得た。
本会合を通して、参加各国は、南南協力を実施するうえで直面している課題について討議し、各国の経験・ノウハウの共有が図られる等、大きな成果が得られた。また、参加国は、南南協力に関するネットワークを強化する重要性を確認し、今回の会合の成果をフォローアップするため、今後も同様の会合を開催することに合意した。また、本会合を通し、TICAD IIへの積極的参画の呼びかけが行われると共に、わが国とのパートナーシップ・プログラムの対象国拡大等の方向性が打ち出された。
(2)シンポジウム「21世紀の開発協力-南南協力支援のあり方」
本シンポジウムは、2001年10月、JICA、UNDP共催により、開発途上国の南南協力実施機関及び窓口機関とドナー機関の参加を得て、東京で開催された。本シンポジウムは、実務者ワークショップと一般公開シンポジウムの2部で構成されている。実務者ワークショップでは、参加国の南南協力の事例が紹介され、これを踏まえた南南協力及びその支援に関し意見交換が行われた。特に、ITを活用したネットワークの構築等の具体的手法や、持続可能性、政策支援、効果的な評価、受益者の参加等、共通課題について活発な議論が交わされた。
一般公開シンポジウムは、有識者、NGO、学生、在京大使館等、幅広い層から約130名の参加者を得て行われ、JICA、UNDPによる南南協力支援の成果について事例の紹介を中心にプレゼンテーションが行われた。
(3)「持続可能な開発に関する世界首脳会合(WSSD)」におけるワークショップ開催
2002年9月、南アフリカ共和国で開催されたWSSDで、JICAは、わが国の南南協力支援に関するワークシップを開催した。本ワークショップでは、南南協力支援に対するわが国の取り組みについてプレゼンテーションを行うと共に、わが国の南南協力支援案件のカウンターパートが、タイ、チュニジア、チリ、ケニアでのわが国の支援による南南協力の事例を紹介した。本ワークショップには、途上国政府関係者、NGO等も含め140名以上が出席し、南南協力実施にあたっての周辺国に対するアプローチの方法やアジアの経験のアフリカへの適用等について、活発な質疑応答が行われた。
1 Non-Aligned Movement、1961年に設立された。
2 1964年、第一回国連貿易開発会議において、開発途上国77ヶ国が連帯して共通の経済的利益を追及することを目的に発足した。
3 開発途上国の著名な政治家・学者・外交官等27人で構成される独立した国際委員会。1987年に設立された。現在は、「南」委員会の後継組織として南センター(The South Centre)が「南」側諸国に対し、国際経済、社会、政治にかかる情報、分析結果、助言の提供を行っている。
4 途上国間技術協力(TCDC)は、必要に応じて国連や二国間ドナー等の外部からの助言と財政支援を受け、途上国が相互に経験と技術能力をシェアする途上国組織による開発活動及びプロジェクトの実行と運営を指す。
5 途上国間経済協力(ECDC)は、先進国の支援に頼ることなく開発途上国の間の協力により自らの開発を促進しようとするもの。幅広く、民間セクターや投資・貿易を含む概念。
6 途上国間経済協力(ECDC)は、先進国の支援に頼ることなく開発途上国の間の協力により自らの開発を促進しようとするもの。幅広く、民間セクターや投資・貿易を含む概念。

