南南協力支援評価調査
第1章 調査の概要1.1 調査の背景
1.1.1 調査実施経緯
わが国の政府開発援助(ODA)は、国際貢献の重要な柱の一つであり、支援規模は世界のトップクラスに位置づけられる。一方、近年、国内の厳しい経済状況を背景に、より効率的・効果的な援助の実施が求められ、ODA評価の重要性が増大している。
このような中、評価体制の改善に向けた議論が活発化し、2000年3月には、外務省経済協力局長の私的諮問機関である評価検討部会が、外務大臣に宛てて「ODA評価体制の改善に関する報告書」を提出した。その中で、政策レベル評価の導入、プログラムレベル評価の拡充、評価の一貫性の確保(事前から中間、事後に至る評価システムの確立)等が提案された。
政策レベル評価の制度については、その骨格が順次形成されつつある。1998年、中央省庁等改革基本法が成立し、2001年には「行政機関が行う政策評価に関する法律」(通称政策評価法)が成立した。ODA事業については、既に20年以上に亘り、プロジェクト評価を中心に各種評価が行われているが、政策評価法の成立を受けて、政策、プログラムレベルの評価が評価制度の中で明確に位置づけられ、一層強化されるようになった。
このようなODA評価を巡る一連の動きを背景に、外務省では、政策、プログラムレベル評価への取り組みに向けた努力がなされている。その一環として、2000年度には「政策レベル及びプログラムレベル評価の手法等に関する調査研究」を実施した。今回の評価調査もこの流れに則し、政策レベル評価を行うものである。わが国のODAにおける政策レベル評価は、国別評価と重点課題別評価であり、前者はわが国の国別援助計画など国別に策定されたODAの基本政策に関する評価、後者はわが国が提唱した重点課題別イニシアティブなど、重点課題別に策定されたODAの基本政策に関する評価である。
今回の評価調査は、重点課題別の政策レベル評価として南南協力支援を取り上げる。南南協力支援の重要性は1996年5月採択のDAC新開発戦略に明示されており、わが国のODA中期政策の中でも積極的に取り組むべき援助手法の一つとして掲げられている。開発途上国が他の途上国に対し援助を行う南南協力は、援助の受益国にとってより適した技術移転を可能とし、また、途上国による技術協力は先進国が行なうよりも低コストである場合が多いことから開発資源の効率的な活用の点からも有効であると考えられている。さらに援助実施主体の裾野を広げ、援助実施国と受益国の間で地域内協力を推進する意義もある。
このようなさまざまな利点を持つ南南協力に対し、わが国は1970年代から支援してきており、現在、南南協力への支援を最も積極的に推進している援助国の一つとなっている。南南協力を支援するわが国の協力スキームとして第三国研修や第三国専門家派遣等が挙げられる。また、新興援助国がより主体的な援助国に移行できるよう総合的な協力の枠組みを定めて支援する「パートナーシップ・プログラム」が設けられている。さらに、国連開発計画(UNDP)内に設立した「人造り基金」の中からイヤーマークし、国際機関による南南協力支援へも積極的に協力を行っている。1998年5月に南南協力支援会合、2001年9月にJICAとUNDP共催「21世紀の開発協力-南南協力支援のあり方」を開催した他、第2回アフリカ開発会議(TICAD II)で策定された東京行動計画においては、アジア・アフリカ間の南南協力を重点とする等、南南協力を積極的に推進してきている。
南南協力支援がわが国のODA中期政策の中で重要な援助手法として明示されてから3年を経た現在、本調査においてわが国の南南協力支援政策を総合的に整理・分析・評価し、今後のわが国の南南協力支援の質的向上に資することが求められている。
1.1.2 調査の目的
上述の経緯を踏まえ、本調査は、(1)これまでのわが国の南南協力支援政策に関する取り組み及び実施体制について総合的かつ包括的に評価し、(2)今後の南南協力支援政策の企画、策定及び実施を行っていくうえで実行可能な具体的提言をまとめる、ことを目的とする。さらに、本調査結果が、わが国のODA関係諸機関にフィードバックされ、今後のわが国の南南協力支援が一層効果的、効率的に実施されることを目指す。
1.1.3 調査の対象範囲
本調査では、政策レベル評価を行った。わが国の南南協力支援政策は、1999年に発表されたODA中期政策の中で言及されている。政策評価の枠組みの中で「政策」は、政策、プログラム、プロジェクトの総体とみなされることから、本評価調査では、ODA中期政策が発表された1999年以降に実施された南南協力支援プログラム及びプロジェクトを評価対象とした。一方、過去の経緯を踏まえ、また中期政策発表以前と以後を比較するうえで、第三国専門家派遣制度が開始された1995年以降の南南協力支援プログラム及びプロジェクトの内容に充分留意しつつ評価を行った。左記を踏まえ、本調査で評価の対象となる「南南協力支援政策」を下図に示す。
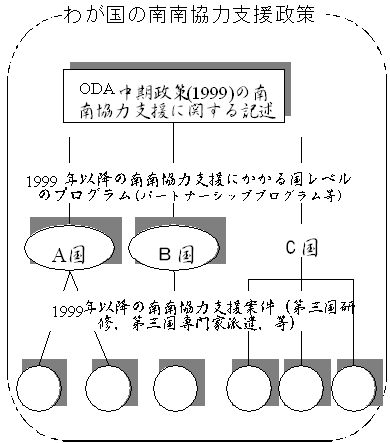
尚、本調査では、エジプト、チュニジア、セネガルを事例国として取り上げ、現地調査の対象国とした。エジプト、チュニジアが位置する北アフリカ中東地域では、近年、わが国の南南協力支援案件が増加傾向にある。また、エジプトはわが国の南南協力支援の協力実施国として歴史が長く、多くの第三国研修を実施した経験を有する。一方、チュニジアは、わが国の南南協力支援の新しい協力実施国として、1999年以降、案件数が徐々に増加している国である。協力実施国として経験豊富なエジプトと、新しい実施国であるチュニジアでの調査結果の比較を通し、今後の課題を分析することも試みた。また、エジプト、チュニジアを協力実施国とした南南協力支援案件の共通の受益国として、セネガルを取り上げ、わが国の南南協力支援政策の効果と、同政策プロセスへの受益国の関わり方について検証した。
1.2 評価の方法
1.2.1 評価手法~理論、プロセス、効果の検証と総合分析~
本調査では、政策レベル評価の手法に従いこれまでわが国が実施した南南協力支援政策について、政策の背景にある理論、政策実施のプロセス、政策の効果を検証すると共に、理論、プロセス、効果それぞれの評価結果を統括し、総合的かつ包括的に評価を行った。
理論の検証では、現時点における南南協力支援政策の妥当性を、わが国のODA政策との整合性から評価した。プロセスの検証では、南南協力支援プログラム及びプロジェクトの実施プロセスのメカニズムを整理、分析し、「適切性」と「迅速性」の観点から評価を行った。「適切性」を測るため、(1)政策プロセスへの関係者の参加、(2)協力実施国の比較優位性の把握、(3)協力受益国のニーズの把握、(4)協力実施国、受益国、わが国三者間の役割分担とその遂行、を分析の視点とし、これらが充分に行われたか否かについて検証した。「迅速性」については、南南協力支援の政策プロセスを(1)パートナーシップ・プログラムの策定、(2)南南協力支援案件の形成、(3)南南協力支援案件の実施に分類し、各プロセスが予定通り遂行されたか否かについて検証した。効果の検証は、政策目標の達成度合いと間接的・波及的効果の観点に分けて情報を整理、分析し、南南協力支援における成果と目標の達成度、効果の持続性について評価した。
これら理論、プロセス、効果の検証から得られた各評価結果を総合し、相互の関連性を整理、分析したうえで、教訓と提言をまとめた。
1.2.2 評価調査の手順
本調査では、(1)国内調査、(2)現地調査(エジプト、チュニジア、セネガル)、(3)国内解析、と3つに大別された手順に従って作業を進めた。各手順に含まれる作業内容を以下に概括する。
(1)国内調査
評価調査開始にあたり、調査方針、成果物、作業予定、有識者の選定等について、本調査の委託元である外務省評価室と打合せを行った。本調査は、有識者及び関係者の参加を得て勉強会を定期的に開催し、調査の進捗と方向性を確認しながら作業をすすめた。
次に、評価対象となる南南協力支援プログラム及びプロジェクトの実績に関するデータ、関連調査報告書、プログラム及びプロジェクト実施にかかる文書等、関連情報を収集、レビューした。また、関係者からの聞取り調査を行い、南南協力支援プログラム及びプロジェクト実施体制とプロセスについて情報を収集した。これら国内で収集したデータ及び情報を整理すると共に、本調査の評価枠組みを策定し、評価項目をまとめた。また、プログラム及びプロジェクトに関するデータは、分野別、地域別、援助スキーム別の観点で整理した。
上記で策定した評価枠組みと評価項目に従い、国内調査の結果も踏まえ、現地調査用の質問項目を策定した。現地出発前に、有識者及び関係者との勉強会を行い、現地での調査方針及び調査項目について確認した。
(2)現地調査
エジプト、チュニジア、セネガルにて現地調査を行った。調査団は2つのグループに分かれ、個々にエジプトとチュニジアでの調査を実施し、セネガルで合流した。
現地調査では、在外公館、JICA事務所、当該国関係政府機関、国際機関及び二国間ドナーを訪問し、質問票の内容に沿って聞取り調査を実施した。また、評価枠組みと調査項目に従い、現地関係機関から必要な情報、データを収集する。協力実施国であるエジプト、チュニジアでは、第三国研修講師及び第三国専門家を対象にフォーカスグループディスカッションを実施した。協力受益国であるセネガルでは、第三国研修参加者及び参加者の派遣機関を対象にフォーカスグループディスカッションを実施し、南南協力支援スキームの一つである第三国研修の効果について調査した。
現地調査で収集した情報、データを評価枠組みと調査項目に従って整理した。
(3)国内解析
国内調査及び現地調査で収集、整理した情報、データを、評価枠組みに従って分析した。分析結果をもとに、わが国の南南協力支援にかかる阻害要因と促進要因を整理し、教訓と提言をまとめた。
1.2.3 現地調査日程・主要訪問機関一覧
エジプト
| 月日 | 曜日 | 訪問先 | 面談者 |
| 1月11日 | 土 | 移動 | |
| 1月12日 | 日 | 移動 | |
| 1月13日 | 月 | 在エジプト日本大使館表敬 世界銀行事務所 JICAエジプト事務所 |
野口一等書記官 Mr. Gamal El-Kibbi, Senior Program Officer 下村所長、橋本所員 |
| 1月14日 | 火 | Egyptian for Technical Cooperation with Africa
(EFTCA) USAID |
Mr. Mortada A.M. Lashin, Deputy Secretary General Mr. Tarek El Meligy, Third Secretary 他2名 Ms. Linda Walker, Director of Training |
| 1月15日 | 水 | エジプト農業国際研修センター(EICA) JICA(専門家とのグループディスカッション) |
Mrs. Faten Khalil, Director General Mr. Magdi Abdel Tamad, Deputy Director General Dr. Fekry El-Keraby, Vice President of Agriculture Research Center (ARC) 梶原班長、清野専門家、浦山専門家、中川専門家 |
| 1月16日 | 木 | 計画省 | Ms. Asmaa Thabet, Head of Planning and Finance Sector |
| 1月17日 | 金 | 資料整理 | |
| 1月18日 | 土 | EFTCA、資料整理 | Mr. Tarek El Meligy, Third Secretary |
| 1月19日 | 日 | スエズ運河大学医学部 | Dr. Ahmed El-Gohary, Head of Clinical Pathology Dept. |
| 1月20日 | 月 | CETEC UNDP |
Eng. Mostafa Hegazy, Director General Ms. Sohie De-cean, Deputy Resident Representative Ms. Manuela Sler, UN Volunteers |
| 1月21日 | 火 | 中央冶金研究所(CMRDI) | Dr. Bahaa Zaghloul, Chairman |
| 1月22日 | 水 | 在エジプト日本大使館 JICAエジプト事務所 |
野口一等書記官 下村所長 |
| 1月23日 | 木 | 移動 |
チュニジア
| 月日 | 曜日 | 訪問先 | 面談者 |
| 1月11日 | 土 | 移動 | |
| 1月12日 | 日 | 移動 | |
| 1月13日 | 月 | 在チュニジア日本大使館 JICAチュニジア事務所 |
甲斐大使、大森書記官、池田書記官 伊禮所長、富澤所員、月井企画調査員 |
| 1月14日 | 火 | 開発国際協力省 外務省 チュニジア技術協力庁(ATCT) |
Mr. Jilani, Director General, Bilateral Cooperation,
Mr. Kammoun, Asia Dept. Head Amb. Goutari, Director for Asian Affairs 他3名 Mr, Bouhawala, Dorector General, Mr. Mokuni, Deputy Director他2名 |
| 1月15日 | 水 | 第三国専門家とのグループディスカッション UNDP |
Mr. Attia, Mr. Jouini Mr. Francais, resident representative |
| 1月16日 | 木 | 国家人口家族公団(ONFP) ONFPA長官表敬 第三国研修講師とのグループディスカッション(ONFP) |
Dr. Messaoud,Director 他1名 Prof. Gueddana, Director General他5名 |
| 1月17日 | 金 | チュニジア国立科学技術研究院・水・環境研究所(INRST) 第三国研修講師とのグループディスカッション(INRST) 在チュニジア日本大使館報告 JICAチュニジア事務所報告 |
Prof. Bennaceur, Director General Dr. Ghrabi 他5名 甲斐大使、大森書記官、池田書記官 伊禮所長、月井企画調査員 |
| 1月18日 | 土 | 資料整理 | |
| 1月19日 | 日 | 資料整理 | |
| 1月20日 | 月 | 移動 |
セネガル
| 月日 | 曜日 | 訪問先 | 面談者 |
| 1月20日 | 月 | 移動 | |
| 1月21日 | 火 | 在セネガル日本大使館 JICAセネガル事務所 |
西内書記官、反町書記官、中山書記官、谷井専門調査員 小西所長、天野次長、小森所員 |
| 1月22日 | 水 | 政府事務局技術協力局 UNDPセネガル事務所 外務省 |
Papa Birama Thiam 局長 M. Ahmed Rhazaoui代表 Papa Talam Diaoアジア課長、Coly Seckアフリカ課長 |
| 1月23日 | 木 | 国立漁業技術要請センター ダカール大学医学部 |
M. Alassane Ouma Ba所長 M. Doudou Thiam医学部長、Cheikh Soad-Bouh Boye医学副部長 |
| 1月24日 | 金 | 第三国(エジプト)研修受講者派遣機関関係者グループディスカッション 第三国(チュニジア)研修受講者派遣機関関係者グループディスカッション |
|
| 1月25日 | 土 | 資料整理 | |
| 1月26日 | 日 | 資料整理 | |
| 1月27日 | 月 | 第三国(エジプト)研修受講者のグループディスカッション 第三国(チュニジア)研修受講者のグループディスカッション |
|
| 1月28日 | 火 | JICA専門家グループディスカッション 政府事務局技術協力局 |
北村専門家、清水専門家、野田専門家、船場専門家 Papa Birama Thiam 局長 |
| 1月29日 | 水 | JICAセネガル事務所への報告 在セネガル日本大使館への報告 ダカール発(AF719) |

