南南協力支援評価調査
第4章 教訓と提言本節では、本調査で得られた調査結果をもとに、わが国南南協力支援政策に関する教訓と今後のあり方及び方向性についての提言をとりまとめる。教訓と提言は、「プロセスに関わる教訓と提言」及び「効果に関わる教訓と提言」の2つに分けて整理する。
4.1 プロセスに関わる教訓と提言
プロセスの検証においては、パートナーシップ・プログラム~実施計画の策定~案件形成~案件実施に至る一連のプロセスを総合的に検証した上で、以下の4点を指摘した。
(1)パートナーシップ・プログラムに関する継続的な対話の必要性
(2)わが国の南南協力支援における協力受益国関係者との対話を促進する
(3)費用分担化の制約によるプロジェクト形成調査への影響
(4)南南協力支援のための協力実施国における体制強化の必要性
これらの教訓に対して以下を提言する。
提言1:行動計画(Action Plan)を策定する(上述教訓の(1)に対応)
「パートナーシップ・プログラム」の署名により、わが国と当該協力実施国が協力し、南南協力を推進していこうとする方針が両国政府間で合意される。しかし、署名されたプログラムの内容は、今後の方針を表明するに留まり、具体的な内容は詳述されていない。このため、プロセスの検証でも指摘された通り、わが国と協力実施国の間で、費用分担化に関する見解の相違がみられ、また、窓口機関の役割が明確でなく実施体制が複雑化する等、案件の効率的な実施に課題が生じている。
パートナーシップ・プログラムに署名後は、同プログラムの内容について当該協力実施国との対話を通し、プログラムの適用範囲、目標、戦略等、を明確にする新しいプロセスが必要と考えられる。このプロセスにより、パートナーシップ・プログラムの内容に、両国間で共通認識を図ることが可能となる。このような新しいプロセスの一案として「行動計画」の策定が挙げられる。パートナーシップ・プログラムに署名後、わが国と協力実施国とが共同で今後の「行動計画」を策定する過程を通して、同プログラムの内容について、より詳細に共通認識を図り、具体的な方向性について合意形成できるものと考えられる。
現在は全く別々に行なわれているUNDPを通じた南南協力支援とJICAを通じた南南協力支援の位置付けや、南南協力支援以外の協力スキームとの連携、バランス等についても、上述のプロセスの中で明確にすることにより、パートナーシップ・プログラムのより効果的な実施が可能となる。
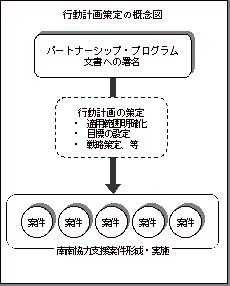
提言2:わが国の南南協力支援における協力受益国関係者の役割を明確化する (上述教訓の(2)に対応)
わが国の南南協力支援案件は、協力実施国とわが国関係者の主導で実施されており、わが国大使館およびJICA事務所を含む協力受益国関係者の関与は少ない。このことは、わが国の南南協力支援案件が、協力受益国ではなく、協力実施国の開発政策の文脈の中で形成されていることを反映している。
一方、セネガルの事例では、開発途上国は、協力受益国として第三国研修に研修生を派遣する際、わが国との外交関係を重視し、派遣を決定していることが確認された。これは、協力受益国が、協力実施国を通したわが国の南南協力支援を、わが国から協力受益国への開発協力の案件の形成、実施に盛込んでいくことが望ましい。
しかしながら、現行の協力スキームの中では、日本大使館、JICA在外事務所を含む協力受益国関係者が、南南協力支援案件の形成や実施にどのように関わるべきかについて明らかにされておらず、協力受益国関係者の関与が少ないままに留まっている。この点について、先ずはわが国の政策レベルで、南南協力支援において受益国関係者が果たすべき役割について明確にし、案件の形成、実施プロセスに受益国側の各関係者が積極的に関わることが可能となるメカニズムをつくることを提案する。
提言3:南南協力支援における「費用分担化」の原則に関する理解の共有(上述教訓の(3)に対応)
第三国研修の実施に際し、協力実施国が新興援助国である場合には、原則として費用分担化を行なっており、協力実施国の費用分担化の割合は、無償対象国15%、非無償対象国30%と設定している。しかしながら、エジプトの例にみられるように、新興援助国の経済は未だ不安定であり、決められた割合の費用分担化の実施が困難な状況に陥るケースや、また、国の経済、財政状況と案件の窓口機関の予算状況は必ずしも同じでないことも調査において明らかになっており、被援助国を無償対象国、非無償対象国に区分して一定の費用分担率を設定することに対して懸念が生じている。
協力実施国に「オーナーシップ」を持たせ、さらに共同で開発に取り組むという「グローバルパートナーシップ」の考え方に基づいて、費用分担化を行なうことは評価できるが、これが、南南協力支援政策の実施を妨げるような事態が生じることは、政策の意図と異なるものであり、望ましくない。
前述の通り、費用分担化については、無償対象国15%、非無償対象国30%と費用分担化の比率を設定しているが、相手国実施機関の状況等を踏まえ実態に応じた運用を行うことになっている。しかしながら、エジプトの事例において、在外プロジェクト形成調査における費用分担化が協力実施国の調査への参加の妨げになっていることが確認されたように、費用分担化について関係者間でさらなる協議が必要なケースが見受けられた。さらに、チュニジアの事例においては、わが国の費用分担化の適用範囲の明確化や会計上の手続きの効率化が必要であることも確認されている。
このような状況を踏まえ、外務省は、相手国実施機関の状況等に応じ、実態に応じた費用負担の運用を行なうことを改めて実施機関ならびに相手国政府に伝えること、また、費用分担化に関する具体的な適用範囲や内容につい関係者に対して説明する必要がある。
提言4:南南協力支援のための協力実施国における体制を強化する (上述教訓の(4)に対応)
南南協力支援政策は、JICAをはじめ、協力実施国政府機関、実施機関、協力受益国政府、協力受益国における受け入れ機関等、多くの関係者が関わるため、プロジェクトの形成、実施にかかる手続きが複雑であることに加え、見積もり、精算等の事務作業も膨大である。エジプトでは、南南協力支援を主体的に担当する企画調整員(1998年~)及びローカルコンサルタント(1985年~)を配置することで、このような問題に対処してきた。今後、わが国が南南協力支援政策を他国においても拡大していくためには、エジプトの例を参考として、必要に応じて協力実施国におけるJICA在外事務所の実施体制の強化を図っていくことが望まれる。
また、プロセスの検証でのチュニジアの事例で、南南協力の窓口機関であるATCTの「調整役」としての役割が明確でないことが指摘された。チュニジアのように協力実施国側の政府機関が複数にわたる場合は、予め各々の機関の役割分担を確認し、わが国と協力実施国政府との間に合理的な実施体制を構築することが重要である。この点は、パートナーシップ・プログラムの署名文書や、署名後に作成されるべき行動計画の中で、わが国南南協力支援における各政府機関の役割を明確にすることも一案と考えられる。
4.2 効果に関わる教訓と提言
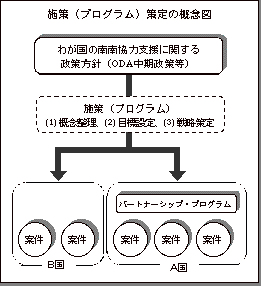 効果の検証においては、政策目標の達成度合い及び間接的効果の観点から検証した。その結果、政策目標の達成度合いについては、適正技術の移転、新興援助国の育成による援助資源の拡大、地域間協力の推進、ODA経費の削減において、各々効果の大きさは異なるものの、プラスの効果が確認された。また、間接的効果として、南南協力支援政策による、日本のプレゼンスの強化、ネットワークの構築、技術の再移転が確認された。これらプラスの効果をさらに高めることを目的として、以下の5点を指摘した。
効果の検証においては、政策目標の達成度合い及び間接的効果の観点から検証した。その結果、政策目標の達成度合いについては、適正技術の移転、新興援助国の育成による援助資源の拡大、地域間協力の推進、ODA経費の削減において、各々効果の大きさは異なるものの、プラスの効果が確認された。また、間接的効果として、南南協力支援政策による、日本のプレゼンスの強化、ネットワークの構築、技術の再移転が確認された。これらプラスの効果をさらに高めることを目的として、以下の5点を指摘した。
(1)新興援助国の育成の対象者の具体化
(2)地域間協力の推進の目的と戦略の具体化
(3)協力実施国と協力受益国の適切なマッチングの必要性
(4)パートナーシップ・プログラムの締結によるわが国のさらなる経費削減
(5)日本のプレゼンスの向上のための努力
これらの教訓に対して以下を提言する。
提言5:南南協力支援政策の概念、目標、戦略を明確にする(上記教訓の(1)、(2)に対応)
南南協力支援政策は、わが国の効果的な援助を目的として行なわれており、政策の成果として適正技術の移転、新興援助国の育成による援助資源の拡大、域内又は地域間協力の推進、ODA経費の削減等の効果が期待されていることは理論において検証した通りである。しかしながら、概念自体が明確には整理されておらず、南南協力支援政策の具体的な目標と戦略が明らかではない。例えば、ODA中期政策の中で、南南協力支援が「地域内協力や、地域間協力の推進にも資する」とされているが、これが誰の立場からのどのような推進を目指すのか、については、具体的に示す政策文書が無く、これに関する目標や戦略も明らかにされていない。また、本調査では南南協力支援政策の目標の達成度合いを、(1)新興援助国の育成による援助資源の拡大、(2)域内又は地域間協力の促進、(3)適正技術の移転、(4)ODA経費の削減の4つの観点を指標として検証したが、これらの指標にはODAの効率性に関するものと効果に関するものとが混在しており、十分整理されていないのが現状である。このため、効果的な南南協力支援を目指しつつも、その効果を図る指標が不明瞭で、目標の達成度を明確に示すことが困難な状況にある。
南南協力支援に関する政策方針、政策方針の概念の整理、目標の明確化、目標達成のための戦略等を改めて明確化することは、政策のより効果的、効率的な実施を図る上で有意義である。具体的には、「施策(プログラム)」を作成し、それに基づいた案件の形成、実施を行うことも一案である。
提言6:協力受益国に対して協力実施国のリソースに関する情報を提供する(上記教訓の(3)に対応)
効果の検証結果から、言語、文化等の共通性や分野の特徴に配慮し、協力実施国と協力受益国のマッチングが行われたわが国の南南協力支援(第三国研修)は、プラスの効果をもたらしていることが明らかとなった。南南協力支援の効果を最大限に引き出すためには、協力実施国のリソースと協力受益国のニーズが適切に組み合わされる必要がある。
この点について、協力実施国の当該分野における比較優位性とそのリソースに関する情報を、協力受益国に対して明確に伝えることが重要である。建設機械に関する第三国研修の参加者からは、協力実施国で使用されていた機械が、研修生の出身国で使用されている機種に比べ旧式であったため、研修で習得した技術が、帰国後の業務に活かせなかった経験があるとの指摘を受けた。このような事例が生じないよう、協力実施国での研修内容とそれについての当該国の比較優位性に関する情報を明確に協力受益国に伝え、協力受益国が自国の開発ニーズに沿って主体的に参加を選択、あるいは研修生を適切に選定できる仕組みをつくることが重要である。先ず取り組まれるべき例として、協力実施国政府および協力実施国におけるJICA在外事務所が、第三国研修の参加者を募集する際に協力受益国に送付されるコース・インフォメーション(GI)の内容を精査し、研修内容の詳細、当該研修分野における研修実施国の比較優位性等を、明確に協力受益国に伝えることを提案する。協力実施国と協力受益国で使用言語が異なる場合は、GIを協力受益国の言語に翻訳する。その際、翻訳の質に十分配慮することが重要であることは言うまでもない。さらに、協力受益国におけるJICA在外事務所についても協力受益国政府関係者との対話を通じて、上記のプロセスが適切に行なわれているかどうか定期的に確認し、必要に応じて協力実施国におけるJICA在外事務所に対して現地の状況を報告することが望ましい。
また、上記と関連し、受益国が研修生の選定に主体的に関与できる仕組みを工夫することが重要である。現行の協力スキームでは、協力実施国から当該第三国研修のコース・インフォメーション(GI)送付を受け、受益国側は、短期間に研修生を選定しなくてはならない状況にある。これでは、受益国が研修の内容を自国の開発ニーズに照らし参加の有無を決定し、適切な参加者を選定することは難しい。協力実施国のリソースと協力受益国のニーズを適切にマッチングさせるためには、協力実施国からの一方向のアプローチでは不十分で、受益国の研修参加へのモチベーションを高め、適切な研修生の選定に受益国が主体的に関わる双方向のアプローチが重要であり、それを促す工夫が必要となる。一案として、当該受益国を対象に今後実施予定の南南協力支援案件(第三国研修等)リストを作成し、受益国関係者に定期的に送付することが挙げられる。これにより協力受益国は、自国が参加可能な南南協力支援案件の全体像を捉えることが可能となり、自国の開発ニーズに鑑み、事前に、主体的に、参加を決定することが可能となると考えられる。
提言7:パートナーシップ・プログラムの拡大(上記教訓の(4)に対応)
南南協力支援政策の下で行なわれている第三国研修及び第三国専門家派遣の経費を本邦研修及び日本人専門家派遣と比較した結果、南南協力支援政策は、わが国のODA経費の削減に直接的なプラスの効果をもたらしていることがわかった。さらに、パートナーシップ・プログラムの枠組み文書に署名している国との南南協力支援では、費用分担化の原則により、わが国のODA経費のさらなる削減につながっていることが確認されたことから、わが国が、協力実施国の南南協力実施能力と費用負担能力を勘案しつつパートナーシップの締結国数を増やしていくことは有意義であると考える。
提言8:南南協力支援会合の定期的な開催によりわが国のプレゼンスを強化する(上記教訓の(5)に対応)
第三国研修における日本人講師の存在やわが国南南協力支援に関する報道が、協力実施国においてわが国援助のプレゼンスを高めていることが確認された。1998年に沖縄で開催した南南協力支援会合を協力実施国で開催することは、わが国援助のプレゼンスをより高める良い機会であるとともに、他ドナーへの情報提供や、協力実施国間の情報交換の場を提供する上で有益であると考える。

