第3章 評価結果
3.2.1 対モロッコ水資源開発分野支援のインプット及びアウトプット実績
1999年度から2001年度までにモロッコに対して我が国が実施した農業用水、飲料用水確保のための水資源開発分野支援は、(1)「灌漑施設の整備」、(2)「水源の確保(中規模ダムの建設)」、(3)-1「中規模都市の給水施設の整備」、(3)-2「地方村落部の給水施設の整備」、及び(4)「施設の運営管理」を中間目標とするサブセクターに整理される。以下にこれらサブセクター毎のインプット・アウトプット実績を整理した。
なおインプットは1999年度から2001年度までにの間に調達手続き、進捗中、もしくは完了した案件全てを含めた。有償・無償の金額はE/Nベースとした。またアウトプットは2001年度末までに完了(有償については貸付完了)したもののみを対象とした。
(1) 灌漑施設の整備
1999年度から2001年度の間、灌漑施設の整備分野における投入は、有償資金協力1件(135.48億円)、草の根無償資金協力3件(0.11億円)、研修員受入3件(3名、10.8人・月)であった。
この時期におけるアウトプットとして、19,000haが新規灌漑され、17.3kmの幹線水路が建設された。同灌漑面積は2002年現在で実現されたモロッコの通年灌漑地区面積101.62万haの約1.9%、また灌漑部門の5ヵ年計画(2000-2004)の新規灌漑開発99,740 haの約19%に相当する。

(2) 水源の確保(中規模ダムの建設)
1999年度から2001年度の間、水源の確保(中規模ダムの建設)分野における投入は、開発調査1件(5.09億円)、研修員受入2件(2名、1.2人・月)であった。

(3) 中規模都市の給水施設の整備
1999年度から2001年度の間、中規模都市の給水施設の整備分野における投入は、有償資金協力3件(215.11億円)であった。
この時期におけるアウトプットとして、24個のポンプ施設、23個の貯水槽(29,600m3)、413.1kmの管路(新設391.0km、リハビリ22.1km)が建設された。

(4) 地方村落部の給水施設の整備
1999年度から2001年度の間、地方村落部の給水施設の整備分野における投入は、有償資金協力2件(74.66億円)、無償資金協力26件(11.59億円)、研修員受入4件(4名、7.9人・月)であった。 この時期におけるアウトプットとして、102個のポンプ施設、8個の貯水槽(1,100m3)、357.9kmの管路、83箇所の共同水栓、15台の給水車が新規に建設もしくは供与された。
表3.2.4 インプット・アウトプット実績(地方村落部の給水施設の整備)(PDF)
(5) 施設の運営管理
1999年度から2001年度の間、施設の運営管理分野におけるインプット(投入)は、専門家派遣6件(5名、35.1人・月)であった。

(1) 農業生産性の向上
表3.2.6に過去9年間における主要農産物(小麦・トウモロコシ等の穀物、大豆等の豆類、落花生等の油脂作物、及び甜菜・綿等の産業用作物)別の収穫面積、生産量、単位面積収量の国レベルでの推移を示す。
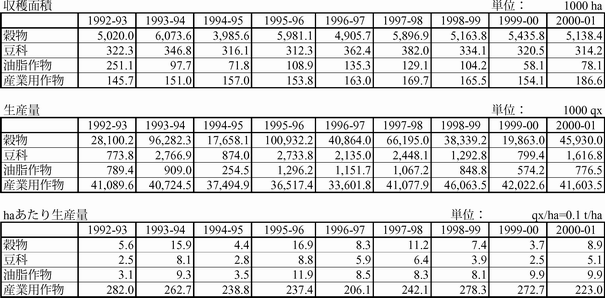
主要農産物生産量
主要農産物の生産量は年格差の程度差があるものの、いずれも横ばい状態にあり伸び悩みの傾向にある。穀物に着目すると、2000/01年における生産量は459万トンであり、最近9年間では、177万トン(1994/95)から1009万トン(1995/96)の間で大きく変動しているが、これは全国的にみれば主として天水に依存している穀物生産の生産基盤の脆弱さを示している。同様に豆科や油脂作物についても変動幅が大きい。一方、産業用作物については期間を通じ比較的生産量が安定している。
ヘクタールあたり農産物生産量
生産量を収穫面積で除したhaあたり生産量は、穀物生産では0.4トン/haから1.7トン/haでやはり大きく変動しており、気象変動の影響を物語っている。一方、油脂作物は1995/96年以降、また産業用作物は全期間で単位面積あたりの収量が比較的一定しており、全国で進められている灌漑農業の効果がでているものと推測される。
添付-4に穀物の収穫面積、生産量、単位面積収量を州別にまとめて示す。なお、本評価調査が対象とする「アブダ・ドゥカラ灌漑計画」については本格的な通水が2004年からであること、またその他の事業は小規模な草の根無償協力であったことから、我が国が実施した(1)「灌漑施設の整備」による国・州レベルでの指標への影響は確認できなかった。
(2) 飲料水の供給
表3.2.7に過去11年間における都市部給水量、給水契約世帯数、各戸給水率の国レベルでの推移を示す。また、地方村落部での飲料水アクセス率の推移を合わせて示す。
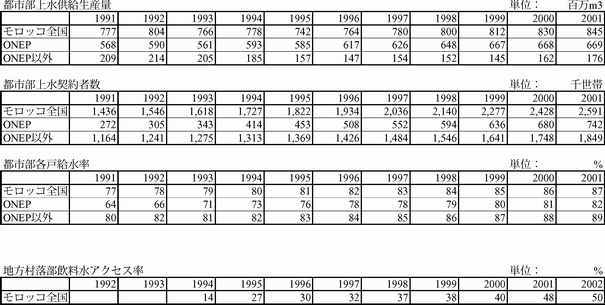
(i) 都市部
給水量
モロッコ全国の都市部での飲料水総供給量は2001年には8.45億 m3に達した。前年比で1.8%、1991年以降で平均して0.8%の伸び率で順調に増加している。ONEPに限れば、2001年の供給量は6.69億m3で前年比0.1%、1991年以降で平均1.6%の伸びとなっている。
給水世帯数
都市部給水契約世帯数は、自治体の運営公社、民間及びONEPを合計すると2001年で259.1万世帯に及ぶ。前年比で6.7%、1991年以降の伸びは平均で6.1%の伸びとなっている。ONEPの2001年の契約世帯数は74.2万世帯で前年比9.1%増、1991年以降では平均10.6%の伸びとなっている。
各戸給水率
都市部の各戸給水率は1991年に77%であったのが2001年には87%に着実に向上している。
添付-4にONEPの生産量、契約世帯数を州別にまとめて示した。我が国が(3)-1「中規模都市の給水施設の整備」の一環として実施した「上水道セクター整備事業」は2000年以降に各都市で完成したため、2001年の給水量・給水世帯数もしくは各戸給水率の対前年比の伸びに効果があったものと考えられる。しかしながらその寄与度合いは直接的には読み取れなかった。
(ii) 地方村落部
飲料水アクセス率
地方村落部の飲料水アクセス率については、1994年に14%であったのがPAGERの実施により2002年には50%迄着実に向上している。
我が国が(3)-2「地方村落部の給水施設の整備」の一環として実施した各無償資金協力は上記アクセス率の向上に貢献しているものと想定されるが、その寄与度合いについては直接には読み取れない。
なお1999年から2001年の間に建設が終了しサービスを開始した飲料水供給案件により直接・間接に裨益した人口を支援対象となった都市もしくは村落の人口計で評価すると、全国で合わせて約140万人(都市部で122.7万人、地方村落部で16..3万人)と推定される。
(iii) 水道事業体の財務
ONEPの自己資本率
水道事業体としてのONEPの経営・財政状態をみるために、近年における自己資本率の推移を下表に整理した。
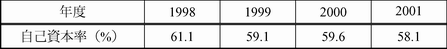
漸減傾向にあり、建設投資財源への借入資本の増大が伺える。
(3) 住民(零細農民や地方部住民)の生活向上
以下の社会指標の変化はモロッコの全国レベルのものであり、日本の協力の成果を抽出したものではないが、幾分かはこれらに貢献したものと考え、参考までに示すことにする。
水汲みに要する時間
住民の生活向上をはかる直接的な指標として、水汲み時間の変化が考えられる。データのある2000年までの変化を見ると、水道普及率、未普及世帯の水道までの距離、水汲みに要する平均時間については、都市部・村落部とも、全国レベルで着実に改善している。水道未普及世帯の水汲み時間は、都市部で平均7.4分(2000年)、村落部で14.6分(同)にまで減ってきている。
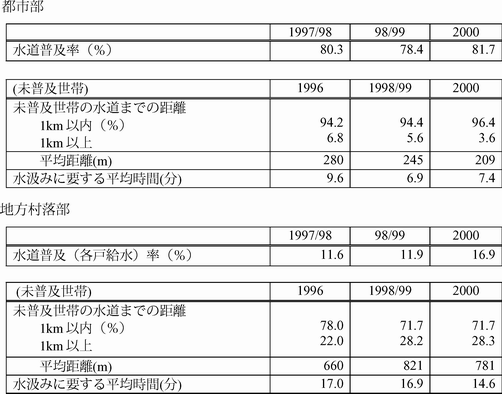
就学率(純)
水汲み労働の軽減は、就学率の上昇を促すと考えられているが、モロッコにおける就学率は、市部、農村部、男子、女子、全て上昇している。特に、もともと低かった女子の、中でも地方部での就学率の伸びが目覚しい。ただし、教育政策や他の施策の効果も高いと見られ、水汲み労働軽減の就学率向上への貢献度合いは特定されていない。
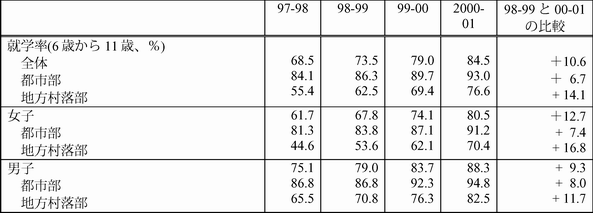
水因性疾病発生数
飲み水から感染することの多いコレラについては、多い県では年間100件以上の患者数が見られた1990年からわずか12年で、ほぼ絶滅の状態になっている(図3.2.1参照)。これは保健衛生関連の施策による効果は勿論であるが、衛生的な水の供給とくにPAGERが大きく貢献しているとの意見もあった。 i
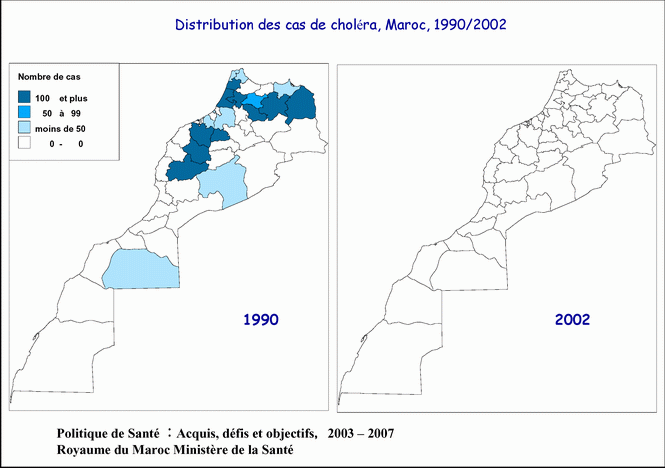
乳幼児死亡率
一般的に水の不衛生なところでは高いとみられている乳幼児死亡率の推移は、以下の表のとおりとなっており、確実に漸減傾向にある(ただし、99年以降は見込みの数字である。)
しかしながら、乳幼児死亡率は、飲料水供給の成果指標としては間接的な指標でしかない。他に影響する要因として、保健医療施設へのアクセス、出産前の妊婦指導、出産時に受けられるサービス、妊産婦の栄養状態、母親の識字や教育の度合い等があげられる。 ii
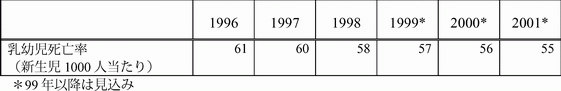
i 保健省Dr.Tyane Mostapa人口局長インタビュー(2003年9月23日)による。
ii 同上。

