第3章 評価結果
3.1 目的の妥当性(1) ODA大綱(1992年)との整合性
1992年6月に策定されたODA大綱は、その重点事項として、以下の5項目をあげている。
| (1) | 地球的規模の問題への取り組み |
| (2) | 基礎的生活分野(BHN)等 |
| (3) | 人造り及び研究協力等技術の向上・普及をもたらす努力 |
| (4) | インフラストラクチャー整備 |
| (5) | 構造調整・累積債務問題の解決に向けた支援等 |
我が国が実施した対モロッコ支援の中間目標の内、「地方村落部の給水施設の整備」は、上記(2)「飢餓・貧困により困難な状況にある人々や難民を対象とする基礎的生活分野を中心とした支援及び緊急援助の実施」に該当する。具体的な案件としては、有償・無償資金協力を通じての地方給水計画(PAGER)への参画、旱魃により水へのアクセスが悪化した山間地域への給水車の提供(草の根無償)などがあげられる。
研修生受入や「施設の運営管理」での専門家派遣、は上記の(3)「人造り及び研究協力等技術の向上・普及をもたらす努力」に該当する。
また、「灌漑施設の整備」、「水源の確保(中規模ダムの建設)」、「給水施設の整備」(「中規模都市の給水施設の整備」、「地方村落部の給水施設の整備」)はいずれも、上記の(4)「経済社会開発の重要な基礎条件であるインフラストラクチャーの整備への支援」に該当する。
以上より、我が国の対モロッコ支援はODA大綱との整合度が高かったと言える。特にBHNに係る「地方村落部の給水施設の整備」でその度合いが大きい。
(2) 政府開発援助に関する中期政策-重点課題-との整合性
1999年8月に策定された「政府開発援助に関する中期政策」は、以後5年間のODAの基本的考え方、重点課題、地域別援助のあり方を明らかにしている。
<重点課題>
重点課題として、以下の7項目が挙げられている。
| (1) | 貧困対策や社会開発分野への支援(基礎教育、保健医療、女性支援、安全な水の供給、貧困緩和) |
| (2) | 経済・社会インフラへの支援(運輸、通信、電力、河川・灌漑施設等や都市・農村の生活環境整備) |
| (3) | 人材育成・知的支援 |
| (4) | 地球的規模問題への取り組み(環境保全、人口・エイズ、食料、エネルギー、薬物対策) |
| (5) | アジア通貨・経済危機の克服等経済構造改革支援 |
| (6) | 紛争・災害と開発(紛争と開発、防災と災害復興) |
| (7) | 債務問題への取り組み |
このうち、「(1)貧困対策や社会開発分野への支援」では基礎教育、保健医療、開発途上国における女性支援(WID)と並んで、「安全な水の供給、水資源開発や水資源の管理・利用のための支援が重要」とされており、更に、「地域間格差の是正のため、農村等貧困地域に対する支援が重要である」と述べられている。モロッコ水資源開発分野への協力は、水供給だけでなく水資源開発(水の確保)を含んでいること、また水道の普及が遅れている地方部への支援が積極的に行なわれていることから、これらの方針と合致する。
地方村落部・中規模都市の上水道整備、灌漑施設の整備は、「(2)経済・社会インフラへの支援(運輸、通信、電力、河川・灌漑施設等や都市・農村の生活環境などの経済・社会インフラの整備)」に該当する。また、同項目では「資金協力と技術協力の連携による施設の維持・管理面での協力を進め、持続的な効果が発揮できるように努める」と述べられているが、南部における地方水供給プロジェクト(無償)と長期派遣専門家の連携は、持続的な効果の発現に大きく貢献している。
また、研修生受入、専門家派遣、第三国研修支援などは「(3)人材育成・知的支援」に該当する。特に、モロッコ自らが周辺国の国造りのための人材育成を行なう第三国研修の継続的な実施は、「広域的な効果の期待できる事業形態の積極的な活用」をうたった中期政策に合致するものである。
<地域別援助のあり方>
中期政策における「地域別援助のあり方」のなかで、中近東地域については次の諸点を重視して援助を行なうとしている。
| (1) | 中東和平プロセス支援 |
| (2) | 比較的低所得の国における農業、水資源開発等の経済・社会インフラ整備支援 |
| (3) | 比較的高所得の湾岸諸国における脱石油のための経済多角化 |
| (4) | 比較的高所得の国等における環境保全対策への支援 |
このうちの(2)にモロッコ水資源分野の協力は該当する。ところで、モロッコの所得中近東地域でどのあたりに位置するのだろうか。モロッコの中東における一人当たりGNPと所得を見てみよう。
表3.1.1は、中近東諸国の一人当たりGNPを示したものである。中近東地域の被援助国のうちデータのない国を除く13カ国中で、一人当たりGNP(1998年)は280$(イエメン)~7,640$(バーレーン)の幅にあり、モロッコ(1240$)は上から9番目、下から5番目となっている。

表-3.1.2は、同様に中近東諸国の一人当たり所得を示したものである。中近東地域の被援助国のうちデータのない国を除く11カ国中で、一人当たり所得(購買力平価。2000年)は780$(イエメン)~11,050$(サウジアラビア)の幅にあり、モロッコ(3410$)は上から9番目、下から3番目となっている。また、モロッコに対する水資源開発分野の支援に関しては、旱魃が断続的に続き水不足が切実な問題であった99年前後の事情も考慮しなければならない。
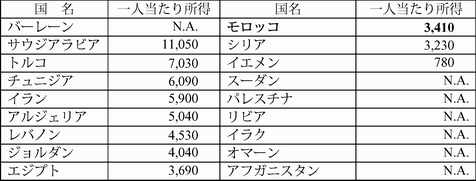
図3.1.1は、以上の諸点をわが国のモロッコに対する政府開発援助の目的体系図として整理したものである。
(1) モロッコ国家開発計画における水資源開発の位置づけ
第2章で既述した通り、モロッコの国家開発5ヵ年計画(2000-2004)では社会セクターの長期的な重点課題として教育、雇用、保健衛生、水資源、道路、住宅、食糧の7つを挙げており、水資源開発は国家開発計画において重要な位置を占めている。
上記重点課題の内、「水資源」では水需要を満たすための水源(ダム・井戸)開発、都市部及び地方村落部での上水の普及、又「食糧」については需要増に対応するための国家灌漑計画 (PNI)の達成等が謳われている。これらは、我が国の実施した水資源開発分野支援の中間目標の内、「灌漑施設の整備」、「水源の確保(中規模ダムの建設)」、「給水施設の整備」(「中規模都市の給水施設の整備」、「地方村落部の給水施設の整備」)とまさに合致している。
また同じく5ヵ年計画には経済・社会開発の基本方針として、制度改革、経済成長と雇用創出、農村部の開発、国土開発と地域格差の是正、人的資源の開発と教育改革、社会開発と不平等の是正の6つが掲げられている。この内、「農村部の開発」では国家灌漑計画・地方給水計画等の推進が謳われているが、これは我が国支援の「灌漑施設の整備」、「地方村落部の給水施設の整備」と合致するものである。
「人的資源の開発と教育改革」で挙げられている職業訓練の向上は、我が国支援での研修生受入と整合している。また「社会開発と不平等の是正」の為の基礎的サービスへのアクセス向上は、我が国支援の「地方村落部の給水施設の整備」が該当している。
以上の通り、我が国の対モロッコ支援は同国の国家開発5ヵ年計画(2000-2004)の重点課題及び基本方針と整合性の高いものであった。
なお、5ヵ年計画の経済・社会開発の基本方針の内、「国土開発と地域格差の是正」では、自然環境の保護が謳われており、また「社会開発と不平等の是正」でも基礎的サービスへのアクセス向上として給水、電化に加えて下水道が挙げられている。下水道施設整備は我が国の対モロッコ支援には含まれなかったが、同国の開発計画において重要な位置に置かれていることが伺える。
(2) モロッコ水資源開発政策の内容との整合度合い
国家開発5ヵ年計画(2000-2004)における水資源開発政策は、水に係る上位政策である水資源法や流域別水資源開発計画、あるいは国家灌漑計画(PNI)や地方給水計画(PAGER)等との整合性を保っており、水利部門、灌漑部門及び飲料水供給部門別に記述がなされている。
図3.1.2に、国家開発5ヵ年計画(2000-2004)における水資源開発政策を目的体系図として整理して示す。
水利部門
水利部門が5ヵ年計画に掲げる目的は、(i) 都市部及び地方村落部での飲料水供給への貢献、(ii) 食糧供給への貢献、(iii) 水利施設の修復・維持、(iv) 水質の改善・維持、(v) 河川氾濫や洪水からの国民・財産の保護、(vi) 水力発電のための包蔵水力開発、(vii) 全土への公平な水の分配とそれに伴う地域振興、の7つであるが、この内 (i)及び(ii)は我が国支援の「水源の確保(中規模ダムの建設)」が、また(iii) は「施設の運営管理」がそれぞれ該当している。更に、(vii)は地方格差の是正に寄与する「地方村落部の給水施設の整備」との整合性が高い。
同5ヵ年計画で水利部門は9つの基本方針を示している。我が国支援の「水源の確保(中規模ダムの建設)」は、同基本方針の内「水資源開発の実施」の中規模ダム建設、及び「ダム整備に係る調査」と合致している。また「施設の運営管理」は「水利施設の保全」と、「地方村落部の給水施設の整備」は「水資源開発の実施」の地方給水計画と、それぞれ合致している。
灌漑部門
灌漑部門が掲げる主要活動計画は、新規灌漑開発及び灌漑効率の改善(リハビリ及び近代化)である。我が国支援の「灌漑施設の整備」はアブダ・ドゥカラ灌漑計画を主体とするものであるが、これは国家灌漑計画及び5ヵ年計画において新規灌漑開発として取り上げられており、モロッコ側の政策と我が国支援の間に明らかな整合性がある。
飲料水供給部門
飲料水供給部門では目的として、(i) 都市部各戸給水率89%、(ii) 地方村落部飲料水アクセス率62%(いずれも2004年)、(iii) 生産・配水施設の維持管理、(iv) ONEP自己資本率の向上、(v)水質の改善と経済的なサービス提供、が謳われている。(i)は我が国支援の「中規模都市の給水施設の整備」、(ii)は「地方村落部の給水施設の整備」、(iii)は「施設の運営管理」がそれぞれ該当している。
以上から我が国の対モロッコ支援は国家開発5ヵ年計画にある水資源開発政策との整合性が高かったことが確認された。但し2章にて述べたように現在モロッコの水資源政策は過渡期にあり、既存の流域別水資源開発計画の見直しや、水資源の有効管理の重視等が特徴的となってきている。また水利部門や飲料水供給部門の目標にも掲げられている水質の改善・維持の為に、下水道事業の重要性が増してきている。特に今後の援助政策の策定にあたってはこうしたモロッコ水分野の最新動向を踏まえる必要があろう。
第2章で見てきたように、国際的な水資源開発の主な動向としては、ミレニアム開発目標及びヨハネスブルグ実施計画における安全な飲料水及び基本的衛生へのアクセスに関する目標設定、ハーグ宣言とダム委員会報告書、その後の第3回世界水フォーラム、G8エビアンサミット等の一連の国際会議の中で議論が進展してきたと捉えることができる。UNDPをはじめとする国連機関、世界銀行、アフリカ開発銀行、EUも、これらのコンセンサスに則った戦略の策定となっている。
ポイントとしては、まず、飲料水の確保の重要性は世界的コンセンサスであること、そして次が、淡水資源の有限性・生態系の保護等を考えること、地方分権、適切な料金設定を含めた需要管理、あらゆるステークホルダーの参加による意思決定、ジェンダー主流化、環境保全など、さらにこれらを内包した、統合的水資源管理の推進、ということになる。水資源の確保・給配水という旧来の発想から脱し、総合的な水管理を考えた政策・戦略が必要となっている。
評価対象期間における日本の対モロッコ水資源開発分野協力をこの観点から見ると、統合的水管理の考え方を全面的に取り入れた上で各案件が実施されたわけではないが、飲料水へのアクセスの増加、水への投資の増加、という大枠に関しては明らかな整合性が認められる。
ダム委員会の報告書については、モロッコ国は1997年に4地点のダム建設のための円借款を要請したが、環境影響評価が不十分である等の理由により不採択となった。このため改めて中規模ダム建設の開発計画策定として開発調査(1999-2001)が要請され、採択された。なお、調査の実施に際しては、住民移転への適切な手当てが重要であるとされている。
灌漑、上水供給、中規模ダム建設のための調査、給水車提供など、一つ一つの案件は農業や飲料水の供給のために効果的であるが、1999年から2001年の評価対象案件を見る限りでは、積極的に需要管理や制度改革に配慮した案件形成には至らなかった。

