第2章 評価対象を取り巻く状況
近年水に関する数多くの国際会議が開かれ、様々な宣言や報告書が出されているが、ここではこれらの世界的な流れを概観する。
(1) 水に関する国際的な流れ-ダブリン原則に至るまで-
水に関する初の政府間国際会議は、1977年にアルゼンチンのマル・デル・プラタで開催された国連水会議(United Nations Water Conference)である。同会議では、水管理の重要な要素に関する勧告及び個別分野に関する決議から成るマル・デル・プラタ宣言(行動計画)を採択した。その後1980年の国連総会において、1980年からの10年間を「水供給と衛生の10年」とすることを決定し、WHOや世界児童基金(UNICEF)が、世界規模でその活動を主導した。しかし人口増加、水消費の拡大、環境悪化などから水をめぐる問題は一段と深刻化する結果となった。i
1992年にアイルランドのダブリンで開かれた「水と環境に関する国際会議(International Conference on Water and the Environment)」では、次の4つの原則(以後"ダブリン原則"と呼ばれる)が打ち出された。
| (1) | 水資源の「有限性」 淡水は、生命と開発と環境の維持に不可欠な、有限で損なわれやすい資源である。 |
| (2) | 「参加型」での水資源開発・管理 水資源と管理は、あらゆるレベルの利用者、計画立案者、政策決定者を含む、参加型アプローチによるべきである。 |
| (3) | 水供給・管理・保全における「女性の役割」 女性は、水の供給、管理、保全に中心的な役割を担う。 |
| (4) | 「経済財」としての水 水は、あらゆる競合的用途において経済的価値を持ち、経済財として認識されるべきである。 |
「ダブリン原則」は、水問題の議論については、すべてのレベルの利害関係者が議論や決定に加わること、そのために関係者の対話を開始することがまず重要であるとの原則を示したもので、その後の国際的な水の議論において広く受け入れられ、今日に至るまで共通の基調となっている。とりわけ、それまでに多くの議論を経て徐々に形成されてきた「統合的水資源管理(Integrated Water Resources Management:IWRM)」の概念iiが、ダブリン宣言に集約され、水資源管理についての基本的概念を大きく変えるものとなった。(IWRMの概念はその後、ダブリン原則をもとに、水資源は土地やその他関連資源との調整が重要であること、管理にはボトムアップアプローチが重要である等の概念が徐々に加わり形成されていった。)
同年(1992年)に開催された「国連開発環境会議(United Nations Conference on Environment and Development)」(リオ・サミット)で作成された「アジェンダ21」の18章(淡水資源の質及び供給の保護)にもダブリン原則が反映された。
(2) 第一回世界水フォーラム(1997年3月)
世界水フォーラムは、1996年に国連教育科学文化機関(UNESCO)・世界銀行が中心となって水分野での研究等を行うために設立された世界水会議(World Water Council)iiiが提唱し、モロッコ政府の協力を得て、1997年3月にモロッコのマラケシュで開催された。このフォーラムには63カ国約500人が参加し、マラケシュ宣言を採択した。iv
マラケシュ宣言は次のように謳っている。
「第一回世界水フォーラムは、政府、国際機関、NGO及び世界の人々に、マル・デル・プラタとダブリンの原則、及びリオ・サミットの「アジェンダ21」第18章を実践し、地球の水資源の持続可能性を確保する『青い革命』を開始するよう呼びかける。特にこのフォーラムは、きれいな水と衛生施設を持つという人間の基本的ニーズを認識する行動、共有された水の管理のための効果的なメカニズムを設立する行動、生態系を支援し保護する行動、効率的な水利用を奨励する行動、及び、市民社会のメンバーと政府の間のパートナーシップを奨励する行動を勧告する。世界水会議に対し、21世紀における水、生命及び環境についての地球規模のビジョンをもたらす三年間の研究、協議及び分析を開始することを委任する。」v
水問題の重要性を認め、どのような行動が求められているかについて一般的に触れた上で、具体的な指針を含むビジョンについては次のフォーラムまでの三年間の活動に託したのである。vi
マラケシュ宣言のポイントをまとめると次のようになる。
| (1) | BHNである安全な水と衛生設備を満たすための行動 |
| (2) | 水利権を確保するための効率的な機構の設立 |
| (3) | エコシステムの保護 |
| (4) | 水の有効利用の推進 |
| (5) | 水利用におけるジェンダーの公平性の確保 |
| (6) | 住民組織と政府の協調体制の推進 |
(3) 第二回世界水フォーラム(2000年3月)
マラケシュ宣言を受けて、1998年、水問題に関わる国際的な機関が中心となり、「21世紀のための世界水ビジョン」の策定が始まった。2000年3月、オランダのハーグで開催された第二回世界水フォーラムでは、各地で何百もの会合が催され、約1万5千人が参加した。このプロセスにおいて、「水をすべての人々の課題に(Making Water Everybody's Business)」とする「世界水ビジョン」が発表され、議論された。このフォーラムでの議論の結果に基づき、閣僚級会議において「21世紀における水安全保障(Water Security)に関するハーグ宣言」が採択された。
ハーグ宣言は、水安全保障を達成するための主な課題として、
| (1) | 基本的ニーズの充足 |
| (2) | 食料供給の確保 |
| (3) | 生態系の保護 |
| (4) | 水資源の共有 |
| (5) | リスク管理 |
| (6) | 水の価値の評価 |
| (7) | 賢明な水統治 |
の七つの課題をあげ、これらの課題に取り組んでいくために統合的水資源管理を行うとした。さらに、合意された原則を行動に移すために、
| (1) | 目標、戦略の設定 |
| (2) | 国連機関による、淡水資源の定期的な点検等の活動の支援 |
| (3) | 水文化発展のための協力 |
| (4) | 汚染防止のための協力 |
| (5) | 多国間組織を通じた水関連政策の強化 |
| (6) | 国連組織内における協調と整合性の強化 |
等の具体策を挙げた。vii
また、「世界水ビジョン」では、<三つの目標>として、
| (1) | 水利用の決定権を女性、男性、地域社会に委ねる |
| (2) | 水一滴当たりの穀物収量及び生産量を増やす |
| (3) | 水を管理して淡水と陸上生態系の保全を実施する |
をあげ、これらの<目標達成のための重要な行動>として次の5点をあげている。
| (1) | すべての利害関係者が総合管理に関与する |
| (2) | すべての給水にフルコスト価格設定を導入する |
| (3) | 研究と革新に向けて公的資金を拡大する |
| (4) | 国際河川流域を共同で管理する |
| (5) | 水への投資を大幅に増加させる |
(4) ミレニアム開発目標(2000年9月)
2000年国連総会(ミレニアムサミット。147の国家元首を含む189の加盟国が参加)で21世紀の国際社会の目標として、国連ミレニアム宣言を採択した。これは、平和と安全、開発と貧困、環境、人権とグッドガバナンス(良い統治)、アフリカの特別なニーズなどを課題として掲げ、21世紀の国連の役割に関する明確な方向性を提示したものであるが、この宣言と90年代の各種国際会議で採択された開発目標が統合され、ひとつの共通の枠組みとして「ミレニアム開発目標(Millennium Development Goals)」にまとめられた。
子供の死亡率削減、妊産婦の健康の改善及び持続可能な環境作りなどの八つの目標と18のターゲットが掲げられた。その中で目標7(環境の持続可能性確保)のターゲット10では「2015年までに安全な飲み水へのアクセスがない人口の割合を半減する」との目標が掲げられた。
(5) 世界ダム委員会(1998-2000)
世界ダム委員会(the World Commission on Dams:WCDviii)は1998年に世界銀行と国際自然保護連盟(IUCN)の提唱で発足し、2000年11月に報告書「ダムと開発(Dams and Development)」をとりまとめた。同報告書でWCDは、公平性、持続性、効率性、参加型意思決定、説明責任の5つの理念に基づき、ダム建設に関わる意思決定の枠組みとして、以下を提唱している。ix
- 開発の選択と合意のための交渉においてすべての正当な利害関係者を特定するための、「権利とリスクのアプローチ」
- 水資源とエネルギー開発のための7つの戦略的優先事項:公共の支持、包括的な選択肢評価、既存ダムへの取組、河川と人々の生活の維持、権利の認識とダムがもたらす恩恵の分配、ルールの遵守、平和、開発、安全のための河川共同利用
2002年以降の動向は、評価対象期間外であるのでこれをもって過去の援助を評価するのは不適当であるが、今後のモロッコ水資源開発分野協力の参考としてレビューしておくことにする。
(1) ヨハネスブルグサミット(2002年8月)と日米水協力イニシアティブ(2002年9月)
2002年8月26日から9月4日に開催されたヨハネスブルグサミット(持続可能な開発に関する世界首脳会議)でも、ミレニアム開発目標の再確認と、「2015年までに基本的な衛生施設(下水道設備等)を利用できない人々の割合を半減する」という実施計画が採択され、2005年までに統合的水資源管理や水利用の効率性向上のための計画策定に取り組むことが決定された。
日米水協力イニシアティブ(2002年9月)
またヨハネスブルグサミットでは、日本と米国が、安全な水と衛生を世界の貧しい人々に提供し流域管理を改善し、水の生産性を向上させるための共同の取り組み、「きれいな水を人々へ」イニシアティブを発表した。x
日本のイニシアティブは、三つの要素から成る。
- 給水率が比較的低い国または地域においては、日本は、安全な飲料水の安定的な供給を重点的に推進する。また、日本は地下水開発を含め、水資源開発に関するモデル事業を実施する。
- 給水率が比較的高い国または地域においては、日本は、水管理委員会の設置及び女性が重要な役割を果たす住民参加のモデル創設を通じ、水資源管理のための能力構築を支援する。
- 人口が集中し下水道普及率が低い都市部においては、日本は、下水道整備を支援する。
第三回世界水フォーラムでは、世界水ビジョンの実現や、ミレニアム開発目標の中の「2015年までに安全な飲み水へのアクセスがない人口の割合を半減する」という目標の実現、2002年8月のヨハネスブルグサミットで採択された「ヨハネスブルグ実施文書」の中の「2015年までに基本的な衛生施設(下水道設備等)を利用できない人々の割合を半減する」という目標の達成に向けて、具体的な施策が策定されることが期待され、182の国・地域から2万4千人が参加した。閣僚会議では、世界各国や国際機関が水問題解決のために公約として取り組む「水行動集(Portfolio of Water Actions)」が発表され、閣僚宣言が採択された。
「閣僚宣言」の要点は以下のとおり。xi
| (1) | 全般的政策-貧困者及びジェンダーへの十分な配慮、地方自治体及びコミュニティの権限強化。グッドガバナンス、キャパシティビルディング、統合的水資源管理の促進、汚染者負担原則、民間部門を含む資金調達手段の探求など。 |
| (2) | 水資源管理と便益の共有-統合的水資源管理及び水効率化の計画を策定、水需要管理措置、水のリサイクルなど。 |
| (3) | 安全な飲料水と衛生 |
| (4) | 食料と農村開発のための水-コミュニティベースの開発促進、参加型灌漑水管理、既存水利施設のリハビリと近代化など。 |
| (5) | 水質汚濁防止と生態系保全 |
| (6) | 災害軽減と危機管理 |
「水行動集」には、36カ国、16国際機関等から、合計422件の行動が提出された。「水資源の管理と便益の共有」、「安全な飲料水と衛生」に関する行動が多い。日本の国土交通省河川局は、内陸水運活動の支援、災害に迅速に対応できるシステムの確立、また開発途上国に技術援助及び能力強化支援を供与することを約束した。xii
(3) エビアン・サミット(2003年6月)
2003年6月1日から3日までフランスのエビアンで開催された主要国首脳会議(G8サミット)における議論の結果、計13の各種行動計画等が発表されたが、そのひとつが「水に関するG8行動計画」である。この行動計画において、G8首脳は、「我々は、・・・2003年3月に日本で開催された第三回世界水フォーラムと閣僚級会議の成果の上に、目標の達成に向けた国際的な努力においてより積極的な役割を果たすことを約束する」と表明した。xiii
(1) UNDP
UNDPの水戦略の基本は、「水問題をガバナンスの問題としてとらえる」ということである。
「UNDPの水戦略 効果的水ガバナンスに向けて」(Water Strategy of UNDP- Approach towards Effective Water Governance,2003,UNDP)によると、
UNDPは、ミレニアム開発目標及びヨハネスブルグサミットで設定された二つの水に関する具体的な目標(「2015年までに安全な飲み水へのアクセスがない人口の割合を半減する」、「2015年までに基本的な衛生施設(下水道設備等)を利用できない人々の割合を半減する」)の達成のため、水ガバナンスを優先させ、草の根レベルから国レベルに至るまで、能力開発を強化し、持続可能かつ革新的な水ガバナンスを推進し、戦略的パートナーシップを継続させることに重きをおいている。技術の進展や、水の供給増大だけでは水問題を解決することはできず、水の使い方、管理の仕方を変えること、そして利害関係者が参加することによって、即ち、水ガバナンスの仕組みを正しく変えることが、持続可能な水資源管理を成功させる鍵と考えている。
そのためには、既存の地域社会メカニズムを活用し、地域社会において水資源、水供給、衛生に関わる革新的な活動を支援するとしている。また、政策支援、啓蒙、戦略的パートナーシップの構築によって、水に関する取り組みを、質が高く、一貫性があり、連携のとれたものになるように促す。重点テーマは次の6つ。
| (1) | 水資源、水供給、衛生に関する地域社会レベルでの管理-家庭や地域社会を単位とした適切な水供給技術、下水処理、小規模灌漑などの開発。水の使用量を減らし、汚染を防ぎ、排泄物の再利用を目指す、環境調和型衛生設備(エコロジカル・サニテーション)の推進。 |
| (2) | 統合的水資源管理(IWRM)-各国の開発の枠組みにIWRMを組み込むことを、対話の促進と政策支援により実施。海洋資源の管理強化の推進。 |
| (3) | 共有水域の課題-国際河川領域を対象に、沿岸諸国間の対話と、流域組織の形成を支援。 |
| (4) | 水と気候変動-気候変動の影響を水管理のあらゆるレベルで検討する。 |
| (5) | ジェンダー主流化-水資源管理と衛生に関する活動に男女がともに参加できるよう、「水資源管理におけるジェンダー主流化のリソース・ハンドブック」を作成。 |
| (6) | 効果的な水ガバナンス実現のための能力開発(統合的水資源管理のための能力育成プログラム)により、水ガバナンスの向上を目指す世界中の機関と提携する。地域主体であることと、地域の要望にこたえることが、能力育成を図る上での中心的原則である。 |
また、UNDPも参画している世界水発展報告書1は、国連の23機関による共同作業の結果であり、2000年に設立された世界水アセスメント計画(World Water Assessment Program 事務局はUNESCOの中にある。)が中心となってまとめられたこの報告書は、第3回世界水フォーラムにあわせて発表されたxiv。その構成は、第2回世界水フォーラムのハーグ閣僚宣言に沿った内容となっており、ポイントは、生命と福祉に関する6つの課題と、管理と統治に関する5つの課題につき、これまでの評価と、今後の指針を示している。
<生命と福祉に関する課題>
| (1) | 基本的ニーズと健康に対する権利 |
| (2) | 人類及び地球のための生態系の保護 |
| (3) | 都市環境において競合するニーズ-生活用水及び工業用水の需要に対する水供給の統合的管理、汚染物質や汚水の管理、洪水や氾濫の防止、水資源の持続可能な利用などが必要。また、多くの都市では、管轄の外から水を引き、汚水を下流に放流して他の利用者に影響を及ぼしているため、他の行政機関との協力が必要。 |
| (4) | 増大する世界人口に対する食糧確保 |
| (5) | すべての人の便益のため、よりクリーンな工業の奨励 |
| (6) | 開発需要に見合うエネルギーの開発 |
<管理と統治に関する課題>
| (1) | 水に起因する自然災害リスクの軽減及び不確実性への対処(保険制度など) |
| (2) | 水の分配-共通の利益の明確化 |
| (3) | 水の多面性の認識及び価値評価 |
| (4) | 知識ベースの確立-共同責任 |
| (5) | 持続可能な開発のための懸命な水管理 |
(2) 世界銀行
世界銀行の水資源管理政策(Water Resources Management - A World Bank Policy Paper1993年)では、以下の点が重要課題としてあげられていた。
工業用水:
- 広域の水管理、地下水の保全
- より効率的でアクセスが容易な飲料水供給・下水処理を普遍的に広めること
- 民間セクター、NGO、水利用組合の更なる参加
- 近代的な灌漑方式、原価回収への更なる注力、塩害対策、農業活動がもたらす水汚染への対策、既存施設の維持・改修、小規模灌漑への投資
- エネルギー需要管理、小規模かつ再生可能なエネルギーの開発、流域保全、既設ダム施設の利用
- 水関連プロジェクトの設計・実施における、住民移転の最小化、生態系の保全への更なる注力
- 水資源管理/効率の向上を新規水供給に優先させる
- 農業/地方給水のための、低価で環境に優しい新規水供給開発
- 水資源への投資、政策、制度を構築するための包括的な枠組みの開発
- 原価の回収、水資源のよりよい配分を可能とする料金政策の採用
- 参加型の政策形成
- 水中生態系の保護、地下水の過剰開発の禁止
- 灌漑事業による塩害発生の防止
- 環境保全、独占価格の排除を可能とする法的枠組みの構築
さらに、2002年3月のWater Resources Sector Strategyは、上記戦略を実施に移すためのもので、第二回水フォーラムや、世界ダム委員会報告書に依拠した内容となっている。ポイントとしては、水管理(Water Management)の重視であり、具体的には、法規制や制度整備などにより、水基盤施設(Water Infrastructure)と水管理を、同時に進行させなければならないことを強調している。
世界銀行は、水資源に関する融資残高が90億ドルにのぼるが、内80%は水資源関連施設に充てられ、残りの20%がキャパシティー・ビルディングに充当されている。しかし近年では、旧来の施設やセクターベースから制度的な側面における環境資源管理への投資へとシフトしてきている。xv
(3) アフリカ開発銀行
統合的水資源管理レポート(2000年、アフリカ開発銀行)では、その名のとおり、統合的水資源管理政策を基調としたものとなっている。要点は次の通り。
制度面
- 統合的水資源管理政策
- 水資源の量/質の評価/モニタリング
- 水資源に関わる人材の育成
- 統合的水資源管理に基づく洪水・旱魃対策
- 灌漑用水の効率向上、漏水の改善、水の再利用等による水利用・供給の増大
- リハビリを新規投資に優先
- 原価の回収
- 需要管理のツールとしての料金設定
- 中小規模の灌漑を優先支援
- 女性の水汲み時間短縮に貢献する案件
- 参加型意思決定
- 水因性疾病の防止
- 下水処理
- 浄化後の水の灌漑・工業への再利用
(4) EU
水資源開発協力のためのガイドライン(1998年)によると、EUの戦略は次のとおり。
プログラム
- 水資源評価及び計画
- 基本的飲料水供給及び下水処理
- 都市部給水及び下水処理
- 農業用水供給及び管理
- 制度改革、人材育成
- 参加型プロセス、ジェンダー
- 生態系・自然の保護
- 水資源関連情報の収集
- 需要管理と料金設定
- 水の価値に関する認識形成とコミュニケーション
(1) 他ドナーによる当該分野への協力実績
水資源開発分野は、多数のドナーからの援助を得ている。多国間援助機関では、EUが1976年から2002年の間に6億ユーロ以上の支援を行ってきたし、二国間援助機関ではフランスが、地方給水、水資源の保護、下水の再利用などの分野で、92年から2002年の間に9900万ユーロ(多くがAFDを通じた借款)をモロッコの水分野に支援している。ドイツもフランスと同様の分野で協力を行っており、ベルギーにとっても地方の給水と下水が最大の支援分野となっている。日本の協力のシェアも大きくなっており、評価対象期間中にかかる案件に限れば、金額では最大となっている (表2.3.1参照)。
これらの支援を得られたのも、PAGERというプログラムがモロッコ側にあったことが大きい。PAGERに対する支援だけでも、95年からの通算では、借款6機関、贈与が13機関となっている。またONEPが財政的に独立した存在であったことも有利に作用した 。xvi
他方、灌漑に関しては、近年モロッコ側が援助受け入れに必ずしも積極的ではなくなってきた、と指摘するドナーもあるxvii。比較的支援額が大きいのがEUと世銀であるが、そのEUや世銀でさえも、2002年から2004年までの農業分野の支援は限定的なものにとどまっている。
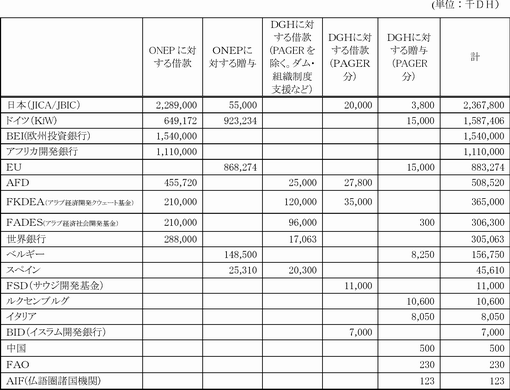
(2) 各ドナーの支援状況と方針
モロッコの水分野においては、UNDPが、かつてはPAGERのためのドナーコミュニティからの資金調達などに大きな役割を果たしてきたが、現在は、フランスとEUが、この分野で初めての本格的なドナーコーディネーションを試みるなど、オピニオン・リーダー的な存在となっている。さらに組織改革・水資源開発計画の策定支援などを行なっている世銀を合わせた三者が、日本以外の実質的な主要ドナーとなっている。アフリカ開発銀行もこれに同調している。
以下、モロッコの水資源開発分野における日本以外の主要ドナーの、1999-2001年を中心とした支援実績と方針を述べる。(水分野のONEPとDGHに対する各ドナーの支援実績は添付-5を参照。)
(1)フランス開発庁
フランス開発庁は、EUと並び、モロッコ全体としてもリーディングドナーである。
まず水供給については1993年から2003年に準備中の案件も含めてONEPを実施機関として6件、7500万ユーロの借款、PAGERではDGHを実施機関として1996年から2001年までに5000万ユーロの借款を供与した(EU、KfW、世銀、OECF (当時)との協調融資1143万ユーロ(98-2003)を含む)。
灌漑では、2000年にGharb平野の灌漑に2200万ユーロの借款を供与、中小規模灌漑としては1995年に1100万ユーロを供与した。その他セブの中規模灌漑(95-99、4970万ユーロ)など5件の借款を供与している。
下水に関しても、フェズの下水案件で世銀との協調融資2119万ユーロ(1996-2002年)、アガディールで1350万ユーロ(2000-2004)、メクネスでの欧州開発銀行との協調融資で1210万ユーロ(1999-2004)、ウジュダで1200万ユーロの借款(2001-2004年)を供与した。
ダムに関しては、灌漑及び水供給を目的とした3ヵ所の中規模ダムの建設(1997-2001、2600万ユーロ)に対する融資を行なっている。
AFDでは、2003年2月に、水分野の包括的な評価を行なったxviii。その結果、灌漑、衛生、水など別々の案件がセブ川流域管理局と十分なコーディネートせずに進めていたことが判明し、今後はフェズの流域管理局を支援することになった。目的は、各省、関係機関、流域管理局の連携である。
現地でのAFDインタビューによると、PAGERへの支援は、担当組織機構の再編が完了するまでは新規案件は行なわない方針である。また、大規模灌漑についても、ORMVAが組織改革中のため、農業省もそれが完了するまで大型融資の受入は控えたい意向で、AFDもこの意向を尊重している。中小規模灌漑についても、モロッコ政府の財政事情を考えると中小規模灌漑のために借款を要請することのプライオリティは低いとみている。
EU、AFDを中心として、水分野で協力している国がワーキンググループを作り、包括的な報告書を作成して、9月17日に外務協力省に提出したxix。報告書は、水分野の診断、水政策の進展、サブセクターごとの進展・診断、EU諸国のこの分野における援助の分析、提言という構成となっている。主な提案は、贈与と借款をインフラファンドとしてプールすることなどであるが、この報告書をきっかけに、ドナー同士、モロッコ側との本格的な対話が始まることが期待されている。
(2)EU
<EUの水資源開発分野の戦略・方針>
数年前からEUは包括的なPolicy Reformを財政支援するという戦略を取るようになった。水資源開発分野においても、セクターの改革案に対して、その移行コスト(Transitional Cost)を支援し、財政負担を軽くするための贈与を行っている。
同分野における改革に関する方針は「水フレームワーク」(FAS EAU MAROC Annex II.1)に述べられているが、その要点は、
| (1) | 95年の水資源法の実施支援(中央集権から、9つの流域ごとの流域管理局への分権化)。95年の水資源法制定以前は、ダムを作ることが政策であり、水の活用(Mobilization of Water)や需要管理は二の次であった。その意味で水資源法の制定は政策の大転換であったが、実施が思うように進まなかった。 |
| (2) | 上記に関し流域管理局への財政支援を実施する。 |
| (3) | コストをカバーできる水準への、水道料金の設定の方法論の策定。 |
| (4) | ORMVAの会計システムの支援-灌漑用水の使用料の徴収と活用の透明化。水の使用量の透明化。 |
| (5) | 汚染に対するペナルティの徴収。 |
以上に関し、120milユーロを供与している(構造調整のための贈与。2002年。水分野の構造調整-水資源法の施行、流域管理局の設立支援、統合的水管理、プライシングのシステム作りなど-に充当する。2003年以降、モロッコ側が最低でも年間1000万ユーロの予算を水分野に配分することが条件。)これにアフリカ開発銀行が協調融資で参加している。
<プロジェクトベースの協力>
これとは別に、旧来型の、プロジェクトベースの協力も行っている。主な案件としては、
- ONEPを実施機関とした飲料水・衛生プロジェクト。1972年より実施しており第五次が1993-2001年で2700万ユーロ(2億DH)の借款。
- DGHを実施機関としたPAGER 支援プロジェクト(1998-2005。Tata他、1億DHの借款)
- フェズの北100kmの灌漑プロジェクト(20milユーロの贈与)
- 中部HaouzとTessaout下流の灌漑(2002年に終了)(2150万ユーロ、贈与)
- 灌漑資金として、農業開発基金に500万ユーロを贈与した他、2006年までの総合農村開発に2840ユーロを供与
- 飲料水供給-2002年ソーラーポンププログラムの実施に220万ユーロの贈与
- 水経済管理-2002年Sidi Drissの土壌流出防止に550万ユーロの贈与
(3)世界銀行
<世銀の水資源開発分野の戦略>
2001年の世銀のメモランダム(Country Assistance Strategyxx)によると、モロッコはEUをはじめとする譲許的借款(Concessional Loan)を得られること、及び民営化による一時収入により以後3年間で5billionUS$の資金が見込めることから、海外からの大規模な資金援助は必要ないとしている。その中で、(1)地方部の支援、とくに地方分権化の支援、(2)引き続き構造改革のパートナーとなること、(3)政府機関の調整メカニズムの改善を受けて、他のドナー、とくにEUとアフリカ開発銀行とのパートナーシップを強化することを三つの戦略としてあげている。
また、近年、モロッコにおける世銀の支援は分析やアドバイザリーサービスへシフトしてきており、民営化などの際の政策支援、農村開発等に関する広範な調査を行なっている。現在の主要なエリアとしては予算の近代化、農業戦略、分権化と地方自治体のマネージメント(地方自治体のインフラにおける民間セクターによるファイナンスを含む)等があるxxi。
水分野については、1998年より、DGHへの借款などにより水資源法の実施を支援している。主な分野としては、キャパシティビルディング(流域管理局第一号の立ち上げを支援)と水に関する計画作り(National Water Plan:包括的な水分野のマスタープランでDGHがベクテルのモロッコ現地法人に委託して作成中。まもなく完成する)である。
水資源法自体は、1995年の制定であり、戦略的にはアップデートする必要があると世銀は考えている。例えば流域管理局が、財政的にも組織的にも国から独立するためには適正な料金の設定などが必要であるとしている。
地方部の飲料水供給プロジェクトとしては、
- PAGER支援-1997年に1000万ユーロの借款、1998年に2160万ユーロの借款
- 水経済管理-1999年、アズィラルの流域管理に550万ユーロの借款
- 水処理施設建設-1996年に下水処理・再利用施設の建設に4320万ユーロの借款
<灌漑>
世銀では全ての灌漑プロジェクトを2000年に一旦終了してアセスメントを行った。その結果、大規模灌漑については、利益が維持管理に活かされない構造が明らかになった。灌漑による収益が、水の分配そのもの、新規灌漑の開発、農業開発に使われていた。そこで、給水サービスを二つに分けることを提案した。すなわち、零細農民が料金を払わずに給水を受けられる公的なサービスと、PPPなどを活用して民間や大口の利用者が料金を支払って、サステナビリティを確保するという二つの機能に分離することである。現在、世銀は大規模灌漑についてはプロジェクトを実施しておらず、この機能分離に注力している。
小規模灌漑については、Irrigation-based Community Development プロジェクトを実施している。これは農業省、ONEP、水利庁、保健省を巻き込んだ総合的な村落開発である。
2002年以降の案件では、2002年にアジラル、ケニファ、エルフズの中小規模灌漑に3480万ユーロを供与。また、2003年に、灌漑分野の組織制度開発支援に500万ユーロの供与が予定されている。
(4)アフリカ開発銀行
アフリカ開発銀行の対モロッコ戦略は、(1)マクロ経済の安定化と持続可能な成長、(2) 民間セクター開発、(3)貧困削減、(4)グッドガバナンス、となっている。xxii
この中で水関連としては、
-農業セクターレビューにより、気候変動によるインパクトの軽減を検討する(上記(1)関連)。
-様々な借款の供与によるインフラストラクチャーの強化(飲料水供給など)(上記(2) 関連)。
主な案件としては、
- PAGER-1999年に2650万ユーロの借款、2000年にONEPに対し70地区の飲料水供給のための借款(2008万ユーロ)
- 都市給水1999-2002年にボズニカ、ティズニット他の都市で2500万ユーロの借款
(5)UNDP
<UNDPの水資源分野の方針>
UNDPはモロッコの水セクターを積極的に支援してきており、とくに飲料水供給は、過去10年間のNo.1プライオリティであった。ONEP の設立や、DGHのNational Plan of Drinking Water の策定を支援し、PAGER計画の策定にも関わってきた。とくにPAGER計画の開始においては、前述のように、UNDPがファンドレイジングを行った。(ラバトとニューヨークでそれぞれラウンドテーブルを主催。その後3回目をFAOがローマで開催。)これらのファンドレイジング活動により、たとえば中国がはじめてモロッコに対する協力に参加するなど、広範なドナーの支持を集めることに貢献している。またNGOをPAGERに動員するためのプロジェクトも実施したほか、DGHやONEP職員のトレーニング、流域管理局のキャパシティビルディングも支援してきた。しかし現在は、ONEPやDGH等の水セクターにおける関連機関の機能が再構築されている途中であることから、水分野のプロジェクトは飲料水・灌漑とも行っておらず、水供給は環境案件の一環として実施している程度である。
他方、多くの社会問題(教育、衛生、女性の識字など)が水問題を取り巻いている。長時間の水汲み、しかも質の低い水しか得られない状況から女性・女児を解放することが必要であるとUNDPは考えており、2002年からの機構改革の結果に期待している。xxxiii
(3) ドナーコーディネーション
モロッコでは、既述のとおり借款の案件については財務民営化省が取りまとめ、優先順位を決めている。無償や技術協力については外務協力省が窓口となり各ドナーと個別に協議している。PAGERのように海外から大規模な支援を受けているプログラムにおいても、ドナー同士が話し合うことはなく、モロッコ側がドナーの希望を勘案して地域等を調整、振り分けている。
他ドナーからのヒアリングでは、PAGERという一つのプログラムであってもドナーにより様々な条件で実施しており、ドナー間の情報交換が効果的に行なわれていたとは言えない。各ドナーには各ドナーの制約があり、例えば借款に技術協力のコンポーネントがつけられないドナーは完工後の維持管理をモロッコ側に一任するしかないが、それがうまく行っていないケース、単独で借款を決めていたのにモロッコ側により協調融資をもちかけられて大幅に遅延し最終的に全額ディスバースできなかったケースなど様々な問題があり、より綿密な情報交換が必要と認識されている。PAGERに関しては、2002年2月に世銀主催の大規模な中間レビュー会合がラバトで開催された。
既述のようにEUでは加盟各国が協力し水分野のワーキンググループを作り、包括的な調査を行なうなどして、この問題の改善を試みている。
モロッコ全体としてのドナー会合は2003年3月よりフランス大使館とEUが主導しフランス大使館で開催されている。メンバーはフランスのほかスペイン、ドイツ、ベルギー、カナダ、日本、イタリア、ギリシャ、UNDP、USAID、世銀、EUとなっており、日本は大使館の経済協力担当官がメンバーとなっている。2003年9月までに4回の会合が行なわれており、四つあるワーキンググループの進捗報告、各ドナーからの報告やディスカッションが行なわれている。これ以前にも、カナダ大使館書記官主催のインフォーマルな昼食会が開かれていたことがあるが、1999-2001年のドナー会合の存在は確認できなかった。
今後水分野ではとくにEUとフランスを中心とした情報交換や協議が行なわれるとみられ、この動向にも留意していくことが必要である。
1 世界水開発報告書と訳されている場合もある。(UNDPホームページなど)
i 小林正博(2003)「第三回世界水フォーラムと国際協力」、『国際協力研究』、Vol.19 No.1:49-57、村上雅博 (2003)『水の世紀』、日本経済評論社
ii 統合的水資源管理の定義には統一されたものはないが、「世界水パートナーシップ(Global Water Partnership)」の定義では、「統合的水資源管理とは水や土地、その他関連資源の調整を図りながら開発・管理していくプロセスのことで、その目的は欠かすこのできない生態系の持続発展性を損なうことなく、結果として生じる経済的・社会的福利を公平な方法で最大限にまで増大させることにある」(石森康一郎(2003)『統合的水資源管理』、FASID)
iii 世界水会議:World Water Council (WWC)-世界銀行、国際水資源学会(IWRA)など、水に関する国際機関や国際学会などが中心となり、水に関わる国際政策の検討会などを行うことを目的に1996年に設立されたシンクタンク。
iv 第3回世界水フォーラムホームページwww.world.water-forum3.com/jp/statement.html、国土交通省ホームページwww.mlit,go,jp/tochimizushigen/mizusei/wwf3/shisaku/index.html, 大原淳子(2003)「第3回世界水フォーラムの成果」、『FASID最新開発援助動向レポート』No.7:1-9
v World Water Forum, Marrakech Declaration (March 22, 1997). http://www.Waterforlife/jp/wwf /wwf_003 _00.html
vi 側嶋秀則(2003)「第三回世界水フォーラムの意義と課題」、『国際問題』、日本国際問題研究所 35-36)、小林正博(2003)「第三回世界水フォーラムと国際協力」、『国際協力研究』Vol.19 No.1:49-57
vii 「21世紀における"水のセキュリティ"に関するハーグ閣僚級会議での宣言」 http://www.idi.or.jp/visioin/dec-j.htm, Declaration of The Hague Complete Text http:// www.waterforlife /jp/wwf/wwf_003_01.html
viii 世界ダム委員会は12人の委員からなる委員会。委員の構成はダム反対のNGOから産業界、先進国・途上国と微妙なバランスの上に成り立っていた。1998年5月の設立以降世界各地でヒアリングや会議を重ね、2000年11月に報告書を作成して解散した。以後UNEP(国連環境計画)がフォローアップを実施している。
ix Dams and Development:A New Framework for Decision-Making, (November 16, 2000) . http://www. dams. org
x http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/wssd/clearw.html
xi 第3回世界水フォーラムホームページwww.world.water-forum3.com/jp/statement.html
xii 第3回世界水フォーラム最終報告書(2003)、第3回世界水フォーラム事務局 2003
xiii 側嶋秀則(2003)「第3回世界水フォーラムの意義と課題」、『国際問題』、日本国際問題研究所:34-35
xiv 国連World Water Assessment Program『世界水発展報告書』(2003)
xv 石森康一郎(2003)『開発援助の新しい潮流:文献紹介No.24 Water Resources Sector Strategy: Strategic Directions for World Bank Engagement』、FASID
xvi フランス大使館 Financial Aid to Development in Morocco(May-June 2002)
xvii 同上。その他ドナーインタビューによる。その理由として、i) 灌漑事業の目標値が既にある程度達成されたこと、ii) ORMVAが組織改革の途中であること、iii) 農業セクター政策への他国からの干渉を避けたい意向があること、等が指摘されている。
xviii AFDモロッコ事務所Charge de Mission, Fornage氏インタビュー(2003年9月19日)による。
xix Union Europeenne, Le Secteur de l'eau au Maroc Rapport du Groupe Thematique Eau, 2003
xx World Bank, Memorandum of the President of the International Bank for Reconstruction and Development and the International Finance Corporation to the Executive Directors on a Country Assistance Strategy of the World Bank Group for the Kingdom of Morocco(May 7, 2001)
xxi World Bank, Morocco in Brief (June 2003) http://wbln0018.worldbank.org/mna/mena.nsf
xxii African Development Bank, Morocco Country Strategy Paper 2000-2002 (September 2000), Country Department-North Region
xxiii UNDP モロッコ事務所Meryen ZNIBER氏インタビュー(2003年9月19日)による。

