第2章 評価対象を取り巻く状況
2.2 モロッコの水資源開発政策モロッコの国家開発計画として5ヵ年計画(2000-2004)を、また水資源開発政策として上記5ヵ年計画の他に、水資源法、流域別水資源総合開発計画、国家灌漑計画(PNI)、地方給水計画(PAGER)の内容を概観し、合わせて最近の動向についてとりまとめた。
(1) 長期的な人口動態及び社会・経済の展望
モロッコ国政府は国家開発計画に基づいて政策を推し進めており、現在は(2000-2004)5ヵ年計画の段階にある。従来はマクロ経済の安定化や経済成長が重視されてきたが、同5ヵ年計画ではこれらに加え貧困問題、教育、地域格差等の社会的課題への対応により積極的な姿勢がみられる。
同計画では計画期間内の人口増加率を年1.6%と想定し、1999年に28.2百万人だった人口が2004年に30.5百万人、2010年には33.2百万人に達するとしている。15歳未満の若年層が全体に占める比率(2001年時点で31.6%)が依然として高いこと、また1992年には50%にとどまっていた都市部人口が2010年には62%に達すると見込まれることから、こうした人口動態の帰結として、(1)教育、(2)雇用、(3)保健衛生、(4)水資源、(5)道路、(6)住宅、(7)食糧への更なる需要が増加することを想定し、これらの重点セクターに対して中長期の具体的な数値目標を設定している。
(1) 教育:中等教育修了者は1999/2000年(7‐6月)の510万人を、2004/05年に640万人、2010年には700万人に増加させる。高等教育就学者数は、1999/2000年の25.1万人から2004/05年に34.8万人、2009/10年には45万人に増加させる。大学入学者数は1998年の7.2万人を2005年に10.1万人、2010年に13万人に増加させる。
(2) 雇用:2000年から2010年までの間に年間30万人の新たな雇用を創出する。
(3) 保健衛生:医療保険の被保険者率を現在の15%から2004年には30%に引き上げる。医師数を1999年の12,082人(医師一人あたりの国民数2,300人)から2004年には15,270人(同2,000人)に増加させる。
(4) 水資源: 2020年に予想される水需要を満たすために必要なダム及び地下水井戸の建設を実施する。とりわけ、今後年4%の増加が予想される飲料水需要に対しては、2010年までに飲料水の供給を倍増することで対応する。具体的には、都市部の上水道普及率を1999年の85%から2010年には94%に引き上げ、農村部でも1999年に38%であった普及率を向上させる。また水資源分野の民営化を推進する。
(5) 道路:2.5万km区間における補強・舗装、130ないし150箇所の道路構造物のリハビリ、400箇所の整備事業を実施する。
(6) 住宅:75万戸の供給不足を解消する為、現在の2倍に相当する年18万戸のペースで住宅を建設する。
(7) 食糧:需要増に対応するため、国家灌漑計画(PNI)の達成等に取り組む。
(2) 経済・社会開発の基本方針
5ヵ年計画(2000-2004)で列挙されている経済・社会開発の基本方針は、(1)制度改革、(2)経済成長と雇用創出、(3)農村部の開発、(4)国土開発と地域格差の是正、(5)人的資源の開発、教育改革、(6)社会開発と不平等の是正である。各方針で記載されている内容は以下の通りである。
(1) 制度改革:行政の近代化、司法制度改革、公益事業改革、地方分権推進、開発計画への市民参加、等
(2) 経済成長と雇用創出:繊維産業の強化、投資の奨励、輸出促進と世界経済との融合、金融セクター強化、土地問題の解決
(3) 農村部の開発:国家灌漑計画・地方給水計画・地方電化計画・地方道路計画等の推進
(4) 国土開発と地域格差の是正:持続可能な開発、自然環境の保護
(5) 人的資源の開発、教育改革:初等・中等教育、高等教育、科学・技術研究、職業訓練の向上、非識字率の低減、等
(6) 社会開発と不平等の是正:貧困撲滅と基礎的サービスへのアクセス向上、保健衛生、女性・若年層の地位向上、等
水資源開発との関係では、(3)農村部での開発と(6)社会開発と不平等の是正で、地方村落部での給水に言及している点が注目される。
水資源法iは1995年9月政府により承認された水に関する政策づくりの基本法である。同法では、「水と気候に関する最高協議会」に対し、水・気候に関する国策・一般ガイドラインの策定を命じている。
モロッコにおける最初の水関連制度の条文は1914年の勅命 (Dahir) に遡る。以降、水資源は原則として公共財と見做され、法的に承認される場合を除いて私的な専用が認められなくなった。同勅命に続いて他の条文が追加的に制定されてきたが、全般として水に係る制度の本質的な部分は20世紀前半にできたものであった。水資源法(95-10)制定前はこれら別々の条文がそれぞれ異なる過程を経て改定されてきた。当時は需要そのものが小さく、また水資源開発技術が未熟であったという点で現在の水利用状況は当時と異なる状況にあった。こうしたことから水関連の法律を改定し、一つの法律にまとめる必要性が認識され、1995年の水資源法制定に至った。
水資源法の目標は、合理的な水利用、水へのアクセス拡大、及び地域格差の是正であり、これらを達成するために以下の目的を設定している。
- 首尾一貫しかつ融通のきく流域レベル及び国家レベルでの水資源開発の計画策定。
- 国家水計画で設定される優先順位を反映した、すべての水資源の最適な開発と合理的な管理。
- 地形学的単位、即ち流域を枠組みとする水資源管理。流域は水資源に係る問題を認識・解決すると同時に、共通の水資源を利用する利用者の地域的連帯意識を醸成するのに最も適するとしている。
- 公共財としての水の質的・量的保全。
- 適切な水行政。
水資源法は13の章、123の箇条から成っている。章立ては、(1)公共財としての水、(2)公共財としての水に対する既得権、(3)公共財としての水の保全と防御、(4)水利流域開発と水資源利用の計画、(5)水利用の一般取り決め、(6)水汚染の克服、(7)飲料水及び食品用の水、(8)治療目的に資する自然水の開発と販売に関する処置、(9)農業用水の開発と利用に係る処置、(10)渇水時の水利用に関する処置、(11)その他処置、(12)ローカル共同体と水、(13)水の監視(違反と罰則)からなる。
第4章「水利流域開発と水資源利用の計画」では、「水と気候に関する最高協議会」の機能・構成、「国家水計画」と「流域別水資源開発計画」の定義、「流域管理局」の責任・運営協議会の構成・予算等が定められている。
「水と気候に関する最高協議会」は水と気候に係る国家政策の方針、即ち以下の策定を担う。(i) 気候を認識しその水資源開発への影響を把握するための国家計画、(ii) 流域別水資源開発計画、(iii) 国家水計画。同協議会のメンバー構成は、半数が中央政府・流域管理局・水道公社(ONEP)・電力公社(ONE)・地域農業開発公団(ORMVA)、他の半数は水利用者・府ないし県代表、専門分野別有識者等から構成される。
「流域別水資源開発計画」は、各流域毎の水資源に関わる長期(20年間)のマスタープランであり、流域境界、流域内の水資源賦存量・水需要の評価、セクター別の水配分計画、水資源の開発・保護の為の施策等が定められる。これらの流域別計画に基づき、「国家水計画」が策定される。同計画には国家レベルでの水資源開発とその優先度、並行して実施すべき組織・制度上の対処、流域間の水資源導水等が定められる。流域別計画と同様、20年間を対象期間とする。
「流域管理局」は、流域別水資源開発計画の策定、同計画の実施、水利用の許諾、水資源開発・汚染防止を行う官民組織への財政的支援、水資源開発管理・水理地質等の調査実施、水質の維持、渇水もしくは洪水時の対処実施等を行う。同管理局を司る評議会は、中央・地方政府、水関連の公社・公団、関連業界協会、水利組合等の代表からなる評議員で構成される。またその予算は、水利用の料金、政府補助金、借入等から調達される。
また第13章「水の監視(違反と罰則)」によれば、中央政府と流域管理局から委任された執行官は警察とは独自に、井戸、取水口へのアクセス、検査、及びそれらが違反に該当する場合での使用停止命令を下すことができる。水利施設の損壊、執行官への妨害、法に違反しての表流水・地下水の取水等の場合には罰則が適用され、流域管理局は認可を受けていない取水口を閉鎖する権限を有する。
(1) 流域別水資源開発計画
流域毎の水資源開発長期政策は、国を大きく6つの流域に区分して計画が立案され、流域別水資源開発計画に記述されている。これら計画の目的は飲料水、工業用水、灌漑及び水力発電等の異なるセクター毎の水需要を予測し、統合された水資源開発を最適化することにある。

2020年におけるセクター別の水需要は表2.2.2のように予測されている。これらの需要は各流域内の水資源、及び流域外水資源の転流により満たすこととされている。
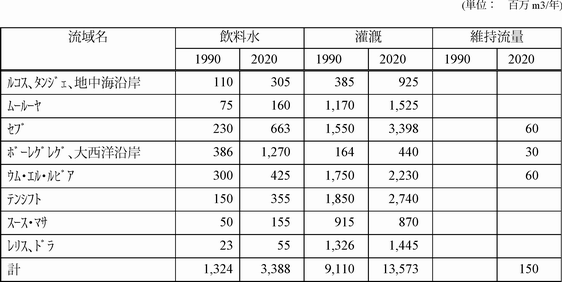
(出所) SYNTHESE DES PLANS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT INTEGRE DES EAUX DES DIFFERENTS BASSINS DU ROYAUME, SECTEUR EAU POTABLE, 1999, ONEP
(2) 国家水計画
世界銀行の資金により1999年7月より、従来水系ごとに策定していた水管理計画を取り纏める目的で「国家水計画」策定が実施されている。セブ、ボーレグレグ、ウム・エル・ルビア流域他の流域別水資源開発計画の策定からすでに10年近く経過していること、また近年の渇水により利用可能な水資源量が低減していることから、既存の流域別計画の見直しを行っている。
国家5ヵ年計画(2000-2004)では、水利部門(水利総局)の目的として、(1)都市部及び地方村落部での飲料水供給への貢献、(2)食糧供給への貢献、(3)水利施設の修復・維持、(4)水質の改善・維持、(5)河川氾濫や洪水からの国民・財産の保護、(6)水力発電のための包蔵水力開発、(7)全土への公平な水の分配とそれに伴う地域振興、が掲げられており、これらの目的を達成するための基本方針とプログラムとして以下が列記されている。
- 水資源の把握と評価:質・量の面からの水資源の正確な把握と迅速な管理を目的として「水資源評価目録プログラム(PIERE)」を実施する。具体的には水文観測所15箇所新設と200箇所改修、水文データの分析と情報処理、水資源調査の強化、水質の調査と管理等。
- 水資源開発計画の策定:国家水計画の策定と既存流域別水資源開発計画(ムールーヤ、セブ、ボーレグレグ、ウム・エル・ルビア)の改定・強化。
- 水資源開発の実施:ダム建設による表流水開発、地下水開発プログラム(PROMES)、及び地方給水計画(PAGER)の3種のプログラムから成る。
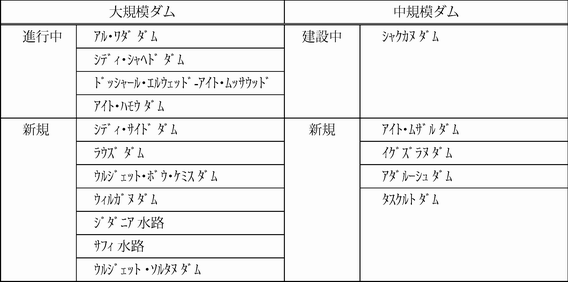
地下水開発プログラム(PROMES)は地下水資源の把握とその開発を目的とするものであり、深層地下水の開発と飲料水・灌漑用地下水開発の2つの内容からなる。前者は深刻な水不足に直面している高・中ムルヤ、タウリルト-ウジュダ地域、エッサウイラ-アガディール地域等を対象とし、3万mの井戸掘削を予定している。一方、後者は都市部・地方村落部の飲料水・灌漑用水の需要を満たすためのプログラムであり、全長20万mの井戸掘削を予定している。
地方給水計画(PAGER)では地方村落部で1999年時点に38%の飲料水アクセス率を2004年に62%まで引き上げることを目標としている。
- 水資源の運営管理:水の運営管理(PGRE)として、国家洪水防御計画の立案、ガルブ平野の洪水防御、ダムの堆砂調査・堆砂対策計画、ダム下流の段波に係る調査、水の需要管理に係る調査、水質保全のための施策を行う。
- 水利施設の保全:日常的な補修、大規模な修復、ダムの貯水容量の確保等を行う。
- 洪水対策:実施中案件を計画期間内に完遂する。
- ダム整備に係る調査:13件の大規模開発に係る調査継続、10件の大規模案件・26件の中規模ダム案件に係る新規調査、及び地方からの要請に従って小規模ダム案件の調査を実施する。
- 情報処理システムの強化:情報処理ガイドラインの策定、中央情報システムの更新、情報・管理システムの設置、地方部での地質情報システムの強化、ダムの維持管理への適用強化を行う。
- 制度改革:事後評価システムの導入、水行政の能力強化、水資源法の適用、流域管理局の設立、既存水利権に係る調査、一般市民への啓蒙を実施する。
国家5ヵ年計画(2000-2004)における灌漑部門の活動計画は、(1)新規灌漑開発、及び(2)灌漑効率の改善(リハビリ及び近代化)の2つの主要項目よりなる。
新規灌漑開発事業は、大規模灌漑事業86,120 ha及び中小規模灌漑事業13,620 haの計99,740haからなる。前者は国家灌漑計画事業(PNI)第1期事業の完了32,900 haとPNI第2期事業53,220 haからなる。一方、後者はPNI第2期事業3,300 haと、PNI以外の事業10,320 haからなる。
一方、リハビリと近代化を通じての灌漑効率改善に関する事業は、計150,900 haで、その内訳は大規模灌漑事業14,400 ha、中小規模灌漑事業は136,500 haである。
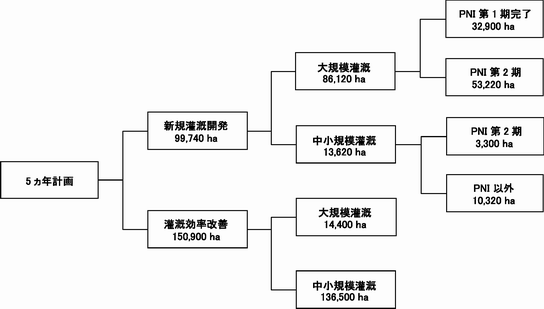
図2.2.1 5ヵ年計画における灌漑事業
なお、国家灌漑計画(PNI)は大規模灌漑の新設227,900 ha・リハビリ 66,100 ha、及び中小規模灌漑事業の新設16,120 ha・リハビリ 138,000 haで構成される。
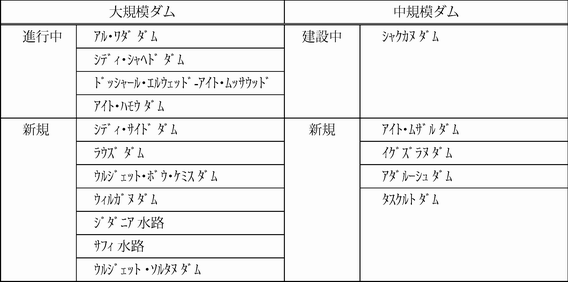
(出所) Programme National d'Irrigation
国家5ヵ年計画(2000-2004)の飲料水供給部門の目的としては、(1)都市部で2004年に各戸給水率89%の達成、(2)地方村落部で2004年に飲料水アクセス率ii62%の達成、(3)飲料水生産・配水施設の適切な維持保守、(4)ONEPの自己資本率の向上、(5)水質の改善、及びより経済的なサービスの提供が謳われている。これらの目的を達成するためのプログラムとして以下が同計画に列記されている。
- 都市部(ONEP):5ヵ年計画期間中にONEPは81.84億ディルハムを投資額として計上している。その内訳は生産に49.74億ディルハム(全体の61%)、配水に6.28億ディルハム(同8%)、調査等の共通費に24.42億ディルハム(同30%)となっている。またこれとは別に水資源・環境の保護に1.4億ディルハムを見込んでいる。
- 都市部(ONEP以外):自治体の公社、民間及び厚生省の投資額として、計48.2ディルハムを見込んでいる。
- 地方村落部:5ヵ年計画期間中に地方給水計画(PAGER)の為に、DGH計画に28.2億ディルハム、ONEP計画に12.45億.ディルハムをそれぞれ計上している。
モロッコは現在、1995年に制定された水資源法を具現化する作業を進めている。同法で謳われている「流域別水資源開発計画」の策定が、一部(レリス・ドラ流域)を除いて終了したが、それらの見直し・取り纏めとして「国家水計画」の策定が目下実施されている。また「流域管理局」が各流域で設立され、流域を単位とする総合的な水管理に取り組み始めている。
2001年に開催された「水と気候に関する最高協議会」第9セッション以来、モロッコでは水管理の重要性が一段と認識されてきているiii。即ち、これまで整備されてきたダム・灌漑・給水施設が同国の飲料水や食糧の確保に多大な貢献をなしてきたことを認めた上で、こうした施設整備による供給増に加え、限られた水資源の有効利用のための需要管理や組織・制度面での改革をより重視する方針が明確に打ち出されてきている。この背景には今後開発可能な水資源賦存量が漸減していくことに加え、地下水の過剰な開発による枯渇、ダムの堆砂、あるいは全国レベルでの水質悪化が進んでいることに対する危機感がある。
他に注目されるのは、ONEPの機能強化である。PAGERは当初2010年までに地方村落部で飲料水アクセス率を80%迄引き上げる計画であったが、2002年には国王が目標達成率向上の勧告を行い、2007年までに90%のアクセス率達成が新たな目標となった。これまでPAGERはDGHが水源開発、ONEPが配水管分岐というように分担して行われてきたが、2004年1月以降は原則としてONEPが全てを担当するという方針が打ち出されている。
またモロッコ政府はONEPが下水道事業にも参加できるような法改正を行った。従来、中小都市での下水道事業は地方自治体が担当してきたが、人口増加や財政悪化等により下水道整備は上水道に比して進捗が見られなかった。同事業に参入可能となったONEPは上水を配水している全ての管轄区域をカバーする投資計画を立案している。
i Loi N ° 10-95 sur l'Eau
ii アクセス率は、通常水場までの距離が0.5km以内、散村では1km以内を想定(ONEPでのヒアリングによる。2003年9月22日。)
iii CSEC, La Gestion de l'Economie de l'eau

