第2章 評価対象を取り巻く状況
2.1 モロッコの概要(1) 国土・人口
モロッコはアフリカ大陸の北西端に位置し、北は地中海、西は太平洋、東はアルジェリア、南は領有権を主張する西サハラを経てモーリタニアと接している。
国土面積は45.9万km2で日本の約1.2倍、西サハラを含めば約71万km2となる。人口は西サハラを含めると約2917万人(2001年)iでこの内約半数強が都市部に居住している。人口の65%をアラブ人(淡黄褐色の皮膚-セム族系)、残り35%をベルベル人(北及び北東アフリカの白人系住民-ハム族)が占めている。公用語はアラビア語だが、フランス語も広く用いられている。イスラム教が国教となっており大部分を占めるが、その他にキリスト教、ユダヤ教徒もいる。
モロッコの地方行政単位は、16の「州」 (region)、26の「府」 (prefecture)及び45の「県」 (province)、1547の「コミューン」(市町村にあたる)で構成されている。添付-3に地方行政区分図を示す。
(2) 政治
政治体制は立憲君主制を採っている。元首は国王で1999年7月のハッサン2世死去に伴いモハメド6世が王位を継承した。同国王は、前国王による内外政策(立憲君主制・複数政党制の堅持、経済の自由化、地方分権、人権の尊重、法治国家の建設、西サハラ統一等)を基本的に継承しており、政治は比較的安定している。
国王はまた行政府及び国軍の長であり、国王が首相を指名し首相が閣僚を指名する。議会は比例代表制直接選挙による下院と間接選挙による上院からなる二院制をとっている。1996年に国民投票を経て二院制を創設するための憲法改正が行われ、翌1997年に両院の議員選挙が実施された。その後2000年には上院の改選、2002年にはモハメッド6世国王治下初めての下院選挙が実施された。
1997年に行われた両院選挙を受け、1998年には40年ぶりに社会主義・中道政党からなる連立政権であるユスフィ内閣が発足した。同政権は2000年8月に国家開発5ヵ年計画 (2000-2004) を国会で通過させ、民主化や経済自由化等の課題に取り組んできた。2002年の下院選挙では連立与党が勝利し、選挙後の組閣においてジェットゥ首相が任命された。ii
内政上の主要施策としては、行政改革、雇用創出、農村部の開発、地域格差の是正、人的資源の開発、社会開発と不平等の是正等が5ヵ年計画で謳われている。
外交については、モロッコは非同盟、親欧米を基調としており、アラブ諸国の中でも穏健派に属する。アラブ・イスラム諸国やEU・米国との協調関係を基本としつつ、サハラ以南のアフリカ諸国及び中南米諸国との関係強化も図っている。また、今後EUへの加盟が見込まれている東欧諸国との交流を活発化させ始めている他、アジア諸国との交流も行っている。
我が国は1956年6月にモロッコの独立を承認し、1961年に大使館を設置した。モロッコも1965年に我が国に大使館を設置しており、両国は伝統的に友好関係にある。最近、両国の要人往来が活発に行われると共に、有償・無償資金協力、技術協力等を通じてのモロッコへの経済協力が活発に行われている。また、文化交流を通じて相互理解の増進が図られている。
(3) 経済
モロッコの主要産業は、農業、繊維業、漁業、鉱業(燐鉱石)等であり、2002年のGDP及び国民1人当たりGDPはそれぞれ362億ドル、1,222ドルiiiであった。GDPに占める各産業の割合は農業分野16%、工業31%、サービス業53%ivとなっている。
農業生産が天候に左右されやすく、96年は降水量に恵まれ11.8%の経済成長率を達成したものの、翌年は旱魃のためマイナス成長を記録した。旱魃がほぼ隔年に訪れ、その影響で成長率がマイナスを記録する傾向がある。2000年は前年に続く旱魃に見舞われたが、政府の補助金投入等の積極的対策により、プラス成長に転じ、2001年は6.5%、2002年は3.2%の経済成長を記録した。
総貿易額は輸出78億ドルに対し輸入118億ドル(いずれも2002年)で輸入超過となっている。主な輸出品目は、既成服、生地・織物、燐酸液、甲殻類、燐鉱石、肥料等、また輸入品目としては原油、機械、小麦、化学製品等となっている。海外の出稼ぎ労働者からの送金も主要な外貨獲得源となっている。なお、我が国との貿易に限ると、歴年モロッコ側の黒字計上となっている。2002年の対日輸出額は3.19億ドルでその品目がタコ、イカ、燐酸塩等である一方、輸入額1.37億ドルで、品目は産業用車両、特殊車両、各種機械等であった。
(4) 社会
人口増加率は近年低下傾向にあるものの、2001年は前年比で約1.6%であった。地方農村部での人口がほぼ横ばいであるのに対し、都市部では約2.9%の増となっており都市部への人口集中が認められる。教育・医療等の社会インフラ及び運輸・通信等の経済インフラが都市に集中し、地方村落部との格差を広げているのがその一因と考えられる。また旱魃の影響を受ける年には地方村落部から都市部への人口流入が顕著となり、社会不安をもたらしている。こうした背景から、モロッコ政府は地方村落部と都市部の地域格差解消を重点課題の一つに掲げて取り組んでいる。
とくに北部地域では大麻の栽培、密輸の防止のため、これらの取り締まりを強化するとともに、麻薬栽培の中心となっている地域の開発を進めるため、農民に代替作物への変換を勧め、農業開発や社会インフラの整備を積極的に推進している。
また人口構成を年齢別にみると、15歳以下の若年層の比率が依然として高く、今後教育・雇用問題への対応を迫られることになる。一方コーランに基づく身分法は男女の基本的区分を定めており、女性の権利を制限している。女性の就学率・識字率は男子に比べて低く、就労の機会にも恵まれない状況にある。
モロッコはアルプス造山帯の一部をなすアトラス山脈上に位置し、地形的には中央部の山岳地帯とその西側の大西洋岸沿いの平地及びその東側の乾燥丘陵地に大きく区分される。山岳地帯は北からリフ、中アトラス、高アトラス、アンチアトラスの4山脈からなっている。この内、中アトラス山脈にはセブ川、ウム・エル・ルビア川等、水源としての河川が比較的多く、これらは大西洋及び地中海岸の平地を横切り海に注いでおり、その周辺には農業地帯が形成されている。一方、高アトラス山脈を水源とし南部に流れる川は、砂漠の中に消えている。
モロッコの地中海沿岸から大西洋沿岸中部までの一帯は地中海気候で、夏は乾燥して暑く、冬は温暖で雨が降る。平地部では内陸に入るに従い雨量が減少し、大西洋南部から西サハラにかけては、半乾燥地帯から砂漠へと続いている。山岳地帯では高度を増すにつれて降水量が増加、気温も低下し降雪が見られる。一方、東部モロッコと高アトラス山脈の南側は降水量が少なく、半砂漠地帯から本格的な砂漠地帯になっている。
過去20年間 (1980-1999) の主要都市における気象観測データを整理したものをを表2.1.1に示す。

(出所) 地方水資源開発計画調査 最終報告書 Vol.III
モロッコの主要河川の概要を表2.1.2に示す。
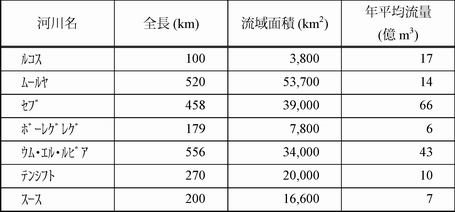
(出所) 地方水資源開発計画調査 事前調査報告書
モロッコの年降雨総量は年により500億m3から4000億m3の間を変動するが、平均で1500億m3に達し、この内、蒸発散で年平均1210億m3が失われる。残りの水資源賦存量290億m3の内、技術的・経済的に開発可能な水資源量は年平均で200億m3であり、その内訳は表流水160億m3、地下水40億m3であるv。

モロッコでは以前から水資源開発が重要視されていたが、近年の都市化の進展、工業の発達、灌漑面積の拡大などにより水需要の伸びが著しく、水資源開発の重要性が一層認識されるようになった。同国全土でこれまでに103の大規模ダムが建設され、総貯水容量は157億m3に達している。この他に13の導水システムや、地下水開発の為の施設が建設され、これらにより年平均130億m3相当が既に開発済みとなっている。vi
同国では従前より水利総局(DGH、2002年に設備省から国土整備水利環境省の水利庁に移管)が国全体の水資源政策の策定、水関連機関の調整、管理、水資源調査を担ってきた。都市部の給水は1972年に設立され1995年に設備省の管轄下より独立した水道公社(ONEP)が担当、また地方自治体が直接、あるいは公社を設立して給水にあたっている。一方、地方村落部の給水はDGHが水源開発、ONEPが配水管分岐によるというように分担して行われてきた。この他、農業・農村開発省は農業用水施設の施工、維持管理を担当している。
(1) 農業
前述したようにモロッコ経済において農業は基幹産業であり、同国国内総生産の約16%を占めている。2001年における農業労働人口(林業、水産業を含む)は約430万人で、全労働人口の約41%に及んでいる。特に地方部では農業関連産業が経済活動の主要部分を占めており、農業振興による地方経済の活性化が同国の重点課題として掲げられている。
モロッコの国土面積は45.9万km2(西サハラを除く)、そのうち耕地面積は902万ha(2000/01)で国土の約20%を占めている。穀物耕作地の面積は、全耕作地の57%を占めている。また地域的には、同国北西部の地中海沿岸地域が降雨及び肥沃な土壌に恵まれており、農業利用が比較的に進んでいる。
小麦、大麦、トウモロコシなど主生産物である穀物類は主に天水を利用して栽培されており、気候条件により大きな影響を受けている。最近9年間の穀物生産は、177万トン(1994/95)から1009万トン(1995/96)の間で変動し、その収量も0.4トン/haから1.7トン/haで変動している。2000/01年における穀物総生産量は、459万トン、その内訳は硬質小麦、軟質小麦、大麦、トウモロコシがそれぞれ104万トン、228万トン、116万トン、5万トンであった。vii
同国では穀物類の他に豆科、油脂作物、ビート・サトウキビ等の産業用作物、果樹栽培等が盛んである。一方、畜産業はほとんどが伝統的な放牧により飼育されており、牧草や飼料作物の栽培は灌漑地域以外ではあまり普及していない。
(2) 灌漑
モロッコの農業形態は、アトラス山脈を境に大きく東西に分かれる。西部は主として天水や河川水を利用した農業地帯、東部の半乾燥地は洪水及び揚水ポンプやハッターラと呼ばれる地下水路による灌漑が営まれている。土壌の透水性が高いこと、元来水資源自体が非常に限られていることから、コンクリート管半割り高架水路などや点滴灌漑などの節水灌漑による集約的農業が広く営まれている。
モロッコで潜在的に灌漑可能な面積は166.4万haで、これは通年灌漑地区136.4万haと季節灌漑ないし洪水灌漑地区30万haに大別される。通年灌漑地区は更に数千ないし数万ヘクタールを対象とする大規模灌漑 88万haと数十ないし数千ヘクタールを対象とする中小規模灌漑 48.4万haの2種に区分される。2002年現在、実現された通年灌漑地区は101.62万haに達し、その内訳は大規模灌漑が68.26万ha、中小規模灌漑が33.36万haとなっている。viii

灌漑開発における担当部局は国家レベルでは農業省・農村開発省で、新規プロジェクトへの投資は5ヵ年計画に沿って予算措置される。建設後の運営管理は地域・地方に移管され、地域農業開発公団(ORMVA)及び県単位での地方農業局が所轄する。ORMVAは上記大規模灌漑の運営管理を一元的に所轄する独立採算制の機関である。現在、全国の9地域にORMVAが設置され、当該地域の大規模灌漑を推進している。

(出所) l'Irrigation au Maroc, 2003
(1) 都市部
2001年における都市部での飲料水総生産ix量は8.45億 m3で、2000年に比して1.8%の増加となっている。同生産量の80%を水道公社(ONEP)が担い、他の20%を民間会社のElyo等が供給している。
一方配水xは、自治体の運営公社、民間もしくはONEPが担当している。自治体の運営公社は全国で15組織あり、2001年時点の契約顧客数は103.8万世帯で全国の40%を占めている。次いでカサブランカ・ラバトでサービスを行っているLYDEC・REDALの2社の契約顧客数が合わせて81.1万世帯(都市部の31%)に達している。一方ONEPが運営する配水センターは全国で281箇所に及び、契約顧客数は74.2万世帯(同29%)となっている。

同年時点での都市部での各戸給水率は全体で87%、内LYDEC及び自治体の運営公社によるものが89%、ONEPによるものが82%となっている。xi
(2) 地方村落部
1990年より行われた調査xiiにより、地方村落部ではわずか14%の住民が安全な飲料水源にアクセスを有するにすぎないことが判明した。全国に散在する村落の内、46%は200人程度の集落、1,000人程度の農村は6%にすぎず、こうした人口の配置が地方給水事業の制約要因となっていた。
「水と気候に関する最高協議会」は1994年に開催された第8回セッションで上記調査結果を承認し、これに基づきモロッコ政府は3.1万箇所の地方村落(人口11百万人)に給水施設を供給することで地方村落部での住民の飲料水アクセス率を80%に改善する地方給水計画(PAGER)を1995年より開始した。同計画の進捗に伴い、地方部での飲料水アクセス率は14%(1990年)から50%(2002年)へと改善している。
i Annuaire Stqtistiaue du Maroc 2002
ii 外務省ホームページhttp://www.mofa.go.jp/mofaj/area/morocco/data.html
iii 同上
iv World Bank, Morocco at a glance
v CSEC, La Gestion de l'Economie de l'Eau
vi 同上
vii Annuaire Stqtistiaue du Maroc 2002
viii 農業・農村開発省l'Irrigation au Maroc 2003
ix 生産:取水・浄水及び給水塔までの導水を指す。
x 配水:給水塔から水栓までの配水を指す。
xi ONEP, Secterur de l'Eau Potable, 2001,
xii UNDP, Etude du Schema Directeur National d'Approvisionnement en Eau Potable des Population Rurals

