第3章 国際緊急援助隊制度の評価
3.3 制度の実施体制の評価
制度の実施体制は、第1章の表 1 4および表 1 5で整理され、第2章で概要が述べられたとおり、(1)通常時の体制と(2)派遣時の体制<(i)要請から派遣まで、(ii)被災国における活動>に分けられる。(2)(i)の手続き、実施関係者については、設立時から現在まで関係省庁、必要手続きについて変化のないものであるが、それ以外の体制については、適宜体制の見直しが行われ、ガイドラインやマニュアルは更新されてきた。したがって、それらに関しては、「評価時点(2003年10月)で想定されている体制」を基準に評価を行った。
3.3.1では、(1)通常時の体制について、3.3.2では、(2)派遣時の体制<(i)要請から派遣まで、(ii)被災国における活動>について、文献調査に加え、国内および現地関係者への「質問票」回収結果、インタビュー結果を取りまとめた。(2)に関しては、派遣の事例ごとに1件1件異なる対応がとられているので、2003年5月のアルジェリア地震「救助チーム」「医療チーム」「専門家チーム」、および2003年3月のベトナムSARS「専門家チーム」をケーススタディーとし評価を行った。それら事例の実施体制の運用の「概要」については添付資料11を、「評価」については添付資料12を参照されたい。また、トルコ、台湾については、文献レビューに基づく評価を行ったが添付資料13を参照のこと。
3.3.1 通常時の実施体制の評価
通常時の実施体制に関しては、文献調査に加え、質問票は8つの関係者(外務省経済協力局国際緊急援助室、JICA国際緊急援助隊事務局、警察庁、消防庁、海上保安庁、国内支援委員会、厚生労働省、国土交通省)に送付し、ガイドライン等に照らした各実施段階の運営実施状況の適切度をA~D(A=明確に行っている。B=行っている。C=あまり行っていない。D=全く行っていない。)の4段階で評価するよう依頼した。その後、調査団は質問票の結果および補足電話インタビューを基に、各項目について、マニュアルの整備と実際の一致度合いを個別に検証し、結果の達成との関係から良点と課題について整理した。
(1) 通常時の国内準備体制のガイドライン等との適切性
通常時の実施体制について、質問票の回答を検証した結果、ほぼ、AまたはBの回答であった。したがって、すべて定められたガイドライン等に従って、通常時の体制が整備されていた。
(2) 通常時の国内準備体制の良い点と課題についての整理
1)通常時の準備体制
| ガイドラインどおり、適切に整備されており、常時、関係省庁とネットワークを構築し、海外での災害情報を収集する等して、派遣のための体制を整えている。
外務省国際緊急援助室およびJICA国際緊急援助隊事務局の現在の人員体制についても、下表のとおり、活動遂行のために十分に確保されている。ただし、外務省国際緊急援助室は、国際緊急援助隊の派遣に際し、団長として職員を派遣するため、大規模災害時には人員が不足することもあるが、同省地域課等の協力を得、団長として派遣したり、国際緊急援助室に加勢してもらい対応している。一方、JICA国際緊急援助隊事務局は近年では1999年のトルコ地震の時の「現地調整員の中に、緊急援助の経験、知識のあるJICA職員が不足していた」経験に基づき、調整員4名を確保した。 |
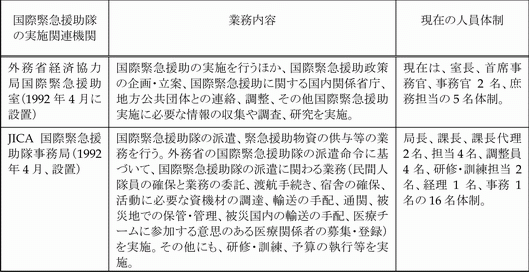
2)マニュアルの整備
「救助チーム」
|
マュアルの整備は、2002年11月以降進められてきた。被災国における活動体制は、過去の派遣事例からの提言等を盛り込む形で、見直しが行われている。現在も外務省、JICAと関係3庁の間で、協議の上、策定・改定を行っており、体制が整備されている。過去6年間で派遣された「救助チーム」の派遣に際し、個別報告書の中で行われてきた制度に関する提言は、添付資料1419」に示すとおり。現在のマニュアルでは、それらの過去の提言を受け、「救助チーム」に、救助犬、医療班(「医療チーム」登録医師、看護師から構成)、通信班(警察庁からの専門家により構成)、広報団員(JICA広報課の人員)等が同伴する体制に整備された。これは、2003年5月のアルジェリア地震の際に、実践された。この体制の変遷は、国際的な救助活動に関するINSARAGのガイドライン(International Search and Rescue Response)の整備、動向20」とも合致している。
現在はまだ、派遣対象要員全員にマニュアルが配布されておらず、今後、製本し配布することが予定されている。また、警察庁、消防庁、海上保安庁のそれぞれの専門分野や災害の種別ごとのマニュアルの整備の要望もみられる。ちなみに、消防庁では国際緊急援助隊の活動のために独自のマニュアルの整備を行い、この3月に完成、配布予定であるとのことであった。 |
「医療チーム」
|
マニュアルは、「支援委員会」を中心に改訂作業が進められてきた。過去6年間の派遣に際し、個別活動報告書の中で行われてきた制度への提言内容は添付資料14のとおりであるが、これら過去の提言が活かされ、最近では、「医療チーム」の活動を派遣期間中により効率的に実施するための情報収集や活動サイト選定を目的とした先遣隊の派遣や、国際機関、他の援助機関との連携をより重視するための、チーム構成およびチーム能力の見直し、被災国のニーズに幅広く対応するための公衆衛生活動の導入等が検討され、積極的に実践されてきた。2003年5月のアルジェリア地震に際して、従来の12名体制に代わり、新21名体制が実践された。新体制の主な特徴は次の4点ある21。
現在は、1998年版のマニュアルが使用されており、記述が古く、あまり実用的でないとのコメントが派遣経験者から見られたが、これら新体制を盛り込む形の更新版マニュアルが2004年中には発行される予定である。 |
「専門家チーム」
|
個別事例に応じて、適宜ふさわしい人選が行われ、派遣されるので特にマニュアルの整備は行われていない。したがって、外務省国際緊急援助室が中心となり、「専門家チーム」の派遣の方針を決定し、派遣を行うことになる。過去6年間の派遣に際し、個別活動報告書の中で行われてきた制度に関する提言は添付資料14の通り。それら提言で共通することは、「専門家チーム」は災害直後に短期間派遣され、その期間で今後の災害対策等に関しての提言を行うものであるため、被災国主体の通常時からの防災体制整備の重要性の指摘、およびそれを支援するための他のODAスキームとの連携の可能性の示唆である。
近年では、2003年に初めての事例として、「緊急感染症対策」の分野で、専門家が本制度下で派遣されたことから、新分野での派遣方針の整理が課題となっている。すなわち、農水省、厚生省等のもつ専門家派遣スキームとの役割分担や、当分野のように、原因不明の病気に対応する場合、専門家の負うかもしれないリスクの軽減方法、および、専門家が万が一感染した場合の退避手段や国内体制の整備等の課題についてのどこまで確保した上で派遣するかといった、派遣方針の策定が必要とされている。 |
3)派遣要員の登録状況
| 「救助チーム」の派遣要員の登録状況(2003年9月時点)は、以下の表 3 6のとおり。警察庁では約440名(9都道府県警察の救助隊)、消防庁(62自治体消防本部の救助隊)600名、海上保安庁の合計約1,100名の人員登録体制が整備されている。 |
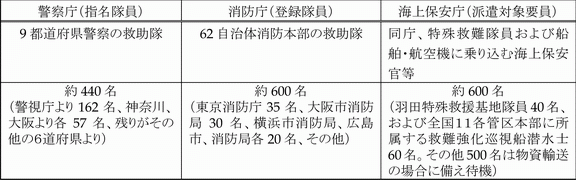
|
||
| (出所)国際緊急援助事業概要、2003年9月、JICA国際緊急援助隊事務局等より作成 |
| 「医療チーム」は、JICA国際緊急援助隊事務局に、全国から医師、看護師、薬剤師、業務調整員等の希望者が任意に登録している。2003年9月8日現在、登録者は648名おり、そのうち約70%が民間人である。参考までに、「医療チーム」の前身JMTDRの創設時の1982年9月8日の登録者は44名であったが、11年後の1993年7月23日には524名と10倍以上に増加し、さらに10年後の2003年には、648名と10年間で20%以上増加した。登録員は、JDR事務局の運営・管理の下、派遣され、被災国の活動に当たってはチームの団長の指揮に従うことになっている(表 3-1および図 3-9参照)。 |
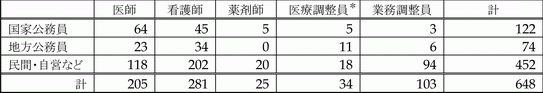
|
||
|
(登録者のうち海外在住者76名) (注)*臨床検査技師、放射線技師等医療系バックグラウンドがある人を対象。 (出所)国際緊急援助事業概要、2003年9月、JICA国際緊急援助隊事務局(2003年9月8日現在) |
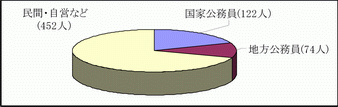
|
|||
| (出所) | 国際緊急援助事業概要、2003年9月、JICA国際緊急援助隊事務局(2003年9月8日現在) | ||
|
以上のように、国際緊急援助隊の派遣に備え、多くの人材が登録・待機しているが、その一方、本制度は被災国政府あるいは国際機関からの派遣要請が出て初めて派遣されるという制度になっており、派遣国側の意図だけでは派遣できず、登録者全員が数年間に必ず派遣機会に遭遇する状況にはなっていない。たとえば、医療チームは現在全国に648名の登録者がいる一方、過去の実績(1987年~2003年)の医療チーム1回あたりの平均派遣者数は、約11.5人(この中には外務省やJICA職員など非医療関係者も含む)と、登録者数と実際の派遣者数の間に大きなギャップがある。
したがって、医療チーム「支援委員会」は登録人材の有効活用法についても検討している。現行の国際緊急援助隊制度の枠組みにとらわれず、難民支援を含めた災害救助医療活動に取り組み、これまでの国内外での災害救助活動の経験と知恵を活かすことを目的にJDR医療チームへの登録者を中心として、災害人道医療支援会(HuMA:Humanitarian Medical Assistance)という特定非営利活動邦人(NPO)が2002年6月に設立された。HuMAは、NGO、経済界、政府が対等なパートナーシップの下、三者一体となり、それぞれの特性・資質を活かし協力・連携して、難民発生時・自然災害時の緊急援助をより効率的かつ迅速に行うためのシステムである「ジャパンプラットフォーム」22の参加NGOの1つでもある。 しかしながら、関係者の意見によると、『国際緊急援助隊は、NGOの活動に比べ、「被災国政府の要請に基づいた派遣であるので現場のニーズの高いところに確実に到着できる。」、「適切な携行医薬品を備えている。」との利点があるので、今後もこの点を活かしながら、NGO等とも協力して活動をして行きたい。』とのことである。 |
「専門家チーム」
| 登録体制はなく、派遣対象の災害に応じ、適宜14省庁と連携し、自然災害の被害状況によって、ふさわしい専門家を選出して派遣することになる。 |
「3チーム共通」
いずれのチームの派遣に際しても、JICAから業務調整員が同行することになるが、2003年9月8日現在の登録者は455名(出所:同上)である。
4)研修・訓練の実施状況
| 「救助チーム」「医療チーム」の研修・訓練の2002年度、2003年度の実績は以下の表 3-10のとおり、ほぼガイドライン等に従って行われている。ただし、研修・訓練への参加者人数の枠に関して、改善への要望が見られた。 |
「救助チーム」
| 現在は約1,000以上の登録者がすべて研修・訓練に参加できるわけでなく、毎年関係3庁から合計で45名程度が参加しているのみである。この点は、派遣時の被災国における活動に際し、障害となっている可能性が国内質問票回収結果の中でも指摘された。すなわち、研修・訓練を受けず実際に派遣される者もおり、「総合訓練」の実施回数の増加、または参加者枠の拡大の必要性が指摘された。ちなみに、消防庁では、独自に国際緊急援助隊参加に備えるために、通常訓練ではカバーされない、国内活動と異なる点等についての研修・訓練を実施している(2002年2日間、参加者62人、2003年3日間参加者80名)。 |
「医療チーム」
| 研修は、新規登録者を対象に必ず、「導入研修」を実施している。次に登録者の中の希望者に対して、「中級研修」を実施している。中級研修は、先にも触れた派遣のチャンスに恵まれない登録者のつながりを保ち、士気の低下を留めるために効果的だと関係者は評価している。「上級研修」については、2003年度は、海外で行われる適当な研修・訓練がなく、また、アメリカの治安状況の悪化の関係で実施しなかったそうである。 |
「国際機関への研修」
| 外務省では、1991年のINSARAGの地域会合以降、同会合に参加している。1999年頃からINSARAGの会合が活発化し、INSARAGのフォーカルポイントへの登録を開始するとともに、積極的に参加している。関係3庁からの参加は、今までに3回の会合(ウズベキスタン、韓国、フィリピン)に対して行われたが、実際の災害を想定したシミュレーション、ロールプレーが経験できる点に関し大変好評であり、さらに積極的な参加への要望が見られた。 |
5)携行機材の整備状況
「救助チーム」
| 現在マニュアどおり、JICAの携行機材が使用されている。これら機材の整備について、常に関係者間で見直しが行われている。見直し事項の例としては、消防登録隊員による成田倉庫の備蓄状況確認等による、梱包、資機材名表示方法等の改善、不足する資機材の消防において常時使用している資機材の携行等の、提案が行われてきた。 |
「医療チーム」
| 携行機材の整備についても、「支援委員会」の下で、見直しが実施されている。衛生材料や薬剤は災害ごとに患者の種類が異なるので、いつも完璧には準備できない点との指摘はあるものの、想定する医療ニーズに対応して準備している。 |
6)情報公開
|
外務省、JICAは国際緊急援助隊に関するホームページを作成し、制度や実績に関しての広報を行っている。その他にも、JICAの定期刊行物「JICAフロンティア」、海外研修生向けJICAニューズレター等で「国際緊急援助隊」に関する特集を適宜行っている。また、各関係省庁も自らの広報誌の中で適宜紹介している。今回の調査においては、通常時における、一般的な日本国民における本制度の認知度については十分に検証できなかったが、派遣時における日本国民の認知度については、「中間目標2の達成度」の項で検証したとおりである。
国際緊急援助隊事務局による機関誌は、現在「医療チーム」に関しては、2000年3月30日付けを第1号として、「医療チーム」登録者を対象に、「きいろいてんと」が約1,000部程度、年一回程度の頻度で刊行されている。以前は、「救助チーム」関係者(外務省、警察、消防、海保)、「医療チーム」登録者、防衛庁及びJICA内部を対象として、JDRの機関誌「国際緊急援助」(旧 JICA JDR NEWS)が発行されていたが、第23号をもって最終号となり、現在機関紙は「きいろいてんと」のみとなった。 その他にも、各種セミナーや講演会で日本国内向けの広報を実施している。2002年は、大学のJICA講座や、医療関係の学会や防災対策、消防関係のセミナーにおいて、合計約14回の講演活動を実施した。2003年度も同様に12回実施している。一方、海外からの研修員受け入れ事業で国際緊急援助隊事業の紹介を実施している。2002年は「ODA紹介セミナー」、「救急救助セミナー」、「防災行政管理者セミナー」、「消火技術コース」、「災害総合保健医療コース」等、合計10回実施した。2003年度は、同様に7つのセミナーで実施している。 |
7)派遣終了後
|
従来、国際緊急援助隊の派遣終了後に、国際緊急援助隊に関する事後調査やフォローは実施されてこなかったが、国際緊急援助隊の派遣事業の評価の必要性から、評価ガイドラインが、2003年3月に策定されたところである。2003年の派遣事例から、評価および派遣終了後のフォローアップも行う体制が整備され始めた。
その結果、2004年1月にアルジェリア地震(「救助チーム」、「医療チーム」)の事後評価および外部有識者による評価が実施された23。「専門家チーム」に関しては、2003年12月にベトナムSARS「専門家チーム」派遣の試行的評価が実施されたところであり、評価ガイドラインは現在作成中である。今後、事後評価が導入され定着化することが期待されている。この事後評価調査の重要性については、本調査の現地調査でも判明した。すなわち、災害直後は、先方政府は災害状況、救助、医療等のニーズ、外国チームの活動実績について、十分把握しておらず、国際緊急援助隊チームが、その成果および達成度についての定量的評価を十分行うことが困難である。従って、災害が落ち着いて数ヶ月経過してから、先方政府に対して国際緊急援助隊の成果を正確に記録させるとともに、全体の災害状況に関する情報収集を行い、国際緊急援助隊の全体の成果に対する貢献度を確認することが必要であることが判明した。 |
(3) 通常時の国外準備体制(在外公館・JICA事務所)のガイドライン等との適切性
| 今回の現地調査対象国に限り評価が可能であったが、質問票による検証の結果、ほぼAまたはBの回答が得られたが、若干の項目にCも見られた。 |
(4) 通常時の国外準備体制の良い点と課題についての整理
通常時の準備体制
|
第一に、3.2.2「中間目標2」の評価結果においては、アルジェリアのケースで、在外公館・JICA事務所が通常時から築いているマスコミとの良好な関係が緊急時に役立ち、国際緊急援助隊の派遣時に活動がタイミングよく現地のメディアに報道され、一般国民に認識されたことが確認されたことに関連し、通常時からマスメディアとの連携を密に行うことの必要性が確認された。
第二に、在外公館、JICA事務所における通常時の国際緊急援助隊準備体制では、担当者の割り振りは確実に行われているが、緊急事態のためのネットワーク構築を積極的に常に行っているという状況ではなかった。また、職員による本制度についての認識は、個々の職員の経済協力業務への関与度合いや在外公館・事務所への勤務経験状況により異なった。総じて、いずれの大使館等においても、以前に本制度に関わった職員が駐在しており、迅速な受け入れが可能であった。今後も引き続き、在外公館・JICA事務所は、担当者の交替に際し、引継ぎを徹底するとともに、実際の受け入れに当たり何をする必要があるかを想定し、緊急時に十分に備えておく必要がある。また、災害多発国においては相手国政府に対して、本制度の目的と支援可能な範囲を説明しておく必要がある。さらに、派遣を決定した場合、その派遣中、派遣後において、先方政府へ本制度の説明を誤解を与えることなく十分に行い、関連案件があればフォローアップしていく24が必要がある。 |
派遣終了後
|
派遣終了後の在外公館や、JICA事務所を中心としたフォーローアップ体制については、被災国での認識度合いについてのフォロー、すなわち、報道振り、任国政府からの感謝、被災民の声等の広報素材の収集・報告は通常業務として行っていた。
一方、災害データ等の在外公館やJICA事務所による把握は、「国際緊急援助隊評価ガイドライン」が策定された2003年以降実施されることになった。以下にこの点に関しての、アルジェリアとベトナムの事例を紹介する。 |
アルジェリア地震災害(2003年)のケース
災害が落ち着き、全体像のデータの把握が可能となった時期に、国際緊急援助隊が被災国に与えた波及効果等について事後データをフォローする必要がある。アルジェリアの場合は、2004年1月のJICAの外部評価を通じて、フォローを行った。地震が起こってから8ヶ月目に当たり、震災のデータを被災国政府防災関係者が整理を始めたところであり、この時期にデータ収集を行うことは適切であった。
ベトナムSARS集団発生(2003年)のケース
JICA事務所は、物資供与後のモニタリング調査の実施に関して、特に、多量に供与した資機材、たとえばマスク等については特に、モニタリング調査を実施しておらず、またその必要性も低いとの回答を得た。しかしながら、バックマイ病院で技術協力プロジェクトを通じて、国際緊急援助隊の行った感染症防止活動も引き続き進行中であり、その中でのフォローが可能であった。
3.3.2 派遣時の実施体制の評価
派遣時の実施体制の運用にあたっては、(i)「要請から派遣まで」については、外務省国際緊急援助室、JICA国際緊急援助隊事務局を中心に、(ii)「被災国における活動」については、文献調査に加え、実際に派遣された副団長、中隊長以上のレベルの隊員を中心に、質問票を送付し、ガイドライン等に照らした各実施段階の運営実施状況の適切度を、第1章で整理した実施体制の点検項目(表 1-4、表 1-5)のそれぞれにつき、A~D(A=順調に行った。B=行ったが十分とはいえなかった。C=行ったが十分といえなかった。D=全く行わなかった。)の4段階での評価を依頼した。評価団は質問票の回収後、補足電話インタビューを基に、各項目について、マニュアル等と運用の一致度合いを個別に点検し、結果との関係から良い点と課題について整理した。
なお、本調査における点検項目は、現地政府や国際機関との連携を主眼に活動する外務省団長とJICAの副団長が主に行う項目を中心に作成したものである。したがって、点検項目は実施可能性のある項目の列挙であり、実際の実施の要・不要は、個別災害の状況により異なる。さらに、この4段階チェックについては、回答者個別の判断に基づくチェックであり、それぞれが相対化、平均化できるものではない。
(1)派遣体制のガイドライン等との適切性
アルジェリアとベトナムの事例について、点検した結果、(i)と(ii)の両方に関して、A、Bの回答が多く、全体的にガイドライン等に定められているとおりに実施されていた。ただし、両ケースにおいて必要のなかった項目に限って、CまたはDとの回答が見られた。
(2)派遣体制の良い点と課題についての整理
上記のようにガイドライン等に従って実施されていることから、次に「評価の枠組み」にしたがって、制度の「結果」の達成との関係から、実施体制の良い点と課題についての整理を行った。
整理に当たっては、(i)から(ii)全体を通じての派遣時の実施体制を、次の6つの観点から分析を行った。この6点と、(i)(ii)および表 1-5との関連は下表 3-11のとおり。
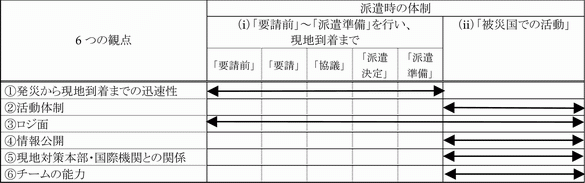
1)発災から現地到着までの迅速性
|
発災から現地到着までの手続きは、1)相手国政府からの要請の受領、2)外務省における派遣決定、3)JICA国際緊急援助隊事務局における派遣手続き(人選、交通手段の選定等)の3つに時系列に分類することが出来るが、本調査では、タイミングについて、1)~3)に分けて検討せず、発災から現地到着までのタイミングについて評価することとした。
|
「救助チーム」
|
評価:
発災後72時間を過ぎると要救助者の生存の可能性が低くなるとの統計的な目安もあり、派遣の迅速性が重要な課題である。過去の6年間の実績に関して、4件25(1998年のコロンビア地震、1999年の台湾地震、トルコ西部地震と2003年アルジェリア地震)の被災国の活動サイト現地到着までの時間は平均、1.4日である。 さらに迅速性は、ニーズの高い活動サイトへの到着やその他の要因と相まって、効果が上がる。また、迅速性は「中間目標1:肉体的苦痛の軽減」の達成だけでなく、「中間目標2の後半:認知度の向上」の達成にも関係があることが推量された。以下に、「3.2 結果の評価」でみた結果と、発災から活動サイトの到着までの迅速性の関係について、ケーススタディーに関して、表 3-13にてまとめる。 |
(過去6年間の実績)
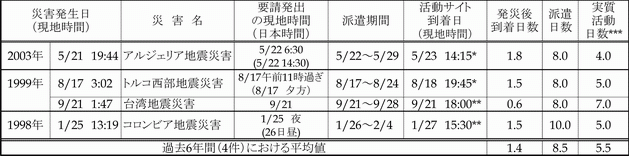
|
|||
| (出所) | 国際緊急援助隊の個別活動報告書より作成 | ||
| (注) | * 現地対策本部への到着時間 ** 被災現場への到着時間 *** 先方政府への報告も含む | ||
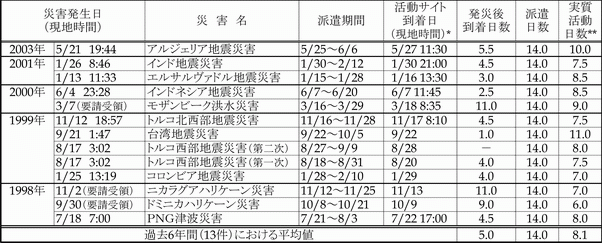
|
|||
| (出所) | 国際緊急援助隊の個別活動報告書、「アルジェリア地震に対する国際緊急援助隊医療チームの活動評価」(2003年6月23日)、外務省国際緊急援助室、より作成 | ||
| (注) | * 被災地に到着し、現地到着本部との協議の開始または医療テント等の設営準備開始時刻 ** 撤収活動も含む。 | ||
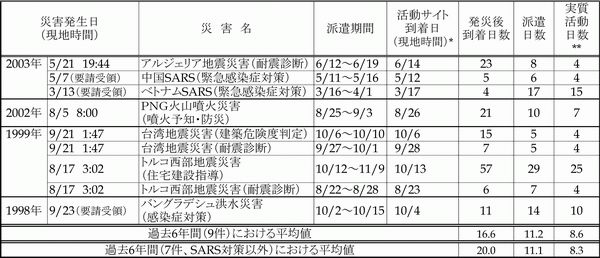
|
|||
| (出所) | 国際緊急援助隊の個別活動報告書より作成 | ||
| (注) | * 被災国受け入れ機関との協議開始日時 ** 関係機関への報告を含む | ||
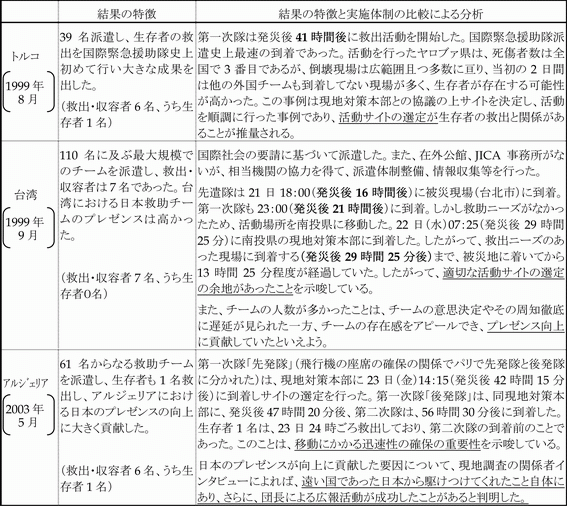
|
||
| (出所)各活動報告書より作成 |
|
課題:
過去の事例の文献調査によれば、「救助チーム」の派遣人数や活動現場への到着に関して、日本から被災国までの移動に際し、民間商用飛行機の使用により制約を受けている実態が明らかになった。具体的には、座席の確保状況により、派遣人数が決まり、関係3庁別に人数が振り分けられる、さらに、民間商用飛行機の飛行ルートと出発時刻によって、いくら迅速に現地に到着したくても、チームを数回に分けて派遣せざるを得ない、あるいは、待ち時間が生じるという制約を受ける。したがって、国内質問票回収結果からも明らかになったが、さらなる迅速化に対する要望は強く、より迅速な移動手段の確保、への要望が強かった。 その一案として、政府専用機およびチャーター機の利用が指摘されている。現在も政府専用機の利用は制度上可能であるが、実績として、国際緊急援助隊派遣のために利用したことはない。チャーター機については、2004年2月末のモロッコ地震に際し利用され大きな成果をあげた。これは、条件が整えば、より多くの隊員を一度に運ぶことができ、かつ派遣隊員の民間商用機利用の場合に消耗する肉体的負担を軽減出来るという利点がある。今回の、在仏日本大使館へのインタビューにおいても、本制度の第一の改善点として指摘された。
|
「医療チーム」
|
評価:
過去6年間に合計13件26派遣されている。「医療チーム」に対しても、「救助チーム」程ではないが、同様に、派遣の迅速性が期待されている。過去6年間の平均は、5.0日である。このタイミングは、発災の3日間に災害救急医療のニーズが高い27ことを考慮すると必ずしも、被災国のサイトに迅速に到着しているとはいえない状況にあるが、被災国側からは特に問題は指摘されなかった。現在、「医療チーム」は、災害後の時間経過に伴い変化する医療ニーズ(現地医療機関の機能低下に伴う供給不足、テント生活者のための公衆衛生へのアドバイス等)に対応する体制として整備されてきている。また、「救助チーム」に比べ、「医療チーム」は、活動開始までに時間的猶予をもって到着していることから、適切なサイトの選定の実現可能性が高いといえよう。活動サイト到着までの迅速性の議論は、適切な活動サイトの選定と緊密に関係しているので、詳細の分析は、活動体制と結果との分析の項において行う。ちなみに、アルジェリアの地震の場合、発災後5.5日、トルコ西部地震の場合は、発災から4.0日で、台湾地震の場合は発災から1.0日で、医療活動サイトに到着している。 課題: 国内質問票調査によれば、「医療チーム」についても、迅速性の確保、および、より多くの隊員の運搬可能性から、政府専用機およびチャーター機等の利用の要望が見られた。
|
「専門家チーム」
|
評価および課題:
従来の「専門家チーム」(地震後の耐震診断専門家、火山噴火予知専門家、防災専門家等)は、災害後に専門的観点から、長期的な将来のためのアドバイスを実施するために派遣されるもので、「救助チーム」、「医療チーム」に比べて、現場到着までの迅速性はさほど要求されていない。過去6年間の実績を見ても、「専門家チーム」の活動サイトへの到着時間の平均(SARS対策以外)は、20日であり、「救助チーム」の1.4日、「医療チーム」の5.0日に比べても大幅に遅いタイミングでの派遣となっている。ただし、「専門家チーム」に関しては、災害に応じて対応が適宜とられるべきであり、ケースごとに多様であった。個別ケースの迅速性の評価と課題については、活動体制と結果との分析と同時に述べる。
|
| 「救助チーム」「医療チーム」「専門家チーム」の派遣事例を横断的に評価した結果、チームの枠を超えての、国際緊急援助隊派遣制度の課題として、大きく2つの課題が見られた。 |
活動の効率性(実質活動日数):
|
前項で見た迅速性の確保とともに、適切な活動サイトへの到着が重要な課題である。したがってここでは、適切な活動サイトの選定を行うことの重要性を「3.2制度の結果」との関係の視点から確認する。過去6年間の実質活動日数の一覧は、表 3-12参照。
「救助チーム」 「医療チーム」 タイミングとしては「救助チーム」の後に派遣されるので、比較的時間の余裕を持った活動サイトの選定が可能である。トルコ、台湾、アルジェリアの事例においてサイトの選定状況は表 3 12の通りである。適切なサイトの選定を行い限られた活動期間の中で実質的活動日数を増加し、また、投入する医師の数を増やせば、理論的にはより多くの人を診療できる(もちろん、被災国及び活動サイトの被災状況の特殊性等に応じて個別検討を加える必要はある)。しかし投入を増やすのは必ずしも容易ではないため、まず改善できる点として、適切なサイト選定の迅速化と実質活動日数の増加がある。そのために、先発の「救助チーム」に参加する外務省職員(団長以外)が事前に活動サイトの選定も行うことが有効であることがアルジェリアの事例からは明らかになった。
|
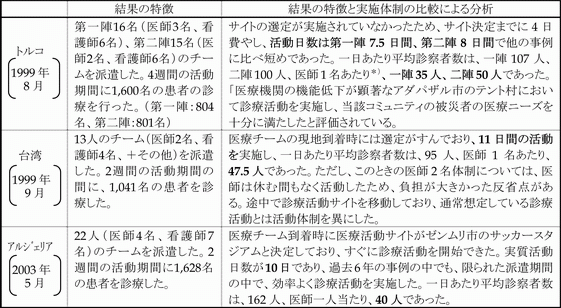
|
||
|
(出所)各活動報告書より作成 *)実際は適宜休息をとり、ローテーションによる診療を行うの体制であり、厳密な意味での医師一人当たり診療数ではない。 |
「専門家チーム」
「専門家チーム」は、先方機関と協力して作業を行うもので、自らサイトの選定を行う必要はないが、逆に現地の災害後のニーズに関して迅速に情報収集を行い、ふさわしい専門性を備えた専門家を派遣することがまず、重要課題である。そして、現地で、先方機関のニーズに応える活動成果を出すべく活動を行う。過去の事例を見てみると、トルコ西部地震の仮設住宅建設指導のための専門家派遣時以外は、専門家の派遣期間は、一回の派遣あたり、約1週間から10日前後、第一陣、第二陣を通じた、実質活動日数は、4日から15日である。
たとえば、台湾地震の場合は、発災から6日で活動サイト入りしており、既存報告書のレビューでは、タイミングについて問題点は指摘されていない。実質活動期間については、第一陣、第二陣ともに4日間であったが、一定の成果に繋がった。トルコ地震の場合は、発災から6日で「専門家チーム」が活動サイト入りしている。既存報告書のレビューでは、タイミングについて問題点は指摘されていない。実質活動期間は第一陣は4日と短かく、第二陣は、仮設住宅指導を行うもので、実質活動日数は25日間と長期に亘った。それぞれ報告書レビューの限りでは特段問題点は指摘されていない。さらに詳細な実施体制と成果との関連の検証の実施は、以下の囲みの中で、アルジェリアとベトナムの場合に限り検証を行った。
また、「専門家チーム」は実質活動期間に専門性に基づき先方機関への助言を行うとともに、報告書を作成し、提出することが多い。過去の報告書の文献調査を行うと、数ページ程度の報告書を現地派遣期間中に提出しているケースが多い。しかし今後の課題として、先方機関のニーズに応える活動を行い、報告書を作成するためには、派遣期間の見直しや、レポート作成方法の見直し、帰国後の迅速な先方政府への提出が必要であろう。
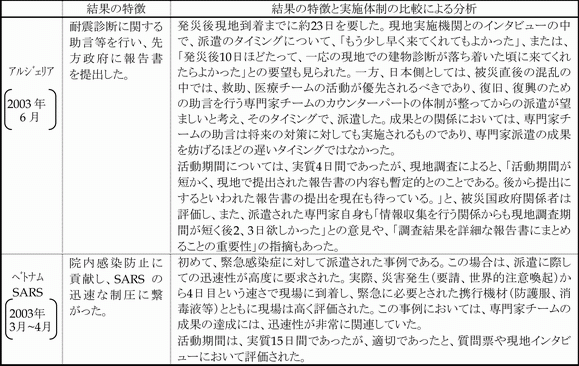
|
|||
| (出所)各活動報告書より作成 | |||
リスクと国際貢献の課題:
|
これは、過去の派遣事例に共通する課題であった。通常、国際緊急援助隊は海外での自然災害等に際して、災害直後のニーズに応えるために、たとえば地震等の場合は余震の危険等、隊員の身に危険が及ぶ可能性がある段階で派遣される。したがって、このようなリスクを、どこまで国際緊急援助隊員が引き受けるかに関して議論がある。以下に、アルジェリア地震「医療チーム」の場合と、ベトナム「専門家チーム」において議論された点について紹介する。それ以外の事例においても同様のことが指摘されている。(添付資料14参照)
結果として、緊急時においては即時の判断が要求されるので、従来のまま団長が判断を行うのが妥当であるが、活動に際しては、現地の治安情勢に最も精通している在外公館の助言は貴重であり、在外公館が引き続き、邦人の安全確保のための全面的協力を行うことの必要性が確認された。 災害が起こって生存者のいる可能性の高い72時間以内に活動を行うことを目的にしているため、早く到着することが第一の課題であった。サイトの選定に関しては、自ら救助ニーズの高いサイトを選定するというよりも、現地への到着順に国際チームに対して、ニーズの高いサイトが割り振られるのが一般的であるため、早く被災国に乗り込むことは重要である(結果とサイトの選択の関連性については表 3 11参照)。過去の派遣例でも、実際は、現地対策本部や国際機関も正確な現地の救助ニーズを把握していない、または割り当てられたサイトに行っても、実際には被災ニーズがない等の理由により自らサイトを探すことも多く、また、適切な活動サイトにめぐり合うには偶然の要素が高いことも判明した。 |
アルジェリア地震災害(2003年)「医療チーム」のケース
初日の診療を終え、ホテルに向かう途中で大規模な地震に遭遇し、救急医療の必要な患者が発生しているとの情報を得たため、「夜間診療を行うか否か」、「実施というリスクをどこまでとるべきか」が、議論となった。この場合、余震の可能性に加え、テロに関わる治安が懸念されるという特殊な状況もあり、特に判断が難しかった。
活動を行う成果(国際貢献)と危険(安全上のリスク)を比較し、「医療チーム」の通るルートの安全性も確認した結果、チームの半数が、再度現場に戻り夜間ではあるが医療活動を実施することに決定した。このチームの判断は、在アルジェリア日本大使館等との協議の上、団長が判断を行った。実際に活動を行った結果としては、朝までに7人の患者を診療し、同じ医療テントのあるスタジアムで働く人や、住民の信頼を得ることに成功した。
ベトナムSARS集団発生(2003年)「専門家チーム」のケース
初めて、「緊急感染症対策」分野で、病気の原因も不明、治療法も確立されていない時点で専門家が派遣された。外務省は、院内感染防止のための指導をして欲しいという被災国の要請に基づき、「専門家チーム」派遣を決定し、専門家の業務範囲として、直接SARS患者の診療を行わないこととした。
現地に到着したチームは、1日状況調査を行い、追加携行資機材のニーズ報告を行うとともに、団長判断により、「病気が飛行機を通じて国境を越えて日本を含めて世界的に拡大する危険もあること」の危険性を述べたSARS「緊急報告書」を日本外務省に提出し、通常の専門家チーム派遣とは異なる対応がとられた。(SARSがそれまで世界で例のない新興感染症であり、かつベトナム国内だけでの問題に治まらないという緊迫した状況であったことから、感染症専門家の立場から確認できた事項をできるだけ正確かつ迅速に日本国内関係者に伝達する必要性が極めて高いと判断されたことによる。)
一方、現地での活動に当たり、現地大使館、JICA関係者は、「彼らが万が一感染したらどうするか?日本に帰国させるのか?とどめるのか?」等の方針の検討が重要課題であった。
3)ロジ面
| 過去の派遣活動報告書の文献調査によれば、多くの派遣に際し、現地や経由国・近隣国の在外公館やJICA事務所の多大な支援を受けていることが分かった。アルジェリアの場合は特に、通信面や航空券の確保の面で、多大な支援を受けた。逆に言えば、これら在外公館や事務所の支援なくしては、国際緊急援助隊の順調な活動に支障が及びかねない状況があった。このように、近隣国の在外公館やJICA事務所の支援が、国際緊急援助隊の順調な実施のためには制度上不可欠である。 |
アルジェリア地震災害(2003年)「救助チーム」「医療チーム」のケース
通信面: 地震発災直後には、在アルジェリア日本大使館のファックス等の通信機能が遮断されたために、在仏日本大使館を経由して、外務省本省と地震に関する第一報等の連絡を行った。さらに、在アルジェリア日本大使館の通信機能の復旧・確保のために、在伊日本大使館から通信担当官の応援を得た。
航空券・国内移動手段の確保: アルジェリアに入国するにはパリ等での乗り継ぎが必要である。「救助チーム」の場合は61名と大勢の隊員の移動が必要であったが、パリ-アルジェ間の航空券の確保、パリ市内での空港の乗り継ぎ、約4トンにも及ぶ携行機材の運搬に際して、在仏日本大使館やパリJICA事務所の多大な支援を受けた。
| 一方で、アルジェリアのように、JICA事務所がないところでは、在外公館の数人の人員では、受け入れに当たり24時間体制で、多くの隊員の受け入れ支援を行うにも体力的にはかなりの負担を強いることになる状況があることが見られた。 |
4)情報公開
| 国際緊急援助隊は「中間目標2:国際緊急援助隊の活動を積極的に情報公開し、日本の実施した活動が国際社会および日本において認識される」とあるように、情報公開はひとつの大きな課題になっている。「救助チーム」「医療チーム」に比べて、「専門家チーム」に関しては、報道に関して、災害の特殊事情に応じ、国際緊急援助隊の活動内容の情報公開や報道に関する制約を受けることも見受けられた。以下の囲みに、アルジェリアとベトナムの例について述べる。しかしながら、被災民や国民の混乱を招かないように留意しながら、よりプレゼンスをあげるべく「専門家チーム」の活動の情報公開を行う余地があることがうかがえた。 |
アルジェリア地震災害(2003年)「医療チーム」のケース
在アルジェリア日本大使館が中心となって、積極的に現地のプレスを招き、情報公開を実施した。さらに、現地活動期間の最も長かった「医療チーム」の団長が現地で広く流通しているフランス語に堪能であり、活動中は精力的に、プレス対応を行ったことから、国際緊急援助隊の活動が大きく報道されかつ正確に伝えられた。(「3.2 結果の評価」参照) 「専門家チーム」に関しては、日本人専門家のアルジェリア国の建物やインフラに対しての構造分析の結果が、政府への批判と受け取られないよう、専門家チームの活動内容のメディアへの情報提供には注意が必要であった。
ベトナムSARS集団発生(2003年)「専門家チーム」のケース
一回の派遣人数は、3人と少数であった。プレス対応に関しては、ベトナム側の慎重姿勢および国内への影響を配慮し、慎重に行ったという経緯がある。一方、日本と同様ベトナム保健省とともに活動し、SARS患者のベットサイド診療も行ったWHOは、広報に積極的であり、診療の映像を効果的に報道し、ベトナム国民に対して強い印象を与えたようであった。
5)現地対策本部・国際機関等との関係
|
過去、現地対策本部、国際機関等との連携は考慮されてきた。今回現地調査も行ったアルジェリア地震とベトナムSARSの場合の両事例においては、チームもこれらを重視し構成されていたため、順調に行われた。たとえば、「救助チーム」の場合、国際機関等の実施する研修に参加した団長、副団長が被災国活動サイトで何をすべきか了解していた。「医療チーム」に関しても、それら機関との連携を念頭に副団長等が配置されていた。「専門家チーム」は被災国の受け入れ機関とは十分な情報交換ができたことも確認された。ちなみに、連携がうまく行った背景には、「在外公館が通常時から構築している良好な関係が緊急時に役立った」ことも、現地調査を通じて明らかになった。
これらの順調な連携がサイト選定等の適切性、国際緊急援助隊の活動の効率化に貢献し、結果を出すこと、すなわち「中間目標1」「中間目標2」の達成に繋がることがケーススタディーにおいて確認された。従って、こうした現地対策本部・国際機関等との連携強化は引き続き重要であることが確認された。 |
6)チームの能力
|
チームの規模、構成員、専門性はチームにより異なる傾向が見られる。構成員数について過去の全派遣実績を見ると、「救助チーム」の平均は、42.9名、「医療チーム」の平均は11.5名、「専門家チーム」の平均は、8.5名となっている。構成員数と結果との関係については、「救助チーム」は、表 3 11にて、「医療チーム」は、表 3 12にて、「専門家チーム」は表 3 13にて述べた。「救助チーム」は、チーム規模の大きさと「中間目標1」の達成には相関関係は特に見られず、「中間目標2」については、正の相関関係が見られた。「医療チーム」は、チームの規模(特に医師の人数)と、「中間目標1」の達成度については正の相関関係が見られ、さらに「中間目標2」についても同様であることが推量された。「専門家チーム」は、人数の多さと「中間目標1」の関係を推量することは困難であり、「中間目標2」との関連については、推量も可能であろうが、先発で派遣される「救助チーム」「医療チーム」の成果やプレゼンスの高さの影響を増進するのに効果があることがアルジェリアの事例において確認された。
チームの隊員の個人の能力に関しては、「救助チーム」「医療チーム」については、派遣に備え、研修・訓練が実施されてきた。3チームに共通す点として、団長については、コミュニケーション能力、語学力等が重要である。「救助チーム」の隊員については、アルジェリア、台湾、トルコの事例を見ても、派遣される隊員が必ずしも総合訓練の参加経験者ではないのが現状であり、今後の研修・訓練への参加枠の増大の希望が見られた。「医療チーム」についても同様で、研修制度の充実の要望が見られた。 チーム全体としての能力は、人数の増加に伴って、在外公館等の協力者に対して余計な混乱を招かないために、現場での指揮系統の一本化と、役割分担が必要となることが、在外大使館等への調査により判明した。「救助チーム」に関しては、関係3庁の混成でチームが構成され、警察庁の治安維持、通信網の整備力、消防の救助技術力、海上保安庁の国際チーム等とのコミュニケーション能力等の技術が活かされている。一方、「医療チーム」についても、派遣経験者と未経験者を混合し、適切な医師、看護師、薬剤師、医療調整員等が派遣されている。 同時にチームの能力のひとつである携行機材の整備状況の整備も引き続き行われるべきである。 |
(3) 派遣時の国外支援体制(在外公館・JICA事務所)のガイドライン等との適切性
今回の現地調査対象国に限り評価が可能であり、質問票による点検結果、ほぼAあるいはBの回答が得られた。
(4) 派遣時の国外支援体制の良い点と課題についての整理
(i)要請から派遣決定し、現地に到着するまで
|
外務省本省への第一報:
アルジェリアの場合は、JICA事務所がないため、在アルジェリア日本大使館が中心に、外務省本省との連絡を行った。同日本大使館も被災し、通信機能が地震により遮断されたという困難な事態があったが、ガイドライン等のとおりに外務省本省への第一報や、被災国外務省と協議、要請を受領、これら本省への連絡に当たっては、インマルサットを使って在仏日本大使館経由で行った。ベトナムの場合も、現地大使館、JICA事務所を中心に、WHO等とも情報収集を行いつつ、日本への状況報告を実施しつつ、専門家派遣の要請をベトナム保健省より受領、本省に伝えた。 国際緊急援助隊受け入れのための事務: アルジェリアの場合は、「救助チーム」に関しては、在外公館が、早急に実施することが必要な、民間航空機の航空券の確保、派遣隊員のための車や宿の手配、現地報道機関への連絡、現地災害情報および現地ニーズの確認等の多くの支援業務を実施した。ベトナムの場合は、「専門家チーム」受け入れのために、保健省やWHOとの連携を進め到着後すぐに活動出来体制の整備を行った。
|
(ii)被災国での活動実施中
|
いずれの派遣においても、在外公館やJICA事務所は、24時間体制で活動中の支援を行っている。そして、在外公館やJICA事務所の支援は、手厚いものであったと、国際緊急援助隊チームから高い評価を得ている。一方、在外公館や、JICA事務所側からは、一部の事例において、活動支援に際し、国際緊急援助隊の指示が混乱することもあったとの指摘もある。
国際緊急援助隊の初動の情報収集は在外公館に頼らざるをえず、また、在外公館はチームの活動範囲に関して、治安面を考慮し適切な助言を与えることができるので、引き続き、国際緊急援助隊の受け入れと活動中の支援は、在外公館の重要な役割のひとつとして位置づけられる必要がある。 |
19各派遣事例ごとの活動報告書に記載された提言内容から、スキームレベルの提言を抽出した。なお、1999年台湾地震(救助チーム)、トルコ地震(医療チーム)については、事後評価報告書も作成されており、参考とした。
201999年のトルコ、台湾、ギリシャの地震の反省をかねて、INSARAG会合が同年12月に行われた際に、国際的救助活動に関する立法化の気運が高まり、INSARAGガイドライン作成が開始された。2002年12月には国連総会により、「国際的都市型救助活動の有効性と連携を強化するための規則(General Assembly Resolution on Strengthening the Effectiveness and Coordination)」(GA Resolution 57/150、2002年12月16日)が採択された。これにより、国連加盟国は、GA Regulation およびINSARAGガイドラインを、国家の緊急対策計画や国際的または国内の都市型救助チームのための訓練プログラムを組み込むことが期待されるようになった。INSARAGでは当ガイドラインの改訂作業を進めており、2004年内には、改訂作業が完成する予定となっている。
21(出所) 「きいろいてんと(2003.10・20、No.5)」, JICA 国際緊急援助隊事務局
22ジャパンプラットフォームは2000年8月設立された。http://www.japanplatform.org/work/index.html#。HuMAは2002年12月17日より参加承認された。
23本外務省評価調査と同時期に実施された。
24外務省・JICAとしても、国際緊急援助隊を、自然災害後の防災復興支援の第一段階として捕らえており、国際緊急援助隊の後には、個別専門家派遣、開発調査、無償資金極力、技術協力プロジェクト等への災害復興支援も念頭においている。たとえば、アルジェリアの地震のあとには、無償資金協力で地震計測機器を近隣諸国と同時に供与したりしている。また、2003年12月末のイランのバムの地震「医療チーム」の派遣に引き続き、1月には、バム市の緊急復興計画策定のための調査団を派遣している。
252004年2月のモロッコ地震への「救助チーム」の派遣は除く。
262003年12月末のイラン地震災害への派遣は除く。
27地震災害による被災者の医療ニーズ発災後の経過時間との関係で、阪神淡路大震災の事例等から分類し、次のように言われている。(出所:JICA「トルコ地震災害救済国際緊急援助隊医療チーム」事後評価報告書)
| ・ | 「災害救急医療期間または急性期」(発災から初期の3日間(被災後1から3日)):負傷者が多く、救急医療、医薬品確保、血液確保等の災害救急医療が必要とされる。 |
| ・ | 「災害地域医療期間(亜急性期)」(発災後4日以降から医療機関がおおむね機能を回復するまでの時期(3ヶ月程度)):保健予防、救護所医療等の災害地域医療が中心になる。 |

