第3章 国際緊急援助隊制度の評価
3.2 制度の結果の評価
本節では、「評価の枠組み」に従い、国際緊急援助隊制度の実施の結果の有効性、すなわち、「中間目標1:人的(肉体的・精神的)被害の軽減」および「中間目標2:国際緊急援助隊の活動を積極的に情報公開し、日本の実施した活動が国際社会・相手国および日本において認識される。」の達成度を検証する。
まず、入手可能な情報・データに基づき可能な範囲14で、国際緊急援助隊の過去の派遣実績全体を対象に「結果の有効性」について検証し、全体についての考察が困難なものについてはケーススタディーを通じて確認することとした。すなわち、「中間目標1」については、過去の実績値に対して目標達成度を定量的に推定し、さらにケーススタディーにおいて達成度について詳細を検証することとした。「中間目標2」については、過去の派遣事例についてすべてについて定量的に分析することは不可能であったので、現地調査を行い詳細データを入手することとしたアルジェリアとベトナムの2つのケーススタディの結果の中で分析した。台湾、トルコについても、報告書のレビューにより判断可能な範囲で検証した。
3.2.1 「中間目標1」の評価
「救助チーム」
過去の派遣実績は9件であり、総勢386名の救助隊員が派遣された(詳細は添付資料3参照)。その中で救出・収容者数の結果が判明しているのは、表 3-1に示す1996年以降の5件であった。これら5件の結果をみると、271名の隊員派遣に対し、56名を救出・収容し、そのうち2名は生存者の救出であった。救出・収容者数が多いのはエジプトのビル崩壊災害の32名であった。
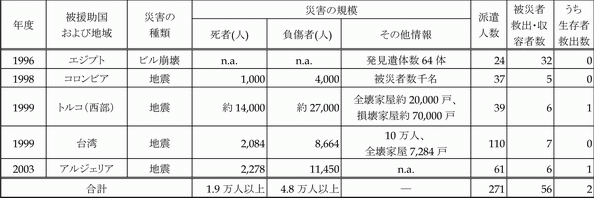
|
||
| (出所)国際緊急援助隊派遣 各報告書、「国際緊急援助事業概要(2003年9月)」JICA国際緊急援助隊事務局 |
地震の4事例においては、各事例とも救出・収容者数は5~7名の範囲であった。そのうち、1999年のトルコ西部地震、2003年のアルジェリア地震の2件では、生存者を1名ずつ救出できた。各ケースを比較すると、被災規模は、たとえば死傷者約5,000人~41,000人と、日本からの距離も、南米、中東、アジア、アフリカと、派遣人数も24~110名と多様であったが、救出・収容者数は5から7人の範囲であった。さらに詳細は、「3.3実施体制の評価」で検証するが、災害発生から活動サイト到着のタイミングも、0.6日~1.8日、活動日数も4~7日と多様であったが、救出・収容者数は一定範囲であった。具体例を挙げるとたとえば、台湾地震災害(1999年)の場合は、派遣人数は110名と大規模で、災害発生後の到着タイミングが0.6日、実質活動日数は7日であった。トルコ地震災害(1999年)の場合は、39名を派遣し、現地到着までのタイミングは1.5日、実質活動日数は5.0日であった。アルジェリア地震災害(2003年)の場合は、61名を派遣し、現地到着までのタイミングは1.8日、実質活動日数は4.0日であった。
一方、成果の達成度については、一概に救出・収容者数の多寡を判断・比較し、結果に結びついた要因の特定を行うことは容易でない。これは、災害の規模、救出活動場所、出動回数、国際チームとの作業分担等の兼ね合い等の条件があり、また、いかに迅速に現場に駆けつけることができ、かつ優れた救助能力を持っていたとしても、生存者救出の機会に遭遇するのは、偶然の要素が大きいとも一般的に言われているためである。しかし、いずれのケースにおいても一定の成果を出したと評価できよう。
結論として、中間目標1の達成度については、規模、内容、被災地が異なること、データの数も6件と限られているから信頼性の高い分析は不可能であるが、少なくとも1996年以降に関しては、「救助チーム」の派遣に対し、毎回、一定の救出・収容者者数があったこと、5回の派遣のうち2回については生存者の救出もあったことから、人的被害の軽減に貢献する部分があったと評価できる。
アルジェリア地震災害(2003年)「救助チーム」のケース
地震発生(5月21日19時44分)から約48時間後の5月23日19時20分、「救助チーム」第1陣(18人)がブルメデス県ゼンムリ市の海岸沿いのホテル(6階建て)の倒壊現場で救助活動を開始し、その2時間後の21時30分、生存者1名(ホテル男性従業員)を発見し、合同で作業を行っていたトルコチームと協力して救出・収容に成功した。最終的に、1生存者、5遺体の救出・収容に成功している。(添付資料4)
<肉体的苦痛の軽減>
上で述べたように、日本チームは、生存者1名を含む6名を救出・収容したことからも肉体的苦痛の軽減に貢献したといえる。さらに、日本チームによる救出・収容者数について、全体の救出・収容者数に対する貢献度を確認してみる。最終的な救出・収容者数は、アルジェリア政府より公式発表されていないが、少なくとも国外28ヶ国から派遣された救援チームにより、生存者16名が救出され、254体の遺体が収容されている。そのうち、生存者を救出した国は7カ国、すなわち、フランス(8名)、スペイン(3名)、オーストリア(1名)、トルコ(1名)、ルクセンブルグ(1名)、イギリス(1名)、日本(1名)であり、日本チームも生存者救出という形でも貢献しているといえる(ただし、日本チームはトルコチームと合同で1名救出しているが、先方の記録ではこのような形になっていた。)。また、総遺体収容数254名中、日本は5名を収容している。(詳細は添付資料4参照)。
<精神的苦痛の軽減>
「救助チーム」が被災民の精神的苦痛の軽減(震災時の精神的不安の軽減、支援者がいるという安心感の付与の観点)にとても役立ったとの意見が、現地調査インタビューでは多く得られた。たとえば災害時の記憶を思い出してもらうと、彼らは、「各国からの救助チームが遠くから、それも驚くべきほど早く到着した印象を持ったこと」を第一に挙げ、さらに、「日本は遠い国のひとつであり、驚きをもって迎えられた。」「救助チームが被災国に派遣されること自体が、国民および被災民を精神的に勇気付けることになった。」ということが指摘された。
アルジェリアの場合、大規模地震災害の経験は少なく、十分な救助技術を有していないため、外国に対して、救助の経験や高い救助技術を期待していた。特に、日本に対しては、1995年の阪神淡路大震災が国内で広く知られており、救助技術、医療技術への信頼度は高かった。したがって、日本の「救助チーム」は、現地の救助ニーズに応えたことも分かる。実際に、「救助チーム」と活動を行った、ブメルデス県防災局職員や、救助活動を行った倒壊現場のホテルのオーナーによると、「日本の救助技術の高さ、チームの士気の高さ、チームワークのよさから、大いに救助技術を学ぶことが出来た」とのことであった。
「医療チーム」
過去の派遣実績(2003年末まで)は27件(ひとつの災害への数次派遣も個別に計算に入れると32件15)、総勢378名の隊員が派遣された。この内、結果のデータが判明しているのは、1996年以降であり、全部で14件である。表 3-2に示すとおり、アジア、アフリカ、中南米、中東、太洋州諸国の13カ国に対し、247名派遣し、16,572名の被災者の診療を行った。
それら14件について、派遣人数、実質活動日数、診察者数を等を表3-2に示した。派遣人数5~31人に対し、診療者数は339~2,611人となっている。1件あたり平均では、16.5名の派遣人数で約1,100名の患者の診療を行っており、従来「医療チーム」マニュアルの想定している診療者数の目安16を概して達成しているといえる。しかし、災害の種類・規模、診療活動場所の位置や条件が異なるので、派遣人数の数、発災後の到着日数(1.0~11日)、実質的な活動日数(6.0~11.0日)等の投入量の多さが、診療者数の多さという結果に必ずしもつながっていないことが推量できる。個別派遣事例ごとにサイトの適切な選定が行われたかどうか等の実施体制についての確認は、「3.3実施体制の評価」で行う。
ケース別には、トルコは、4週間(実質活動日数15.5日)1,605名、台湾は2週間(実質活動日数11日)で1,041名の患者を診療しており、マニュアルの目安としている一日の診療の想定する患者数以上を診察している。アルジェリアの派遣事例の場合、「医療チーム」派遣は、肉体的、精神的苦痛の軽減に役立ったということが確認された。(囲い参照)
以上、定量的情報の結果およびケーススタディの結果に基づくと、「中間目標1」の人的被害の軽減に貢献したといえる。

|
||
|
(出所)国際緊急援助隊派遣 各報告書、「国際緊急援助事業概要(2003年9月)」JICA国際緊急援助隊事務局 (注) *) サイト設営及び、サイト撤収活動も含む。 |
アルジェリア地震災害(2003年)「医療チーム」のケース
実質10日間(5月27日~6月5日)の診療活動を行い、延べ1,628名(1日平均約162名)の診察を行った。
<肉体的苦痛の軽減>
十分なデータがなく全診療人数に対する日本「医療チーム」の貢献度を明確に示すことは困難である。現地調査によれば、現在ゼンムリ市の診療所の一日の患者診療数は120名であり、それに比較し十分な数の患者の診察を行ったといえよう。
<精神的苦痛の軽減>
「医療チーム」の到着は、「救助チーム」に引き続きやってきたという点が、大々的に報じられた。「救助チーム」と同様で、遠くからはるばるやってきたという点で、被災民や国民に対して、驚きとともに、安心感を与えることが出来たことが、現地調査インタビュー等により判明した。また、日本の医療技術に対する住民からの期待は高く、日本の医療テントに来ることを希望する患者が多く、日本の活動について感謝していることとは、現地調査で当時日本の医療テントの隣で活動したアルジェリア人医師へのインタビューでも指摘された。
「専門家チーム」
「専門家チーム」の過去の派遣実績は21件(ひとつの災害への数次派遣も個別に計算に入れると25件17)であり、総勢232名の専門家が派遣された。「専門家チーム」の成果は、専門性等によって異なるが、先方政府および実施機関に対して技術的助言、指導を行うとともに、多くの場合、報告書の提出を行った。場合によっては、帰国後に詳細な報告書や分析結果を先方に提出するような配慮がなされた(以上、詳細は添付資料3を参照)。現地における活動の成果の例としては、たとえば、1999年トルコ西部地震の場合は、第一陣は、地震により被害を受けた建物、インフラの安全性の確認、今後の補強策に関する技術指導・助言及びこれらに関連した今後の協力ニーズを明らかにし、第二陣は、仮設住宅500戸18中、50戸について関与した。すなわち、16戸については、専門家による実技を中心とした技術指導を行い、残り34戸は、トルコ側の施工により専門家チームが技術支援を行った。1999年の台湾地震の場合は、建築物の被災状況及び応急危険度判断の制度等に関する調査および我が国からの協力ニーズについての調査等を実施した。
詳細については、以下の個別ケーススタディーにて検証した。その検証を行った範囲では、いずれも中間目標1を達成したと判断された。
アルジェリア地震災害(2003年)「専門家チーム」のケース
「専門家チーム」7名は6月12日~19日の8日間、首都アルジェおよびブメルデス県を中心に被災現場のサイト調査を行い、アルジェリア中央政府の震災対策本部、住宅・都市計画省ならびに公共事業省と協力し、1)建造物の耐震診断の実施、2)倒壊を免れた建築物に係る補強方法、3)社会インフラの復興計画策定、4)都市復興に必要な行政の取り組み、などに関する技術的助言活動を行い、また1)~4)に関する助言をまとめた報告書をアルジェリア政府へ提出した。
<肉体的苦痛・精神的苦痛の軽減>
「専門家チーム」も「救助チーム」、医療チーム」のそれぞれが、大きな成果を出し、大々的に成果が報じられていたことから、アルジェリア国民の大きな期待を持って受け入れられた。ちなみに、それ以外にも、期待が高かった理由には、次の2点もある。1)当時被災から3週間ほど経過した時点であったが、アルジェリア国政府の震災対策の遅れ等から日本チームへの期待も高まっていたということ、2)アルジェリア地震の数日後に日本でアルジェリア地震と同規模の地震が起きたことにもかかわらず、死者が0人であったことをアルジェリア国民はTV報道で知っており、日本の建設技術、耐震構造建築技術の期待が高まっていたこと。
「専門家チーム」は、到着後、住宅・都市計画省、公共事業省とともに活動を行い、建物やインフラの被害状況の視察を行った。直接被災民の家の耐震診断を行ったわけではなく直接的に住民の肉体的苦痛を軽減したわけではないが、震災後の住民の不安がある中で日本の「専門家チーム」の派遣は、彼らを精神的に勇気付けることに繋がった。また、現地での政府関係機関へのヒアリング結果によると、「専門家チーム」の提言と技術はアルジェリアの状況に合致したものであり、適切であったとの評価であった。
ベトナムSARS集団発生(2003年3月)「専門家チーム」のケース
3月12日にフレンチ病院が閉鎖、グローバルアラートが発出されて、バックマイ病院に患者の移送が開始され以降、3月16日に「専門家チーム」は、緊急感染症対策のための携行機材とともに、ハノイ入りし、保健省、WHO等との協議を行い活動を開始した。第一陣と、第二陣が3月25日まで活動を実施した。その派遣のタイミングは、バックマイ病院を拠点としてSARS患者の治療と感染防止対策が行われ、新規感染者数が感染の疑いのある者も含め急増中かつ、まだ病気の原因・感染経路等が解明されていない段階であった(添付資料7参照)。
<肉体的苦痛の軽減>
1.肉体的苦痛の軽減としては、ベトナムSARS制圧が迅速に行われたことがあげられよう。
「専門家チーム」の派遣後、バックマイ病院において新たな第二次感染者も発症することはなく、4月28日、WHOはベトナムの制圧宣言(20日間新規発症例が見られない場合に制圧したとみなされる)を出し、伝搬確認地域の指定地域から除外された。したがって、国際緊急援助隊の派遣は、SARSの制圧、すなわち、肉体的・精神的苦痛の軽減に貢献したといえよう。ちなみに、ベトナムの制圧までに要した時間は、2月23日から45日間であり、迅速性についての国際的評価も高い。死亡者を数多く出した順に、中国は200日、香港は、106日、カナダは110日、台湾は111日、シンガポールは70日制圧までにかかっており、ベトナムの迅速な対応が評価されることが分かる(添付資料9参照)。
2.現地調査の関係者インタビュー結果によれば、「専門家チーム」派遣に付帯して現地に持ち込まれた携行機材*)について、高い評価を得た。評価のポイントは第一に、その迅速性が感染拡大防止の大きな要因であったことと、第二に、現場での必要な機材の種類等に関する示唆を与えた効果があったことである。
*) 第一陣は、3月16日に、診療に当たる医師の感染防止のための防護服5着、人工呼吸器2台、その他、マスク、グローブ、ガウン、ハンドソリューションといった感染症防止のための薬剤を、携行機材として、現地に持ち込んだ。ちなみに、JICAプロジェクト関係予算からも資機材が供与されたが、到着のタイミングは早くて、3月20日であり、専門家チームより4日遅いものであった。第一陣の携行機材の合計金額は約1,300万円、第二陣は、85万円に相当する。なお、JICAプロジェクト関係予算を含めるとSARS関連資機材総額は6,200万円に相当する(添付資料6参照)。
<精神的苦痛の軽減>
SARSが発生し、ベトナム保健省や病院関係者は、同僚が原因不明の病気によって感染し、死亡しパニックに陥った中で、国際機関の支援に加え、日本の「専門家チーム」の派遣は、「現場の医師が、自分たちを支えてくれる人の存在に励まされ、勇気付けられた」ことが、インタビューにより得られた。このように、彼らの「精神的苦痛の軽減に役立った」との意見が現地調査にて収集されたことから、国際緊急援助隊が精神的苦痛の軽減に貢献したと言えよう。
<その他の波及効果:日本の国内の肉体的・精神的苦痛の軽減への貢献>
「専門家チーム」は、3月18日(火)早急に、「SARS緊急報告」を日本向けに提出し、SARSが国境を越えて日本にも広がる危険性を示し、日本における対策整備の必要性を示した。このときの緊急報告が、どのように国内体制整備に活かされたのかは、本調査の範囲ではないが、このような日本にとっても必要な情報収集を国際緊急援助隊は実施し、日本へ及ぶ苦痛の軽減にも貢献したと言えよう。
早期SARS制圧成功への「専門家チーム」の貢献以外の要因としては、以下が挙げられるている。
| 1) | ベトナム政府の対応 |
| 早い時期から情報を公開し、WHOや日本など諸外国へ支援を要請、SARSの拡散前に、フレンチ病院およびバックマイ病院へSARS患者を集中させる等、適切な対応を取った。 | |
| 2) | 国際社会の支援と連携 |
| WHO、日本、米国疾病管理予防センター(CDC)、国境なき医師団(MSF)など国際社会が迅速に支援を行い、ベトナム政府との連携がスムーズに行われた。 | |
| 3) | JICAバックマイ病院技術協力プロジェクトの存在 |
| 当プロジェクトが進行中のため、現地事情に詳しい日本人専門家の人選を迅速に行うことが可能であった。また、当病院はプロジェクト活動の一環として院内感染対策に掛かる支援に力を入れていたことから、院内感染対策に係わる基盤整備を進め、意識が高かった。 | |
| 4) | 病院スタッフの貢献 |
| 当病院のスタッフが真剣にSARS感染防止、制圧に向けた活動に取り組んだ。 |
3.2.2 「中間目標2」の評価
過去の派遣事例ごとの活動報告書の文献調査によると、派遣事業についてのプレスリリースの実施頻度についての確認はできなかったが、国際緊急援助隊についての新聞掲載記事が添付されており、国際緊急援助隊が被災国において注目を集めたことや、一定の報道がなされたことが確認できるものもあった。特に、入手した報告書の約半数においては国際緊急援助隊の新聞記事等が添付されており、現地報道の度合いにも注目していることがうかがえる。
詳細については、以下の個別のケースにおいて検証した。その結果としては、いずれもプレスリリースを積極的に行う等し情報公開の努力がうかがえ、その結果としてメディア報道もされており、一定の達成は認められるが、中には情報公開の方法を一層充実すべき課題も見受けられた(トルコと台湾の事例は添付資料12を参照)。
アルジェリア地震災害(2003年)「救助チーム」「医療チーム」「専門家チーム」のケース
(1)前半部:情報公開について
アルジェリア国において
在アルジェリア日本大使館は、「救助チーム」の到着した5月22日から「専門家チーム」の帰国の翌日の6月20日までに、合計6件のプレスリリースを、アルジェリアのプレスサービス・テレビ、ラジオ各1社と新聞の合計15社に向けて、実施した。加えて、活動現場においては、各チームの団長がテレビ、新聞などの取材に応じる体制をとった。
日本において
外務省は「救助チーム」の派遣決定とともに、インターネットによる情報提供を開始し、6月11日までに、14件の情報公開を行い、国際緊急援助隊の派遣や活動概要について伝えた。「救助チーム」には衛星通信機器を携行し専門家による通信班も同行したため、日本向け情報発信が順調に実施された。同時に日本のメディアの取材も受けることが出来た。
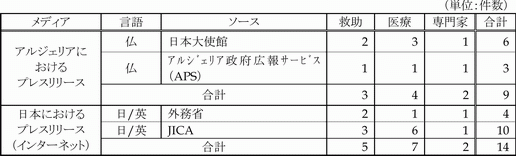
|
|||
| (注) | インターネットおよびプレスリリースは、言語が日本語、英語、現地語と分かれても、内容が同じものであれば、1件分としてカウントしている。(詳細データは、添付資料9参照) | ||
(2)後半部:認識度について
アルジェリアにおいて
新聞・インターネットの報道:アルジェリアにおいては現地の仏語新聞により合計58件の国際緊急援助に関する報道があり、日本の国際緊急援助隊について触れられていた。その58件中32件が写真付きの記事であった。また、58件中、23件については、日本の国際緊急援助隊の特集記事であり、好意的な扱いのものであった。このことから、国際緊急援助関連の新聞報道において日本のチームの取り扱いの割合が高かったことが伺える。(新聞掲載記事の例は添付資料4参照。)
また、現地調査における現地プレスへのインタビューでも、「日本の国際緊急援助隊に関する報道量は他国と比べても多かった」、「その活動が報じられた背景として、はるばる遠い国から救助隊がやってきたというニュース性があったこと」、「日本大使館の報道機関に対するアプローチが積極的であったこと」が指摘された。
相手国からの謝意の表明:国際緊急援助隊は、次のような形で、相手国からの謝意を伝えられている。
| 「救助チーム」に対して、「ホテルオーナーからの感謝状」 | |
| 「医療チーム」に対して、「保健省大臣の感謝状と楯」 |
日本において
日本の新聞では、合計31件、国際緊急援助隊に関する記事が掲載され、そのうち17件は写真つきのものであった。また、17件中、13件が日本の国際緊急援助隊に関する特集記事であった。報道内容としても、日本のチームがアルジェリアでも高く評価されているとの好意的な記事が多かった。日本における報道は、チーム別でみると、「救助チーム」の扱いが31件中12件と最も多い。記事の中で、日本の「救助チーム」が生存者1名の救出に成功したことを大々的に伝えている。
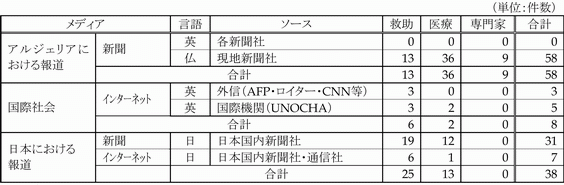
|
||
| (詳細データは、添付資料9参照) |
ベトナムSARS集団発生(2003年3月)「専門家チーム」のケース
(1)前半部:情報公開
ベトナムにおいて
プレスリリースについては、在越日本大使館は、「専門家チーム」が到着した3月14日から、4月4日まで、合計6回行った。プレスリリースは通常、現地メディアとしては、ベトナムテレビ局・ラジオ局3社、ベトナム新聞社・雑誌社29社に対して、日本および海外メディアとしては、テレビ局2社、ラジオ局2社、通信社14社、新聞社8社、雑誌社2社に対して、配信している。
さらに、国際緊急援助隊の活動として、2003年3月31日には保健省、ベトナム国内医療関係者を対象とした感染症対策セミナーを開催し、国際緊急援助隊の情報公開を行った。
日本において
情報提供を14件行った。この数は、アルジェリアの場合と同数であり、本件は「専門家チーム」のみについての報道であることを考慮すると、広報量としては多い。加えて、現場では「専門家チーム」の団長がテレビ、新聞などの取材に応じている。

|
|||
| (注) | インターネットおよびプレスリリースは、言語が日本語、英語、現地語と分かれても、内容が同じものであれば、1件分としてカウントしている。(詳細データは、添付資料10参照) | ||
(その他:JICA事務所、JICAバックマイプロジェクト等によるフォローアップ)
「専門家チーム」帰国後、JICA同プロジェクト専門家と病院スタッフが中心になり、SARS制圧に関する経験を発表するセミナーを数回開催した。具体的には、2003年6月に、SARS感染症セミナー(バックマイ病院技術協力プロジェクト主催)、2003年10月に、SARSシンポジウム(保健省主催)を実施し、「専門家チーム」の広報とともに、「専門家チーム」が作成に貢献したSARS感染症対策マニュアル、ビデオ、パンフレット等が、使用、配布された。特に、2003年10月のセミナーにはASEAN各国を始め、韓国、米国、ニュージーランド等の諸外国や、NGO、メディア関係者も多数参加しており、国際緊急援助隊の活動成果は、ベトナム以外の国へも広げられたことが推量される。
それ以外にも、ベトナム保健省、バックマイ病院でも、SARS対策の経験をもとに論文や出版物の発表を行っており、また、派遣専門家も帰国後、メディアの取材を受けたり、論文の寄稿などの他に、セミナーや学会での発表などを行っており、国際社会への波及効果が推量される。
(2)後半部:認識度について
ベトナムにおいて
新聞報道が22(英語8件、ベトナム語14件)行われ、そのうちの5件が日本の「専門家チーム」に関する特集記事であった。ちなみに、22件中、写真が掲載されていたのは3件であった。22件は、アルジェリアの場合の9件に比べると倍以上であるが、記事内容については「専門家チーム」の派遣の事実のみを客観的に報道するものが多く、紙面スペースを割いてその活動を詳しく紹介するものは少なかった(添付資料8参照)。
現地・国内調査での関係者へのヒアリング、FGD、質問票の回答などの結果から、日本の国際緊急援助隊の活動に関する認識は、ベトナム政府関係者および医療関係者の間では非常に高かったことが明らかになった。また一般国民の認識としては、SARS制圧は、ベトナム政府や医療関係者等の努力と取り組みによるものであるとの考えが一般的であるが、FGDを行ったハノイ市民によれば、「TV報道を頻繁に見ているハノイ市民においては一定の認知はされているはず」との意見であった。
(相手国からの謝意の表明)
ベトナム政府はSARS制圧に対する日本の協力と貢献を認め、日本大使およびJICAベトナム事務所所長に対して、保健省大臣より「人民の健康功労勲章」が授与された。
日本国内において
日本国内新聞での取り扱いは、アルジェリアの31件に比べて、ベトナムは10件であり、少なかった。この理由としては、「専門家チーム」の活動時期は、日本のメディアは、米英軍のイラク攻撃前後であり、関連記事に紙面を割いたこともあげられよう。ちなみに、日本国内において大々的にSARS関連報道がなされ人々の関心が高まったのは、中国でのSARS感染者が急増した2003年5月頃以降であった(添付資料8参照)。
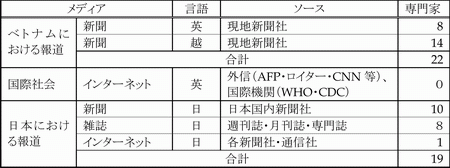
|
||
| (詳細データは、添付資料10参照) |
14第1章 「本評価調査の限界」(p1-5) を参照のこと。
151990年のイラン地震(第1~5次)を5件、1999年のトルコ西部地震(第1~2次)を2件として計算。
16JMTDRマニュアルによると、12名体制(医師3名、看護師6名、調整員3名)で2週間(14日)に渡って一日100人を診療することを基本の目安としてきた。1回の派遣の実質活動日数約10日とすると、約1,000人の診察者数がひとつの目安となる。2004年中にマニュアルは改定予定であるが、アルジェリア地震の時から実践された21名体制(医師4名、看護師7名、薬剤師1名、医療調整員3名、ロジ班5名)が反映される予定である。
171988年のイランアルメニア地震(第1~2次)を2件、1999年のサウジアラビア石油流出(1~2次)を2件、1997年のインドネシア森林火災(第1~2次)を2件、1999年のトルコ西部地震(第1~2次)を2件として計算。
18兵庫県から無償で提供され、海上自衛隊により運び込まれた。

