第1章 評価の概要
1.2 評価の方針「国際緊急援助隊」制度の評価に当たっては、外務省「ODA評価ガイドライン3」 に従って、評価の枠組みを策定し、制度の「目的」、「結果」、「実施体制」の3つの観点から、総合的、包括的に評価を行った。
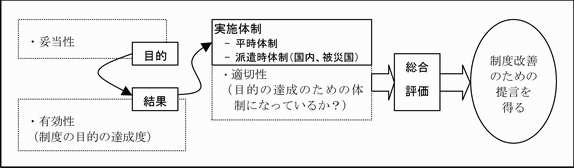
1.2.1 評価の枠組みの策定
評価を始めるにあたっては、まず、「目的」「結果」「実施体制」の3つの各視点につき、「調査内容」「調査項目」「評価基準」「指標」「情報源:調査手段」「情報収集元」に分け、整理し、「評価の枠組み」を作成した(表 1-1参照)。
その結果、第一の「I. 制度の目的の評価」については「妥当性」を、第二の「II. 制度の結果の評価」については、制度を実施した結果、制度の目的がどの程度達成されていたかを見ることにより「有効性」を、第三の「III. 制度の実施体制の評価」については、手続きやマニュアルの遵守度合いを見ることにより「適切性」を検証することとした。「妥当性」「有効性」「適切性」の考え方および定義については、評価者や評価対象がプロジェクトか制度かにより一様でないため、本調査では下記の表1- 2に示す意味において使用することとした。
さらに、「評価の枠組み」の策定においては、可能な限り評価者の違いによるばらつきを生じにくく、また評価の再現性を保てるよう評価対象、方法および判断の元となる情報源を明示することに努め、各評価視点を踏まえ、調査実施の可能性と内容を吟味し、「調査項目」ごとに指標と評価基準を設定した。指標設定にあたっては、別評価者の追跡が可能となるよう、定量的指標のみならず定性的指標についても構成要素を分解し、より厳密な評価基準を定義することに努めた。
情報の集積に伴い、「評価の枠組み」の「評価基準」と「視点」については、適宜評価者間で協議・調整のうえ、修正を行うものとした。
また、本来であれば「評価の枠組み」のI~IIIの全てにおいて、「最終目標(=国際協力の推進に寄与すること)」の達成度を考慮した評価を行うべきであろうが、本項目においては「最終目標」の達成度は考慮しなかった。なぜなら、「国際協力の推進」は、国際緊急援助隊というODAの一つのスキームによってのみにて達成が期待されているわけではなく、各ODA制度の成果の総体として達成されるものであり、本スキームの成果と「最終目標」の達成度の関係を明確にすることは困難であるからである。
最後の「IV. 総合評価」では、I~IIIの結果を踏まえて、国際緊急援助隊制度が「最終目標(=国際協力の推進に寄与すること)」の達成にどのように貢献しているのかについて、I~IIIで行った中間目標レベルの評価結果を受けて、「最終目標」への貢献度を測ることとした。
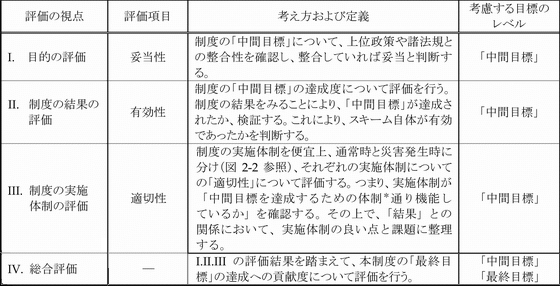
|
||
| *既に想定された実施体制のデザインであり、通常ガイドライン、マニュアル等で定められることが多いと理解する。 |
本評価調査の限界
本制度の「II.結果の評価」においては、定量的に制度の介入効果(インターベンション)を、制度の実施前と実施後で把握したいと考えた。しかし、本制度においては、定量的に制度全体としての達成度を判断するに当たり、下のような限界が見られた。
具体的に、「中間目標1」については、「救助チーム」と「医療チーム」は、有効性と関連する定量的指標として、救出・収容者数、診療者数等が挙げられるが、派遣事例ごとにその数の意味を分析するためのベースが異なり、また、十分なベースラインデータが収集されているわけではなく、プロジェクト間の比較、結果―要因分析に限界がある。したがって、「何人救助すればよしとするのか」、また、「何人診療すれば目的を達成したというのか」については、国際緊急援助隊のマニュアル等で想定している目標との比較において、派遣事例ごとに確認するしかなかった。「専門家チーム」については、①その活動分野が多岐にわたること、②協力対象が直接の被災者ではなく、被災国政府に対する技術的な助言や指導などを中心とすること、③活動成果は相手国実施機関の能力強化や政策への反映など中長期的なスパンで現れる傾向がある、ことから、明確な客観的定量データを得、何をもって専門家チームの目標が達成されたとするのか評価するのは困難であった。「中間目標2」についても、定量的に計る指標が、既存の報告書の中では記載されておらず、全ケースについて確認することは不可能であった。
そのため、評価作業は既存報告書等にある定量的情報(各種数値情報)の抽出・吟味と、現地調査実施分に関しては、アンケート調査、インタビューおよびフォーカス・グループ・ディスカッションにより得られる定性的情報を基にした各評価指標の意味解釈の積み重ねとなった。すなわち、量的データの信頼性を踏まえたうえで、インタビュー等から得られる質的データや報告書に蓄積された過去の事例を参考とした演繹的方法と、特定事例に基づく帰納的方法の双方からの評価を実施した。
ケーススタディを中心とした調査
以上のように定量的データの把握について限界があることから、本調査では、近年派遣された4つの国と地域に対する以下の派遣事例をケーススタディとして、評価結果に反映させた。
| 「救助チーム」「医療チーム」「専門家チーム」 | |
| 「専門家チーム」 | |
| 「救助チーム」「医療チーム」「専門家チーム」 | |
| 「救助チーム」「医療チーム」「専門家チーム」 |
上記4事例に関しては、直近の事例で、事後評価も行われてない、アルジェリアおよびベトナムに対する派遣に関しては、文献調査に加え、現地調査も含めた詳細調査を実施し、一部事後評価の行われているトルコ(「医療チーム」)および台湾(「救助チーム」)に対する派遣は、現地調査は行わず、文献レビューを中心に行った。
1.2.2 「国際緊急援助隊」制度の目的の整理
外務省「評価ガイドライン」によると、評価を行う際は「目的体系図4」を作成し、評価対象の制度の目的を整理している。制度評価において、制度の「目的」を制度の内容との関連付けて明確にすることが必要だからである。国際緊急援助隊制度の目的体系図の作成にあたっては、制度の根拠法、制度の概要および実績書、制度関連ガイドライン、国際緊急援助隊の個別活動の評価手法である「国際緊急援助隊評価ガイドライン“STOP the pain”5」等を参考とし以下の通り整理した。特に、当ガイドライン“STOP the pain”のPDMモデルの主要部分の「プロジェクト目標」(救助チーム、医療チーム共通)の「被害地における人的(肉体的・精神的)被害の軽減」および「成果」の「(1)チームが迅速に現地に到着する(救助チーム)/迅速にチームが派遣される(医療チーム)」「(2)被災者のニーズにあった救援活動が展開される」「(3) チームの救援活動が広報される」を参考とした。
| 「国際協力の推進に寄与すること」 | |
| (出所:国際緊急援助隊の派遣に関する法律(1987年施行、1992年6月改正)、第一条) | |
| 「人的(肉体的・精神的)被害の軽減」、 | |
| 「国際緊急援助隊の活動を積極的に情報公開し、日本の実施した活動が国際社会・相手国および日本において広く認識される」 |
また、「インプット」として、「救助チーム」、「医療チーム」、「専門家チーム」ごとに、活動内容、チーム構成、実施主体も整理した(図 1-1参照)。
1.2.3 「国際緊急援助隊」制度の実施体制の整理
制度の実施体制6については、「通常時」と「派遣時」に分け、以下のように整理した。
| 通常時における実施体制 | ||
| 派遣時における実施体制 | ||
| (i) | 要請から派遣までの体制 | |
| (ii) | 被災国における活動体制 | |
次に、国際緊急援助隊の実施に係わる各関係機関ごとに、実施のための体制や手続きをマニュアルやガイドラインに定められたものに従って、点検項目という形で整理した。整理に際し、「派遣時」における“(i) 要請から派遣までの体制”は、制度の創設時から現在まで同じ体制がとられているが、それ以外の体制については、体制の見直しが行われてきたため、調査の時点(2003年10月)での想定されるガイドライン等を基準とした(表 1-4 および表 1-5参照)。
1.2.4 本調査における用語の定義
本調査で使われている用語は、以下の表 1-3の意味で用いることとした。
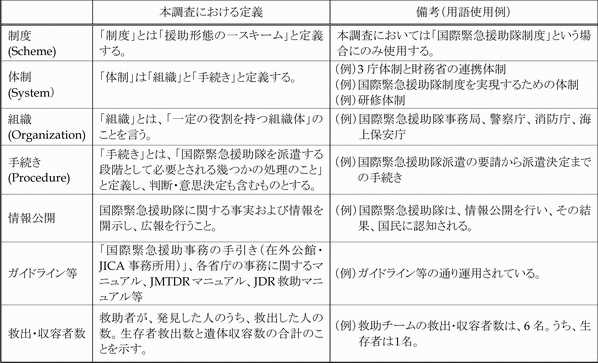
| 表 1-5 派遣時における実施体制(点検項目) | |
| (i)要請から派遣まで(PDF) | |
| (ii)被災地における活動(PDF) | |
3「ODA評価ガイドライン」外務省経済協力局評価室(2003年3月作成)。
4制度の目的を、「最終目標」、「中間目標」に整理し、同時に、制度のインプット(国際緊急援助隊の場合は、活動内容、チーム構成、実施主体)内容をツリー状に示したもの。
5平成15年3月作成、国際協力機構・国際緊急援助隊事務局
6実施体制について、派遣時の「発災から被災国の要請を受け、派遣決定を行いチームを派遣する」体制は、制度の創設時から現在まで変わらない。一方、通常時におけるチーム別「研修・訓練内容」や、派遣時における「被災国での活動体制」については、適宜見直しが行われている。

