4.インドネシア小規模灌漑管理事業(SSIMP)に見る参加型開発
(1)インドネシア小規模灌漑管理事業(SSIMP)
インドネシア小規模灌漑管理事業(Small Scale Irrigation Management Project:SSIMP)は、インドネシアでも開発が遅れた東インドネシアの水資源灌漑農業開発を促進し、農業生産を増大することにより農民の所得向上を図り、地域格差是正と地域の安定に資することを目的とした事業である。
プロジェクトは、海外経済協力基金(現、国際協力銀行)の円借款により第1次SSIMP(1990-95年)が実施されて以降、第2次SSIMP(1995-98年)、第3次SSIMP(1998-2002年)と3次にわたり実施されている。インドネシア側実施機関は公共事業省水資源総局であり、円借款金額はそれぞれ19.0億円、81.4億円、167.0億円である。
対象地域は第1次SSIMPではインドネシア東部の2州(西ヌサトゥンガラ、東ヌサトゥンガラ)の3地区(3,100ha)であったが、第2次SSIMPにおいては南スラウェシが加わり3州の11地区(15,600ha)、第3次SSIMPにおいてはさらに中部スラウェシ、東南スラウェシ、マルクの3州が加わり6州、19地区(24,000ha)と地域を段階的に拡大している(図4-1-1(PDF)、表4-1-1)。今回の調査では、すでに完了している第1次、第2次SSIMPを主たる調査対象とした。
本プロジェクトは当初、1985年に、USAID(米国国際開発庁)によって開始(無償700万ドル+借款4,300万ドル)、東部の3州(南スラウェシ、西ヌサトゥンガラ、東ヌサトゥンガラ)が対象地域とされ、地下水灌漑を含む15件の新規灌漑システム開発が計画された。しかし、ハード部分の進捗が遅かったため(24,770haの新規漑を行う当初計画に対し完成は1994年時点で5,080ha(21%))、インドネシア政府は、ハード面の遅れを取り戻すため、日本政府へ協力を要請した。
要請を受けた日本は、海外経済協力基金が1988年に案件形成促進調査(SAPROF)を実施した。SAPROFは、円借款の要請があった事業について、その必要性が認められるものの事業内容の確認が必要とされる場合に行われる補完的調査である。本案件はSAPROFの第1号である。こうした結果、1990年12月から第1次SSIMP(1990-95年)がOECFとUSAIDの協調融資で実施された。協調融資の形態は、1994年3月にUSAIDがSSIMPへの協力を終了するまで続いた。
プロジェクトの概要は表4-1-2、表4-1-3に示すとおりであり、主な内容は1)地下水、ダム、堰による灌漑および飲料水等の水資源開発、2)末端灌漑施設整備、水利組合設立等を通じた灌漑開発整備、3)営農指導である。
プロジェクトの特徴的事項として、農民参加型アプローチとNGOの参加、灌漑農業の経験のない地区での農業開発、案件準備段階から施設完成後までの一貫した営農指導サービス等があげられる。たとえば、USAIDが地元NGO(LP3ES、LEPPSEM)を水利組合(P3A、WUA)設立のオーガナイザーとして雇用し、高い成果をあげたことから、現在でもNGOを活用している(南スラウェシ等)。地下水灌漑開発地区においては、農民グループの組織化の可能性により規模が判断されている(東ヌサトゥンガラ等)。
表4-1-1 SSIMPプロジェクトリスト
| 灌漑面積 | |
| SSIMP-1 | |
| Tiu Kulit Dam Irrigation Sub-project (NTB) | 1,800 ha |
| Oesao Groundwater Irrigation Sub-project (NTT) | 600 ha |
| Pamasar Embung Irrigation Sub-project (NTB) | 700 ha |
| SSIMP-2 | |
| Bringin Sila Weir Irrigation Sub-project (NTB) | 2,400 ha |
| Pelara Weir Irrigation Sub-project (NTB) | 2,292 ha |
| Gapit Dam Irrigation Sub-project (NTB) | 1,300 ha |
| Sumi Dam Irrigation Sub-project (NTB) | 2,542 ha |
| Sumbawa Groundwater Irrigation Sub-project (NTB) | 200 ha |
| Wae Mantar II Weir Irrigation Sub-project (NTT) | 1,436 ha |
| Wae Wagha Spring Irrigation Sub-project (NTT) | 474 ha |
| Kahale Weir Irrigation Sub-project (NTT) | 620 ha |
| Oesao Groundwater Irrigation Extension Sub-project (NTT) | 600 ha |
| Awo Weir Irrigation Extension Sub-project (SulSel) | 2,200 ha |
| Salomekko Dam Irrigation Sub-project (SulSe1) | 1,722 ha |
| SSIMP-3 | |
| Batu Bulan Dam Irrigation Sub-project (NTB) | 5,406 ha |
| Pelaparado Dam Irrigation Sub-project (NTB) | 2,455 ha |
| Tilong Dam Irrigation & Water Supply Sub-project (NTT) | 1,484 ha |
| NTT Groundwater Irrigation Sub-project (NTT) | 500 ha |
| Sinorang Weir Irrigation Sub-project (SulTeng) | 2,220 ha |
| Biromaru Groundwater Irrigation Sub-project (SulTeng) | 200 ha |
| Kelara-Karalloe Irrigation Water Management Sub-project(SulSe1) | 7,004 ha 440 ha |
| Southern SulSel Groundwater Irrigation Sub-project (SulSel) | 360 ha 470 ha |
| Rumbia Groundwater Irrigation Sub-project (SulTra) | 508 ha |
| Bulu Island Groundwater Irrigation Sub-project (Maluku) | 500 ha |
| Bringin Sila Weir Irrigation Extension Sub-project (NTB) | 400 ha |
| Pelara Weir Irrigation Extension Sub-project (NTB) | 486 ha |
| Sumbawa Groundwater Irrigation Extension Sub-project (NTB) | 600 ha 500 ha |
| Wae Mantar II Weir Irrigation Extension Sub-project (NTT) | |
| Oesao Groundwater Irrigation Upgrading Sub-project (NTT) | |
| Awo Weir Irrigation Extension II Sub-project (SulSel) | |
| Gapit Dam Irrigation Additional Works (NTB) | |
| Sumi Dam Irrigation Additional Works (NTB) | |
| Salomekko Dam Irrigation Additional Works (SulSe1) | |
NTB:Nusa Tenggara Barat(西ヌサテンガラ)
NTT:Nusa Tenggara Timur(東ヌサテンガラ)
SulSel:Sulawesi Selatan(南スラウェシ)
SulTeng:Sulawesi Tengah(中部スラウェシ)
SulTra:Sulawesi Tenggara(東南スラウェシ)
Maluku(マルク
表4-1-2 プロジェクトの概要
| SSIMP-1 | SSIMP-2 | SSIMP-3 | 合計 | |
| 実施期間 | 1990.12-95.9 | 1995.10-98 | 1998-02 | |
| 円借款(億円) | 19.0 | 81.4 | 167.0 | 267.4 |
| 対象州(案件数) | 2(3) | 3(11) | 6(25) | 6(26) |
| 灌漑面積(ha) | 3,100 | 15,800 | 43,000 | 61,900 |
| 給水人口(千人) | 0 | 10 | 250 | 260 |
| 貯水ダム(個所) | 1 | 3 | 3 | 7 |
| ため池(個所) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 頭首工(個所) | 0 | 6 | 8 | 14 |
| 井戸(本) | 248 | 192 | 310 | 750 |
| 灌漑用水路(km) | 50 | 170 | 290 | 510 |
表4-1-3 SSIMPによる主なダム
| ダム名 | ティウクリット | ガピット | スミ | サロメッコ | バトゥブラン | ペラパラード |
| SSIMPプロジェクト | I | II | II | II | III | III |
| ダム形式 | ロックフィル | アースフィル | ロックフィル | ロックフィル | ロックフィル | ロックフィル |
| ダム高(m) | 32 | 30 | 45 | 29 | 39 | 61 |
| ダム体積(万m3) | 58 | 62 | 80 | 50 | 110 | 150 |
| 有効貯水量(万m3) | 1,000 | 900 | 1,700 | 700 | 4,900 | 1,400 |
| 灌漑面積(ha) | 1,800 | 1,300 | 2,542 | 1,722 | 5,406 | 2,455 |
| 給水人口(千人) | 0 | 2 | 6 | 90 | 50 |
(2)南スラウェシにおけるSSIMPの事例
(イ)地域の概要:南スラウェシ
SSIMPプロジェクトの対象地域は東インドネシアと呼ばれるインドネシア東部の開発の遅れた島々である。バリ以東の小スンダ列島の島々、カリマンタン島、スラウェシ島、マルク諸島、イリアンジャ(ニューギニア島の西半分)からなる。面積でインドネシアの約70%を占めるが、人口は20%に過ぎない。
表4-2-1から明らかなように、プロジェクト対象地域のスンバワ島を含む西ヌサトゥンガラ州と南スラウェシ州の所得水準は低く、中央政府による地方搾取とそれゆえの貧困を理由に独立を要求して混乱が続くアチェよりもかなり低い。貧困線以下にある貧困層の割合も他地域と比較してはるかに高い。このような西ヌサトゥンガラ州を含む東インドネシア地域では、SSIMPに代表される小規模な灌漑プロジェクトは取り残された農村地域の農業生産を高め、地域の経済活動を活性化して貧困脱却への具体的な手段を提供するものとして意義が大きい。
表4-2-1 SSIMPプロジェクト実施州の経済水準(州別地域所得:経常価格、1997年)
| 島・州 | 地域所得 (1,000ピア) |
対ジャカルタ比=100 | 貧困線以下の人口 (%,1996年) |
| 西インドネシア | 2992 | 30.5% | 10.6% |
| スマトラ島 | 2959 | 30.2% | 9.8% |
| アチェ | 4341 | 44.3% | 10.8% |
| ジャワ島 | 2994 | 30.5% | 11.5% |
| ジャカルタ | 9808 | 100.0% | 2.5% |
| 東インドネシア | 2641 | 26.9% | 15.4% |
| バリ | 3347 | 34.1% | 4.3% |
| 西ヌサトゥンガラ | 1208 | 12.3% | 17.6% |
| 東ヌサトゥンガラ | 1864 | 19.0% | 20.6% |
| 東ティモール | 1011 | 10.3% | 31.2% |
| マルク | 1864 | 19.0% | 19.5% |
| イリアンジャヤ | 4392 | 44.8% | 21.2% |
| スラウェシ島 | 1760 | 17.9% | 8.8% |
| 南スラウェシ | 1742 | 17.8% | 8.0% |
| カリマンタン島 | 4752 | 48.5% | 14.2% |
| 全インドネシア | 3130 | 31.9% | 11.3% |
(注) 貧困ラインの値は州別都市農村別に異なる。ちなみにインドネシア全体の平均で96年農村部27,413ルピア、都市部38,246ルピアであった。
南スラウェシ州は東インドネシアの中では米やカカオおよびコーヒーの生産地と知られる農業州である。州都マカッサル(1999年9月まではウジュンパンダンと呼ばれた)は人口100万人にのぼる大都市であり、工業団地が形成されているなど工業生産活動も活発だ。州内の幹線道路網の整備も1980年代後半以降急速に進んだ。また、東インドネシアの島嶼地域の窓口として商業流通のターミナルであり、内航海運上重要な位置を占める。しかもシンガポールなどとの国際貿易の拠点でもある。こうした特質から、南スラウェシは東インドネシアの開発拠点としての役割が期待されている。
カリマンタンとイリアンジャヤを除けば東インドネシア地域は木材や石油その他の資源に恵まれず、一般的には農業以外にさしたる資源がない。南スラウェシ州も同様であるものの、農業資源には恵まれ、水田農耕が従来から盛んで、東インドネシアでは比較的人口が多い。インドネシアではそう多くない米の純移出地の一つとなっている。それゆえ農業開発が地域経済の発展上重要な位置を占める。南スラウェシの脊梁山脈をはさんで雨季と乾季のシーズンが約4カ月ずれている。このため水資源を確保して適切な水稲生産を行うと域内でほぼ通年の米栽培が可能になるという大きなメリットがある。
(ロ)アウォ堰灌漑サブ・プロジェクト(Awo Weir Irrigation Project)
a)プロジェクトの場所
アウォ堰灌漑プロジェクトは南スラウェシ北東部、マカッサルから270km、パロポから南に80kmの地点にある(図4-2-1)。
堰地点でのアウォ川の集水面積は400km2である。山岳地帯を流れており、上流域51kmにわたって急峻で堰地点まで速度の速い流れがみられる。その後、海に注ぎ込むまでの26kmにわたって、広範囲な平坦地域が続いている。この平坦地は長い間、米の生産地として利用されてきた。年間平均雨量はほぼ3,086kmであるが、通常55%は4月から7月までの4カ月間にかけての雨季に降る。雨季以外には十分な降雨は望めないので、米の生産には灌漑が必要であった。
堰下流の広範囲にわたる平坦地は、ハイウエイによって東部と西部の二つのパートにわかれている。現存のアウォ堰および2,500ヘクタールの灌漑地帯はハイウエイ西部に位置しており、インドネシア政府およびUSAIDの資金を利用して、1992年~1994年にかけて完成した(アウォI)。ついでハイウエイ東部側の2,200ヘクタールを灌漑するために、OECF借款の援助を得てアウォIIが実施された。今回の評価対象になったのは、OECFが担当したアウォIIのプロジェクトである。さらに現在500ヘクタールの灌漑面積を拡大すべく、OECF(JBIC)の支援を得てアウォIIIが実施中である。
b)プロジェクトの概要
アウォ・プロジェクトの目的は、次のようなものである。
| 1) | 当該地域における農民の生活水準の改善。 |
| 2) | 農産物、とりわけ米の生産増加のために水資源の利用可能性を開発すること。 |
| 3) | 地域経済の活性化。 |
| 4) | 農民が利用可能な支持サービス水準の改善。 |
| 1) | アウォI:完成1994年
60mの堰の建設、8mの高さの石/セメントによる組積工事。 沈殿トラップ、右岸取水口の建設。 右岸灌漑システム、左岸灌漑システムの建設。 |
| 2) | アウォII:1996年に着手、1997年に完成。
第2次水路 38,821m 排水路 13,958m 第3次水路 27,585m 点検道路 13,591m |
c)プロジェクトの維持管理
建設終了後2年の間にメイン・システムの維持管理はカブパタン・ワジョ(Kabupatan Wajo)地方政府の責任となり、第3次水路の維持管理および第3次取水口は農民(水利組合)の責任となる。維持管理費はインドネシア政府から支出される。
アウォには、アウォIが完成した1994年以降、ランティングが置かれた(ランティング:Rantingとは、灌漑の維持管理事務所の責任者を指す言葉である)。アウォIIの完成に伴って7人のサブ・ランティングが追加された。サブ・ランティングは一人当たり12~20の第3次水路単位を管轄している。この他に5人のランティング・スタッフがいる。それぞれの担当は、行政、オペレーション、維持、水利組合指導、そして安全、である。また33人のゲートキーパーがいる。
プロジェクト完成以前からアウォIIのための維持管理設備はすでにあった。すなわち、十分な広さのランティング・オフィス、ランティング・スタッフ用の大きい住居、7台のモーターサイクルと10台の自転車、6台の携帯用電話である。これらに、ランティング・オフィスのための機材(コンピュータ、家具、等)、ゲートキーパーのための小さな住居、ピック・アップトラック、携帯用電話3台が追加された。
慎重に水が使用され、また植付け開始時期を分割することによって、ピーク時の水需要を引き下げることができるならば、4,700ヘクタールを灌漑できるだけの十分な灌漑水がある。水利組合のリーダーは、ゲートキーパーを通して、農民の水需要の必要性をサブ・ランティングのチーフに伝達する。ランティング・チーフは定期的に取水口の設定変更を決定する。
川に十分な水量があるときには、上記のシステムはうまく機能する。しかし水量がきわめて少なくなったときには、よりインテンシブな水量調整システムが必要となる。こうした事態が生じたときには、より強力で活動的な水利組合が不可欠となる。
灌漑システムの維持責任は、第1次/第2次水路システムと第3次水路システムとでは異なっている。第1次/第2次水路の場合には、公共事業省水資源開発局(PU)のランティング・スタッフが維持・修繕の責任を負っている。日常的および予測可能な維持のための費用は、政府の年間維持予算から支払われる。この中には灌漑維持管理スタッフの給料、オフィスの設備費、交通費、住宅費、通信費、除草費、沈殿物除去費が含まれている。また毎年ランティング・ヘッドは例外的な維持・修復費として特別予算を要求している。
これに対して第3次取水口よりも下流の第3次水路の場合には、農民が維持・修復の責任を負っている。この作業は個々の農民によって行われる場合もあるし、水利組合が労働者を雇って行われる場合もある。
アウォIIでは農民グループは、プロジェクトの当初から最終オペレーションの段階に至るまで、プロジェクトに関わっている。農民グループ(水利組合)の形成、強化、訓練は、レプセム(LEPPSEM)と呼ばれる地元NGOによって遂行された。LEPPSEMは、公共事業省水資源開発局と契約を結んでいる。アウォIでは17の水利組合が結成された。またアウォIIでは25の水利組合が結成された。
d)プロジェクトのインパクト
アウォ灌漑プロジェクトIIの完成によって、作付け形態と米の生産性に顕著な変化がみられるようになった。プロジェクト実施前のアウォ地域の作付け形態は雨季と乾季とでは大きく異なっていた。すなわち雨季(4月~7月)に米作が行われ、乾季(8月~1月)にはパラウィジャ(Palawija:メイズ、大豆、ピーナッツ、緑豆など二次作物の総称)というパターンであったが、プロジェクト完成後には雨季(4月~7月)、乾季(11月~3月)での米の二期作が可能になった(図4-2-2(PDF))。灌漑完成以前のこの地域における乾季作物は緑豆であった。作付け面積は440ヘクタールであった。また雨季の米の作付け面積は2,200ヘクタールであった。プロジェクト完成後には、雨季、乾季ともに2,200ヘクタールの米作が可能になった。また米の生産性も大きく改善した。プロジェクト完成以前のそれはヘクタール当たり2.1トンであったが、プロジェクト完成後には雨季のそれが5.63トンに、乾季のそれが5.69トンへと飛躍的な増加をみた。その結果、米の総生産量は(籾ベース)でみて、プロジェクト完成以前は4,620トンであったのに対し、プロジェクト完成後には24,904トン(雨季12,386トン、乾季12,518トン)と5.4倍増となった(表4-2-1)。また耕作集約度をプロジェクトの完成前と後で比較すると20%の増加となった。
表4-2-1 アウォII・プロジェクトのインパクト
| 作物 | 耕作面積(ha) | 収量(ton/ha) | 生産量(ton) | |
| プロジェクト実施以前 | ||||
| 雨季 | 米 | 2,200 | 2.1 | 4,620 |
| 乾季 | 緑豆 | 440 | 0.4 | 176 |
| プロジェクト実施以降 | ||||
| 雨季 | 米 | 2,200 | 5.63 | 12,386 |
| 乾季 | 米 | 2,200 | 5.69 | 12,518 |
表4-2-2 乾季における生産コストと農家所得の変化
| 生産物 | プロジェクト実施以前 緑豆 |
プロジェクト実施以降 米 |
|||||
| 単位 | 量 | 単位価格 (ルピア) |
総額 (ルピア) |
量 | 単位価格 (ルピア) |
総額 (ルピア) |
|
| 1.農家投入財 | |||||||
| a.種子 | kg | 25 | 4,500 | 112,500 | 25 | 2,800 | 70,000 |
| b.肥料 | |||||||
| 窒素肥料 | kg | 0 | 1,050 | 0 | 250 | 1,050 | 262,500 |
| TSP | kg | 0 | 1,650 | 0 | 150 | 1,650 | 247,500 |
| KCL | kg | 0 | 1,550 | 0 | 50 | 1,550 | 77,500 |
| c.殺虫剤等 | |||||||
| 殺虫剤 | ltr | 2 | 70,000 | 140,000 | 3 | 70,000 | 210,000 |
| 殺鼠剤 | kg | 0 | 10,000 | 0 | 5 | 10,000 | 50,000 |
| 殺菌剤 | kg | 0 | 70,000 | 0 | 5 | 10,000 | 50,000 |
| 小計1 | 252,500 | 967,500 | |||||
| 2.労働力 | |||||||
| a.耕起・砕土 | Animal Days | 2 | 20,000 | 40,000 | 2 | 100,000 | 200,000 |
| b.堤防修復 | Man Days | - | - | - | 4 | 7,500 | 30,000 |
| c.植付・除草等 | Man Days | - | - | - | 90 | 7,500 | 675,000 |
| d.収穫 | Man Days | - | - | - | 30 | 5,000 | 150,000 |
| e.植付カラ収穫マデ | Man Days | 47 | 7,500 | 352,500 | - | - | - |
| 小計2 | 392,500 | 1,055,000 | |||||
| 3.生産コスト(1+2) | 645,000 | 2,022,500 | |||||
| 4.生産 | kg | 400 | 3,500 | 1,400,000 | 5,630 | 1,200 | 6,756,000 |
| 5.純収入(4-3) | 755,000 | 4,733,500 | |||||
生産コストと農家所得にはどのような変化がみられたであろうか。表4-2-2は、乾季におけるコストと所得を比較したものである。この資料はLEPPSEMによって準備されたものであるが、乾季における農家の純収入はプロジェクト実施以前の75万5,000ルピアからプロジェクト実施後には473万3,500ルピアへと6倍以上になった。
なお、プロジェクト実施後の雨季における米作のコスト・所得構造は、プロジェクト実施後の乾季における米作のコスト・所得構造と同じである。表4-2-3は、プロジェクト実施前と後の純収入総額を比較したものである。プロジェクト実施以前には、雨季における天水米作と乾季における緑豆の生産によって、総額で29億1,489万ルピアの純収入があった。プロジェクト実施後は米の二期作が可能になり、純収入の総額は209億8,580万ルピアとなった。プロジェクト実施前と後との間で、純収入増加額は実に180億7,091万ルピアであり、7倍以上の純所得増となった。
表4-2-3 プロジェクト実施前と後の純収入
| 作物の種類 | 合計 | ||||
| 天水米作 | 灌漑米作 (雨季) |
灌漑米作 (乾季) |
緑豆 | ||
| A.プロジェクト実施以前 | |||||
| 1.耕作面積 (ha) | 2,200 | 440 | 2,640 | ||
| 2.ヘクタール当たり純収入(Rp) | 1,173,950 | 755,000 | |||
| 3.純収入 | 2,582,690,000 | 332,200,000 | 2,914,890,000 | ||
| B.プロジェクト実施以降 | |||||
| 1.耕作面積 (ha) | 2,200 | 2,200 | |||
| 2.ヘクタール当たり純収入(Rp) | 4,805,500 | 4,733,500 | |||
| 3.純収入 | 10,572,100,000 | 10,413,700,000 | 20,985,800,000 | ||
| C.純収入増加(Rp)(B-A) | 18,070,910,000 | ||||
e)維持管理と水利組合
アウォIおよびアウォIIの維持管理の予算は、政府からのものと農民自身からのものとからなる。第1次水路および第2次水路の予算は政府から支出されるが、第3次水路のそれは「ゴトン・ロヨン(相互扶助)」によって農民自身で行われている。
維持管理活動は表4-2-4から構成されている。維持管理活動における問題は、政府から支出される予算が十分ではないという点である。このため将来第2次水路および第3次水路の維持管理の実施は「水利組合連合」に移行する案が検討されている。
また、現行の維持管理の責任体制は次のようなものである。すなわち、水路維持は水利組合とランティング、ゲート・コントロールはランティング、堰管理は州政府レベルでのランティング(Ranting Dinas)、である。
表4-2-4 アウォでの維持管理活動の内容
A. 管理
|
|||||
B. 維持
|
|||||
アウォIおよびアウォIIには全部で42の水利組合がある。このうち17組合がアウォIで、25組合がアウォIIで結成された。表4-2-5は42にのぼる水利組合の概要である。この表からわかるように、1水利組合ごとのサービス・エリアの広さは43ヘクタールから252ヘクタールまでとかなりの幅がある。また1水利組合ごとの加盟者数は45名から198名までと、こちらもかなりの幅がある。また、水利用料金の徴収比率も水利組合ごとに0%から95%までときわめて大きな差がある。アウォという同一地域においても、ブロックごとにこれだけの大きな相違がみられる。集会の開催頻度はいずれの水利組合でも年2回の常会、そして付随的なものが年4回(組合によっては5~6回のものもある)開催されている。
アウォIとアウォIIとの水利組合を比較してみると、次のことがわかる。
| 1) | アウォIの場合、1水利組合当たりの平均サービス・エリアの大きさは141.3ヘクタールであるのに対し、アウォIIのそれは52.4ヘクタールとかなり小さくなっている。 |
| 2) | アウォIの場合、1水利組合当たりの平均加盟者数は107名であるのに対し、アウォIIのそれは77名と、これまたかなり少数になっている。 |
| 3) | アウォIの場合、水利組合1加盟者当たりの平均サービス・エリアの大きさは1.32ヘクタールであるが、アウォIIの場合には1.14ヘクタールと小さくなっている。 |
| 4) | アウォIにおける水利用料金の平均徴収率は43.1%であるが、アウォIIのそれは28.7%にとどまっている。 |
表4-2-5 アウォ水利組合の概要
| 水利 組合 番号 |
サービス エリア (ha) |
組合 加盟 者数 |
1加盟者数当たり サービスエリア |
設立年 | メンバー・フィー徴収率(%) | 所属村落名 | |
| 水利用 料金 |
灌漑 サービス 料金 |
||||||
| アウォI | |||||||
| 1. | 64.0 | 48 | 1.33 | 1993 | 25 | すべての 水利組合 で平均90% |
Awota |
| 2. | 208.0 | 198 | 1.05 | 1993 | 60 | Awota | |
| 3. | 53.0 | 45 | 1.18 | 1993 | 50 | Awota | |
| 4. | 148.5 | 126 | 1.18 | 1993 | 40 | Lauwa | |
| 5. | 228.0 | 122 | 1.88 | 1993 | 40 | Lauwa | |
| 6. | 252.0 | 136 | 1.85 | 1993 | 50 | Alesilurungnge | |
| 7. | 130.5 | 96 | 1.36 | 1993 | 30 | Alesilurungnge | |
| 8. | 112.0 | 82 | 1.37 | 1993 | 25 | Alesilurungnge | |
| 9. | 148.3 | 132 | 1.12 | 1993 | 20 | Simpellu | |
| 10. | 124.4 | 94 | 1.32 | 1993 | 35 | Simpellu | |
| 11. | 114.8 | 84 | 1.37 | 1993 | 40 | Simpellu | |
| 12. | 225.0 | 191 | 1.18 | 1993 | 45 | Simpellu | |
| 13. | 88.0 | 76 | 1.16 | 1993 | 75 | Lompo Loang | |
| 14. | 180.0 | 115 | 1.57 | 1993 | 40 | Lompo Loang | |
| 15. | 160.0 | 130 | 1.23 | 1993 | 60 | Lompo Loang | |
| 16. | 87.0 | 89 | 0.98 | 1993 | 50 | Lompo Loang | |
| 17. | 78.0 | 62 | 1.26 | 1993 | 20 | Lompo Loang | |
| 合計 | 2,401.5 | 1,826 | |||||
| 平均 | 141.3 | 107 | 1.32 | 43.1 | |||
| アウォII | |||||||
| 水利 組合 番号 |
サービス エリア (ha) |
組合 加盟 者数 |
1加盟者数当たり サービスエリア |
設立年 | メンバー・フィー徴収率(%) | 所属村落名 | |
| 水利用 料金 |
灌漑 サービス 料金 |
||||||
| 18. | 53.6 | 47 | 1.14 | 1996 | 80 | すべての 水利組合で 平均90% |
Lauwa |
| 19. | 79.8 | 79 | 1.01 | 1996 | 50 | Lauwa/Paojepe | |
| 20. | 80.5 | 59 | 1.36 | 1996 | 40 | Paojepe | |
| 21. | 82.7 | 49 | 1.69 | 1996 | 20 | Paojepe | |
| 22. | 43.0 | 47 | 0.88 | 1996 | 90 | Paojepe | |
| 23. | 123.7 | 94 | 1.32 | 1996 | 50 | Paojepe | |
| 24. | 64.4 | 46 | 1.40 | 1996 | 30 | Lauwa/Paojepe | |
| 25. | 99.5 | 67 | 1.49 | 1996 | 50 | Lauwa | |
| 26. | 149.2 | 110 | 1.36 | 1996 | 60 | Alesilurungnge | |
| 27. | 142.8 | 117 | 1.22 | 1996 | 95 | Benteng | |
| 28. | 76.4 | 59 | 1.29 | 1996 | 50 | Benteng | |
| 29. | 71.6 | 71 | 1.01 | 1996 | 0 | Benteng | |
| 30. | 54.5 | 54 | 1.01 | 1997 | 20 | Benteng | |
| 31. | 58.7 | 70 | 0.84 | 1997 | 20 | Tobarakka | |
| 32. | 106.1 | 92 | 1.15 | 1997 | 0 | Tobarakka | |
| 33. | 55.0 | 100 | 0.55 | 1997 | 50 | Tobarakka | |
| 34. | 50.9 | 100 | 0.51 | 1997 | 0 | Tobarakka | |
| 35. | 102.9 | 81 | 1.27 | 1997 | 0 | Benteng | |
| 36. | 97.2 | 75 | 1.30 | 1997 | 0 | Benteng | |
| 37. | 131.5 | 147 | 0.89 | 1997 | 45 | Benteng | |
| 38. | 67.9 | 72 | 0.94 | 1997 | 50 | Benteng | |
| 39. | 98.1 | 60 | 1.64 | 1997 | 0 | Benteng | |
| 40. | 125.2 | 75 | 1.67 | 1997 | 0 | Benteng | |
| 41. | 98.4 | 81 | 1.21 | 1997 | 0 | Benteng | |
| 42. | 88.9 | 76 | 1.17 | 1997 | 0 | Benteng | |
| 合計 | 2,202.5 | 1,928 | |||||
| 平均 | 52.4 | 77 | 1.14 | 28.7 | |||
すなわちアウォIのほうが、1水利組合当たりの平均サービス・エリアの大きさ、1水利組合当たりの平均加盟者数、および水利組合1加盟者当たりの平均サービス・エリアの大きさのどの指標をとってみても、アウォIIよりも規模が大きい。また、アウォIのほうがアウォIIよりも水料金の徴収率が高い。これはやや常識に反する結果である。通常は、規模が大きくなると監視(モニタリング)コストが高まるために水料金の徴収率が低くなる(逆に規模が小さくなると徴収率は高くなる)と想定されるが、実態はこれとは逆である(アウォIの水利組合の設立年が古く、年数を経てきたことが組織を強固にし徴収率を高めているとも考えられる)。前述したように、ADBのFMISの場合には、「規模を小さくしたことが農民間での相互監視(peer pressures)を強化することにつながり、これがFMISプロジェクトの成功の一原因となった」との説明を受けた。FMISのプロジェクト平均規模は84ヘクタールである。これと比較するとアウォIの場合のそれは2,500ヘクタール、アウォIIのそれは2,200ヘクタールであって、比較にならないほど大規模である。アウォの場合には各水利組合が担当するサービス・エリアの大きさが、ADBのFMISプロジェクトの平均規模に匹敵する大きさである。
ところでアウォIIでの水料金の徴収率を低めている要因は、ベンテン(Benteng)村およびトバラッカ(Tobarakka)(特に前者)に属する水利組合の多くで徴収率がゼロであることである。ベンテン村およびトバラッカ村に属する水利組合同士を比較すると、水利組合員一人当たりの平均サービス・エリアの小さいほうが水料金の徴収率がより高いという傾向がみられるものの、両者の間の相関はそれほど緊密なものではない。また設立年次でみると、1997年に設立された水利組合での徴収率が極端に悪いことがわかる。1997年に設立された水利組合は、いまだ経験が浅いためにその機能が十分に果たせていないということが推測される。いずれにしてもベンテン村およびトバラッカ村に属する水利組合には、他の村落にはない特殊要因があることが推測される。
アウォIIプロジェクト視察時点で、ベンテン村に属する三つの水利組合員たちからのヒアリングの機会に恵まれた。ベンテン村の村長のあいさつでは、1)OECFからの灌漑プロジェクトに対して感謝の言葉が述べられ、2)昔から農民は灌漑を望んでいたこと、3)灌漑プロジェクト完成によって米の二期作が可能になり、その結果農民の所得が向上したこと、4)今後ともOECFからの支援を期待していること、5)プロジェクトの維持管理をしっかりして灌漑の利用度を高めることに努力すること、が述べられた。
水利組合に属するメンバーたちからのヒアリングから、次の点が明らかにされた。
| 1) | プロジェクトの完成によって、米の二期作が可能になった。ヘクタール当たりの米の生産量は以前には3トン(天水依存)であったが、プロジェクト完成後には5トン以上の米が年2回とれるようになった。米の生産耕地の大きさは大半の農民の場合、1~2ヘクタールである。 |
| 2) | 灌漑地区以外の耕地には、カカオと丁字(特に前者)を植えている。耕作規模は、1農民平均で1ヘクタール弱である。キログラム当たりのカカオの出荷価格は1998年2,000ルピア、1999年4,000ルピアと好調である。 |
| 3) | 米は共同組合に売却されるのに対し、カカオは民間の商人に売却される。 |
| 4) | 大半の農民はカラーテレビおよびモーターサイクルを所有している。支払いはクレジット払いである。 |
| 5) | 年間の水使用料金は、1シーズン・1ヘクタール当たり15,000ルピアである。農民サイドに水使用料金を払う意志はあるが、ヒアリング時点までに支払った農民は全体の50%にとどまっている。水使用料金を払えない農民は、米を売却できない農民である。米の値段が下がっているので、値段があがるのをまっている状態である。水使用料金を払わない農民に対して罰則はない。 |
| 6) | 灌漑の完成によって、失業がなくなり、また土地の値段があがった。 |
| 7) | 1ヘクタール当たりの米作によって得られる所得は、1シーズン当たり約300~500万ルピアである(年間で約600~1,000万ルピア)。 |
| 8) | 所得使途のうち金額の大きいものは、結婚式(2,000万~1億ルピア)、メッカへの巡礼資金(2,000万ルピア)、そして子供の教育費(大学までいった場合1,000万ルピア)である。農民の子弟の90%が高校まで通学しており、さらにこのうち40%が高等教育を受けている。 |
ベンテン村に属する水利組合での水利用料金の徴収率が著しく悪い理由は、農民からのヒアリングを通してもはっきりとはわからなかった。しかし、少なくともベンテン村に属する農民の所得水準が著しく悪いからという理由ではなさそうである。むしろ「機を見るに敏な農民」による合理的な選択行動の結果であるように思われる。農民には、米価の市況回復をまってから「水利用料金を支払おう」という考えがある。また「水利用料金を支払わなくても、ことさら罰則がない」という事実には、かなり驚いた。料金支払い期限という考えがないように思われる。すなわち、「米が売却された段階で支払えばよい」という考えである。しかし料金未払いに対して罰則がないとするならば、農民間での不平等が生じるであろうし、やがてモラル・ハザード(倫理の欠如)が蔓延して、ほっておけば誰も料金を払わなくなる可能性がある。アウォ地区の全般で、水利用料金徴収率が著しく低い原因であろう。
f)プロジェクトにおける参加型アプローチの評価
アウォII灌漑プロジェクトは、当初から「農民参加型アプローチ」を採用したプロジェクトである。具体的には、施設の完成後、灌漑システムの運営はすべて農民グループが実施する一方、ダムや頭首工灌漑システムの運営は2次水路までは行政機関が、3次水路以降は農民の水利組合が担当するというプロジェクトである。そして、このプロジェクトを持続可能なものにするための一つの不可欠な条件は、機能する水利組合が組織化されることであり、そのためにファシリテーターとしてNGOを利用するというアイデアである。
アウォI灌漑プロジェクトは、インドネシア政府とUSAIDの協力によって完成したものであるが、そのプロセスで全国レベルで活躍しているNGO(LP3ES:Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial)を雇用した。このLP3ESは公共事業省との契約下で、17にのぼる水利組合を組織化し、農民グループに対する訓練と組織強化に携わった(補遺1:インドネシアにおけるNGO参照)。アウォIプロジェクト完成後の1995年に、このNGOのうちアウォ灌漑プロジェクトに関わったメンバーは、新たにレプセム(LEPPSEM:Lembaga Pengembangan dan Pembinaan Sosial Ekonomi Masyarakat )と呼ばれる地元(ブギス)NGOグループを結成した。OECFの援助によるアウォIIプロジェクトでは、この地元NGOが引き続き活用された。その理由は、このNGOが第一期プロジェクトで経験を積み、十分なレピュテーションを得ていたためである。インドネシアでNGOという場合、その実態は「契約に基づき業務を行う、間接費のかからないコンサルタント」に近い。
アウォIIプロジェクトにおけるNGOの役割は次のようなものであった。
(1)準備段階(6カ月)
- 農民/土地所有者の特定、および土地所有マップの作成。
- 灌漑システム(特に第3次水路)の改善/追加に関する農民からの提案を要請し、そ れらをプロジェクト・スタッフに提出する。
- 農民グループ(水利組合メンバー)の特定化と境界の線引き。
- 農民グループの責任者の選出、機構の準備、および運営予算の準備に対する支援。
- 農民グループと政府/プロジェクト・オフィサーを支援して、行政村、県、州レベルで 農民グループが公式に認定されるようにする。
- 契約を締結したり、銀行口座を開設できたり、銀行ローンが受けらるように、農民グル ープを法律上の認定団体にすることを支援する。
- 農民および地元居住者とプロジェクトとの関わり(アクセス、土地の借り入れ、紛争 等)を支援する。
- 農民とコントラクター間のビジネス利益の領域(労働供給、物資供給等)での支援。
- 第3次水路建設期間に農民とコントラクターとを支援する。
- 農民に対して、第3次水路の維持管理の訓練をほどこす。
- 最初のオペレーション期間に、問題解決の支援をする。
本プロジェクトでは、NGOが予想以上の働きを示した参加型開発の成功例であると評価できよう。しかし、それでもなおいくつかの留保が必要である。
第1は、インドネシア政府による水利組合の法律上の位置付けが依然として明確でないことである。国家レベルでの制度改革の意志と位置付けが必要となる。
第2は、そのためにすべての水利組合が十分に機能している状態にないことである。
第3は、小規模灌漑参加型アプローチを成功させるためには、十分な実行能力と意志をもち、かつ現地の事情に精通したNGOの協力が必要であるが、そのためにはそうしたNGOそのものをも育成しなければならないことである。
第4は、最終的には自ら灌漑システムを維持管理できる農民グループ(水利組合)が形成されなければならないが、そのためには農民自身に灌漑システムに対する所有意識(オーナーシップ)が根づかなければならない。アウォ灌漑プロジェクトは、広い目で見ると、現在、第3次アウォ灌漑プロジェクト(500ヘクタール)として継続中のプロジェクトである。USAIDがはじめてアウォ灌漑プロジェクトに着手したのは1985年のことである。これまでの成果は目覚しいものであるが、将来アウォ灌漑プロジェクトがすべて終了した後に、水利組合が十分に機能しているかどうかは今の時点ではわからない。
第5に、水利組合が維持管理責任を負っているのは第3次水路だけである。行政サイドが維持管理の責任を負っている第1次および第2次水路のパートが十分に機能しないために、灌漑システムが十分に機能しない可能性がある。
第6に、本プロジェクトの最終目的(上位の目的)は「東部地域の農民の貧困軽減」である。灌漑プロジェクトの完成によって農民の所得向上には目覚しいものがあるが、しかしなお留保が必要である。アウォII灌漑プロジェクトには営農指導プログラムが含まれており、乾季の畑作に関する指導とデモンストレーション・ファームがある。これはプラクティカルな、すばらしいアイデアである。しかし他方で、政府自身による営農指導があまりにも弱い。農産物の生産から流通に至るまでの、首尾一貫した政府レベルでの政策と諸制度が必要である。そうでなければ、「東部地域の農民の貧困軽減」というプロジェクトの上位目標はかなえられないであろう。こうした問題は、個々のプロジェクトの積み重ねだけでは解決できない。参加型アプローチの利点を活かすためにも、個々のプロジェクトをとりかこむ政策と制度の環境が整備されなければならない。
アウォ灌漑サブ・プロジェクトに関する疑問点を述べておきたい。第1は、サブ・プロジェクトの規模に関してである。アウォIIの灌漑面積は2,200ヘクタールである。またアウォIIIが完成すると、アウォ地区の灌漑面積は合計で5,500ヘクタールとなる。はたしてこれだけの規模があるプロジェクトを、「小規模」灌漑プロジェクトと呼ぶことが妥当であろうかという疑問である。他のサブ・プロジェクトに関しても、同様の点が指摘できる。たとえばスンバワ島のスミダム・プロジェクトの場合には、500世帯にのぼる農家の移転(resettlement)が必要になるほどの規模であった。
第2は、アウォ地区は年間降水量が極端に少ない地域ではないという点である。アウォ地区の降水量は、たとえばスンバワ島地区における降水量の約2倍である。インドネシア「東部地区の農民の貧困軽減」という目標に照らし合わせてみた場合、はたしてアウォ地域の選定が十分に妥当であったかどうか、議論の余地がある。貧困地域および貧困層の選定基準を一層明確にする必要がある。
(ハ)サロメッコ(Salomekko)ダム灌漑プロジェクト
a)プロジェクトの概要
南スラウェシ州ボネ県のサロメッコ、トンラ両郡にまたがるサロメッコ川流域の灌漑開発である(図4-2-3(PDF))。この地域の降雨量は年間2,700nnと豊富だ。ただし、雨季と乾季との降雨の差が顕著である。雨季は4月から7月で、年間降雨量の68%がこの4カ月に集中する。さらに、年々の降雨の変動が大きいという特徴がある。たとえば1995年には実に7,000m近い雨があったが、その10年前の85年の寡雨年にはわずか829mしか降らなかった。灌漑対策が極めて重要であることをうかがわせる。サロメッコプロジェクトはSSIMPIIとして1996年1月より建設開始98年7月に完成した。建設契約額は158億ルピアであった。これにより1,722ヘクタールの水田で二期作ができるようになった。プロジェクトによる建設の概要は次のとおりである。
- アースフィルダム:
- 堤長300m、堤高30m
- 人造湖容積820万m3、有効貯水量770万m3
- 集水域13.2km2
- 水没地面積84ヘクタール
- 灌漑水路網:1次幹線1.6kmおよび2次幹線水路計24.4km
- 末端水路網:52ブロック 1,722ヘクタールに建設
- 人造湖容積820万m3、有効貯水量770万m3
| 作物 | 事 前 (1991/92) |
事 後 (1998/99) |
増加倍率 |
| 作付面積(ha) | |||
| 雨季水稲 | 1,200 | 1,600 | 1.33 |
| 乾季水稲 | 0 | 1,360 | |
| 緑豆 | 760 | ||
| 作付面積合計 | 1,960 | 2,960 | 1.51 |
| 農地面積 | 1,200 | 1,722 | 1.44 |
| 土地利用集約度 | 163 | 172 | 1.06 |
表4-2-7 サロメッコダム灌漑プロジェクトによる土地生産性の向上
| (ton/ha) | ||||||||||||
|
プロジェクトの成果は表4-2-6、表4-2-7に示されるとおりである。乾季に水稲作が行えるようになった効果が大きい。年間の作付け面積の合計は1991/92年に比すれば、1998/99年には約1.5倍に拡大した。土地利用集約度(作付け面積/農地面積)が163から172へとわずか6%程度の増加でしかないが、これは乾季の畑作がなかったためで、今後、乾季の畑作が増加すれば土地利用集約度はさらにあがることが期待できる。いずれにしても、農民は価格動向を睨みながら収益性の高い作物を選択する余地が拡大したことは間違いない。
反収も表4-2-7が示すように、プロジェクトの前後でいずれの作物も2倍以上高くなっている。ただし、このデータは南スラウェシの他のSSIMPプロジェクトであるアウォプロジェクトでも用いられている。デモンストレーションファームなど営農・肥培管理が理想的に行われたときの水準を示すものと思われる。農家段階の実際の反収は表4-2-7の示す水準より低い可能性は否定できない。
反収の著しい伸びはヘクタール当たりの収益性を高める結果となっており、図4-2-4が示すように純収入の比率はプロジェクト完成によってプロジェクト以前と比較し、大幅に改善された。収穫面積の拡大と併せて、当該プロジェクトによって発生する全体の便益は顕著である。
水利組合は1996年9月から11月にかけて相次いで設立された(表4-2-8)。水利費徴収の実績は必ずしも芳しいといえず、全体の単純平均は36%の水準にとどまっている。この組合費は、役員等への報酬や技術料といった内容であるが、水利組織維持のための費用としては徴収率が低く、組合への農民の参加意欲や組織としての持続性が懸念される。受益者農民の、より積極的な参加を図ることが必要と思われる。
図4-2-4 サロメッコプロジェクトにおける粗収入と生産費構造(ヘクタール当たり)
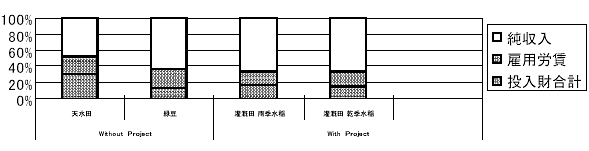
図4-2-5 サロメッコプロジェクトの一年当たり便益(と比較)(WithとWithout比較)
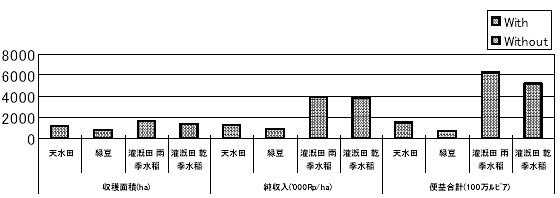
| 水利組合P3A名 |
所在村 |
組合員数 |
面積 (ha) |
面積 (ha/世帯) |
水利費徴収率 実績(%) |
| 1. Mappedeceng | Ulubalang | 47 | 43.3 | 0.92 | 20 |
| 2. Polewali | Ulubalang | 226 | 153.1 | 0.68 | 35 |
| 3. Padaelo | Ulubalang | 225 | 186.6 | 0.83 | 30 |
| 4. Padaidi | Ulubalang | 160 | 104.3 | 0.65 | 25 |
| 5. Ellung Mangenre | Ulubalang | 127 | 92.1 | 0.73 | 40 |
| 6. Cenning Atie | Kel. Pancaitana | 113 | 108.4 | 0.96 | 30 |
| 7. Toddopulie | Ulubalang | 81 | 88.0 | 1.09 | 40 |
| 8. Hatu | Biccoing | 58 | 54.5 | 0.94 | 50 |
| 9. Temmappasisalae | Biccoing | 84 | 55.2 | 0.66 | 30 |
| 10. Mamminasae | Biccoing | 236 | 155.7 | 0.66 | 50 |
| 11. Sipurio Spurennu | Muara | 234 | 107.7 | 0.46 | 30 |
| 12. Samaenre | Biccoing | 190 | 151.3 | 0.80 | 40 |
| 13.Mallilu Sipakainge | Biccoing | 254 | 192.5 | 0.76 | 45 |
| 14.Ciling Cinae | Biccoing | 199 | 156.5 | 0.79 | 25 |
| 15.Mappasiame’e | Bacu | 177 | 70.7 | 0.40 | 50 |
| 合計 | 2411 | 1719.9 | 0.71 | 36 | |
b)プロジェクトにおけるNGO
サロメッコプロジェクトは、アウォプロジェクト同様、SSIMPにおいてNGOを導入して本格的に住民参加をあおいだプロジェクトであった。NGO、LEPPSEM(Lembaga Pengembangan dan Pembinaan Sosial Ekonomi Masyarakat )はUSAIDによって1980年代より実施されたアウォプロジェクトの活動を組織の起源としている。そこでの経験を活かし、SSIMP下のサロメッコ、アウォ両プロジェクト、そしてスンバワにおけるプロジェクトでも活動している。
LEPPSEMには専任のスタッフが約20名いる。大学で社会政治学や農村社会学を学んだものが多く、農業普及活動に必要な栽培技術も身に付けている。多くは地方行政府に公務員として雇われてもおかしくない若者たちであるが、雇用情勢が厳しく、また他方では民主的な開発を目指す理想から活動に参加している。また彼らは農村に住み込んで住民と直に接しながら活動しているので、同じ方言を話す同一地域の出身者であることがメンバーとして条件付けられている。フィールドでの活動家の給与は月75万ルピアである。資金はプロジェクト当局とNGOとの契約によっている。このこともあり、実際の活動の中での政府との関係は、地方行政府や農業局などよりも公共事業省下のプロジェクト事務所や県庁内の灌漑局との関係が緊密である。
NGOによる住民「参加」支援活動は、第1に地元と行政との連絡調整、第2に地元農民間の利害調整、第3に営農指導である。LEPPSEMは、農民らに対し生活環境、法制度、教育指導など人的資源の開発、コミュニティ開発などに関して、農民たちを直接教化する活動を行っている。農民の人権が損なわれないように、そして「市民社会」の形成と発展を目指すとのことである。1999年の大統領令によりこのような国民のエンパワメントをインドネシア政府においても重視するようになった。
他の活動事例としては、金融へのアクセスを改善する意味で、たとえばLEPSSEMはサロメッコ地域でイスラム銀行を設立している。また婦人に対しては、家庭内や地域社会での地位の向上、保健衛生や出産等における婦人の自覚と知識や能力の向上を支援する、などの活動を行っている。
(3)スンバワ島におけるSSIMPの事例
(イ)地域の概要:スンバワ島
スンバワ島は西ヌサトゥンガラ州に含まれ、同州はスンバワおよびロンボクの二つの大きな島よりなる。スンバワ島は州の約4分の3に当たる面積1万5,400km2を占め、人口142万7,000人(98年)、平方キロ当たり人口密度93人である。近年は人口増加が著しい。ロンボク島は人口236万9,000人、人口密度506人であり、同じ州内の島といっても社会経済的条件は大きく異なる。
ロンボク島は水源に恵まれ水田農耕が盛んであるほか、バリ島の観光産業の発展が同島にも及んでいる。それに対してスンバワ島は農業以外にさしたる産業がない。しかも年間降雨量が1,000mmを下回るところも多い乾燥地帯であり、人造湖や貯水池を建設し、水資源を確保しなければ水田農耕はできない。そのため、農業といっても天水に頼る稲作と畑作か畜産が見られるに過ぎなかった。開発が遅れ、人口密度も低い地域である。
スンバワ島では、灌漑開発によって水源を確保し、水田の二期作化を図ることが農業生産と地域経済の発展にとって必須条件ともいえる。SSIMPはこのような要請に応えるうえで効果的な開発プロジェクトである。他方、政府はスンバワで移住入植事業を行ってきた。水さえ確保できれば、バリやロンボクの過剰人口を受け入れて開発する余地がまだ残されているからである。
(ロ)ティウクリット(Tiu Kulit)ダム灌漑プロジェクト
ティウクリットダム灌漑プロジェクトはSSIMPIとして水資源開発保全プロジェクト(PPKSA: Proyek Pengembangan dan Konservasi Sumber Air)の一環として行われた。県庁所在地スンバワブッサールから東に約45kmに位置する。行政的には同県プランパン(Plampang)郡に含まれる地域である。
表4-3-1 テイゥクリトダム灌漑プロジェクトのスケジュール
| 活動 | 規模 | 事業年 | |||||
| 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | ||
| 1. 土地収用 | 45ha | ―― | ―― | ―― | ― | ||
| 2. 事務所 | 600m2 | ― | |||||
| 3. アクセス道路 | 3km | ― | ― | ||||
| 4. ダム | 1 | ―― | ―― | ― | |||
| 5. 灌漑幹線水路網 | 25km | ―― | ― | ||||
| 6. 末端水路網 | 1,800ha | ― | ― | ||||
Direktorat Jenderal Pengairan, Departemen Pekerjaan Umum.
ダムの概要は次のとおりである。
- センターコアロックフィルダム:
- 堤体容積56万2,000m3、堤長419m、堤高31.7m
- 人造湖容積1,100万m3 有効貯水量1,000万m3
- 灌漑水路網:1次幹線および2次幹線水路計24km
- 末端水路網:1,800ヘクタール
- 人造湖容積1,100万m3 有効貯水量1,000万m3
土地生産性は表4-3-2が示すように水稲で1.7倍、大豆で2倍、緑豆で2倍と大幅に改善された。ただし、この表はプララ堰灌漑プロジェクトにも適用されているので、デモンストレーションファーム等で政府の指導とおりに営農が行われた場合の理想的反収水準であろうと思われる。個別の農家がこの水準を実現しているかは、さらに詳細な調査が必要である。収穫面積は、水稲で3.9倍、大豆で6.1倍、緑豆で6.6倍と大幅に拡大した(表4-3-3)。
表4-3-2 スンバワのSSIMPプロジェクトにおける土地生産性の向上
| (ton/ha) | ||||||||||||||||
|
表4-3-3 スンバワ島 SSIMPプロジェクトにおける収穫面積の拡大 面積(ha)
| 1996 | 1997 | 1998 | ||
| ティウクリットダム | ティウクリットダム計 | 836 | 3,512 | 3,925 |
| 水稲 | 550 | 2,084 | 2,140 | |
| 大豆 | 200 | 803 | 1,220 | |
| 緑豆 | 86 | 62 | 565 | |
| プララ堰 | プララ堰計 | 1,413 | 1,589 | 3,091 |
| 水稲 | 1,023 | 1,023 | 2,370 | |
| 大豆 | 558 | |||
| 緑豆 | 390 | 566 | 163 | |
表4-3-4 ティウクリットダム灌漑プロジェクト地域の水利組合(P3A)
| 水利組合P3A名 | 面積(ha) |
| 1. Maris Gama | 105.5 |
| 2. P. Sakti | 55.0 |
| 3. S. Semung | 54.5 |
| 4. S. Sakti | 80.8 |
| 5. Saling Beme | 160.5 |
| 6. Aisidu | 37.5 |
| 7. Unter Lupi | 133.5 |
| 8. E. Ketujer | 89.3 |
| 9. Keban Nyer | 130.2 |
| 10. Beme Rara | 130.6 |
| 11. K. Samurung | 103.8 |
| 12. Orong Rea | 130.8 |
| 13. KT. Pisak | 52.5 |
| 14. Panto Langan | 63.8 |
| 15. U. Tumpes | 143.9 |
水利組合(P3A: Perkumpulan Petani Pemakai Air、略称ペーティガアー)は表4-3-4に示したように当初17組合が組織されたが、1999年末現在は2組合が増えて19組合が組織されている。50ヘクタールないし150ヘクタールが水利組合の一つのブロックである。
土地収用から水利組合を組織する過程でNGOが重要な役割を果たした。特に農民と政府・行政との調整においてNGOの介在が効果があったとされる。南スラウェシのアウォプロジェクトで経験を積み実力をつけ、この地で活躍するNGOスタッフの努力に対する農民の評価は高いものがあり、農民たちは彼らを「アウォ」と呼び習わしている。また、伝統的に水利を担当する長はマラール(malar)と呼ばれ、一つの村(desa)に一人ないし二人いて、村内の農業用水の調整管理を行ってきた。このような伝統が、水利組合の形成と比較的順調な灌漑網の維持管理活動に寄与していると推察される。
農民の代表による現状の説明、要望には次のようなものがあった。1)水稲の二期作が可能になり大変感謝している、2)籾の収量が大幅に増えたものの、それらを貯蔵する倉庫の容量がなく、また建設する資金もない、3)米の販売・流通に問題があり、価格はまずまずだが納得できるほどの価格水準ではない、4)乾燥機がないので雨季は籾の乾燥が難しく、脱穀用具も十分にない、5)農業のための様々な資金が必要だ、6)耕起などに使う畜力が不足している、7)2次幹線水路の幅が十分でない、8)壊れた水路の補修費を援助してもらえないか、9)収入は上昇しているが若者は農業を継ぎたがらない。
(ハ)プララ(Pelala)堰灌漑プロジェクト
プララ堰はスンバワ県南部ルニュッ(Lunyuk)郡に位置するSSIMPIIプロジェクトである。県庁のあるスンバワブッサールから約100kmの距離にある。同郡の人口は約1万7,000人である。プロジェクト対象地域の住民構成は75%が地元のスンバワ人だが、25%はバリおよびロンボクからの移住入植者である。1960年代前半、バリ島のアグン山の噴火によって移住を余儀なくされた人々の移住入植地である。以来、道路と灌漑堰の建設は長い間住民の強い懸案事項であった。アスファルト道路が完成する以前は、スンバワブッサールへは馬で片道数日を要するという辺境の地であった。
産業はスンバワ島の他地域同様農業が中心である。農業生産は降雨に大きく依存しており、水を多量に必要とする水稲は雨季に年一回が従来のパターンであった。雨季後の作付け期では、水資源自体は十分あるため、堰等によって水を確保さえできれば農業生産は飛躍的に伸びるとされ、灌漑開発事業への期待は高かった。
プララ堰が完成する以前はクアンラコ堰によって農業用水を確保していたが灌漑面積はわずかに100ヘクタールに過ぎなかった。プララ堰灌漑は2,292ヘクタールの農地を灌漑する計画で建設が行われ、1997年より灌漑を開始した。96/97年(96年末の雨季の開始期より1年間の意味で96/97と記す、以下同様)では年間作付け面積は1,588ヘクタールに過ぎなかったが、プロジェクトが完成した98/99年には6,789ヘクタールへと5,201ヘクタール増加した(表4-3-5)。
灌漑条件の改善と政府の栽培指導により、現在の一般的な作付けパターンは水稲二期作に乾季の大豆、緑豆などの畑作物となっている。水稲、大豆、緑豆に栽培が集中しているが、その他の畑作物の主なものはトウモロコシや落花生である。
1998/99年の雨季水稲作は、1996/97年の2,623トンから8,325トンへと約3倍強にも増加した。雨季作の収穫面積は1,850ヘクタール、乾季前半(乾季1)は1,261へクタールの灌漑が行われた。この結果1998/99年水稲収穫面積の合計は3,111ヘクタールに上った。営農指導を行うためのデモンストレーション圃場が3ヵ所に計24.5ヘクタール設けられ、そこで水利用維持管理の訓練も行われている。
表4-3-5 プララ堰灌漑プロジェクトの事前(1996/97)事後(1998/99)比較
| 作物 | 事 前 (1996/97) |
事 後 (1998/99) |
増加倍率 |
| 作付面積(ha) | |||
| 水稲 | 1,023 | 3,123 | 3.05 |
| 大豆 | 286 | 1,588 | 5.55 |
| 緑豆 | 47 | 2,078 | 44.2 |
| その他の畑作物 | 232 | 0 | 0 |
| 作付面積合計 | 1,588 | 6,789 | 4.28 |
| 農地面積 | 1,023 | 1,935 | 1.89 |
| 土地利用集約度(%) | 109 | 267 | 2.45 |
表4-3-6 プララ堰灌漑プロジェクト地域の水利組合(P3A) 1)
| 水利組合P3A名 | 所在村(Desa) | 組合員数(世帯) | 面積(ha) | 世帯当たり (ha/世帯) |
| 1. Harapan Kita | Lunyuk Ode | 183 | 274.5 | 1.50 |
| 2. Harapan Makmur | Lunyuk Ode | 215 | 323.0 | 1.50 |
| 3. Saling Beme | Lunyuk Rea | 182 | 273.5 | 1.50 |
| 4. Saling Sakiki | Lunyuk Rea | 187 | 280.5 | 1.50 |
| 5. Mertha Sari | Sukamaju | 241 | 298.3 | 1.24 |
| 6. Bina Karya | Pola Suka | 222 | 333.2 | 1.50 |
| 7. Karya Bakti | Pada Suka | 311 | 467.0 | 1.50 |
| 合計 | 1,542 | 2,250.0 | 1.46 |
(注1)1997年現在
プロジェクト対象地では7水利組合が組織された。水利組合の設立には県知事および地方裁判所の認可が必要とされるようになったが、これにより従来の水利組合のような単なる寄り合い的なものとは異なり、法人格が与えられ、水利関連以外の事業も行えるものとなった。水路の補修管理や水配分等いわゆるO&Mの責任はこの水利組合に任される。末端水路だけでなく、灌漑プロジェクト地域内の幹線水路以下全体を管理し、水を配分する責任が与えられている。その実施を円滑かつ確実にするために水利組合の連合組織が作られている。バリやロンボクからの移住者が混じる社会文化的には不均質な地域社会であるものの、以上のような水利組合の結成に当たって混乱や問題を生じている様子は観察されていない。ただし農民からは、農民側の責任を果たすための労働力が足らない、水路の整備が遅れたために水没する水田があるなど問題が指摘されたが、こうした問題点はプロジェクト実施者も把握しているとのことで、プロジェクトを実施する行政と農民との意思疎通は良好である。
水利組合について、1997年10月に設立された水利組合(P3A)サリンベメを事例として紹介する。各メンバーの負担する水利費は大きく分けて3種類ある。第1は設立出資金でメンバー一人当たり5,000ルピア、第2は負担義務金で一作期当たり1ヘクタールにつき15,000ルピアである。これは組合役員報酬として20%、技術料などとして40%、維持補修活動費として30%、村の財政に10%が充てられる。第3は、特別納付金で水路補修・建設、組合員からの借入金返済、IPAIR(Iuran Pelayanaan Irigasi)プログラム支払いなどのためのもので、その額は組合大会で決定される。
組合員の不正行為、たとえば盗水、水路の損壊、飼育動物による圃場荒しに対して各々50,000ルピアの罰金、決めた耕作パターンに従わない場合には同額の罰金に加えて水の供給停止、集会や出役義務を理由なく欠席した場合には5,000ルピアの罰金、役員らによる公金横領等の不正には組合被害額の2倍を徴するなどの罰則規定を定めている。
プララ堰灌漑地域の農家の平均的な土地所有面積(経営面積とほぼ同一)は約1.5ヘクタールである。0.5ヘクタールに満たないジャワなどに比べればかなり広い面積であるが、従来は水稲一期作しかできなかったため農業収入は低く、貧しい。今後は水稲二期作に加えて、さらに大豆などの乾季作も安定するであろうから、農家の所得の向上は大いに期待できる。
プロジェクトの成果としては、年三作が可能となり所得水準が上昇した、そのおかげで子弟を学校にやるにも余裕ができた、保健衛生にも気を配れるようになった、道路整備のおかげで農産物を市場に出せるようになりつつある、など農民の声が聞かれた。また、ここ2~3年の経済危機で農産物価格が上昇し、この地域の農民にとって幸運であったとの声も聞かれた。
(ニ)ティウクリットダム灌漑プロジェクトとプララ堰灌漑プロジェクトの効果
ティウクリットダム灌漑プロジェクトとプララ堰灌漑プロジェクトの経済効果をみたものが、図4-3-1~6のグラフである。1996年から1998年の時系列変化で見たものであるが、灌漑の完成により、1)収穫面積が大きく増加するとともに(図4-3-1)、2)各作物の土地1ヘクタール当たりの純収入が向上している(図4-3-2)。これを作物別に示したのが図4-3-4~6である。3)プロジェクト地域全体の経済的便益が大幅に増加している(図4-3-3)。完成後の便益の立ち上がりの早さは、水利組合の形成とそれを通じた普及事業等のソフト面での対応が伴っているためと思われる。ただ、両地域でデータ値が同一であることから、このデータはデモンストレーションファームのものと思われる。
収益性は、1997年~98年にかけて急激に改善しているように見られるが、これは土地生産性の上昇によるものではなく、価格の上昇によるものである。重要なことは価格変化に対して農家が柔軟に対応して作付け面積を拡大できたことである。これは灌漑が整備され水の供給が保証されるようになった効果にほかならない。プララ堰プロジェクトの収穫面積の変化がこのことを示している(図4-3-1)。
図4-3-1 スンバワ島 SSIMPプロジェクトにおける収穫面積の拡大
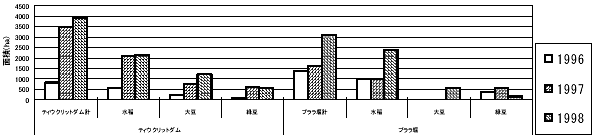
図4-3-2 スンバワ島 SSIMPプロジェクトにおけるヘクタール当たり純収入
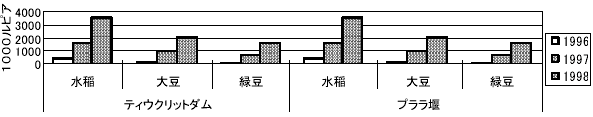
図4-3-3 スンバワ島のSSIMPプロジェクトの便益
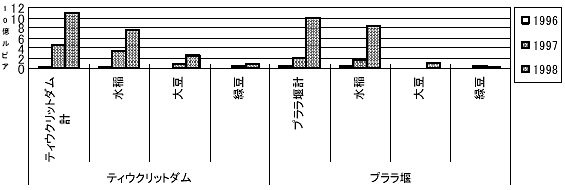
図4-3-4 スンバワ島SSIMPプロジェクトにおける水稲の粗収入と生産費の構造(ヘクタール当たり)
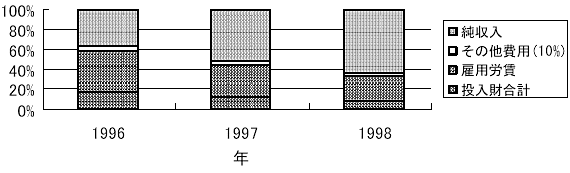
図4-3-5 スンバワ島SSIMPプロジェクトにおける大豆の粗収入と生産費の構造
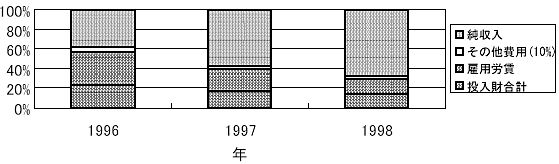
図4-3-6 スンバワ島SSIMPプロジェクトにおける緑豆の粗収入と生産費の構造(ヘクタール当たり)
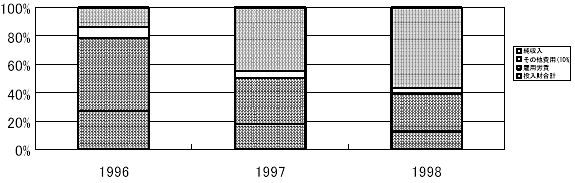
(ホ)ウンパン地下水灌漑プロジェクト(Empang Groundwater Irrigation Project)
a)プロジェクトの概要
ウンパン地下水灌漑プロジェクトは、SSIMPII(1995年~1998年)のスンバワ地下水灌漑サブ・プロジェクト(Sumbawa Groundwater Irrigation Sub-project) の一環として展開されたもので、スンバワ島中央部のウンパン村地域に立地している。4月から11月にかけての乾季8カ月間は、農耕が不可能なこの地域に灌漑農業を定着させ、農業生産性の向上、ひいては農民の所得・生活水準の改善を図るものである。具体的には、1)264ヘクタールの乾燥農地に、小規模な管井戸(tubewell)を23本設置し、2)ポンプ・アップした地下水を、配水管を通じて各農家に灌漑用水として利用させ、3)乾季畑作の促進、ひいては、雨季における稲作(天水米作)への依存度の軽減を図るものである。各配水管からは9世帯の農家に灌漑用水が供給されている。
なお、本灌漑プロジェクトでは、プロジェクトの初期計画段階から、農民の積極的なコミットメントの促進が図られている。それは、農民の間に、自分たちの灌漑施設という自覚(Sense of Ownership) を定着させて、プロジェクトの持続可能性の向上を図るものである。具体的には、1)受益農民に水利組合を設立させ、その「自主的」運営を全面的に支援する、2)スンバワブサールに設置されたSSIMP事務所によるキメ細かな営農指導、を二本柱としている。
b)維持管理と水利組合
ウンパン地下水灌漑プロジェクトは、ウンパン村およびそれに隣接する村落にまたがっており(総面積264ヘクタール)、農民参加の水利組合を軸とする、農民自身による灌漑施設の維持管理、ひいては積極的営農が目標とされている。その概要は次のとおりである。
| 1) | 17の水利組合が結成され、加盟者総数は、330人に達している。 |
| 2) | 灌漑面積が最大の水利組合は、27ヘクタール(加盟者29人)。また、最小の水利組合は、7ヘクタール(加盟者17人)である。なお、一番小規模な水利組合は、9名の加盟者から構成されている。 |
| 3) | 水利組合は、1996年から1997年にかけて結成されている。その具体的な手順は、a)加盟農民による、規則と細則の作成、b)村長の署名、c)郡長の署名、d)県知事の署名・布告(decree)、e)県裁判所の署名、となっている。こうして正式に発足し、法的人格を付与された水利組合は、加盟者から強制的に水利用料金を徴収する権限を獲得する。 |
| 4) | 水利組合には、それぞれ固有の名称が付けられている。また各水利組合には、組合長(head)、書記(secretary) 、収入役(treasurer) の3役が選出され、水利組合運営の任に当たる。 |
| 5) | 灌漑施設(管井戸やポンプ等)の維持管理に必要とされる経費は、政府(県)予算から賄われてきた。しかし、2000年からは、加盟者から徴収する水利用料金(自主財源)により必要経費(ポンプ操作員の人件費を含む)を充当する予定となっている。 |
| 6) | 水利組合の会合は、年1回の総会(全員会合)、および各耕作期ごとに開かれる小会合(年3回)とから構成されている。ただし、組合によっては、適宜会合をもつ場合もある。会合への出席率は90%。ただし、夜に開かれることが多いため、女性の出席率は低い。 |
c)プロジェクトのインパクト
1995年に開始され、1998年に完成したウンパン地下水灌漑プロジェクトは、ウンパン村の農業形態に大きな変化をもたらしつつある。その最大のものは、作付け形態の劇的な変化である。従来、ウンパン村の農業は、雨季の天水稲作、およびそれに付随する大豆の栽培がすべてであり、農地が乾燥し、一面茶色となる乾季においては農耕は不可能であった。作付けは、米-パラウィジャ(palawija:大豆、落花生、緑豆等)-休耕のパターンであった。地下水灌漑プロジェクトの完成により、ウンパン村の作付け形態は、雨季の天水稲作に加えて、乾季の農耕が可能となった。こうして、乾季にも、米、とりわけ大豆、落花生、緑豆(mungbean) 等の二次作物の栽培が行われるようになったのである(米-米/パラウィジャ-パラウィジャの作付けパターン)(表4-3-7)。
プロジェクトのインパクトとして次の点をあげることができる。
| 1) | ウンパン地下水灌漑プロジェクトの対象範囲は、4年間で、180ヘクタール(初年度、1995年度)から264ヘクタール(完成年度、1998年度)へと拡大した。それは、年間を通じての農地の有効利用(多毛作)を可能とし、ウンパン村の延べ可耕地面積(年間)は、234ヘクタールから、ほぼ3倍の703ヘクタールへと飛躍的に拡大した。 |
表4-3-7 ウンパン地区作付け面積の拡大
| (単位:ha) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表4-3-8 ウンパン地区単位あたり収量
| (単位:tons/ha) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表4-3-9 ウンパン地区総生産量
| (単位:トン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | 乾季における可耕地の大幅な増大は、これまでウンパン村にとって無縁であったパラウィジャの作付けにあてられた。しかしそれと同時に、米の作付け面積も増大した。すなわち、パラウィジャの作付け面積は、短期間のうちに126ヘクタール(初年度)から506ヘクタール(完成年度)へと拡大し、それに連動するかたちで、米の作付け面積も、108ヘクタール(初年度)から197ヘクタール(完成年度)へと拡大した。 |
| 3) | 収量(1ヘクタール当たりの生産量)も着実に改善され、雨季の米の収量は、2.50トン(初年度)から4.50トン(完成年度)へと増大した。同様に、新たに乾季に栽培されるようになった大豆と落花生の収量も、0.55トン(初年度)から1.18トン(完成年度)へと倍増した。さらに、緑豆の収量も0.45トン(初年度)から0.90トン(完成年度)に増えた。作付け集約度(Cropping Intensity)も、灌漑施設の完成により、130%から266%に倍増した(表4-3-8)。 |
| 4) | 雨季における米の総生産量(籾ベース)は、270トン(初年度)から、833トン(完成年度)へと3倍の伸びを記録した。また、乾季における大豆と落花生の総生産量は、30トン(初年度)から234トン(完成年度)へと、10倍にも達する勢いとなった(表4-3-9)。 |
| 5) | 米の生産による年間純収入は、4,900万ルピア(1996年)、2億1,000万ルピア(1997年)、6億4,000万ルピア(1998年)と年を追うごとに増大した。同様に、大豆の生産による年間純収入も、2,400万ルピア(1996年)、1億5,000万ルピア(1997年)、5億7,000万ルピア(1998年)と飛躍的な増収を記録しており、米の生産による純収入に迫る勢いである(表4-3-10)。 |
表4-3-10 ウンパン地区作物別純収入
| (単位:千ルピア) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
d)水利組合Barora Tebalの状況
灌漑面積21ヘクタール、加盟者18の大きな水利組合Barora Tebalを視察した。この水利組合は、スンバワブサールからビマへ至る幹線道路沿いに立地しており、ポンプや配水管等の灌漑施設は特に問題はなかった。
われわれとの会合に出席した40名余の農民のプロジェクトに対する評価はきわめて高く、乾季の畑作物栽培が可能となったことにより、収入が増加し、子供の教育費や被服費に充当することができるようになったと強調した。とりわけ、乾季の灌漑農業による落花生栽培は高い収益をもたらした。それは灌漑農業の成果を農民にアピールする絶好のデモンストレーションとなった。ただ、落花生の価格は必ずしも安定しておらず、価格が暴落する場合もあり、落花生生産農家相互間の相互連携、必要に応じて作付け調整を行うこと、落花生の市況動向の把握が必要である。
こうした水利組合の今後の発展については、今年(1999年)より本格的に開始される水利用料金の徴収状況が鍵を握ると思われる。
(ヘ)ソンハジャ地下水灌漑プロジェクト(Song Gajah Groundwater Irrigation Project)
a)プロジェクトの概要
ソンハジャ地下水灌漑プロジェクトは、SSIMPIII(1998年~2002年)のスンバワ地下水灌漑拡張サブ・プロジェクト(Sumbawa Groundwater Irrigation Extension Sub-project) の一環として展開されるもので、火山台地を地下水灌漑により農地として蘇らそうとする試みである。ソンハジャ地区には現在200世帯、1,000人余が生活を営んでいるが、すべて他の島・地域からの移住者である。その内訳は、ジャワ島:40世帯(20%)、バリ島:50世帯(25%)、ロンボク島:40世帯(20%)、そして同じスンバワ島東部の中心都市ビマからの移住者:70世帯(35%)となっている。
プロジェクトの内容は、次のとおりである。
| 1) | 乾燥地に小規模な管井戸を4本設置する。 |
| 2) | それぞれの管井戸を通じて、10~15ヘクタールの土地に灌漑を行う。 |
| 3) | 総計48ヘクタールの乾燥地を乾季の可耕地へと転換させる。 |
b)プロジェクトのインパクト
火山の裾野に立地する無住の乾燥地であったソンハジャ地区は、本プロジェクトにより、生活居住空間へと変貌を遂げつつある。人口が稠密で、生計を維持するのに十分な農地を確保できなかったジャワ、バリ、ロンボク、そしてビマ等の農民はソンハジャ地区へと移住し、出身地ごとに棲み分け、一世帯当たり2.0ヘクタール(住居:0.5ヘクタール、農地:1.5ヘクタール)の土地を保有することができた。地下水灌漑施設の設置によって新たに400ヘクタールに及ぶ生活居住空間ができたのである。
われわれとの会合に出席した60名余の農民は貧しいながらも活気に満ちており、トマト、キャベツ、赤タマネギ、落花生、メイズ、胡椒、さらに間作物として米を栽培していた。現在不足しているものとして、農耕機具(ハンドトラクター、現在2台あり)、防虫スプレーをあげていた。
(ト)スミダム灌漑プロジェクト(Sumi Dam Irrigation Sub-Project)
a)プロジェクトの概要
スミダム灌漑プロジェクトは、SSIMPII(1995年~1998年)のサブ・プロジェクトとして建設されたもので、スンバワ島東部のビマ県に立地している。雨の少ないこの地域にダムを建設して、表流水を貯え、農業用水として活用することにより、乾季における畑作農耕を実現することを目的としている(この地域の年間降雨量は、1,400~1,500mmであり、絶対量としては決して少なくないが、そのほとんどが雨季に集中するため水を上手に蓄え、活用することが最大の課題であった)。
b)スミダムの建設(1998年完成)
スミダム灌漑プロジェクトの中核施設を構成するスミダムは、SSIMPで建設された4番目(スンバワ島では3番目)のダムで、ダムの形式は中央コア型ロックフィルダム、ダムの高さは45m 、ダムの体積は80万m3、有効貯水量1,700万m3である。建設に際しては予定地に地滑り地形がみつかり、急遽ダムサイトを3.5km上流に移動させた。
c)農民の移転
ダムサイトの上流への移動に伴い、ダム上流の川沿いにある水田や畑が水没することとなった。スミダム周辺には三つの村があったが、いずれも貯水池水面より高台にあり、農民の住居が水没することはなかった。水没する農地を保有する3カ村の農民(500世帯)の大多数は、生活の糧である農地が水没するのであれば、元の村に住む必然性はないとの理由から、新たな農地を求めて移転することになった。ここに至る過程で、県知事を通じて農民の移転に関する理解と協力が取り付けられた。移転先は、元の居住地から5~6km離れた無住の政府所有地で、インドネシア政府が土地(一戸当たり水田0.1ヘクタール、畑0.1ヘクタール、住宅用地250平方メートルを無償提供し、補償金(水田には1ヘクタール当たり300万ルピア、畑は250ルピア)の支払いを行った。移転した農民の住居は組立式であり、移転・建設された。移転した農民は、新たな移転先で水稲、トウモロコシ、マンゴ、バナナの栽培を行っている。なお、移転をしなかった一部の農民のために追加工事で農村へのアクセス道路が建設された。
d)灌漑
スミダムにより貯えられる表流水は、1次水路、2次水路、そして末端の3次水路を通じて、灌漑用水としてダム周辺の乾燥農地に供給される。灌漑の対象とされる地域の総面積は2,542ヘクタールである。
なお、参加型開発(農民のエンパワーメント)の考えに基づき、本灌漑プロジェクトにおいても、プロジェクトの初期計画段階から、農民の積極的なコミットメントの促進が図られている。それは具体的には、受益農民による水利組合の設立とSSIMP事務所によるキメ細かな営農指導を核とするものである。
e)維持管理と水利組合
スミダム灌漑プロジェクトは、ビマ県サペ郡に広がる乾燥農地2,542ヘクタールを対象としている。1次水路、2次水路はインドネシア政府による維持管理が行われ、3次水路に関しては農民参加型アプローチの観点から農民自身による灌漑施設の維持管理がいわれ、水利組合が結成されている。さらに水利組合には、農民のエンパワーメントという視点から、積極的な営農指導が行われている。水利組合の概要は、以下のとおりである。
| 1) | 23水利組合が結成され、加盟者総数は、3,570人に達している。灌漑面積は、エンパン地下水灌漑プロジェクトの10倍で、加盟者数も10倍となっている。その割りには、水利組合の数は少なく、1水利組合当たりの規模(灌漑面積と加盟者数)が大きいものとなっている。 |
| 2) | 灌漑総面積2,542ヘクタールに対して、水利組合が結成されている面積は2,297ヘクタールであり、灌漑面積の90%で水利組合が組織されている。 |
| 3) | 灌漑面積が最大の水利組合は、640ヘクタール(加盟者115人)。また、最小の水利組合は、33ヘクタール(加盟者85人)である。 |
| 4) | 水利組合は一括して、1999年1月に、県知事の署名・布告を受け、同年5月、郡裁判所の署名により登録を完了し、法的人格を付与されている。 |
| 5) | 水利組合には、それぞれ固有の名称が付けられている。また各水利組合には、組合長(head) 、書記(secretary)、収入役(treasurer) が選出されており、水利組合運営の任に当たっている。 |
f)プロジェクトのインパクト
1995年に開始され、1998年に完成したスミダム灌漑プロジェクトは、受益地域の農業形態に大きな変化をもたらしつつある。それは作付け形態の劇的な変化である。従来、この地域の農業は、雨季の天水稲作のみであり、乾季にはわずかに緑豆が栽培されるだけであった(米-パラウィジャ-休耕のパターン)。ところが、スミダム灌漑プロジェクトが完成し、灌漑農業の導入により、雨季の稲作の後で、乾季に二次作物の栽培を行うことが可能となった。こうして乾季にも、緑豆、大豆、メイズ等のパラウィジャの栽培が積極的に試みられるようになった(米-米/パラウィジャ-パラウィジャのパターン)。
とりわけ注目されるのが、インドネシア人の食生活から切り離すことのできない赤タマネギ(Bawan Merah) の栽培である。移動による損傷が少なく、保存性も高い赤タマネギは、商品価値が高く、収益性の大きい畑作物として、場合によっては、乾季に2~3回にわたって栽培されることも稀ではなくなった。その結果、この地域で収穫された赤タマネギが、周辺地域のマルク州やバリ州、さらには遠くジャワにまで移出され、農家にとって大きな現金収入源となっている(ただし、5,000~12,000ルピア/kgという価格変動の大きさに問題がある)。
このようなプロジェクトのインパクトを、スンバワブサールのSSIMP事務所の資料(1995年~1998年、3年間の実績)に依拠し、概観すると以下の諸点が指摘される。
| 1) | スミダム灌漑プロジェクトの対象範囲は、4年間で、1,300ヘクタール(初年度)から2,542ヘクタール(完成年度)へと拡大した。年間を通じての農地の有効利用(多毛作)を可能とし、当該地域の延べ可耕地面積(年間)は、1,704ヘクタール(初年度)から2,769ヘクタール(3年度)へと大きく増大した(表4-3-11)。 |
| 2) | 乾季における灌漑農業の導入は、米の作付け形態を大きく変化させた。すなわち、それまで事実上、雨季のみに限定されていた米の作付けが、乾季においても雨季に迫る規模で行われるようになった。1995年から1998年にかけて乾季における米の作付け実績をみると、1995年から1997年の2年間はわずかに14ヘクタール(各年)に過ぎなかったのが、1997年~1998年には実に748ヘクタールへと飛躍的な伸びを示している。スミダム灌漑プロジェクトは、これまで不毛の季節とされてきた乾季に、パラウィジャの栽培を可能とし、さらに米の作付け面積拡大をももたらした。 |
| 3) | 収量(1ヘクタール当たりの生産量)も着実に改善された。雨季および乾季における米の収量は、2.50トン(初年度)から4.50トン(3年度)へと増大した。同様に、乾季における緑豆の収量も、0.45トン(初年度)から0.9トン(3年度)へと2倍の伸びを示した。大豆の収量は、0.55トン(初年度)から1.1トン(3年度)へと着実な伸びを示した。作付け集約度も、灌漑施設の完成により、131%から150%へと着実に向上した(表4-3-12)。 |
| 4) | 雨季における米の総生産量(籾ベース)は、3,250トン(初年度)から、5,850トン(3年度)へと2倍に迫る勢いを示した。さらに、乾季における米の総生産量の伸びはきわめて顕著であり、35トン(初年度)から一挙に3,365トン(3年度)へと100倍近く伸びを記録した(表4-3-13)。 |
| 5) | 米の生産による年間純収入は、6億ルピア(1996年)、21億3,000万ルピア(1997年)、73億3,000万ルピア(1998年)と飛躍的な伸びを記録している。同様に、緑豆の生産による年間純収入も、3,000万ルピア(1996年)、3億8,400万ルピア(1997年)、2億6,000万ルピア(1998年)と顕著な伸びを示している(表4-3-14)。 |
表4-3-11 スミダム地区作付け面積の拡大
| (単位:ha) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表4-3-12 スミダム地区単位あたり収量
| (単位:トン/ha) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表4-3-13 スミダム地区総生産量
| (単位:トン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表4-3-14 スミダム地区作物別純収入
| (単位:千ルピア) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
g)Pamali水利組合の状況
スミダム灌漑プロジェクトは、SSIMPのプロジェクトのなかでも規模の大きなプロジェクトである。それは、灌漑面積の広さや水利組合への加盟者数の多さが示している。調査チームは、Pamali水利組合のメンバー約40名余と面談する機会をもった。同水利組合は、灌漑面積73ヘクタール、加盟者数107名と、スミダム灌漑プロジェクトにおいてはほぼ平均的な存在であり、そこでは次のような事項が提起されたが、他の水利組合にも共通する事項である。
| 1) | 灌漑農業により、乾季畑作が可能となり、所得、ひいては生活水準が向上した。特に収益率の高い赤タマネギの生産が可能となったことは大きな成果である。 |
| 2) | 収穫量を維持するために、赤タマネギの種子はフィリピンから輸入しており、コストがかかる。生産した赤タマネギは、商人(中国系)が一括して引き取っている。 |
| 3) | 商人は、労働者と輸送車両を伴って畑まで来て買い付けを行う。農民は、赤タマネギを収穫するために必要なナイフも十分に揃っていない。また、農民には、赤タマネギの市況(価格や需給状況等)に関する情報が欠如している(新聞もない)。その結果、農民は商人に対する駆け引き能力を欠いており、商人のペースで買い付けられている。 |
| 4) | 当面の課題として、ハンドトラクター、二輪車、それに籾擦り機が必要である。ただしそれらは非常に高価であり、クレジット制度へのアクセスが不可欠である(ハンドトラクターは12万円~20万円、二輪車は5万円)。 |
| 5) | 3次水路にはコンクリート製でないものもある。末端にまで水が届いていない場所もある。 |
今後、発足したばかりの水利組合が本格的に水利用料金の徴収に踏み切った場合、受益農民の反応が重要な問題となる。すなわち、今までタダであった表流水に対するコスト負担を住民がどれだけ違和感なく了解するかである。水利用料金徴収の成否は、水利組合の今後、SSIMPの基本的アプローチである参加型開発の将来を占う試金石となる。
(4)参加型開発アプローチが重要となる局面
参加型開発という点から着目すべき点について検討してみたい。プロジェクトの事例を踏まえると、土地収用、住民移転、灌漑の維持管理の負担(そのための水利組合の形成)といった場面は、受益者の利害に係わる部分であり、参加型視点が重要である。土地収用の検討に入る前に、土地制度そのものについてスンバワ島を中心に概観する。
(イ)土地制度
西ヌサトゥンガラ州も1970年代以降は開発が進みつつある。1970年代以来、森林の開発による土地問題が起きている。ロンボク島はバリの裏玄関として1980年代より観光開発が活発化し、土地の転用に伴う土地問題が発生している。スンバワ島にもしだいに開発の波が押し寄せている。土地に関する問題は、地方社会に緊張を醸成し、社会の安定を損ないかねない性格を持っている。慎重な配慮が必要である。2000年1月19日にロンボクで発生した暴動事件の背景の一つには、観光開発に伴う土地問題と社会の緊張が間接的にせよ影響している可能性は否定できない。
土地に関する売買や収用事業を難しくする背景には、慣習的な土地の権利や観念に関係する場合が少なくない。売買しているという土地の権利も現在の土地法(Undang-undang Pokok Agraria)上の所有権(hak milik)とは限らない。
スンバワでは土地に関する伝統慣習がかつて存在した。ダトゥ(Datu)あるいはデア(Dea)と呼ばれる称号を持つ上層の支配者が土地を持っていた。一般の庶民農民層タウサナ(tau sanak)も土地を所有できるが、その権利は王によって与えられ、王による制約を受けていた。また、ロンボクにも同様の慣習が存在し、かつてあった王権のもとでは土地の所有はプルムナッ(permenak)と呼ばれる上層階級に集中していた。とはいえ実際の耕作、土地利用はジャジャルカラン(jajar karang)、あるいはカウラ(kaula)と呼ばれる隷属農民によって行われていた。彼らは土地を所有せず、分益小作(nyakap)や定額小作(meleisin)を行っていた。
スンバワにおいて今なお生きている慣習法(hukum adat)は、土地を見出し、利用管理するものが土地所有者であるというものである。この慣習法は王権によって次のように制限されていた。
王に召喚されれば出頭せねばならぬ。
王に命じられれば直ちに退去せねばならぬ。
王に授けられれば拝受せねばならぬ。
王に求められれば返却せねばならぬ。
土地を獲得するために一般庶民は王にとって有用な大いなる行いと貢献をなして忠誠を示さねばならない。土地を所有する民の権利はそこから得られる成果が必要十分を満たす程度までにとどまり、それ以上は王のものであるとの観念がスンバワの諺にも示されている。(Tim Studi KPA Wilayah NTB “Kondisi dan Permasalahan Agraria di Nusatenggara Barat,” In Dianto Bachriadi; Erpan Faryadi; and Bonnie Setiawan eds, Reformasi Agraia, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universita Indonesia, 1997, pp.258-259.)
以上のような土地制度は独立後も基本的に存続していた。1950年代まではかつての支配層が大地主であった。このような支配層によって支配された土地において、かつての農民であるタウサナッが耕作者や分益小作人あるいは農業労働者となり今日に至っている。このような土地の占有関係のために私的所有権が必ずしも明確でないことが多い。さらに以下のようなスンバワの歴史が土地に関する慣習的権利を複雑にしている。
1815年のタンボラ山の大爆発は1万人とも推定される多数の死者をだし、島外に人々は移住して去った。島の西部、現在のスンバワ県ではその影響が特に大きく、人々の再入植が生じるのは19世紀後半以降といわれる。しかし島に流入した人の多くはかつての住民ではなくジャワ、マカッサル、ブギス、ササッなどの人々であった。このことがとりわけ海岸地域をいわば移民社会にしている。土地に関する慣習法もいずれの移民の人々の慣習によるのか、あるいは古来からのスンバワの慣習によるのかあいまいにならざるを得ない状況がある。こういった制度上のあいまいさが、発生した土地問題の解決を難しくすることが推察される。農民同士、住民同士の利害の衝突を調整する共通のルールが成り立っていない場合があり得るからだ。
土地の耕作者が慣習的に権利を認められてきたのが実情だが、その権利を所定の手続きを経て土地法上の所有権として登記してあれば問題はあまりない。政府は80年代以降プロナ(Prona)と称される所有権の登記事業を推進してきた。慣習的権利を土地法上の所有権ないし他の土地権利に転換(konversi)してこれを登記させたのである。このプロナが行われた地域では、土地収用をはじめとする権利関係の調整は比較的順調にいったようである。
南スラウェシのサロメッコプロジェクトの場合、事業が行われるずっと以前の1982年にプロナ(Prona)と称される土地登記プロジェクトが行われていた。そのおかげで、収用対象地の地権者の確定等が比較的容易に進んだといわれる。スンバワでも、たとえばプララ堰プロジェクトの地域ではプロナが以前に行われていた。
しかし、土地に関する古い慣習法は住民の観念の世界には依然として残っており、無主地の利用はおおむね慣習法に従っているようである。山間地での焼畑耕作はその事例といえよう。村の住民や村役人たちは、政府、たとえば公共事業省や県の役人がいる前で、村に焼畑(tanah berpindah-pindah)地域があるとはいわない。政府の立場から、焼畑は国有林内での違法耕作と多くの場合みなされるからである。水資源の保全と土壌流出防止のために、国有の急傾斜の山間地での焼畑耕作を政府は禁止している。しかし、スンバワでは焼畑耕作が山の上まで這い上がり、煙があがっている光景がしばしば見られる。
(ロ)土地収用と地価評価
プロジェクトの準備段階は、住民の合意形成と積極的な参加をあおぎ、住民の意識変化をうながし、必要に応じて新たなルールや組織を作るといった社会化の観点から特に重要である。こういった課題の事例として土地収用とその際の地価等の評価問題があげられる。
収用は土地、家屋およびその他の建物、立木が対象となる。受益者参加、農民参加を支援するNGOは、土地収用(pembebasan tanah)においても重要な役割を果している。NGOの役割は、まず住民への情報提供と理解を得ることである。しかし、これはやりようによっては、実質的にはプロジェクトに同意させるための説得に過ぎなくなる。NGOもコンサルタントに過ぎないとの批判がしばしば聴かれるが、NGOの本質を理解するうえで重要な活動事例といえそうである。住民・農民の積極的な関与を呼びかけ、住民・農民自らのイニシアティブでプロジェクトに対応しようとする動きをうながす過程がソーシャリサシ(sosialisasi)である。
土地収用の過程で次に行うのはインベントリー調査である。土地所有者と耕作者を確定し、土地に関する権利と位置と面積を明らかにする作業を農民とともに行う。ダム建設による水没地、アクセス道路用地、水路用地などが収用の対象となる。収用に反対する者には賛同を得るための情報を提供し、プロジェクトと住民との話し合いをセットするなどの支援活動をNGOが行っている。出稼ぎ、転職等により不在の土地権利者も少なくないが、そのような者が土地収用に反対する場合、最終的に村長や郡長らによる交渉と説得が行われた。水利組合の形成や運営においては、耕作者が組合メンバーであるから、不在地主の存在は特に問題ではないが、土地収用では私的所有権の抹消が必要であるから、ジャカルタなどに転出している者でも、地権者であれば同意を得るための交渉が不可欠であった。当初は収用に反対した人でも、プロジェクトの意義そのものに反対する者はなく、多くは地価交渉で納得がいかず、そもそも収用単価については交渉の余地がないことを問題にするケースが多かったようである。
収用価格は市場価格ではなく、県土地収用委員会の答申に基づいて県知事が決定する。市場価格で収用を行える財政的裏づけが全くないのが現実だ。公定の収用単価を基礎価格(harga dasar)と呼ぶ。プララ堰灌漑プロジェクトのLunyuk Ode村の事例では、収用地の価格は1m2当たり350ルピアに過ぎなかった。これは約20年前、1980年頃のアサハンプロジェクト(水力発電所とアルミ精錬所建設プロジェクト)が行われたスマトラの土地収用基礎価格とほとんど変わっていない。サロメッコ地域では、土地によって収用価格に差があるが、平均するとヘクタール当たり100ルピアであったという。95年頃のことだが、当時水田1m2当たりの地価は収用単価の5倍500ルピアであった。99年時点の市場地価は実にその10倍5,000ルピアになっている。このような大きな差からみて、住民たちが市場価格での土地収用を望むのは当然といえよう。
収用価格決定をはじめとして、従来からの収用事業の形式と方法が、基本的に変わることなく踏襲されている。収用のための基礎価格は市場価格に比して大幅に低いのが現状で、価格の決定に住民の声が直接反映される制度にはなっていない。ここに住民・農民の不満が集中する。既定の方針どおりに収用が進められて住民の意見を反映せず、変更・修正が何もなされない場合、受益者といえども強いられているとの印象は拭えぬものがあろう。仮に参加型を謳ったとしても、参加の実体が伴っているとは言い難い。今後の収用価格のあり方には十分注意が必要である。
「開発」という大義名分のもとに土地の収用は行われてきた。農民や住民は政府の示した収用価格に結局は同意してきた。同意したとはいえ、市場価格での買取りを希望する住民は少なくない。いずれはこのような無理な価格での収用は不可能となるに違いない。プロジェクトの受益者であるから、地価は公定で低くてよいという理屈は、将来的には通らなくなるであろう。社会化や住民参加の名のもとに、公定の基礎価格を住民に押し付けることは望ましくはない。
(ハ)住民移転
住民移転に伴う問題も影響は大きい。スンバワ島ビマ県のスミダム建設に伴い、約500世帯の住民移転が必要となった。当初、ダムはより下流域に造られる予定であったが、当初、建設予定地に地滑り地形がみつかり上流に建設され、農地が水没する農家の移転が必要となった。
住民移転のために支払われた補償金は、水田には1m2当たり300ルピア、すなわちヘクタール当たり300万ルピアであった。畑は250ルピア、林地は住民所有でないという原則のもとに支払われなかった。移転費用は中央政府からのプロジェクト予算による。他方、移転地の手当ては地元県政府の責任とされる。より上流部の移転地に用意された土地は一戸当たり水田0.1ヘクタール、畑0.1ヘクタール、住宅用地250m2であった。他に小学校2校、中学校1校、村役場、保健所、簡易水道施設等が提供された。地元ビマ県の平均的な農地所有面積は狭く0.3ヘクタールといわれるが、それよりも狭いものであった。
移転地付近の山々の多くはすでに禿山で、中腹まで焼畑耕作地があがっていた。山の傾斜地の焼畑耕作は土壌の侵食をうながし、下流のダムや堰にとっては悪影響を及ぼすが、これらを防止する短期的な方策は難しい。移転地での農村工業の育成等、土地によらない経済活動を助成し、同時に道路、交通手段の整備等の格別な支援が必要である。このような課題はプロジェクトの責任外かもしれないが、重要なのは、改善の要望が住民自らの間にあがり、これを聞く窓口が行政の側にあるかということである。ここでもNGOは重要な仲介あるいは触媒の役割を果たし得ると思われる。
(ニ)水利組織の形成と運営
住民の参加を制度的に支えるのが、水利組織の形成でありその運営である。SSIMPプロジェクトでは、この活動はNGOの協力を得て順調であったといえる。ただ、今後の維持管理に必要な水利組合費の徴収率は良いとはいえず、将来に課題を残している。
プロジェクトの活動の中で、水利組織同士の境界を確定し、村の中のどのような単位で水利組織を形成し、あるいは分割するかといった点をNGOは調査する。水利上の境界、行政的な村の境界、住民の社会文化的な境界を明らかにすることから始まる。スンバワではバリやロンボク、ジャワあるいはスラウェシなどからの移住者もいるなど、宗教・社会文化的には複雑であり、この点に特に注意が必要とされる。現在は末端水路の維持管理のために、すでに水利組合(P3A)が組織されている。維持管理費用として水利費(IPAIR: Iuran Pelayanaan Irigasi)が組合員から徴収されている。これは従来、政府の収入とされてきたが、今では水利組合が独自財源として直接利用できるように変わっている。オーナシップを持たせるうえでも好ましい方向がでているといえる。
さらにいくつかの水利組合が連合した水利組合連合(Gabungan P3A)の形成も検討されている。これは、幹線水路の維持管理をも水利組合に移管することが意図されているためである。維持管理を大幅に受益者に移管するには、数十人単位のP3Aではその任に堪えないことは明らかで、人的にも資金的にも連合化し、規模を大きくする必要があるからだ。幹線水路の維持管理権を水利組合連合に移管することは、さらに多くの責任と費用負担を農民に移転することを意味する。そして維持費用として水利費の徴収がさらに重要な課題となってくる。法制度の検討が行われているが、このような負担増を農民が納得したうえで同意するか、SSIMPの諸プロジェクトはその実験場としての意義をもっている。
同時に、水利組合を越えて農民の経済活動全般を視野に入れた組織化が今進められようとしている。1998年にはいるといくつかの地域では水利組合を母体とした協同組合を立ち上げた。この協同組合は従来からある官制の農村協同組合(KUD)とは異なり、農民たち自身のものであるとの意識が強いように見受けられる。さらに水利組合連合の結成に対応して連合協同組合(Koperasi Gabungan P3A)を結成しようとの動きもある。こういった動きの中で、NGOは行政と農民との間に立っていわば触媒としての重要な活動を行っている。
NGOは営農指導も行っている。たとえば、作付けパターンを定め、水利用のために農民間の調整を行う。また肥料、農薬その他の購入に必要な農業・農村金融への接近を容易にするように支援している。耕作シーズンごとに普及員と農民は営農計画を立てて、営農に必要な投入財の準備、そのためのクレジットの申請手続きを行わなければならないが、これはRDKK(Rencan Daftar Kebutuhan Kerja)と呼ばれ、NGOは普及員と農民との間に立ってこのRDKKの作成を支援する。
(5)参加型開発アプローチへの教訓と課題
(イ) 受益者の「参加」化の条件
従来の行政の枠組みの中で住民・農民参加が全くなかったわけではなく、たとえばインフォーマルリーダーの動員などの方法で住民の間接的参加をあおぐといった方法はとられてきた。従来の方法を動員方式と呼ぶとしても、その中に住民参加が全くなかったわけではないのである。問題は、住民・農民の利害を代表して行政とわたりあえる組織や機構がスハルト体制下では弱かった点である。「開発」の大義名分の下に、発生する責任や損失の多くが住民・農民に押し付けられる可能性が少なくなかった。特に土地収用や住民移転を伴うとき、あるいは水路の補修等の維持管理において、その責任と負担を行政サイドから強制されるなどの場合である。
政府職員の不正や怠慢があってもこれを制裁する具体的な手段はほとんどないに等しい。行政が何をどう行っているか、そのアカウンタビリティが高ければ、あるいは農民サイドに立ったモニタリングがあれば、そのような不備からくる危険は大幅に減じられるはずだ。
NGOの介在と活動は、触媒として機能しており、行政と住民・農民との間にあって彼らを助けて行政とわたりあい、あるいは行政をモニタリングし、このことを通じて行政側がアカウンタビリティを高めることが期待できよう。しかしこのような活動は本来なら事業の受益者が自ら組織化し活動することが望ましい。外部のリソースであるNGOに依存しつづけることは望ましい姿とはいえまい。住民・農民による中間的組織の発展強化が重要であり、水利組合が自ら担うべきである。
利害関係が発生したとき、自らが利害を調整し、問題を解決しようと関心と努力を結集することができるかどうかが、水利組合の永続性と農民の参加を保障する鍵であろう。日本の歴史的経験では、水利組合は村単位の組織であり、村と村あるいは地域と地域との間に発生する水を巡る緊張関係の中に成立し展開したものである。一定の社会的緊張があってこそ組織は強化される。日本の水利組合の形成過程では、村落間の緊張関係が背景にあった。そこでは個人や世帯ではなく、村が構成員であるという村落連合としての性格が強かった。
これまでの稲作アジアの水利開発では、農地の末端まで政府が建設と管理を行う例が支配的であるとされてきた。しかし日本では、江戸時代の中期頃になると、江戸や城下町の周辺では資力を蓄えた上層農民や町人層などが出資する「百姓寄合新田」や「町人寄合新田」が盛行した。江戸後期には特に、末端の農地の水利開発や統制を村落の共同体や地主層が掌握していった。
今日なおインドネシアの貧困地域の農民の多くは、生計の確保に日々追われている。日本のような歴史的な経験が少なく、経済的なインセンティブが十分に働かないところで、農民による参加型の、あるいは自主的な水利の維持管理が持続的に行えるかどうか、疑問が残る。たとえば、米価の変動等により農民が経済的不利益をこうむれば、水利組合費の徴収は影響を受ける。SSIMPをはじめとして公共事業省は水利組合の連合組織(FederasiまたはGabungan)を作らせようとしている。しかし、村落間の利害調整を必須とする状況に至っているようにはみえない。内発的な動機が必ずしも熟成されていないのが現状である。このように契機が熟していない、つまり利害の対立が明確に意識されないところでは、農民の参加や組織化・強化の条件もないのではあるまいか。利害の対立は、あるとすれば農民と行政との間にある。村落連合組織としての水利組合連合(Gabungan P3A)がインドネシアの水田農村地域で広く一般的に形成されるか、されたとしても永続的な組織機構として定着するかは今後とも検証課題といえる。
利害の対立が行政と住民・農民との間で発生するような過程では、住民・農民の組織化が彼らの自主的な動きとして発生するよりも先に、組織化と動員、つまりは行政による抱き込みによって機先を制せられてしまうことがある。こうして住民・農民と行政、あるいはそのエージェントであるコントラクターやコンサルタントとの間で問題が発現する場合、むしろ問題がないものとして扱われたり無視される可能性がある。意図的であるにせよないにせよ、問題が結果的に隠蔽されてしまうことがあり得る。このような場合、住民・農民の自立的な組織化の展開の芽はつまれてしまう。問題の訴えどころを失って悪くすれば、社会化、政治化の過程を飛び越えて暴力化する危険さえある。住民や農民の組織ができても利害調整のメカニズムが住民・農民同士や行政との間で作動しないとなれば、本質は従来の動員型開発とさして変わらない。そうであれば、現在組織化が進みつつある水利組合P3Aも単なる行政文書上の水利組合に堕しかねない。
(ロ)地方分権とグッドガバナンスへの動き
インドネシアの土地制度では、土地法と慣習的法上の土地権利との間で混乱を生じやすい。また河川法の整備が進んでおらず、慣行的水利権の有無やその実態の調査も不十分で、水資源の利用を進める際に、そういった資源を利用する住民や農民の存在が無視されかねない。
今のインドネシアが直面している問題は、開発手法としての「参加」の問題を超えるものがある。統治の良し悪しという体制のあり方全体にかかわる問題なのである。統治制度が不完全であることを前提とした対応が必要といえそうだ。このような条件下で援助を行うとすれば、制度や行政機構の改善にまで踏み込まざるを得ないことが多々ありうる。参加型はこのような点で一歩踏み込んだ方式といえる。住民・農民らプロジェクトの受益者・費用負担者の声を通じて制度や行政の不備を発見し修正する余地がある。現在推進されつつある分権化の施策の中では、参加を促進する制度改革が一定程度実現されようとしている。地方分権化においては従来の州に替わり、県が重要な役割を担うことになっている。政府は分裂の危険を避けつつ地方分権を進める方法として、分権の単位を県にまで落とし、そこにオートノミーを与えようとしているように見受けられる。
県知事は県議会に対する責任が明確化され、議会の反対によって県知事は罷免もありうることとなった。住民に対するアカウンタビリティ、対住民責任は大幅に改善されるであろう。今までになかった対抗的チャンネルが築かれようとしているのである。このような制度的枠組みの変更を実あるものにする意味でも、「参加」型開発はインドネシアにおいて極めて重要な位置にあるといわざるを得ない。
(ハ)問題の所在の明確化
土地収用、住民移転といったプロジェクトの準備、農民組織の形成、水利費負担等による日常的な維持管理活動の中において、住民・農民たちは少なからぬ負担を様々な形態で担ってきた。問題が表面化しないまでも、いくばくかの社会的緊張が発生することは間違いない。このような利害を巡る緊張関係とその的確な処理にこそ、「参加」を求める実質があると考えられる。それゆえ住民・農民らの努力、費用や責任の分担に対する慎重な配慮と正当な評価が重要である。
しかし現実は、住民・農民の努力の評価が十分といえない。受益者である農民たちが土地収用をはじめとしてこれらを首尾よくやれば、全く問題なく農民の理解と協力が得られたとしか記録には残らないことが多い。だが、内部的に生じているであろう問題を認知しなければ、ソーシャリゼーションや住民参加の過程を正しく捉らえることはできない。プロジェクトの実施責任者は、センシィティブで厄介な問題を記録にとどめ、プロジェクトの実施過程をトランスペアレントにしておくことが、今後同種のプロジェクトを実施する参考となる。
(ニ)NGOの役割と援助の戦略性
インドネシアでは各地で土地をはじめとして慣習的な権利の観念が生きている。このような観念を共有するものが利害を代表して、プロジェクトを実施する行政との交渉にあたるのであれば、住民・農民から信頼されるだろう。彼らがプロジェクトの準備段階から参加すれば、住民・農民のプロジェクトに対する理解や協力を得やすくするであろう。NGOはこのような仲介者、触媒の役割として重要である。
参加型開発の問題点と特質を整理すると、第1には、何をどこから手をつけるかというプライオリティと戦略性の問題である。インプットとアウトプットの関係だけをみてきた従来の援助・開発の方法に対して開発の過程、すなわちスループットに着目した点は優れた進歩といえる。だが、開発のプロセスの全般にわたってモニターし、関与することが援助の方法として適当であるか、ということになればこれは問題である。社会づくりの全体を限りなく援助し続けるわけにはいかないであろう。
効果的な住民・農民参加の方法があるはずだが、参加型開発においても、提供できるサービスの質と量の間にはトレードオフの関係があろう。また、行われてしかるべきであるにもかかわらず、不十分だった点を行政ではなくNGOが補完しているに過ぎない、といった問題もある。しかもNGOに支援された「参加」からの「卒業」がなくてはならないはずである。社会づくりを援助はどこまで支援できるか、見通しと限定が必要と思われる。さもなければ、参加型開発とはNGOをはじめとする外部の資源による社会づくりそのものとなってしまう。援助の一環として行われるとすれば、対象となる地域や住民の社会の全体を構築することを目指すものではないだろう。援助の限定と戦略性をどう考えるかという課題がここにある。
第2に、対象となる社会の初期条件がいかなるものか、対象となるコミュニティのアイデンティフィケーションを誰がどう行うかという問題がある。これが綿密に行われないと受益者の特定や彼らの便益費用を正しく把握できない。たとえば土地制度と住民の経済組織のありようは、開発の対象となる社会を性格付けるうえで重要な制度的基礎である。そこに生きる伝統的な経済取引の制度と慣行を無視した人々の、開発への動員(mobilization)は社会的混乱を招くどころか社会そのものを崩壊させかねない。灌漑プロジェクトの実施担当者は、技術畑の人間が中心であって、プロジェクト実施上の技術的問題として住民・農民社会の問題を捉える傾向があるように思われる。それは一つの見識であるかもしれないが、大事な点が看過されがちである。それは結果的に問題の疎遠化や隠蔽となってしまう。ここでは、第三者的立場の組織や人が介在する必要性と意義が高いと思われる。SSIMPの事例は、NGOの参加がこのような弊害を防ぐうえで有効な手法であることを示唆している。
(ホ)地域開発の視点
農業生産が活発化すれば、その生産物の販路の開拓、投入資機材の調達が重要度を大幅に増す。したがって、農業開発、灌漑開発においては、農民のみならず商人、とりわけ農村地域内部に生活と経済活動の基盤を置く半農半商的な商人を含めて考える必要がある。
地域資源としては、水、土壌、森などの自然的資源をはじめとして、ローカルな企業家や商工者など人的資源、ローカルな金融、環境等がある。これら地域資源は地域経済において密接に連関し合って均衡している。農業・灌漑開発の過程では、これらの間の均衡が崩れないよう慎重な配慮が必要である。商人や流通を含めて地域経済を一体として捉える視点が不可欠である。
(ヘ)参加型開発アプローチの課題
参加型開発において重要なのは、対象となる受益者社会の特質を的確に把握することである。さらに経済行動の特徴を明らかにすることである。これらに関する方法的議論は必ずしも十分に行われていない。
灌漑対象面積、反収の増加、生産費構造、作付けパターンの変化等の情報は多いが、これらはいずれもいうなればエンジニアリングデータであって、住民・農民参加を検討するための社会経済データとしては不十分である。SSIMPプロジェクトはエンジニアリング的情報に関してはよく収集分析されている。今般の調査でもプロジェクトの成果に関する諸々の情報は得られた。
しかし、所有や経営規模の分布構造、農家の労働力賦存と労働投入の実際の変化、平均生産量、生産費等も規模別のデータは得られなかった。よくいわれるようにプロジェクトの便益は等しく受益者に均霑されるとは限らない。プロジェクトの効果は農家の経営規模や労働力の賦存によって異なると思われる。水利費支払いや労働など役務提供の農家における負担の程度も、経営規模や家族労働の賦存によって異なるはずである。戸別、規模別に農業経営の実態を明らかにできる、サンプリング調査などによるデータは十分収集されていないようである。社会経済構造を踏まえて経済的利害得失を推計することは、参加の条件を検討し、問題の所在やその要因を探るうえで基礎的な作業である。
本プロジェクトは、一つ一つの事業は小規模であるとはいえ、6州、26件にわたる事業の集合体である。NGOが農民・住民と行政府の仲介者・触媒として機能することで参加促進の鍵となってきた。こうしたプロセスで注目すべき点は、コンサルタントによるこのプロセスの体系化、組織化努力がもうひとつの鍵となっていることである。

