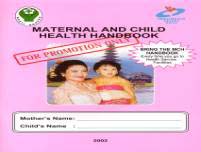添付資料2 視察案件
| 案件名: | ビリビリ灌漑(有償資金協力) | ||
| 実施期間: | 1996年~2005年(予定) | ||
| 対象地域: | 南スラウェシ州マカッサル(ジェネベラン川下流) | ||
| 案件概要: 本事業実施地域は土壌が灌漑に適する土地が多いとされるスラウェシ島、南スラウェシ州に位置している。円借款により、ビリビリ多目的ダム事業も実施されており、ジェネベラン川上流に多目的ダム建設により開発された水資源を有効に活用して灌漑事業を推進することにより多目的ダム事業の事業効果発現に有効である。 借款資金(5,472百万円)は、下流の(マカッサル地区の)農地24,600haを整備するための、灌漑水路建設・リハビリ等の費用に充当される。 多目的ダム建設事業に加え、ジャネベラン川の下流、流域面積60.5km2を洪水被害から守るために、河川改修工事、マカッサル市内の排水系統の改良を行う「ジェネベラン川緊急治水事業」も実施されている(1993年12月に貸付完了)。
考察: 洪水被害抑止、電力供給、上水供給、灌漑用水供給という4つの目的を持って実施されたビリビリ多目的ダム事業は1994年に借款契約が結ばれた。灌漑用水については、取水堰建設、水路リハビリが実施されている。ダムの建設により灌漑地域における浸水被害が解消され、農業生産へのダメージがなくなった。水路については2次水路までの円借款事業で整備し、3次、4次水路については住民が参加して整備が行われつつある。現地NGOが施工監理コンサルタントからの委託により工事事務所、コンサルタントと地元農民との仲介機能を果たした。農家調査、農民への事業の説明、農民による水利組合の設立、農民の意向をコンサルタントに伝え、設計に反映し、水路用地確保の合意形成をNGOが担った。こうした現地NGOの関与が農民により水路建設への参加、円滑な用地確保につながったものと考えられる。今後のインドネシアの開発プロジェクト運営に対しての教訓となると思われる。 | |||
| 案件名: | 母と子の健康手帳プロジェクト(技術協力) | ||
| 実施期間: | 1998年~2003年 | ||
| 対象地域: | 西スマトラ州および北スラウェシ州、準重点州としてブンクル州、東ジャワ州、ジョグジャカルタ特別州、南スラウェシ州、西ヌサテンガラ州(プロジェクト事務所はジャカルタ保健・福祉省内) | ||
|
案件概要: インドネシアでは妊産婦死亡率(425/ 10万出生 1993年)、乳児死亡率(47/1,000出生 1995年)が他のASEAN諸国に比べても高い。母子保健サービスの充実は第6次5ヵ年計画(REPLITA IV)においても重点項目である。 我が国は1989年11月から5年間にわたり「家族計画・母子保健プロジェクト」を実施し、中部ジャワ州をモデル地区として、乳幼児・妊産婦の保健衛生の質の向上と、それを支援するサービス・デリバリーの強化を図った。同プロジェクトで開発され、試行が開始された母子健康手帳は母子保健個別専門家(1995年5月より1997年8月まで)に引き継がれ、フォローアップと最終評価調査を経て、母子健康手帳が母親と子供への健康教育教材および保健サービスの手段として有効であることが確認された。その成果を受け、母子保健手帳プログラムをコンポーネントとした母子保健サービス改善を目的とした技術協力プロジェクトが要請された。 プロジェクト対象州における母子保健状況が改善されることを上位目標とし、プロジェクト目標は全国版母子保健手帳の導入を通じ、地域保健サービスが改善され、地域において母親が子供たちと母親自身のために、より健康的な生活を営むことである。
考察: 上記のとおり2州をプロジェクト対象州、その後6州を準重点州として支援を行ってきた。現在ではインドネシア31州のうち、25州で母子保健手帳が発行されるなど、プロジェクト対象州以外でも母子保健手帳サービスが普及している。手帳印刷費用の一部は州政府、県・市の予算で負担されている。2002年には東ジャワ州では総印刷数、199,152冊のうち、56%が州政府によって印刷されている(平均するとインドネシア側による印刷は20%程度)。 母子保健手帳活動が広域にわたって実行された要因は、1)インドネシア保健省の上層部に強い政治的コミットメント、熱意、オーナーシップが存在した、2)インドネシア側の中核となるカウンターパートに移動がなかった、3)上記2点もあり、母子保健手帳が保健省のプログラムとして認知された、4)日本側が中部ジャワ家族計画母子保健プロジェクト、個別専門家、本プロジェクトと10年以上にわたって継続的な支援を行ってきた、5)他のドナー、NGOとの連携を重視した、6)16州で母子保健手帳の表紙写真が各民族を代表する母子あるいは両親と子となっており、文化的多様性に対する配慮をした等が考えられる。 | |||
| 案件名: | 電気系ポリテクニック教員養成計画 | ||
| 実施期間: | 1999年~2004年 | ||
| 対象地域: | 東ジャワ州スラバヤ | ||
| 案件概要: 本スラバヤ工科大学に隣接するキャンパスに、1986年に無償資金協力(18億9,500万円)でスラバヤ電気工学ポリテクニックを設立した。1987年から7年間、プロジェクト方式技術協力(現技術協力プロジェクト)「スラバヤ電子工学ポリテクニック」を実施した。同ポリテクニックは電子工学と通信工学の2学科、定員360名、3年制ポリテクニック(日本で言えば短期大学相当)として発足し、国公立工業高等専門学校協会が中心となって専門家が派遣された。 教育省が、電気、機械、土木の3系統においては全国で各1校ずつポリテクニック教員養成のための人材育成校を選定し、電気分野についてはスラバヤ電子工学ポリテクニックを選定し、既存の技術者養成過程(D3)を土台に電子工学、電気工学、通信工学の3分野について新たに教員養成課程(D4)(大学卒相当)を設置することを決定した。併せて産業界のニーズが高い情報工学分野の中堅技術者育成のため、情報工学分野の技術者養成過程(D3)も新たに同校に設置することとなった。1999年10月より2004年9月を協力期間として技術協力プロジェクト「電気系ポリテクニック教員養成計画」が始められた。
考察: スラバヤ電気工学ポリテクニックの主な特色は下記のとおりである。 (1)教員の熱意: ポリテクニックの校長、副校長、教員のほとんどがスラバヤ工科大学(ITS)出身である。ポリテクニック創成期には教員は20歳台から30歳台前半と若く、彼らが安い給料で自分の家であるかのようにポリテクニックをみなし、情熱を持って指導を行った。 (2)就職斡旋制度: 専門家とカウンターパートはプロジェクトの初期の段階から卒業生の就職候補先の企業や政府機関を訪問した。現在は約20社が本ポリテクニックで採用試験を行っている。ルールを決めて毎年この方式を行うことにより、就職斡旋制度は多くの企業に認知されるようになった。 (3)機材保守管理制度: ポリテクニック教育では非常に多くの教育機材を日常的に使う。故障した輸入品の電子計測機器などは代理店がないためスラバヤで修理することが出来ず、故障した機材の山が出来ることが心配された。そこで教育用機材を可能な限りポリテクニック内で保守管理できる体制を作った。電子部品などを管理するスペアパーツセンターおよび修理のための部屋を作り、短期専門家により指導が行われた。他のポリテクニックも機材の保守管理について強い問題意識を持っており、本ポリテクニックのメインテナンスセンターがモデルとなっている。 | |||
| 案件名: | 地域開発政策支援、地方行政人材育成 | ||
| 実施期間: | 2001~2004年(地域開発政策支援)、2002~2005年(地方行政人材育成) | ||
| 対象地域: | 北スマトラ州メダン、南スラウェシ州マカッサル | ||
| 案件概要:
2001年1月から施行された地方分権化に伴い、地方行政、地方開発を担う人材の育成が課題となった。「地域開発政策支援」ならびに「地方行政能力向上」の2つのプロジェクトからなる「地方行政能力向上」プログラムが実施されている。ジャカルタの内務省にプログラム事務局が設置されている。プログラムの全体調整はマカッサルでは南スラウェシ州のBAPPEDAをカウンターパートとしている。スラウェシ島5州にて県知事・市長、州開発企画局の職員を対象にセミナー・ワークショップを実施している。その内容は予算作成・事業計画の作成の仕方が中心である。セミナーでは日本の事例の紹介も行っている。講師として日本留学経験者の多い南スラウェシ州にあるハサヌディン大学から招くことも多い。 参加型地域開発を目指している。参加型開発で目標とするところは、従来の富める人がさらに豊かになるという開発ではなく、小規模灌漑や道路など、住民の身近なところにある開発事業を実施しようというものである。これは以前、各ドナー間の方針の違いがコミュニティに混乱をもたらしたことへの反省もある。 地方行政人材育成プロジェクトは北スマトラ州のメダン、南スラウェシ州のマカッサルをモデルサイトとして、州・県の職員の能力向上につながる研修を実施するもの。マカッサルでは南スラウェシ州人材育成局をカウンターパートとしている。研修の内容は、日本の自治制度の紹介、開発計画の作成等である。 南スラウェシ州では日本の地方自治制度を学びたいというニーズが高い。昨年は南スラウェシ州の州議員を10名、州職員を10名、州の予算で日本での研修に派遣した。2003年は州の職員を4名、州の予算で日本に派遣する予定である。
考察: 地方分権化がスタートした2001年の段階では南スラウェシ州の職員、とくに一般の職員にとっては自分のことではないという認識だったが、2003年になってようやく地方分権に対する意識が高まってきたとのこと。他のドナーは州ではなく、いくつかの県をモデル県として地域開発プロジェクトを実施している。我が国では州と県の両方を関与させていくことが、各県の優れた事例・取組みを他県に普及させやすく、また、州だけで開発計画を作成していては県で計画をいいものに改善しようというイニシアティブがなくなってしまうと考えている。 地域のリソース(人材・制度)を活用した開発計画づくりというアプローチは、地方政府の人材育成に対しても効果的であるように見受けられた。 | |||
| 案件名: | 国立公園森林火災跡地回復計画(無償資金協力) | ||
| 実施期間: | 1999年~2004年 | ||
| 対象地域: | ランポン州ワイカンバス国立公園 | ||
| 案件概要:
インドネシアは世界屈指の熱帯林保有国であり、種の多様性が高く、多くの貴重動植物が生息し、全国に34ヵ所の国立公園が指定されている。しかしながら、同国では度々異常乾燥による森林・農地等における大規模な火災が発生し、貴重な動植物にも多大な影響を及ぼしている。特に1997~1998年に発生した大規模な森林火災は、マレーシア、シンガポール等の周辺国への煙霧害に加え、自然環境保護や地球温暖化等、地球規模の環境問題として国際社会の注目を集めた。 スマトラ島のワイカンバス国立公園においても、公園面積13万haのうち8,500 haが森林火災の被害を受け草地化し、森林の自然回復には数十~数百年が必要と言われている。国立公園の生物多様性を維持し、絶滅の危機に瀕している種や原生生態系保全のためにも在来種による早期の人工的な森林復旧が求められている。 このような状況の下、インドネシア政府はワイカンバス国立公園の自然植生を回復するため、日本政府に本案件を要請してきたものである。本案件はワイカンバス国立公園の森林火災被害地のうち約360 haを対象に植林を行うものである。
考察: 1997~1998年に発生したスマトラ島・カリマンタン島を中心とした大規模森林火災は周辺国にも影響を及ぼすほどの大きな問題となり、1999年7月の第8回CGIにおいて初めて森林問題が大きく取り上げられた。本案件は高まる森林保全のニーズに対応して実施されたインドネシア初の植林無償であり、タイムリーかつ妥当性の高いものであった。 サイトにおいて、現在までに60万本前後の植林が実施されており、2004年に完了する予定である。苗木は日本の3倍程度のスピードで成長するが、植林の効果が現れるまでには最低5年ほどが必要である。植林は地域住民を中心に行われており、植林に係る技術・知識の移転が行われている。現在までに約5万人の新規雇用がなされ、地域住民の生活に大きなインパクトを与えている。 同国立公園では、本案件の他に「森林火災予防計画」及び「森林火災防止機材導入事業」が行われており、森林火災予防にも効果を上げている。日本の植林技術者が中心となり、地域住民の自発的な消火チームを組織するなど、地域住民の森林火災に対する意識も大きく向上した。 本案件の植林対象面積は360 haであり、同国立公園の面積(13万ha)からすればほんの一握りに過ぎないが、植林対象サイトは展示効果も期待されており、公園管理関係者、地域住民の森林保全に対する意識の向上による今後の波及効果が期待される。 | |||
| 案件名: | 生物多様性保全計画(無償資金協力、技術協力) | ||
| 実施期間: | 1995年~2003年 | ||
| 対象地域: | 西ジャワ州チビノン、ボゴール、グヌン・ハリムン国立公園 | ||
| 案件概要:
インドネシア政府は91年に「インドネシア生物多様性行動計画(BAPI)」を制定し、自然環境保全に着手した。一方、1992年に発表された「日米グローバル・パートナーシップ・アクションプラン」のなかで日米環境共同協力事業として開発途上国における自然資源の管理と保全のための事業がうたわれ、インドネシアが対象国として選定された。これを受けて、インドネシア政府は同国の生物種保全を図ることを目的として、我が国に対して技術協力プロジェクト「生物多様性保全計画」を要請した。 我が国は1995年から97年までフェーズ1協力を、98年から2003年までフェーズ2協力を実施した。無償資金協力によって、チビノンに生物学開発研究センター動物部施設(生物多様性情報センターを含む)、ボゴールに自然保護情報センター、グヌン・ハリムン国立公園に管理事務所、リサーチステーションを建設した。
考察: インドネシアは、世界でも有数の種の宝庫となっている。種の多様性は、エコシステムの維持、種としての希少性、医薬品などとしての将来の利用可能性などの面で重要な資源として位置づけられる。しかし、急速な開発の進展によって絶滅に瀕している種も多い。こうした意味で本案件は、インドネシアの開発ニーズにタイムリーにマッチしたものであったと言える。 また、本案件は日米環境共同協力事業として実施されたものであり、国際的な環境保全に対する我が国の取り組み姿勢を示したものであった。 プロジェクトは当初の目的を達成し、2003年に終了した。生物学開発研究センターはJICA専門家が帰国した後も独力で維持されている。メンテナンスの状態も今の時点では良好と言える。また、独自に他の機関との共同プロジェクトの計画も行なわれている。しかし、どこまで現状を維持していけるかには若干の不安も残る。種のサンプルの収集活動への予算の確保、他国の研究者の招聘など活動活性化のための諸策などが必要である。 ボゴールの自然保護情報センターについては、データベースはジャカルタの本部に移管されてしまっており、現在、ソフト開発機能のみとなっていた。その結果、同センターの情報提供サービスは弱体化したものと判断される。今後の同センターの活用方法を考える必要がある。 種の多様性に関しては、今後も、国民に広く啓蒙活動を行なっていく必要がある。その点に関しては、本案件が対象としたグヌン・ハリムン国立公園は、啓蒙活動の一つの拠点になると期待される。 | |||
| 案件名: | インドネシア経済政策支援(技術協力) | ||
| 実施期間: | 2002年~2004年(予定) | ||
| 対象地域: | インドネシア全土 | ||
| 案件概要:
インドネシアは、1997年に発生したアジア通貨危機によって最も深刻な影響を被ったが、持続的な成長軌道へ再び回帰するためには、民主的で近代的な経済・社会システムの構築が求められている。インドネシアは、マクロ経済の安定、地方分権化、グッド・ガバナンスなどの各種改革を進めていくことを大きな目標としている。 我が国政府は、大学教授をメンバーとした日本人有識者6名とインドネシア側主要閣僚との政策対話を通じ、経済政策支援を進めている。マクロ経済運営、金融セクター改革、中小企業振興、民間投資拡大、民主化、地方分権の6分野について、メガワティ大統領に対して政策提言を行なっている。 適宜、政策助言が必要とされる時期に日本側有識者チームがインドネシアを訪問し、大統領への政策助言を提出するとともに、関係閣僚を集めた全体会議、あるいは個別会談を通じて政策対話を行なっている。また、ラクサマナ国有企業担当大臣が率いるワーキング・チームとの間では、政策支援に資する共同研究やセミナー等を行なっている。
考察: (1) マクロ経済運営に対する政策提言 マクロ経済運営の最高責任者である大統領及び関係閣僚に対する政策提言を行なっており、高いレベルでの政策支援を行なっている。 (2) ポストIMF経済政策への貢献 IMF卒業後の経済運営に関しては日本に対するインドネシアの期待が大きい。持続的経済成長の牽引役となるべき投資を活性化するための提言を行ない、大きな影響力を与えている。 (3) 今後の課題 ポストIMF政策を実施していくためには、政府内部だけでなくアカデミックな分野、民間部門、ドナーの間にコンセンサスを築いていく必要がある。今度は、こうした面でも貢献していくことが効果的であろう。 | |||
| 案件名: | 鋳造技術分野裾野産業育成計画 | ||
| 実施期間: | 1999年~2004年 | ||
| 対象地域: | 西ジャワ州バンドン | ||
| 案件概要:
インドネシアにおいては、自動車、電気電子製品等の組立産業に部品を供給する裾野産業が十分育成されておらず、工業化の障害となっている。鋳造技術は、裾野産業の代表的な要素技術の一つである。我が国は、金属機械工業研究所(MIDC)の機能を強化し、鋳造技術分野等の裾野産業振興を図り、インドネシアの産業構造を強化・高度化することを目的として、技術協力プロジェクトを実施している。 MIDCはベルギーの援助により69年に設立された。「鋳造技術分野裾野産業育成プロジェクト」は、MIDCが中小鋳造企業に対して質の高い技術サービスを提供できるようにすることを目的としている。 支援内容は、鋳鉄の鋳造技術のうち、(1)鋳造方案、(2)模型製作、(3)溶解、(4)造型、(5)検査の各分野において、試作品製作、巡回指導、セミナー等の実施を通じたOJT中心のカウンターパートへの技術移転である。また、現地中小鋳物企業に対する指導能力の向上も図られる。
考察:
| |||
| 案件名: | 貿易研修センター協力事業・人材育成計画、地方貿易研修・振興センター計画 | ||
| 実施期間: | 1989年~2006年(無償資金協力、技術協力) | ||
| 対象地域: | 西ジャワ州ジャカルタ、東ジャワ州スラバヤ、北スマトラ州メダン、南スラウェシ州マカッサル、南カリマンタン州バンジャルマシン | ||
| 案件概要:
貿易研修センター(IETC)は、1989年、無償資金協力を受けて建設され、88年9月から1993年9月まで「貿易研修センター協力事業」(技術協力プロジェクト)が実施され、1994年1月から1995年9月までフォローアップ協力が実施された。貿易研修、商業日本語、輸出検査、展示研修の4分野で支援が行なわれた。貿易振興ために貿易分野における更なる人材育成が重要との認識から、貿易セクター人材育成計画(フェーズ2)が97年3月から2001年2月まで、フォローアップ協力が2001年3月から2002年2月まで実施された。協力活動内容は、(1)コースプランナーの育成、(2)インストラクターに対する情報提供、(3)貿易関連情報の外部への提供であった。 地方分権化が進展するなか、地方都市数ヵ所に「地方貿易研修・振興センター(RETPC)」を設立し、これまでのIETCでの成果を地方に展開することを目的とした技術協力プロジェクト「インドネシア地方貿易研修・振興センター計画」(2002年7月~2006年6月)が現在実施中であり、地方分権、人材育成、輸出促進という3つの開発課題に総合的に取り組まれている。RETPCは、州政府が建物を提供し、商工部が運営費を負担するかたちになっている。東ジャワ州商工部RETPC(スラバヤ)、北スマトラ州商工部RETPC(メダン)、南スラウェシ州商工部RETPC(マカッサル)が既にオープンしており、2004年に南カリマンタン州商工部RETPC(パンジャルマシン)がオープンする予定である。
考察: (1) 財務面での自立性の確立 2002年度は、収入(受講料収入が中心)は支出とほぼ同額に達している。将来的には独立法人化を目指している。受講者数は、毎年2,000人を超えている。2003年度については予算の執行が半年遅れたため、1~6月累計で905名にとどまっている。実践的な講義を行なっていることが受講者増加の理由となっている。 日本が供与した機材もよく維持管理されている。IETCは、認証機関ではないが検査の受託業務も行なっている。バイヤーが輸出者にIETCの認証を要求するケースもある。 (2) 地方を指導できる人材の育成 地方の貿易研修・振興センターの所長はIETCから派遣。副所長は地方のDinasから、輸出振興担当部長はNAFEDから、研修担当部長はIETCから。JICA専門家は、各センターにおいても、そのセンターの周辺地域に支所を作り、指導する能力を蓄積させる方針である。 (3) 他のドナーの協力 IETCの能力が高いことに注目して他のドナーもIETCに対する協力を開始している。オーストラリアは積極的である。その他、オランダ、ドイツ、中国などが支援を行なっている。 | |||