日本政府は、インドに対する援助のあり方を国別援助方針に定めている。従来より、インドが南西アジア地域における政治・経済上の重要国であること、伝統的に日本とインドが友好関係にあること、巨大な貧困層の存在により援助需要が高いこと、経済自由化に積極的に取り組み市場志向型経済の推進を図っていること等から、円借款を中心として積極的な援助を行うとの姿勢をとってきた4。同時に、技術協力については、インドは人口衛星を打ち上げることができる程の技術を有し、近隣諸国等へ自ら技術協力を行うなど既に技術的には相当進んでいる分野もあるため、概して技術協力に対する要請(特に専門家派遣、開発調査等)は多くない、との認識を示している5。この認識は、上述の通り円借款が大部分を占めている実態を裏付けている。
1990年代以降の日本の対インド援助実績の推移とその特徴を見てみると、まず、1990年代を通じてほぼ一貫して日本はインドにとって最大の二国間援助供与国であり、1990年代後半には二国間援助額のうち概ね50%以上を占めてきた6。また、日本の二国間援助の累計実績7の中においても、インドはインドネシア、中国、フィリピン、タイに続いて第5位の受け取り国であり、最近の毎年の供与額順位で見ても常に上位に位置付けられている(図表2-23)。2000年度までの対インドODA供与累計総額は、2兆1千億円にのぼる8。
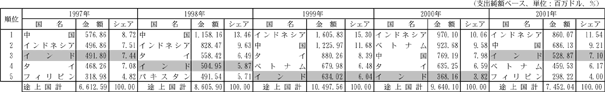
出所:ODA白書各年版
最近の動向としては、2003年4月より日本の対インドODA全体の戦略性・透明性・効率性の向上のための現地体制の強化を目的として、在インド日本大使館、JBIC、JICAを正式メンバーとした在印ODAタスクフォースが結成された。現地でのインド政府との政策協議に向けた対処方針を作成すると共に、その内容を今後策定予定の日本の対インド国別援助計画の策定に反映させることを主な活動内容としている(図表2-24)。
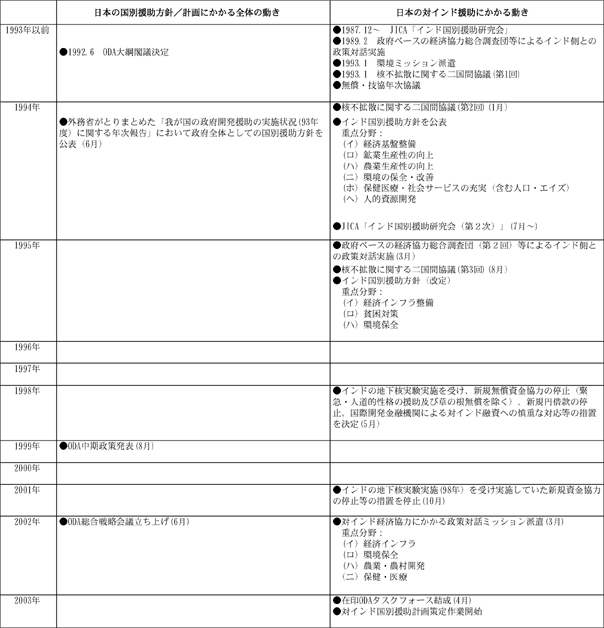
対インドの援助方針としては、1989年2月に派遣された政府ベースの経済協力総合調査団によるインド側との意見交換に基づいて、6つの重点分野9が設定された。その後、インドの開発に関する各種の調査・研究及びJICAにおける「インド国別援助研究会」(第2次)の成果を基に、1995年3月に派遣された経済協力総合調査団及びその後のインド側との政策対話を踏まえ、改めて次の分野が重点分野とされた10。
(1)経済インフラ整備
(2)貧困対策
(3)環境保全
上記3分野は、現行の「対インド国別援助方針」における重点分野として維持されてきた。
しかしながら、1998年5月、インドの地下核実験実施に対応して、日本政府はインドに対し、新規無償資金協力の停止(緊急・人道的性格の援助及び草の根無償資金協力を除く)、新規円借款の停止、国際開発金融機関による対インド融資への慎重な対応等の措置を決定し、その後3年半にわたり、新規資金協力は凍結されることなった。2001年10月に、政府は同措置の停止を発表した11が、その後も2001年度中には、有償資金協力、無償資金協力(草の根無償資金協力を除く)共に新規案件の実施には至らなかった。
尚、評価対象期間外であるが、核実験に対する上記措置の停止による本格的な援助再開を受けて、2002年3月に、日本政府は対インド経済協力にかかる政策対話ミッションを派遣し、今後のインドへの経済協力の方向性についてインド政府と意見交換を行った。その結果、経済インフラ、環境保全、農業・農村開発、保健・医療の4分野を新たに重点分野とすることを確認した。
1990年代の日本の対インド援助実績の形態別内訳の推移を見ると、金額ベースで9割を有償資金協力が占め、残りの1割を技術協力と無償資金協力が分け合う構成となっている(図表2-25)。
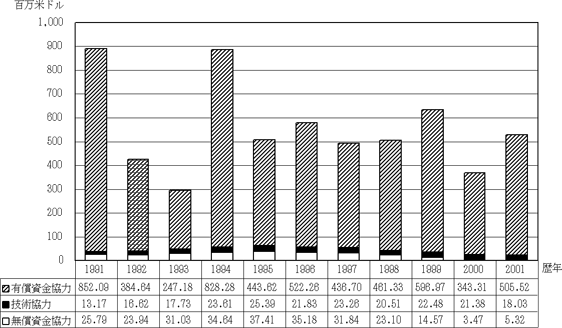
有償資金協力については、1980年代後半から2001年度までの円借款の部門別承諾累計の推移を下図に示した(図表2-25)。インフラ部門の割合は一貫して最大であり、特に、電力・ガス、鉱工業、運輸の3部門で2002年3月末には承諾額全体の73%を占めている。その一方で、社会的サービス(上下水道・衛生、観光、都市・農村生活基盤など)や農林・水産業、灌漑・治水・干拓など、1980年代には見られなかった分野への協力が拡大傾向にある。
1997~2001年度の5年間をそれ以前の5年間と比較すると、新規資金協力停止等の措置の実施を反映して、承諾案件数(15件)、承諾累計額の伸び幅(2,190億円)共に、1992~1996年度(45件、6,190億円)のおよそ3分の1となった。承諾案件15件の部門別内訳は、電力・ガス7件、運輸3件、灌漑・治水・干拓1件、農林・水産業3件、鉱工業1件であった。
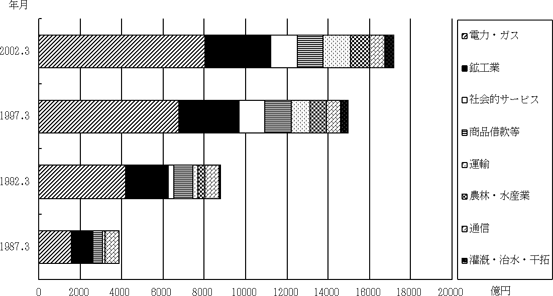
一方、技術協力については、1997~2001年度の毎年の国際協力事業団(現独立行政法人国際協力機構)の対インドの分野別経費実績を1990年度との比較において示した(図表2-27)。1990年度の合計約8億円から、1998年度以降は概ね毎年10億円規模の支出となっている。分野別内訳を見ると、1997年度以降は公共・公益事業、農林水産といった従来から支出割合が大きい分野の他に、保健・医療及び社会福祉分野の拡大が目立っている。
尚、インドへの技術協力を開始して以来、2001年度までに実施済及び実施中のプロジェクト方式技術協力案件は、合計で12件に留まっている。そのうち、1997~2001年度に該当する案件は4件(サンジャイ・ガンジー医科学研究所、二化性養蚕技術開発、二化性養蚕技術実用化促進、新興下痢症対策プロジェクト)である。
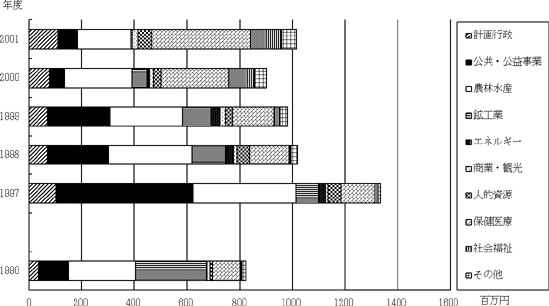
無償資金協力については、1991~2001年度の10年間に合計293億円が供与された。1991年度から1997年度までは、保健・医療及び教育分野12や食糧増産援助、債務救済を中心に、年間30-40億円レベルの協力が行われた。しかし、1998年度以降は緊急無償を除けばポリオ撲滅計画(ユニセフ経由)と債務救済のみが実施され、供与額も年間15億円前後となった。一方、この10年間に合計242件の草の根無償資金協力が実施されたが、実施件数はむしろ1990年代前半の年間10件程度から、後半には毎年30件以上にまで増加した13。
4 外務省、ODA白書 各年版
5 同上。同時に本評価の現地調査における日本側関係機関及び他ドナーのヒアリングからは、インド政府は一般的にオーナーシップ意識が高く、ドナーに援助政策を押し付けられることや、ドナーが連携して政策を押し付けることを好まない、とのコメントを複数得た。
6 DAC各国の対インド援助総額(支出純額)のうち日本の援助が占める割合は、1997年には53.0%、1999年には75.6%、2001年には58.5%(暦年ベース)。
7 1998年までの支出純額ベース。
8 2001年版ODA白書国別データブックより。尚、支出純額ベースでは2001年までの累計額が7,925百万ドル。
9 (1)経済インフラの整備、(2)工業生産性の向上、(3)農業生産性の向上、(4)環境の維持改善、(5)保健医療・社会サービスの充実、(6)人的資源の開発(出所:ODA白書1993年版)
10 外務省、ODA白書2001年版 国別データブック
11 その理由として、日本政府は「核実験モラトリアムの継続や、核・ミサイル関連の物質・技術の輸出管理の厳格な実施を表明するなど、インドの核不拡散上の取り組みを評価し、また、今後のテロへの取り組み及び南西アジア地域の安定化に大きな役割を果たすインドに積極的な関与が必要との立場から」措置を停止するとしている。(外務省「ODA白書2001年版 国別データブック」128頁)
12 例えば、保健・医療分野では、オスマニア総合病院医療機材整備計画(1994年度)、カラワティ・サラン国立小児病院改善計画(1995/97年度)、ポリオ撲滅計画(1996/97年度)。教育分野では、プネ工科大学教育機材整備計画(1991年度)、インディラ・ガンジー国立公開大学教材製作センター整備計画(1993/94年度)、バラナス大学医科学センター教育機材改良計画(1993年度)など。その他の主な無償資金協力案件としては、ニザムディン橋建設計画(1994/95/96/97年度)、優良種子開発計画(1995年度)、港湾浚渫船建造計画(1997年度)などがある。
13 前述の通り、草の根無償資金協力はインドの核実験に対応した新規資金協力停止等の措置の対象外であった。

