2.フィリピン
(現地調査期間:1998年3月8日~18日)
■高橋 彰 国士舘大学政経学部教授
■鳥飼 行博 東海大学教養学部助教授
■成家 克徳 東京外国語大学講師
■下村 暢子 海外コンサルティング企業協会副主任研究員
■二階堂幸弘 外務省経済協力局評価室長
■佐川 昌也 外務省経済協力局評価室事務官
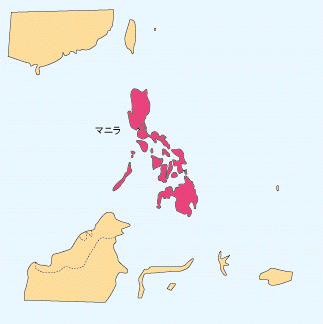
はじめに-国別評価とは
国際社会の相互依存、グロバリゼーションをふまえると、日本による開発途上国の援助は、我が国が国際社会のリーダーとなり、自らの国益を求めていくというよりも、世界の繁栄と平和に寄与するために必要不可欠となっている。そこで、財政事情に拘らずODAの質の改善、すなわちODAの効率的・効果的な実施は常に求められるものであり、透明性を確保してODAの資金負担者である国民の理解を高めることが課題となっている。
我が国のODA評価については、ODAの実績をプロジェクト単位、分野別、国・地域別に評価しているが、これによって援助政策の策定、案件発掘・形成、援助事業の実施などに有益な教訓・提言を得ることができる。また、その評価を公表することによって国民の理解を深め、参加型の開発にも結びつくことになる。
評価の内容は、外務省経済協力局(1998)『外務省国別評価ガイドライン』では、時系列的に、(1)審査、(2)モニタリング、(3)終了時評価、(4)事後評価、の4つに分けているが、事後評価を援助政策策定や案件発掘・形成→計画策定→実施→評価、と繋げることで、開発援助のプロジェクト・サイクルが形成される。また、外務省の主導する評価活動としては、(1)国別評価、(2)分野別評価、(3)有識者評価、(4)他の援助機関との合同事後評価、(5)在外公館による評価、(6)被援助国による評価、(7)援助実施・受入体制の評価、が挙げられている。
本報告は国別評価であるが、これは相手国の経済発展や民生向上に対する日本のODAの効果を事後分析し、相手国での評価セミナー、年次協議などによって被援助国に伝えようというものである。そして、国別評価の項目は、(1)目標達成度、(2)妥当性、(3)波及効果、(4)効率性、(5)自立発展性、とされる。ここで(1)の目標達成度については、経済発展、民生向上に結びつく交通網の整備や発電能力向上といった目標の場合、具体的数値を示したとしてもプロジェクト案件が完工すればおおむね達成することができる。つまり、案件が途中で放棄されたり、計画に大きなる誤算が生じない限り、目標達成度が低いとはいえないのであって、このような事例はごく希であろう。また、(2)の妥当性については、案件自体よりも他の代替的な案件との比較考量によって、吟味することが望まれる。つまり、目標に対して貧困解消、民生向上、経済発展への寄与など効率や公正の観点から妥当であったかどうかが吟味されなくてはならない。(3)の波及効果については。経済インフラの場合、外部効果として広く多数の経済主体に便益を与えるであろうが、その定量的な計測は、 ODAの効果として識別できない可能性も高いことに留意すべきである。例えば、道路整備のもたらす波及効果は自動車の性能、燃料価格、自動車保有台数、他の地域の道路の状況など様々な要因と相関関係にあり、因果関係のうえですべて道路整備に帰することはできない。したがって、あくまでも我が国のODAの評価という限られた視点で波及効果を検討しているという限界には留意しておかなくてはならない。(4)の効率性 については、プロジェクト一つ一つを検討する時間的、資金的制約からも費用便益分析によって具体的に効率性を判断することは困難で、実施したとしても上記の波及効果をいかに取り込むかで恣意が入り込む。そこで、効率性に関しても訂正的な評価にとどまってしまう場合が多いであろう。(5)の自立発展性は、援助後の相手国の資本、技術、運営管理能力などが改善され、自国の力でプロジェクトを推進したり、財政的手当を自国で賄ったりできるかどうかを判断するもので、自助努力が可能となるような状況を作り出すことを求めている。したがって、案件が過度に集中していたり、長期にわたって支援を受けているのであれば、効率性の観点からは望ましくとも、自立発展性の上からは好ましくない場合も生じる。
以上のように、国別評価の項目は定量的に評価することが難しい場合が多く、項目相互にトレードオフがあることから評価主体によって評価内容が異なってくることが考えられる。しかし、国別評価によって、プロジェクトサイクルを循環させ、我が国のODAを検討し、よりよい援助案件を支援することで、相手国の経済発展、民生向上に寄与できるのであれば、限られた評価ではあるといっても重要である。また、第三者も参加する国別評価は開かれた援助、参加型の開発にも寄与する。したがって、本報告書では外務省、海外経済協力基金、国際協力事業団から提出された資料、1998年3月に11日間実施された現地視察の成果、フィリピンの統計資料などを活用して、フィリピンに対する我が国のODAを評価することを試みる。
1 フィリピン経済の概要
1.1フィリピン経済社会の社会的性格
1980年代に東南アジア諸国の多くが急成長を続けていたあいだ、フィリピンでは、独裁体制をめぐって政治混乱が続き、それによって引き起こされた外国投資の衰退・逃避、アメリカをはじめとする西側供与国の経済援助の削減などが重なって、経済の停滞が著しかった。1984~85年には7%を超えるマイナス成長を記録しているほどであった。1986年にマニラで生じた軍内部の反乱と、その支援に立ち上がった民衆と聖職者の直接的行動によって、強権的抑圧は拭い去られ民主体制が回復されたが、それは同時に、1972年以前のオリガーキー体制への復帰という側面を基本的には持つものであったことは否定できない、この政変が生み出したものは、まず何よりも、旧特権層の復活だった。それによって国民大衆の社会的経済的階層構成が変化したわけではなく、また社会移動が活発化したわけではなかった。この政変が「民衆革命」などと呼ばれることはあったけれど、結局のところ、革命revoludonであるよりは復古restorationとしての性格を強く示すものだったのである。
強権体制から脱却したあとも、経済の伸びは順調ではなかった。軍や国内少数民族などによる政治治安の暗雲が社会を覆い続けたし、日本をはじめとする援助供与国は負の遺産を引き続いた新政権を助けるべく資金援助を増やしたので、1988~89年ごろは若干の成長を見たものの、その後インフラ建設の遅れによる電力をはじめとする公共サービスの劣化は経済活動に甚大な打撃を与えた。さらに90年代はじめの自然災害の多発に苦しめられ、91年にはマイナス成長を示したほどであった。フィリピン経済が成長の勢いを取り戻したのは、ラモス政権による自由化政策がある程度の成長をみせた90年代半ばになってからであった。その後は比較的順調な伸びをみせ、1995年にようやく一人あたり国内総生産が1000ドルを超えるにいたった。だが、1997年半ばから東南アジアに吹き荒れた通貨金融危機の嵐はこの国にも及んだ。タイやインドネシアに比べればその打撃は甚大でなかったとはいえ、ペソ価と株価の下落、海外からの投資削減、消費の冷え込み、輸出不振、石油価格上昇、失業増大など、その影響は決して軽微なものにはとどまらなかった。とりわけ、海外契約労働者の送金が外貨収入に占める割合が大きいだけに、シンガポール・香港など東南アジア経済の凋落は今後その面でもフィリピン経済を逼迫させることになろう。1998年6月末に新政権が誕生したが、厳しい経済環境の中で困難にいかに立ち向かおうとするのか、その施策はまだ明らかではない。
そして人口の急増が経済問題をいっそう厳しいのもとしている。人口増加率は徐々に低下しつつあるとはいえ、今も2.32%に及んでおり、1960~95年の35年で総人口は2.5倍になったのである。
元来フィリピンは東南アジア諸国の中で比較的恵まれた経済条件のもとでの独立を果たした国であった。民族内部に成長した豊かな経営資源とアメリカ向け一次産品輸出に導かれた投資の拡大によって第2次世界大戦前にある程度の産業の発展をみていたし、独立当初のアメリカからの投資移転もあって、東南アジアでは高い経済水準をもっていたのである。国連統計によっても1950年の一人あたり国民所得152ドルは日本より24%も高いものであった。この数字が当時のペソの過大な対ドル・レートによるところが大きかったにせよ、この国が相当な経済水準から出発したことは留意されてよい。
この国での開発協力を考える際に考慮すべきフィリピン経済社会の基本的な特質として次の諸点について述べておきたい。
第1はフィリピンの政治的正統性である。東南アジアでもっとも長い植民地としての歴史を持つ国であるが、植民地化以前の土着社会に中央権力が成立していなかった。19世紀末の独立運動は回帰すべき伝統的政治体制が不在であったところがらアジアでも早い時期に短命ではあったが共和体制を発足させた。この国の政治においては、つねに伝続に正統を求めようとするよりも、外来の価値を志向する傾向が著しかった。具体的な行動が土着の価値意識に発することはいうまでもないが、観念上の規範は欧米とりわけアメリカから学んだものであることが多い。アメリカ軍芯地貸与条約は延長されなかったけれど、アメリカヘの熱いまなざしが消えたわけではない。
フィリピンは他の東南アジア諸国に比べて、政治のもつ優越性の著しい国であった。中央と地方の政治家は恩恵と集票力とで結びつき、国家資源の利権を争う。近年左翼政党も現れたが多くの政党は選挙時にポピュリスト的スローガンを謳うことはあっても、実質的には明確な政策的独白性を示すことはなく、離合集散を繰り返している。官僚制は弱体で、キャリア官僚は政治エリートに追従する。強権政治の時期を別にして、軍と官僚がリーダーシップを取ることはなかったといってよい。
第2はこの国の言語状況と地方性である。スペイン領期のカトリック諸国教団を通じる統治のもとで、スペイン語の普及は特権層にとどまり、むしろ地方ごとの言語的分断状況と地方主義義的傾向が強められた。さらにアメリカ統治期に公用語とされた英語が独立後もその地位を保った。立法・行政・司法をはじめ、科学技術・メディアや初等教育をふくむ令教育課程で英語への依存がみられるが、反面、国語・地方語による教育は重視されなかったため、英語を話さない国民は、長く地域的階層的な言語の分断状況に置かれた。このことは一方で多数の英語に堪能な国民を生み出したが、同時に、国家的情報が英語を話す国民に独占され多くの国民を疎外する状態を作り出した。同氏のなかには法律はもちろん、政府の刊行物にすら接近できないものが少なくない。教育で国語を重視するべきであるとする声が、現大統領を含んで、あげられたこともしばしばだったが、言語的既得権者の強い反発によってかき消されてきた。近年、国語教育の進展とともに、テレビや新聞・コミックなどが国民の間に同語を広げていることは顕著に認められる。今後、フィリピンでは一層国語が普及するであろうことは疑いない。そして地方主義的傾向は特に1991年以降の地方分権政策実践によっていっそう強まることが予想される。
英語の能力と人格を等値する傾向の強いフィリピンにおいて、日本から派遣される経済協力要員の英語が案件実施上の大きな問題になることがしばしばであったが、英語ばかりではなく、国語および地方語の力の養成を重視しなくてはならないであろう。
第3は社会階層の問題である。植民地期に形成され独立後にも引き続かれた典型的な二階層的社会構造そ長くフィリピンの特徴とされるものであった。伝統的な大農園主を出自とする社会経済的エリート層と権利な大衆層とのあいだの懸隔は大きく、その間に中間層が欠けており、社会移動のための階梯もないという状況が長く続いたが、1970年代からの経済の拡大に伴って、徐々に中間層が成長しつつあることは、最近の政治変動の一因となっている。
フィリピンにおいても経済の成長が国民の全般的な生活水準の上昇をもたらしてきたことはいうまでもない。しかし、階層格差はこの20年まったく縮小していないことは政府統計からも知られる。地域格差も大きくマニラ首都圏の世帯あたり所得に比べて農業部のそれは30.6%(1994)にすぎない。フィリピンが東南アジアのなかでも著しい特質はこの農村部の貧しさである。タイ・マレーシア・インドネシアに比べても、フィリピンの農民の多くの暮らしぶりが住居・什器・家具・食事・上水・保健衛生などさまざまな面で、とくにストックにおいて劣ってることが観察される。このような貧困は、まさにカシケ制とよばれた大土地所有制によってもたらされたものであって、低生産性、社会不安、農民の諦観、狭隘な国内市場など経済発展阻害要因の多くがここに発していた。この問題の解決のためにアメリカ統治期から小作立法や土地買収分配などの農地改革・政策が繰り返されてきたが、社会経済的に本格的な意味を持ったのは戒厳令下の米・とうもろこし作地を対象とした1972年の土地改革令であった。しかしその後、農地改革の実施は滞り、70年代前半の経済成長も、膨張を続ける農村過剰人口によって、今は蚕食されつつある。
1.2 経済の現況
(1) 人口
フィリピンの国土面積は27万6,900平方キロメートルと日本の75%に相当し、大小7,150の島から構成されている。人口は1990年は約6,070万人、1995年は約6,862万人と5年間で13%も増加し、特に首都圏(NCR:National Capital Region)としてマニラ、ケソン市、カローカン市などから構成されるメトロマニラは1990年は約795万人、1995年は945万人と18.9%の増加をみている(表1-1参照)。メトロマニラの年平均の人口増加 率は1970~1975年4.62%から1990~1995年の3.30%に低下したが、全国平均の人口増加率は各年で2.78%、2.32%であるから、依然として都市化は急速に進んでおり、人口密度は14,865人と全国平均の229人の65倍にも達している。1995年人口の年齢構成は、全国平均では15歳未満の年少人口比率38.3%、65歳以上の老人人口比率3.5%であるが、メトロマニラは各々32.5%、2.5%と従属人口比率が低く、生産年齢人口の比率が高い。
このようなメトロマニラヘの人口集中は、都市交通、住宅、衛生、環境などに関連した公共サービスの相対的不足を招来し、交通渋滞、大気汚染、不法占拠者の増加、水質汚染などの問題を悪化させ、あわせて製造業における雇用が十分でないために、都市インフォーマル部門と呼ばれるような露天商などの雑業に従事する都市貧困層も増加させた。しかし、全体からみれば、地方における雇用機会の欠如が地方から都市への人口移動を引き起こし、都市人口の社会増をもたらしている。したがって、人口集中による都市化、地方の貧困といった地域格差の問題が深刻である。
| 1970 | 1980 | 1990 | 1995 | ||
| 人口(万人) |
全国 メトロマニラ |
3,668 397 |
4,810 593 |
6,070 795 |
6,862 945 |
|
人口密度 (人/平方キロメートル) |
全国 メトロマニラ |
122 6,237 |
160 9,317 |
202 12,498 |
229 14,865 |
(2) GNP
フィリピンの1996年のGNPは2兆2,830億ペソで、消費者物価上昇率は前年比8.4%にとどまり、実質6.9%増の経済成長を遂げた。産業部門別のGDP構成比は農業(農林水産業)21%、工業(製造業、建設業、鉱業、電気・ガス・水道)36%、サービス業(商業、運輸など)43%で、趨勢的には農業の比率が低下し、サービス業の比率が上昇している(表1-2参照)。1996年の農作物の生産額は2,752億ペソで、その構成比は米33.7%、トウモロコシ10.0%と穀物が中心であるが、ココナツ10.5%、サトウキビ7.8%、バナナ4.5%などの生産も盛んである。また、漁獲高も801億ペソと農産物生産額の30%に達している。他方、1994年の製造業の付加価 値生産額は8,256億ペソで、その構成比は食料19.6%以外は、石油・石炭13.5%、電機12.4%、化学10.4%など重工業が中心である。
他のアジア諸国と経済パーフォーマンスを比較すると、実質GDP成長率は、1991年マイナス0.6%、1992年0.3%と低迷し、タイ、マレーシア、ベトナムの8%を上回る成長率に比して大いに劣っており、ASEANの中でも例外的に経済が低迷しているとされていた(表1-3参照)。実際、1人当たりGNPは1994年までは 1,000ドルに達せず、1995年にようやく1,091ドルにまで増加したが、依然としてタイ、マレーシアの半分にも達していない。消費者物価上昇率も他国と比して高く、インフレも進行している(表1-4参照)。
しかし、GDP成長率は1994~1995年は4%台、1996年は5.5%と景気は回復しているが、この背景には投資の伸長がある。つまり、他国に比較して低いとはいっても、国内貯蓄率の上昇に支えられて、投資の対GDP比は暫時上昇している(表1-5、表1-6参照)。特に、製造業において民間投資が進んでおり、通信分野での規制緩和、国営企業の民営化など民活導入が窺われる。こうして、財政の健全化も含め、フィリピンでも市場適合的政策が次第に効果をあげつつあるといえる。
表1-2 産業別GDP構成比
| 1985 | 1990 | 1996 | |
| GDP(億ペソ) | 5,719 | 7,207 | 8,485 |
|
農業 工業 製造業 サービス業 |
24.6 35.1 25.2 40.4 |
22.3 35.5 25.5 42.2 |
21.0 35.7 25.3 43.4 |
| 海外純移転 | -3.6 | -0.5 | 4.0 |
出所:1997 Philippine Statistical Yearbook, National Statistical Coordinadon Board, 1997, table 3.4より作成
表1-3 各国のGDP実質成長率
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |
|
フィリピン インドネシア タイ マレーシア ベトナム 中国 |
-0.6 8.9 8.5 8.7 6.0 9.3 |
0.3 7.2 8.1 8.0 8.6 14.2 |
2.1 7.3 8.3 9.0 8.1 13.5 |
4.4 7.5 8.9 9.1 8.8 11.8 |
4.8 8.2 8.7 10.1 9.5 10.2 |
5.5 7.8 6.7 8.8 9.5 9.7 |
表1-4 各国の消費者物価上昇率
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |
|
フィリピン インドネシア タイ マレーシア ベトナム 中国 |
18.7 9.4 5.7 4.4 81.8 2.9 |
8.9 7.6 4.1 4.7 37.6 5.4 |
7.6 9.6 3.4 3.6 8.4 13.2 |
9.0 8.5 5.1 3.7 14.4 21.7 |
8.1 9.4 5.8 3.4 12.7 14.8 |
8.4 7.9 5.9 3.5 6.0 6.1 |
(3) 投資
経済成長を牽引した投資については、1991年では対GDP比で19.9%に過ぎなかったが、1996年には23.9%にまで回復している(表1-5参照)。また、投資の資金を賄うには国内貯蓄が重要であるが、この対GDP比も18.2%から20.5%に上昇した(表1-6参照)。投資一貯蓄ギャップは1.7%から2.4%に拡大したが、この差額は対外債務というよりも、主に直接投資、公的移転(政府開発援助など)を通じて賄われた。直接投資の認可額は1989~1993年は毎年たかだか200億ペソ程度であったが、1994年627億ペソ、1995年481億ペソで、1996年も250億ペソ程度である。
フィリピン政府は民間投資の導入を積極的に進め、1968年の外国人業務規則、1970年の投資促進法、1977年の農業投資促進会は1981年にオムニバス投資規則に統一され、これは1987年に投資優遇規則Investment Incentive Code)に引き継がれた。1987年投資優遇規則は国内民間投資と外資の導入を促進するために、(1) 所得税の6年または4年間の減免、(2)資本設備、機械などの輸出入税の5年間の免除、(3)登録プロジェクトの労働者への賃金増加分に対しては50%の税控除とする、(4)輸入手続きの簡略化、(5)1991年にはメトロマニラ が48.1%を占め、人口集中、都市化の背景が窺われるが、輸出加工区(EPZ:Export Processing Zone)へも外資の積極的な導入が図られている。さらに、輸出加工区は輸出入税、付加価値税の減免、外国投資の保証など進出企業への優遇が認められる地区で、フィリピン輸出加工区庁の管轄下にある政府所有の常設の輸出加工区はパターン、マクタン、バギオ、キャビテの合計4ケ所で、この他、特別加工区や民間工業団地がスーピックなど14ヶ所に設置されている。つまり、フィリピンでも主に外資を含めた民間投資を導入して、輸出指向工業化を進めているといえる。
表1-5 各国の投資の対GDP比
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |
|
フィリピン インドネシア タイ マレーシア ベトナム 中国 |
19.9 33.5 43.4 39.3 15.6 34.7 |
20.8 33.9 40.8 37.1 18.3 36.2 |
23.6 34.5 41.3 39.8 26.0 43.4 |
23.5 33.7 42.0 42.5 26.2 40.0 |
21.6 34.8 44.2 45.4 27.5 41.2 |
23.9 27.7 43.8 45.1 30.1 39.6 |
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |
|
フィリピン インドネシア タイ マレーシア 中国 |
18.2 30.4 35.4 29.2 39.3 |
19.4 32.3 34.5 34.1 40.1 |
18.1 32.8 34.2 35.3 41.6 |
19.0 31.9 35.2 35.5 41.5 |
19.0 31.4 35.0 36.4 39.0 |
20.5 33.7 35.3 38.8 39.3 |
(4) 雇用
総雇用は1996年10月段階で、2,744万人で農業雇用は1,145万人、その雇用比率は41.7%にも達している(表1-7参照)。これに対して、製造業の雇用は276万人、建設157万人である。つまり、農業のGDP構成比は 21%と小さく、農業における労働生産性(雇用1人当たりの生産額)は、製造業に比して遥かに低いのであって、ここに貧困の一つの要因をみることができよう。サービス業の雇用は、商業406万人、運輸・通信166万人、公務・個人サービス業502万人などで、性別比は男子63.1%、女子36.9%であるが、商業、公務・個人サービスでは女子の雇用比率が男性を上回る。ただし、製造業でも女子雇用比率が44.3%に達しており、電子部品の組立など電機における女子労働者の活躍が窺われる。
|
人数 (万人) |
構成比 (%) |
|
|
農業 鉱業 製造業 電気・ガス・水道 建設業 商業 運輸・通信 金融 公務・個人サービス 総雇用 |
1,145 12 276 12 157 406 166 68 502 2,744 |
41.7 0.4 10.0 0.4 5.7 14.8 6.0 2.5 18.3 100.0 |
出所:1997 Philippine Statistical Yearbook, National Statistical Coordinadon Board, 1997, table 11.3より作成
(5) 財政
国家の歳出は、1996年4,156億ペソ(GNPの18.2%に相当)、1997年4,762億ペソ(予算)である。1997年の歳出の項目別構成比は社会サービス支出が32.8%、経済サービス支出は26.3%、一般行政サービス17.3%、国防7.8%、国債利払い15.6%となっている(表1-8参照)。歳出の内訳は、社会サービスでは教育19.6%、地方自治体への補助金5.5%が、経済サービス支出では運輸・通信10.7%、農業・天然資源6.6%、地方自治体への補助金5.2%が中心となっている。他方、歳入は1996年4,105億ペソである。歳入は1995年で税収が3,105億ペソで大半を占め、その内訳は所得税(法人所得税と個人所得税)1,112億ペソ、売上税(付加価値税などを含む)548億ペソ、関税980億ペソ、印紙収入124億ペソなどで、関税の占める比率が高い。また、公共サービスの運用収入と手数料、国営企業の収入などからなる非税収入も507億ペソを記録しているが、趨勢的には伸び悩んでいる。もっとも、フィリピンはIMFが提起する構造調整を受け入れていることもあって、予算計画は下回るものの財政赤字を着実に削減し1994年には財政黒字を計上し、以降の赤字幅は縮小した。
表1-8 国家財政の歳出と歳入の構成比
| 歳出(1997年予算案) | 歳入(1995年実績) | ||
|
社会サービス 教育 経済サービス 運輸・通信 国防 一般行政サービス 利払い |
32.8 19.6 26.3 10.7 7.8 17.3 15.6 |
税収 所得税 相続税 売上税 関税 印紙収入 非税収入 |
86.0 30.8 0.1 23.5 27.1 0.4 14.0 |
| 総額(億ペソ) | 4767 | 総額(億ペソ) | 3612 |
出所:1997 Philippine Statistical Yearbook, National Statistical Coordination Board, 1997, table 15.2, 15.3, 15.4より作成。
(6) 貿易
貿易をみると、1974年以来一貫して貿易赤字が続いている。1996年も輸出205億ドルに対して輸入は324億ドルと差引119億ドルの赤字を計上しているが、これは過去最大の赤字幅である。輸出入の構成は、1987年にはココナツ油、パイナップル、木材、銅、石油などの伝統的一次産品が23.9%を占めていた。そして、1994年の輸出入品構成をみると、石油、農水鉱産物などの一次産品は輸出向けもあるが、輸入も少なくなく、輸出入のバランスがとれている。他方、電機の輸出構成比が1987年の19.6%から1996年の48.6%に、機械・輸送機器が1.4%から6.3%に上昇する反面、衣類は19.2%から11.8%に低下している。特に、1972年以来設置されてきた輸出加工区(EPZ)は外資に法人税や関税の減免、外資の100%出資も認めるかわりに輸出義務を課しており、外資導入と外貨獲得の双方に寄与してきた。1994年の貿易相手は米国への輸出38.2%、輸入18.5%で、日本は各々15.1%と24.3%と圧倒的シェアを誇るが、シンガポール、香港、台湾などとの貿易も急増している。1994年の輸入はセミコンダクター・ディバイスなどの電機26.7%、機械・輸送機器20.2%、石油製品9.6%など工業製品が82.2%を占めている(表1-9参照)。そこで、輸出に占める電機、輸送機器など高付加価値の工業製品が増え、それが輸出の中核を成しているとはいっても、電機、機械・輸送機器の輸入はその輸出を遥かに上回る。つまり、産業構造と輸出品の高度化は進んだが、依然として部品、中間財を輸入に依存しており、国内の生産工程は加工や組立の一部を担っているに過ぎないと考えられる。換言すれば、電機、機械・輸送機器の分野における生産は依然として委託加工、アウトソーシング、逆輸入など外資を中心とした企業内貿易に依存していることが窺われる。
表1-9 輸出入の構成比(1994年)
| 輸出 | 輸入 | 輸出 | 輸入 | ||
|
鉱産物 石油 木材 食料 ココナツ油 衣類 |
3.0 1.8 0.2 10.0 2.9 16.5 |
1.4 9.6 0.5 6.5 0 0.1 |
金属製品 化学 電機 機械・輸送機器 その他 |
3.2 2.3 36.2 4.5 19.4 |
6.0 9.4 26.7 20.2 19.6 |
| 金額(億ドル) | 134.8 | 213.3 |
表1-10 輸出入の構成比(1996年)
| 輸出 205.4億ドル | 輸入 324.2億ドル | ||
|
伝統的輸出品 ココナツ製品 砂糖 非伝統的輸出品 水産物 衣類 電機 機械・輸送機器 |
8.9 3.5 0.7 88.7 1.4 11.8 8.6 6.3 |
燃料 電機 輸送機器 産業機械 通信機器 繊維 鉄鋼 |
9.6 |
出所:1997 Philippine Statistical Yearbook, National Statistical Coordination Board, 1997, table 7.1, 7.3, 1995
Philippine Yearbook, National Statistics Office, 1995, table 18.3より作成
1.3 今後の展望
フィリピン経済は、雇用の上では農業の比率が依然として高いのであるが、生産額の上では、製造業、特に電機、電子、機械・輸送機器の伸長が著しく、貿易においても一次産品の比率は低下し、これらの部門の輸出が急増している。たしかに、実質経済成長率は1991年にマイナスとなったが、これ以降は年々上向いており、順調に経済成長を遂げている。また、失業率、インフレ率も1991年以降、改善され、マクロの経済パーフォーマンスはタイ、マレーシアと比較すれば劣るというものの、総じて好転している。また、1997年後半から深刻化したアジア通貨危機は、タイ、インドネシア、韓国などの株価暴落につながったのみならず、為替レートの大幅減価が対外債務の返済を困難にし、各国の資金繰りを悪化させ、投資、消費も冷え込んでしまった。これに比して、フィリピンでは従来から対外債務の返済に苦労しており、IMFのコンデイショナリティを受け入れつつ、構造調整に努めていた。そこで、経済パーフォーマンスの上では他国に劣っていたのであるがアジア通貨危機に際してはこれが幸いし、比較的被害は小さい。為替レートは1996年までの1米ドル24~27ペソから、1998年には40ペソ台にまで落ち込んだが、他国と比して小さな下落率にとどまり、資金繰りの悪化、投資の低迷といった事態は概ね避けられている。ただし、1998年にはエル・二一ニョによる干ばつの影響が農業に悪影響を与えることが懸念される。したがって、フィリピンは、都市への人口集中、地域格差、農村の貧困など依然として様々な問題を抱えているが、ASEAN諸国の多くが不況に陥っている中、「アジアのトラ」として今後も順調な成長を遂げることが期待される。
しかし、ここでの問題は、産業構造が電機、機械・輸送機器など分野に高度化し、その輸出が伸長しているといっても、部品や中間財の輸入や外資に依存するところが大きく、国内の非外資資本、地場産業との連関効果が乏しいことである。特に、部品生産などを担う裾野産業に対する後方連関効果は、ローカルコンテンツ要求にも拘らず小さく、これがメトロマニラと地方、あるいは輸出加工区とその他の地域との所得格差を生む大きな要因になっている。したがって、今後のフィリピン経済の課題は、地域格差を是正するためにも地域の産業振興、地域経済に貢献できる中小企業や個人経営体の育成にあると考えられる。しかし、この支援のためには財政的基盤が不可欠であるが、フィリピンの場合、雇用機会の不足もあって、サラリーマンを中心とする中間所得層が十分に育っておらず、個人所得税の拡張は望めない。そこで、対フィリピンODAを供与する際にも、地域格差の是正、輸出加工区との連関効果の拡大、中小企業や個人経営体などの経済発展の担い手や税収や貯蓄の基盤となる中間所得層の育成を念頭におく必要があると考えられる。
1.4 フィリピン現行の中期開発計画(1993~98年)
(1) 中期開発計画(1993~98年)の概要
現行の1993~98年中期開発計画の概要は以下の通りである。まず開発の目標では、同計画のゴールを「民衆の力の向上」を通じた全てのフィリピン国民の生活水準の向上とし、具体的には、1998年までのマクロ経済目標として国民所得一人当たり1,180ドル以上、GNP成長率平均5.6~7.2%以上、貧困人口30%以下という数値を設定している。また、このゴール達成の戦略として、a.人材の育成、b.国際的競争力の強化、c.持続的発展を掲げている。
次に、開発計画の各論としてa.マクロ経済と開発資金調達、b.持続的アグロインダストリー開発、c.人材開発、d.インフラストラクチャー開発、e.開発管理につきそれぞれ過去の実績評価及びゴールと目的が述べられるとともに、各個別分野のターゲットが設定されている。
また同開発計画では、前アキノ政権の目標であった「雇用の創出」、「社会的公正」及び「貧困の撲滅」も継続的目標として掲げているが、これらは国際的競争力の強化と総合的人材開発のための統合されたアプローチを通して追求されるべきものとしている。
またラモス政権は上記開発計画と並行して2000年までに一人あたり国民所得を1,000ドルとする「フィリピン2000」計画を推進した。同キャンペーンは広く国民にフィリピンの経済発展と成長への努力という意識を浸透させる目的であらゆるメディアを利用して行われており、世界的に市場経済化が進むなかで、民間部門を刺激するという目的も含まれている。分野別の課題としては、伝統的産業である農業の生産性向上、製造業部門の活性化、経済インフラ整備、地方分権化推進、基礎的インフラの整備などが挙げられる。
上記開発計画の目標は、全てのフィリピン国民の生活向上であるが、かかる目標の達成のために以下の主要目標を掲げている。
- 貧困の緩和(Poverty Alleviation)
- 社会的公正の推進及び不平等の是正(Social Justice and Social Equity)
- 持続可能な成長の達成(Sustainable Development or Growth)
- 生産に結びつく雇用機会の創出(Generation of Productive Employment)
- 人間の開発(Human Development)
上記「中期開発計画」をさらに整理すると、持続的経済成長を実現するためには、まずはフィリピン経済の再建が急務であり、このため適正なマクロ経済運営、インフラの整備、環境保全にも取り組む必要がある。具体的な経済政策として、輸出振興、国内産業の体質改善、民間投資環境の整備が課題である。中長期的観点からは、地域間格差の是正や人的資源の開発が重要であり、マニラ首都圏への人口集中緩和を含めた地域総合開発の他、行政能力・援助吸収能力向上の観点からの人材育成も検討が必要である。以下に各重点分野の政策と課題についてまとめた。
| 重点分野 | 主要政策 | 開発推進上の問題点 |
| (1)マクロ経済運営・管理 |
|
|
| (2)開発管理 |
|
|
| (3)アグロインダストリー開発 |
|
|
| (4)人材開発 |
|
|
| (5)インフラ開発 |
|
|
| (6)地域開発 |
|
|
(2) 中期公共投資計画(1993~1998年)
「中期投資計画」は政府の年間予算策定の基礎となるものである。また、1993~1998年計画は特に、貧困 緩和、不平等の是正、雇用機会の創出、包括的人材開発及び持続的成長の確保を中心に据えている。1994年の公共投資総額は986億ペソ(中央府467億、公社・小公団519億)であり前年比18.4%増を達成した。1995年目標投資額は1,001億ペソである。
| 部門 | 1993 | 1994 | 1995 |
| 1)インフラ開発 | 630 | 744 | 761 |
| 2)人的資源開発 | 77 | 136 | 150 |
| 3)アグロインダストリー開発※ | 114 | 88 | 40 |
| 4)開発行政と災害対策 | 12 | 17 | 50 |
| 合計 | 833 | 986 | 1,001 |

