第6章 国際専門家による評価
道路設備と都市給水(ケニア)
(現地調査期間:1997年3月23日~28日)
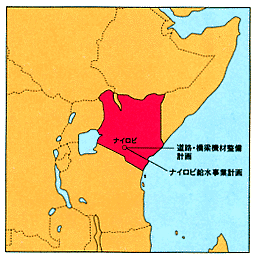
■ハーバード国際開発研究所 ロイ・ケリー
<評価対象プロジェクト>
| プロジェクト名 | 援助形態 | 協力年度、金額・年度 | 協力の内容 |
| 道路・橋梁機材整備計画 | 無償資金協力 | 1993年度、5.47億円 | ケニア政府は生活道路の建設等に重点を置いた第三次道路セクター計画を策定し実施しているたが、経済状況の悪化や道路・橋梁の維持管理用機材の老朽化のため困難をきたしていたため、我が国よりトラック、振動ローラ、コンクリートミキサー等を供与した。 |
| ナイロビ給水事業計画 | 有償資金協力 | 1988年度、53.42億円 | 本事業は、テイカ川を水源とするダム、パイプライン、浄水施設等一連の施設の供与により急増するナイロビの水需要に対処するものであり、世銀等の協調融資。我が国援助は水道本管の建設に充てられた。 |
1 道路・橋梁機材整備計画
(1) 序文
1990年代初頭、ケニア政府は「第3次道路セクター・プログラム(1992~2000)」を効果的に実施するための国際的な援助を、公共事業省(MOPW)を通じて要請した。要請の一環として、ケニア政府は日本政府に道路や橋梁の保守に必要な資機材を援助するよう求めた。この要請の背景には、自力で道路や橋梁を保守するための資機材を求めていた公共事業省の事情があった。
公共事業省(MOPW)は、故障のため道路建設や保守に使用できない古い資機材を大量に保有しているという根本的な問題を抱えていた。そのため、MOPWは使用可能な資機材を酷使することになり、それが新たな故障を招き、結果として使用不能の資機材がさらに増えることになった。新しい資機材を要請することで、この悪循環を断ち切ろうとしたのである。
この要請に応えるため、国際協力事業団(JICA)は 1992年、基本設計調査チームを派遣し、ケニア国建設省の資機材ニーズを特定するためのプロジェクト設計を行った。プロジェクト・ニーズの分析に基づき、基本設計調査チームは、MOPWの資機材の管理能力を高め、道路交通サービスの質を向上させ、また、雇用を促進し、経済的かつ費用安定型の交通サービスを確立するための資機材一式を特定した。
(2) 評価結果
a. プロジェクト
「基本設計調査報告書」に引用されているように、本計画の目標は、「道路や橋梁の十分な保守活動を容易にするための資機材を供給することである。これらの資機材は公共事業住宅省の資機材管理能力の向上と道路交通サービスの『質』の向上に貢献するであろう。……また、雇用を促進し、経済的でコストの安定した交通サービスの確立に貢献するであろう。」
一言で言えば、このプロジェクトは、道路と橋梁の保守用資機材 231点を購入する資機材調達プロジェクトであったといえる(予算のうち20%はスペアパーツの購入と配送に配分された)。1994年12月に完了したこのプロジェクトには、5億4,700万円(約500万米ドル)の無償資金が投入された。プロジェクト設計報告書には、「資機材の管理能力に貢献し、雇用を促進する」プロジェクトであると記されていたが、実際にはこれらの点を考慮した要素はプロジェクトには特に見あたらなかった。
b. プロジェクトの結果
資機材選定、調達、引渡しのみを行うプロジェクトとしては、明らかに成功である。JICA やケニア政府の職員とのすべての話合いでも、資機材ニーズの特定、資機材の調達、引渡しの面で、このプロジェクトは全般的な目標を達成したことが確認された。プロジェクトの報告書によると、当初のスケジュールは遵守され、コンサルタントの動員、資機材の選定、調達、配送、ケニア政府への引渡しの各段階で実質的な遅れは見られなかった。ケニア政府やJICAの技術者との話合いでも、適切な資機材一式が選定・供給されたという意見で一致した。但し資機材の一部は(プロジェクト設計の技術仕様には完全に合致していたものの)、ケニアの乾燥した土壌には合わなかったようである。例えば、以前購入されたグレーダーは期待ほど性能を発揮できなかったという指摘があった他、今回のプロジェクトで購入されたピックアップ・トラックには問題があったようである。このような問題は、次のような理由で起こると思われる。
- 特定のメーカー、あるいは特定の車両に必要なスペアパーツやサービスを提供できる業者がない。
- そのような業者がケニアにあっても、国内にその型の車両が十分な台数なければ、修理技術やスペアパーツを保持する動機づけを民間業者に望めない。
経済的恩恵という点では交通経済専門家の間で、道路保守プロジェクトは一般的に非常に高い収益率を達成するとの認識で一致している。例えば「ケニア都市交通改良プロジェクト」では、ケニア都市道路の定期的保守、修復、交通量改善などの各プロジェクトの収益率は41%であると見込まれている。したがって、日本の援助によるこのプロジェクトは、非常に高い収益の生成に貢献する能力を秘めている。このような恩恵は、資機材が調達され、適切に配分、管理、利用されて初めて実現するものである。資機材が入手できるか否かが大問題となるケニアでは、この点を熟慮すべきである。実際、このような問題があるために本計画が必要なのである。公共事業住宅省の道路部保守交通課(MTD)が道路資機材の管理と保守を任されている。このMTDは「資機材保守システム(EMS)」を開発し、資機材の在庫を「使用可能(SV)」、「使用不能で修理不能(US)」、「修理中(UR)」、「報告なし(NR)」、「事故(ACC)」、「使用不能だが修理可能(ER)」に分類して管理している。プロジェクト設計文書の中で、日本の援助で供給された資機材の状況を監視するメカニズムであると紹介されているのがこのシステムである。公共事業住宅省から提供された情報をもとに、このプロジェクトで購入された機材の一部の現在の状況をまとめたのが表3である。表が示すとおり、車両の65%が使用可能、26%は状況についての報告無し、5%が修理不能、2%が修理中または事故記録有り、1%が使用不能だが修理可能である。これは1994年に購入された、つまり供給から2年ほどしか経過していない資機材の状況である。
| クラス | SV | US | UR | NR | ACC | ER | 合計 |
| 102 | 22 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 34 |
| 202 | 29 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 41 |
| 203 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 405 | 23 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 35 |
| 803 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12 |
| 合計 | 80 | 6 | 2 | 32 | 2 | 1 | 124 |
(出典:ケニア政府 公共事業住宅省 保守交通課)
稼動機材がない理由としてよく挙げられるのは、スペアパーツの不足である。この問題を克服するため、このプロジェクトではプロジェクト総資金の20%をスペアパーツの購入に配分した。スペアパーツは「需要の期待度」に基づいて購入され、基本的な資機材と共に配送された。よいアイディアであったが、スペアパーツの多くは使用されることなく倉庫に保管されている。これら未使用のスペアパーツの交換(バーター)は車両サービスに不可欠なのだが、財務省の政策によって禁止されている。つまり貴重な未使用の資本が倉庫に眠ったままなのである。このことは巨額の機会費用を意味し、スペアパーツに配分する資金をより効果的に使用する方策について、さらに考察する必要があることを示している。EMSの状況報告書及びケニア政府やJICA専門家との議論で、資機材の保守・サービスの不十分さが、道路・橋梁保守のために購入された資機材の性能に悪影響を与えていることは明白である。これらの機材に必要なスペアパーツは資金不足で入手できず、一方倉庫には日本の援助で供給された不必要なスペアパーツが保管されている。このように、日本が供給した資機材にはケニアに実質的な経済的恩恵をもたらす潜在的能力があるという点では一致しているものの、この援助が最大限に力を発揮するためには克服しなければならない制度的・構造的な問題がいくつか残されている。次のセクションではその方策を探り、いくつかの提言を行う。
(3) まとめと提言
一般的に道路保守プロジェクトは実質的な経済的恩恵をもたらし、経済的収益率は41%にも上るという共通の認識がある。本報告書で評価している「道路・橋梁機材整備計画」は(純粋な資機材調達プロジェクトとしては)本質的に成功したと考えられる。改善すべき唯一の点は、車両や資機材の型式をケニア国内で保守・管理できるものに限定するということである。
プロジェクト設計報告書によると、資機材を保守するための公共事業住宅省の管理能力を向上させることもプロジェクトの目標のひとつだったが、この目標を実際に達成するための資金や技術支援を行う要素はプロジェクトに盛り込まれていなかった。車両や資機材の保守における非体系的なアプローチや日本の援助で購入された車両や資機材の現状から立証されたとおり、供給された資機材が一貫して保守・管理されることを保証できるよう、適切な動機づけや支援を行う必要があることは明白である。以下に述べるのは、考えうるオプションである。
オプション1:資機材を供給するだけではなく、車両や資機材の保守と管理に重点を置いた技術支援も含めたプロジェクトに範囲を広げることも可能である。こうすることで、プロジェクトで購入された車両や資機材が適切に保守・管理されることを保証する組織的能力やシステムを育成することができる。このプロジェクトの設計書には「管理能力を高めること」が目標のひとつに掲げられているが、実際のプロジェクトには技術支援の部分が含まれていなかった。
オプション2:車両保守のコストを最初からプロジェクトに含めておく。これはケニアに置けるドイツの技術支援にならったアプローチである。ドイツは最初の3年間について、車両だけでなく車両保守を含めたパッケージを供給した。この方法はケニア政府を保守の責任から解放し、保守を地元の代理店網に任せて、必要な資金を提供するというものである。この方法の長所は、適切な保守が保証され、その車両がもたらす恩恵を完全に享受できることである。短所は、コストがかかる上、供給された資機材を保守しよういう制度的な動機づけ(および「所有意識」)がMTDに育たないということである。したがって、これは長期的問題に対する短期的解決にすぎない。
オプション3:被援助国の政府に正しい動機づけを与えるには、購入・供給を一度に行うのではなく、適切な保守・管理を行うことを条件にして段階的な供給を行う。つまり、供給を2回に分けて実施し、1年目に車両・資機材の50%を供給し、その後2年間、ケニア政府が保守と車両の配分を適切に記録するという条件を満たせば、残りの 50%を供給することを契約に盛り込むことである。このような条件付きの契約は公共事業住宅省にとって、きちんと保守・管理を行おうという適切な動機づけになり得る。これと同様の条件付き契約は、公共事業住宅省の地方作業所にも応用し得る。つまり、既存の資機材を体系的に保守・管理できた地方作業所にのみ日本から供給された車両を配分するのである。こうすることでよい意味での「競争心」を創り出すことができ、適切な保守・管理を促すことができる。しかし、これはMTDが自ら保守を行わねばならないという意味ではなく、保守作業の一部を民営化することも可能である。大切なのは、MTDが保守の「創出」ではなく、保守の「供給」に責任を持つということなのである。動機づけとしての条件設定は、世界各国の構造改革やセクター政策ローンで非常に効果的であることが証明されている。
オプション4:グラントの一部をスペアパーツに配分するのは合理的であるが、これをさらに効果的にする方法がある。例えば、最初の年に「需要の期待度」に基づいて20%分のスペアパーツを購入するのではなく、同額をスペアパーツ基金として2~3年後に使用するのである。こうすれば、不足がちな資金が倉庫に眠るスペアパーツに化けてしまう問題は回避できるだろう。例えば、最初の年には消費型のスペアパーツ(オイル・フィルター、エア・フィルター、点火プラグなど)を2年分購入する。この方法は、JICAの資金を受けてフィリピンで実施された同様のプロジェクトで用いられた。フィリピンでは最初の総コストの5%が消費型のスペアパーツに充てられた。残り15%は2~3年後に必要になったスペアパーツを購入するために保留する。2~3年後になって初めて、非消費型スペアパーツを特定することができるからである。
オプション5:資機材を適正に選定し購入することが、この種の調達プロジェクトには非常に重要である。しかし、車両の技術的仕様を決定するだけでは不十分で、どの車種にせよ、被援助国で管理・保守ができることが重要である。この問題を克服するためには、供給する型式を国内でサービスできる型式に限定するという条項を技術仕様に追加する必要がある。このことで、いくつかのメーカーや型式を排除することになるが、ケニア国内でより容易に保守できる車両を適切な組み合せで供給することができる。別の方法としては、現地駐在のJICA専門家やケニア政府職員を入札手続きに参加させ、資機材の支援や車両数の面で現地の知識を取り入れることが考えられる。
(4) 将来に向けての考察
"Strategic Plan for the Roads Sector"(ナイロビ:ケニア政府1996年)にも反映されているケニア政府の政策転換を考え合わせると、道路セクターに対する援助の将来的役割を注意深く探ることが重要である。道路セクターには今後も技術的・財政的援助が必要だが、援助の性質や範囲については、現在ケニアに導入されつつある新しい戦略的指針に沿った改変が必要である。
ケニア政府の新しい道路セクター政策は、いくつかの劇的な変化を遂げつつある。道路セクターの全般的構造や性質を変革しようとする勢いがある。また、道路保守、「営利化」、民間セクターとの契約などに重点が置かれるようになり、MTDの公共セクター内での位置づけが変わり、資機材/プラント・プールを営利事業化し、とりわけ道路保守の責任を委任しようという動きが見られる。さらにケニア政府は、ケニア全土の道路保守に必要な実質的な財源を確保するため、「道路保守課税基金」を制定した。また同時に、道路保守を地方自治体に委任する可能性も探っている。1997年、ケニア政府は世界銀行の援助によって「ケニア都市交通改良プロジェクト(KUTIP)」を開始している。
これらのさまざまな変化によって、日本は援助の役割や実施方法を再評価する必要に迫られるだろう。ここまでの3つの資機材供給プロジェクトは、公共事業住宅省が道路や資機材の保守を自力で行う古いシステムのもとで設計・実施された。ケニアの道路セクターの変革に合った援助を実現するため、日本は今後、さまざまなプロジェクトの在り方を考えてゆくことが重要である。
2.プロジェクト名:第3ナイロビ給水プロジェクト
(「ナイロビ給水事業計画」88年度、有償)
(1) 序文
1970年の「第1ナイロビ給水プロジェクト」および 1978年の「第2ナイロビ給水プロジェクト」の成功にもかかわらず、ナイロビの急速な都市化と飲料水に対する潜在的需要の増加によって、ケニア政府は首都ナイロビの給水量を拡大・改善する必要に迫られている。事実、「第2ナイロビ給水プロジェクト」が完成に近づいた1984年の時点で、既存の給水能力を需要が追い越すのは時間の問題であった。そこで、世界銀行の「第3ナイロビ・エンジニアリング・クレジット」によって資金を得たナイロビ市は1985年、「第3ナイロビ給水プロジェクト」に向けた調査と計画策定をコンサルタントに依頼した。
このエンジニアリング・クレジットのもとで計画された「第3ナイロビ給水プロジェクト」には、次のような工事が含まれていた。
- ティカ・ダム:ローラーでならした 63メートルの土塁堤防の建設。貯水量は7,000万立方メートル。
- 原水アクアダクト:ティカ/チャニア間トンネル、チャニア/マタアラ間トンネル、マタアラ/ンゲトゥ間パイプラインの3工事から成る。
- 処理施設の強化:ンゲトゥ処理施設の処理能力を1日当り22万立方メートルから46万立方メートルに増強する。
- 処理水の移送:ンゲトゥとギギリを結ぶ送水パイプの水量を拡大する。キアンブ貯水池を既存のンゲトゥ/ギギリ間パイプラインに連結する。
- 最終貯水池:キアンブ近郊に新しい最終貯水池を建設することで、貯水量を4万6,000立方メートル増やし、総計22万4,000立方メートルにする。
- ダンドラ下水処理プラント:ダンドラ下水処理プラントを修復・拡張し、処理能力を1日当り9万立方メートルに引き上げる。
これらの工事の完成によって、2010年までにはナイロビに十分な飲料水を供給できると期待されている。プロジェクトの全費用は2億1,600万米ドルと概算された。世界銀行の調整のもと、必要な資金は欧州投資銀行(EIB)、アフリカ開発銀行(ADB)、世界銀行(国際開発協会を通じて)、海外経済協力基金(OECF)が供給することになった。日本政府はOECFを通じて約4,300万米ドル(プロジェクト総費用の約20%)の有償資金を供与することに合意した。プロジェクトの詳細を見る前に、次項ではまずナイロビの上下水セクターの背景を概説し、大規模な海外援助による最初の3件のナイロビ給水プロジェクトから得た教訓についてまとめる(表4参照)。
全般的に見て、最初の2プロジェクトは給水量の拡大という当初の目標は達成した。しかし、両プロジェクトとも調達手続き、入札の評価、契約認証の決定が大幅に遅れるという事態に直面した。「第1ナイロビ給水プロジェクト」では(配水に関するプロジェクト事業の拡張が決定されたため)3年半の遅れ、「第2」では2年半の遅れが生じ、ケニアシリング建てで26%(米ドル建てで2%)ものコスト超過を招いた。「第3エンジニアリング・プロジェクト」にもわずかながら遅れが生じ、結果的に「第3ナイロビ給水プロジェクト」の実施スケジュールが1995年~2005年の期間に変更されることになった。しかし、この「第3エンジニアリング・プロジェクト」によって、上下水道部は制度的な基盤の改善や職員研修によって、事業効率を向上させることに成功した。その後、このプロジェクトには、料金を徴収できない水(non-tariff water, NTR)を減らすために漏水を検出する事業が加えられた。1978年、水道料金体系が改訂され、水道料金が値上げされたため、上下水道部は財政的な自立が可能になった。
| プロジェクト名 |
第1ナイロビ給水プロジェクト (承認:1970年) (完了:1977年) |
第2ナイロビ給水プロジェクト (承認:1978年) (完了:1982年) |
第3ナイロビ・エンジニアリング・プロジェクト (承認:1985年) (完了:1991年) |
第3ナイロビ給水プロジェクト (承認:1989年) (完了予定:1998年) |
| 海外の援助機関 |
世界銀行 (ローン714-KE) |
世界銀行 (ローン1520-KE) |
世界銀行 (クレジット1566-KE) |
世界銀行 (クレジット2060-KE) OECF、EIB、ADB |
| プロジェクトの目標 | 増大する需要に応え、財政運用面も含む上下水道部(WSD)を強化するため給水システムを拡大・改善する。 | ナイロビ市の飲料水供給量を増やす。配水システムを改善・拡大する。上下水道部の会計システムおよび管理システムを改善するにあたって、その設計や実施の研修や支援を行う。 | 上下水道部が第3段階の給水投資プロジェクトに備えるための援助を行う。具体的には、急増するナイロビ市の1990年代半ばまでの飲料水需要に応える。第3段階のプロジェクトを請け負えるだけの効率と能力を向上させるため、上下水道部の事業および財政管理を強化する。長期的な体系的発展を目指して提言を行う。 | ダムや貯水池を新たに建設することで水源を拡大し、ナイロビ市への給水量を増やす。配水システムを拡大し、低所得者層にも水道管を通じて水を供給する。ダンドラ下水処理プラントを拡張し、ナイロビ市の衛生状態を維持する。ダム建設に伴う住民の移住を支援する。上下水道部を改善するために、研修や技術支援を行う。 |
| プロジェクトの総額 | 2,020万米ドル | 2,940万米ドル | 860万米ドル | 2億1,600万米ドル*(* プロジェクトがまだ完了していないため概算値である。) |
「第3ナイロビ給水プロジェクト」については、表5に示したとおり、このプロジェクトはほぼ完了しているものの、まだ未完成の事業がいくつか残っている。世界銀行の"Aid Memoire"(1997年2月付)によると、未完成の事業が適切に完了するようプロジェクトの期限が1998年6月まで延長されたという。
「第3ナイロビ給水プロジェクト」の完了に伴い、飲料水の総供給量は 2010年までの需要を満たせるほどに拡大した。しかし、プロジェクトがほぼ完成しつつある中、ナイロビ市上下水道部では飲料水をナイロビ市東部から西部へ移送するためのインフラ整備に向けて追加資金を獲得しようという議論が始まっている。「第3ナイロビ給水プロジェクト」によってナイロビには十分な給水量が実現したのだが、人口に対する飲料水の配分が明らかな問題となって浮上してきた。つまり、「第3ナイロビ給水プロジェクト」の結果、ナイロビ市東部は十分すぎるほどの飲料水供給を受ける一方、市西部では供給がますます逼迫している。そこで市は、既存のインフラを改善し、新たに供給された飲料水を市西部に振り替えようと考えているのである。総工費は明らかになっていないが、ナイロビ市はOECF(ナイロビ)に資金提供の可能性について打診しているようである。
(2) 評価結果
a. プロジェクト
「第3ナイロビ給水プロジェクト」の構造は「並行資金調達」の方式を採用し、各機関が特定の事業の責任を担うことで合意された。OECFは53億4,200万円(約4,500万米ドル)を提供してプロジェクトに参加することに合意した。「第3ナイロビ給水プロジェクト」の総費用(2億2,160万米ドル)の約20%を占めるOECFの資金は、水道本管の建設に充てられた。「第3ナイロビ給水プロジェクト」は当初1987年の開始を目指したが、工事開始は1989年までずれ込み、1996年に一応の完成を見た。日本が援助した事業(水道本管)は、1993年に完了し認定された。
b. プロジェクトの結果
純粋な水道本管建設プロジェクトとして見れば、このプロジェクトが成功を収めたのは明らかである。水道本管工事は完成し、1993年12月9日、Defects Liability Certificateが発行された。OECF、世界銀行、ケニア政府職員と共に話し合った結果からも、水道本管を建設するこのプロジェクトは成功したことが確認された。また、ケニア政府が財務省を通じて定期的に返済を行っていることから見て、純粋な有償資金契約としても成功したと言える。
| 契約番号 | 契約内容 | 財政支援機関 | 当初契約額 | 契約の状況 |
| C207 | 取水口、トンネル、アクセス道路 | 欧州投資銀行 | 359.1 | 完了(1993年9月30日)、支払:未了 |
| C208 | ティカ・ダム | アフリカ開発銀行及びナイロビ市 | 829.1 | 完了、Defects Liability Certificates発行(1996年4月10日)、支払:未了 |
| C209 | ンゲトゥ下水処理施設の電気機械設備 | 世界銀行及びナイロビ市 | 133.6 | 実質的に完了(1996年6月30日) |
| C210 | ンゲトゥ下水処理施設送水本管 | 世界銀行及びナイロビ市 | 143.9 | 実質的に完了(1996年6月30日) |
| C211 | 送水本管 | OECF | 783.6 | 完了、Defects Liability Certificates発行(1993年12月9日) |
| C212 | 貯水池の建設 | 世界銀行、ナイロビ市 | 120.0 | 小規模な工事を残して進行中。 |
| C213/1 | 配水本管の建設 | 世界銀行、ナイロビ市 | 139.6 | 最後の管を95年12月に埋設。最終的な経費は計算中 |
| s214/a | ギギリ・ポンプ・ステーションの高電圧設備 | 世界銀行、ナイロビ市 | 18.6 | 1995年6月30日完了 |
| s214 | ギギリ・ポンプ・ステーションの電気機設備 | 世界銀行、ナイロビ市 | 27.76 | ポンプ稼動開始(1995年7月)、Taking Over Certificate発行(1995年12月) |
| C215 | ギギリ・ポンプ・ステーションの建設 | ナイロビ市 | 10.1 | Taking Over Certificateが間もなく発行 |
| C217 | 職員の住宅及び事務所 | ナイロビ市 | 74.6 | 実質的完了(1995年3月) |
| S218 | 管および付属品の供給・引渡し | 世界銀行、ナイロビ市 | 122.2 | 最終的計算書をナイロビ市に提出(1996年7月) |
出典:世界銀行Aide Memoire(1997年2月7日)Annex 3
総合収支分析の観点から見ると、管による給水プロジェクトはおおむね非常に高い経済的収益を上げている。世界銀行の"Staff Appraisal Report"によると、予想される経済的コストと収益の35年にわたる分析に基づいて算定された「第3ナイロビ給水プロジェクト」の予想経済収益率は、12.6%である。総体的に、給水プロジェクトの財政的収益率は低い(運用コストを賄うため一定レベルの補助金が必要になることが多い)が、経済的収益率は高い。このように大きな差が両者に生じるのは、管から給水を受けることの社会的利益の高さと、それに比べた料金の低さのせいである。
「第3ナイロビ給水プロジェクト」が直面する大きな問題は、物理的なエンジニアリングの問題ではなく、上下水道部の財務・管理に関連する問題である。同様の問題は給水セクターにおける国際援助開始時期から指摘されていた。1970年代初頭、世界銀行が初めて援助をする際の条件のひとつが、上下水道部(WSD)の新設だった。もうひとつの条件は、特別な給水基金(給水セクターからの収益による別個の基金)を設立することであった。当初は、この給水基金が収益の流れを十分に分離し、給水プロジェクトの債務、日常のシステム保守に必要な費用、給水事業の運営費用など、すべての支払を保証するものと期待されていた。使途不明の水や未収金の削減など、さまざまな財務上の条件がつけられた。しかし、プロジェクト開始以来、ケニア政府はこれらの財務上の条件を守りきることができなかった。事実、財務上の条件を守れなかったことから、世界銀行は2度にわたって信用供与を見合わせた(1996年10月付"Aide Memoire"参照)。
財務面の諸問題は「ナイロビ給水プロジェクト」のみならず、ケニアにおけるすべての給水プロジェクトの実施を危うくするものである。将来的には、ケニア全土の給水プロジェクトに対する資金援助がすべて危機に陥る。このことは何を意味するのか。ケニア政府の"Report of the Task Force on Mutual Indebtedness between Local Authorities, Government Ministries and Parastatals"によると、ナイロビ市はケニア政府や準国営機関に対して純負債状態にある。地方自治体がケニア政府に負っている全債務の92%がナイロビ市の債務であり、ナイロビ市の債務の95%は、国際援助によるプロジェクトに関連したものだという。ナイロビ市の債務の事実上すべてが給水セクターの事業から発生したものである。1996年12月現在、ナイロビ市はケニア政府に対して14億ケニアシリングの債務があると言われている。
財務省との話し合いで判明したことだが、ナイロビ市は「第1ナイロビ給水プロジェクト」および「第2ナイロビ給水プロジェクト」の債務返済を延期した上、「第3ナイロビ給水プロジェクト」については一切の返済を行っていない。「第3」の返済を行わない理由は支払猶予期間のためであると思われたが、話し合いの結果、猶予期間はあくまで原則で、ナイロビ市は工事期間中も利息の支払いを行わなければならなかったのである。
ナイロビ市が給水プロジェクトの債務返済を行わないことによって、非効率的で不公平な飲料水の配分、脆弱な財務秩序、そして良からぬ先例がケニアにもたらされた。このことはつまり、(1)ケニア全土の一般納税者がナイロビ市民のみが享受する飲料水に補助金を交付していることになる。(2) 利用者負担の原則が遵守されないことになり、ケニアにおける非効率的で不公平な飲料水供給を助長する。(3)債務返済を行わないことで、ナイロビ市は水道料による収入を市財政の流動資産として保有することになり、歳出の合理化や歳入の結集を図る必要がなくなる。(4)良からぬ先例が、ケニアで実施される他の給水プロジェクト(すなわち、日本の資金によるナクル給水プロジェクト、世界銀行の資金によるモンバサ給水プロジェクトなど)に悪影響を与え、ナイロビ市が支払い責任を負わないなら、自分たちも支払わないということになりかねない。このような事態になれば、有償資金に基づくインフラ整備援助は深刻な打撃を受けるであろう。
(3) まとめと提言
純粋な土木建設プロジェクトとしては、OECFの援助を受けたこの「第3ナイロビ給水プロジェクト」は成功したと言える。また、社会経済的な収支分析というより広い観点から見ても、このプロジェクトが一旦稼動すれば、成功を収めると思われる。プロジェクトが経済的・社会的利益を確実にもたらすため大幅な改善が必要な領域は、管理、財務、制度などの非エンジニアリング部門にある。この部門は初期の段階から指摘されていたとおり、プロジェクトの利益を実現、持続させるための鍵である。
給水事業の資金調達や地方自治体の将来の債務返済にとって非エンジニアリング部門が重要であることから、問題の解決は非常に重要である。したがって、国際的融資機関は非エンジニアリング部門に対してより広範に注目してゆくべきである。現在、国際融資機関の中で資金援助に条件をつけることを行っているのは、世界銀行のみのようである。そのため、世界銀行は非エンジニアリング部門に積極的に目を向けている。一方、筆者の理解するところでは、OECFは貸付を行う際、目標を達成するための政策的・財政的条件づけをほとんど行っていない。途上国の開発に特化しているOECFにとっては、融資契約に財政的・政策的な条件を加えることで非エンジニアリング部門に介入する努力を始めることが重要である。もしこれを行わなければ、OECFは開発援助機関ではなく、単なる融資機関としてのみ名を知られることになるであろう。開発援助で最大限の効果を上げたいとする日本にとって、関与しないことは、その機会を失うことである。
OECFは「第3ナイロビ給水プロジェクト」のような共同融資プロジェクトをより積極的、前進的に監督することができるはずである。プロジェクトの主な出資機関として、OECF職員は監督ミッションにもっと参加し、プロジェクトの進捗状況報告書や世界銀行の"Aide Memoire"(監視ミッション書類)などのコピーを監視・検討すべきである。また、OECF職員は折にふれて世界銀行の監督ミッションに同行し、世界銀行との間で書面による契約を交わした上で、関連する全ミッション報告書のコピーを受け取ることを勧める。そうすることで、OECF職員はプロジェクトにより深く関与することができるであろう。

