10. 南太平洋の医療(フィジー・キリバス)
(現地調査期間:1996年12月2日~12月15日)
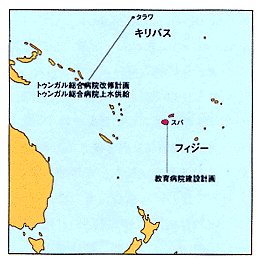
■東京女子医科大学国際環境・熱帯医学教室主任教授 小早川 隆敏
<評価対象プロジェクト>
| プロジェクト名 | 援助形態 | 協力年度、金額・年度 | 協力の内容 |
|
教育病院建設計画 (フィジー) |
無償資金協力 |
1991年度、10.87億円 1992年度、10.15億円 |
CMW病院は、フィジー最大の総合病院であると同時にフィジー医学校の臨床教育施設であるが、老朽化が著しくその機能を果たし得ない状況であった。このため、新病棟を建設し、必要な医療機材を供与することにより、同病院の機能回復、拡充を図った。 |
|
トゥンガル総合病院改修計画 (キリバス) |
無償資金協力 |
1989年度、9.21億円 1990年度、4.85億円 |
トゥンガル総合病院は、キリバス唯一の病院であり、保健、医療サービスの中心であるが、老朽化が著しく、内部設計も効率的ではなかった。このため、同病院を建て替えるとともに、必要な医療機材を供与することにより、同病院の機能回復、拡充を図った。 |
|
トゥンガル総合病院上下水道改善計画 (キリバス) |
無償資金協力 | 1992年度、1.96億円 | トゥンガル総合病院では、改修後の活動の活発化に伴い、必要な上水両の確保が困難になった。このため、雨水を診療活動に利用するために必要な施設、機材を整備した。 |
1 フィジー教育病院
フィジー医学校、The Fiji School of Medicine(FSM)は創立以来107年の歴史を有し、一環して、フィジー国及び太平洋島嶼国の医師、歯科医師及び各種パラメディカルの人材を養成して来た。
FMSの全てのコースの在籍者も年を追うごとに増加してきた。しかしながら学生数の増加に伴っての予算の増加は十分でなく且つ、施設、機材、教員数、運営、教育内容も満足出来ぬ状態が続いた。
そのような背景の中、1988年に同国保健省(MOH)はWHOの支援のもと、“Plan of Action for the Development of the Fiji School of Medicine as a Centre for the Education of Health Personnel in the Pacific”を策定した。この計画はカリキュラムの改善、学部への格上げ創設、運営支援施設機材の改善からなっており、1989年にフィジー国政府より承認された。
これを受けて日本は教育病院の建設及びそれに対する主要な機材の供与を行い学生及び卒業生の教育訓練活動を支援することとした。尚、ニュージーランド(NZ)は学生寮を建設、WHOは引き続きカリキュラムの改善と助言を行い更に、豪州、WHO、NZは教員の派遣を支援し、且つ域内島嶼国からの学生への奨学金の援助を行っている。
我国の援助は無償資金協力によって、Colonial War Memorial Hospital(CWMH)をFSMの臨床教育病院として、更に中央・東部地域(MOHは医療行政を行う上で国土を西部、中央・東部、北部に分けている)の地域病院(Divisional Hospital)かつフィジー国全体のレファラル病院としての各種疾病に対する診療に関する部門の施設改善、および、医療機材の調達を実施し、その機能を回復・充実させることにあった。
尚、フィジー国は本来所得水準が高い為、一般無償は原則的に困難であるが、本病院がFMSの教育病院として域内島嶼国からの学生の教育・訓練の場として裨益効果があると判断され、実施されたものである。従って、本調査は、CWMHがフィジー国の中心医療機関として如何に機能維持・発展がなされているかの観点もさることながら、FSMの医学生、各種パラメディカルコースの学生、更には同じく我国の無償援助で建設供与されたフィジー看護学校、Fiji School of Nursing(FSN)の学生、及びそれら卒業生の教育研修の場としての評価を総合的に行うものとした。尚、CWMHの完成引渡しは、1993年12月6日で、本調査は3年経過した時点で行われたこととなる。
(1) 現状
この援助により救急部門、総合外来、特別外来(主として退院後の患者のフォロー)、放射線診断部(CT1台、超音波1台、X線4台含む)、臨床検査部、薬剤部、外来受付及びカルテ保存部門が旧病院より移り、その結果として1992年の416ベッドから22%増加し現在507ベッドとなった。
更に従来の旧病院には教育専用の施設はなかったし、病棟は極めて混雑し、働く臨床医も教育に手を割ける精神的物理的環境になかったが、新病棟には救急部門、外来、放射線診断部等に大講堂と幾つかの小講義室があり、外来患者を用いてのよりよい教育環境が整備された。
職員数に関してはTable 1に示す通り定員1,114人中パートの循環器専門医を含めても96名で、1,051人が充足している。職種別にみると医師数は一時的に大幅に減少したが、現在も1990年と比し3名減となっており、且つ34名が外国人医師であり、依然として充足は課題である。奈央1990年時に欠員であった整形外科専門医は補充されている。その他例外的に以前CWMHコンサルタントとして働いており定年退職した循環器専門医を週一回半日、パートタイマーとして雇っている。現在の法律では、民間で働いている医師は公立病院でパートタイム勤務は出来ぬこととなっているが、このケースは、専門性により例外的にMOHで認められている。国全体としては概して医師数は充足しているとのことで、この規則の改正が望まれている。看護婦は1990年時に比較して実数70人の増加であるが、定員に20人不足である。但し、WHOの基準では460~470人が必要と考えられる。問題は看護婦は外国へ出るとフィジーでの給料の3倍(8,000→24,000フィジードル)になるため流出の傾向がある。以上の職員に要する経費は1170万フィジードルでこれはCWMHの総経費の76%に達している。
| 職種 | 実数 | 定員 | 欠員 |
| 医師 | 95 (99) | 111 | 16 |
| インターン医師 | 13 (11) | 13 | – |
| 看護婦 | 393 (323) | 413 | 20 |
| 歯科医 | 8 (6) | 11 | 3 |
| パラメディカル | 138 (98) | 156 | 18 |
| バイオメディカル | 5 | 5 | – |
| 事務 | 41 | 47 | 6 |
| その他 | 358 | 358 | &nmdash; |
| 計 | 1,051 | 1,114 | 63 |
現在医師の海外流出を防ぐため、南太平洋だけでなく豪州、NZで承認される卒後1年間の臨床diploma課程を新設し、既に1996年1月産婦人科、小児科、麻酔科を開始、更に1997年には内科、外科を新に開設する。このdiploma取得医は更に2~3年の修士課程を豪、NZで修めるがこれはフィジー政府との取り決めで帰国の義務があり帰国後専門医として任につくことになる。
次にCWMHの利用状況であるが、1995年度は外来患者は300,000人を越し、入院患者も21,000人を越した。各々1989年時と比較すると平均17%、30%の増加となる(Table 2)。
| 1989 | 1993 | 1994 | 1995 | |
|
外来 一般外来 特殊外来 合計 |
170,142 72,840 262,982 |
166,935 116,371 283,306 |
249,334 131,374 380,708 |
175,164 125,285 300,449 |
| 入院 | 15,011 | 19,814 | 23,236 | 21,845 |
| 平均病床占有率 | 81% | 69.73% | 58.00% | 70.30% |
| 平均在院日数 | 8.8日 | 6.1日 | 5.4日 | 5.8日 |
| 病床数 | 402 | 402 | 461 | 496 |
| 放射線件数 | 56,580 | 70,230 | 61,734 | 64,606 |
| 手術数 | 5,657 | 7,851 | 7,417 | 6,337 |
| 臨床検査 |
33,676/ 1月のみ |
955,211 | 1,201,728 | 1,343,757 |
1995年に於けるCWMHの運営経費は1,520万フィジードルである。このうち76%にあたる1,170万フィジードルが人件費である。これらのための歳入は殆ど国庫からで、利用者からの収益によるものは2%にすぎない。これは診断に関しては無料で、検査、薬品代、手術代は個人負担であるが、医療費の負担が困難であると認められた人々や、15歳以下の小児、産前産後の婦人、公務員は無料となっていることが大きな要因である。尚、特別室はバストイレ付きVIP用の2室の個室が25フィジードル、バストイレなし個室10フィジードル、同2人部屋7フィジードル、差額大部屋4フィジードルである。何れも料金には食事を含む差額ベッド費で、当然検査手術等の費用は別となる。これに対し最近の調査では約50%の患者はサービスの質が保たれるなら医療費負担を諒としており、将来への運営改善の材料となろう。
更に、職員の充足不足と並び技術水準も向上し、従来技術不足並びに設備不足の為、重症患者を豪州、NZへ搬送することが多かったが、現在は放射線治療の為と心臓バイパス手術以外はリファーする必要がなくなっている。
又、特記すべきは、施設の使用に対する清潔の観念は十分に行きわたっており、最もその尺度となるトイレも極めて清潔に使用管理されており印象深かった。
以上CWMHの現状を1996年8月、フィジー国の監査院が250人の外来患者を対象に評価をさせた結果をTable 3に示す。
| 外来サービスと施設 | 評価 | |||
| 劣る(%) | 優(%) | 良(%) | 無回答(%) | |
|
待ち時間 受付けのサービス トイレの施設 衛生・清潔度 看護婦サービス 医師サービス 薬品の充足度 指示・情報 |
62 15 2 1 11 10 18 8 |
20 37 26 28 33 28 32 42 |
14 40 55 68 47 54 30 33 |
4 8 17 3 9 8 20 17 |
この結果では、62%の患者が待ち時間の長さに不満を抱いている以外、他の要素に関しては極めて高い評価があり、特に便所の設備及び衛生・清潔度に関しては殆どの患者が満足していることが示された。
次にこのような無償資金援助で病院を建設した際に最も問題となる設備、機材の維持等の現状に関し述べる。
メンテナンス:水、電気、蒸気及び日常の清掃を除くインフラは通信建設・運輸省の公共事業局Public Work Department(PWD)が行うが、機器の点検、維持、補充はCWMHのBiomedical Engineering Unit(BEU)が行い、独自の工場を持ち、5人の技師が専属で働いている。その中には豪、日本で研修を受けた者もいる。この数年で能力的には、向上がみられ、現在の処、部品に関しても時に豪からとり寄せることもあるが問題は生じていない。しかし、開院以来3年であり、部品の問題は5年を過ぎた当りから増加すると考えられる。現在国家的にPreventive Maintenance Program(予防的維持計画)が施行され、全ての病院で機器の安全点検と安全基準に合わぬ機器の取り換えが行われている。更にBEUは全ての機器の95%に関する情報をコンピュータへ入力しているが、この入力情報には、機器のタイプ、製造会社、モデル、連続番号等は入っているが、機器の獲得期日、購入価格、推定使用可能期間、維持点検の頻度、経費、原価消却価格は入力されていない。
BEUは専門性、能力的に秀れ、向上しているが、一方で、使用者が機器使用のノウハウに欠けることがあり、特に先端的機器に於て、それに起因する問題が生じているようで使用者側への教育も必要である。
又、現在のCWMのBEUの貯蔵スペースが狭く、新しい工場の建設が始まる予定とのことである。更に現在指導的地位にある二人が間もなく定年になる為、後継者が一人豪州で研修中である。
1995年、フィジー国に南太平洋諸国の保健大臣が集まった際、域内でのFSM、CWMHの重要性及びその増加に鑑みFSM、CWMHを域内の「Original Medical Institution」と位置付けることが合意され、ついで、フィジー政府で承認された。これによりFSM、CWMHを1998年迄にfull economical autonomy/one-line budget(独立採算)とする。当面、1997年度は人件費以外を手当し、この決議を法政化し、1998年の全面実施に向け対応する。これが実現すれば、国内機関としてよりも、域内国際機関としての位置づけが強くなり独自性が期待し得るが、76%が人件であり、完全実施は容易ではなかろう。
冒頭述べた如くCWMHに対する無償資金協力は、フィジー国が、高所得水準のため、本来は一般無償資金協力は、原則的に困難なる処なれど、域内周辺島嶼諸国からの学生を多く受け入れているFSM及びFSNの臨床研修病院であるところから域内への裨益効果が期待される処から実施された。従って、主としてFSMの現状を把握し、その将来への展望と、現在の域内への裨益度を調査することは我が国のFSM⇔CWMHへの将来の協力への提言となり得ることで肝要なることと思料される。
現在FMS は主として8つの専門性のもと、17種の教育課程をもっている。因みに8つの専門性とは医学、歯学、放射線学、薬学、物理療法学、臨床検査学、栄養学、環境衛生学である。
1994年時で17コースの全在籍学生数は488人である。そのうち350人(71.7%)がフィジー国出身で138人(28.3%)が域内島嶼国の出身である。
これら域内島嶼国の内訳は、ソロモン群島国、バヌアツ、西サモア、アメリカサモア、トンガ、ツバル、クック諸島、キリバス、ナウル、トケラ、ミクロネシア連邦、マーシャル群島及びミヤンマーの13ヵ国である。しかしながら、これら138人中98人(71%)はソロモン群島国、バヌアツ、西サモア、アメリカサモア、トンガの5大島嶼国の出身である。
現医師養成課程の精度は、新旧併存しており、新しいカリキュラムの特徴と併せ述べることとする。旧課程の医師養成コースMBBS(Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery)は最後の学生が1995年に卒業し、現在はPSP/MBBSと呼ばれる新課程となった。この新課程は2つの段階があり教育内容としては医学生は先ず3年間のPCP(Primary Care Practitioner)課程を終え、更に1年間(1997年から半年間)の保健所地域病院で臨床及び予防医学の研修を行う。そしてその計4年間の課程を終了した者にPCPの資格を与える。その後更にPCP取得者の中から希望者はFSMに帰り2年間の医学教育を受けMBBSの資格称号を得る。
このように1990年にWHOの支援で行われたカリキュラムの改変は主として地域保健に重点を置き、最初の3年間のPCP課程は、FSMでの座学、実習以外多くの時間を保健所での地域保健実習に割いている。
その次の4年次の1年間(1997年からは半年)は全面的に地位会内で働くが、他の島嶼国出身者は一旦国に帰り、出身国での地域保健活動を行う。その残りの5、6年次はCWMHで臨床実習が行われている。この地域保健重視はPCP/MBBS課程だけでなく他のパラメディカルコースにも適応されている。この新カリキュラムは現実対応優先のProblem based learningで且つ地域とより密接に関連し、地域内での健康ニーズを明らかにし、解決策を求めていく方法といえる。
この新課程のもとに1994年に最初のPCP終了者が出、最初のMBBS卒業生は1996年12月に出た。1996年度の終了/卒業生の内訳はPCP課程36人中17人、MBBS課程18人中4人が他の島嶼国出身者であった。
次に教職員の充足状況であるが、1994年現在68の専門職定員がある。その内訳は43が教育職、6が技術職、19が事務職である。これに加え28の非専門職定員がある。従って総定員は96であるが68の専門職定員中15の欠員があり、そのうち12が教育職で、2が技術職、1が事務職となっており、とりわけ教育職の不足は大きな問題である。
FSMの施設の老朽化、及び教育機材の不足はCWMHが立派であるだけに目立っている。一部の学生寮だけはNZの援助で新設されているが85%の学生を収容している為、古い学生寮は4人部屋で落ちついた勉学環境にない。図書館に関しては、先端的な学術書もなく、量的にも充分とはいえぬまでも、各分野の主要定期刊行書は講読されており、不合格とはいえない。幾人かの学生に質問した処、概して教育環境には満足しているが、解剖、免疫学等、重要な基礎医学の教科書が内容的に古いことを指摘し改善を望んでいた。
(2) まとめ
1) CWMHは施設機器はよく管理維持され利用度も順調に増加している。とりわけ清潔度に関しては満点に近い印象がある。尚全体として日本政府の無償援助で建設された他の国々の病院に比べ格段に管理運営が秀れていると考えられる。
2) 機器の維持に関しては体制・能力的にも充分と感じられるが部品の交換等の問題点は更に数年後に生じる可能性はあろう。
3) 職員も徐々に充足しているが、医師を始め、更に定量充足に向け雇用を進める必要がある。
4) full economical autonomy/one-line budgetの最終実施成果は興味をもってみる必要がある。
5) CWMHと機能的に車の両輪を形成するFMSのハード、ソフトへの協力が大いに望まれるが豪州の長年の関わりもあり、日本の効果的な協力関与の形態をとるのは容易でないとの感がある。
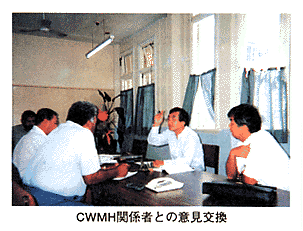
2 キリバス共和国トゥンガル総合病院
キリバス国の保健・医療体制はプライマリー・ヘルス・ケア (PHC)を担当する村落福祉グループ (Village Welfare Group)、その上に島ごとの診療区に設けられた診療所があり、更にその上に半径5キロメートルの範囲内の保健医療を行う保健所があり、これらを統轄した核として、トゥンガル総合病院(Toungal Central Hospital:TCH)がある。TCHはキリバス国唯一の第3次医療サービスの提供が可能な総合病院であり、全国の第1次、2次医療機関からの患者の受入れを行っているが、TCHで治療可能な患者は1996年時点で年間5名はニュージランド政府負担、更に5名はキリバス政府負担でニュージランドに移送加療される体制となっている。TCHには更に保健省、WHO事務所、看護学校等全ての国の保健医療機関が集っている。しかしながらTCHは築後30余年を経て諸施設は老朽化し、また、医療・検査機器の故障及び不足により医療機能の低下をもたらしたため、改修が1989、1990年にわたり、更にその後のTCHの活発化に伴う上水需要増大に伴い雨水集水設備、受水槽、送水ポンプの整備等が1993年度に日本政府の無償資金協力により行われた。
小職の滞在中の視察及び相手方との討議により明らかになった、現状及び問題点を以下に述べる。
(1) 現状
医師:外科医1名、麻酔科医1名、産婦人科医2名、内科医1名、精神科医1名、小児科医1名、救急外来医1名、結核・感染症1名、総合外来1名、その他検診及びふるい分け担当医(Medical clearance screening doctor)3名(うち2名はBetio、及びX-mas島の保健所へ各1名ずつ)合計13名
これは1988年当時の8名(うち1名英国ODA)より比較して増加しているが依然としてキリバス人の医者の割合は少なく中国人4名、印度人1名、オーストラリア人1名、エストニア人2名、計8名が外国人医師であり、TCH内にあるビルマ人のWHO の代表も元来眼科医であることから手助けをしている。
看護婦:上級看護婦15名、看護婦87名、合計102名で1988年当時の71名に比し、31名の増加である。
臨床検査技師:11名で1988年当時の8名より3名の増である。
TCH 利用状況: 外来患者60~80名/日
救急外来患者数10~15名/日
入院患者数は6~8名/日
尚病床は103の設計となっているが、現状は120あり、常に満床状態である。
X線診断件数:1987年時865/月であったが1995年は月当り600~2,000件で推移している。
手術件数:1987年総計361であったが、1995は大手術530例、小手術1,250例の計1,780例、又産婦人科手術は1987年総計69例であったのが648例とそれぞれ大幅に増加している。
臨床検査は1987年との比較で以下に示す。
| 1987年 | 1995年 | |
|
血液検査 生化学 血液銀行業務 微生物 |
4,666 2,467 3,096 3,771 |
5,500 22,080 1,263 5,500 |
患者のリファラルに関しては国内の他の島々より2週間に平均10件位TCHへ送られている。関連教育機関としては、TCH内に看護学校があり年間の受入定員を15から30に増員したところである。本看護学校は正規コースは3年制であるが更に1年の補助医師(medical assistant)コースが附設されている。経費全額免除のため人気があり次年度210名の応募がある。問題は、医師、看護婦の卒後研修で、予算が限られているため殆ど実施されていない。末端の医療機関はメディカルアシスタントのいる保健所が22ヶ所、公衆衛生看護婦のいる診療所が67ヶ所存在している。尚87年時点では前者が37ヶ所後者が24ヶ所となっている。
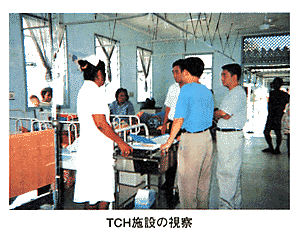
(2) 問題点
1) 塩風にさらされるため、冷房機器、厨房のレンジ等金属が錆つき、相当数機能していない。特に医薬品貯蔵室の冷房が稼働不全であることは問題である。尚従前より問題になっていた海岸側からの侵食減少は何らかの気象学的変化が生じたのか、むしろ顕著に後退しており、当面は更に侵食が病院側に進展するとは考えられない。
2) 薬品そのものは突発的な伝染病の流行でもない限りは、予算的にも供給ラインにも問題はない。若干バルク調整のスペースが狭いとの訴えが職員よりあった。
3) 臨床検査部門はスペースも手狭となっているが、加えて日本から入れた機器は殆ど他の援助国からのものに変えられている。これは殆どが些細な問題で稼働せぬ時、その問題点を見付け出せず、機器そのものを全部変えるということである。基本的にルチンな機器維持整備の習慣・技術が未熟であることに起因していると考えられる。
4) 同様の問題が放射線診断装置にもあり小さな問題点を見出し得ず、平均毎年2回位、豪州島津から専門家を要請派遣しているが極めて高い対価を要しているようである。
5) TCH内の公共の便所は、殆ど使用に耐える状態にない。その原因は先ず、水洗の為の水は海水をプールして用いているが、需要の増加でプールの絶対量が不十分であること。更に公衆道徳の低さより、清潔に使わぬのみならず、殆どの台座が持ち去られておりフィジーのCWMHの便所の感動的清潔さと対照的である。
6) 海水プールだけでなく、他の生活用水に用いられている天水も量的に十分でなく、これは追加的な小規模整備で克服可能と考えられる。
7) 焼却炉が電気系統の故障により使用不可能となっている。これに対しては、ある意味では病院の生命線でもあり、大使館書記官の方より草の根無償への応募が推められ、手続きの説明がなされた。申請が期待されるところである。
(3) 結語
1) 南地平偸尾の環礁国であるキリバス共和国にTCHが建設されたことは極めて意欲的であり日本の協力のモニュメント的意義もさることながら域内の医療事情、地理的条件と、それに対する現況を鑑案するとき予想にたがわぬ裨益効果が生じていると評価される。
2) TCHの受益者の共同利用施設の清潔度、機材維持状況は不良である。これは当国のpublic moralityが未だ十分に堪養されていないことに起因し、基本的衛生教育も含めて生活規範を高める必要がある。このことは今回機会あるたびに発言をしたが、朝の海水中の脱糞習慣は、施設の未整備よりやむを得ないとも考えられるが、公共の道端のいたる所にゴミが散らかっており、一方に於いて、自分の家の周辺は比較的清潔であり、not in my backyards的な観念が支配的であることは明らかである。この問題は単に保健衛生上のみだけでなく国際的にも観光その他で国を外に開く時肝要なことと考えられる。
3) 放射線機器及びマイナーな故障で使用されていない臨床検査機器に関する補修は、各1名の短期専門家を派遣することにより格段の効果が期待されると考えられる。
(1997年度に、フォロアップ調査団を派遣し現状を確認の上、必要に応じ資機材供与を行う予定。また、機材の有効活用を図るため、再活性専門家を派遣する予定。)

