9. 工業技術の人材育成(ブラジル)
(現地調査機関:1997年4月9日~20日)
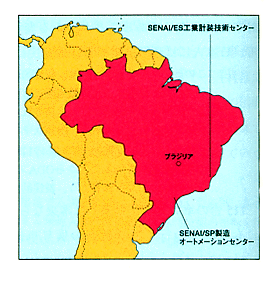
名古屋大学大学院国際開発研究科助教授 廣里 恭史
<評価対象プロジェクト>
| プロジェクト名 | 援助形態 | 協力年度、金額・年度 | 協力の内容 |
| SENAI/ES工業計装技術センター | プロジェクト方式技術協力 |
1985年3月~1990年 (フォローアップ) 1990年3月~1991年3月 (アフターケア) 1994年4月~1995年3月 |
工業開発に伴う近代設備を有する企業の増加による工業計装技術者の不足を解消するため、近代設備を持つ企業が多く進出しているエスピリト・サント州において、工業計装技術の職業訓練を行う。 |
| SENAI/SP製造オートメーションセンター | プロジェクト方式技術協力 | 1990年6月~1995年6月 | 工業界における製品の多品種生産傾向に対応するため、工業の中心地であるサンパウロ州において、品質管理技術や自動化技術の技術者養成を目的として職業訓練を行う。 |
1 「職業訓練」プロジェクトにおける評価手法
一般に、職業訓練教育プロジェクトの評価においてはプロジェクトの「効率性」と「効果」に関する評価が適用される。それらの「効率性」や「効果」の評価基準は、「量的・質的内部効率性(Quantitative and Qualitative Internal Efficiency)」と「外部効率性(External Effeciency)」、及び「外部効果性(External Effectiveness/Impacts)」に大別される。更に「自立発展性(Project Sustainability)」、即ち、協力期間終了後の自立的なプロジェクトの管理・運営及びプロジェクト効果(プラスの効果)の持続という観点からの評価が行われる。
(1) 内部効率性(Internal Efficiency)
内部効率性とは、職業訓練システム内に投入される訓練資源(インプット)を用いて卒業制(量的・質的アウトプット)を生み出す際の効率性である。
1) 量的内部効率性(Quantitative Internal Efficiency)
より高い量的内部効率性は、中途退学や留年による職業訓練システムの浪費を減らし、量的なアウトプットとしてより多くの学生を進級・進学させること、あるいはより多くの人材(卒業生)を労働市場へ送り出すことによって達成される。量的内部効率性を表わす指標としては、進学率や生存率が用いられる。
2) 質的内部効率性(Qualitative Internal Efficiency)
一方、より高い質的内部効率性は、訓練機材、訓練カリキュラム、教師、訓練時間、訓練形態、施設・機材の質や稼働状況等の訓練資源(インプット)の組み合わせを吟味し、質的なアウトプットとしての訓練達成度を高めることによって達成される。
(2) 外部効率性(External Efficiency)
外部効率性は、訓練カリキュラムと労働市場(企業)ニーズの関係や人材(卒業生)と労働市場における就業可能性との関係によって判断され、通常、卒業生の就職率が重要な指標となる。実際に用いられる際には、卒業後一年以内に就業する卒業生の割合と定義される。
(3) 外部効果性(External Effectiveness/Impacts)
外部効果性とは、訓練アウトプットが職業訓練システム外の経済社会部門やその他の関連部門に当たる影響に関するものであり、直接的効果としての技術的効果、経済的効果、社会的効果、及び間接的効果(政治的効果、環境への効果、組織強化効果)に大別される。但し、間接効果は、いわゆる教育訓練投資の「外部性」に関わる次元であり非常に測定が困難である。今回の有識者評価に際しても、データ及び評価期間の制約上、間接効果に関する評価は除外せざるを得なかった。
1) 技術的効果(Technical Impacts)
技術的効果は、主に技術移転の達成度として測定される。その判断基準としては、カウンターパートの数や配置状況、カウンターパートへの技術移転状況、カウンターパートの定着率、移転された技術の外部への展開、カリキュラムや訓練機材の自己開発能力、等が挙げられる。
2) 経済的効果(Economic Impacts)
経済的効果は、卒業後の経済活動における生産性向上である。労働市場が完全に競争的であれば、生産性向上は所得の増大に結びつく。その結果、消費や貯蓄も拡大され、経済的にプラスの影響を与えると考えられる。
3) 社会的効果(Social Impacts)
社会的効果は、所得格差、性差、地域格差といった様々な格差を乗り越え、均等な職業訓練機会の実現とその成果が平等に分配されることによって、貧困層あるいは中間層からの社会移動が促進されることである。また、職業訓練を受けることによって社会に存在する不平等を発見し、それらを改善しようという意識が生まれ、社会格差が是正の方向に進むことも期待されるであろう。
(4) 自立発展性(Project Sustainability)
職業訓練プロジェクトの自立発展性に関しては、特に、協力期間終了後もプロジェクトが当該国や機関の責任の下で管理運営され、当該国の技術開発や経済社会開発に持続的に貢献していることが確認される必要がある。また、プロジェクトの将来に渡る有効性が、プロジェクト実施機関の組織としての自立度を中心に検討されねばならない。
更に、プロジェクトの自立発展性を維持するためには、プロジェクトの内部効率性と外部効率性及び外部効果をより動態的に捉える必要があろう。動態的なモデルにおいては、まず第1周期で職業訓練プロジェクトが内部・外部効率的であり、かつ外部条件に変化が生じなければ外部効果の発生を期待することができる。これによって経済社会状況が変化し(例えば当該国の財政負担能力の拡大、完全雇用の達成、等)、新しい職業訓練システム改革が必要となる。そして第2周期では、新たな経済社会状況に対応して、職業訓練システムの目標が再設定され、プロジェクトにおける内部・外部効率性の計画基準が更新されると伴に、新たな外部効果がもたらされるのである。
2 ブラジルの職業訓練開発と全国工業職業訓練機関(SENAI)方式
(1) SENAIの設立と組織・運営体制
SENAIは、1942年に、労働者の質的改善と産業界の需要に見合った技術や能力を有する労働者の育成を目的として、当時の大統領令によって正式に発足した。SENAI本部にはその最高意思決定機関である全国審議会が、そして、各州毎に設置されているSENAI 支局には地方審議会がそれぞれ設置されている。このように州別にSENAI支局が設置されていることによって、各地域の産業界の需要に柔軟かつ迅速に応え、効果的な職業訓練プログラムを提供することが可能となるのである。
(2) SENAIの職業訓練プログラム
SENAIの職業訓練プログラム分野は、品質向上、製造機械、自動車、電気・電子、繊維、建設、出版、通信、運輸、造船、科学など多岐にわたる。SENAIには現在全国で932の各種訓練ユニットがある。設立以来の55年間に、これら全ての訓練ユニットを合わせると約2,700万人を対象に職業訓練を行ってきており、現在では約220万人がSENAIシステムにおて訓練を受けている。
SENAIの訓練カリキュラムの特色は、理論面の訓練と企業実習を組み合せる方式にある。基本的には2年間のプログラムの内、最初の1年半は各センターにおいて訓練機材を用いつつ理論面を中心とした基礎的訓練が行われ、その後の半年間に、企業実習を通して、より高度な応用技術の習得を目指す。特に企業実習期間中は、見習い期間に相当し、そこでよい成果を挙げることがその後の受入企業における雇用に繋がることが期待されている。
(3) SENAIの財源と配分方式
SENAIがこうした職業訓練活動を実施するための財源は、社会保障財務管理院(IAPAS)によって、いわば社会保障制度の一環(間接税)として徴収される工業、運輸、通信及び漁業関係の各企業における従業員給与全体の1%に相当の補助金によって賄われている。各地方局単位で集められた徴収金は、まずIAPASが1%を保留する。残りの99%から、その内の85%が徴収された各地方局に割当てられ、15%はSENAI本部へ回される。SENAI本部へ回された徴収金は、本部の管理運営費、関連企業が少ない、即ち徴収金の少ない地方局への補助金等に使用される。
更に、従業員が500人以上の企業からは、上述した1%に加えて0.2%の付加金が徴収される。この付加金は、企業による人材養成の為の奨学金、SENAI職員の為の奨学金及び企業実習費、等に利用されている。
(4) SENAI改革の方向性
SENAI本部では、1990年代後半から2000年以降にかけてのブラジル産業界を取り巻く変化に一層の柔軟性を持って対応すること、またSENAIによる職業訓練活動の更なる質向上を目的にSENAIシステムの改革を進めており、1996年から2010年までの戦略的計画案を取りまとめた。1997年度中に改革案の本格的な実施に移行することを目指しており、その改革の要点か以下の通りである。
第一に、1997年4月時点で、総裁室(在リオ・デ・ジャネイロ)と国際局(在ブラジリア)に分かれているSENAIの本部機能のブラジリアへの統合である。今回の改革では、集団的な管理運営体制の構築が目指されており、戦略的管理運営、コミュニケーション、国際協力の各分野を所管する3名の総裁を置くことが提案されている。また、国際局を含む殆どの本部機能が既にブラジリアに移転されていることから、3名の総裁は全てブラジリアにおいて執務に従事する方向性にあることが確認されている。
第二は、各SENAIセンター間への競争原理の導入である。SENAI本部では、従来、国全体での方針を決定してきたが、此の度SENAIの職業訓練活動を詳細に分類し、各々の審査基準を設け、金・銀・銅の3レベルに分類した。各SENAIセンターは、外部監査評価によって、銅レベル(全国的水準)ら銀レベルを経て金レベル(国際的水準)への昇格を目指し、職業訓練活動の質向上を競うことになった。
第三に、もはやSENAIシステムの量的拡大を目標の中心に据えるのではなく、既存のSENAIセンターの中で各分野の中核を担うセンターを国家技術センター(CENATEC)に昇格させ、周辺の訓練ユニットに対する助言・技術援助、情報提供、応用研究等を実施することによって、SENAIによる職業訓練活動の効率と質を高めようとする動きである。
第四に、多様性に富むブラジル各地域における産業開発の優先課題を明確にし、各州のSENAI支局への一層の権限委譲を図りながら、州工業連盟との連携を深めつつ、各州の産業界ニーズに合った職業訓練活動を展開して行くことである。
第五に、これらの諸改革の中での最重要課題と言って良いSENAI財源の多様化である。従来の主要財源であった関係企業からの徴収金が近年になって急激な減少傾向にあり、この趨勢では2002年にはSENAIの活動基盤を危うくするほどの財政的困難に直面することが予測されている。この減少傾向の背景には、大きく3つの潮流が存在する。まず、ブラジルの経済改革の一環として税制システムの見直しが政治日程に上がっており、SENAIが財源としてきたIAPASによる徴収制度そのものの変更が行われる可能性があること、ブラジル国営企業の民営化あるいは民間企業の合理化が目指される中で、従業員数の削減が実施され、企業の人件費負担の軽減が進められていること、そして、工業化の進展に伴い、生産のオートメーション化による従業員数の削減と企業の人件費負担の軽減が進められていること、である。
このような人件費の軽減は、即ち、SENAIの財源である各企業の従業員給与全体の1%に相当する規模は少なくなることを意味し、後述するように、協力案件におけるカウンターパート予算の確保という、プロジェクト成功の主要因に重大な影響が及ぶ事態を招く可能性がある。従って、SENAI本部及び各SENAIセンターでは、従来の財源調達システムの見直しに着手することを決意し、現行の従業員給与1%相当の徴収金制度を継続する為の政治的働きかけを強めると同時に、財源の多様化を推進することが今回の改革の大きな課題となったのである。SENAI本部が構想する具体的手段としては、1)企業側の最新技術に関する訓練を行うことを理由に、授業料を取る(法的には、14~17才までの技能教育は無償であり、授業料を取れるのは18才以上を対象としたプログラムである)、2)昇格した国家技術センターによる企業への技術援助を有料にする、3)各SENAIセンターにも自立性を持たせ財源の多様化を図る(企業への有料での講師派遣、コンサルティング・サービスの提供、製造品販売)、等がある。
3 「SENAI/ES工業計装技術センター」
(1) 評価結果
本協力案件に対しては1989年に終了時評価調査及び1994年にはアフターケア調査が実施されている。従って、主に1995年以降のSENAI/ESの活動に焦点を当てた評価を行った。
1) 内部効率性
1)-1 量的内部効率性
SENAI/ESが提供してきた主要な訓練プログラムであるテクニコ・コースの就学状況を1987年の開校時から追って視ると、1996年第2半期までの就学者数合計の298名に対して、留年・中退者数とも非常に少なく合計で25名のみで、273名の訓練生が卒業していることがわかる。生存率は実に92%に上り高い量的内部効率性が達成されてきたことが判る。
1)-2 質的内部効率性
SENAI/ESのカリキュラムは、テクニコ・コースの計装分野では計装一般から応用に関する知識を一貫して習得でき、さらに理論と実習が組み合わされ、理想的カリキュラムとなっている。このカリキュラムは、SENAI/ESが中心となって進める全国7ヶ所にあるSENAI計装センターにおけるカリキュラム標準化のモデルとなり、訓練の効率化に資するものと思われる。
日本側が供与した訓練機材は当初企業ニーズの先端をカバーするものであり、現在も応用可能な基礎理論の習得に役立っており、雇用企業先での「訓練可能性(新たな技能を習得する能力)」を高めることに貢献している。機材の活用状況は、スペアパーツがないために作動しない機材や使用頻度が高く磨耗が激しい機材も一部見受けられたが、全般的に良好である。
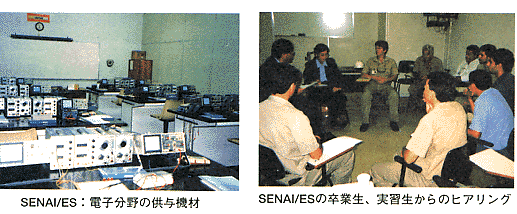
2) 外部効率性
訓練生の進学率及び就職率は各半期ともほぼ100%に近く、進学・就職状況から見る外部効率性は極めて高い。1996年に実施された訓練生の追跡調査等から得られた所見によると、訓練生の70%が計装、電子・電気分野での就職を畑氏、30%が大学への進学と他の分野への就職機会を得ている。雇用先企業での職務内容は、テクニコ・コース卒業生は計装や維持管理部門への配属が主となっており、特別コース卒業生は、シーケンス制御、計装基礎、電子回路等の職種へ就いている。
PLC(Programmable Logical Controller)分野のカリキュラムには一部企業ニーズへの対応の遅れが認められたものの、SENAI/ESの訓練コースはこれまで十分に企業ニーズに対応してきたと見做して良いであろう。特に、計装分野では、企業ニーズを絶えずカリキュラム内容に反映させようという試みが行われてきた。しかし、今後の技術革新や設備近代化の速度を鑑みるならば、SENAI/ESとして早急に何らかの対応を行う必要があるだろう。例えば、多くの企業はアナログ式計器からデジタル式計器への移行や連続鋳造システムの導入など近代的な制御システムによる操業が行われつつある。現有の訓練機材では中小企業の技術的ニーズには十分対応が可能であるものの、大企業のニーズへの対応が難しくなってきている。同じく、電気・電子分野のカリキュラム及び訓練機材に関してもSENAI/ESでは殆どが1987年に導入された機材であり、早晩、企業ニーズに合わなくなってくることが予想される。
3) 外部効果性
3)-1 技術的効果
当初予定されたカウンターパートへの技術移転計画は概ね達成されたと見做して良い。日本人専門家のセンター運営に関する助言から各分野における研究開発、教科書・訓練マニュアルの共同作成、機材の維持管理等の活動を通した技術移転能力が高く評価されている。計装分野は技術革新・進歩の速度が早く、機材等のハード面は確かに企業ニーズに合わなくなって来ることが予見される。しかし、センター運営や品質管理・向上、最適化の分野等で実施されたソフト面における技術移転はより長期的な効果を持続できるものと思われる。
フォローアップ協力期間終了時の1991年に在籍していたカウンターパートは、殆どが管理運営スタッフや技術インストラクターとして現在も活動を続けている。さらに、1991年以前に一旦は退職していったカウンターパートもSENAI/ESへ戻ってきている。また、1994年以降は、法改正によって非常勤スタッフの雇用が可能になり、様々な特別コースの開設によって新しい訓練ニーズへの対応が容易になった。
3)-2 経済的効果
SENAI/ES卒業生の初任給は大方700レアル(1レアルは約1米ドル)から800レアルで、昇給も比較的はやい。卒業生の昇給速度が一般に速いということは、彼らの「訓練可能性」が高く、生産性向上が伴っていることの有力な証左であろう。卒業生の経済活動による社会的収益性に関しては、公的資金によって運営されている連邦の職業訓練校との比較が考えられる。連邦の職業訓練校はブラジル全土で35校あるが、その予算額は932の訓練ユニットを抱えるSENAIの予算額とほぼ同額でありながら、卒業生の雇用状況はSENAIの方が遙かに良好である。SENAIの訓練ユニット当たりの訓練効率の高さを裏付けると同時に、より高い社会的収益性が生じていることが窺える。
3)-3 社会的効果
一般に、急激な技術進歩は労働者間の経済社会的不平等を助長する傾向にあると考えられているが、雇用企業の見解では、SENAI/ESの卒業生は、十分に新たな技術環境に対応出来ているとのことである。一方、卒業生の経済的成功が、社会的地位の上昇に繋がっているかどうかに関してはあまり判断材料がない。確かに、SENAI/ESでは奨学金の貸与や企業推薦等の就学補助を行い、SENAI/ESにおける訓練機会の平等化に努めている。しかし、SENAI/ESはあくまで中堅技能者としての資格を提供することを目的としており、卒業生が雇用先企業の経営幹部や管理職へ昇進できる資格を保障するものではない。また、そもそもSENAI/ESへは中間層からの入学志望者が多く、卒業後も直ちに彼らの社会的地位が上昇するわけではない。従って、卒業生の中には、将来の管理職への昇進資格を満たそうと在職しつつ大卒エンジニア資格の取得を希望するものが多い。SENAI/ESでの訓練効果がどのように卒業生の社会移動と結びついていくのかを見極めることは、今後とも協力効果を評価していく際の重要な課題であると言えよう。
3)-4 自立発展性
SENAI/ESは1995年12月に実施された外部監査によって銅レベルと判定され、計装分野のCENATECへ昇格した。次回の外部監査は2年毎の1997年に12月に予定されており、銀レベルへの昇格を目指している。従って、センターの自立発展性を支える大きな要因である技術移転の深化及び組織強化が順調に進んでいるものと考えられてよい。カウンターパートの定着に関しても、同レベルの民間の技術者の給与と比較した場合、SENAI/ESの給与が民間のそれを上回っており、少なくとも給水水準からはカウンターパートの離職に繋がることは考えにくい。
これまでのSENAI/ESの発展は、前述したようにIAPASを通しての徴収金制度によって安定的に供給されてきた財源によるところが大きい。しかし、ブラジル国営企業の民営化、民間企業の合理化、設備の近代化、労働人口の減少等の複合的要因により、この徴収金制度そのものの見直しが行われることが予見されている。今後の財源の確保は、まさにSENAI/ESの存続に関わる死活的な課題である。この問題は、全国・州の工業連盟やSENAI本部をはじめ、SENAIシステム全体の問題として認識されており、SENAI/ESとしては、1997年から2000年の間に自己財源のみによる財務体制を確立することを目指し、様々な実験的な試みを行ってきた。例えば、授業料の徴収(短期の特別コース)、情報サービス、研究開発、教材作成と普及、企業への講師派遣やコンサルティング・サービスの提供、講習会の開催等の営利活動である。これらの自助努力により、IAPASを通しての徴収金制度の帰趨に左右されない強固な自己財源基盤が確立されることが、長期に渡る自立発展性が確保される条件となろう。
(2) 提言
本プロジェクトは、SENAI/ESの高い内部・外部効率性に基づき、直接的な外部効果を発揮していること、また今後とも一層の自立発展性の向上を目指した自助努力を行っていること、等が確認され、非常に成功した案件であると判断されて良い。
しかしながら、SENAI/ESを取り巻く経済社会状況の変化及び近年の急激な技術進歩に伴う設備近代化の必要性等、これまで成功の前提条件に変化の兆しが見えている。既に指摘したように、計装分野ではアナログ計器からデジタル計器への技術革新が進み、現有の訓練機材や従来の技術移転内容では十分に対応できない状況になりつつある。また、工業計装技術の習得に欠かせない電気・電子分野においても急速な技術革新が進み、訓練機材・内容のレベルアップが必要である。こうした技術面での劣化は、企業のニーズ、特に大企業のニーズとの適合を一層困難なものにし、ひいては外部効率性や外部効果性の低下を招くことになる。
特に、ブラジル経済改革の一環としての税制改革の中でIAPASからSENAIへ配分される徴収金は今後減少していく傾向にあり、新機材の購入に充てる費用は殆ど拠出できない状態にある。従って、SENAI/ESでは、財源の多様化を図り自己財源基盤の確立を目指すと同時に、機材の新規購入を行うことなく、新たな企業ニーズに対応する方策を試行中である。例えば、企業実習への参加等によって、訓練費用を抑えて新技術の習得を行うこと、また、「コモダート(Comodato)」と呼ばれる企業からの機材借用方式の導入も、SENAIにとっては機材購入費の削減、企業にとってはSENAIを通しての自社技術の普及を意味し、双方への利点がある。特に、先端技術への対応に関しては、このような企業との協力によって、訓練費用を最小限に押え、訓練の効率・効果を一層高めていくことが期待される。
従って、今後とも何らかの協力が要請される際は、将来の企業ニーズ増大が予想される品質管理や最適化の分野等におけるセンターの対応を見極めた上で、ソフト面での技術移転を重視した協力を検討することは一つの選択肢である。また、一層の自立発展性を確保するために、1)財源の多様化を含めたセンター運営のノウハウや情報戦略・技術ネットワークの確立に関する助言、2)これまでの技術移転成果を普及させる為のSENAI/ESを拠点とした第三国研修の実施、及び3)企業や市場ニーズの調査、卒業生の追跡調査といった各種調査の導入、等における協力の必要性が認められる。
4 SENAI/SP製造オートメーションセンター
(1) 評価結果
本協力案件に対しては、1995年に終了時評価が実施されたところであるため、今回の評価は1995年以降のSENAI/SPの活動に焦点を当てて実施した。
1) 内部効率性
1)-1 量的内部効率性
SENAI/SPは1992年2月に開校されたが、それ以降1994年第2半期までの就学状況を見ると、開校当初の1992年には留年・中退者数がやや多く生存率は60%台の水準にあった。中退者は、若干の進路変更を行った者があるものの、約7割が経済的理由による者であった。しかし1993年からは80%台を維持し、1992年第1半期から1994年第2半期までの平均で78%に達した。これは企業からの推薦入学者数が増加したこと、またSENAIの奨学金制度によって就学に関わる経済的制約が緩和された為であろう。次に、本協力終了時以降の就学状況を見ると、一層の改善が確認される。入校者の生存率は、1995年第1半期は88%、1995年第2半期は94%、1996年第1半期は94%、1996年第2半期は96%、と各半期毎に順次高い量的内部効率性が達成されてきた。
1)-2 質的内部効率性
自動生産機械の導入や、経営管理部門のコンピュータ化という近年の産業界における急速なニーズ変化に対応する為に、1989年に訓練に対するニーズ調査を行い、その結果をもとにしてカリキュラムの作成が行われた。このカリキュラムにおいて、訓練生は製造オートメーションに関する基礎から応用に至る必要な知識及び技能を2年の訓練期間を通して効率的に学習した上で、習得した知識や技能を6ヵ月間の企業実習において実際に活用することが出来るようになっている。企業実習では主に生産オートメーションやメインテナンス部門に配属され、センターにおける訓練分野と直結した分野での実習を受けている。更に、将来の企業ニーズの変化に対応する為、1995年には新カリキュラムを提案するなどしてより一層の訓練プログラムの効率化・適正化を図っている。また、近年のセンターへの応募倍率は平均して6倍に近い高水準にあり、質の高い訓練生を確保していると言える。更に、訓練の達成度に関してSENAI/SPとブラジル全国平均との比較を見ると、多くの訓練項目において、SENAI/SP訓練生の成績が全国平均を上回っており、SENAI/SPにおける訓練生の習得技術の質の高さが確認できる。
日本からの供与機材は有効に活用されており、そのメインテナンス状態も概ね良好である。しかし、設備・機材の適正度と企業(とりわけ大企業)のニーズとの間に乖離が生じるようになってきた。例えば、訓練カリキュラムの適正度を高める為にはPLC分野における機材の更新が必要である。また、技術進歩が目覚しいロボット工学に関しては、将来の製造業における機械化を完全なものにする為、SENAI/SPとしては新たに導入が必要な分野であると認識している。
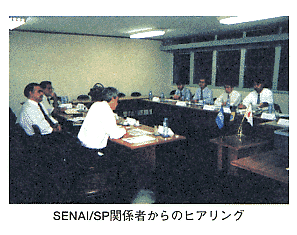
2) 外部効率性
SENAI/SPの外部効率性は極めて高く、進学率・就職率を合わせるとほぼ100%に近い。また、修了した訓練分野に対する就職率も94%に達しており、全国のSENAIセンターの中でも非常に高い水準にある。雇用先企業の主力は徐々に大企業から中小企業へと移ってきているものの、実習を受けた企業にそのまま定着し就職するケースが殆どであり、SENAI/SPの卒業生に対する企業の評価が高いことを示していると言えよう。つまり、SENAI/SPにおける訓練カリキュラムとその後の就職機会が効率的に繋がっており、訓練カリキュラムの有効性が高いことが判る。評価時(1997年4月)においては、第7期(1995年第1半期入校)のセンターでの訓練修了者28名が企業実習期間に入っていたが、1996年末の実習先企業選考時点において52の企業から求人(実習受入れ依頼)があり、需要の半分も満たせない状態にあった。
SENAI/SP実習性の受入れ企業及び卒業生の就職先の一つである自動車メーカーのGMは、現在3名の卒業生をエンジニアとして採用している。GM側としては、通常の大学出身者よりもSENAI/SP卒業生の技能を高く評価しており、長期的な業務ローテーションの中で、最適な部門への配属が行われるとのことである。更に、GMでは合計1年の実習期間を設けており、その間にSENAI/SPでは十分に対応できなかったロボット工学分野での実習を継続する等、SENAI/SPの訓練カリキュラムとの補完関係を強めている。
また、大型トラックの製造メーカーであるSCANIAは、SENAI/SP卒業生10名を採用し、4名の訓練生を受け入れている。SCANIAでは、経営の合理化に取り組んでいるが、経営の合理化、即ち従業員削減のプロセスにおいて、逆にSENAI/SP卒業生の優位性が高まってきていることがSCANIA側より指摘された。
3) 外部効果性
3)-1 技術的効果
管理運営スタッフ及びインストラクターともに、若干の移動(転勤・離職)があったものの、その補充は適切に行われ、定着率も高い。カウンターパートへの技術移転は、綿密な計画の下に順調に行われたと言って良い。専門的知識・技術の習得だけでなく、各分野の指導法、訓練計画、教材開発、等における指導的役割を担える能力が十分に養成されている。定着しているスタッフの殆どが日本での研修を終えており、高い技術レベルに達している。1995年に更新された新カリキュラムは、日本人専門家とカウンターパートの共同作成であったが、その課程でカウンターパートのカリキュラム改善に対する能力開発が十分に行われた。教材開発に関しても、日本人専門家の指導により、将来は、自助努力による教材作成が量的・質的に十分な水準に達することが期待される。
技術の再移転に関しても、近年、積極的にセンター外部へのサービスを実施しており、カウンターパートの十分な意思と能力を確認しうる。この活動は、センターの財務基盤を一層固めるといった目的によって助長されており、技術の再移転との相乗効果が顕著である。例えば、企業における短期訓練コースは、1992年には年7件(研修対象者数128名)であったが、1995年は年162件(研修対象者数3,466名)そして1996年には年152件(研修対象者数3,263名)と既に現在のセンターが保持する訓練能力の限界点に達しているとのことである。また、コンサルティング・サービスの件数も1992年には年1件であったが、1995年には年19件、1996年には年42件と飛躍的に増加してきた。その他、企業や大学との共同研究における研究開発等も行われている。更に、1997年度中には先端製造技術に関する「第三国研修」も計画され、近隣諸国への技術移転にも貢献して行くことと思われる。このようなセンター外部における活動を通し、SENAI/SPから再技術移転が展開されているのと同時に、技術インストラクターが外部においてまた新たな技術を習得し、センター内での訓練に還元しているといったダイナミックな技術の波及・浸透課程が生み出されていることが重要である。
3)-2 経済的効果
SENAI/SP卒業生の雇用先企業にける待遇は良く、卒業生の月平均給与は900レアルを超えている。ブラジルのテクニコ(中堅技術者)の月平均給与が500~700レアル、大卒エンジニアのそれが1,000~1,200レアルであることを考えると、SENAI/SP卒業生の給与は相当高い水準にあると言えよう。また、企業実習生としての支給金の月平均も、第4期生(1993年第2半期入校)の522レアル、第5期生(1994年第1半期入校)の530レアル、第6期生(1994年第2半期入校)の546レアル、第7期生(1995年第1半期入校)の563レアルと上昇基調にある。雇用先企業も、SENAI/SP卒業生の技術・知識や応用能力を高く評価しており、それが卒業生の給与の相対的な高水準に反映されていると言えよう。
SENAI/SP卒業生の経済活動における生産性の向上が、どの程度まで社会的収益性に繋がっているかに関しては明確な判断材料はない。但し、SENAI/ESの評価で指摘したように、連邦の職業訓練学校との比較において、より高い社会的収益性が生じていることと思われる。しかも、サン・パウロ州はブラジル経済の中心地であり、製造オートメーション分野での高い知識・技術を有する人材に対する需要が高いことから、SENAI/SPの存在自体が人材の供給面でサン・パウロ州の産業を支える大きな要因となっている。
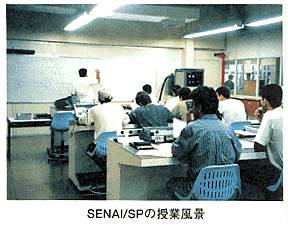
3)-3 社会的効果
SENAI/ESの評価で指摘したように、SENAI/SPでの訓練効果と卒業生の社会移動と関係を明らかにすることは今後の課題である。SENAI/SP卒業生は同レベルの資格保持者と比べ相対的に高水準の給与を受けて取っているにもかかわらず、やはり大卒エンジニアの資格の取得を希望する者がおり、実際に夜間コースに通う卒業生も確認された。ブラジルでは、高い社会的地位や高水準の待遇を求めて転職を繰り返すジョブ・ホッピングといった現象は未だ顕在化しておらず、一層の社会的上昇を伴う直接の社会的効果はまだ限られた水準にある可能性が高い。
4) 自立発展性
SENAI/SPはブラジルにおける中堅技術者の養成という人的資源開発政策において重要な役割を担ってきた。また、1996年度に銅レベルと認定され、製造オートメーション分野におけるCENATECへ昇格した。1997年2月の外部監査でも銅レベルを維持し、1998年の審査で銀レベルを目指すことになっており、将来的にも一層の訓練プログラムの質の向上が見込まれている。技術的効果として確認されたように、既に「第三国研修」が計画される等カウンターパートへ移転された技術がセンター内部から外部へと再移転されつつあること、またカウンターパートの定着状態も非常に良好であることから、技術及び組織面での自立発展性の高さが窺える。一部、ロボティクスやPLCは、機材の更新、技術インストラクターの再訓練等、SENAI/SPとして新たな対応が求められる分野であるが、当面は企業実習期間を有効に生かしたり、この分野の非常勤講師を採用する、等の対応策を講じることが望まれる。
本協力案件に対してはおよそ1,600万ドル(日本側900万ドル、ブラジル側700万ドル)が投入されてきたことから、今後ともプロジェクト効果を持続させ、自立発展性を高めて行く使命を負っている。しかし、SENAI/ESの評価において指摘したように、自己財源の多様化と訓練プログラムの一層の効率化によって財政的基盤を再び強固なものにする必要がある。1994年は僅か4万レアルであった自己収入は、1995年には11万レアル、1996年には17万レアルと、着実な増加傾向にあるものの、SENAI/SPの総年間予算の約5.6%(1996年)を賄っているに過ぎない。従って、公的資金の投入が、今後も何らかの形で継続されていくことがSENAI/SPにとって死活条件である。暫定的な措置として、SENAI/SPでは1997年7月より機材購入費やスタッフの給与等のセンター本体の運営予算は従来通り徴収金からの配分で賄い、教材費や維持管理費等の運営費はSENAI/SP自身で調達する体制が導入される予定である。
(2) 提言
本プロジェクトは、SENAI/SPの高い内部・外部効率性に基づき、直接的な外部効果を発揮していること、また今後とも一層の自立発展性の向上を目指した自助努力を行っていること、等が認識され、非常に成功した案件であると判断されて良い。
しかし、今後に残された課題としていくつかの点が上げられる。まず第一に、ブラジル経済における工業部門の重要性が増しつつある中で、経済自由化の推進や国際競争力の強化の為にも一層の品質改善・生産性向上が求められている。SENAI/SPは、中堅技術者を養成し関連企業に人材を供給することによって、特に製造オートメーション化の企業ニーズに積極的に対応してきた。しかし、ロボティクスやセンサー技術等、一部に技術進歩の速度が急激な分野があり、現在のSENAI/SPが提供しうる訓練プログラムと企業(主に大企業)ニーズとの乖離が生じている。SENAI/SPとしてもメカトロニカの完成を目指し新たにこの分野を強化する必要性を認識しており、日本からの協力可能性を打診しているところである。これに対しては、機材供与や専門家派遣によるアフターケア協力、あるいは「第三国研修」の中で補完的に取り上げる、等の選択肢が考えられよう。
第二に、短期訓練コースの充実や教科の選択的受講といった卒業生からの要望及び企業の必要とする分野での訓練強化といった雇用先企業からの要望にいかに対処していくのかといった課題がある。これらの要望に限らず、卒業生や企業からのニーズを絶えず汲み取れる仕組みを生み出し、制度化していく必要があろう。現在は、主に企業内研修への講師派遣とそこからのフィードバックによって情報を得ているが、有効な手段としては卒業生のネットワーク化や企業の訓練担当者との定期懇談会の開催等が考えられる。
第三に、IAPASを通した関連企業からの徴収金の規模が今後大幅に減少していく可能性があるSENAI/SPでは、新機材の購入費などを含め、自己財源で賄っていく方法を模索しなければならない。一方、この問題はSENAIシステム全体のものとしても検討されており、今後とも公的な資金源を維持出来るように連邦・州政府への働きかけが行われている。SENAI/SPとしても、企業研修への講師派遣やコンサルティング・サービスを開始するなど財源の多様化を目指した試みに着手しているが、今後はより本格化させる必要があろう。
最後に、SENAI/SPから日系企業への就職例はまだなく、学生の実習に止まっている。自動車産業を例にとれば、日系企業としては、トヨタ自動車が、現在サン・パウロ州インダイアツバ市でブラジルにおける初の工場を建設中であり、ブラジルを拠点として今後南米市場への進出を予定している。また、ホンダもサンパウロ州スマレ市において工場を建設中である。南米の自動車業界では、欧米企業が先行しているものの、今後進出を予定している日系企業への就職者が増えれば、就職先の枠が広がることでSENAI/SPの訓練生にとっても良いインセンティブとなるであろう。
本プロジェクトのフォローアップとして、97年度より中南米12ヶ国を対象とした第3国研修を実施している。また、ロボティクス分野のアフターケア協力を、 年 月より実施している(する予定である)。
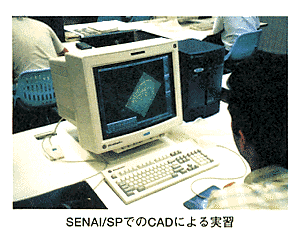
5 総合評価:成功要素と新たな課題
(1) 経済発展、労働市場及び中堅技術者育成
第二次大戦後のブラジル経済発展は、主に工業部門の伸びによって達成されてきたが、それを人材面から支えてきたのがSENAIの人材育成システムであった。しかしながら今後のブラジル経済は、長年の保護政策下で顕在化した非効率性の是正、国際競争力の強化と輸出志向の工業化が中心的課題となる。その為には製造業における品質改善・生産性向上が不可欠であり、新技術の導入・開発、生産方式の革新、産業界の情報化、そして労働需要の変化が必然的に伴う。こうした労働需要の変化に対し、人材供給側はより高度な技術・知識を有する、あるいは技術変化に柔軟に対応できる「訓練可能性」の高い労働力を育成し、労働市場のニーズを満たしていく必要がある。
更に、一層の経済自由化によって国際市場への統合を進めるブラジルは、1995年1月にアルゼンチン等と協力して「南米共同市場(メルコスール)」と銘打った関税同盟を発足させ、以後自由貿易地域の形成を目指している。そのメルコスールは徐々に拡大し、南米地域をカバーする巨大な市場となることが期待される。そうした中、各国企業が南米市場へ進出し、ブラジルがその生産拠点となるのは必死である。メルコスール形成に伴う経済発展の新たな局面において、SENAIシステムが中堅技術者の養成面で果たす役割は、今後ブラジル国内は元より南米という更に大きな枠組みの中で重要性を増していくであろう。
SENAIは、2つの協力案件で確認されたように、非常に効率的かつ効果的な人材育成・供給システムへと発展してきた。特に、連邦の職業訓練校との比較では、SENAIは企業ニーズの変化、即ち労働需要の変化に敏感であり、訓練内容も柔軟性に富んでいる。連邦の職業訓練がより非効率でニーズに合致しないものであれば、SENAIシステムの更なる強化・普及がブラジル全体にとってより有効な投資となり得る。経済成長に伴い、今後とも中堅技術者に対する需要の増大が見込まれる中で、ブラジルの人材育成システムを見直し、SENAIとの比較・検討を十分に行った上で、人材育成に関わる投資優先順位を明確にすべきである。
(2) 職業訓練行財政と管理・運営体制
ブラジルにおける経済改革の波は、国営企業の民営化、民間企業の合理化やリストラとなって現れ、SENAI財源である徴収金の大幅な減少が見込まれている。現行のIAPASを通した企業徴収金に対する見直し論に関しては、1)リストラによる従業員給与の絶対額の減少のため、1%を増加させることによって、職業訓練の間接的な受益者となる企業から費用回収を行うか、2)連邦の職業訓練校の合理化・効率性の改善を通して、そこへ投入されていた公的資金をSENAIへ振り向けることにって、企業からの徴収金の補填を行うか、3)SENAIをより自給自足体制へ近づけるべく、企業からの徴収金の減少あるいは廃止を視野に入れ、一層の訓練プログラムの効率化を達成すると同時に、自己財源の多様化を図る、といった選択肢があろう。
いずれにせよ、SENAIによる自己財源の多様化が最重要課題であることに変わりがない。財政基盤を多様化する方策としては、1)18歳以上の訓練生に対する授業料制度の導入、2)企業へのコンサルティング・サービスの提供、3)企業内研修のための講師派遣、4)各センターにおける製品・部品の製造販売、等が考えられる。授業料制度の導入は、受益者負担の立場からも原則的に正当化されて良いが、訓練機会の平等化を維持する為に奨学金制度を組み合わせることが肝要である。コンサルティング・サービスや企業への講師派遣等は、SENAIの有する技術・知識を外部に普及するに留まらず、技術インストラクター等が外部の要望やニーズに実際に接することによってSENAI内部の訓練活動の向上に役立つという相乗効果も期待しうる。
(3) 職業訓練における民間部門の役割
先端技術の分野ではカウンターパートの技術・知識不足、そして機材の老朽化などの立遅れがみられた。急速な技術の変化・進歩に対応していくには、絶えず訓練内容の向上・改善が必要となってくる。しかし、財政基盤の多様化を図るとしても、新規機材の購入などの点ではコスト面での限界がある。そこで、民間部門との協力により、訓練コストを抑制しつつ訓練効果を上げて行くことが望まれる。まず民間部門の担うべき役割として、先端技術分野の企業実習がある。最先端の技術習得にはそのための機材だけでなく、SENAIにおける技術インストラクターの再研修や新規採用も必要となり、相当な時間と財政的負担が大きくなる。また先端技術は、変化の厳しい分野だけに、その更新が幾度となく必要となる。そこで先端技術分野の訓練を企業実習に委ねることは、SENAIにとっては直接・間接の費用を軽減し、企業にとっては必要な技術を訓練生に習得させるという二重のメリットがある。また、SENAI/ESで採用されているような、「コモダート」方式も有効な手段と考えられる。
以上の領域を民間部門が担うとすると、SENAIが担うべき役割は、基礎分野における訓練をより一層充実させること、及び技術変化に柔軟に対応できる人材を育成することである。基礎的技術・知識を有することで、企業実習や就職後の企業内訓練・研修によって短期間かつ少ない費用でニーズに見合った技術を習得することができる。技術水準は常に変化・進歩を続けることから、その変化に長期的に対応していくことが可能な人材の育成・供給こそが、SENAIの担うべき役割なのである。
6 提言:今後の協力の方向性
(1) 職業訓練分野の協力方針
今後のSENAIシステムの自立発展を促すためにも、引き続きカウンターパートへの技術移転を重視した協力を検討すべきであろう。特に、職業訓練部門は外部状況の変化に迅速かつ敏感に対応することが生命線であり、訓練内容に柔軟性を持たせることが必要となる。その為にも、指導方法の開発、教材・カリキュラム開発、訓練コースの設定、等が将来的に独自で行えるような支援が重要と考えられる。協力の重点分野としては、先端技術分野における技術移転に関わる機材供与及び専門家派遣等が考えられるが、品質管理・向上や生産向上のソフト面における協力も重要性を帯びてくるまた、技術革新の現状や今後の動向についての情報提供、労働市場に関する情報システムの確立等の情報面での協力も重要である。更に、今後の協力形態としては、1)職業訓練部門の合同評価の実施。2)「南南協力」(ブラジル側呼称「三角協力」)の促進による技術の再移転、3)日系人への裨益効果創出が考えられる。
(2) 職業訓練部門分析・評価の実施
今回の評価対策案件であるSENAI/ESやSENAI/SPに限らず、各SENAIセンターに対する日本のこれまでの協力は高く評価されてきている。今後はSENAIシステムの自立発展を重視していく方向で、各SENAIセンター間の水平的な交流によってこれまでの協力の相乗効果を高めたり、ブラジル北部・東北部のSENAIセンターへの協力による地域格差是正を視野に入れていく必要がある。その為にも、ブラジルにおける職業訓練部門を分析・評価し、先端技術分野の訓練方法、財源の多様化、民間部門との役割分担、連邦の職業訓練校との比較、等SENAIが抱える新たな課題に関する総合的な検討を行うべきである。こうした分析・評価は、日本とブラジルの双方に有益な所見をもたらすものであり、両国合同によることが望ましく、その成果を今後の協力計画策定や事業実施段階へフォードバックさせていくべきである。
(3) 「南南協力」(ブラジル側呼称「三角協力」)支援
現在SENAIの各センターは、ブラジル国内に限らず中南米地域における関係分野の指導的機関となっている。国内においては、ブラジル北部・東北部のSENAIセンターの地域格差是正における役割が注目されている。また、国外においては、自由貿易圏を目指すメルコスール形成による南米市場の拡大に備えた人材面での支援が大いに期待されている。更に、SENAI本部は現在、アフリカのポルトガル語圏地域(アンゴラ、モザンビーク等)に対して職業訓練分野の協力を実施または交渉中である。このような「南南協力」は、ブラジルを拠点とした協力枠組の拡大を意味し、日本が直接的に協力を実施することが困難な国や地域に対して、ブラジルを通じた間接的な技術移転効果を期待することができる。現在SENAI/SPが中心となって計画されている「第三国研修」や域内の専門家を登用する「三角協力」を積極的に推進して行くことが求められる。
(4) 日系人(日系企業・日系社会を含む)支援
SENAI/SPの位置するサン・パウロ州には、世界最大の日系社会が存在している。現時点までは、SENAIに対する日系人の訓練ニーズは極めて低い状況にある。これは、SENAIの提供している訓練内容あるいはその雇用状況が、日系社会の要望に適合していないためと考えられる。そこで、短期もしくは夜間のハイテクコースや、コンピュータ、情報技術のコースを設置するなどして、日系人も含む幅広い層から訓練生を獲得していくべきであろう。
日系社会に関しては、南米市場への進出が目覚ましい自動車産業を中心に、SENAIの活動にどのように取り込んでいくかが課題となる。日系企業はSENAIにとって卒業生の吸収先であるとともに、先端技術や新たな生産方式に関する知識・技術の情報源でもある。今後日系企業のニーズを把握し、活動を行うことが、SENAIの発展の重要な要素となろう。
3 ブラジルでは1942年に「職業訓練に関する基本法(Organic Law on Industrial Training)」が制定されたことを受け、主にドイツの制度を模したSENAIのような職業教育システムが形成されはじめた。1940年代のブラジル経済は、流れ作業を主体とした大量生産に特徴づけられ、徒弟制度のような長期にわたる技術習得は次第に見送られるようになっていた。
4 全国工業連盟は、ブラジル工業界の代表的機関として、1938年に設立された。その運営目的は、工業界の利益保護とサービスの提供である。当初の戦略は、産業構造を多様化しそれを統括することであったが、1990年代初頭より主にブラジル産業の競争力の強化を目指している。

