8. 穀物倉庫と飲料水(マラウイ)
(現地調査期間:1996年10月25日~11月4日)
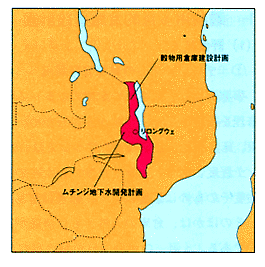
■読売新聞社論説委員 南条 俊二
<評価対象プロジェクト>
| プロジェクト名 | 援助形態 | 協力年度、金額・年度 | 協力の内容 |
| 穀物用多目的倉庫建設計画 | 無償資金協力 | 1991年度、4.41億円 | 農業が最重要産業になっているマラウイにおいて、農産物の貯蔵、流通に不可欠な貯蔵倉庫を建設し、穀物の収穫後の損失を防ぐ。 |
| ムチンジ地下水開発計画 | 無償資金協力 |
1992年度、6.46億円 1993年度、2.37億円 1994年度、2.71億円 |
給水普及率が17%であるムチンジ県に、衛生的で安定した飲料水を供給するため、300本の深井戸を建設する。 |
はじめに
日本は1994年度にマラウイに対する援助のトップ・ドナーとなったが、同国が在外交館未設置国(在ザンビア大使館が管轄)であることなどもあり、過去の評価実績は必ずしも十分と言えない状態にある。ODAの質向上の観点から、実施後のプロジェクトに対するフォローアップ、アフターケアの充実が従来以上に求められている今、プロジェクトの確実なフォローを確保する観点から、同国における有識者評価を実施する。
日本は、従来から、同国の民主化、経済改革努力を支援すべく、同国が後発途上国であることも勘案しつつ、食糧、農業、水供給、保健医療などの分野を中心に実施してきた。
今回評価では、上記代表的案件の評価・視察を行い、これまでの同国における日本のODA事業の取り組み、援助の効果などを検証するとともに、将来のプロジェクト形成に生かすべき教訓を引き出し、同国の開発に役立つ効果的な援助方策について提言する。
1 穀物用多目的倉庫建設計画
(1) 評価の概要
a プロジェクトの維持管理状況
- 事務所棟に設置された金庫のフレームがゆがみ、扉が完全に締まらなくなっている。修理を検討中だが、金額がかさむため、決断できないようである。
- 倉庫の外観(内外の壁、床、屋根、鉄扉など)については、外側の一部に、コンクリートの柱の隙間に幅3センチ程度、高さ30センチ程度にわたって、シロアリの巣ができているのが認められた。強度そのものに影響はなく、修理は容易で、近く修理する予定。
- その他は、倉庫の内外ともに清掃が行き届き、清潔である。維持管理はおおむね良好。
- 鍵は、外側から通常のかんぬき式の錠前を使用しているが、防犯上の理由から内側から施錠する方式を希望している。これもまだ、予算上の判断ができていない。これまで盗難にあったことはない。
- 備品については、
- 2台ある煙霧器(ドイツ製、商品名SWING FOG)がいずれも、火を吹いて故障。ほとんど使えない状態。修理は困難と判断。対応策は未定だが、速やかな判断が必要。
- 6台のコンベアのうち、1台が、チェーンの破損、プラグ不良で使用不能。予算措置ができていない。繁忙期を過ぎているため当面は支障なしとみているようである。
- 携帯用水分器など、その他の機材はきれいに管理されている。頻繁に活用されているかは不明。
b プロジェクトの適正度など
- 本倉庫は、マラウイ北部地域で生産されるメイズなど食糧、同地域で使用される肥料、農薬などの集散基地としての機能を期待されていた。総合的に見て、実際に、その機能を果たしていると判断される。農業省や農業開発マーケティング公社(ADMARC)など関係者は、倉庫の役割を高く評価し、援助した日本政府に感謝している。
- また、昨年までの早魃では、リロングェの備蓄サイロから不作に苦しむ北部の農民にメイズを配給したが、配給品は、この倉庫へ40トン大型トラックで運ばれ、ここから小型トラックで、各村に小口配送をする、という形で、円滑な配給が可能になった、という。主食のメイズ不足から農民を救う配給の核としての機能を果たした。これは事前には予想されていなかった効果である。
- メイズなど主要農産物の収穫期は毎年4月に始まり、8月にかけて倉庫の収容はピークになる。
- 今回の調査時点の倉庫稼働率は閑散期であることもあり、20%程度と見受けられたが、ハイブリッド・メイズの種子、ヒマワリの種子、日本からの援助の肥料、シュガー・ケインなどがきちんと区分けされて、木製のパレットに乗せて置かれていた。
- 倉庫完成後、昨年までは早魃による減産のため、フル操業にはならなかった。今年は、昨年秋からの雨期に降水があり、倉庫のあるマラウイ北部地域もメイズの増産が期待されたが、中小農民が、昨年までの不作で手持ちの資金が不足し、メイズに使う肥料を十分手当てする余裕がなかったためメイズの生産が伸びなかったこと、資金のある農民はタバコなど本倉庫保管対象作物以外の換金作物の生産にまわり、首都のリロングェなど消費地に直接、産品を持ち込んだこと、などから、1996年の倉庫の利用量は、昨年よりさらに落ちている。
- この原因としては、昨年までの早魃に加え、新政権の経済自由化策の一環として、農民は作物の種類を自由に選べるようになり、金になる換金作物の生産に走る傾向が出てきたことがある。また、この倉庫を保有・管理するADMARCの市場独占体制が崩れ、民間の流通・倉庫業者も参入を始めていることも影響している。
- 本倉庫は、1993年に政府からADMARCに譲渡され、維持・管理を委託されている。
- ADAMRCは、法律に基づいて設立された公社に近いもの。理事の一部を政府の役人が占めるが、理事長は民間人が務める。政府は銀行借入に対して債務保証はするが、補助や融資はしない。わが国の公社よりも、民間企業に近い。
- ADMARCの現地責任者は「現在は過渡期であり、自由化、市場経済が進めば、生産者も、相場をみながら、産品を市場に出すようになり、市場に出すまでの間は倉庫に置いておこう、ということになるので、従来よりも倉庫の利用が増えることが期待できる」と楽観視しているが、現在の利用状況をみると、必ずしも楽観できない状況にある。
(2) 教訓と提言
- 倉庫を所有、管理しているADMARCの責任者は誠実に努力しており、本倉庫は短期的には、目的に沿って利用され、早魃時の地域支援にも予定外の機能を果たした。
しかし、新政権の経済自由化政策のもとで、ADMARCの機能に変化が出てきており、日本の無償援助による農業用倉庫の機能も、少なくとも一時的に低下している。法律に基づいて設立された公社であるADMARCは分割民営化の可能性があり、倉庫についても売却などの事態を予想する政府関係者もいる。今後、所有・管理者であるADMARC、倉庫の機能、位置付けが変わる可能性があり、
- 日本政府としては、北部地域の農業生産の安定、増加のための当初の機能を果たす形での活用を求める必要がある。
- 今後、この種の協力要請があった場合は、こうした経験を十分に踏まえ、相手の対応を明確にしたうえで判断する必要がある。
- なお、本倉庫は、完成直後にマラウイ政府からADMARCに譲渡されているが、ADMARCの性格からみて、無償援助が適切であったか、若干の疑問が残る。
外務省コメント1:本プロジェクトでは、当初計画から、倉庫施設の建設及び機材の調達を農業省、完成後の保守運営をADMARCが行うこととしていた。ADMARCは、1971年に小農の生産拡大と農産物の販売強化を目的に政府が100%出資して設立され、農民から作物を買い上げ国内販売及び輸出を行うとともに、農民に対して種子、肥料、農薬等の供給、資金の貸付を行っている機関であり、無償援助の対象としては適切であったと考える。
- さらに言えば、同国の穀物、食糧流通全般の在り方について指導助言する形で、アフタケアを行い、関連の政策立案、実行能力を政府関係者の間に育てることを検討すべきである。「点」としての倉庫を作るだけでは、援助の効果に限界がある。
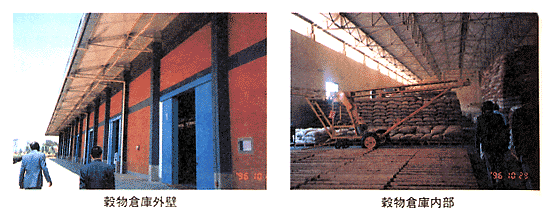
2 ムチンジ地下水開発計画
(1) 評価結果の概要
- 300本の井戸のうち、現在完全に使用されているのは298本。2本はここ2か月動いていない。ポンプそのものが重大な破損をしたわけでなく、住民の維持管理体制がうまく機能せず、スペア部品を購入できないため、という。
- また、昨年までの早魃期にも、枯れた井戸はなかった、という。
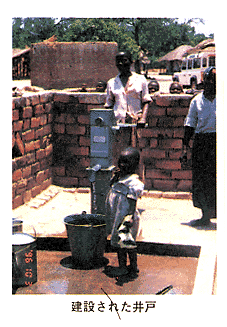
- 日本の援助で作られた井戸を使用しているムチンヂ市郊外の二つの村で、村の維持管理委員会のメンバーや利用者の主婦の声を聞いたが、いずれも、以前は汚れた水溜まりに近い状態の水場を利用していた。距離はそれほど変わらないが、村の中心に近い場所にあり、いつ行ってもふんだんに清潔な水をくみ取ることができることに満足している、と異口同音に語っていた。
- 炊事が清潔な水でできるため、下痢などの病気にかかることがほとんどなくなり、洗濯や水浴びも頻繁にできるようになって、清潔に暮らせることに喜んでいた。井戸が日本の資金で作られた事も、大半が知っているようである。病気がなくなった、あるいは半分になって、ことを、大人も子供も一番の効果として評価している。
- 水くみの距離は短くなっても水くみの回数は、水の利用とともに増えたと思われる。したがって、女性の水くみの労働が軽減された、とは思われず、他の仕事などに使う時間が大幅に増えた、との声も聞こえなかった。ただ、子供のころから女性の当然の仕事として、行っているためか、少なくとも意見を聞いた女性たちからは、不満の声は聞かれなかった。
- 皆が井戸の有り難さを痛感しており、それが、住民が資金負担、あるいは共同で資金稼ぎに力を合わせ、スペア部品を購入し、定期的に井戸をチェックし、井戸の回りを清掃し、井戸を守っていこう、という高い意識につなかっている。
- マラウイ政府(灌漑・水資源省)は、ムチンジ地区に3人のコーディネーターを配置し、月一回は各井戸を巡回している。だが、各井戸の利用者の維持管理委員会の設置や維持管理活動の指導は、全面的にイギリスのNGO、SAVE THE CHILDREN FUND(SCF)の力によっているようである。
- SCFはムチンジにも、マラウイ人を養成して、指導員として常駐させており、井戸の回りに家畜が近寄るのを防ぎ、清潔に保つための高さ1メートル、幅2メートル・長さ数メートルの長方形のレンガ積みの囲いを指導して、住民に作らせるなど、彼等の自主的な努力を引き出す形で、維持管理体制を固めさせている。囲いに必要なセメントはSCFが援助して購入したものという。
- 日本政府が供与した掘削機2台(1台は前のプロジェクトで使用したもの)のうち1台は、他地域でスポット的に井戸の掘削に利用されているが、1台はスペア部品がないため稼働していない。「日本製の部品で、地元にはディーラーがいないので、入手できない。日本の無償援助を要請中」との説明がマラウイ政府からあった。「維持管理は貴国政府の責任ではないか」との当方の質問に明確な答えは得られなかった。
(2) 教訓と提言
- 100%近い井戸の稼働率は、この国の通常の井戸の稼働率の2倍近いとも言われている。
- その原因は、井戸を使用する地域住民が自主的な維持体制を作り、定期点検、清掃、自費による交換部品の調達、交換などを確実に続けているためである。つまり井戸を介在したかたちで、住民の自治体制を育成するという副次的な効果も認められた。
- 住民の意識がここまで高まったのは、SCFの活動によるところが大きい。マラウイ政府だけでは、とてもここまでのことは出来なかったと思われる。
このことを踏まえ、現在、マラウイ政府の要請により、日本政府が実施を検討しているムジンバ地区での地下水開発計画については、「井戸作り」だけでなく、できた後のアフタケアの体制もあわせて考える必要がある。
外務省コメント2:給水案件では、掘削技術の移転とアフターケア体制の充実が重要である。このため、本プロジェクトにおいては、工事期間中にOn-the-job Trainingにより先方技術者を指導するとともに、維持管理が容易な仕様の給水ポンプを選択している。また、平成8年度に実施した「ムジンバ西地区給水計画」では、井戸施設の維持管理費用について、食糧増産援助の見返り資金の使用を認める等の配慮を行った。
- SCFも、この点を懸念しているが、「今後予定されているムジンバ地区でのプロジェクトに対しては、当方に財政面での余裕もない」としており、今からアフタケアの十分な体制作りの必要性を強調している。ノウハウの提供はすすんで協力の用意を表明している。
3 横断的提言
(1) 必要なアフタケアも考慮した援助
今回の評価の対象となった穀物倉庫プロジェクト、地下水開発プロジェクトは、それぞれに地域の農業生産、地域の日常生活に役立っているが、同国政府あるいは現地住民の能力などからみて、完成後のアフタケアなしの援助では、その効果を長期にわたって持続、発展させることは難しい、と判断される。
実例を挙げれば、ムチンジ地下水開発計画については、先に述べたように、100%近い井戸の稼働率の原因は、井戸を使用する地域住民が自主的な維持体制を作り、定期点検、清掃や自費による交換部品の調達、交換などを確実に続けているためである。井戸を介在した形で、住民の自治体制を育成するという副次的な効果も認められたが、住民の意識がここまで高まったのは、英国のNGOの活動によるところが大きい。これなしには、これほど高い稼働率は不可能である。現に、こうしたアフタケアの無い他地域の井戸の稼働率は極めて低い。
現在、マラウイ政府の要請により、日本政府が実施を検討しているムジンバ地区での地下水開発計画については、「井戸作り」だけでなく、完成後のアフタケア、人材育成も重要になっている。地下水開発計画に限らず、今後は、単に設備を作る資金を出す援助から、供与設備の維持・管理を自力で行っていけるような現地教育・指導を含めた援助を合わせたものとすることが重要と思われる。
また、マラウイにおいてすでに始まっている保健省公衆衛生研究所の機能強化のための技術協力、漁業関係の「在来種増養殖研究計画」のようなプロジェクト方式の技術協力のような総合的な援助も、長期的な観点から現地の自立能力を高めていくために、強化していく必要がある。
(2) 総合的な計画策定、実施支援を
マラウイは、政治的安定こそ周辺諸国より高いが、天候など自然条件による影響を受けやすいため、経済は穀物など農産物の出来、不出来に大きく左右されるなど不安定である。農産物以外の天然資源に恵まれない同国では、農産物の安定的な増産を確保することが、経済の安定的な発展にとって、極めて重大である。
より根本的には、並行して、脆弱な農業生産基盤を総合的な整備するために、現行の農業開発計画の見直しを含む具体的な経済開発計画の策定と実施を支援していく必要がある。
今回評価対象となった農業倉庫を例にとれば、前述したように所有・管理者であるADMARC、倉庫の機能、位置付けが変わる可能性がある。特に、このような状況のもとでは、個別の支援プロジェクトを実施しても、一国のあるいは地域経済のために、長期にわたって役立てていくことは困難である。
言い換えれば、「点」としての倉庫を作るだけでは、援助の効果に限界がある。同国の農産物生産、食糧流通全般の在り方について指導助言する形で、アフタケアをするとともに、関連の政策立案、実行能力を政府関係者の間に育てていくことを提案したい。
日本政府は世界銀行との協調融資の形でマラウイ共和国の財政改革・規制緩和計画(FRDP)に対して、所要資金53億7,600万円を限度とする円借款を供与することで、96年12月に交換公文を交している。償還期間は10年据え置きの30年。金利1%である。
FRDPは、同国経済の構造調整を支援することを目的としている。同国は81年より構造調整に取り組んでおり、対外通貨勘定の自由化、国債・債券市場の整備、各種輸出入規制の緩和・撤廃などを実施してきたが、税制、農業・土地改革、公企業の民営化、輸出振興などにはまだ手が付いていない。これらの分野での構造調整の推進がFRDPの狙いであり、今回の円借款は、これを支援しつつ、同国の厳しい外貨事情を改善する目的で、計画実施中に必要な一般輸入決済資金として供与された。
しかしながら、その狙いは評価できるとしても、現地政府の状況や政策執行の現状を見たうえで判断するに、この円借款がどれほどこの国の構造改革や持続的経済成長に役立つのかが、具体的な説得力に欠けるようにみえる。単なる外貨不足の穴埋めにとどまる可能性もあるのではないか。財政が破滅状態にあったり、飢饉の発生で緊急援助が必要など、やむを得ない場合を除いては、同国が持続的な経済成長を遂げるためにも、制度的基盤整備のため、より直接的な効果が期待出来る実施計画策定支援、技術協力と組み合わせた無償援助などの効果的な実施を優先すべきである。
外務省コメント3:構造調整借款は、国際収支悪化等、構造的な問題を抱える開発途上国に対して、持続的な経済成長と国際収支安定の回復・維持に必要なプログラムや政策及び制度改革を支援する目的で供与される世界銀行の融資(資金の使途は一般輸入商品で、短期的な国際収支支援の形態をとる)と協調して円借款を供与するものである。構造調整借款においては、対象国の構造調整を実施するために設定された条件(コンディショナリティ)が達成されなければ資金の支出は行われないため、単なる外貨不足の穴埋めを目的とするものではない。なお、本借款については、現在までにマラウイ政府の努力によりFRDPのコンディシャナリティのほとんどが実施済みとなっており、所期の目的はほぼ達成されている。
ベトナムに対しては、二国間援助ベースで日本として初めての総合政策支援を実施している。第一フェーズとして、ベトナム政府の5か年計画(1996~2000)策定作業に対して協力。1995年6月から1996年10月まで、現地での調査研究、相手政府関係者との対話などをもとに、総合経済開発計画策定への提言を行った。さらに第二フェーズとして、その成果をもとに、国営企業改革、農業・農村開発、財政・金融政策など4つの個別テーマについて調査研究に着手し、1997年10月を目途に同国政府に提言を予定している。
マラウイはもとより、他の開発途上国、特に後発途上国に対しては、ベトナムに対して行われている総合政策支援を、各国の現状に即して実施することが、極めて有用である。
マラウイにおいても国民に潜在的な自立能力がないのではない。地下水プロジェクトの現地調査でみた村の人々は、自分たちで必要な維持費を稼いで、井戸を大切に管理している。一つの自立の形である。援助側は、そうした能力を育てるのを怠っていたのではないか。
一方で、ある地方のハイスクールでは、校長が、生徒の教育問題そっちのけで、生徒によって破壊された校舎の改修費を日本の援助で賄いたい、と繰り返した。なぜ生徒たちが暴力を振るうのか、改めるにはどのような努力を学校側がしたらいいのか、など反省は全くなかった。自助努力の意欲を失わせて一因が、バラマキ的な援助にあったのではないか。
財政赤字の穴埋めや、外貨不足の補填、あるいは、本来自国政府自身が行うべき公共事業や箱モノの建設を肩代わりするような支援は、できるだけ減らすべきである。現地を見て、もう一度、援助の原点に戻り、当該国が、自力で金を稼ぎ、公共事業を行い、国民を養えるようにするには、どのような支援、援助が必要が、相手がそれを理解できないなら、理解させる努力から始める必要を痛感した。
幸い、同国の政府関係者の間には、途上国の多くに見られるような、「援助をもらうのは当たり前」という援助ずれした姿勢は、会見した人々に関する限り、まだ見られなかった。自立を助ける総合的な支援を実施する余地はまだ残っている、と判断される。
(3) 欠かせない人材育成
以上に関連して、計画策定・実施の能力を育てる必要がある。若手には若干の人材も見られるが、経済自由化の中で、各分野の総合的な計画の策定、実施に当たる人材が決定的に不足している。そのことについてはマラウイの政府関係者からも指摘された。同国の各分野、各層の人材養成は、経済・社会発展のための重要な課題であり、そのための総合的な支援プログラムの策定、実施が求められている。
また、各分野の経済計画の計画策定・実施にあたる専門家を継続派遣することも重要である。現在、農業・畜産省では計画部門の顧問としてJICAから派遣されていた専門家が帰国後、顧問ポストが空席になっている。同専門家は、同国の農業開発計画の策定に不可欠な役割を果たしてくれた、との評価が高く、計画実施の重要な時期を迎えて、同省は日本に専門家の再派遣を強く求めている。現地人の人材育成ともからんで前向きに検討すべきである。
外務省コメント4:一般的に、経済計画の策定・実施にかかる技術協力は長時間を要する場合が多いが、最初から継続派遣を前提とするのではなく、派遣された専門家がその任期中に必要な技術移転を完了し得るよう被援助国側も努力をすることが重要である。但し、専門家、被援助国双方の努力にも拘わらず技術移転が不十分である場合には、専門家の継続派遣につき可能な限り前向きに検討することとしている。
経済協力開発機構(OECD)の開発援助委員会(DAC)は1995年秋に作成した日本の開発協力政策および計画に関する審査報告書で、日本の在外交館、JICA、OECF事務所における現地人スタッフの雇用について、「日本は、機密保持と言語の問題を一つの理由として、途上国のミッションで現地の専門家を雇用することに消極的な姿勢を取ってきたが、OECFとJICAの双方で新しい傾向が現れている」とし、「現地専門家の雇用の増大は、ODA大綱が要請する途上国の能力形勢を促進し、ひいては日本の援助の効果的な実施を助けるものとなる」と指摘している。このような日本側現地事務所における現地人スタッフの雇用のみならず途上国の経済・社会発展に重要な各分野についても現地人の専門家を雇用し、専門技能を育て、さらに彼等が現地での人材育成に当たる事ができるようなシステムも検討する必要がある。その際、イギリス人は二人のみで、各村落での井戸のアフタケア指導などは80人の現地スタッフが担当しているのはNGO、Save the Childrenの活動が参考になる。日本の場合、NGOの活動は歴史も浅く、海外での活動もまだまだ弱体であるが、主体性を尊重しつつ、緊密な連携の下に経験を重ね、スタッフを充実していくような支援も必要と思われる。
外務省コメント5:我が国では、被援助国に対して技術協力を実施する場合には、「自助努力」の原則に基づき、被援助国政府が(自助努力により)雇用する現地人専門家に対して専門技術の移転を行うことを前提としている。また、我が国が現地人専門家を技術移転の対象者として雇用することは、我が国が際限のない雇用責任を負うこととなる懸念もあるため、慎重に検討する必要がある。
(4) 「顔の見える援助」の一環として
NGOの活動を含む人的協力の強化とともに、日本の顔の見える援助を進めるために、日本の援助による事業には、地元の人々が日常的にそれと分かる表示を徹底する必要がある。国民の貴重な税金を使用している事業に、表示を遠慮する理由はない。むしろ積極的に表示することが、日本と被援助国との友好関係を明確にするなどプラスが多い。
今回のマラウイに限らず、南アフリカでも、また一昨年訪れたパプア・ニューギニア、ソロモン群島でも、病院、橋梁はじめあらゆる事業について、そうした表示がきわめて不完全であった。つまり、日本の援助による事業であることが、日常的に利用する人々に十分認識されるような表示がされていないのである。場所によっては、相当予算を使ったと思われる表示も見られたが、設置場所も含めて目立たないものが多く見られた。
井戸のように、もっとも住民に不可欠かつ身近な施設についても、幹線道路の入り口に看板があるのを除くと、日常的に使用する住民には、ほとんど日本の援助は分からない表示がポンプについているにすぎない。
JICAは別個に供与器材にステッカーを貼っていたが、これもよくよく見ないと日本の援助かどうかはっきりしない、供与側の「自己満足」の表示に終っているように見えた。
単純なものていい。例えば「JAPAN・MARAWI/COOPERATION」という表示とともに、両国の国旗をカラーで添えた、各被援助国に対して共通のステッカーを貼り付けることを提案したい。
今回のマラウイでは、現地訪問前の1996年6月に、救急車113台、トラック2台が無償供与されたが、引き渡し式で救急車4台にODAステッカーが貼られたのみで、他の車には、日本の無償供与であることが分かる表示は無かった。またODAのステッカーそのものも、日本人には理解出来ても、地元民にはほとんど分からないデザインである。
115台の車の「宣伝効果」は本来なら絶大なはずである。実際、わずか数日の滞在中にも、われわれの行く先で数台の供与車に出会った。すべての車に、塗装の段階で「JAPAN・MARAWI/COOPERATION」を刷り込むか、それが無理なら上記のステッカーを貼り付けてから引き渡すべきであった。そうすれば、この国の国民に「日本」の好ましいイメージがもっと浸透したはずである。
極端に言えば、このような表示を欠いた援助ならしない方がまし、とさえ言えると思う。援助実行の担当者は、援助を国民の税金で行っていること、国民から被援助国国民へ伝わるような援助を行うべきことを常に念頭に置くべきである。

