7. 村落の井戸建設
(現地調査期間:1996年7月27日~8月10日)
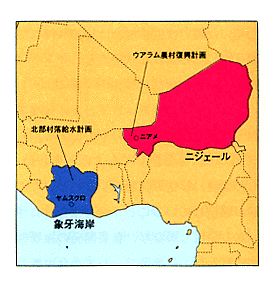
■NGO活動推進センター嘱託研究員 福井 慶則
<評価対象プロジェクト>
| プロジェクト名 | 援助形態 | 協力年度、金額・年度 | 協力の内容 |
|
北部村落給水計画 (コートジボワール) |
無償資金協力 |
1992年度、3.12億円 1993年度、2.43億円 1994年度、2.94億円 |
適切な給水施設を持たない或いは揚水の不足に困窮している地域の村落に、深井戸400本を建設するることにより、衛生的で安定した生活用水を供給し、住民の生活の安定と生活水準の向上を図る。 |
|
ウアラム農村復興計画 (ニジェール) |
無償資金協力 |
1990年度、3.65億円 1991年度、4.41億円 1992年度、3.39億円 |
旱魃、砂漠化の進行により農業生産力が減退しているウアラム郡の村落に、複合井戸65本、浅井戸35本、及び灌漑施設12ケ所を建設し生活用水の確保及び乾期作復興を図る。 |
貧困緩和や地域の生活水準向上を目指して協力事業においては、地域住民の積極的参加が協力の成果を高める上できわめて重要な要素である。そこで、今回、「住民参加」というテーマで、西アフリカにおける水供給案件について、プロジェクトの裨益者とのインタビュー、井戸の利用に関する生活状況の観察等を通し、草の根の視点からプロジェクトの効果や自立発展性等について、評価を行うこととした。
1 コートジボワール北部村落給水計画
(1) 評価
1) 妥当性
水供給は、保健、教育分野と並んで西アフリカ全般おけるBHN分野の重要課題である。
また、同国政府の国家開発計画においては農業生産の拡大が基本目標とされており、水供給は社会基盤の改善と地方開発の強化という同国開発5カ年計画の基本方針にも合致している。特に本案件対象地域である北部地域は開発ポテンシャルの大きな地域として積極的な開発が望まれている。
2) 効率性
工事開始が4ケ月遅れたが、適切な工程管理によって全工事を契約工事期間内に達成したことは高く評価される。
目標数(400本)を上回る本数(439本)の井戸が建設された。但し特定の地方(コロゴ県)に井戸が集中していることや、目標本数を大きく下回った県もあるなど(テンゲレラ県83%、フェルケセドゥグ県70%)地域格差がみられる。
3) 目標達成度
同国政府の要請は北部5県における450本の深井戸建設であったが、日本側が協力して実施する範囲は、不確定要素に対処するため、約10%に相当する井戸を予備数として400本の井戸建設とされた。これに対して、成功率の向上によりハンドポンプ付き深井戸が439カ所建設された。
4) インパクト
本プロジェクトの達成により、以下の3つの直接効果が期待された。
- 計画地域の村落住民に対する所期の計画給水目標(15~20リットル/日/人)が達成される
- 不衛生な飲料水に起因する疾病の抑制する事ができる
- 水の運搬に費やす労力を他の生産活動に廻す事ができる
1については、
個人当たりの給水量=稼働施設数×施設能力(深井戸6,000リットル、浅井戸4,000リットル/井戸)÷対象人口という計算からは北部5県の対象地域の平均は17.3リットル/日/人となり、目標を大きく上回っている。しかし、オディエンネ、テンゲレラ、ブンディアリの西方3県では、15リットル/日/人に達しておらず、地域格差が見られる。
実際に調査を行なった村落(いずれもコロゴ県内)では水不足は起こっていなかった。また建設からそれほど年数が経っていないため、現在まで井戸及びポンプに問題は出ていなかった。しかし
- 水汲みは妻の仕事であり、家事(燃料となる薪集め、調理)や耕作の補助などの理由により、井戸の使用が朝・夕に極端に集中する
- ハンドポンプを設置したことにより1度にひとりしか井戸を使用できない
などの理由により、井戸の水量を100%利用できない実状があるので、今回は調査日数の制限から実際の水の使用料を調査することはできなかったが、井戸の水量や人口などの数値から水源の充足率を見るだけではなく、実際の各家庭の水の利用状況の調査が必要であると思われた。
さらに、近隣の新式浅井戸に設置した数年前のポンプが壊れてきており、それの修理期間(修理できない場合は継続的に)中、近隣部の人々も本計画によって建設された深井戸及びポンプを利用しており、裨益者数は明らかに予定より大きくなっている。
これまで同地域で飲料用に伝統的に利用されてきた表流水、マリゴ、旧式浅井戸は、この地域の水因性疾病の一因となっていた。

同国の給水計画による新式浅井戸の設置と井戸の蓋を兼ねるハンドポンプの設置、それに続く本計画の深井戸の建設及びハンドポンプの設置は、確かに2の水因性疾病の抑制効果が期待できるものである。また水資源局は井戸建設だけでなく、食器類の衛生的な洗浄と保管などの啓蒙活動も計画実施してきた。
しかし、本計画対象地域の疾患に関する1991年以降のデータがまとまっておらず、具体的に本計画実施村落で水因性疾病がどの程度抑制されたのか提示することはできない。
また、北部5州の本計画対象村以外の村落では、表流水、マリゴ、旧式浅井戸が飲料用に使用され続けている。さらに本計画対象地域においても、日中の農作業時には表流水やマリゴが依然飲料水として利用されている。従って水因性疾病の問題は、井戸の建設によってある程度の抑制はできても根本的な解決方法ではない点を認識し、広く衛生意識の向上を目指した啓蒙活動の実施がより一層望まれる。
新しい給水地の建設による、水の運搬に費やす労力の軽減は、本計画の大きな評価ポイントとして、インタビューを行なったすべての村人からあげられた評価であった。具体的にこれまでの水の運搬に費やす労力が軽減された効果の一例として、以下のような状況が見られる。
同国北部地域では、農作業は男性が行ない、忙繁期に女性が作業の補助を行なったり、畑へ食事を運んだりするのが一般的であったが、農業の普及と給水労働の軽減により、女性の畑が作られるようになっているVIII。(但し、労力の軽減は水の運搬距離の減少であり、一回に運搬できる水量と、各家庭の貯水量は変化しておらず、水を汲みに行く回数が減っていない点を忘れてはならない。)
なお同地域には、現在水利関係で他国援助・国際機関・NGOなどの活動はまったく入っておらず、同計画による日本の援助は、知名度・評価ともに非常に高いものであった。
5) 自立発展性
ハンドポンプの整備率、水管理委員会の組織率は明らかに低下傾向にある。(表1参照)
深井戸の設置は村落単位のレベルで資金調達できる計画ではなく、同国政府にしてもその資金は現在のところまったくない。従って同地域における給水量を今以上に引き上げることは新たな援助無くしてあり得ない。
| 地域 | 年 | ポンプ整備率 | 水管理委員会組織率 |
| コロゴ県 |
1990 1995 |
91% 71% |
85% 81% |
| オディエンネ県 |
1990 1995 |
90% 66% |
88% 85% |
出典:コートジボワール政府資料
従って現在の給水量を維持していくことが不可欠であり、そのためには現在使用している新式浅井戸と深い井戸及びポンプの維持管理が必要となる。
本計画では、完成下施設の水資源局負担分の維持管理費としては今後10年間、年間600万CFAが見込まれていた。しかし、引渡後、完成した施設の維持管理にはまったく予算が付けられていない。
また、本計画のために譲渡された2年分のスペアパーツは首都におかれており、8台の車輛は
首都の経済インフラ省 4台
ブアケの地理物理局 1台
ダロアの別の水利計画 1台
オディエンネで中部村落開発計画のため 1台
コロゴ水資源局 1台
に配置されており、本計画のために使用できる車輛は現在1台のみとなっている。また、コロゴの水資源局事務所の予算は事務所長に200~300リットルの車輛燃料費があるのみで、啓蒙活動を行なうための予算もまったくない。
首都の水資源局本局との意見交換によれば、現在は中部・南部の給水状況が悪いため、予算、資機材ともプライオリティーは北部ニないとのことであった。
以上の理由により、現状では水資源局は本計画をまったくフォローできない。
しかし、「象牙」政府の水源施設の維持管理方法が確立されていないことによる既存の水源施設の稼働状況の低下の問題を認識した上で、1987年以後新規水源の建設を中断して既存施設の最整備、住民による維持管理体制の確立を主な目的として世銀資金により実施された「井戸施設再整備計画」は、まさに上記の問題に対処する為のものであったはずである。
この「井戸施設再整備計画」により作られた組織がなんとか現在の井戸の維持管理を支えている状況であり、水資源局事務所もこれを中心に既存井戸の維持を考えている。
「井戸施設再整備計画」により、以下の活動が行なわれている。
- 井戸の利用に関する啓蒙活動
- 水管理委員会の設置
- 担当者の研修
各村の水管理委員会は以下の5人からなる。
ポンプ修理人(グリースの注入のみ) 2名
維持管理(井戸の回りの掃除)担当(女性) 2名
会計担当 1名
財源は井戸水使用量の分担金徴収か水の販売によっている。
さらに、ポンプ修理職人が北部(オディエンネ県を除く)に61人(20~30井戸/人)置かれ、ポンプの修理5,000 CFA、その他3,000 CFAを村が負担する仕組みになっている。
スペアパーツは民営の販売店(CNCI)が担当し、国がスペアパーツを購入してCNCIに卸している。なおコロゴには、すべての郡(4郡)にCNCIがある。
調査の結果以下のことが明らかになった。
1)ポンプ故障時にポンプ修理職人に修理を依頼するシステムと井戸の回りの清掃は機能している。
2)水管理委員会のシステムの現状の問題点は資金的なところに集中している。
- 会計担当が経理ができない
- 村の伝統的ヒエラルキーと結びついていないため、分担金が予定通りに集められない
- 修理費用のプールが少ないので将来的に、ポンプの耐用年数(5年)後ポンプを交換(75万CFA)できないのは明らかである
(2) 提言
1) 村レベル
維持管理費の捻出が一番の問題であるが、より多くの維持管理費を貯える為には、
- 啓蒙活動をすすめる
- 水管理委員会の選任、特に会計担当役は、文盲でない、計算ができる、という最低条件に加え、村の中である程度の実力者という厳しい条件を加える
などが必要であろう。
しかし根本的に、現在の分担金徴収システムでは、10万CFA以上の金額を常時確保することは現実的に困難であり、村落内の井戸のある村落では国が徴収する税金の一部を井戸の維持管理費に充てるなど、行政のサポートによるシステム作りが必要であると思われる。
2) 地方事務所レベル
井戸建設の契約に於いて、井戸回りの整備(壁、扉2、家畜用貯水槽、排水口)を地域住民が行なうこととなっているが、村の家畜数と家畜用の飲料用の貯水槽の大きさが比例していないように思われた。また井戸を保護する壁や扉の材質が村によりバラバラである。実用強度のあるもの、村の実体にあったものが作られるよう指揮マニュアルを作成することによって、きめの細かい指導をすることができるのではなかろうか。
井戸完成後の水管理委員会のフォローが不可欠である。具体的には、維持費のコンスタントな徴収とその支出管理の指導がポイントである。
3) 中央レベル
数年後には、ハンドポンプの壊れた井戸が次々と出てくるという事実をはっきりと認識し、建設後のフォロー計画を再検討する必要がある。
中部村落給水計画を実施していく上で、前述の問題点を充分に考慮した対応が必要であろう。
例えば、日本の援助の枠組みの中で、1年間のフォロー(維持管理のための啓蒙活動)の費用もプロジェクトに含むことは不可能なのであろうか?
裨益者を明確にするために、また裨益効率を上げるために、給水計画の対象村をある程度の規模以上のものに限定する理由は明確であるが、それによって裨益者と非裨益者の紛争が起きないように気を付けねばならない。本計画の実施された北部地域は、広大な未開発地を利用した牧畜も盛んに行なわれており、コロゴ及びフェルケセドゥグ両県には家畜用の水飲場として家畜生産振興事業団により建設された小規模ダムも数多く見られる。従って、具体的な裨益者数が把握できない地点、特に乾期に牧畜民及び家畜の飲料用水の必要な地点を調査して、このような地点に井戸を建設するような配慮も必要と思われる。
(現在は、井戸建設プロジェクトを実施する際は、維持管理のための啓蒙活動をプロジェクト実施中に併せて行うよう、調査計画段階から検討し、採り込むようにしている。)
2 ニジェール共和国ウアラム農村復興計画
(1) 評価
1) 妥当性
ニジェールの国家経済社会開発5カ年計画(1987~1991年)の基本目標の中で、水源確保を含む住民福祉の向上が重点分野となっている。また農村生活環境整備計画においては、具体的な計画として以下の事項が掲げられている。
- 農村住民の生活改善:水、食糧、医療、教育の改善
- 生産環境の回復と保全:水源や土壌の管理と保全
- 生産向上:生産の集約化と多角化
畜産管理、育種、疾病対策
森林の管理と造林
さらに、同国政府は1993年3月に国家最高評議会に於いて水に関する法律「水法」を制定しており、農村・牧畜地域では公共の水保全のため水管理委員会を設置し、村民共通の利益の確保と促進を図らなければならないとしている。
また、水源の配分は、国民の社会・経済的需要を考慮に入れて次のような優先順序で給配水がなされている。
1)住民への飲料水の供給
2)家庭用水
3)家畜飲用及び灌漑用
4)水産養殖
5)工業用
6)水運用
7)電力生産用
8)レクリエーション用
9)衛生・汚水処理
本計画は以上のように、同国家開発計画、水利用の優先順位、地域住民の必要性を踏まえたものである。ただし、
1 水配分の優先順位の3)の家畜飲用のみならず、2)の家庭用水においても、家畜の飲料が考慮されている
また、
1)同地域の大部分の農民が家畜を所有し、牧畜も生活基盤の一部としている
2)牧畜民が多数存在する(特に本計画対象地域北部・中部)
3)農業と牧畜が共生関係にあり、農民と牧畜民の関係維持が非常に重要である
など、
2 同国に於いては「農村」という概念が常に「畜産」も含んでおり、特に本計画に於いては牧畜民及び家畜の存在が非常に重要な要因であるという2点にも関わらず、基本設計調査ではこの点にほとんど言及されておらず、同計画にも計画対象地域の住民の一部である牧畜民への配慮が少ないと思われる。
本計画によって建設された井戸には家畜の飲料用の貯水槽が回りに配置されているが、これは対象村の家畜の為だけのものであり、埃や糞を運んでくる牧畜民の大量の家畜が井戸を利用することも断っている村も多いのである。
2) 効率性
現在ニジェール国政府が構造改善を推進中であり、中長期予算計画を立案しにくい状況、同国北部の治安が安定していない状況などにより、本計画が行なわれていた期間から現在に至るまで、ニジェール国のマクロ経済政策の中でこれまで同地域の農村復興計画は非常に重要なものであった。また、
1)同地域の井戸使用の実状を踏まえ、いたずらに給水量の増加を追求せず、維持管理の困難なポンプを設置しなかった
2)同地域の状況に応じて、柔軟に複合井戸と浅井戸を使い分けて掘削した
3)水源の豊富な場所を厳選して灌漑施設の設置場所が定められている
など、地域の実情に非常によく応じた適正規模の事業が行なわれた点は高く評価される。ただし「農村復興計画」として同計画を見るならば
1)農業分野にとらわれず、より広く環境保全に関わるプログラムを組み込む
2)住民の維持管理に関する啓蒙活動などのアフターケアを計画段階から考える
などの配慮があれば本事業の効率はより大きなものになったと思われる。
3) 目標達成度
1 生活用水の確保
施設建設においては、以下のすべての施設が完成している。
複合井戸 65本
浅井戸 42本
灌漑施設 12ケ所
これによる生活用水の確保(給水量の増加)は25リットル/日/人と推定される。
2 乾期灌漑農業
評価時期が雨期であったため、乾期灌漑農業の実状を実際に調査することはできなかった。しかし、パイロットファームが利用されている形跡は見受けられた。また、パイロットファームの周辺で灌漑用の井戸水を利用して、トマト栽培を行なっていた個人の畑の跡が見られた。

4) インパクト
(1) 生活用水の確保
財務計画省によれば、第1フェーズは30ケ村、第2フェーズは107ケ村が同計画の裨益地域となっている。井戸施設を訪れてみると、確かに1ケ所の井戸は1ケ村のみで利用されているのではなく、近隣5~6か村で利用されているケースが多かった。更に、乾期にマリゴの水がなくなると利用者数は一層多くなるようである。
生活用水の確保で困窮度の高い村落への浅井戸及び複合井戸の建設は、給水のための多大な労力の軽減に大きな効果をもたらし、給水量の向上のみならず、他の生産活動への影響(農業生産の増加及び改善など)も大きなものであると思われる。水の運搬に費やす労力の軽減は、本計画の大きな評価ポイントとして、インタビューを行なったすべての村人からあげられたものであった。(但し、井戸の増加による労力の軽減は、水の運搬距離の減少であり、一回に運搬できる水量と各家庭の貯水量は変化しておらず、水を汲みに行く回数は減っていない点を忘れてはならない。)しかし、行政の不備及び反政府活動の影響などにより、同地域の統計データがほとんどない現状では、具体的な指数を提示することは不可能である。
(2) 井戸の維持管理
本計画で設置された各地の井戸に滑車が設置されたり、井戸を囲む塀や水瓶を置く場所が作られたりしている。施工業者の説明では住民が自主的に設置したものであるとのことであったが、すべてAide et ActionというフランスのNGOが援助したものであった。これは、本計画が広くNGOにも評価され有効利用されているとみることができる。
一方、ドイツGTZの同様のプロジェクトが本計画対象地域で実施されているという情報が現地には入っておらず、他の援助機関との協力関係が配慮されていない点は残念であった。
(3) 灌漑
本調査時期が雨期であり、乾期の灌漑農業を実際に見ることはできなかったが、灌漑施設とその利用跡を見る限り、パイロットファームとして作られた本計画による0.2 ㌶の灌漑施設の回りに、住民が野菜栽培地を作っている形跡が見受けられた。
村によっては、ニアメの業者と契約を交わし、収穫時期になると業者がトラックで農作物を買い付けに来るところもあるとのことである。
(4) 保健衛生の向上
計画対象地域において飲料水に適さない河川水、沼水等を利用している村落の住民に、水系疾病防止対策として清潔な水を安定供給することにより、地域住民の保健衛生面を向上させる効果が期待されるが、この点について具体的なデータは入手できなかった。しかし村落でのインタビューにおいて、複合井戸を利用している村落では主な疾病として雨期のマラリヤ(これも水系疾病)、乾期の感冒のみがあげられたのに対して、浅井戸を利用している村落では、下痢が大きなウエートを占めていたことから、複合井戸の衛生面での効果があるものと思われる。
(5) 過疎化
前述のように灌漑施設の建設は、農業生産の増加及び改善に繋がる可能性があるが、飲料用の浅井戸及び複合井戸のみでは、生活の安定を図ることはできないため、井戸の設置だけが行なわれた村の中では、住民の離散を現在の主要な問題点としてあげていた。
5) 自立発展性
(1) 井戸の及び灌漑施設の維持管理
青年海外協力隊の緑の協力推進プロジェクトの専門家及び隊員からも指摘があったように、ニアメ及びその北側の地域の農民は、共同作業を行なうという意識が皆無であり、従って公共施設としての井戸の維持管理は非常に困難であると思われる。
本調査では確認できなかったが、灌漑施設の利用に於いても、共同作業の意識の欠如から開水路が活用されていないという報告もあった。また灌漑施設では、圃場の周囲に設置したネットフェンスが家畜によって破損された個所も見受けられたが、ネットの材質が簡単に手に入るものでないためそのまま放置されていた。
灌漑用の水路やネットフェンスは効率的であるが、技術的、資金的な問題があり、このシステムは住民に普及できるものではない。この意味でこの灌漑施設を次の段階へのテストのためのパイロットファームとしてみることはできるが、住民への灌漑システム普及を目的としたデモンストレーションファームとして位置づけるのは難しい。
なお、灌漑施設の周囲に小さな菜園がいくつか作られているところがあり、農業活動に対する意欲を高めた点は高く評価できる。しかし上記の理由からか、これらの菜園は灌漑システムを有しないものであった。また各菜園の規模から、それぞれの菜園は個人(家族)単位のものであると考えられ、やはり村としての共同意識の形成は認められなかった。
(2) 現地の主要問題
各村でのインタビューにおいては、日常生活における問題を問うても即答されることが少なかったコートジボアールの北部村落とは大きく異なり、ウアラム郡では、この問いに対して食糧不足と医療施設の不足がすぐさま挙げられた。雨期はどの住民も自然発生する野草を利用しているが、乾期はウアラムの町に副食を買いに行く必要があると一様に述べている。
(2) 提言
本計画に対してニジェール国政府は、以下のような中長期目的(上位目標)を設定していた。
- 農業、森林、家畜生産力の保護と復興
- 食物自給率の改善
- 農家収入の改善、生活環境の改善
- 開発計画への住民参加
これを踏まえて、以下に提言を述べる。
1) 村レベル
1 井戸
複合井戸と浅井戸の衛生面での水質(細菌)の違いを調べる必要があると思われる。仮に両井戸の衛生環境に大きな違いが表れた場合は、浅井戸を利用する村を重点とした衛生啓蒙活動などが必要となろう。
また本計画対象村以外の村落では、マリゴ、浅井戸が飲料用に使用され続けている。本計画対象村においても、日中の農作業時にはマリゴが依然飲料水として利用されているのみでなく、本計画によって設置された井戸以外の、古い井戸もやはり使用され続けている場合がほとんどである。また、本計画で建設された井戸における食器洗いや洗濯、子供の体洗いが行なわれているケースも見られ、従って水因性疾病の問題は、井戸の建設によってある程度の抑制はできても、根本的な解決方法ではない点を認識し、広く衛生意識の向上を目指した啓蒙活動の実施が望まれる。
複合井戸と圃場は、衛生面の配慮からあえて距離を置いて建設されたが、住民にはこの点がまったく理解されておらず、むしろ不平が上がっていた。建設したものの利用方法やその建設意図を説明することで、より適切な施設の利用がなされるものと思われる。
2) 地方事務所レベル
1 灌漑施設
灌漑施設を農業活動の普及のためのデモンストレーションファームと位置づけるのであれば、村人の(資金・技術)レベルでできるようなものにする必要がある。また、農業活動への意欲向上のためには、きめ細かな農業指導、特に営農指導を中心としたフォローか不可欠であろう。
灌漑用の圃場の土地は、村の男性の頭数で分割されている。しかし、野菜栽培の灌水は女性の仕事であり、一夫多妻や未亡人の存在の多い同地域の現状にこのシステムは適合していない。施設の利用を計画する段階から、地域の土地利用に対する知識と経験を有する地方の農業事務所との連携が必要であると思われる。
3) 中央レベル
1 環境保全への対応
ウアラム地域を対象とした世銀による「自然資源国家プログラム(PNRN)」が計画されているが、これに、本プロジェクトで建設された井戸、灌漑施設及びその建設の基本方針が理解され、その維持管理を考慮に入れた具体的なプログラムが作成されることが望まれる。
今後の水資源の利用計画においては、世銀等をドナーとする、植林を含む環境保全の「環境と持続的開発国家プログラム(PNED)」が1995年から25年のタームで実施されているので、これをよく分析し、その方針を取り入れることが必要である。
2 NGO等との連携
ニジェール政府が単独では、事実上まったくプロジェクトの実施及びフォローができない現状を鑑み、前述のAide et Actionのような機関と、計画段階から意見を交換し、協力形態を確立した上で計画を実施するようなスキームが採れないのであろうか。例えば、日本政府による施設の建設後のフォローを他の機関に委託するシステムが考えられる。
3 医療機関などとの連携
実施段階で活動分野を限定した場合(今回であれば水資源・農業分野)でも、「農村復興計画」と謳うのであれば、実施しなかった分野について、相手国政府が次のステップにこれをどう組み込んでいくのか、ある程度のガイドラインを策定する必要があろう。
4 畜産への対応
1990年末から始まったトゥアレグを中心とする反政府活動の要求を汲んで定められた1995年10月のタウア会議により、遊牧民の権利及び牧畜への配慮が大きく取り上げられている現在、定住民だけでなく、実態を把握しにくい牧畜民も開発計画に組み入れる配慮が不可欠である。

