6. 水力発電と農業開発(ブータン)
(現地調査期間 1997年3月27日~4月9日)
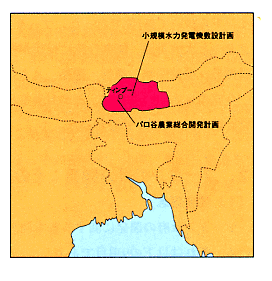
■明治学院大学国際学部教授 平島 成望
<評価対象プロジェクト>
| プロジェクト名 | 援助形態 | 協力年度、金額・年度 | 協力の内容 |
| 小規模水力発電機敷設計画 | 無償資金協力 |
1985年度、6.24億円 1989年度、8.74億円 1990年度、5.67億円 |
ブータンは第5次5ヶ年計画において、国民生活の質的改善のため教育・医療・通信各公共施設の整備を進めている。しかしその対象地域の多くは電気の供給がなく障害となっている。大規模な水力発電所や送配電網の建設は社会経済事情から極めて困難であるため、小河川を利用した小規模水力発電施設による電化を進めることとし、その中で緊急度の高い10ヶ所の施設の建設と、必要な機材を供与した。 |
|
パロ谷農業総合開発計画 |
無償資金協力 |
1989年度、6.25億円 1990年度、4.34億円 1993年度、8.56億円 1994年度、7.16億円 1995年度、5.87億円 |
ブータンにおいては、農・畜産業は国内純生産の41.4%、就業人口の87.2%を占める最も重要な産業である。しかし国土の大部分がヒマラヤ山脈の山岳地帯で占められ、農地が8.8%、356,000ヘクタールと少なく食糧自給が達成されていない。パロは農業の先進地区とされているが、灌漑施設、農道及び河川護岸の農業基盤が未整備であるため、これらの基盤を整備し農業の近代化を図ろうというもの。 |
1 はじめに
ブータンは、人口60万足らずの南アジアの小国である。この国が経済開発に本格的に取組み始めたのは、1961年に始まる第1次五ヵ年計画であるが、その後GNH(Gross National Happiness)の向上を目標として着実に成果を挙げ、現在第8次五ヵ年計画(1997~2002)に入ったところである。
ブータンの開発努力は、当初インドによって支援され、現在も続行しているが、第3次計画の頃からその他の外国援助が増加し、全国で数多くのプロジェクトが進行している。日本は農業(Renewable Natural Resource)セクター、テレコムの発展に寄与しており、第7次五ヵ年計画の外国援助額3.26億ドルの14%を占め第1位であった。。また1994年時点のデータでも、日本はインドを抜いて第1位であった。(第1図)。ブータンに対する外国援助のセクター別分類は第1表のとおりであるが、農業セクターと人的資源、開発行政に援助が多く集まっている。その他の分野としては、地域開発、保健医療、通信・運輸、エネルギーが挙げられる。
今回の日本ODA評価は、その対象を小規模水力発電施設整備計画とパロ谷農業総合開発計画の2つに絞って行われた。訪問地と面談者、行動工程等は別表のとおりである。
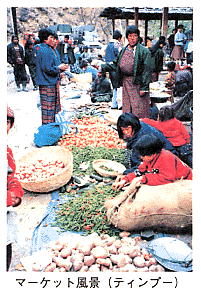
2 ブータンの経済開発:その基本的スタンス
(1) 開発理念
ブータン政府の開発に関する基本的アプローチは、第8次五ヵ年計画の中に明示されている。それは以下の9項目である。
1.自立 (Self-reliance)、2.持続性(Sustainability)、3.文化、伝統的価値の保存、4.国家安全保障、5.均衡のとれた発展、6.生活の質的改善、7.制度基盤の強化と人的資源の開発、8.地方分権化とコミュニティー参加、9.民営化の促進
これら9項目に述べられた開発理念を要約すると、宗教的、文化的伝統によって国家のアイデンティティーを保ち、地域の特性、環境に調和した経済成長とその成果の適正な分配を通じ自立を図るということになる。実質的にはルピー経済圏にある小内陸国ブータンが、第2のシッキム化を避ける手段は、インドからの自立であり、そのためには健全なマクロ経済運営と、住民参加による社会セクターの充実を核とする地域開発が不可欠であると認識されているのである。したがって、教育、医療、農業、電力、通信・運輸、エネルギーが開発の重点分野として位置づけられることになる。
この点は第1次五ヵ年計画から第7次五ヵ年計画の資金配分にもよく表れている(第1表)。インド政府によって支援されていた第1次、第2次五ヵ年計画の重点項目は、インフラ建設、社会セクター、農業であった。その後の計画で一貫して高いのは社会セクターと農業セクターであり、インフラへのウェイトは減少している。注目すべき点は、第5次計画以降、政府行政、地方行政への資金配分が急上昇していることである。これは中央・地方行政の効率化を実現するための制度化策と見ることが出来る。
(2) ブータンの社会セクターの発達
ブータンのここ10年間の社会セクターの発達には目を見張るものがある。総合的指数としてのUNDPのHDI(Human Development Index)を用いて示すと、1984年は0.310であったが、1994年には0.510に上昇している。この数字は、同年のスリランカ(0.665)には及ばないものの、インド(0.382)、パキスタン(0.393)、ネパール(0.289)、バングラデシュ(0.309)を大きく上回るものである。同様に成人識字率も28%から46%に上昇し、南アジアではスリランカ、インドに次ぐ数字である。その他の社会セクターの指標(乳幼児死亡率、医療関係機関、平均余命等)も過去10年間に著しい改善を示している(付表1)。これらの実績は、初期レベルの低さもさることながら、スリランカを除く他の南アジアの諸国と比較する時持ち出している。しかし、さらなる発達は、運輸・通信、電力といった地域開発の根幹となる分野への投資に依存している。その意味で、通信、電力、農道を含めた農業開発をODAの中心に置いてきた日本のアプローチは適切であったと言える。
3 小型水力発電計画
(1) マイクロ(micro)、ミニ(mini)発電の背景
すでに述べたように、ブータン政府はGNH達成のためには、地域開発が重要であるとしている。第7次五ヵ年計画には、開発へのアプローチとして次の6点を挙げているが、均衡のとれた地域開発もその1つである。
1.自立(self reliance)、2.持続性(sustainability)、3.効率と私的セクターの発達、4.住民参加と地方分権化、5.人的資源開発、6.地域の均衡発展
第4点に挙げられている住民参加と地方分権化の促進も、地域開発の核となるアプローチである。これらの目標を達成するために最大の制約となっているのが運輸・通信と電化である。ブータンの包蔵水力は2万メガワットで、その中開発可能な水力は6000メガワットと言われている。第5次五ヵ年計画(1981~87)の1984年当時、最大の水力発電所チュッカ(chukka)はまだ完成しておらず、電力供給設備は19000キロワットで、23町、93村落、9300戸が電化されているにすぎなかった(全町村の3%)。民需の大部分(1990年ですら77%)が薪に依存していた。電化されていた地域も首都ティンプー(Thimphu)、空港のあるパロ(Paro)、1部の南部地域(プンツオリン、Phuntshuolinq)に限られていた。国全体が山岳地帯で地形が急峻であるのに加えて、小規模な住居区が散在しているので、送配電網の建設は技術的にも困難であり、経済性もないと判断されている。このような状況の下で、ブータン政府は全国150ヵ所の小規模水力発電施設整備計画を策定した。しかし、これを実行に移すには、資力も技術力も不足していた。そこでブータン政府は、日本政府に対し、その中で最も緊急度の高い10地点に関して、無償援助による協力を要請したわけである。
この要請を受けて、JICAは1985年4月7日から5月5日にかけて基本設計調査団をブータン国に派遣した。同調査団は、7県(Punakha、Bumthang、Tongsa、Wangdi Phodrang、Shemgang、Moogar、Geylegphug)に存在する10地点の調査を行い以下のような結論に達した。
1)Thimphu、Phuntsholinq、Geylegphugを除き、多くの国民は山間部に散在している。
2)電力供給は、Thimphu、Paro、Phuntsholinqに集中し、地形的に相互融通が不可能である。
3)包蔵水力は6000メガワット(600万キロワット)存在するものの、河川勾配が急で地質も複雑であるために、大規模貯水池式発電所の適地は少い。しかし、流れ込み式中小規模の水力発電の可能性は、多くの中小河川、渓流、灌漑用水路を利用することにより高い。
したがって、マイクロ水力発電(50~60キロワット以下)とミニ水力発電(200キロワット程度)の建設は、以下の便益をもたらし、地域開発の目標に合致するものと考えられる。ちなみに、今回の建設予定地は、Tongsa県を除いては全て未電化地域である。
1)地域社会の教育、医療レベルの向上
2)地域の産業経済活動の促進による雇用効果
3)照明、炊事、暖房用薪木集めの労働節約による生活の改善
4)森林資源の保護、治山、治水効果
5)ディーゼル職人・外貨の節約
6)住民参加の維持管理、電力局の巡視点検等による技術移転と人材育成
ブータン国に対するこれまでの水力発電協力は2つのフェーズに分けられている。
フェーズI:マイクロ水力発電10基
プロジェクト期間:1986~87
無償資金供与:6.24億円
フェーズII:ミニ水力発電3基
プロジェクト期間:1990~92
無償資金供与:14.41億円
(2) 計画の概要
フェーズIは第7表及び第3図に示されるように、1987年の2月~4月に完成した。発電能力は20~70キロワットと小規模である。これらの発電所は、まずその地域の公的施設に電力を供給し、余った電力は民間に供給される仕組みである。公的施設の代表は学校及び寄宿舎、病院、BHU、農業関連施設、地方事務所である。電力の供給を受けた民家の数は各発電所当たり25~95戸の範囲に止まっている。
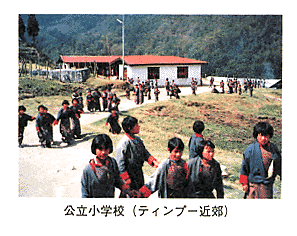
フェーズIIは、発電規模を拡大し200キロワット(100キロワット×2)の発電所を3ヶ所(Shemgang, Chirang, Daga)に建設した。1992年4月に全て完成し、政府関係施設及び民間の電化に貢献している。
これらの発電所の維持・管理は、住民参加の原則が守られ、水路の清掃、運転を担当し、日常的な技術管理は、地方事務所(ゾンカ)の技師が担当する。しかし、より高度な技術管理は、本局(通産省電力局)から派遣される6ヶ月に1度の巡回点検班に委ねられる。ミニ水力発電の方は、当然日常の技術管理に当たる技師の数も多く、3~4人を数える。維持管理費はブータン国政府の管轄事項である。
(3) 総合評価
小規模水力発電機敷設計画の上位目標は、国家開発計画で設定された目標の中の、住民参加による地方分権化、地域開発の促進に求めることが出来る。その上位目標は、地域における社会セクター(教育・医療)の向上、地域行政の効率化、地場産業の育成等によって達成されると想定され、これらがプロジェクト目標となる。プロジェクトの直接的アウトプットは、いうまでもなく、プロジェクト目標を達成するための電力供給である。
上記の枠組の中で、評価5項目について所見を述べることにする。
1 実施の効率性(Efficiency)
このプロジェクトは、ブータンの自然条件、居住の形態、資源賦存度、要素比率等の諸条件から判断し、最適の選択であったと思われる。総合的にこのプロジェクトは成功したと評価することが出来るが、その主な要因は以下のように考えることが出来よう。
第1、ブータン政府の良き統治(good governance)である。力量の差は別として、中央の電力局の担当者も地方の技師もそのaccountabilityには一定の評価を与えて良い。
第2、発電機の選択に際して、出来るだけ自動化の進んだ機種を選択したことである。このことは、O&Mに高度な技能を要する機種であれば、ブータンの技術水準では償却期間が縮小されるという判断に基づいている。日常の操作が村人にも簡単に出来、ローカルの技師は簡単な日常の維持管理を行い、高度な修理は中央からの巡回点検に委ねるという方式は、現状に関する正確な理解に基づいて工夫されたものである。
第3、規格の標準化がなされたが、同時にインドで生産可能な部品との互換性を考慮した点である。この点は重要である。
第4、電力供給の最優先度を家庭の電化でなく社会セクターに置いたことである。地域開発の視点として最も重要な側面がきっちり認識されている点を高く評価したい。
第5、フェーズIではマイクロ水力発電であったが、フェーズIIではミニ水力発電が試みられている。後者は前者に比べて地場産業育成への電力供給も射程内に入ってくることが確認されたので、今後はミニ水力発電の可能な地域には、マイクロ水力発電よりもプライオリティーが置かれることになると思われる。
第6、住民参加の視点として重要なことは、その受け皿になる村落レベルの組織力、自治能力の水準である。苛酷な環境の中で、稀少資源の動員、維持、分配のために築きあげた自然村レベルの組織力が、このプロジェクトの遂行のために重要な役割を果たしていることを銘記しておきたい。
2 目標達成度 (Effectiveness)
全ての水力発電機が大きな故障もなく作動し続けていることは何よりの実績である。すでに述べたように、マイクロ発電所は、その地域の教育、医療施設、政府関係事務所に24時間体制で電力を供給し、余剰電力は市町村住民の電化を可能にした。ミニ発電所は、これに加えて、産業の育成にも寄与している。その意味で、設置された能力の範囲で、これに加えて、産業の育成にも寄与している。その意味で、設置された能力の範囲で、これらの発電所は、プロジェクト目標を十分達成していると言える。
3 インパクト(Impact)
このプロジェクトの上位目標は、プロジェクト目標の達成によって部分的には達成されたと言えよう。部分的という意味は、地域開発という「面」の広がりをもつ目標に対して、これらのプロジェクトは未だに「点」にすぎないからである。さらに、このプロジェクト、特にマイクロ発電は、すでに述べたように、地域開発の核を形成する部分にインパクトを与えているものの、地域住民の電化の夢を十分達成しているわけではない。地域開発には、住民への電化の普及とともに、産業構造の高度化を促進するための電力供給という今1つの核の部分が残されている。この部分は、ミニ発電プロジェクトが、わずかではあるが、その可能性を示唆している。しかし、これも「点」以上の何ものでもないのが現状である。
このプロジェクトの最も大きな便益は、すでに述べたように、教育向上に与えたインパクトと、医療保健に与えたインパクトであろう。しかし、このプロジェクトによる発電能力は余りにも小さく、薪木に代替する電力は住民には供給されてはいない。したがって、森林資源の保護や、治山、治水へのインパクトは認め難い。しかし、既電力化地域のディーゼルの代替は実現したので、わずかであろうとも外貨節約には貢献していると言えよう。
このプロジェクトに関するネガティヴなインパクトを見出すことは困難である。強いて見出すとすれば、立地選択における不透明さぐらいであろうか。
今1つ特記しておきたいことは、このプロジェクトによって日本ODAが高く評価されたことと、しかもローカルなレベルで評価されている点であろう。
4 妥当性 (Relevance)
このプロジェクトは、国家開発目標に合致するものであることは繰り返し述べた。それよりも重要なことは、Tongsaを除いて全て未電化地域にプロジェクトが立地し、ローカルなニーズの核心部分を満たす端緒を作ったという点であろう。今後共にこのようなプロジェクトが「点」から「面」を目指して推進されることが望ましい。
5 自立発展性(Sustainability)
このプロジェクトによる13の水力発電所は10年を経過した今日まで全て稼働している。投入された機材1施設、人的資源、資金も有効に活用されている。ブータン政府も中央、地方共に維持管理費と人材を確保している。
問題があるとすれば次の点であろう。
第1、問題は発電機そのものでなく、取水堰、水路上に見られる。玉石が水路に流入するのを防ぐカバーは、例外なく流出(紛失)していたし、砂道の制御ハンドルも2ヵ所で故障して放置されていた。故障箇所が放置されている理由の1つは、中央と地方の予算の仕組に見出せる。地方の予算が計上されると、その年度に予算外の支出を要する事態が発生しても、中央予算も地方予算もそれに対応することが出来ない仕組になっている。このことの解決には、先見性と同時に、予算の構造の修正が必要と思われる。
故障箇所の放置が予算の仕組によって部分的に説明出来ても、2年以上放置されることの説明や、故障の発生源の説明にはならない。前者に関しては、発電そのものに決定的支障がないという判断、後者については、家畜の通過を取り締まれなかったという事実が存在する。そのいずれにしても、管理体制の不十分さを指摘せざるを得ない。
第2、技術水準の低さ、特に中央と地方とのギャップの大きさが問題になる。プロジェクトが持続可能になるためには、少なくとも2段階を経なければならない。まず第1は、現在6ヶ月に1回の中央電力局からの巡回点検の技術を、地方(ゾンカ)レベルの技師でまかなえるようトレーニングすることである。第2段階として、中央電力局の技術水準を、発電機のオーバーホール出来る水準まで高めることである。そのためにも、プロジェクトに関係する技術者のトレーニングは、海外研修も含め時間をかけることが必要であるし、それが持続性を高める近道でもあることを強調しておきたい。
4 パロ農業総合開発計画
(1) 計画の概要と推移
プロジェクトの対象地域であるパロ県は、ブータン国農業の最先端地域である。ブータン国の農業セクターは、プロジェクトの始点でGDPの41.4%、労働人口の87.2%、農地の8.8%を占める基幹産業であった。
ブータン政府は、第6次5ヵ年計画(1987~92)における農業開発の目標を以下の3点におき、全投資の20%をこれに当てている。
- 主要食糧穀物の自給率の向上
- 換金作物の導入による所得増加
- 土地、労働生産性の向上
この目標達成の手段として、いわゆる「成長軸」の考え方を援用し、農業生産性の高い5つの地域を農業開発重点地区に定めた。プロジェクト対象地域であるパロもその中の一つである。

1987年FAOアジア太平洋地域事務所は、ブータン政府の要請を受け、パロ谷4地区の農業開発計画案をまとめた。その報告を受けて、ブータン政府はその実施を日本に要請してきた。JICAの事前調査は、1988年11月に行われ、1989年3月29日~4月26日には基本設計調査団が派遣された。
FAOの基本設計に対し、日本側が修正を加えたのは3点である。
- FAO原案では、パロ谷を流れるパロ川とその支流であるドーティー川の中、ドーティー川地区を重点に開発を進めることになっていた。この案では、農家当り投資額が巨大になり、他の地域開発のモデル的役割を果たさない。したがって、パロ谷全域をカバーするエクステンシブな整備計画にするべきである、というのが日本側の考え方であった。
- 整備計画の内訳として挙げられている灌漑用水路、農道、河川護岸、圃場整備は妥当であると判断された。しかし、そのために必要な建設機材、コンクリートプラントの建設が必要とされ、計画に追加された。
- 圃場整備に関しては、パイロット事業として位置づけるのが妥当であると判断された。
以上の修正点を取り入れた日本案は2つのステージに分け実施されることになった。当初の事業計画は第8表のとおりである。初年度はコンクリートプラントの建設に当てられ、次年度(ステージI-2)から灌漑、護岸、農道の改良及び新設が始められることになっていた。ステージ(I-1)は、1990年6月に開始され、ステージ(I-2)は1991年2月から着工され、1992年2月に完了予定であった。しかし工事途中の1991年9月に計画地区内のジャンサ橋(Jansa)が洪水のため破壊された。この橋の修復なしにはプロジェクトが進行しないとあって、ブータン政府は急拠日本政府に対し、ジャンサ橋の掛け替えを要請した。これを受けて、ジャンサ橋の建設がステージ(I-3)で行われることになった。したがって、ステージ(I-3)は1993年9月に開始され、1995年の1月のステージ(II-1)に引継がれ、1997年3月のステージ(II-2)をもって完了することになった。(付表2)
プロジェクトの総費用は以下のとおりである 。
ステージ(I-1) 6.25億円、ステージ(I-2) 4.34億円、ステージ(I-3) 8.56億円
ステージ(II-1) 7.16億円、ステージ(II-2) 5.87億円、 合計 32.18億円
(2) パロ農業の位置付けと特徴
すでに述べたように、パロはブータン農業の先進地域であり、かつ5大重点開発地区の1つである。当プロジェクトの位置付けをするために、先ずブータンとパロの関係にスポットを当ててみよう。
第9表は、パロ農村の特徴を見たものであるが、ブータン国全体の農村の数は1737であるが、その5.6%の97村がパロに存在する。しかし、村落規模も1農家当たり人口も全国平均より小さい。パロの特色は農業機械化の進展とともに家畜頭数の多いことに求められる。(第10表、第11表)前者に関しては、winnower、脱穀機、パワーティラーの普及が見られ、後者に関しては、1戸当たり5頭の役・乳牛を保有し、ヤク、馬、豚の保有も全国平均を大きく上回わっている。
第12表は、土地利用についてパロの特徴を見たものである。同表によって明らかな点は、先ず耕地に関しては、水田、畑地、果樹園比率が全国平均を大きく上回わっていることである。しかし耕地比率は平均より低い、これはパロに焼畑地帯がないせいである。森林に関しては、高度の関係もあり、針葉樹の比率が圧倒的に高い。
第13表は、農業生産におけるパロの特徴を見たものである。先ず作付形態の特徴は、コメ、小麦、ポテト、リンゴ、野菜の作付比率の高さに見られる。総生産におけるパロの比重は、リンゴにおいて他を圧倒し、全国生産のほぼ半分を占める。次にポテト(12.1%)、小麦(13.4%)、野菜(9.9%)、唐辛子(10.1%)が続いている。パロは収量においても平均を上回わり、平均を下回わっているのは、メイズ、小麦、オレンジのみである。
以上のデータから、ブータン国における農業開発目標である主食穀物の増産、作付多様化の促進、土地・労働生産性にとって、パロ農業に対する期待が伺えよう。当プロジェクトはこの目標達成のためのインプットである。
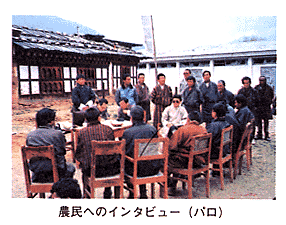
(3) プロジェクトの計画と実績
パロ農業総合開発計画は、当初5つのコンポーネントから成り立っていた。すなわち、灌漑用水路、取水堰の改修、農道建設、護岸工事、圃場整備、コンクリート・プラント建設である。しかし、最終的には圃場整備が中止となり、工期中に壊れたジャンサ橋の建設が追加された。
(4) 総合評価
パロ農業総合開発は、この国の開発目標の柱の一つであるself-relianceと地域開発という上位目標を達成するための手段として位置づけられる。プロジェクト目標は、5つのコンポーネント、すなわちコンクリート・プラントの建設、灌漑用水路の改修、農道の建設、河川護岸、ジャンサ橋の架替による農業生産性の上昇、主食穀物の増産、換金作物の増産、農地保全、農業機械化の進展、農産物出荷量の増加等を通じ、農家所得の増加と地域の活性化を実現することである。
これらの枠組を念頭に入れ、項目別評価を行うことにしたい。
1 実施の実効性(Efficiency)
第17表は、プロジェクトで計画されていた工事と実績を比較したものである。灌漑用水路の改修に関しては、達成率は87.7%である。これはジャンサ橋の架替期と重なって、ステージ(I-3)で工事が出来なかったことによる。ただし、フェーズIの基本設計調査報告に計画されていた取水堰は、コンクリート取水堰が2ヵ所(水路№21、28)、木工沈床堰が1ヵ所(水路№17)が追加建設されている。農道建設の達成率は105.1%、河川護岸の場合107.6%といずれも目標値を上回った。
コンクリートプラントも予定通り完成し、建設機械も1ロット追加納入された(第18表)。圃場整備は中止されたが、これは妥当な措置であったと思われる。直接的理由は、工事期間中の所得補填にあったと言われるが、圃場整備は本来新規に用水路が建設される時に行うべきものであり、本プロジェクトのようにリハビリが主体である場合はなじまない。
ブータン政府は、このプロジェクトに61名のスタッフを配置しており、支援体制が整っていたこともプロジェクトが実効性をもった大きな要因であったと思われる 。
実効性(efficiency)について2点コメントを加えておきたい。第1点は、このプロジェクトはグラントであるので、プロジェクト資金の経済性を厳密に問題視する必要はないかも知れない。しかし、もしこのプロジェクトの直接的便益が、期待値の範囲であるならば、その収益性は8%となり、資本投下の効率を実証することになる。第2点は、このプロジェクト運営の仕組に関するものである。このプロジェクトにより供与された建設機械類はブータン政府(農業省)の所有となる。そしてこれらの機械類はオペレーター付きで、工事を担当する建設会社(大日本土木)に賃貸される。建設会社の納める賃貸料は政府の収入となる。第19表はこの面の収支バランスを示したものであるが、1994年度から収入が支出を上回り、プロジェクト期間で見ると収入が支出を51%上回っている。これもブータン政府の実効性を示すものと言えよう。
2 目標達成度 (Effectiveness)
すでに検討したように、プロジェクトの物理的側面での目標達成度は満足すべきものであった。しかし第4図に示されるプロジェクトコンポーネントと生産増、所得増との因果関係を確定するにはデータが不十分である。この点で検証されるべき事項は以下のとおりである。
—灌漑用水路及び取水堰の改良は、農業生産を安定させ、かつ土地生産性を上昇させたか否か。
—農道の改修及び新設は、労働生産性を向上させ、作物の多様化と市販余剰の増加を促進したか否か。また、農業機械化と投入財の搬入を容易にすることにより生産増加と効率の向上に貢献しているか否か。
—河川護岸は農用地保全に寄与しているか否か。
—建設機械、コンクリートプラントは、今後の土木工事にとって、技術移転、人的資源の開発の面でプラスに作用しているか否か。
これらの設問に答えるために2つのデータを提示する。第20表は、1997年にブータン政府(農業省)の協力を得て評者が行った農村調査の1部である。この表は、今回プロジェクトの対象になった8村落の5村を選び、各村落から10戸の農家をランダムに選びインタヴューしたものである(付図3)。この表によって傾向的にはっきりしていることは、コメの改良品種の普及、収量の増加、リンゴの作付面積の増加、野菜の作付面積の増加、乳牛の増加、市販余剰、農家所得の増加、灌漑用水の増加と安定、農産物、投入財、農業機械の搬出入の容易さ等である。その他の項目に関しては各村落によって答えにバラつきがあり、一般化して言うことは出来ない。しかし、これらの傾向は、プロジェクトのコンポーネントが村落社会にインパクトを与えていることを証明するものである。
| 村名 | Tsento | Shani | Wangchang | Shaba | Lango | ||||||||||||||||
| A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | ||
| 1.コメ(品種NO.11)の作付面積 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | |
| 2.コメ(赤米)の作付面積 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
| 3.コメの収量 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
| 4.ポテトの作付面積 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5.リンゴの作付面積 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 6.野菜の作付面積 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| 7.牛乳の頭数 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
| 8.農業機械の使用 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | |
| 9.労働交換に費やす時間 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | |
| 10.共同作業に費やす時間 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | |
| 11.市販余剰 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| 12.非農業所得 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| 13.農業所得 | 8 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| 14.灌漑用水の量 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
| 15.灌漑用水の安定性 | 4 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
| 16.洪水からの防御 | 1 | 5 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| 17.搬出入の容易さ | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
| 18.肥料投入量 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| 19.農家の使用量 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 20.賃働きの度合 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
(出所) パロ谷5村の調査より
A=増加、B=不変、C=減少、D=該当せず/回答なし
さて、そのようなインパクトは、具体的にどのような成果となって定量的に把握出来るだろうか。第21表は、プロジェクトの開始時点とその最終段階に相当する時期(1990~1996)において、農産物の生産が当初の目標値に達しているか否かを検証したものである。プロジェクト計画書には、プロジェクト完成により、コメ900トン、ポテト2,800トン、リンゴ3,400トンの生産増加が実現し、その市場価値は2.6億円であることが明記されている。第21表からは、生産の増分がコメ3,673トン、ポテト1,840トン、リンゴ3,004トンであることが示される。コメは目標値の4倍を達成したが、ポテトは66%、リンゴは88%であった。ただし、リンゴに関しては、プロジェクトによる作付面積の増加はまだ十分生産に反映していない。収量の減少がこれを示している。もし全てのリンゴが成育すると、収量は1990年の水準に戻ると思われるので、生産の増加分は3,004トンでなく4,058トンとなる。目標値は達成されると考えて良い。したがってポテトのみが目標値を下回ることになる。全体として2.6億円の生産増加は達成されているし、何よりも主食のコメの増産が目標値をはるかに上回った点と、リンゴの増産が、コメの減少を伴って実現しているわけではない点を良しとしたい。
| リンゴ | ポテト | コメ | |||||||
| 作付地 | 生産量 | 収量 | 作付地 | 生産量 | 収量 | 作付地 | 生産量 | 収量 | |
|
1990 1993 1995 バランス (1989~1995) |
144.6* - 725.0 580.4 |
1.346* - 4.350 3.004 |
9.31* - 5.97 (-)35.8% |
489.7 544.4 625.0 135.3 |
3,413 5,253 5,253 1,840 |
6.97 - 8.40 20.5% |
1,509.5 - 2,6700 1,160.5 |
4,521 - 8,194 3,673 |
3.00 - 3.07 2.3% |
出所)1995年 GOB. LUPP Dzongkhg Data Sheet for Bhutan,
1995
1989年、1993年 JOCV小松氏のご協力により入手(農林省データ)より作成
* 1989年の数字
参考:
プロジェクトによる直接効果目標値(生産増加)と達成率
コメ 900トン (408.1%)
ポテト 2,800トン (65.7%)
リンゴ 3,400トン (88.4%)
3 インパクト(Impact)
まずこのプロジェクトの性格として理解しておかねばならないことは、全く新しく作られた部分は、コンクリートプラントを除くと、農道のみであるということである。この点の要素移動に果たしている役割は多くを論じることはないだろうし、第20表にもそれははっきりと示されている。直接生産にかかわる部分の灌漑用水路と取水堰は、新規の付加部分ではなく、既存の施設の改良である。上水路の三面舗装、取水堰のコンクリート、木工沈床による恒久化は、生産効率の向上に寄与する投資である。そして河川護岸は、それがなければ流出してしまう危険性のある農地の保全であり、耕地拡張ではない。
4 妥当性(Relevance)
本プロジェクトは、全体計画、そのコンポーネント、中盤の変更、どれをとってもブータン国のニーズに合致するものであったと言える。問題があるとすれば、取水堰の選択であろう。つまり木工沈床である。すでに指摘したように、今回の灌漑工事は、既存施設の改良にあった。そして、それを維持管理する組織も伝統的に存在していた。したがってそれを前提とした時、一時的な背割堰を恒久的なコンクリート堰に切り替えるにはリスクが高いと判断された。松の木を用いる日本の伝統技術である木工沈床は、丁度両者の中間にあり、既存の維持管理組織の機能を生かし続けることが出来る(木工沈床は木枠の中に金網で包んだ玉石が積まれており、常時玉石の流出をチェックし補充する作業が必要である)という配慮があった。しかし、後述するように、水管理組織が全く新しく衣替えしたために、本来の管理機能が動かなくなっている。伝統水利に対する近代技術の調整的適応というノーブルなアイデアが生かされるか否か即断は許されないが不安の残る点ではある。
5 自立発展性(Sustainability)
プロジェクトの全てのコンポーネントは順調に活動している。コンクリートプラントで作られるU字溝はもとより、不良品にいたっても需要農家が絶えない有様である。
投入機材、施設、人的資源、資金も有効に活用されている。
ブータン政府(農業省)も、必要な人材をリクルートし、プロジェクトのもつ技術の吸収に積極的である。使用された資材もローカルなものとインドからの輸入であることから、為替変動による資材調達の問題も深刻ではない。
ブータン政府のgood governanceとaccountabilityは特筆に値する。同時に厳しい環境の下に生業としての農業を営む過程で築き上げた村落レベルの自治組織の存在も、プロジェクト遂行と維持管理にとって重要であったと思われる。
5 ブータンへの我が国ODAの展望
(1) 地域開発の視点
急峻な山岳地帯にある小内陸国ブータンの開発努力を支えているのは、第2のシッキム化へのおそれである。労働不足国ブータンが自国の労働調達力を超える外国の大プロジェクトを受け入れないのは、それに伴って必然的に起こる大量のネパール人、インド人の流入をおそれているからに他ならない。第2のシッキム化を回避する最善の方法は、「良き統治」と「良き経済運営」によってGNHを達成することである。そしてこの目標を達成するために地域開発の視点は不可欠である。
従来の地域開発論に欠けていたのは、中央における「良き統治」の存在と、社会セクターの拡充を不可分とする開発の視点である。経済インフラは、地域開発の必要条件ではあっても十分条件ではない。この点、ブータン政府の地域開発の構想には、広義の社会的間接資本(経済および社会インフラ)のみならず、環境保全、伝統文化の保持という要素が組み込まれている。しかも、繰り返し指摘したように、中央政府のガバナンスは良好である。
ブータン政府の対ODA政策は、自国で管理出来る範囲で、各ドナーの比較優位をもつ分野を限定して協力を要請するというものである。自立のために必要な投資分野は明確に認識されており、水力発電による外貨収入が安定するまでの間、ICOR(限界資本係数)の高いプロジェクトは外国のグラントに依存するという立場をとっている。
地域開発の中で核の部分をなす社会的間接資本は、道路、通信、電力等の経済インフラと、教育、保健医療等の社会インフラ(セクター)である。その基盤の上に農業、製造業、サービス業の地域産業が発達する。このように考えると、日本のODAは、経済インフラの分野では通信網の建設、電力供給を支援し、社会インフラの分野では、教育、病院、BHU等への電力供給で貢献している。産業の分野では、パロ州に限定されてはいるものの、農道建設を含めた農業総合開発に関与してきた。これらの分野は、日本が比較優位をもっており、本報告書で検討したように、一定の成果を挙げている。しかし、そのインパクトはまだ「点」であり「面」への拡大はこれからのODA政策にかかっていると言える。
(2) 鍵を握る2つのセクター:水力発電と農業
ブータンの包蔵水力は2万メガワットと言われているが、その中の6000メガワットは現時点における開発の経済性を持つと言われている。
しかし、インドの援助によって建設されたチュッカ(Chukha)発電所の発電能力は、わずか368メガワットで、しかもその殆どをインドに輸出しているのである。そしてこれはブータンにとって貴重な外貨(ルピー)収入源であり、歳入である。(第22表)このことは2つのことを意味する。第1は、水力発電は将来にわたり外貨収入源として重要なセクターであるという点である。第2は、ブータンの作り出す電力は、インドの需要とその伸びを考えるとわずかなものでしかないという点である。事実インドは、第8次五ヵ年計画中に予定していた電力の供給増分は3万メガワットであったが、実際にはその半分程度しか作り出せなかった。このような状況から、インドはバングラデシュ、ネパール、パキスタンとの域内エネルギー貿易に積極的である。
ミクロ、ミニ発電は目下日本の独壇場であるし、すでに述べたように、この協力は地域開発の観点から望ましいものである。しかし同時に、よりマクロ的にみた大型発電プロジェクトにも参加しても良いと思われる。ブータンの電力開発は、その地理的条件から、環境、移住の問題が少ないということも好条件である。ただし、水力発電は輸出市場が確定していることから有償条件にする必要があろう。
水力発電と異なり、農業開発の重要性は、地域開発の観点から必要であるし、また変化に富んだ山岳地帯で、わずかな距離の中で豊かな高度差をもつことは、農業の開発が画一的であってはならず、location specificであるべきことを示唆している。事実、第23表に示されるように、ブータンの作付形態はすでに多様性を示している。
農業における日本の協力を考える場合、有利な点は2つである。1つは、末端の自治組織が発達している点である。今1つは、日本の稲作及び園芸作物の技術体系が応用できる点である。注意を要する点は、有畜農業における経験不足である。したがって、この点はインド、パキスタンの技術を援用するのがベストであろう。したがって、日本が協力できる地理的条件を明確にしておく必要があると思われる。
(3) その他
今後のブータンへのODAを考えるに当って、2点コメントを残しておきたい。
第1は、ブータン社会に関する情報不足である。パロのプロジェクトが、ハードの部分の貢献にもかかわらず、その維持・管理に問題を残しているのは、農村社会に関する情報不足に由来すると思われる。ODAの失敗の例は、ほぼ例外なく計画の中の社会・人文科学的分析の欠落に基づく単純なものである。ハードな構造物を動かすのはその社会の人間と組織であることをもうそろそろ理解しても良いのではなかろうか。その意味で、我が国のブータン社会に関する知識の集積は余りにも貧しい。ブータンも国際社会の一員である。その社会の正確な理解が協力関係の持続的発展にとって前提となる。本格的研究の場を設定することを提言しておきたい。
第2、上記と同じコンテクストではあるが、正確な情報を得、迅速かつ適格な判断を下すためには拠点が必要である。現在ブータンに大使館を置いているのはインドとバングラデシュであるが、日本も常駐の事務官を1人リエゾンとして置くことを考えても良い時期に来ていると判断される。JOCVにその役割を代行させることにも政府として限界があるはずである。

