4. 遺跡保護と砂漠化防止(インド)
(現地調査期間:1997年3月6日~3月15日)
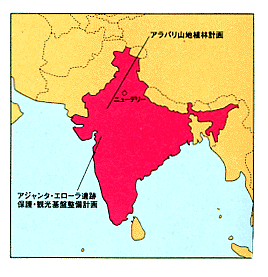
■早稲田大学政治経済学部教授 西川 潤
<評価対象プロジェクト>
| プロジェクト名 | 援助形態 | 協力年度、金額・年度 | 協力の内容 |
| アジャンタ・エローラ遺跡保護観光基盤整備計画 | 有償資金協力 |
1991年度 |
アジャンタ・エローラの石窟寺院遺跡を保護し、増大する観光需要に応えるため、円借款により、道路、空港、上下水道、電力などの観光基盤を整備する。 |
| アラバリ山地植林計画 | 有償資金協力 |
1991年度 80.95億円 |
アラバリ山地における砂漠化を防止し、その生態的状況を保護するため、円借款により、地域住民が参加して、11.5haの植林を行う。 |
1. はじめに
インドは東西冷戦体制終結の後、とくに1992年以降、急速に従来の国家統制主義体制を改め、自由化、開放体制化、市場経済化の方向を強めている。また、1996年5月の総選挙では国民会議派政権の長期政権に代わって、ジャナタ・ダル等13党の連立政権が発足した。このようなインドの政治経済の大きな転換期にあたって、日本の有償資金協力の現状がどうか、今後どのような方向で日本の経済協力はインドの経済社会の新しい進展方向に沿ってこれを支えていくことができるか、について考察することを目的とし、マハラシュートラ州における「アジャンタ・エローラ遺跡保護・観光基盤整備計画」、ラジャスターン州における「アラバリ山地植林事業」の2つの円借款案件を評価対象として取り上げた。
2.「アジャンタ・エローラ遺跡保護・観光基盤整備計画」
(1) 案件概要
アジャンタ-エローラ遺跡はマハラシュートラ州北部のマントラヤ県にある。マハラシュートラ州はインドの商工業センターであるボンベイ市を擁し、有力な先進州の一つだが、デカン高原入口のこの県は目立った産業もない後進地域である。本案件は、1980年代初めに、ヒンズー教徒とイスラム教徒の不和相克を乗り越えるべく、地域開発をはかろうとして設置されたヴェルール(エローラの別名)開発委員会の提案に始まる。同委員会は1981年に公表した報告で、1)多文化融合の象徴であるエローラ遺跡の保全、2)博物館・史料館の設置、デカン文明研究所等を核とする観光開発、3)地域開発計画の作成、を勧告した。
この委員会勧告は、マハラシュートラ州の開発計画で取り上げられ、アジャンタ-エローラ遺跡保護と観光・開発をセットとした観光開発計画が策定された。他方で、1980年代を通じ、インドへの観光客が年率18%の勢いで伸び、1950年代には年数万人だった外国人観光客数は1990年代には200万人を越えるようになり、観光インフラの欠如が痛感されるようになった。この他、国内観光客も年間1億人(有料観光客-この他に巡礼が1.5億人いると推定されている)に及んでいる。こうした事情から、交通運輸網や観光インフラ整備を軸とした「全国観光発展計画」が1992年に制定され、観光開発はインドの経済開発計画でも重点政策の一つとなった。
その後、1990年代に入り、とりわけインドの自由化、開放体制への移行と共に、国内外からの観光客は急増するようになっており、それはアジャンタ-エローラ地区でも例外ではない。
1995年のアジャンタ-エローラ地区観光客数は約50万人、オーランガバード空港到着外国人観光客数は約4万3,000人以上に上がる。マハラシュートラ州観光局の観光開発プランによれば、2010年には総観光客数は150万、内外国人観光客数は16万、2020年には各250万、35万としている。遺跡保護、インフラ整備の事業はまことに急務といえる。
本計画は37億4,500万円の借款供与によりまかなわれ、いくつかのコンポーネントから成っている。
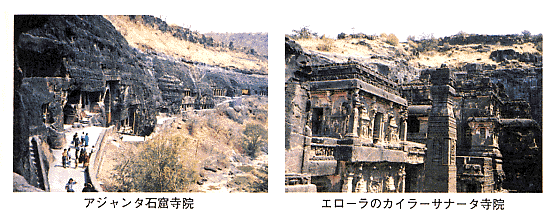
(2) 評価結果概要
まず全体的な進捗状況として目につく2点がある。
第1は、事業の全体について約2年の遅れがみられることである。本件は1991年度承認案件で、1992年1月に契約が締結され、1993年8月にパシフィック・コンサルタント社とタタ・コンサルタント社がコンサルティング企業として選定された。それから急遽「第1期」として事業が始まったので、実際の施工期間は1993年から1996年末となっている。この遅れは主としてインド側の準備体制の遅れに由来すると、現地で説明を受けた。ただ施工状況は概して予定どおり進んでおり、本年度中に完成すると見込まれる道路部分と「第2期」回しとされた観光センター関連設備を残して、後はほぼ予定通り96年末までに完了していた。
第2は、37億4,500万円の借款合意額に対し、1996年末までの貸付実行額が8億6,200万円と、かなり少ない。支出期限は1999年3月末で、1996~1997年の支出額がこれから請求されるにしても少ない。これは、1992~1995年の円高により、現地通貨利用額が大きくふえたためで、最終的には当初の借款契約で想定された現地通貨予算がほぼ支出されることになるだろう、とのことである。ただ、その場合でも日本側の円建て借款供与額はほぼ半分のみ使用される、ということになろう。
次に、事業の各コンポーネントの現状を説明する。
A 遺跡保護
この部分では遺跡保護のエンジニアリング・スタディ、保護地区の保護柵設置、見学路、階段等の補修が行われていた。
ただ、この点では2つの問題が注意される。
一つは、この事業(「第1期」)では、遺跡保護部分への支出が全体の1%で極端に少なく、この部分の支出も、当初計画で想定された電気自動車(アジャンタ遺跡から4キロ離れた地点に観光センターと駐車場を設け、そこから電気自動車で観光客を遺跡まで運ぶという案)は結局、維持管理の問題が解決されず、遺跡保護を担当する考古局(Archeological Sarvey of India)が自分たちの足としての自動車2台とファックス等若干のOA機器を購入した形に変わってしまったことである。
このことは第2の、より重要な、遺跡保護に関する基本コンセプトについて、インド側内部で2つの異なる考え方が存在する、という問題と関連している。
歴史遺産の保全に関しては今日、2つのアプローチが存在する。1つは、古典的といってもよい、長い年月の間に壊れてきたものを補修し、復旧する、というアプローチであり、修復(cure)アプローチといってよい。第2は、周囲の環境の変化により、歴史遺産の破壊進行が見越される場合に、これをいかに予防し、遺産の全体像を守っていくか、というアプローチであり、予防(prevention)または配慮(care)アプローチと呼ばれる。この2つのアプローチは本来矛盾するものではないのだが、インド考古局は大英博物館伝来の修復技術に長けていることもあり、修復アプローチ以外のアプローチについては認識度が薄いように見受けられる。このため、後者のアプローチにより遺跡保護に接近しようとする観光省との間で未だ最適な遺跡保護手段についての合意が必ずしも形成されていない。これが考古局側からの予算要求がほとんど提出されていない大きな原因になっている。
本事業が第2期に移るとすれば、必要な遺跡保護アプローチについて、インド側関係者の合意が形成されることが最低の条件となろう。さもなくば、観光基盤の空港、道路、ホテル等はどんどん整備されて、観光客が流入しても、遺跡(とくにアプローチの限られたアジャンタ)ではシャットアウトされるという、最悪の事態になりかねない。
最近、考古局は、とくに温度や湿気の変化に弱い貴重な壁画部分を残すアジャンタ遺跡については、いくつかの石窟で1回の入場者数を20人程度に制限する政策をとっている。アジャンタ石窟28(内4は空)、エローラ石窟34で、1日入場可能な人数は前者4,000~5,000人、後者6,000~8,000人と推定されるが、昨96年の観光シーズン(10~1月)には1日1万5,000人を越える日が何日かあった、と報告されている。観光省の予想するように、観光客数が今後ふえ続けるとすると、とくにアジャンタは考古局の責任者の何人かが述べているように、間もなく閉鎖されるという問題も出てこよう。考古局は既に、観光省のすすめている周辺緑化計画(アジャンタ地区に植林して、公園としての雰囲気を作る計画だが、緑化すると昆虫がふえ、壁画を傷めるとして、考古局は批判的である)や遺跡照明計画には批判的な立場を表明している。
この問題は現在、アジャンタ-エローラ遺跡保護に関する報告書を考古局・観光省が共同で作成しており、これを1997年5月に国際パネル(ユネスコ等の国際諮問委員10名からなる)で討議されることになっているので、この国際パネルでの検討結果を見て、第2期事業を検討することが望ましいと考える。
B 周辺自然環境改善(植林)
森林局の手により、アジャンタ地区周辺500ヘクタール、エローラ地区237ヘクタールに植林し、自然公園化する事業で、第1期の早い時期に完了し、現在、第3~5年目の灌水、管理を行っている。植林箇所はフェンスで囲われ、動物などの侵入を防いでいる。ただし、この事業については前述のように考古局の側からの批判があるので、第2期に植林を継続するとすると、ニーム等防虫作用をもつ植樹をふやすなどの対応処置を研究する要があろう。
C 空港施設改良・整備(オーランガバード空港)
これは1)滑走路の延長、2)安全性確保のための計器着陸システムの導入、の2項目から成る。後者は現在の手動発着誘導を自動計器を導入して悪天候寺・夜間発着可能なように改良した。前者は現在の滑走路6,000フィートを7,000フィートに延長し、現在1日1~2便の発着を常時2便発着可能なように改良した。この延長により、現在のボーイング737に加え、エアバス310の発着まで可能になるとのことである。この事業はインド航空局(AAI)が担当し、ほぼ完了している。
D 道路改良・整備
これはオーランガバードとアジャンタ・エローラ両遺跡を結ぶ州道の拡幅・改修、また遺跡サイト内道路の拡幅・改修の両項目から成り、後者は完了している。前者のアジャンタ道路は7割方完了しており、州公共事業局担当者によれば、本年9月までには完了するとのことである。エローラ道路は5~6月に完了する予定で、プーランバリまでの延長道路のみ9月までかかるとの報告を受けた。前年もここを訪れた同行者によると、全体の道路状況は昨年よりも明らかに改善され、以前はアジャンタまで100キロを4時間程度かかったというが、今回は約2時間で到達した。道路予算の支出推計ではほぼ予定通り、債務額4億ルピーに対し、5億1,827万ルピーの総支出(原則として各項目に対し、82%分を借款、18%を現地通貨で賄う)を見込んでいる。
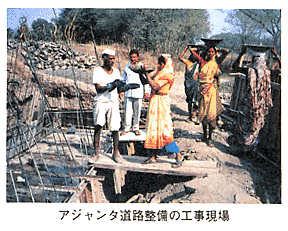
E 上下水道改良整備
上下水道については、アジャンタ地域は当初のヴァグール川より取水する計画がうまくいかず、結局7キロ離れたトンダプールダムの堰を2メートル上げ、取水能力を拡大したが、パイプライン工事が残っている。 エローラ地域については既存のギリジャ川ダムから引くことに決まった。だが、両方とも、水供給先の観光センターの建設が第2期送りとなったため、最後の部分は未完成である。
F 電力設備整備
アジャンタ、エローラ両地域で既存の変電所に新しい5万キロワット/アワーの変電設備をつけ加え、観光センターに電力を供給するもので州電力局が担当している。変電所設備の能力向上は完了したが、送電工事は観光センター未着手のためペンディングである。
(3)教訓と提言
このアジャンタ・エローラ遺跡保護・観光基盤整備事業は、以上見たように、工事スタートの遅れによって、全体に1年程度の遅れを伴っているが、概してみると、道路、空港、ダム、電力等、既存の設備の改良、拡充の仕事から成っており、新しいものが突如としてもち込まれているわけではない。その意味では着実な観光・社会インフラ整備の事業として評価できる。
ただし、遺跡保護と観光の調和に関してはインド側に異なる考え方が存在し、必ずしもまとまっているわけではない。従って、遺跡保護のあり方についてはもう少しつめた合意が必要であるし、それゆえに観光センターと電気自動車による運送システムが第2期に回されたことは、むしろ事業全体の進展にとってはのぞましいこととこれを見ることができよう。
第2期として、インド側では第1期の支出額を約3倍とする発展計画を考えている(表3-2)。これはマントラヤ県にあるもう一つの石窟群ピタルコーラ(Pitalkhora Caves)とアジャンタ、エローラ地区を結ぶ観光回路をつくるというまので、その内容は次の4つの回路から成る。
a エローラ回路 オーランガバードからダウラタバード城塞、エローラ石窟を結ぶ。この地域にはスリバンジャン山でのピクニックやトレッキングができ、野生生物保護区も存在する。
b アジャンタ回路 アジャンタ展望点と石窟群から成る。近隣の森林、河川地域でのトレッキング、ピクニックの可能性あり。
c ピタルコーラ=ガウタラ回路。これは、アジャンタとエローラ北方のピタルコーラ石窟とを結ぶもので、ヒンズー教の聖地パトナ・デヴィ寺院もこの回路にある。この回路は野生生物保護区のガウタラ森林近辺を通ることになり、現在は未舗装の林道が存在する。
d オーランガバード回路 オーランガバード石窟群、州立博物館(スナヘリ・マハール)、ドウニヤネスコワール公園、パイタン聖地等から成る。
この4つの回路を結びつけた-大観光回路を形成しようとするもので、そのために現在の空港、道路、水、電力等のフアシリテイを一段と拡充しようとする。ここでは遺跡保護の部分も第1期の747万ルピーから2億5,721万ルピーへと大幅にふやすことが考えられている。
実際、このような観光回路が形成されればこの地域にただでさえふえている観光客及び巡礼の数が一段と増大し、地域発展が進むことは疑いを容れない。だだし、それにはいくつかの条件が必要となる。
第1は、アジャンタ、エローラ、ピタルコーラ3遺跡の保護方法について、インド側の開発当事者の間で意見の一致がみられることである。そのためには本年中に準備されている専門家会議で、十分な検討が行われることが望ましい。
第2は、特にアジャンタ=ピタルコーラ回路については、野生生物保護区の近辺を通ることもあり、やはり十分な環境アセスメントが必要となろう。
第3は、この地域は歴史遺跡とヒンズー教・イスラム教聖地とが混在しているために、観光客フローの増大が聖地の保全と両立する必要があり、これには遺跡保護とはまた異なった社会的文化的配慮が必要になる。
これらの点を考慮すると、当初のヴェルール地区住民委員会の提案にあるようなデカン文明研究所、博物館の設立を無償協力でサポートし、開発教育を開発事業と並行してすすめることもまた一つの具体的な選択肢として考えることができよう。
また同時に、現在は借款供与が必ずしも技術協力と結び付いていないが、技術協力の要因を加え、インド考古局の専門家に日本やカンボジア・アンコールワット遺跡での遺跡保護状況を視察してもらったり、日本側の専門家との交流をすすめてもらうことも、遺跡保護に関する考え方のオプションを広げるという点で、効果的とも考えられる。
3. 「アラバリ山地植林計画」
(1) 案件概要
ラジャスタン州は面積の3分の2が砂漠あるいは不毛の荒地で「砂漠の州」とも呼ばれる。西方のタール砂漠とインド亜大陸はアラバリ山地で隔てられているが、現在、タール砂漠はアラバリ山地を越えて、東方に拡大してきている。また、インドの現在年1.8%の人口増加率からして、薪木・木材需要はかなり強いと見られ、それが森林のかい廃、砂漠化の進行につながっている。ラジャスタン州の主要産業の一つである牧畜業もまた、森林カバー率を減少させる一因となっている。実際、ラジャスタン州の森林カバー率は全国平均の半分以下の9%にすぎない。それだけに「全国森林政策」の主要目標の一つとなっているように、ラジャスタン州での植林事業はインド全体にとってきわめて重要といえる。
本事業は、住民参加による造林により、砂漠化を防止すると共に、造林地域で薪材、飼料、草、木材、果実及び森林副産物を生産し、地域の生活必要物質を調達し、地域振興に役立てることを目的としている。
そのために、約11万5,000ヘクタールの地域に植林を行う。植林のために苗畑10カ所を建設し、苗木7,500万本を住民に領布する。この総費用を約81億円の借款によりまかなうものである。また、この計画の策定に当たっては住民参加による社会林業委員会を村落レベルで形成し、住民の要望を反映させた事業計画(マイクロ・プランニング)を策定し、住民自身の手によってこれを実施する方法を用いている。
この地域では、首都ジャイプール市から24キロ離れたバンプール・カラン村(人口約1,000人、植林面積15ヘクタール)及び隣接したバスナ村(人口3,000人、植林面積25ヘクタール)を訪ねた。これらの訪問及び収集した森林局関係の文献をベースに評価を試みたい。
(2)評価結果概要
この計画はもともと1992~1996年の5年間にアラバリ山地に11万ヘクタールの植林を行うもので、そのため81億円の借款が合意された。プロジェクト実施の過程で、1999年3月まで、2年3ヶ月延長された。また、貸付実行額は1996年末で43億7,800万円で、借款合意額の約54%にとどまっている。
ラジャスタン州森林局で説明を受けたところでは、1997年3月末までに目標苗木分配7,230万本と目標植林面積11万5,000ヘクタールはほぼ達成する見込みである(表3-4)。現在までの貸付実行額(実際のルピー貨支出額の払い戻し分)が合意額よりずっと少ないのはこの間の円高によるものという。この点では円高によりルピー利用額は大幅にふえたにもかかわらず、当初の目標を着実に実行してきているわけで、好感がもてた。
植林の活着率が高いことも、本事業の特色といえる。森林局によれば、10対象地域中7地域の148箇所で活着率の調査を行ったが、80%以上の活着51%、60~80%の活着43%というのはきわめて高い数字といえる。これは現場を見て判ったのだが、雨期を通じての植林、植えた木の周囲に溝や導水路を掘り、自然灌水する努力、さらに住民参加による日常のケア等があいまって始めて達成されたものである。
本植林計画が住民参加型の社会林業と組み合わされていることは重要な意味をもつ。
村レベルで原則的にパンチャヤットを基盤として、全員参加型の森林委員会が約7,000設立されており、植林計画、樹種、管理・保全方法、利用計画、マーケテイング等を自分たちで決め、評価作業にも加わっている。森林委員会に通常15人程度のメンバーが運営し、最低2人は女性のメンバーがいるとのことである。
森林局は植林事業での日当支払い、苗木供与(10本1ルピー)、技術指導等を受け持っている。
住民参加型社会林業は1980年代後半から、世界銀行の指導によってインドで行われるようになったが、実施の過程でインド独自の要因も加わってきた。
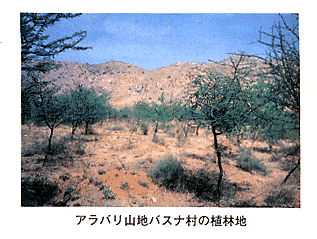
今回の訪問地域は低所得の小農地域で、雇用、燃料、家畜飼料、が住民の基本的ニーズだといえる。かつて森林局は近辺で植林を試みたが、うまく行かなかった。そこから住民を含めた社会林業を単なる砂漠化防止にとどまらず、地方住民の生計維持・向上、水・土壌保全、生物多様性、等多角的な目的と結びつけて、社会林業が始められた。
ここでインドの地方条件に沿って発達した社会林業の特徴は次のようなものである。
第1に、大規模植林にしばしば見られる単一樹種による生態系の変化を避け、多様な住民のニーズに沿った在来樹種の植林により、土壌の収奪を防ぎ、より自然に近い生態系を再現する可能性がある。世銀主導時代には例えば早く生育するアカシア類が主として植えられたが、現在はアカシア類の他に、チーク、ユーカリ、ポプラ、ニーム等の木材や薪木用の樹種、また木苺のような果樹やナッツ類、すすきに似たムンジャ草と呼ばれる屋根ふきやロープ、クッション、家畜飼料として広範に利用される草、その他の潅木や薬草、雑草等がひろく植えられ、伝統的な知恵を生かして樹種が著しく多様化している点が、世銀時代の社会植林と大きく異なる点である。
第2に、従って住民が自分の植林領域に大きな関心を持ち、絶えず見守ったり監視するために、家畜の食害も少なく、干害を未然に防ぐこともでき、それが活着率の高さ、植林の持続可能性につながっていることである。この地方では家畜数が人口の2倍に上るために、せっかく生えた緑も家畜に食べられ姿を消すことが多かった。住民参加はこの深刻な悪循環に解答をもたらしたといえる。
第3に、植林事業が住民の生業と結び付いており、自然発生的な灌木、雑草もむだにされず、ムンジャ草は計画的に増やされて、家畜飼料や日常生活での利用に購買、出荷されている。果樹やナッツは商業利用には未だ早いが、これらが商業利用のペースに入っていくと、さらに住民の生計向上、地域起こし的性格が強まってくることになろう。実際、住民たちは木や草の利用について、これは家具、これはロープ、これは胃や皮膚病の薬、あるいは血をきれいにする、あるいは石鹸に役立つなど明確な知識を持ち、緑の生育に期待をもっていることが看取された。
第4に、これら植林地域は村レベルでのマイクロ・プラン作成という形で村人たちの日常生活と結び付くことによって、一方では住民の結束力を社会・環境教育によって強める面をもつ。こうした住民参加が識字運動と結び付いているケースもあると聞いた。また、他方では代替エネルギー源を多様化する役割をもち、砂漠化のコントロールに役立っている。実際、参観した地域では、不毛の荒地地帯が植林後3~5年でかなり緑が濃くなっていることは印象的であった。
第5に、これら植林事業が現金収入の機会の極度に少ない指定カーストや指定部族、女性をかなりの程度巻き込んでいることも、社会統合にとっては大きなプラスになっていると考えるべきであろう。
この事業の成功にはラジャスタン州森林局の首席保護官D.P.ゴビル氏始めスタッフの並々ならぬ熱意と努力と創意があったことを特筆しておきたい。森林局の側の柔軟な社会林業の理解と地域生態系保全・地域経済振興への熱意がなければ、この大規模な植林事業の成功は決して確かなものとはなりえなかったのではないか。
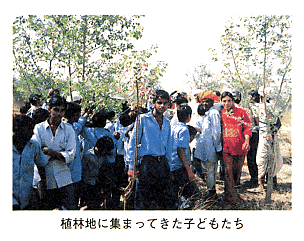
植林事業は決して直接に利益を上げる事業ではないし、それだけに借款形態の協力事業としてもっともなじみがいいかどうか、については一考の余地があろう。だが同時に、これが贈与形態の協力事業であれば、これだけ大規模の植林事業が住民を巻き込んで展開されたかどうかは疑問である。この柔軟性に借款事業のメリットの一つを、評価者自身は見出したい。
借款は中央政府の保証により、地方政府がルピー貨で資金調達する。為替リスクは中央政府が負う。この資金を原資として事業が展開される。地方政府は事業支出の領収書をOECFに送付する。OECFがこれをチェックして、対応する円貨を支払う。従って、事業の進渉に応じて借款が供与されていく仕組みである。円貨返済は経済全体の発展につれて、州・中央政府が行っていく。
こうして必ずしも営利事業ではない植林事業が借款によって融資されており、それを現地側が活用している根拠が理解できた。
(3)教訓と提言
植林事業はインドのように急速に森林面積が減少し、21世紀に向けて国土の3分の1を緑化しようと企てている国にとっては、きわめて重要な「持続可能な発展」をめざす開発事業の一つだといってよい。とりわけ、ラジャスタン州はタール砂漠の東進の最前線にあり、ここでの植林事業の成否はインド亜大陸の環境・生態系保全の要の事業だといってもよい。このラジャスタン州で1990年代に入り、森林面積増加の兆候が現れてきたことはまことに心強い次第である。
また、ラジャスタン州は、隣接するグジャラート州(世銀の社会林業プロジェクトがある)、ウタルプラデシュ州等と並んで、社会林業にきわめて熱心で、独自のインド型といってもよい社会林業を発展させつつある。この成果にはこの州の森林局指導部の熱意と努力があずかって大きい。
現在ラジャスタン州森林局は、アラバリ山地植林事業の成功を踏まえて、より包括的な植林・緑化計画を準備していると聞く。同じラジャスタン州西端で行われているインディラ・ガンジー運河地域植林事業やその他の州で行われている植林支援事業と共に、具体的な成果を戦略的地点で挙げている植林事業として前向きに対応していくことを期待したい。だが同時に、代替エネルギーの研究開発(たとえば簡易火葬施設、太陽熱を用いたソーラークッカー及びケロシン利用の機器、家畜糞尿を用いたガス施設等)についてはさらに技術協力のコンポーネントを入れ、有償・無償・技術協力を総合したモデル事業を組み立てていく可能性も検討に値しよう。
4. 結語-対インド経済協力の新しい方向
インドは1990年代に入り、急速に巨大な変化を経験し始め、21世紀の世界及びアジアの指導的大国となる準備をすすめている。経済の自由化、市場経済化、開放体制の方向はますます進展していくものと考えられる。
2国間ODAでインドにとって第1位を占める日本の経済協力は、今後もインドの経済社会変化、現代化の重要なパートナーとしての役割を期待されることになろう。また、日本にとっても中国と並んでアジアでの大きな変化の動因の一つであるインドとの協力は、とりわけインドが南アジア、東南アジアとの経済的連携を強めている現在、ますます重要となっているといえる。
しかし、第8,9次開発計画以降のインド発展の新しい方向に沿い、日本の経済協力においても新しい条件が出てきている。
その第1は、これまでの円借款主体の協力に代わり、しだいに無償資金協力、技術協力の比率をふやし、とりわけ有償資金協力との有機的連携を考える必要がある、ということである。ソフト・ローンの提供はインド側にとっては非常に使いよい資金であるため、円借款が多用される傾向にあるが、ODA大綱に即した日本側の考え方をも経済協力に反映させていく必要、政府・民間部門との連携、生産性向上の必要性等を考えると、技術協力をも重視していくことが望ましいといえる。
第2は、インド側の社会セクター及び民活インフラ重視の方向に沿い、ODAに関わるパートナーを民間部門に拡大していくことが考えられる。既に民活インフラ部門ではツーステップローンや民間企業への投融資などがはかられているが、今後はこれらの部門の強化と共に、特に社会セクター案件については、プログラム作成段階からのNGOなど社会諸セクターの参加を考えていってよいだろう。そのため、インド開発フォーラムの際に日印・国際NGOを含めたシンポジウムを開催することを勧告したい。
この評価で対象とした2案件については、いずれも第1期がほぼ終了し、第2期事業が立案されている段階である。第1期事業の達成状況からいえば、いずれも第2期協力の可能性はかなりの程度あるといえるものの、いずれの場合にも円借款とリンクして無償資金協力、技術協力を考えていく余地がかなりの程度あり、それが借款事業の効率を更に高め得ることが考えられる。また同時に、今日ユネスコ等の場でも遺跡保全については住民参加の要素が強調されていること、環境保全についても住民参加が効果的であることが3.2事業においても立証され、またそれがインドでも広く認知されてきていることを考慮すると、NGO、住民団体等の参加の要素もさらに強めていく可能性があろう。
ここで対象とした2事業はいずれも、インドの経済社会の新しい進展方向に即した重要な案件であると認められ、 以上の諸点を考慮してさらにフィージビリティを諸アクターの参加により練り上げた第2期事業が構想され、展開されていくことを期待したい。

