3. 都市の居住環境(フィリピン)
(現地調査期間:1997年2月9日~15日)
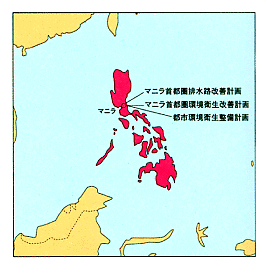
■東京大学助教授(大学院経済学研究科・経済学部) 中西 徹
<評価対象プロジェクト>
| プロジェクト名 | 援助形態 | 協力年度、金額・年度 | 協力の内容 |
| マニラ首都圏排水路改善計画 | 無償資金協力 |
1989年度、 12.31億円 |
マニラ及びその近郊は、排水路の維持管理に必要な機材が極端に不足していることから、既設排水路の多くは堆積した土砂及び塵芥等により殆ど閉塞した状況にある。中小河川(排水路幹線)、大型暗渠(排水本管)及び排水支管の堆積物除去を5ヶ年の作業実施期間で完了するために必要な機材を供与した。 |
|
マニラ首都圏環境衛生改善計画 都市環境衛生整備計画 |
無償資金協力 無償資金協力 |
1986年度、 8.50億円 1989年度、 10.72億円 1991年度、 11.36億円 1992年度、 11.30億円 |
フィリピン政府は近年首都圏人口の増加に伴って増大するゴミを処理する収集車両の増車が困難なことから、ゴミが大量に発生しているため、モデル的ゴミ収集計画を策定し、実施に必要なゴミ収集車の供与を要請した。我が国政府はこれら収集車の供与を実施した。 |
はじめに
本稿は、1997年2月10日から15日にかけて実施された「マニラ首都圏環境衛生改善計画」と「マニラ首都圏排水路改善計画」を対象とする有識者調査の最終報告である。
筆者は、開発経済を専門としており、固形廃棄物処理事業や排水路事業に関する専門技術知識を有していない。やむを得ない事情から評価も6日間という短期間で行われたという制約がある。自ずと筆者の評価の視点は、社会経済的効果の定性分析という限られた側面から行わざるを得ない。以下、この報告における事業評価に固有な2つの視点を論じた後、2つの事業のそれぞれについて議論したい。
1.事業評価の視点
本稿では、マニラ首都圏のおかれている社会経済条件を前提として、微視的評価と巨視的評価という2つの視角から議論を展開したい。微視的評価というのは狭義のプロジェクト評価そのものであるが、ここでは事業の科学技術的な評価や費用便益分析を指すのではない。むしろ、事業の持続的展開・発展のための受入地域の社会的努力に焦点を当てたい。他方、ここでいう巨視的評価とは、ある意味では、プロジェクト事業のパフォーマンス自体の評価とは別のものである。むしろ、その事業が他の社会問題に与える重要と思われる副次的影響を考えるという視点である。
(1) 微視的評価:コミュニティ資源の育成と活用
微視的評価の最も重要な論点は、当然のことながら、事業自体のパフォーマンスである。結論から述べれば、今回の調査では、両事業のパフォーマンスは極めて高く、とくに問題点は見いだせないように思われた。しかし、援助事業を効果的に受入国社会に浸透させ、受入国の自助努力を導き所期の目的を達成するためには、受入国側の援助の活用という観点からの評価が不可欠であろう。
本報告では、その評価の基準をフィリピンにおけるコミュニティ資源の活用という観点から考えてみたい。1991年に施行された地方自治法は地方自治体が有する権限を強化することになった。それは地域特定的なプロジェクト援助に影響を及ぼさざるを得ない。広域行政よりもヨリ地域社会に関する情報を有するはずの地域の自治体行政がどのようにして事業を活用するかという問題は、BOTの視点からも極めて重要な論点である。
しかし、他方において、フィリピンでは、その際、もっとも効果的に作用するはずのコミュニティ資源に乏しいという指摘がしばしばなされている。ここでの評価の視角は、各自治体は希少なコミュニティ資源をどのように育成し発展させ、事業の発展に活用するかという点にある。
(2) 巨視的評価:貧困と環境
ここで取り上げた2つのプロジェクトは、ゴミと既存排水路汚染にかかわる問題を対象としたものであり、いずれもマニラ首都圏の一極集中から派生した都市環境劣化に対する対策の意味をもつ。ここでは、環境劣化の問題によって直接大きな影響を及ぶのが貧困層である点に着目した。
第1に、貧困層にとって環境劣化への対応するためのコストは、富裕層のそれとの比較で著しく重い。例えばマニラにおいて富裕層の居住地の選択にあたっての大きな判断基準は交通渋滞と洪水の頻度といわれている。富裕層は、貧困層とは異なり、他の支出との比較において費用負担が軽く、環境劣化による損害を事前に回避することが可能なのである。
しかし、第2に、貧困層の社会経済活動が都市環境を悪化させているために、環境改善策がしばしば所得分配上、逆進的効果をもちうるということにも注目すべきであろう。たとえば固形廃棄物処理場の衛生埋立化は最貧困層である廃品回収人の職場を奪うことになる。あるいは、排水路汚染の一因を周辺に居住する貧困層が投棄する廃棄物に求めるとすれば、抜本的解決のためには貧困層の立退きを考えざるを得ない。それは、単に都市貧困層ばかりでなく、農村貧困層にまで影響を及ぼすことになるであろう。発展途上国の環境問題は、必然的に、これらの国にとって最大の社会経済問題の一つである貧困や所得分配の問題とリンクしている。
政府開発援助の性格上、環境とともに貧困層への配慮が重要であることは論をまたない。本報告では、巨視的視野からの評価については、貧困と環境のトレード・オフ関係をその視点としたい。
2.「マニラ首都圏排水路改善計画」
(1) 事業概要
1950年代の洪水対策基本計画の策定以来、1970年代の円借款供与の寄与もあり、マニラでは都市を中心に洪水対策施設が建設されてきた。しかし、その後、首都圏人口の持続的な増加にともなって既設排水路への固形廃棄物投棄が急増するに及び、現在に至るまで雨期になると各地で深刻な洪水被害が発生している。洪水はマニラ首都圏の交通渋滞の大きな原因になるばかりでなく、しばしば低所得者層の子どもを中心に疫病を流行させる。こうした経緯から1987~1992年の中期開発計画以来、社会資本の充実の一貫として、洪水対策が強調されてきた。
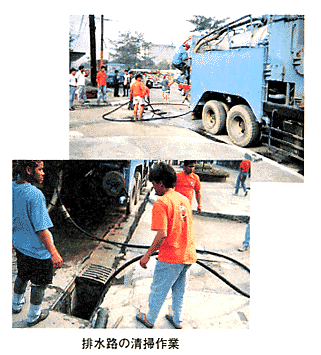
洪水の主たる原因は、既設排水路の維持管理に不可欠な機材が極端に不足しているにもかかわらず廃棄物投棄による塵芥や土砂堆積が促進され、排水路の雨水排水機能が実現できていないことに求められる。それは、中小河川(エステロ)のみならず、大型暗渠(ドレイネイジメイン・アウトフォール)、排水枝管(ラレラル)までに及び、排水路の総合的浚渫事業が必要となったのである。この事業は、機材供与を通じて、エステロからラテラルまでの排水路の機能を回復させ、マニラ首都圏における洪水問題を解決することを目的としている。さらに、モデル施工の実施によって、機械操作及び保守・管理に関する技術移転を実現することも重要な目的である。
(2) 微視的観点に基づく評価
このプロジェクトは、「マニラ首都圏環境衛生改善計画」と同様に、パーフォーマンス上は、日本からの派遣専門家とDPWHとの間の円滑な人間関係に立脚した効率的かつ効果的な極めて優良な事業であると評価することができるであろう。今回の評価調査では、やむを得ぬ事情から事前の現地側準備期間も実際の調査期間も極めて短期であったにもかかわらず、エステロからラテラルまで、浚渫作業について効率的かつ十分な視察と説明を受けることが可能であったことが、このことを雄弁に物語っている。
この事業は、洪水多発地域を特定化したうえで[図参照]、これらの地域を重点的にカバーしている。政府開発援助事業ではサイト決定に疑問が残ることがあるが、この事業では極めて明快な判断基準に基づいて実施されてきたといえよう。
こうした排水路の機能改善が直接的に効果を挙げていることは、事業実施主体のDPWHだけでなく、排水路周辺に居住する低所得者層のタガログ語による直接の聞き取りからも確認することができた。筆者は、マニラ市のサンタ・アナ地区とパンダカン地区のパシッグ川エステロ付近の貧困層居住地区の複数の住民から、このプロジェクトに関する無作為のインタビュを実施した。これによれば、パンダカン地区では、1994年頃までに周辺における洪水は極端に減少し、1995年以降は生じなくなったというし、サンタ・アナ地区の低所得者層に対するインタビュでも1990年代になって洪水は極端に減少したとの報告があった。また、洪水頻度の減少によって幼児の罹病率の抑制が実現されたという評価もそれぞれの地区の複数人の被調査者から寄せられた。
さらに、この事業は、「マニラ首都圏環境衛生改善計画」によるゴミ回収事業の展開や周辺住民への環境意識の改善と有機的に結合し、相乗的効果を挙げている点に注目すべきであろう。筆者が訪れたマニラ市のパンダカン地区では、周辺住民がDPWHに雇用され不法投棄に対する監視を行い、違反者に対して2,000ペソの罰金(最低賃金率換算で月収の約3分の1強)という実現可能な罰則を規定するとともに、1990年代になって、廃品回収人によるゴミ回収は朝5時、市のゴミ回収は朝6時と昼12時に行われるようになり、住民による河川への廃棄物投棄が減少したという。この制度において、定期的に定時のゴミ回収が行われるようになったことに着目すべきであろう。環境保全に直接的に寄与するばかりでなく、貧困層である廃品回収人に回収時間の情報を与え、所得を補償したという分配上の配慮がみられる点は積極的な評価が与えられるべきである。
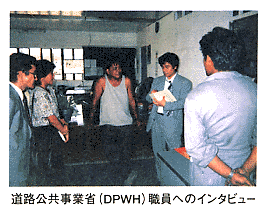
このプロジェクトが以上のような良好なパーフォーマンスを示し、環境改善に大きな効果を挙げているのは、もちろん援助に関わってきた専門家、現地主体の努力によるところが大きいが、事業主体が地域社会のインセンティブ機構を巧みに利用してきたことを軽視すべきではない。すなわち、道路公共事業省(DPWH)は、排水路汚染の事後対策のみならず、バンタイ・エステロ(bantay estero)と呼ばれている監視者を周辺地域から雇用し、コンテストを導入して地域間に競争原理を持ち込み、広報活動を併用して排水路汚染の予防に力を注いできた。それは前述の周辺住民へのインタビュによっても確認できた。
このような積極的な評価の中で、敢えて難点を挙げるとすれば、重機器故障時の部品調達の問題がある。確かに、機材の維持管理に、フォローアップの専門家の方と現地のスタッフは多大な努力を払っていることが確認できたが、現地調達に難がある部品が少なくない点は仕方がないこととはいえ、今後、同種のプロジェクトの実施にあたり、配慮して行くべき点ではないだろうか。とくに半導体を利用した計器類が故障した場合には、現地調達は不可能となり、他の部分は新品同様であるにもかかわらず、活用されていない重機があったことが印象的であった。この点については、筆者の専門外であるので、今後より詳細な事後評価の実施と今後ともなお一層のフォローアップが必要になるであろう。
(3) 環境と貧困
このプロジェクトだけについて考察するのであれば、冒頭に述べたような環境と貧困の間のトレード・オフ関係は存在しないように思われる。しかし、プロジェクトと直接の関係はなくとも、エステロ視察の際に偶然に出くわした現在のマニラ首都圏における河川周辺のスラム撤去事業の展開を勘案するとき、河川汚染と貧困の関係について触れておくことは重要であろう。このプロジェクトが積極的な教訓を導いているように思われるからである。
まず、確認すべき点は、このプロジェクトの運用にあたって、周辺不法占拠者による不法投棄による排水路汚染が過度に強調され、それが短絡的にパシグ川流域の不法占拠者居住地区の強制退去に結び付けられてはならないということである。スラム問題は依然としてマニラ首都圏において重要な社会経済問題であるが、それはあくまでも貧困緩和の観点から喫緊であると考えられる。農村地域開発までも視野に入れ、より広い視野から段階的な解決を図るべきものであって、まずはじめに都市環境保全のためのスラムの強制移転ありきという政策が様々な問題を生起させ逆に貧困の深化をもたらしてきたことは1960年代以来、フィリピンでは周知のところである。
スラムがもたらす深刻な外部不経済を河川汚染と把えるのであれば、まず考えなければならないのは直接河川汚染に焦点を当てた政策であって、スラムの除去ではない。この意味でも、このプロジェクトは重要な示唆を残している。つまり、実現可能な罰則規定を設ける一方で、監視者を地域住民から募り、コンテストを通じて地域に自助努力の誘因を与えるという方法である。この試みが、今後、多くの貧困層居住地域において活動を行っているNGOとの連携を視野に実施されれば、より既存の社会状況と適合的な実現性の高い環境保全が可能になるように思われる。
3.「マニラ首都圏環境衛生改善計画」
(1) 事業概要
「マニラ首都圏環境衛生改善計画」は1987年に交換公文の署名が行われた無償資金援助である。それは、増大する廃棄物問題の緩和によって都市開発における環境衛生事情の改善に寄与することを主たる内容とする事業であり、フィリピンにおいて増車が困難であったゴミ収集車の供与を内容とするものである。1987、1990、1992、1994年の4次にわたり、ゴミ収集車両(8立方メートルと5立方メートルのコンパクタ・トラックおよびダンプ・トラック(227両、処分場用重機類(ブルトーザ、ペイローダ、ランドフィル・トラッシュコンパクタ)12両が供与された。うち、現存する収集車両は127両である。
この事業の意義は、単にマニラ首都圏内の地方自治体が実施しているゴミ収集事業において不足している機材の供与によって、事業の効率化とゴミの回収率を改善することにとどまらない。路上、河川への不法投棄が無視できない規模でみられる現状において市民への啓蒙的意味を持つと同時に、最終処分過程において発生する環境問題の解決のためゴミ圧縮処理と衛生埋立事業を推進する意義を有している。
(2) 微視的観点に基づく評価
結論を先に述べれば、このプロジェクトもまた、各自治体(町と市)の自助努力によって、供与機材が円滑かつ効果的に活用され、極めて良好なパーフォーマンスを実現している。フェーズI(1991年)とフェーズII(1993年)で約6割の稼働率、フェーズIIIで8割の稼働率は十分に評価できるように思われる。じっさい、筆者は、マリキナ町の回収作業に同行し、ゴミ回収車は定期的にバランガイまで行き、ゴミを回収し、マリキナが保有する中継地点で大型回収車にゴミが移し替えされ、サン・マテオの衛生埋立て最終処分場まで円滑に運搬されていることを確認した。すなわち、密閉式圧縮型ゴミ収集によってゴミの拡散を防ぎ、大量のゴミ回収が可能になったばかりでなく、計画的なゴミ収集が可能になり、業務の定型化が実現できたのである。また、マリキナの場合は、中継地点を有するために多大な費用節約が可能となっている。
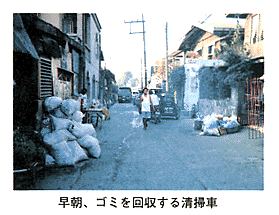
さらに、日中にも回収作業が行われることがあるため、交通事故が多く、収集車の管理・維持は重要な役割を負っている。2箇所のゴミ収集車センターで、他の援助においてしばしば問題点として指摘されがちな機材の管理維持・保守の面においても十分な配慮がなされていることを確認することができた。とくに稼働が不可能になった車両の部品が経常的なメインテナンスに弾力的に利用されている点は評価できるであろう。
ただし、上の回収事業における評価は、実際に訪れることができた、ゴミ回収にあって優良な自治体であるマリキナ町のみであるという批判を受けるかもしれない。確かに、1992年の地方自治体法施行以来、ゴミ回収事業はマニラ首都圏から各市町に権限が委譲され、各地方自治体によってパーフォーマンスのばらつきがみられることは否定しがたい。しかし、マニラ首都圏内で一種の美化コンテストがあり、各自治体の自助努力を引き出すインセンティブとして利用されている。それは、かつてはメトロ・エイドと呼ばれていた主として低所得者層出身の路上清掃人を活用することによって、バランガイ・レベルまで浸透していくことが期待される。
しかし、全く問題がないわけではない。自治体によっては、予算執行の遅れから部品調達に困難を抱えている。さらに、回収事業全体にわたって給与水準が低く、危険性が高いために、職員の定着率が低いという指摘は依然としてなされていた。とくに、末端の作業員の安全性の確保と万一の際の補償は今後とも一層のケアが要求される項目であろう。
(3) 貧困と環境
一般に、このような事業の展開は、ゴミ問題を解決する一方で、廃品回収人を圧迫し、所得分配上逆進的効果がもたらされる懸念がある。たしかに、このプロジェクトとは直接の連関はないが、直接投棄方式の最終処分場を衛生埋立て方式のそれに転換すれば、多くの廃品回収人に影響が出ることはスモーキー・マウンテンの例からも明らかであり、その意味で、ケソン市のパヤタス、マラボン町のカトモンのそれぞれの直接投棄型処分場の問題には今後とも十分な配慮が必要である。
しかし、既に触れたように、この事業が、「マニラ首都圏排水路改善計画」や周辺住民への環境意識の改善と有機的に結合し、相乗的効果を挙げている点に注目すべきであろう。市のゴミ回収時間の情報提供によって廃品回収人の生活を支持していく試みは過渡期において重要である。そして、路上清掃人のみならず、運転手を含むゴミ収集作業員が低所得者層の雇用創出に寄与している点も忘れてはならない。
いずれにせよ、マニラ首都圏におけるゴミ問題は廃品回収人という都市貧困の問題を常にともなっている。スラム問題や最貧地方(東ビサヤ地方とビコール地方)の農村開発の中長期計画とリンクさせ、ゴミ問題の所得分配上の配慮が今後とも不可欠であることは強調されるべきであろう。
最後に、今後のゴミ事業の展開にあって、衛生埋立型処分場が主流となっていくように思われるが、サン・マテオの例では埋め立てが、資材不足から簡単なビニールシートを敷いた上になされており、地下水への汚染の問題が懸念される点に言及すべきであろう。

