第5章 有識者による評価
1. 初等教育とインフラ(カンボジア・ベトナム)
(現地調査期間:1996年9月28日~10月7日)
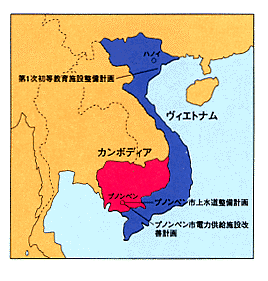
■新潟大学経済学部教授 平木 俊一
<評価対象プロジェクト>
| プロジェクト名 | 援助形態 | 協力年度、金額・年度 | 協力の内容 |
|
第一次初等教育施設設整備計画 (ベトナム) |
無償資金協力 |
1994年度、 14.46億円 |
現在、ベトナムは2000年までに全ての児童が小学校教育を受けられる体制と教育水準の向上を目指して初等教育の完全実施政策に取り組んでいる。しかし圧倒的施設不足の状況にあり、70%の教室は老朽化が著しく立て替えを必要としている。我が国は、台風被災地を中心に小学校施設30校の改修・建設を行った。 |
|
プノンペン市上水道設整備計画 (カンボジア) |
無償資金協力 |
1993年度、 9.8億円 1994年度、 17.71億円 |
プノンペン市の人口は約70万人と推定されているが、水道施設は、1980年代から1960年代にかけて建設されたもので、老朽化が著しく、かつ内戦による破壊、放置及び内戦終結後も資機材や電力不足により水供給不足が深刻な状況となっている。我が国政府は、プンプレック浄水場にかかる修復を実施した。 |
|
プノンペン市電力供給施設改善計画 (カンボジア) |
無償資金協力 |
1993年度、 22.28億円 1994年度、 18.52億円 |
プノンペン市においては電源設備の不足から計画停電を余儀なくされており、市民の日常生活、並びに工業・地域開発に重大な影響を与えている。このような状況下、カンボジア政府は、首都プノンペンの電力設備の改善を図るため、本計画実施への協力を求めてきたのに対し、我が国政府が協力を実施した。 |
ベトナム
1. 第一次初等教育施設整備計画
(1) 背景
1986年から推進されているドイモイ(刷新)による市場経済導入と対外的な開放化により、より一層の経済社会の開発を押し進めようとしているベトナムは、評価当時、第5次計画期間中にあった。1991年に「2000年までの経済・社会発展戦略」との長期的戦略を採択しており、今後10年間にドイモイ(刷新)を更に徹底するものとして、各セクター経済活動の自由化、市場経済メカニズムの秩序あるかたちで進めるための法律・制度の整備、対外経済関係の効率的な拡大等を基本的な開発戦略に掲げている。こうした戦略に基づいて2000年までに実現すべき目標として、1)経済社会の安定、2)貧困と低開発の克服、3)人的資源の育成・強化、4)国防の強化を挙げている。この中、3)人的資源の育成・強化としては、刷新政策による市場経済に向けた発展過程に対し、これに必要とされる創造的な知力と技術吸収力を持つ人材の養成が急務であり、教育訓練の全面的な改革を推進し、新しい形態の労働力の育成を目指すものとしていた。このために、一般教育の普及(Education for All)、職業訓練の拡張、理論偏重の教育を改め実際面の教育の重視、教育内容・カリキュラムを市場経済に適応するよう改善、山岳・少数民族の教育普及、施設の改善等を改善目標として打ち出した。
「Education for All(2000年までの教育普及計画)」においては、6~14歳までの児童に対する小学校教育完全実施を目指すことと、2百万人とされる非識字者に対する識字教育の実施が2つの大きな柱となっており、これらを達成するために学校教育施設の整備、建設を通じ、クラス数/教室比を1.5まで改善し、三部授業の解消を図る、有資格教員の比を70%まで改善する、としている。しかし、小中学校施設についての現状は、既存小中学校17,163校199,466教室は、2部、3部授業を実施するという施設不足にあるばかりでなく、老朽化が著しく、約70%の教育施設が立て替え修理を必要としており、更に中部・北部海岸地域・紅河デルタ地域では、毎年台風被災により損壊する施設が多く、仮設や寺院、倉庫等で授業を行っている状況であった。このような状況において、ベトナム政府は、緊急性の高い地域の学校施設整備計画を策定し、30省610校の改修・建設について要請した。これに対し、世銀等による援助地域との重複を避けつつ、特に緊急性の高い3省33校について調査を行い、そのうち30校に対し、348教室の建設と関連機材の供与を行った。
ベトナムの国家予算に占める教育関連予算は、1987年の6.6%から1993年は10.2%となっており、総額としても毎年対前年比は大きく増大している。しかし、教育予算の大部分は教員の給料・奨学金等の人件費に使われており、1992年には全体の61%(小学校71%、中学校62%、高校52%)が人件費にまわっている。このため、教材、機材等にかけられる費用は極めて限定されるとともに、施設維持や建設に使用できる予算は極めて少ない。中央政府から配分される予算は人件費に使用されることから、施設の費用の大部分は省、郡、人民委員会及び父母の負担となる。
(2) プロジェクトの評価
今次評価に際してタオビン州を訪問したが、タイビン州の人民委員会副委員長の説明によれば、タイビン州では本件計画により10~12教室の2階建ての8つの小学校が建設され、総額3億5700万円(64,500万ドン)、各小学校の費用は4,463万円(800万ドン)に上る。1995年3月に建設が開始され、1996年6月までに完成した。一般的な評価としては、施設は良好で、6,880人の児童を収容するとの目標は達成されており、良質の学校は各村から歓迎されている、とのことであった。以下、本件計画ついて訪問した各学校で聴取した事項をも踏まえつつ、評価する。
(イ) プロジェクト目標の達成度
本件計画の目標は、「ベトナムの経済社会開発計画を推進するために求められる国民の教育水準の向上を図るため、初等教育の全国民への普及、教育改善にむけ、小学校施設を建設し、3部授業の解消を図る。とりわけ施設整備の緊急性の高い台風等被災地域の学校施設の整備・改善を行う。」となっている。
訪問した2校のうちの1校において聴取した各学年毎の児童数は以下のとおりである。因みに、この学区域では6歳から11歳までの就学人口に対し130%の就学率である(貧困等の諸事情で11歳までに小学校教育を受けられなかった児童が入学するため、100 %以上の数値となる)との説明であった。
| 学年 | クラス数 | 児童数 | クラス当たりの児童数 |
| 1年生 | 5クラス | 165名 | 33名 |
| 2年生 | 3クラス | 180名 | 60名 |
| 3年生 | 3クラス | 98名 | 32.6名 |
| 4年生 | 2クラス | 78名 | 39名 |
| 5年生 | 2クラス | 78名 | 39名 |
| <合計 | 15クラス | 599名 | 平均39.9名 |
小学校施設の10教室に対し、15クラスとなっており、クラス数/教室比=1.50という基本設計上の目標値は達成しており、2部授業で消化しても余裕がある。3部授業は解消されている。実際、小学校を訪問した際も一部の教室については余裕があるように見受けられた。クラス当たりの児童数は39.9名となっており、これも基本設計上の目標値36~40名を達成している。またこの小学校ではベトナムの小学校教育で問題となっている中途退学はないとのことであった。
本件計画の基本設計調査においては、上記目標に基づいて、台風などの自然災害の多い地域に限定し、優先地域として今次調査地域であるタイビン省(他の計画対象地域はナムハ省、ニンビン省)が選出された、とある。前記のタイビン省人民委員会副委員長の説明では小学校完成後、2回台風が襲ったがダメージはなく、台風の際、地域住民の避難所として活用されたとあった。また評価者の質問に対する副委員長の説明では、「(計画の対象外の)他の小学校関係者もモデル校として視察に来ており、また副次的に、教員を対象としたワークショップの開催、夏期休暇中の講習・試験等の実施、地域集会等にも活用している。」とのことであった。訪問した小学校については、プロジェクト目標が達成されていると言える。

(ロ) 効率性
基本設計上の設計方針は、出来る限り現地で調達できる資機材の使用と在来工法に準拠することにより、現地に定着し持続的に発展させることのできる適正な技術移転を図るものとする、というものである。このため、訪問した小学校においても、公共施設等の目的で夜間使用が予定されている教室以外は照明施設がなく、その代わりに窓が大きく設計され、採光とともに風通しがよくなっていた。
(ハ) 効果
本件計画の直接的な効果は、教育施設の建設・改修により、3部授業等施設不足の弊害を解消することであり、これらは明らかに達成されている。
ベトナムにおいては、小学校の就学率は全国平均で85%と高い比率であるが、卒業できる児童の数は1981年~1985年で54.5%、1986年~1990年で46.7%と下がってきている。この要因の1つに教員の教育水準の低さが挙げられている。ベトナムでは戦争期間中に配属された初等教育教師は短期の教育訓練しか受けておらず有資格教師の数は小学校で42%と過半数にも満たない状態である。教師の給与の低さや、現職の教師も生活を支えるために副業に忙しく、教育業務に身が入らないためであるが、これは深刻な状況といえる。本件計画は第一次から第三次まで実施されており、全国的な展開を見せているが、実施規模が大きければ大きいほど、教員に関わるこのような深刻な現状は、本案件にも少なからず影響してくるのではないだろうか。ベトナムにおける現在の教育施設不足は、本案件を砂に注ぐ水の如く吸収しているようであり、案件の効果としては好ましい状況を維持するとも思われるが、学校校舎建設が必然的に就学率を挙げる訳ではないので、計画が一層効果を挙げるためにも、教員養成等ソフトの側面を何等かの形で計画の一部とすることを考える必要性が、将来あり得ると思われる。
(ニ) 妥当性
国家レベルにおける妥当性について、上記の「背景」において述べたとおり、必要な小学校施設が圧倒的に足りない状況であるため、本件計画の妥当性は疑う余地がない。特にタイビン省は、教育が盛んな省として知られており、教育実施状況は他の国に比べて高い水準にあるとのことである。州政府では教育を特に奨励しており、州内315校の内、183校(58%)の学校で社会人への初等教育を実施しているとのことであった。因みに、同省の学校施設は全て小・中併設学校となっているが、ベトナムでは、1991年の4月より小学校教育の義務教育化が法律化されており、これによって現在の小中併設学校は各々独立した小学校、中学校として施設を分離する政策が進められている。現状においてさえ足りない施設数で、かかる政策を進めるためには、新たな小学校の建設は不可欠であり、タイビン省における小学校のニーズは他の省にも増して高いと言える。
(ホ) 自立発展性
本計画では、ベトナム政府等からの維持管理の経費がそれ程望めないとの事情から、メイテナンスフリーとして概ね10年間は補修等の費用はかからなく設計する等、維持管理のための費用がなるべくかからない設計となっている、とのことである。先にも述べたが、この他にも例えば、基本的に照明器具、動力ポンプ等を使用しないことにより電気料金は原則として不要としている。しかし、タイビン省人民委員会副委員長によれば、8校の内、2校でトイレ等の給水施設が不良とのことであった。訪問した学校の校長は壁のひび割れを指摘していた。これらは保証期間内であったため、コントラクター、サブ・コントラクターにより修理されるそうであるが、メイテナンスフリーとはいかなかったようである。保証期間を過ぎた時点においては、簡便な修理、補修等の手当てをする何等かのシステムが必要な印象を受けた(注)。一般的に、ベトナムでは小学校の運営は郡(District)の管轄下で、学校教育委員会(人民委員会委員長、学校長、副校長、父母代表)の下に、学校長がこれにあたる。運営予算は基本的に省(Province)の予算が郡の行政組織を通して配分されるものと、これに父母の負担費用を加えたもので賄われるそうである。訪問校がモデル校として地域の他の学校の視察の対象となっていることは先に述べたが、前出の副委員長の説明によれば、タイビン省では小学校8校の供与の後、8人の優秀な校長を選出の上、供与された小学校の管理に当たらせているとのことであった。行政システムの働きにより、一応、体制は整っているとの印象である半面、父母等の我が国のPTAに当たる組織にそっぽを向かれると、学校長に過重な負担がかかりはしないかと、不安な面もあった。但し、この面については、訪問期間・学校数が少なかったこともあり、確認するには至らなかった。
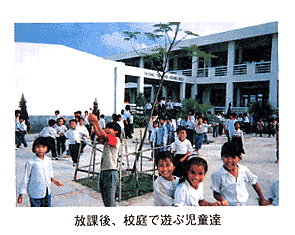
(注)基本的に、現地大使館の判断で支出可能な草の根無償(小規模無償)で、トイレ等の給水施設の極少々の給・排水施設の不具合箇所は、調整できるように推定された(20メートル程度のホースをひき、蛇口1ヶ所付けてやるだけで小学校低学年生でも使用後の水汲みと、その流しが確実に出来る度合いが増加すると観察された)。
従って、この点については、大使館の判断で支出し得る範囲で実現可能と判断される。
カンボジア
2.プノンペン市上水道整備計画
(1) プロジェクトの概要と背景
カンボジアは、1991年11月のパリ平和協定調印後、長年の内戦により疲弊した社会基盤施設の復旧・復興を国際機関及び各国の支援により進めている。我が国の同国に対する取り組みをODA白書(1996年度版)から引用すると次のとおりである。「我が国は、和平合意後の荒廃した国土の復旧・復興及び民主化に向けたカンボジアの自助努力に対して、積極的に支援を行っていく方針である。……1991年12月及び1992年1月にカンボジア側のニーズ把握のために調査団を派遣したが、その結果を踏まえ、人道援助を中心に緊急に必要とされる援助を実施するとともに、中長期的な視野に立って農業、保健・医療等の基礎生活分野、経済インフラ、人材育成等の分野において無償資金協力及び技術協力を実施してきている。」経済基盤を整えつつあるカンボジアへの経済協力において、経済インフラは重要な位置を占めていると言える。このようなわけで、カンボジアの上水道供給が人道上及び緊急性より選ばれたが、その歴史は、1895年の仏によるチュルイ・チョンバー浄水場(処理能力15,000立方メートル/日)の建設から始まる。その後、1958年にチャンカーモン浄水場(10,000立方メートル/日)が、1966年にはプンプレック浄水場(10,000立方メートル/日)が建設され、1966年におけるこれら3つの浄水場による上水供給量は155,000立方メートル/日に達していた。その後の内戦勃発により施設は荒廃し、技術関連文書は消滅し、機材等は消失し、1993年には1日当たり75,000立方メートルの供給量(1975年時の約半分)という状態であった。
1992年の5月末のプノンペンの住民登録済み人口は674,000人であるが、市内には一時的滞在者が多数存在しており、1993年のプノンペン市の総人口は80万人から100万人に達していると言われている。需要水量は1992年推定で1人当たりの日平均使用水量は約100リットルとされており、約50%の漏水率を勘案すると給水人口53万人への一日の平均供給必要水量は106,000立方メートル。上記のとおり、1993年の供給可能量は約75,000立方メートル/日であり、大幅に需要水量を下回っている状況であった。この結果、給水範囲は狭まり多くの市民は水売り、河川水、雨水、池水等の不衛生な水の使用を強いられている。しかも、給水能力の低下は大幅な水圧の低下をもたらし、多くの市民が水道管を切断し、水を導いて使用しており、これが更なる水圧の低下、不衛生な水の配水につながるという悪循環を起こしていた。
このような状況を踏まえ、カンボジア政府はプノンペン市における既存水道施設のうちプンプレック浄水場にかかる修復に係る我が国無償資金協力を要請した。要請対象となっているプンプレック浄水場は、プノンペン市の給水の大半を賄ってきているが、自家発電設備が撤去されていたし、しかも夜間電力制限を受けて1日15~17時間しか運転ができない。当時、流量計設備が不備なため、ポンプ運転時間に基づく推定値で浄水量は56,000立方メートル/日に低下していた。本計画による主な工事内容は、このプンプレック浄水施設の取水・浄水施設の電気設備の改修、送・配水施設の改修(送・配水ポンプの施設及び配水池の新設等)、配水管の新設(L=5,060メートル)及び水道メーター1万個・損傷修理用金具(バンド)の供給であった。
(2) プロジェクトの評価
(イ) プロジェクト目標の達成度
プンプレック浄水場の工事は94年9月に着手され、96年3月竣工。上述のとおり、本計画による主な工事内容は、プンプレック浄水施設の取水・浄水施設の電気設備の改修・送・配水施設の改修(送・配水ポンプの新設及び配水池の新設等)、配水管の新設(L=5,060メートル)及び水道メーター1万個・損傷修理用金具(バンド)の供給であった。これら一連の工事・改修等によりプンプレック浄水場の処理・配水能力は目標の10.7万立方メートル/日まで回復した。同浄水場の処理能力の向上はチャンカーモン浄水場の処理能力10,000立方メートル/日と相まってプノンペン市内の浄水供給能力117,000立方メートル/日を達成した。

また、仏によって1960年代に建設された給水塔に送配水施設を新設し、その機能を発揮させ、約19万人への新規給水を可能とした。本計画以前と以後の水圧上昇の状況を市内の供給地域別に整理すると次のとおりである。
| 供給地域 | 本計画以前(1994年) | 本計画以後(1996年) |
| プンプレック浄水場周辺地域 | 20メートル以下 | 約30メートル |
| 高架水槽周辺地域 | 2メートル以下 | 30メートル |
| ドンペン北部地区 | 2メートル以下 | 10メートル |
| トールコク地区 | 2メートル以下 | 2.5 ~5メートル |
| 市内南西部 | 0 | 5~10メートル |
これらの成果から、本件計画は単にプンプレック浄水場の処理能力向上により当初目標とされていた106,000立方メートルの処理水を供給したのみならず、多くの市民への処理水の配水を可能とした。プロジェクトの当初目的は十分達成されたといえる。
(ロ) 効率性
本件計画の効率性、つまり浄水場の改修、配水システムの改善等という目標を達成するための資材の投入は効率的であったか。本件計画では、現地で調達可能な資機材についての強度を考慮しつつ、コンクリート用骨材、木材、鋼材(小形)、レンガ、コンクリートブロック、タイル、亜鉛メッキ波板鋼板、ストレート波板屋根材、窓、戸扉材、ガラス、ペイント類、燃料、潤滑油(一般)、アスファルト、配管材(PVC配水管)、等々が現地調達とされた。長年の内戦により疲弊した経済・社会状況では、職能工や技術者、資機材に亘る多くの部分を現地調達で賄うには限度があるというカンボジア特有の事情があったと思われる。この点、計画段階で既存施設の有効利用に努め、また雇用・資機材の各々につき現地調達を精査した過程は好感が持てる。本計画において必ずしも大部分を現地調達に求めるには至らなかったが、施工におけるかかる姿勢は今後類似の計画実施においても維持されるべきである。本件プロジェクトサイト視察に先立って外務国際協力省の担当局長を表敬した際に、我が国援助に関わる賃金、商品価値等への認識につき水を向けたが、その時の返答は「コストについては、日本側の標準であるから問題視できない。」という控え目なものであった。今後、類似計画の実施に当たっては、経済的な成長を徐々に遂げつつあるカンボジアの状況を見据えつつ、雇用・資機材の現地調達可能性の精査を続けるべきで、今回の工事におけるように我が国からの調達だけを安易に踏襲することは、厳に避けるべきである。
(ハ) 効果
本件計画の直接的な効果は、プンプレック浄水場の改修、配水システムの整備により、安全な上水をプノンペン市民に供給することであり、これが達成された点については既に述べた。上水施設の改善は、後に述べる電力供給と共に、社会的・経済的なカンボジアの中心地であるプノンペンの発展のための根幹的基礎条件であり、これが整備されたことによる波及効果は計り知れない。WHO基準に適合した上水を供給することにより、衛生保健状況の改善(下痢症状の減少による幼児死亡率の逓減等)は最大人口集積地のプノンペン市人口の寿命を延ばすことの一助につながっていると言えよう。特に上水の供給という面では自立発展性で後述するようにプノンペン市水道公社の経営改善という間接的な効果をもたらしており、プノンペン市発展への揺るぎない基礎を築く一翼を担っていると言える。
(ニ) 妥当性
次に妥当性、つまり、プロジェクトが地域及び全国レベルの開発優先度との関連の中で今でも妥当であるか、についての考察であるが、これについては、カンボジアの開発計画をひもとくことが適当であろう。
カンボジアの経済は、基本的に第2次5ヶ年計画(1991~1995)に則って再建されているが、その中、最優先セクターは農業、二番目の優先部門は電力部門、三番目は運輸交通部門、四番目は都市開発(特に首都プノンペン)、五番目の優先分野は保健、教育、文化といった社会サービス部門である。本件計画は4番目に掲げられている都市開発に関わるが、内戦後の復旧活動において上水道の未整備が開発の主要な阻害要因とされ、主要諸国・国際機関による援助の対象とされていることからも分かるとおり、地域・全国レベルの開発優先度の高いものであった。経済・社会分野における基盤整備を続けるカンボジアにとって、上水道等経済インフラの整備は、現在でも高い優先度を保持していると言える。
(ホ) 自立発展性
本件計画の自立発展性を述べる前に、本件計画の実施機関であるプノンペン市水道公社 (PPWSA)の発展振りにつき述べる。
我が国の他、仏、UNDP、世銀等による援助でプンプレック浄水場、チャンカーモン浄水場が整備され、処理能力が上昇したことが契機となって、PPWSAの経営状況は次のとおり好転した。
(1993年の状況)浄水利用者に対する請求率及び集金率は1993年に各々28%、40%と低いものであった。プノンペ市水道公社(PPWSA)は、この原因が以下の理由に基づくと分析した。
- 利用者に関する記録が長年更新されていない、
- 水道にメーターが取り付けられていない、
- 不法な水道管接続(利用)が多い、
- 公共井戸利用者の多くが請求されていない、
- スクワッターにおける利用者の多くが料金を支払っていない、
- 配水管の多くが長年の使用や維持管理の欠如により漏水している、等々。
(利用者ファイルの更新)1979~1993年の間利用者ファイルは改訂されなかったため、26,881人とされる利用者の中、60%は実存しないか、移転していた。1994年、PPWSAは市当局、世銀、UNDPの協力を得てプノンペン市全域に亘る利用者調査を実施した。13,722人の未請求者が新たに発見され、12,980人の実存しない請求者を利用者ファイルから除外することにより、27,623人の実際の利用者に基づく利用者ファイルを作成した。1995年にはPPWSAは利用者ファイルの更新を続け、2,931人の発見、1,900人の除外により、利用者総数を28,654人とした。1995年末には28,954となった。
(メーターの設置)1993年には3,391ヶ所にメーターが取り付けられていたが、PPWSA はメーター取付に取り組んだ。1994年から徐々に取付が行われて、1994年には1日平均6ヶ所、1,979箇所に取り付けた。1995年の終わりには、総計28,654ヶ所の内、15,203ヶ所(53%)に取り付けた。この期間、643ヶ所の壊れたメーターを修理し、519ヶ所の壊れたメーターが取り替えられた。
この他、「公共井戸からの徴収」「スクワッターからの徴収」等の努力の結果、PPWSAは1993年から1995年までの間に次の表の通り、目覚ましい収入の増加を達成した。
| 年 | 1993 | 1994 | 1995 | |
| 徴収金 | リアル | 595,119,784 | 1,359,507,566 | 3,051,201,654 |
| ドル | 46,772 | 34,409 | 99,251 | |
| 集金率(%) | 40 | 58 | 73 | |
これに加え、1993年から1995年までの間、プノンペン市水道公社 (PPWSA)は世銀/UNDPの協力の下、職員の内32名を海外研修に派遣し、124名に対する国内研修を実施している。我が国を含む諸外国援助による経営好転が契機となって、人材育成を含むPPWSAの経営努力に弾みがついた形となった。本件計画にはPPWSAの自立育成との構成要素は含まれていないが、期せずして、上記のような好ましい結果を招いたと言える。先述したように、長年の内戦により疲弊したカンボジアでは、インフラのみならず、経営基盤の枢要を支える人材にも多分に不足しているのであり、このような効果が現れたことは、特筆に値すると考える。
3.プノンペン市電力供給改善計画
(1) プロジェクトの概要と背景
プノンペンの電力事情も上水道と同様の状況であった。つまり、長年の内戦により施設は荒廃し、数少ない老朽化した施設を利用して発電しているが、プノンペン市内の需要を満たすには程遠く、計画停電が実施されていた。本件計画実施前のプノンペン市内発電所の状況は次のとおりである。プノンペン市内には、№1から№5まで5ヶ所の発電所があり、№5発電所は、旧ソ連の援助で1988年に建設が開始されたが、ソ連の政変により1991年に工事が中断された。残りの№1から№4までの発電所は総設備容量の35%足らずの出力しか出せていなかった。その理由は、これら発電施設の多くが15年以上を経過し老朽化しており、また発電設備が旧式であるためにスペアパーツ等の保守・補修用資機材が不足若しくは入手不能であるためであった。補修用工具・装置も不足していた。内戦で経験ある技術者、技能者を喪失したほか、戦前に建設された設備の運転・保守マニュアル、図面その他各種技術資料等は戦時中にその殆どが消失した。これは既存設備の正常な運転・保守の実施を阻害していると共に、運転・保守者の養成にも支障をきたしていた。これに対し、プノンペン市内の電力需要は93年で昼間17メガワット、夜間で45メガワットであり、可能出力24メガワットは需要の半分しか満たしていない。修復が可能な№2から№4までの発電所については、チェコ、アイルランド、UNDPがそれぞれ修復を計画・実施中であり、我が国は№5発電所に発電設備(5メガワットのディーゼル発電設備2基)を設置する他、電力系統の連携線、配電線の新設、給電指令用無線装置と配電系統監視装置を新設することとなった。
(2) プロジェクトの評価
(イ) プロジェクト目標の達成度
本計画の第1期が1993年11月に開始され1995年2月に完了し、第2期は1994年1月に開始され1996年4月に完了した。EDCの説明によれば、本計画完成の結果、可能出力は昼間で17メガワットから27メガワットへ、夜間で23メガワットから33メガワットへ上昇し、また22キロボルトの配電設備の新設により、各発電所の電力融通を可能にした。電力事業は規模が大きくなればなる程単位当たりの電力供給経費が減少するという特性を有しており、各発電所間の電力融通による電力需要への対応、故障時のバックアップ体制の確立、発電施設の定期的検査等は健全な電力供給にとって不可欠である。かかる措置は、諸外国・国際機関による援助にも含まれておらず、日本による援助が期待されていたが本計画の実施により達成されていた。従って本計画の当初目標はほぼ達成されていると言える。
(ロ) 効率性
本計画に関して言えば、事業の効率性としては、(i)可能出力増加、配電設備の新設等という目標を達成するために資材の投入は効率的であったか、(ii)新たな設備による出力単位当たりのコストは十分低廉なものか、という点である。前者については、「基本設計調査報告書」では、「本計画に使用される資機材については現地で調達できるものはなく、全て日本調達となる。ただし、工事に使用される骨材、煉瓦、木材は現地調達となる。」と記述されており、殆どの資機材は日本調達によった。これは、前述の上水道設備計画と同様、疲弊した経済・社会状況下において、資機材の多くの部分を現地調達で賄うのには限界があったというカンボジア特有の事情により、不可避なものと考えられるが、今後類似の計画実施においては、現地調達等費用低廉化に関わる詳細な調査が引き続き必要である。
(ii)の点に関するEDC側の説明は、「これまでの老朽化した発電施設によれば350グラム/キロワットアワーの燃料を必要としていたが、供与された発電施設では220グラム/キロワットアワーであり、2基の発電施設により1996年末までに55百万キロワットアワーを出力し、燃料が7,150トン節約されることになる」というものであった。因みに、基本設計においては燃料コスト、資本コスト、維持管理コストを合計した総コストでディーゼル、汽力、ガスタービン間の比較計算を行っているが、これによるキロワットアワー当たりの発電コストのランキングはディーゼル0.076ドル、汽力0.082ドル、ガスタービン0.120ドルであり、本件計画により供与されたディーゼルが費用最小となっている。この比較におけるディーゼルの燃料消費量は238グラム/キロワットアワーとされているが、EDC から聴取した220グラム/キロワットアワーは、この値より更に低くなっていた。石油・ガス資源が発掘されていない現在のカンボジアにとって、石油輸入に逼迫している外貨を使用することは、多大な負担となる。このため発電事業においても、長期的には水力発電所建設により(最短でも6~7年が必要とされている)その大部分が賄われることが期待されており、火力発電は水力発電の開発が達成されるまでの間、電力需要の伸びを満たすためのものと位置づけられている。従って単位出力あたりのコストはカンボジア側としても関心を持たざるを得ず、またEDCの健全な操業・成長という観点からも必要であるが、供与施設は、この点の要請を満たしていると言える。
(ハ) 効果
本件計画の直接的な効果は、№5発電所への発電施設による可能出力の増強、配電施設の新設による発電所間の電力融通、これによる安定的な電力の供給や施設の定期検査等の健全で経済的な運用等であるが、これらが達成されていることは前述した。上水道整備計画と同様、電力施設の改善が、社会的・経済的なカンボジアの中心地であるプノンペンの発展のための根幹的基礎条件であり、これが整備されたことにより、カンボジアの発展に揺るぎない基礎を築いたことは疑いがない。この点、後の妥当性、自立発展性において述べるようにEDCの人材育成の面でも本計画は好ましい成果を挙げていることは、見逃せない。
(ニ) 妥当性
本件計画は前述の第2次5ヶ年計画(1991~1995)で二番目の優先部門である電力部門への協力であり、四番目の優先部門である都市開発にも貢献している。国家再建のためにカンボジア側が策定した地方・全国レベルの開発優先度との関連においても妥当な計画であったと言える。本項目との関連で、本件計画に関わるEDCの発言を引用する。
「電気事業に関わる公務員・技術者が初めて外国人と本計画の実地調査を開始した。EDCは開発に必要な事業の調査・実施にあたり、技術力・経験不足に加え、言語上の多大な問題を抱えていた。本計画の実施過程における施工・建設等の請負業者により提供された訓練により、発電力増強等の業績を達成できた。計画完了までの間、日本側専門家と良好な関係を維持し得た。この知識・経験は、仏、アイルランド、ベルギー、ADB、世銀等、他の援助国・国際機関との協力においても活用された。今日、EDC の専門家は案件の調査・実施を遂行することが可能となった。
つまり、カンボジアが必要としている本事業を比較的早い段階において実施し得たため、単に「日本側からの援助は、EDCが老朽化し故障が多い発電施設での操業を余儀なくされていた時期に実施されたものであり、タイムリーであった。」という事業そのものの成果発現のみならず、必要技術のEDC技術要員による獲得、人材育成の面で他の諸外国による協力の誘い水的効果を発揮し得たということである。これまでも繰り返し述べたが、カンボジアにおいては、単に基幹施設が破壊されているのみならず、これら施設の運用・操業を実施する主要要員も欠如していたのであり、この面における本案件の貢献も見逃せない。
(ホ) 自立発展性
発電設備の設置後、設備は故障なく定期点検時以外、毎日使用されていた。10,000時間を経過した時点において、EDCは、案件実施に当たった日本企業の技術者に点検を依頼しらが、その結果は「使用書に従って誤りなく使用しており磨耗も少なく、維持管理状況は良好であった。」ということであった。
維持更新等の保守メインテナンスが、これから必要な時期に入る。大きな故障や、スペアパーツの大量取り替えが発生した場合にEDC側だけで対応できるかにやや懸念が残った。日本のサプライヤーとの連携がフィーや資機材部品の支払いが出来るだけの経営的基盤の強化と人材の育成が引き続き望まれる。場合によっては、保守・メインテナンスの為の技術供与を用意・検討する必要も考えられる。

