第4章 合同評価
UNICEFとの合同評価(バングラデシュ)
(現地調査期間:1997年2月23日~3月8日)
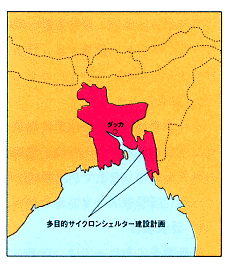
〈評価調査団の構成〉
(日本側)
■長田満江(家政学院筑波女子短期大学教授)
■浜野隆(東京工業大学助手)
■安井英人(システム科学コンサルタンツ株式会社)
■安仁屋賢(外務省経済協力局評価室)
(UNICEF側)
■Deepak Bajurachara (UNICEF, Dhaka)
■Selim Ahmed (UNICEF, Dhaka)
■Yuko Ogino (UNICEF, Dhaka)
■Jun Kukita (UNICEF, Dhaka)
| プロジェクト名 | 援助形態 | 協力年度、期間、金額 | 協力の内容 |
|
多目的サイクロン・シェルター建設計画 (日本側案件) |
無償資金協力 |
1993年度、 |
バングラデシュでは、サイクロン襲来時、高さ5メートルを超える高潮が発生し、多くの人命、家畜、財産に被害が生じており、1991年のサイクロンでは約14万人もの人命が失われた。このような被害を防ぐため、平時は小学校として利用されるサイクロンシェルター25棟(1993年10棟、1994年15棟)を建設した。 |
|
スクール・サニテーション |
無償及び技術協力 |
1992~(継続中) |
5歳以下の子供が1年に少なくとも3回下痢を経験し、これが幼児死亡3分の1の原因となっているバ国において、小学校にトイレ、これに付随するポンプ、手洗い場等を供与しつつ、これを核として衛生教育、これの普及を図る。 |
I 評価調査の概要
(1) 調査の背景
日本政府外務省とUNICEFは、その定例会議において、1996年にOECDの開発援助委員会(DAC)において採択された「開発戦略」の実現に向けて協力することを確認し、それぞれのプログラム及びプロジェクトの質的改善と両者の協力関係強化を目的として、双方のさまざまなプロジェクトを見ることのできるバングラデシュ国において、合同評価調査を実施することが同意された。対象案件として、日本側の実施プロジェクトから「サイクロンシェルター建設計画」、UNICEFプロジェクトから「学校衛生/安全学習環境整備プロジェクト」が選定され、両者評価担当者による評価調査を実施することとなった。
(2) 調査の目的
本件調査は、日本政府及びUNICEFが実施した教育関連プロジェクトについて、それぞれのプロジェクトの成果と貢献度を双方の視点から分析することにより、今後の双方の案件形成・実施、援助方針・戦略及び連携方針等にフィードバックさせることを目的とする。さらに、本調査では、日本・UNICEFの具体的な協力事業形成の可能性について検討する(第4章)。
(3) 調査の方法
本件調査は、国内事前準備作業、現地調査及び帰国後の国内事後作業から成り、各調査段階における作業内容は、現地調査では、各関連機関に事前に質問状を送付し、調査の概要を通知した上で、実際に訪問し、聞き取り調査を行った。また、現地NGOや他ドナー及び国際機関とも協議を行い、本評価調査へのコメントを求めた。
(4) 評価項目
評価調査にあたっては、以下の5項目に注目して実施した。
1) 目標達成度
2) 実施効率性(協力規模・形態、協力実施のタイミング、他の協力形態との連携)
3) 影響・効果(セクターへの貢献度、周辺地域への貢献度・影響度)
4) 自立発展性
5) 当初計画の妥当性
II 対象案件の評価結果
1 多目的サイクロン・シェルター建設計画
(1) 案件の概要
1991年4月の大型サイクロンによる14万人の死者という甚大な被害を受けて、バングラデシュ政府は1960年代以来継続しているサイクロン・シェルター建設を急ぐべく、さまざまな援助機関に災害対策の協力を要請した。日本国政府に対しては、地方自治・地域開発・組合省地方土木局(LGED)が世界食糧計画(WFP)の協力で建設中のキラ(家畜用シェルター:盛り土)40ケ所の上にシェルターを建設することを要請してきた。これを受けて事前調査団が現地調査を実施した結果、シェルター建設に適切なサイトとして18ケ所が設定された。基本設計調査ではこのうちの10ケ所(優先度A:8ケ所、優先度B:2ケ所)について調査を実施した。ただし、キラの状態は建設に適さないものであったため、全て新たに土地収用を行った上、隣接する土地に施設を建設している。また、シェルター専用施設の場合特定時期にしか利用されず、維持管理の面から費用効率がきわめて悪いことに鑑み、平常時には不足している小学校として使用する計画が採用された。
バングラデシュ政府は1993年、残りの30ケ所について再度日本国政府に対して要請し、この後20ケ所が追加され、建設候補サイトは50ケ所となった。このうち、23ケ所が調査対象地として選定され、基本設計調査では、うち15ケ所が適正サイトと判断された。
第1次プロジェクトによりシェルターと教育施設の兼用にかかる妥当性が認められたとして、前回とは異なり本プロジェクトでは、既存の小学校をシェルター機能を付加した施設として改修する計画となった。
従って本「多目的サイクロン・シェルター建設計画」には2つの機能、つまりサイクロン・シェルターとしての機能と小学校としての機能(副次的機能)が果たされることが期待されている。本章においては評価5項目に沿って評価を行うこととするが、その前に本案件の基本的な機能であるシェルターとしての機能を果たすための基本的条件、その他周辺的な条件を述べる。
バングラデシュにおいてシェルターとして期待される機能を考察する際には、数年に亘ってバングラデシュ赤新月社が実施するサイクロン対策に国際赤十字・赤新月連盟および日本赤十字社の派遣員として参加した大橋氏・萱野氏による「防災と住民参加-バングラデシュにおけるサイクロンシェルター建設をめぐって-」(「国際教育研究紀要2」1995年11月発行)が参考になる。以下は右からの引用である。
「この調査結果によれば、1991年4月のサイクロン来襲時の実際の収容住民数は、これまで公式に報告されていたものよりもかなり少なく、収容能力に対する収容割合も同様に低かった。このハティア島には1991年のサイクロンの来襲当時、バングラデシュ新赤月社のサイクロンシェルターが16棟あり、公式の総収容定員は12,800人だった。ところが筆者たちの調査では、このハティア島における1991年サイクロン時の総避難民数は6,750人前後にすぎないことが明らかになった。つまりシェルターの利用率は52.7%である。この低い利用率自体、問題である。…その避難者の多くはサイクロンによる暴風雨と高波によって家屋が破壊されたために、仕方なく避難して来たことが明らかになった。…警報に信頼を置かず、普段の大雨や強風は家を内側から支えることで何とかしのいできた人々にすれば、差し迫った危険が目の前に現れるまでは、家に留まり自力で財産を災害から守るのが合理的選択かもしれない。」
住民は何故シェルターに避難しなかったのか。その要因について同著は次のように分析している。
(社会・心理的要因)「バングラデシュの警報が元々港湾施設に対して注意を促すためのシステムとして発展してきたものであり、住民がサイクロンの接近に応じて適切な避難行動をとりやすいように考えられていないため、また予報の精度が充分でないため、最高レベルの危険警報が発せられながらサイクロンが来ないという事態が度々起こる。このため、住民はサイクロン警報を聞いてもそれを信じなくなるという、いわゆる狼少年効果が起こる。…人々は、これまでの暴風雨は家に留まって切り抜けて来た経験に基づいて家に残る。希少な家畜や財産に対する執着や、盗難に対する恐れがその背景にある。」
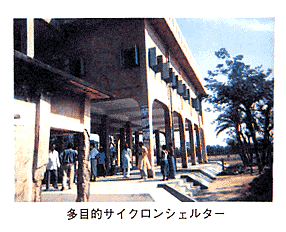
(物理的要因)「現在の多くのシェルターは、シェルターを中心とするおおよそ半径1~1.5キロメートルの住民約1千人から2千人が、1つのシェルターに避難することを前提として建設されている。しかし、現実の暴風雨とぬかるんだドロ道という悪条件下で、徒歩以外に交通の手段がない場合には、避難可能な距離は500メートルがせいぜいだと思われる。」
上記の様な住民の避難を妨げる諸要因への対策、つまりシェルターが有効に利用されるための幾つかの条件として次の点が上げられる。
i)危険地区の住民に正確かつ迅速に情報が伝達されること。
このためには、住民の信用を得た警報の伝達システムが確立していることが必要である。バングラデシュにはバングラデシュ赤新月社と救援・復興省の共同管轄にあるCyclone Preparedness Programme(CPP)が機能している。新規に建設されたシェルターについては、このCPPユニットとの緊密な連携が必要である。
ii)住民が警報に基づき、適切な避難行動をとる(シェルターに避難する)こと。
ここでは、a.シェルターのサイトが住民の住居に近接していること、つまり今回評価したような大規模のシェルターの場合、これらがサイクロンの被害に遭いやすい危険地域(HRA)に位置していること、b.住民が避難しやすいように道路などが整備されていること、c.住民が避難場所としてのシェルターの場所を日頃から認知し(自分達の避難場所として認識し)時宜にかなった避難行動がとれること、更にd.キラの完備等住民の財産への配慮があることも必要となってくる。
iii)建設されたシェルターの施設としての要件
シェルターは、単に建設時に屈強な施設が完成されるだけではなく、その強度やトイレ等備えられた施設の機能が維持されること、つまり平常時のシェルターの維持管理・運営についての責任体系、つまり誰が何をどのようにすべきか、及び費用負担などについて明らかにされている必要がある。また、上記の条件が満たされ住民がシェルターに避難したと仮定して、シェルターは多数の人々が場合によっては数日間を過ごさなければならないため、適切なスペース、安全な水の供給、トイレの設備なども基本的な条件である。
これら諸条件を図示すると図1のようになる。
以上、災害時にシェルターとしての機能を果たすべき条件を述べたが、これに小学校としての機能・条件を加味しながら、評価5項目に沿いつつ、以下に評価を試みる。
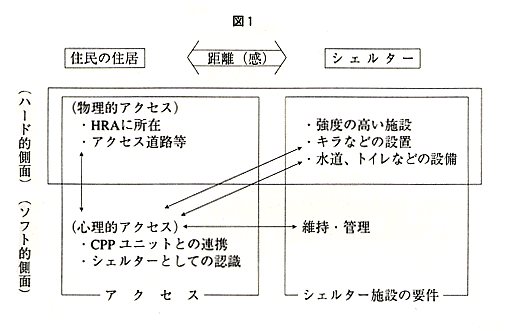
(2) 評価結果
1) 目標達成度
(シェルターとして)
基本設計によれば、以下が本案件のシェルターとしてのプロジェクトの目標である。
i)上位目標:自然災害による被害の軽減。
ii)直接目標:沿岸地域HRAの住民約30,000人の人命を守る。

ある意味では幸いなことに、本調査実施時までに大規模なサイクロンは発生しておらず、当該プロジェクトで建設されたシェルターが実際に利用された記録がまだないため、シェルターとしての機能満足度については、現時点で明確に述べることはできない。これは自然災害への対応を目的とする施設の性質上、致し方ない状況と言わざるを得ないが、現地調査で確認した施設の状況に加え、上記に述べた「多目的サイクロン・シェルター」が利用されるために必要な諸条件を考慮しつつ間接的に評価し得るであろう。
「人命を守るための施設の提供」という点では、(シェルターが完成したのであるから)目標は達成されたと言ってよいであろう。特に日本の無償資金による施設としての本案件は、諸外国の援助によるシェルターを含め、バングラデシュで見られる他のシェルターよりも大規模で頑丈であるように見受けられた(但し、この点は実施効率性の観点から、以下に詳述)。
図1に掲げられた諸条件の中、水道・トイレ等の設備については、2階にポンプを設置し高潮の際でも安全な水の供給が保証されていること、男女別のトイレを複数設置したことにより被災者、特に女性のプライバシーが守られることは、若干なりともシェルターへの心理的アクセスの強化にも貢献すると思われ、高く評価できる。しかしながら、CPPユニットとの連携等この他の心理的アクセスを高めるための対策はほとんどなされていないようであった。基本設計によれば、それらはバングラデシュ政府側の責任領域とされているが、インタヴューからはそれらは不十分であったのではないかという印象である。
また基本設計段階において強く提唱されているキラの建設が全くなされていない点は問題である。シェルターが有効に活用されるために諸条件として上記に述べたとおり、シェルターの有効度を高める意味でのキラの建設は重要である。JICAの「基本設計調査報告書」では、「サイクロンシェルターがその機能を充分に発揮するためにはサイクロン来襲時に住民が遅滞なく避難することであり、それにはシェルターに併設されたキラが、避難する住民の所有する家畜及び家財を充分に収容できることである。」「シェルター建設に伴い、収容する住民の家財・家畜をサイクロンより守るためのキラの建設は不可欠であり、「バ」国側による各シェルターの収容人数に見合ったキラの建設が必須である。」等、随所にキラの必要性が述べられている。上記のような意味でキラの重要性は計画段階で日本側関係者に充分認識されており、その建設はバングラデシュ政府側の責任とされた訳である。キラの重要性が強調されたプロジェクト設計でありながら、被援助国側の都合によりキラが建設されなかったのは残念である。また計画されているキラが、果たして住民の家畜・家財をサイクロンから守るのに十分なものであるか否かについても検討を加える必要があろう。もし、不十分であれば、住民のシェルターへの避難は遅れ、シェルターとしての機能は果たせない。
(小学校として)
目標:「平常時教育施設として、約6,000人の児童に対し安全で快適な教育の場の提供により教育の振興に寄与する。」
シェルターとしての機能と同じく、多目的サイクロンシェルターが完成した時点で、「安全で快適な教育の場の提供」は果たされており、この意味で「サイクロンにより破壊されたあるいはその危険性のある既存の政府小学校をサイクロンシェルターに立て替えることにより、「バ」国の初等教育の環境改善に役立てる。」との第二次的な目標は達成されたとも言える。特に本プロジェクトの計画地となっているチッタゴン、コックス・バザールの各ユニオンでは低年齢層が全国平均に比べて大きい値を占めており、また識字率も全国平均よりかなり下回っていること(基本設計調査報告書)を考え併せれば、本地域において小学校教育により重点を置いた方策が採られることは必要であろう。今回、小学校訪問による調査でも新しく頑丈で、快適な空間が動機づけとなって、生徒の出席率が上昇していることを確認しており、案件の目標である地域の「教育の振興」「教育環境の向上」に寄与している。サイトにおいて聴取した教師の中の一人は、シェルターが完成した後、就学率が20%増え、教育内容の質も向上したと評価していた(学年別に独立した教室があり、教師も教育に専念できるのでやる気が出てきているため)。但し、サイクロンにより破壊されたあるいはその危険性のある既存の小学校をサイクロンシェルターに立て替えたもので、小学校としての機能は副次的・二義的である。従ってHRA内に不足している少なくとも3,000の校舎不足を補足するものとはなり得ず、教育の振興という観点からは、限定的なインパクトしかもち得ないであろう。
2) 実施効率性(協力規模・形態、協力実施のタイミング、他の協力形態との連携)
コスト的側面に関わるシェルターの仕様について基本計画報告書によれば、調査の結果、他の援助機関及び「バ」国自身により建設されたシェルターは全て鉄筋コンクリート造りであることが確認されたため、建設資機材及び技術が現地で比較的容易に調達できる鉄筋コンクリート構造とした。
計画の段階ではコストをおさえるために様々な配慮がなされていることが伺える。例えば、サイト状況確認調査の結果、照明設備を設置した既存小学校は皆無であり、また、夜間授業を実施している学校は一校もないので照明施設は設置せず、できるだけ窓を多くして換気・自然光を利用することとした点。建設に必要な労務職種で特殊な技術を必要とするものはほとんどなく、現地の技術力で充分実施可能であると判断されたため現地の労務で賄うこととしたこと。建設資機材は品質・仕様の許す限り現地産のもので賄うこととしたこと。仕上げ材料等には特殊なものは極力使用しないこととし維持管理に不必要な費用がかからないようにしたこと。地盤調査から、杭基礎でなく直接基礎工法を採用できる場所では可能な限りこれを採用したこと。
このようなコスト低廉化に向けた様々な配慮があったにもかかわらず、基本設計による価格比較表を基に議論を進めると、やはり、他のドナーや政府による建設費と比較して、日本の援助によるシェルターはコスト高という批判は免れない。実際に他の機関により同程度の収容人数の規模を持つシェルターが日本の援助に比べてかなり低い費用で建設されている実績がある。耐用年数が長く高品質であり、また、日本のコンサルタント・建設会社の関与など日本の無償資金協力の制度上の制約から、日本側にとっては当然の数字であっても、上記の理由から被援助国及び他の援助機関から見れば「高すぎる」との印象は避けられない。
確かに、小学校機能を併せ持つための規模や高度ポンプ設置等の構造の他と全く異なる要素があり、単純に一棟当りの建設コストを比較することの是非については議論があろう。また、本計画の建設予定地は沿岸部のような資機材運搬車両の通行可能な場所より遠隔地にあるため、立地条件としては非常に困難なところにある。建設予定地によっては資機材の搬入に人力(プッシュカーなど)に頼らなければならないところもあった(基本設計報告書)。HRA内の建物建設が困難な場所におけるシェルター建設がコストを引き上げる結果となった可能性はあるが、いずれにしても他機関によるシェルター建設との経済・財務分析の比較を実施することは必要かもしれない。
3) 影響・効果(セクターへの貢献度、周辺地域への貢献度・影響度)
ある意味では幸いなことに、建設後シェルターとして実際に使用されたことは未だなくシェルターとしての機能については判断できないので(そしてサイクロンによる被害が最近ないためかCPPとの連携等も希薄なため)、教育の振興という点からの影響・効果ということに絞られるが、インタヴューによれば、快適な校舎が動機付けとなって、生徒の出席率のみならず教師の出勤率が上がり、より積極的にクラス運営をするようになったようである。見学した4棟のシェルターのなかで、最も活発に学校として機能していると思われたのは、ユニオンが協同組合形式をとってシェルターも含めすべての土地が組合の所有下にあるという非常にユニークな場所であった。ここでは、学校運営委員会(School Management Committee, SMC)や教師が積極的に学校運営に参画していた。この例が示しているのは、施設の向上は教育振興の一つの要因であるが、そこに係る人々(教員、SMC、父母、ユニオン議会、地域住民など)の関与の度合いがより重要な要因であるという点である。こうした関係コミュニティの関与が深まるならば、シェルターを教育施設として使うだけでなく、放課後、夜間、休日などに、コミュニティ活動(祭り、集会、各種イベント、講習会)や結婚式などに利用することも考えられよう。これにより、シェルターへの心理的アクセスも一層縮まることにもなる。
4) 自立発展性
まず、維持管理という点では、平常時小学校として使用されている以上、最低限の施設維持管理がなされるものと推測する。しかしシェルターについてのバ国側行政体制が未だ整っていない面もあり(近く整う予定とのバ国側説明あり)、いくつかの問題点が見られた。例えば、シェルターとしてのマネジメントについては、aバ国政府の計画上組織されるべきサイクロン・シェルター運営委員会(CSMC)が作られておらず、コミュニティの人々は、その組織の必要性も知らされていない、b案件がサイクロン・シェルターと小学校の両者の機能を備えているため、CSMCと学校運営委員会(SMC)との役割分担が不明確である、c.トイレの使い方(例えば、男女・教師・児童の使い分け、清掃作業の分担等)について共通の理解がなく、政府による指示もない、等々である。
また、メンテナンスについて誰が責任を持ち、故障した場合、誰に連絡し、誰が修理費用を負担すべきか等の責任体制が未整備な結果として、a.タラポンプや手押しポンプが壊され、放置されているケースが見られる、b.ドア・ノブがなくなっている箇所が多い、c.トイレに常時鍵がかかっている、d.シェルター内の清掃状況に学校によりばらつきがある、等の問題がある。
全体として、案件が存在するコミュニティの参加意識が弱く、また、コミュニティの参加を促進するための活動も希薄なように見受けられた。
シェルターとして見た場合、副次的に小学校としての機能を備えていることから、児童による校舎の日常的利用、児童の父母等心理的に校舎に近い住民を通じて平生より、地域社会による維持・管理活動を活性化し得る可能性が高いだけに、この点の不徹底が惜しまれる。このような観点からも、プロジェクトの企画実施に際し、住民参加を極力取り入れる必要がある。今回の評価においてUNICEF側対象案件である「スクール・サニテーション・プロジェクト」に関わる記述で後程述べるが、この点については、UNICEF側の案件が参考となると思われる(本章2節23参照)。方法としては、建設作業を始める前に(サイト選定の際も含め)、運営委員会、教師、親、CPP、災害管理委員会(Disaster Management Committee, DMC)他、その後の維持・運営と災害時の避難誘導に関係する人々に対し、様々な形態のワークショップなどを通じて、案件の裨益者である住民を巻き込みつつ、オーナーシップの確立と継続のための活動を実施することが必要である。また、この活動は実施(建設中)段階においても、また建設終了後小学校として利用され始めてからも行わなければならない。さらに、小学校の生徒であり、災害時には避難民となるであろう児童に対しても、(UNICEFが保健衛生について行っているのと同様)授業や他の活動を通じて、シェルターの意味合いと災害時の行動要領を周知させると同時に、両親や近隣の人々に伝えさせることも必要である。
5) 当初計画の妥当性
これまでのバングラデシュにおけるサイクロンシェルターの建設の歴史を見ると大災害の後に建設ラッシュが訪れ、数年経って止み、10程度経てまた大災害が引き起こされるというサイクルである。平時における評価の際、この点は強く認識されなければならない。何しろ短時間のサイクロンの襲来で1970年11月には30万人、1991年の大型サイクロンの際は14万人の人命が奪われたのである。これは「日本の災害史上における関東大震災、広島の原爆に匹敵する。」(前出「国際教育研究紀要2」)強度な施設としてのサイクロンシェルターの重要性は強調されすぎることはない(但し、小学校としての機能を備えた大型サイクロンシェルターの有効性の限界については後述)。
サイトについては、シェルターとしての役割を重視すれば海岸線に近い場所を選ぶ必要性があり、小学校としての役割を重視すれば、住宅や幹線道路に近く小学生が多い場所を選ぶ必要がある。かかるトレード・オフの関係を慎重に考慮の上、バランスのとれた場所の選定を行なっているかどうかは、本計画の妥当性をはかる上で重要である。
シェルター建設の基本となったのは、1992年UNDP/WBによる「多目的サイクロンシェルター計画(Multi-purpose Cyclone Shelter Programme)」である。これは、一般に“マスタープラン”と呼ばれ、詳細にわたりかなり包括的に実施された調査である。しかしながら、“マスタープラン”の位置付けにかかるその後の推移を見ると、必ずしも新規シェルターの建設実施を念頭においた「基本計画(マスタープラン)」とされなくなっている点にも留意する必要があると思われる。1995~1996年にかけて世界銀行とヨーロッパ連合により実施された16億米ドルの投資を前提として行われた調査は、先の“マスタープラン”の延長線上にあるものであるが、ここでは新規の大規模シェルター建設のみならず、住民を主体とした防災プログラムや大規模シェルター以外のシェルター機能をもつ個人の家屋を含めたインフラストラクチュア整備などもプロジェクトの一環として捉えている。これからも伺えるように、新規シェルター建設が他の様々なプロジェクトと連携しつつ行われるべきものであって、一人歩きしているのではないことを考えると、日本のシェルター建設の根拠を全面的にマスタープランに依拠したことは疑問視される点である。今後もこの大型シェルターの役割は、シェルターとしても、学校としても残されていくと思われるが、HRAの中で比較的住居の多い集落地域から住居のまばらな地域を手がけていくにつれて、大型シェルターと小型でサイクロンに耐えられるだけのシェルター(従ってシェルター以外の機能は学校に限定されない)とのコンビネーションを考えていく必要に迫られると思われる。この場合、各々のサイトに適合しやすい機能(保健所、集会所、市場等)の検討も併せて必要となってくるだろう。
2 学校衛生/安全学習環境整備(スクール・サニテーション)プロジェクト
(1) 案件の概要
1992年にUNICEFによって開始された本案件は、小学校にトイレ(男子用、女子用1つずつで1ユニット)、これに付随するポンプ、手洗い場(総称:WATSAN-Water & Sanitation設備)を建設し、初等教育の現場における最低限度必要な衛生施設を供給しつつ、これを核として、小学校における衛生教育及び児童の親を通した衛生教育の地域社会への波及に取り組んでいるプログラムである。
スクール・サニテーション・プロジェクトは、単に小学校にトイレ・手洗い場を作るというだけではなく、トイレ等建設のための建設業者の訓練や、小学校教師・学校運営委員会(SMC)委員を対象としたオリエンテーション、子どもたちへの爪切り、虫下し剤等の配布なども含むものである。これは、単に施設を整備することだけが重要なのではなく、地域社会へ公衆衛生を普及させるためには、利用者の理解ならびに所有者意識の醸成が不可欠であるとの認識に基づいている。WATSANの建設段階から地域住民のSMCに、建設のための予算や建設計画の策定などのイニシャティブをとらせていることがあげられる。
(2) 評価結果
1) 目標達成度(アウトプット目標の達成状況)
本案件には次の3つの目標が掲げられている。
- 2000年までに農村部のトイレ設置率を現在の44%から80%にまで高めること。
- 衛生的な習慣、特に石鹸利用の実施率を、現在の27%から2000年までには80%にまで高めること。
- 学校を拠点として、学校関係者だけでなく、子どもたちの保護者やその他の地域住民に衛生的な行動を身につけさせること。
このうち、1番目と2番目の目標については数値目標がはっきりしているが、いずれも2000年までの目標であり、現在のところ評価はできない。3番目の目標は特に数値目標は掲げられていないが、子どもの保護者や地域住民に公衆衛生が普及したかどうかは今回のインタビュー調査では定かではない。ここで注目しておくことは、後に3)で述べるように、本案件が間接的に女子の就学率を上げるとの効果が見られたが、奨学生の就学率の向上は本案件の直接の目標としては掲げられていないことである。本案件は、UNICEFの中でも教育部門ではなく、水・環境衛生部門が担当しており、必ずしも小学校教育の拡充を主目的としたものではない。

2) 実施効率性(協力規模・形態、協力実施のタイミング、他の協力形態との連携)
本プログラムにおいては、当地UNICEFとpMED(Primary Mass Education Division)、DPHE(Department of Public Health Engineering)等バ政府機関との協力が綿密に行われており、プログラム全体としても各種当局間の連絡・調整は、きわめて精緻で有効と見受けられた。
UNICEFとバ国政府機関、地方政府、学校運営委員会の実施・連携体制は図2のようにまとめられる。ここで注目すべき点は、プロジェクト実施のあらゆる段階(ガイドラインの作成、学校選択基準の作成、学校選択のための基礎調査、WATSAN(Water & Sanitation)施設建設のための費用の計算、モニタリングと評価)でUNICEFのみならず、DPHEが、またWATSAN設備の図面作成、入札、建設等においてSMCがかかわっているという点である。あらゆる段階で相手側との調整をはかることにより、実施の効率が高まっている。
3) 影響・効果(セクターへの貢献度、周辺地域への貢献度・影響度)
UNICEFの評価報告書より、次の点が明らかにされている。
- トイレの利用:71%の児童が利用している
- 衛生に関する児童の知識への影響:衛生に関する知識は身に付いているが、行動変容には至っていない場合もある
- (男女別トイレ建設による)女子の就学への影響:3年生から5年生までの女子就学者の増減を1993年と1994年を3月時点で比較したところ、11%(3年生で12%、4年生で10%、5年生で9%)増加している。
まず、トイレの利用については、今回の我々の学校訪問のなかでも児童がトイレを利用している姿がかなり観察されており、児童がトイレ使用後に手洗いするという行動はかなり身に付いているように見うけられた。しかしながら、そのような行動が学校内に限定されているものなのか、それとも家庭でも同様の行動がとられているのかどうかについては定かではない。これは一つには家庭での生活環境の問題が背後にあるものと思われる。ノアカリ郡で我々が訪問したある村では、食器洗いなどの生活用水に池の水を利用していたが、その村の池の水はトイレに直結していた。このような汚水の利用が家庭で通常行われているという環境では、仮に児童が学校でトイレのあとに手を洗うという習慣を身につけたところで、下痢の発生率が下がるかどうかは定かではない。スクール・サニテーション・プロジェクトは、公衆衛生普及の拠点として学校を利用するというもので、あくまで学校は手段として位置づけられている。すでに衛生に関する知識はかなり児童の間に定着しているということであるから、今後は、いかにそれを地域住民に普及させていくか、そのためにいかなる支援が可能かという点が課題となろう。
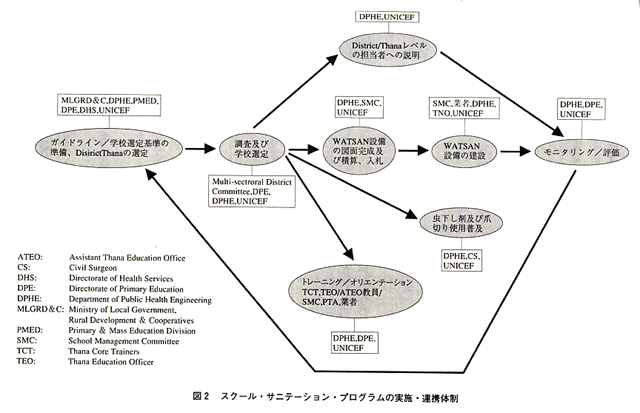
女子就学の増加については、個別に学校を調べていくと必ずしもあてはまらないケースもあり、就学者の増減が様々な要因の影響を受けるため、それらを考慮に入れ、検討することが必要である。ただ、本案件は、女子の就学率が低い原因(家庭での家事育児手伝い、女子教育にお金をかけようとする意識が低いこと、結婚年齢の低さ、女子教員の少なさ、女子トイレがないこと)のうち、コントロールしやすく、比較的安価な「男女別トイレ建設」に目を付けており、効果的な援助といえる。小学校のカリキュラムの中にも、スクール・サニテーションに関する内容(衛生教育)が3年生から5年生までの社会科の内容として組み込まれている。ただし、(バ国初等教育の根幹にかかわる問題ではあるものの)就学率、出席率は必ずしも高くないため、すべての子どもに衛生教育の内容が行き渡っているわけではない(特に衛生教育が行われるようになる高学年では就学率が低い)。また、クラスサイズが大きく、教室がすし詰め状態になっていること、教育施設・設備の貧弱さ、一部教科における教科書の貸与制、教師の質の低さなどから考えて、教科書に衛生教育内容が書いてあれば、子どもたちがそれを確実に学習するというわけでは必ずしもないことがわかる。ただ、こういったバ国初等教育の根本的な問題は容易に解決するものではなく、また、本案件の直接の目的とするところでもないことは付け加えておく必要がある。
4) 自立発展性
自立発展性に関しては、トイレや給水施設の維持管理に関して、その組織・体制が確立されているかどうか、財政的自立発展性はあるか、物的・技術的な自立発展性はあるか、といったことがそのサブテーマとなる。UNICEFの評価報告書によると、維持管理については、次のような結果が明らかにされている。
- トイレの95%が使用可能な状態で保たれている
- トイレのドアの88%がよい状態で保たれている
- Y-Junction(排泄物貯蔵槽へのパイプ)の88%が適切に機能している
- トイレ掃除は児童がやっているという学校が88%、残りの学校は教師がやっている
- トイレが定期的に掃除されている学校は36%
我々の訪問した学校では、SMCがエクストラ・コスト(学校が遠隔地に存在した場合の資材運搬コストの他、トイレ用石鹸箱、排泄物タンクからのガス抜きパイプ等)を自発的に負担しており、これが更にオーナーシップを高めているものと思われる。SMCが盗難を防止している例(放課後、水道の蛇口を外して翌朝設置する、など)も見られた。予定外の学校にもいくつか抜き打ちで訪問したが、ほとんどの学校で維持管理は概ね適切に行われており、トイレも清潔に保たれていた。このようなSMCの活動を見る限り、本案件の当初のねらいである「SMCに建設段階よりイチシャティブをとらせることによるオーナーシップの高まり、その結果としての適切な維持管理」は実現されているように見受けられる。聞き取り調査の結果、それは組織的にも、財政的にも、物的・技術的にも十分可能であるものと思われた。ただ、現在のSMCの委員長やそのメンバーは今後交代してしまう可能性があり、引き続きUNICEF、DPHE、DPEによるモニタリング、評価をつうじたSMCへの継続的働きかけによる維持管理の充実が必要である。
5) 当初計画の妥当性
5歳以下の子供が1年に少なくとも3回下痢を経験し、これが全国260,000人の幼児の死亡を招き(幼児死亡の3分の1)、栄養失調等発育を阻害しているバ国において本案件の目的の妥当性は疑う余地はないであろう。またその方途に関していえば、バ国の衛生状態を改善していくための拠点として、全国にくまなく存在する「小学校」に着眼したという点は高く評価される。更に、施設費用の効率性(1式16万円程度)、および資材の現地調達容易性は極めて高く、そのこともまた地域住民による維持管理を容易にしている。
本案件は、「重点地域アプローチ(ADA)」、すなわち、より保健衛生改善の優先度の高い郡を選定しているが、その選定も概ね妥当であると思われる。また学校選択基準もきわめて明快である。建設されるトイレの数については、一律1校につき1ユニットであり、児童数が多かろうと少なかろうと一律に1ユニットというのにはやや疑問が残るが、本案件実施を公衆衛生普及の「第1歩」として考えれば、一律1ユニットとして、広く学校にトイレを建設することも妥当性があるといってよいと思われる。
また、スクール・サニテーションの副次的効果としてあげられている就学者(特に女子就学者)の増加は、バ国第4次5カ年計画における教育計画でも重視されている「女性の参加」、「初等教育の完全普及」といった教育目標とも合致するものであり、その点でも妥当であるといえよう。
(3) 援助プロジェクトの「展開」
このように目覚ましい成果をあげている本案件も一朝一夕に形成されたものではない。1992年より始まった本案件において第1期に1,089ユニットのトイレを、更に1993年から始められた第2期において1,000ユニットを完成させ、第3期に700ユニットの建設が計画された1994年UNICEFはプロジェクト評価を実施している。このような評価やモニタリング等その他の方法により見出された結果は、(イ)資金支払い、入札、落札、建設中の監督、建設完了等の全体的なプロセスがめんどうで、やたら時間がかかり、無駄が多く、従って高額となっている、(ロ)建設されたトイレの質や利用率が維持されていない、(ハ)第1期、第2期で設置されたトイレの多くは使用されていないか劣悪な状況にある、(ニ)ほとんどの場合において使用者による維持・管理計画の欠如が見られる、(ホ)計画された期間内に建設されておらず、遅延が当たり前のこととして受けとめられるに至っている、という手厳しいものであった。この主な原因としては、(イ)建設業者にとってトイレ1個に配分された資金は魅力がなく、劣悪な資材の使用や、デザインを変えることにより利潤を上げようとしている、(ロ)学校運営委員会(SMC)が計画や実施に関与していない結果として、SMCや教師達はトイレ建設中の管理・監督という効果的役割を果たせず、(ハ)多くの場合において業者は有力な政党の若いエリートであり、教師やSMC、郡レベルの行政官までもが、建設過程における不正を知り得てもこれを責められない、(ニ)地域社会、SMC及び教師による計画、費用分担、案件実施への関与がないため、トイレの質や維持管理への無関心さを招いている、(ホ)政府施設の維持・管理に対する一般的な「無神経」「無関心」が存在する、という点にあることが指摘された。
これを受けて、カマルゴンジ(Kamalgonj)郡モルビバザール(Moulvibazar)地区の5つの小学校において、SMCメンバー11人の内の5人をメンバーとする「プロジェクト委員会」に必要な資金、設計書を与え、SMCの関与を維持しつつトイレを建設し、その結果を業者により建設した場合と比較することとなった(「モルビバザール実験」)。この実験の結果がUNICEFの報告書("A Study on the Implementation of Latrinesand Water Supply System in Primary Schools Through School Managing Committees -An Experiment in Moulvibazar", Dr. Tafail Ahmed)に記述されているが、それは余りに対照的であった。(イ)業者による建設の場合、そのどれもが与えられた40日間の工期で完成することができなかったのに対し(中には6ケ月から8ケ月を要した業者もあった)、5つのSMCは1ケ月以内に工事を完了した、(ロ)SMCによる場合はトイレの水槽、便器、手押しポンプ等全てに亘って資材の質を綿密に検査しつつ使用し、必要な場合には自腹を切ってでも質の良いトイレを完成させているのに対し、業者による場合は半数以上が劣悪な状況である、(ハ)またはトイレ建設への関与を通じてSMCメンバーの間にオーナシップ(所有意識)が生まれ、与えられた業務を自分自身のものとして受けとめており、トイレ完成の暁には一種の「達成感」を持った、等々である。
このような実験の過程を経て、案件の計画段階からのSMCの関与の重要性が強く認識され、それ以後、他の地域においてもより一層のSMCの関与が図られるようになったのである。このように、UNICEFのスクール・サニテーション・プロジェクトは、「評価」や「実験」の過程を経てその手法を「展開」しつつ、現在の姿に至ったといえる。
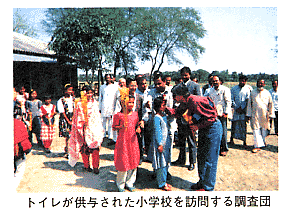
III 本評価調査から導き出される提言
(1) 導き出される提言
日本側案件「多目的サイクロンシェルター建設計画」とUNICEF側案件「スクール・サニテーション」は、両者とも施設供与を含み、その維持・管理が必要である点は共通している(但し前者が比較的大型の施設で維持管理費が高くなりやすく、従ってSMC等への負担が重くなりがちであるのに対し、後者が衛生教育に重点を置き施設としては比較的小型の施設で維持管理費が低く、SMC等にとって扱い易い点が対照的)。どちらの案件も一定の目的のために供与された施設である以上、裨益者によってその目的のために利用されなければ供与した意味がない。またいざという緊急時に地域住民が振り向きもしなくなった時、維持管理が徹底せず使用に耐えない状態となり打ち捨てられた時その援助は無駄であったということになる。この点、単に施設を供与するという案件であっても、余程配慮する必要がある。サイクロンシェルターに関して先述したように、警報への不信感、家畜や財産に対する執着等の理由で、バングラデシュ赤新月社のサイクロンシェルターが収容定員の半分しか利用されていなかったとの国際赤十字社派遣員の指摘は、この意味において、また自分の命に関わる緊急時には施設に避難するであろう、との期待が高いだけに衝撃的である。大型サイクロンシェルター利用のための措置にはこの他にもアクセス道路等整備、CPPユニットとの連携、避難活動に関する住民の知識の向上等、多くの要素がある。これらは、施設案件供与のための調査段階において、援助国専門家による緻密な調査作業によりある程度予見し案件設計に反映することにより回避し得るものも多いが、施設供与後認識されるもの、施設供与後の状況の変化により対応が迫られるものも多い。後者について、被援助国の責任範囲と規定して施設面での供与のみを行うことが必ずしも不適切であるという訳ではないが、そもそも多額の援助資金を費やして施設を供与する際に大型シェルターにおけるキラ、アクセス道路等、必要不可欠な構成要素が欠如している場合、施設が利用される可能性について、心許ない印象を持たざるを得ない。この点、「スクール・サニテーション」の場合は幸いであった。第1期、第2期に供与した施設の状態、利用度が思わしくないことを受けて実施した「モルビバザール実験」を契機にSMCを計画段階から関与させる方法を通じて、短期間・低費用で質の高いトイレを児童に提供することができた。同時にSMCメンバーの間にオーナシップが生まれ、与えられた仕事を自分のものとして受けとめるに至った。またこの過程において初等教育局(PMED)、地方政府技術局(DPHE)等バ国政府機関による関与も維持し得た。
このような「援助案件への住民の参加」が重要との点は随分長い間主張されてきているが、それは主として案件の維持管理の面においてであった。UNICEFの体験はこれが維持管理のみならず、設計、設置場所の選定、建設という案件の初期段階を含むあらゆる面での関与が重要であり、それが案件をむしろ経済的・効率的にしているということである。では何故UNICEFの「スクール・サニテーション」はトイレの維持管理においてさえも危うい状況を乗り越えることができたのであろうか。
プロジェクトの第3期が開始されて半年後の1995年6月、UNICEFはSecretary of the Local Government Division of the Ministry of LGRD & Cを議長としてハイ・レベル会合を設け、ここで「契約業者にトイレ建設を任せる既存のシステムに伴う問題を乗り越えるために限られた数の学校においてSMCを関与させる実験を実施する」との結論を出した。これを受けてUNICEFチッタゴン事務所が契約業者の代わりにSMCによって案件を実施するという画期的な実験を試みた。この過程に見られるように、UNICEFは(イ)日頃のモニタリング、評価によって問題の所在を認識し、(ロ)被援助国政府との話し合いにより事態の好転を検討し、(ハ)試みとして案件の一部において「住民を案件の初期段階から参加させる」という実験を行い、その有効性を確認した後、案件のシステムを変えていったのである。
このような案件の展開は、多くの職員を擁する事務所や地方事務所を持ち、日頃より相手国中央政府のみならず地方政府・事務所と連携をとりつつ案件を実施しているUNICEFにおいて可能であった。また、トイレ施設の供与を全国的に展開しているUNICEF案件の特徴を、案件が大型であるために維持管理費の大部分において地域住民ではなく相手国政府・地方機関に頼らざるを得ない日本側案件にそのままあてはめることはできないが、日本側において、そのメリットを少しずつ学ぶことは可能かもしれない(今次評価調査において維持管理の必要性が確認されたサイクロンシェルターの箇所は、タラポンプ、手押しポンプ、ドア・ノブ、トイレ、清掃状況等SMCによる維持管理が十分可能な部分である)。
IV 我が国政府開発援助とUNICEFとの協力の可能性
日本のODAは、施設建設、機材供与等のハード面においては、さまざまな経験・ノウハウを蓄積し、多くの実績があるものの、社会開発分野、かつ、これに伴うソフトの側面での経験蓄積が望まれることは指摘されてすでに久しい。
最近のこうした「顔の見えるODA」、「量より質の充実」を求める声がある中で、1996年にOECD開発援助委員会(DAC)において採択された「開発戦略」を踏まえ、日本のODAも社会開発分野、あるいは、ソフト面に力を注ぎつつある。本評価の対象となった(施設の無償資金協力案件である)多目的サイクロン・シェルター計画の評価においても、その維持・管理面で、計画段階からの地域住民参画による所有者意識の醸成の重要性が再認識された。
一方、フィールド業務にたけた多数の専門職員を抱える当地のUNICEFが形成・運営しているスクール・サニテーション・プロジェクトは、ハード的整備は最小限にとどめ、ソフト的プログラムの整備とこれを担う現地の人材育成に主眼を置いている。日本の援助がソフト面を重要視している昨今、こうしたUNICEFと協力することは、ドナー間の連携(パートナーシップ)強化を提唱するDAC「開発戦略」に合致するだけでなく、具体的に学び得る点は極めて多いものと思料する。
この意味において、昨年より当地UNICEFがバ国政府と一体となって実施・運営しているIDEAL(Intensive District Approach to Educational for All)は注目に値する。このプログラムは、絵画、歌、踊り、教材、ロール・プレイ等の活用を通じて児童の授業への積極的参画を引き出すことにより、学校をより魅力的なものとし、バ国における長年の悩みである初等教育就学率向上をねらうものであり、当地UNICEFの発案・バ国側政府への働きかけを通じ、今やUNICEFとバ国政府、モデル地域の地方自治体(教育委員会)、対象学校等が一丸となって実施しつつあるプログラムである。本プログラムは、a.開始されて間もなく、b.多角的プログラムであり、ハード・ソフト面ともに参画の余地があることに加え、c.バ国政府側も初等教育における重要プログラムとして位置付けており、d.熱意ある当地UNICEF職員によって運営・モニタリングされており、失敗、挫折の可能性が少ないことに鑑みれば、日本側にとっても協力し易いプログラムであると思われる。このようなプログラムにおける協力は、日本がハード面からソフト面に重点を置いた案件へと新しい展開をする過程にある今、ソフトをこなしうる有能な人材を育成する上できわめて重要かつ有効であると考えられる。先述したとおり、多目的サイクロン・シェルターのように施設を供与する案件においても、施設の活発な利用及び長期的な維持・管理に配慮した場合、コミュニティ参加の促進等ソフト面での手当、工夫は絶対不可欠である。したがって、現在実施中である第3次多目的シェルター建設計画においても、IDEAL及びスクール・サニテーションのスタッフと意見交換することによって、地域住民の動機づけ、住民参加システムの作り方、実施体制の整備などについて学び、それをシェルターの今後の管理・運営に活かしていく必要がある。また、こうした交流の中で、シェルター小学校でのIDEAL導入など、日本とUNICEFの協力プログラムのきっかけをつくることは十分可能である。
これから、日本のODAが社会開発分野に踏み込んでいくにつれて、かかるソフト面の専門家育成は必須の措置であると考えられ、中期的には、例えばバングラデシュにおける活動経験を持つシニア・レベルのJOCV隊員を当地へ3、4人程度派遣の上、IDEAL等のプログラムにおいてフィールドでの活動と共に政策レベルの協力プログラムにも参画し得るポストで経験を積むことは、協力を通じて当地UNICEF側の長年にわたる経験・ノウハウを我が国が習得する観点からも、十分に検討に値すると思われる。

