第3章 特定テーマ評価
居住・生活環境改善(インドネシア)
(現地調査期間:1996年9月8日~9月21日)
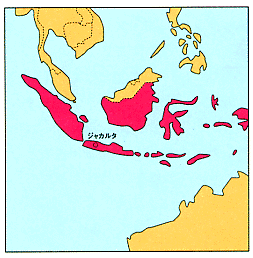
■絵所 秀紀 法政大学経済学部教授
■友野 勝義 日本水道協会主任研究員
■岩井 くに 自冶医科大学地域医療学教室助手
■中畝 義明 世界経営協議会研究調査部課長
| プロジェクト名 | 援助形態 | 協力年度、金額 | 協力の内容 |
| セクター・プログラムローン |
有償資金協力 |
1988年度 724.00億円 1989年度 325.00億円 1990年度 381.22億円 1991年度 675.20億円 1992年度 661.70億円 1993年度 340.56億円 1994年度 208.44億円 1995年度 173.12億円 1996年度 160.05億円 |
インドネシア経済は、1980年代後半から国際資本の急激な移動並びに債務負担の課題に直面しており、更に規制緩和及び国内景気の過熱化に伴う経常収支赤字の拡大への対応、外貨準備率の引き上げが必要となっている。このような状況に対応するため、国際収支の改善を目的として、そこからもたらされる見返り資金を借款供与国と借入人との間で予め合意された重点セクターの開発支援に振り向けるセクタープログラムローンが供与されている。 |
1 セクター・プログラム・ローン(SPL)供与の背景と特徴
(1) SPL供与の背景
インドネシア経済は1986年に、石油・天然ガスの暴落の影響を受け経常収支が大幅に悪化した。インドネシア政府は危機を乗り切るため、わが国にもSPL(セクター・プログラム・ローン)を含む緊急の国際収支支援を要請し、わが国からSPLが1988年度から供与され、1996年度現在に至るまで継続している。
SPLは88年度は円借款総額の41.1%を占め、その後シェアを下げたが、91年度から92年度にかけて再びシェアは上昇し40%を超えた。93年度からは再び減少傾向をたどり、96年度には8.4%にまで減少した。これは「商品借款・既往案件内貨融資→SPL→PTSL(プロジェクト・タイプ・セクター・ローン=クイック型)」と援助形態が変化したためと思われる。ただこれらは、わが国の対インドネシア援助のうちで大きなシェアを占めている。
(2) SPLの特徴
国際収支支援としての円借款は通常は商品借款の形態をとる。ところが、見返り資金の使用が判然としないとの批判があり、こうした批判に答える形で、商品援助の透明性を高める手段としてSPLが生み出された。SPLの特徴として以下があげられる。
SPLは本質的には商品借款の変形であり、国際収支支援を主目的とする借款である。即効性がその第1の特徴である。第2の特徴は、見返り資金を「地方開発、農村開発を含む社会セクター」の開発にあてている点である。第3の特徴は「プログラム・ローン」であるという点にある。しかし世銀のSALあるいはSECALとは異なって、いわゆる「コンディショナリティ(政策変更条件)」は付けられていない。2国間ベースでコンディショナリティを要求するかどうかにはセンシティブな面がつきまとう。インドネシア側に義務として課せられたのは、監査報告の提出と入札書類の保管である。SPLは、何千という小規模プロジェクトの集合体であって、個々のプロジェクトの選択はインドネシア側が決定し、実行している。
(3) SPLからプロジェクト・タイプ・セクター・ローン(PTSL)へ
近年インドネシアの国際収支が改善するに伴って、SPLからプロジェクト・タイプ・セクター・ローン(PTSL)方式へ変わりつつある。PTSLはセクター・ローンであり、国際収支援助と「草の根」型援助とを組み合わせた援助形態である。
海外経済協力基金はSPLからPTSLへと転換を促してきた。インフラとしての性格が強い分野の案件(例えば「地方電化」)の場合にはPTSLへの転換は比較的容易である。しかし、「保健医療」および「社会福祉」分野の場合には保健センターの細々した備品等、現地調達資機材を占める割合が多く、プロジェクト案件として実施していくのは容易ではない。そのため、1996年に至るまで保健医療と社会福祉の2分野にはSPLが供与されることになった。
1988年度から96年度にかけてのSPLの累計額は3,645億7,400万円である。部門別の配分は、運輸(32.0%)が大きく、つづいて教育(13.6%)、水資源(12.6%)、保健(12.2%)、居住環境(10.7%)となっている。社会福祉セクター(3.6%)、森林セクター(2.3 %)への配分比率はわずかである。
今回の調査においては、以下に述べるように保健セクターと居住環境セクターを調査対象とした。
2 居住環境セクター
インドネシアは全国土の7%にすぎないジャワ島に人口の60%強が集中している。地方部への人口集中は住居、水道、衛生施設等に深刻な問題をもたらしている。
インドネシアの水道・都市セクターの行政を管掌する主たる省は公共事業省(Ministry of Public Works)であり、その中で住宅都市総局(Directorate General of Human Settlement: Cipta Karya)が開発計画、上下水道、公衆衛生、住宅建設、地域計画、公共建造物等を受け持っている。
(1) 水道・衛生サブセクター開発の概要
第1次開発5カ年計画(Repelita I 1969/70-73/7)の当時から水道と衛生施設の建設は、政府の一つの重要な政策であった。貧困層で安全な飲料水を得られず、また安全な衛生施設を利用できない人口は都市部および農村部で着実に減少しつつあるが、これをなくするためにはまだまだ大きな投資を必要とする。
水道の普及率は、都市部で61%、農村部で31%である。インドネシアでは中小都市はもちろん、かなりの大都市でも各戸に設置された給水栓によって給水を受けられる人口の他に、共用水栓を利用している多くの住民がいる。中小都市ではそうした共用水栓利用人口が3分の1を越える場合も珍しくない。
(2) 住居・都市サブセクター開発の概要
1980年から1990年の期間に、住環境の基本的サービスである給水と電力供給の普及率は、37.6%から53.6%へ、48.5%から85.3%へと大きく増加した。1970~1980年代、都市インフラ関連投資の多くは主要都市のみに対して、道路、水道建設に対して行われた。KIPは1970年代の末になって加えられた。
Repelita IV(1984/85-88/89)で、IUIDP(Integrated Urban Infrastructure Development Programming:総合都市インフラ開発計画)の概念が導入された。従来、水道、衛生、道路、廃棄物処理、都市排水等、各サブセクターで開発努力がバラバラに行われていた状態の改善が試みられている。現在進捗中のRepelita IV(1994/95-98/99)においては、住環境・住居・都市サブセクターでは、約50万戸の住宅団地の建設、125 都市の21,250ヘクタールのスラムの改善と750ヘクタールの再開発、そして約20,000の未開地区村落の住居と住環境の改善が目標とされている。
(3) SPLによる居住環境セクタープロジェクト
見返り資金を利用し、これら開発事業を行うのはインドネシア側であるが、経済協力の社会開発へのインパクトを見るため、インドネシア側がSPLを利用して行った下記プロジェクトを視察した。
SPL見返り資金で居住環境セクターが取り上げられたのは1988年度から1994年度までであり、このセクターに配分された資金の総額は391億円である。これはSPL総額の10.7%にあたる。対象は、1)首都圏水道、2)地方都市水道、3)居住環境改善(KIP)、4)環境衛生、5)廃棄物管理、6)都市排水、7)住宅整備、8)地域総合開発と多岐にわたっている。
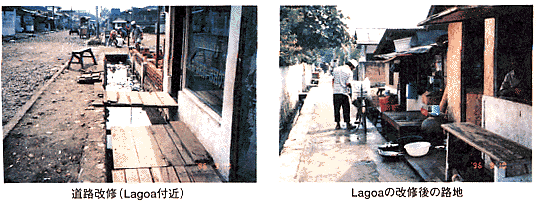
1) Jakarta市内Rawa BadakおよびLagoa地区:Housing/KIP, Prokasih(総費用RP 614,812,000)
Rawa BadakおよびLagoa地区はジャカルタ市北東端Tanjung Priokにある。Kampungに入る道路(1,921メートル)および支道(路地)(453メートル)の改良と無蓋側溝工事(2,822メートル)がプロジェクト対象である。この道路の幅は1.5メートルほどである。
側溝は、ゴミが捨てられてつまっている箇所はないものの、水の動きは鈍い。ほとんど動水勾配がないのが原因である。現状では、大雨が降るとおそらくかなりの部分で道路も冠水するのは避けられないと思われる。給水栓を持たない約半数の家庭は水売りから水を購入している。
2) Jakarta市内Bidara Cina地区:Housing(INP-16)/KIP, Prokasih(総費用RP 549,862,500)
幹線道路Gadotto Subrotoから少し東へ入ったところに位置している。4棟の低所得者集合住宅団地のへの道路(466メートル)、無蓋側溝(466メートル)、有蓋排水溝(243メートル)、駐車場(200平方メートル)が見返り資金で建設された。
かなり深い側溝に蓋がないのは、子供が誤って落ちるケースを考えればよい設計ではない。1カ所マンホールの蓋が壊れており、木を置いてあるだけで危険な状況にあった。住民が維持管理にあたることになっているが、そうした形跡はうかがえなかった。
3) Tawang Sari浄水場(東ジャワ州Taman市Sidoarjo地区)
SPL見返り資金とIBRD、それぞれ50%ずつの資金で1993年に完成した浄水場である。施設の総容量は200リットル/秒(17,300立方メートル/日)であるが、稼働しているのは4分の1の容量(50リットル/秒)のみである。これはインドネシア側の責任で施工することになっている配水管の工事が遅れているためである。
運転の状態は、沈殿池の機能は正常であると認められる。しかし、凝集処理が不十分なため、沈殿水(上澄水)の状態はあまりよくない。Cipta Karyaは経験者を派遣し、薬注処理や施設の運転操作について再指導の必要があると思われる。
4) Krikilan浄水場(東部ジャワ)
SPL見返り資金で建設された容量100リットル/秒のミニ浄水場である。この浄水場から給水タンク車への注水され、給水されている。飲料水用のみでなく、地区内の工場へも給水している。
5) Peninjauan Locasi Ampel Gading(KTP2D/PLP)(東部ジャワ)
マラン地区にあり、プロジェクトの内容は水路建設(500メートル)、サブターミナル(100平方メートル)および住宅改造15戸である。道路の舗装は比較的スムースで損壊箇所もほとんどない。ただ道路側溝が動水勾配を無視して作られているため、排水溝に効率よく排水されていない。
6) Drainase Koda Blitar(東部ジャワ)
プロジェクトのコンポーネントは幹線排水路、汚水(屎尿)処分施設(97カ所)、汚水収集用手押し車(18基)である。幹線排水溝は幅5メートル、深さ2メートルほどで数百メートルの長さがある。状態としては、乾期のため水量は少ないが比較的よく流れている。ただゴミが底部にたまっており、定期的に清掃する必要がある。
7) Lokasi PLPK Kelurahan Pekunden KEC:Sukorejo KOD(東部ジャワ)
新規の場所に建設された21平方メートル型(平屋)の低所得者用住居団地である。各戸には水道が接続されている。この道路と側溝の工事がSPL見返り資金による事業の対象となった。側溝の側壁の構造が脆弱なため、損壊している部分も見られた。将来改良の余地がある。
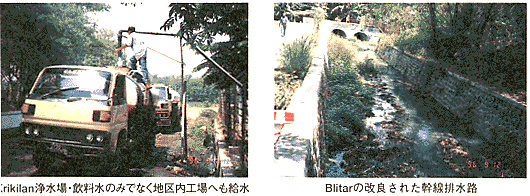
8) Environmental Engineering Laboratory(BTKL)(環境技術研究所)(Balai, Yogyakarta )
SPL見返り資金(INP18および19)によって各種分析機器を購入している。保健省伝染病管理環境衛生局に属し、全国に3つある「環境工学試験所」の1つである。政府機関、病院等から依頼を受け水環境、大気およびガス、騒音等の住環境の調査を行っている。BTKL所長は、SPL見返り資金で有用な分析機器を購入できたことは役立ったとしていた。
視察したプロジェクトは、総対的にプロジェクトの目的を達していると見なすことができる。SPL見返り資金でプロジェクトを実施した担当者は、資金の自由度から、この方式の援助を評価している。ただし、インドネシアによって建設されたものは、下流の排水路の改修をしないまま道路側溝を作ったため道路側溝の水はけが悪い等、効果について疑問のある場合もある。SPLの見返り資金は、インドネシアにとってKampung改善プロジェクトのように、プロジェクトローンでは取り上げがたい分野の開発に使えるというメリットは大きいと思われるが、SPLを供与した側から見るとプロジェクトの設計基準、管理体制、出来具合をチェックしていくには実施体制の確保が必要である。
3 保健セクター
インドネシアの島嶼間の交通の不便さ、感染症や熱帯病の存在に敵した気候等は、医療サービスを提供していくうえでの障壁となっている。低所得者や遠隔地域の住民には公的医療が頼りである。インドネシアの保健セクターに対して、国際機関および2国間援助は、1992年度実績で保健省予算総額の約8%に相当する。
(1) 保健への取り組み
インドネシアの死亡統計における主要な感染症は結核、急性呼吸器感染症、下痢症と消化器感染症、破傷風、ジフテリア、百日咳、麻疹である。これら従来からの感染症のほかに、デング熱、HIV感染症などの新興感染症が問題となっている。
結核は死因の第2位であり、死亡者の10人に1人は結核が原因である。政府は予防接種を推進しているが、BCG予防接種を受けた子供は全体の72%であり、約3割の子供が結核に対して無防備な状態におかれている。
予防接種はPosyandu(Health and Family Planning Village Gathering地域検診活動)に助産婦や看護婦が出向いて行っている。Posyanduの活動をはじめとした住民参加型地域保健活動を展開した結果、乳幼児死亡率は1967年の149から1994年には58まで低下した。保健センターはインドネシア語でPuskesmas(Pusat Kesehatan Masyanahat:Center of Social Health)と呼ばれ、公的診療所、保健所、自治体の行政担当課にあたる3つの機能を有し、地域医療の重要な役割を果たしている。保健センターは各郡に1カ所あり、1994年に全国で7,097カ所に設置されている。標準的業務内容は、患者診療、歯科診療、母子保健、家族計画、感染症対策、衛生、栄養、健康教育、学校保健、ラボ・サービス、精神保健、地域保健看護、保健情報管理、老人保健、職域保健、目の保健と盲目予防、スポーツ保健等の18項目である。このほか対象地域の準保健センター、村の保健婦、Posyanduの指導などの役目も果たしている。SPLの見返り資金から機材の整備が行われている。
1969年からの20年間に保健センターは1,000から5,600以上に、病床数も70,000から120,000に増加した。感染症対策によってコレラは著減し、74年には天然痘の撲滅に成功した。現在実施されている第6次5カ年開発計画(1994/95-98/99)の保健医療セクターでは、計画終了時までに、平均寿命の延長(62.7歳から64.6歳)、死亡率の低下(人口千人当たり7.9から7.5)、乳児死亡率の低下(出生千人当たり58から50)、低出生体重児の減少(新生児の15%から10%)、カロリー不足の子供の減少(40%から30%)、出生率の減少(人口千人当たり24.5から22.6)、人口増加率の低下(年間1.6%から1.5%)やう達成目標としている。
(2) SPLによる保健セクタープロジェクト
見返り資金を利用し、これら開発事業を行うのはインドネシア側であるが、経済協力の社会開発への波及効果を見るため、インドネシア側がSPLを利用して行ったプロジェクトを視察した。
SPLは1988年から1995年までの8年間では総額3,489.3億円が供与され、うち353.4億円が保健セクターに配分されている。これはSPL総額の10.1%にあたる。SPLは保健予算全体の約12%にあたる。
SPLはインドネシアの保健センター整備、伝染病対策に大きな役割を果たしてきた。保健センターの強化拡充プログラムでは、全国27州の保健センターに対し、基本的機器(乳児用体重計、血圧計など)、歯科治療キット、実験室キット、予防接種用機材(小型冷蔵庫、ワクチン容器、蒸気消毒器、注射器、注射針など)、車両、太陽電池などを供給した。機材を受領した保健センターは、INP-16(1992年)で1,502カ所、準保健センター3,637カ所、INP-17(1993年)では保健センターの3,273カ所、準保健センター10,170カ所に上っている。予防接種促進および環境保健強化プログラムでは全国27州を対象に州および県の地方自治体に対し、ワクチン、ワクチン保存・運搬用機材(コールド・チェーン)、車両、検査器械、殺虫剤噴霧器など、多岐にわたる機材が長年にわたり供給されている。
1) Sentolo保健センター(ジョクジャカルタ特別州Kulonprogo県)
有床の保健センターである。医師2名(うち1名は所長)、歯科医師1名が勤務。地域内に44のPosyanduがあり、スタッフは月22回Posyanduに赴く。SPL見返り資金を利用した備品は顕微鏡1、歯科治療ユニット1、手術台1、モーターバイク1である。備品には「OECF」のマークが表示されていた(SPLの見返り資金、すなわちインドネシアの資金で購入したものであるからこのようなマークを付ける必要はないが、保健省の判断で付けたとのことであった)。顕微鏡は保守管理がきちんとなされていた。ここで行われる手術は簡単な外来小外科(創の縫合など)と白内障程度とのことであり、外来小外科手術で手術台が汎用されているか疑問が残る。歯科治療ユニットは歯科診療には不可欠で、毎日使用されている。
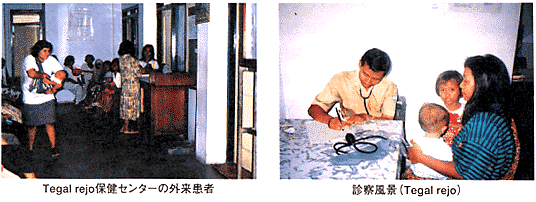
2) Nanggulan保健センター(ジョクジャカルタ特別州Kolonprogo県)
外来のみの保健センターである。SPL見返り資金を利用した備品はワクチンフリーザー、体重計1、歯科治療ユニット2、手術台2、オーディオセット(患者教育用)1、蒸気滅菌器数セットであった。ワクチンフリーザー以外は「OECF」のマークが表示されていた。体重計は壊れていた。
3) Tegal rejo保健センター(ジョクジャカルタ特別州ジョクジャカルタ市)
ジョクジャカルタ市内にあり、スタッフは所長以下66人、保健センターの保健医療プログラム18のすべてを行っている。準保健センターを2カ所を担当している。Posyanduの活動は月20~60回、遠方の地域を優先して行っている。外来患者は1日120人(母子保健活動を含む)、有床で20床のベッドがあり、入院患者は1カ月60~70人(主に分娩目的、入院期間は3日)である。
SPL見返り資金による備品は顕微鏡1、ワクチンフリーザー2、体重計1、歯科治療ユニット1、手術台(分娩台兼用)1、手術器具用テーブル1、オーディオセット(患者教育用)1、保育器1、モーターバイク1であった。ワクチンフリーザー以外は「OECF」のマークが表示されていた。ここで行われる手術は分娩をのぞき月10件程度、手術台は分娩台をかね、よく利用されているようである。体重計は壊れていた。
ジョクジャカルタ地域で調査した範囲においては、SPLで購入された備品は体重計を除き、よく保守管理されていた。しかし、保健センターの患者数や診療内容から、供給過剰と思われるものもあった。機材については一律に配布するのではなく、施設ごとに必要なものを検討する必要があるのではないだろうか(注:その後のPTSL案件では改善され、スマトラ島で実施された保健所整備事業では施設ごとに必要なものをインドネシア側がリストアップし、それを検証し供与している)。インドネシアはSPLの長所として次の点を挙げていた。1)全国を対象としたプロジェクトの展開ができる、2)少額・多様なプログラムに活用できる。
4 調査結果のまとめ
(1) 居住環境セクター、保健セクターの視察から
今回の現地調査で視察した件数は、全体から見ればまさに大海の一滴でしかない。視察した各プロジェクトは、いずれもドキュメンテーション(プロジェクトの場所の特定、土木工事の明細、資機材の明細、受益者の数等)がしっかり整えられており、海外経済協力基金から供与された円借款の見返り資金の使途が明確に把握・追跡できる状態になっていた。商品借款をSPLに転換する際に重視された「透明性」は確実に高まったものと高く評価できる。当初の目的は達成されたといえよう。
しかし、いくつかの問題点も見られる。たしかに、ジャカルタ郊外の海面よりも低い湿地帯に位置するカンポンでは道路と側溝が敷設され、プログラム実施以前の状態と比べると顕著な改善がなされた。カンポンの町並みは整然としたし、道路敷設によって自転車やバイクの行き来もスムーズになった。しかし、インドネシア側がSPL見返り資金を利用して行ったプロジェクトでは、道路および側溝のスタンダードが十分とはいえないことである。その結果、道路および側溝が破壊されていたり、あるいは十分な機能を果たしていない。プログラムの維持管理は、住民の責任においてなされることになっているが、破壊された道路、側溝、マンホールの蓋は修繕された気配がなく、住民による維持管理の形跡が見られなかった。
保健セクターでは、視察したすべての保健所で、ていねいにも手術台、歯科治療台、オートバイ、車、マイク等すべてのものに「OECF」のマークがついていた。中央政府保健省から同行した職員は、保健省の判断で行ったとのことであった。こうした資機材は海外経済協力基金のローンで購入したものではなく、海外経済協力基金の商品借款の見返り資金で購入したものである。言い換えるならば、インドネシア政府の予算で購入したものである。本来ならば、「INP18」といったマークが付けられるべき性格のものである。SPLという借款の特殊な性格が、末端の保健所のみならず、中央政府の保健省のレベルにも正確に伝わっていない。海外経済協力基金はBAPPENASを通じてプログラムを担当している各省庁に周知徹底する必要がある。そうでないと、筋違いの「要請」がでたり、畑違いの「不満」がでたりするおそれがある。
以上の諸問題はいずれもインドネシア側の組織上の問題である。SPLの評価としては、必ずしも踏み込む必要のない問題かもしれない。しかしプロジェクトの社会開発効果というレベルで考えてみると、諸設備のスタンダード、維持管理、資機材の調達等、検討すべき課題が多い。SPLの見返り資金が「社会セクター」に振り向けられたというのは事実であるが、社会開発効果という面では完璧なプログラムではないとの印象を得た。しか し、見返り資金が社会セクターに振り向けられたということは、大きな「進歩」である。
(2) SPLの問題点と将来に向けての提言
SPLは国際収支支援を目的とする緊急時の借款であったが、インドネシアの国際収支(総合収支)は改善され、1989年以来黒字基調が持続し、SPLは国際収支支援効果をあげた。また、見返り資金の使途の「透明性」は確実に増加した。SPLに対するインドネシア政府の評価はきわめて高い。とても「使いやすい」という評価である。ところがSPLにつきまとう最大の問題点もこの点にある。インドネシア政府の「開発予算の補填」として機能しているためである。
国際収支支援としての理由が薄れつつあることに対応し、ここ数年SPLはPTSLへと徐々に転換している。この方向転換は当然である。しかしひとたびSPLがPTSLになれば、単にインドネシア側に対してドキュメンテーションやモニタリングの整備条件を高めることを要求するだけでは不十分である。プロジェクトそのものの内実にはるかに深く踏み込んだ案件の監理が必要となろう。海外経済協力基金では、PTSL案件実施にあたってコンサルタント・サービスの雇用などを通じて監理能力を強化する努力をしている。しかし、今後は人員の強化等を通じて、一層の体制の強化を図る必要がある。
社会セクター案件はインドネシア全土に及んでいる。現在の海外経済協力基金の機構の枠内で、全プロジェクトの維持管理をもカバーするモニタリングは不可能に近い。インドネシア側にも十分な体制があるとは思われない。社会セクター向けの援助を強化すべきこと、また社会セクターの開発にとって「草の根」的なアプローチが有効であることはよく知られている。しかし、海外経済協力基金が扱う場合、現行の体制を前提とするならば「インドネシア全国に広がる小規模プロジェクト」を直接の対象にするのではなく、全国に広がるための「拠点」づくりのためのプロジェクトを選択するほうがはるかに効果的であるし、開発効果も発揮しやすいと思われる。「東部インドネシア開発」という大枠を考慮したうえで、社会セクターの開発拠点づくりをすすめることも一つの方向であろう。このためにはJICAとの連携を一層強化することが有効であろう。住民参加が不可欠とされる全国に広がる小規模プロジェクトを手がけることは、基本的に、内貨予算を使うインドネシアの自助努力に委ねるべきである。
全体的にいえば、SPLは商品借款よりははるかにすぐれた援助形態であるが、しかし国際収支が急速に悪化したときにのみ正当化できる「過渡的な、あるいは実験的な援助形態」である。幸い海外経済協力基金にはPTSLというプロジェクト・タイプの「セクター借款」制度もあるし、「構造調整借款」や「セクター調整借款」という政策支援型のプログラム・ローン制度もある。SPLはこのどちらか(あるいは双方)の制度に引き継がれるのが今後の望ましい選択であろうし、事実そうした方向になりつつある。
今後、インドネシアが対外債務危機に陥らないという保証はない。貿易収支と総合収支は黒字基調が持続しているが、貿易外収支が大幅な赤字のために経常収支は赤字基調が定着している。1994年のインドネシアの対外債務残高は965億ドル、債務返済比率も32.4%と危機ラインを超えている。債務問題解決のために公的資本を供給することは、引き続き必要であろう。とするならば、必要とされていることはむしろ政策支援型のプログラム・ローンを強化して実施することではなかろうか。その場合、「社会セクターへの支援」と「マクロ経済運営」との連関の道筋を明らかにすることが、喫緊の課題となろう。
(本件評価は、絵所秀紀法政大学経済学部教授、友野勝義日本水道協会主任研究員、岩井くに自治医科大学地域医療学教室助手、中畝義明世界経営協議会研究調査部課長のチームにより行なわれた。)

