第2章 援助実施体制評価
スリランカ
(現地調査期間 1997年3月29日~4月7日)
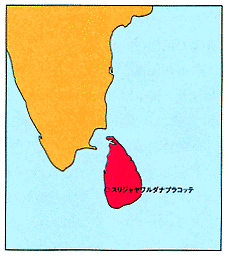
<評価調査団の構成>
■増島 俊之 中央大学総合政策学部教授(元総務庁事務次官)
■安部 忠宏 外務省経済協力局評価室長
■中野 正則 外務省アジア局南西アジア課課長補佐
■鈴木 恵子 外務省経済協力局評価室事務官
■田中 秀和 社団法人 海外コンサルティング企業協会事務局次長
■昌谷 泉 社団法人 海外コンサルティング企業協会副主任研究員
I スリランカ社会・経済の現状
1 政治
スリランカは、1948年の英国からの独立以前から複数の政党が活動する民主主義国家であり、現在にいたるまで政権交代はすべて選挙によるものである。独立以来、自由主義的色彩の強い統一国民党(UNP)と社会主義体制を指向するスリランカ自由党(SLFP)の二大政党が交互に政権党を担当していたが、1977年以降は17年間UNPによる長期政権が続いた。しかし1994年8月の総選挙において、SLFPを中心とした人民連合(PA)が勝利を納めて政権を奪取し、同年11月には党首であるチャンドリカ・バンダラナイケ・クマラトゥンガ氏が大統領に選出された。首相には大統領の母親であるシリマボ・バンダラナイケ氏が就任した。
2 経済・産業
1990年以降、内戦の継続や国際商品価格の低迷といった逆境にもかかわらず、市場経済化政策を推進した結果、比較的良好な経済パフォーマンスを達成してきたが、96年は雨不足による停電等の結果、成長率は落ち込んだ。現PA政権は、経済政策に関しては、前UNP政権同様に開放経済を堅持、外資導入を推進する方針であるが、一方で福祉を重視しており、その支出は増大する軍事支出と共に財政を圧迫し、経済運営を困難にしている。今後、民営化を始めとする構造調整をいかに進めていくかが課題である。
スリランカの産業構造は、伝統的に紅茶、ゴム、ココナツの3大プランテーション作物及び米作を主とする農業を基盤としてきたが、1980年代以降はアパレルを中心とする繊維産業が成長している。今後は繊維以外の製造業の育成、また繊維産業の中では高付加価値化と川中にあたる織布産業の育成が課題となっている。1995年現在のGDP構成は、第1次産業23%、第2次産業25%、第3次産業52%である。
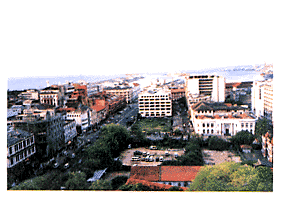
3 民族紛争
現在のスリランカ政府にとって最大の課題は、人口の4分の3を占めるシンハラ人と同じく2割弱のタミール人との間の民族紛争に根差した内戦を終結させることである。両民族の対立は1956年に当時の首相であったS.W.R.D.のバンダラナイケ氏によるシンハラ優遇政策に端を発し、その後もタミール人に不利な政策が採用される中、70年代後半からタミール分離独立運動が広がった。やがて独立運動の中心は過激派に移り、1983年に本格的な戦闘が始まる。以降現在にいたるまで多数の生命が戦闘・爆弾テロ等により失われている。政府軍による積極的攻勢を受けながらも、タミール分離独立過激派であるLTTE(タミール・イーラム解放の虎)は国の北部・東部で依然強い勢力を保ち、コロンボ周辺で爆弾テロを重ねる等、いまだ戦闘終結のメドは立っていない。96年1月にはコロンボのビジネス地区の中心に位置する中央銀行が爆破され、100人近くの死者と1,300人の負傷者が出た。
政府は軍事的攻勢をかける一方、長引く内戦の抜本的解決策として1995年8月に地方政府への権限委譲を発表したが、野党やシンハラ人仏教団体の反対でその国会審議は遅れた。ようやく1997年4月に与野党間の合意が得られたため、同年中にも憲法改正案が成立する可能性はある。しかしながら、地方政府への権限委譲の実施により北東部での戦闘や首都圏でのテロ活動が早急に沈静化する見通しは立っていない。
なお、前述のように1994年以降の戦闘・テロの激化から軍事費は年々増加しており、財政・経済運営に悪影響を与えている。また、頻発するテロにより外国投資額、観光客数は落ちこんでいる。
4 社会開発
スリランカにおける社会開発指標の高さはよく知られるところであり、同程度の所得の国の中では最も良好なパフォーマンスを示している。その理由は、英国植民地時代に築かれた教育制度が独立後も継承され、さらに社会主義的な高福祉政策が採用されてきたことにある。教育分野では、スリランカは1948年独立以来教育機関の充実に力を入れてきており、成人識字率にそれが反映されている。1963年の時点で既に識字率は76.8%であったが、1991年には男性90.2%、女性83.1%となっている。スリランカの公的教育機関においては、小学校から大学まで学費は無料である。また制服の無料支給等の補助も行われており、初等教育就学率は極めて高い。
また、保健分野の指標をみると、乳幼児死亡率は1,000人中17人と途上国の水準としてはたいへん低く、平均寿命も70歳を超える。医師一人当たりの人口は7,143人で、公的医療機関における医療費は原則的に無料である。
ただしこのような手厚い福祉政策は国の経済成長にマイナスの影響を与えたとするのが大方の見方であり、現政権は軍事費が増加し財政赤字が深刻化する中、福祉政策の見直しを迫られている。
5 開発計画
スリランカでは長期間開発計画は策定されていないが、1978年以来原則として毎年、向こう5カ年の中期的な経済開発見通しを提示したローリングプラン(Public Investment Programme:PIP)が大蔵・計画省国家計画局により発表されている。直近の計画は1996年8月に発表された第16次計画「PIP 1996-2000」である。
PIP 1996-2000では、今後5年間の経済パフォーマンスは民族紛争(内戦)解決の進捗に大きく依存するとしながら、年率6%の経済成長と国民全階層の生活水準の向上を目標としている。そのための政策として、民間資金導入によるインフラ整備(いわゆる民活インフラ)の推進、公企業の改革、税制・通関手続の簡素化による輸出促進、貧困層に対象を絞った福祉等をあげている。中でも民間セクターの役割の重要性は繰り返し強調されており、灌漑、電力、道路建設、水道供給、港湾整備などの経済インフラ分野への民間資金導入を積極的に図るとしている。現在のところこれらの分野にも公共投資(実際には多くは外国からの援助資金)を続ける必要性を認めるものの、将来的には、政府支出は教育、保健、貧困軽減、環境、科学技術、村落開発等の分野により多く振り向ける方向であることを明確に打ち出している。
6 民営化
スリランカ政府は前政権時代から民営化を推進しているが、具体的には、公益事業への民間資本の導入、製造業・商業公企業の民営化、プランテーションの民営化を意味する。
プランテーション部門では国有化後に生産コストに占める人件費の増大、世界的な需要に見合った作付転換の遅れ、高収量品種の導入などによる生産性改善努力の不足などによって競争力が次第に低下した。政府は放漫化した経営の改善と生産物の品質改善、高付加価値化などを企画して同部門を再び民営化する政策を打ち出した。製造業、小売業関係の公営企業民営化によって公営企業数は減少しており、残された公共企業についても雇用者数が削減されており最近は財政による赤字補填もほとんど行われていない。民営化が比較的順調に進展した要因としては、そもそも公営企業経営が深刻な問題とはなっていなかったことや、民営化に先だって余剰人員の削減や財政からの資本移転などを利用した経営改善努力が行われるケースがあったこと、雇用者年金基金による退職金の給付が余剰人員削減を円滑に行う上で一定の役割を果たしたことなどをあげることができる。しかしながら、労働者寄りであるSLEPが政権党になったことに伴い労働運動が活発化し、公営企業の民営化の進展にブレーキがかかっているのも事実である。
II スリランカにおける援助実施体制の現状と問題点
1 実施体制と開発案件の採択
1)スリランカ政府の組織
スリランカの行政組織は大統領、首相のもと、19の省から構成されており(1997年4月1日現在)、このうち4省(大蔵計画、計画実施、国防、仏教振興)の大臣は大統領が兼任している。国の開発計画と予想配分の決定は大蔵計画省が担当しており、実施事業の評価を計画実施省が担当している。大蔵計画省のなかで開発援助事業の決定に直接関与する部局が国家計画局(National Planning Department, NPD)と外国援助局(External Resources Department, ERD)である。NPDは国家開発計画である「公共投資5カ年計画」(Public Investment Programme)の策定を担当し、各地方および各省からあがってくる案件の優先順位を決定し、一方ERDは外国からの資金および技術援助がどの案件に適用可能かにつき各国援助機関との調整を担当している。
今回、現地調査の一環として行ったスリランカ政府との意見交換と実態の聴取は大蔵計画省内で上記NPDおよびERDの幹部が中心となって対応し、各実施機関との会合もERDの局長が座長となって各機関からの代表者が順次登場するという方式で行われたことから、大蔵計画省が各省に対する統率力と調整力を持っていることを窺い知ることが出来た。また、本調査団があらかじめ送付しておいた質問票に対しても大蔵計画省(主としたERD)は10ページにわたる解答書を準備し、適切かつ率直な回答内容が書面で提示されたことも先方の対外的な対応能力のレベルを示すものであった。NPDは局長、2名の次長のもと、7部からなり、ERDは次長1名、5部から構成されている。

開発事業の実施はセクター別の各省および省の下に事業体として設置されている庁または公社によって担当されている。今回の調査で会合・訪問の機会をもったのは、灌漑・電力・エネルギー省、農業・土地・森林省、保健・道路・社会福祉省、教育・高等教育省、住宅・建設公共事業省、工業開発省、船舶・港湾・復興再建省、漁業水資源省の8省および電力公社、マハヴェリ開発公社、スリランカ港湾局の3事業体であった。
2)援助案件の採択
国の開発計画としては「公共投資5カ年計画」がNPDによって毎年9月に発売され、これに沿った案件であることが援助対象の条件となっている。各省の要望案件は所定のフォームによりNPDに提出され、NPDでのスクリーニングにかけられる。フォームは3ページ程のもので案件の目的、必要性、費用、環境影響、予想される効果、完成後の管理運営について記すようになっている。これによって開発案件の詳細な調査に入る前に適・不適が選別される。この段階で環境面からのスクリーニングも行われている。
NPDにおいて優先順位がつけられた案件リストは、閣議(Cabinet of Ministers)の了承を必要とする。さらに外国援助案件についてはERDにおいて援助機関と非公式の調整を行いながら援助案件リストを作成し、閣議において最終決定が行われている。したがってNPDと閣議が案件採択の決定を行っているといえる。
3)分野別優先順位
1年の経協総合調査団派遣時の政策対話では5分野が確認され、その後環境分野が加わったが、今回の調査団への回答によると国として11の重点分野があり、そのうち特に日本ODAに対して、円借款へ8分野、無償・技術協力へ5分野を期待分野としている。これらの期待分野のうちで新しい分野は民間セクター開発と地域社会開発である(付属資料27参照)。なお、開発案件のプライオリティーは、セクター毎のマスタープランが拠り所となるが、必ずしも各省がマスタープランを持っている訳ではない。この点ではJICAによるマスタープラン調査およびF/S調査が役に立っている。
上述のように案件採択での閣議の了解は案件のプライオリティー付けと外国援助対象の二つの段階で必要とされている。現在、与野党の勢力が拮抗した状態にあることから、政治的なコンセンサスが行政での決定にも要求されていると見受けられる。
4)援助案件の維持管理
開発案件の維持管理費用については各省でリカレント・コストを準備することを義務づけており、予算措置がはかられている。また、大蔵計画省は各省庁に対して必要な人材、設備、機材の確保を徹底するよう指導している。しかし、現実には厳しい財政事情のなか必ずしも十分な維持管理予算の確保が困難であり、最近の傾向としては公共事業体に財政的な自立(独立採算化)を促す方向にある。日本の技術協力案件である鋳造技術向上センターにおいても独立採算制に移行することになっており、ODAで供与した設備を活用して研修、試作などの技術指導を有償のサービスとして現地産業界に対して提供していくこととなる。
5)援助評価結果のフィードバック
これまでスリランカ政府自身による開発案件の評価は行われていなかったことから、ADBの協力により、計画実施省に“Evaluation Unit”を設置し、プロジェクトのインパクト評価を開始した。今のところスタッフは2、3名でリーダーは担当総局長(Director General)であり、評価結果の関係各部局へのフィードバックまでは行われていない。今後は、ADB等外国からの技術協力を活用し、スリランカ政府内での案件の自己評価能力を高めるとともに、案件の発掘、形成と採択に評価結果を反映していくことが必要となろう。
2 実施上の問題点
1)案件実施の遅れ
政権交代後、しばしば発生した案件実施の遅れは、主に調達手続きの遅れによるものである。政府発注事業に対して汚職を防止するために、より透明性の高いシステムをとり、政府内での決定ではなく閣議了承を必要とするようになったことが調達手続きの遅延の要因である。
5,000万ルビー(約1億円)以上のすべての調達契約には、閣議の了承が必要となったため、閣議に諮る案件数が多くなり、時間がかかるようになった。また、閣議での議論の結果、再入札に至った案件もあり、これらによっても遅れが発生した。その後、ADBの技術援助によって調達ガイドラインが改訂され、閣議に諮る最低額は、外国援助案件については1億ルピー(約2億円)以上となった。しかしながら、これにより調達手続きの遅れが抜本的に改善されたとはいい難く、この問題は依然として日本の援助案件のみならず、世界銀行はじめ他の援助機関においても問題となっている。
2)計画の変更
当初計画どおりに進められなくなった日本のODA案件として次の3件である。これらの背景はいずれもスリランカ側の事情によるもので、1件は住民問題により、また2件については政府の方針変更によるものであった。
1 コロンボ-カトゥナヤケ高速道路
建設予定用地に住民が移り住んできたため土地収用が困難になり、当初計画ルートでの建設が困難となった。代替ルートを検討中。円借款のエンジニアリング・ローンで詳細設計まで完了していた。
2 工業団地開発計画
円借款対象とする2カ所の候補地のうち1カ所(カタノ工業団地)について、空港の拡張用地とするため、工業団地の建設は行わないこととなった。現在、工業開発省が代替地を検討中。
3 コロンボ港北側埠頭開発計画(II)
計画の一部(コロンボ港クィーンエリザベス埠頭開発)について、民間資金による開発を行う方針で検討中。JICAによりマスタープランが作成され、一部円借款による設計が行われていた。
3)民活インフラの推進
スリランカ政府は、民間資金によるインフラ開発(民活インフラ)を推進する方針である。しかし、民活の方針については、日本の援助機関との意見調整もまだ充分でない状況にある。また、世界銀行、米国のUSAIDなどがイニシアティブをとり推進しようとしているが、スリランカ政府機関などでの受け入れ準備は充分に整っていないという問題もある。
例えば、コロンボ港については、1970年代の終わりから、日本がJICAとOECFとの連携により開発を進め、コンテナ中継港としての発展を継続的に支援してきた。日本からはこれまでに830億円もの借款資金が供与されてきた。このような経緯を背景に、1996年9月にはJICAの「新コロンボ港開発計画調査」により、今後の拡張計画が提案されたが、このJICA調査の実施中、民活によるクィーンエリザベス埠頭コンテナ・ヤードの開発案がスリランカ政府により発表された。現在、オーストラリアの船会社P&Oとの間で話が進められているが、内容については公表されていない。このため、今後、同港については、従来のJICAのF/Sに続いて円借款により建設を行うという従来のやり方とは異なる方式により、開発が進められる可能性がある。
また、電力分野でも民活による火力発電案件が進められている。民活により建設された発電所からの電力は、電力庁が買い取り配電することとなる。しかし、電力庁では、民間発電業者からの買い取りコストは高いので採算を取るのが難しいという問題を抱えている。
4)社会セクターと紛争問題
スリランカは社会主義的考え方から、一貫して会社セクターと農村開発への配分を重視して来ている。都市と産業インフラ開発を重視してきたASEAN諸国に比べると、大都市への集中度は低い。マハヴェリの農村開発ではこれまで55万人の土地なし農民を入植させ、92%の人々が定着しており、都市への人口流入とスラム化の抑制に効果をあげていると言われている。しかし国内での比較では、コロンボ周辺に比べ地域格差の大きい北部と南部の開発努力が依然として必要である。また、教育と医療は無料という社会主義的な福祉政策をとって来ていることが、社会サービスへ対価を払う考えの定着を阻んでおり、今後の医療や教育の質の向上を図っていくうえでの障害となっているとも言われている。
スリランカの発展にとって大きな足枷となっているのが北部の民族紛争問題である。政府の軍事支出が国家予算の約18%となっており、財政支出のみならず人的損失や治安問題から外国投資の不振などへも波及している。
なお、UNICEFは“Emergency”地域である紛争地域への協力へ、事業のほぼ3分の2を振り向けており、英国はじめ他の援助国も緊急支援を行っている。日本は、無償資金協力により、紛争地域に対し、住宅建設のための屋根材など資機材供与を行っている。
III 日本の対スリランカODA実施の現状と問題点
1 対スリランカODA実施体制
1)援助の基本方針
日本はスリランカに対し、積極的に経済協力を行っているが、その理由は、1.我が国と伝統的に友好関係にあること、2.独立以来選挙による政権運営を行っている民主国家であること、3.構造調整を実施し経済改革のための自助努力を行っていること、等である。実際、スリランカは日本のODA重点供与国であり、1995年までの支出純額累計で我が国2国間ODAの第11位の受け取り国である。またスリランカ側にとって、日本は1986年以降最大の援助供与国となっており、DAC統計によれば1995年のDAC諸国援助額(ネット)合計のうち日本の占める割合は71%に達する。
また、我が国援助の重点分野は1.経済基盤の整備・改善、2.鉱工業開発、3.農林水産業開発、4.人的資源開発、5.保健・医療体制の改善、の5分野である。さらに近年環境分野を重視している。
ここ数年の実際の援助プロジェクトを上記の援助重点分野に照らし合わせて見ると、ほぼこの重点分野に沿った形になっていることがわかる(付属資料3参照)。しかしながら、第2章3)で述べたように、今回の現地調査の過程でスリランカ側からは日本の援助を期待する重点分野として、経済インフラ建設などの従来の重点分野のほか、民間セクター開発や地域社会開発などの新しい分野が示されており、対話を重ねた上でより絞り込んだ重点分野の検討、選定が必要となっている。
2)現地における援助実施体制
1 援助関連公的機関
現地における日本関係機関は在スリランカ日本大使館、国際協力事業団スリランカ事務所、海外経済協力基金コロンボ事務所の3機関である。このうち、JICAは技術協力の実施業務と草の根無償以外の無償資金協力の実施促進業務注1、OECFは有償資金協力の実施業務を担当する。また、3機関とも、スリランカと共にモルディブ共和国をその管轄としている。
(イ)日本大使館
館員3名から成る経済協力班が経済協力全般の任務に当たっているほか、経済班の館員1名も必要に応じ適宜経済協力に関する業務に携わっている。大使館の業務は、新規要請案件の適否及び重要度の検討が中心業務であり、JICA、OECFと協力しつつ業務を行っている。
注1:草の根無償のほか、JICAが実施促進業務を担当していない無償資金協力には文化無償がある。ただし、文化無償は本件評価調査の対象外であるため、本報告書で無償資金協力という場合には文化無償は含まれていない。
(ロ)JICA
技術協力及び無償資金協力のうち一般無償(草の根無償を除く)、水産無償の基本設計及び実施促進、食糧援助、食糧増産援助の実施促進を行っている注2。人員構成は日本人スタッフ10名(JICA本部からの派遣職員6名、契約調整員4名)とローカルスタッフ25名(専門高級クラーク、安全対策専門クラーク、秘書等)の計35名である。
(ハ)OECF
有償資金協力の業務実施を担当している。日本人スタッフは2名、ローカルスタッフは8名、うち借款業務に携わる高級クラークは2名である。
2 ODA広報
援助案件の起工式・完成式などの式典は、地元のテレビや新聞などのマスメディアによって頻繁に報道されており(付属資料7参照)、日本のODAはスリランカ一般国民に広く知られているといえる。
また、日本側も積極的に日本のODAを広報するために、次のような方策をとっている。
(イ)地元報道機関関係者に実際に援助の現場を見てもらう「経済協力プレスツアー」を大使館が中心となり、JICA、OECFの協力を得て実施する。
(ロ)交換公文締結時等に関係機関へプレスリリースを送付する。
(ハ)供与建物、機材に日本のODAであることを示すシンボルマークを付す。
(ニ)JICA、OECFが広報用パンフレット(各機関の活動や援助案件を紹介したもの)を作成し、配布する。
一方、スリランカには班政府過激派組織によるテロ活動が頻発するという事情がある。このため、反政府組織への不要な刺激を避け、日本人の安全を確保するという配慮から、特に技術協力においては現在のところ広報を積極的には行わないという方針がとられている。具体的には、JICAの公用車からロゴマークをはずす、JICAが定期発行するニューズレターの配布先を限定する等により、日本人が「あまり目立たない」ようにしている。
3 他機関との連携
日本の各機関間の連携については、事務レベルで上記3機関による月1回の定期連絡会が開催され、情報交換、意見交換、業務日程の調整などが行われている。また、所長レベルでは、JETRO所長を含め、2カ月に1回程度の頻度で所長会議が開催されている。また、必要に応じた意見交換、情報交換は日常的に頻繁に行われている。
また、日本援助機関と他ドナー機関・国との連携については表3-1のような定期的会合が行われているほか、必要に応じ現地スタッフやミッションの相互訪問等により情報交換や援助協調(OECFと世界銀行による協調融資など)の促進等が行われている。
注2:但し、実際には実施されていない援助形態もあり、現在の対スリランカ無償資金協力実施状況に即して言えば、JICAは一般プロジェクト無償、水産無償の基本設計及び実施促進、食糧増産援助の実施促進を行っている。
| 会合名 | 開催頻度 | 参加機関(日本) | 参加機関(日本以外) |
|
Doner Officer's Lunch UNDP |
隔月 | 大使館、JICA、OECF | UNDP、Worlld Bank、WHO、UNICEF、UNFPA、UNHCR、WFP、ILO 、Colombo plan、EU、カナダ、ノルウェー、イタリア、英国、USAID(米国)、他 |
| Progress Review Meeting of Integrated Rural Development Programme | 3か月に1回 | JICA | オランダ、ノルウェー、GTZ(ドイツ) |
| ボランティア団体会議 | 四半期に一度 | JICA | APC(米国)、VSO(英国)、KOV(韓国) |
2 無償資金協力
1)援助実績
無償資金協力は1969年に開始され、医療、教育・人材開発、環境、農業分野を中心に幅広い協力を行っている(付属資料3参照)。また、食料増産援助がほぼ毎年供与されている。
協力額は1969年度から1995年度までの累計で1,340億円にのぼる。
2)実施体制
無償協力案件(草の根無償を除く)は大使館JICAが協力して実施している。
一方、草の根無償は大使館が実施している。草の根無償案件の要請は年間100 件以上あり、この中から年間6~15件が採択されている。大使館における担当者は1名である。
なお、現在、無償資金協力及び技術協力においてはスリランカは年次協議の対象国ではなく、平成9年1月に派遣された政策協議ミッションは約2年半ぶりのものである。スリランカ側からは、毎年協議ミッションを派遣してほしいとの要望があった(第4章参照)。
3)実施のプロセス
プロジェクトサイクルごとに実施業務の概略を記すと次のようになる。
まず案件形成の段階で、スリランカ側(主に実施機関)より非公式に、要請を予定している案件が協力可能な案件であるか否か、大使館及びJICAに対し打診があることが多い。また一方で、JICA現地事務所はスリランカ側に対し協力案件の要望調査を実施し、大使館と協議を経て取りまとめ、JICA本部に送付する。
スリランカ側の各実施省庁は、大使館及びJICAからの意見を考慮に入れたうえで大蔵省計画局へ要請案件を提出する。大蔵省計画局がそれら各省庁からの案件を取りまとめ、大使館に対し優先順位を賦した案件リストを提出する。大使館及びJICA現地事務所はその各案件を確認し、適宜必要な事項に関し現地調査等により追加情報を収集し、外務省及びJICA本部に、現地での案件検討(案件概要)が提出される。
その後、外務省、JICA、日本側関係省庁の討議を経て、実施可能性の高い案件についての調査団が形成される。調査団は、その必要性に応じ事前調査団、基本設計調査団、詳細設計調査団等があり、関連機関の代表及び民間のコンサルタントにより形成される(JICA現地事務所も必要に応じ参加)。同調査団により、案件実施の可能性、当国関係機関での取組み、現場での事情等様々な事項が調査・確認され、案件実施前に十分な協議が持たれる。
案件実施(施工)の段階においては、コンサルタントが月例報告(または進捗状況の報告)を大使館及びJICAに対し行い、JICA現地事務所は、必要に応じサイト視察を行う。案件終了時に終了時評価が行われる場合には、JICA本部から調査団が派遣されたり(JICA現地事務所職員も参加)、または、現地事務所が単独で調査を行う。さらに終了後一定期間を経た時点で、案件の現状や効果等を確認するための調査が外務省(事後評価)やJICA(事後評価、事後現況評価等)により実施される。
4)評価
今回の調査においてスリランカ側からは、無償資金協力に固有の問題点の指摘や要望事項は特になかった。スリランカ側の、日本の無償資金協力に対する評価は高く、特に協力の現場(無償機材、設備が設置された場所)においては、例外なく日本に対する謝意が表明された。実際、ほとんどすべての機材が有効に利用されており、その効果は大きいものと認識された。
しかしながら、参考として、次の点を指摘しておきたい。
第一に、草の根無償においては、多数の案件を大使館の担当者が1名で扱っているため、詳細にわたって審査、モニタリング、評価を行うのはきわめて困難である。
第二に、「過去に問題点が指摘されて案件」の1つとして今回の調査対象としたキリンダ漁港建設プロジェクト(付属資料5参照)は、事前の調査としてJICAによる事前調査を実施した後に基本設計調査を実施し、さらに帰国後の国内解析を行う等、事前調査開始以降半年以上の期間をかけて、可能な限り調査活動を実施した。漂砂に関しては、利用可能な現地研究所等の既存の波浪観測データ及び底質調査結果等をもとに、砂の移動等に関する可能な限りの解析・検討をおこなったところであるが、モンスーンの影響により予想を上回る漂砂現象が発生した。今回の調査では、スリランカ側からは「現地調査に充てた期間が十分でなかったのではないか」との見解も示されたが、現在は、すでに再度の無償資金援助による漂砂対策が終了し(キリンダ漁港改修計画)、スリランカ側により適切に維持管理されているため、本案件に関する問題点は解決ずみである。
第三に、JICA現地事務所より報告された問題点としては、プロジェクトの形成等の前向きな作業に比べ、終了案件の評価には手が届きにくい傾向があるということがある。JICAでは評価活動とプロジェクトサイクルにおける重要な過程の一つとして捉え、その強化に努めている。しかし、現在のところ、事務所スタッフの数が必ずしも十分でないこと等により、終了したプロジェクト全てについて事後評価を実施できる状況にはなっていない。プロジェクトサイクルにおける評価活動の果たす役割は重要であり、今後一層、強化・充実していくことが望まれる。

3 技術協力
1)援助実績
技術協力は1954年に開始され、95年度までの累計額は292億円である。技術協力は、i)プロジェクト方式技術協力、ii)専門家派遣、iii)研修員受入、iv)青年海外協力隊派遣、v)単独機材供与、vi)開発調査等の各形態に分類される。
プロジェクト方式技術協力はこれまで大部分が農業水産、保健医療であったが、1995年以降に工業分野のプロジェクトが2件開始された(付属資料3参照)。専門家派遣は、農業水産と保健医療が中心になっている。研修員受入については、人的資源、保健医療、工業分野が増加しているのが最近の傾向である。協力隊派遣は、農業関連分野を中心に、教育、保健、鉱工業などが多い。
2)実施体制
技術協力の実施機関はJICAである。JICAスリランカ事務所の資料等に基づき、各形態別の案件監理、評価体制につき述べる。
1 プロジェクト方式技術協力
JICA現地事務所が、実施中案件については四半期ごとに提出される業務報告書によりモニタリングを行うとともに、必要に応じて事務所スタッフが、協力実施機関やプロジェクトサイトを訪問し、協議を実施している。本部からは計画、実施の各段階で調査団(計画打合せ調査団、巡回指導調査団等、)が派遣される。
終了時には本部派遣ミッションによる案件別終了時派遣評価が実施される。また、終了一定期間経過後、案件監理の一環として案件の現状を確認し、アフターケア協力の要否を判断することを目的として、本部よりアフターケア調査団が派遣される。事務所による事後評価が実施される場合もある。
2 専門家派遣
JICA現地事務所が、専門家の活動につき、派遣期間中においては、専門家から定期的に提出される業務報告によりモニタリングを行い、また終了時においては総合報告書により評価を行う。必要に応じ事務所から配属先を訪問し協議を行う。本部より巡回指導調査団が派遣されることもある。
3 研修員受入
一般の研修は日本国内で行われるので、事業監理、終了時評価ともにJICA本部が行う。帰国後研修員のフォローアップ調査が行われる場合は、本部より調査団が派遣され、現地事務所からも参加する。第3国研修の場合は研修場所がスリランカの政府機関となるので、現地事務所が適宜進捗を確認し、終了時には本部派遣、または事務所による評価を行う。一定期間の後、事後評価が行われる場合もあるが、これも本部派遣によるものと事務所によるものがある。
4 開発調査
開発調査では、JICAと契約したコンサルタントによって構成される調査団が実際の調査業務を行うが、JICA現地事務所は調査団から毎月提出される業務報告により、調査活動のモニタリングを行うほか、必要に応じ調査団やスリランカ側関係機関と協議する。開発調査の最終成果物は調査報告書であるが、その評価は、主としたJICA本部が行う。

3)実施のプロセス
技術協力の実施プロセスは、各形態により手続きの細部や要請から実施にいたるまでの標準的な期間は異なるが、在外公館が相手国政府からの要請書を受けることに始まり、JICA及び外務省による審査を経て実施にいたる点は共通である。終了時には終了時評価(JICA)が、終了後一定期間を経た後には事後評価(外務省、JICA)が行われる。付属資料2にプロジェクト方式技術協力、専門家派遣、研修員受入、青年海外協力隊派遣のしくみを示した。
4)評価
スリランカ側は、日本の技術協力を高く評価している。とりわけ日本人専門家と青年海外協力隊員については、現地事情によく適応して業務の効率を高めており、またモラルも高いと一様に評価されている。
今回の調査においてはプロジェクト方式技術協力案件1件、複数の青年海外協力隊員が参加するプロジェクト1件を現地訪問したほか、JICA専門家、青年海外協力隊員との会合をそれぞれ設定し、技術協力の現状や問題点について聴取した。
聴取の結果、日本側の実施体制に起因する特筆すべき問題点の指摘はなかったが、以下のような意見・要望が示された。
まず、スリランカ側のキーパーソンに研修を受けさせることはきわめて効果的であり、そのための受入枠をさらに増やすべきとの要望が複数の専門家から出された。また、プロジェクトを実施する際、他国援助機関や国際機関では現職の政府高官を好待遇でプロジェクト・リーダーとしてリクルートすることにより、事業の推進に効果をあげているケースもあるので、日本もこのような方法を検討してもよいのではないか、との意見が出された。
4 有償資金協力
1)援助実績
有償資金協力(円借款)については、1965年に援助を開始して以来、1970年代後半までは国際収支支援のための商品借款を供与してきたが、その後、運輸、電力、通信、灌漑等の経済インフラ整備のためのプロジェクト借款が中心となっている。1990年代に入ってからは構造調整借款、さらに近年では環境案件も対象に加わっている(付属資料3参照)。
1996年度までの供与累計額は4,270億円(交換公文締結ベース)である。
2)実施体制
本章第1節で述べたように、現地においては、OECFコロンボ事務所の日本人スタッフ2名と高級ローカルスタッフ2名で年間約350億円(承諾額ベースでは1996年度384億円、1997年度359億円)にのぼる円借款を扱っており、人員不足の感は否めず、実際に現地スタッフからも「人員不足のため一人当たりの仕事量が過大になり、実施中案件の監理(契約承認、入札評価等)に手いっぱいで新規案件の検討や報告書の精査などにあまり時間をとることができない」との声が出ている。もっとも、一人当たりの扱い高は他国OECF事務所に比較して特に大きいわけではなく、この問題はスリランカに限らずOECF全体に共通の問題といえる。
実施中の借款案件のモニタリングは現地事務所によって行われている。実施後の案件については、外務省やOECF本部(詳細評価(外部専門家を含むミッションを現地に派遣して調査する)と机上評価、現地事務所)により事後評価が行われる。さらに事後評価とは別に、事後監理の一環として、OECF本部により、完成より3年後と7年後の時点での事業運営維持管理状況等について調査が行われている。
3)実施のプロセス
有償資金協力実施のプロセスは以下のようなものである。
相手国側から円借款の要請が提出されると、関係四省庁(経済企画庁、外務省、大蔵省、通産省)とOECFによって検討される。この段階で日本政府は必要に応じ調査団を派遣し、相手国政府と協議する。OECFはその結果をふまえて審査チームを現地に派遣し、その審査結果を受けて日本政府は再度要請プロジェクトを検討し、借款供与額、条件等を決定する。日本政府はこの決定を相手国政府に伝え、両政府間で交換公文(E/N)を締結する。これを受けてOECFは借入国側との間で借款契約(L/A)を締結し、プロジェクトが実施に移される。完成したプロジェクトは外務省やOECFにより評価される。
付属資料2に典型的なプロジェクト型借款実施のフローを示した。

4)評価
今回の調査過程において、スリランカ側より、有償資金協力による経済・社会インフラの建設によって、スリランカ国民全体が多大な利益を受けていることが表明された。
一方、以下のような問題点と要望があげられた。
1 円借款の貸出金利が世界銀行(IDA)やアジア開発銀行に比較して高い。
2 趨勢的な円レートの上昇により、ドル建て返済額が大きく膨らんでいる。
3 日本のコンサルタントの報酬が割高である。有償プロジェクトにおいてもコンサルタントの雇用部分は無償にしてほしい。
4 世界銀行やアジア開発銀行のように、複数年のカントリー・プログラムを作成し、それを毎年見直すというシステムを導入してほしい。現状では案件ごとに短期ミッションが訪問し関係機関と協議、ミニッツの締結をするため十分な検討時間かとれない。
5 日本政府援助実施機関(OECF、JICA)の現地事務所、また派遣されるミッションの裁量権限が小さいためか、本部に指示を仰ぐことが多く、援助実施決定までに要す時間が長い。
上記1については、円借款が商業レートに比較すれば非常に低利であることを考えれば特に検討するまでもなく、スリランカ側も深刻な問題とは考えていない。
2については、円借款全体の問題であり、事実他の受取国からも円の増価により返済負担が重くなってる点については再三救済措置を求められている。
3についてもは、スリランカ以外の国からもしばしば指摘される問題である。まず技術的に有償案件にうちコンサルティング部分を無償にすることが可能であるかどうか検討することが必要である。
4と5は有償、無償に共通の問題である。現地事務所への権限委譲については、現実施体制では不可能に近く、委譲を進めるためには人員配置計画から見直す必要がでてくる。ちなみに他の援助供与国では、大幅に本国から権限委譲がされている例もあり。英国ODAはバンコク地域事務所の権限が強く、対スリランカ援助政策の多くがそこで決定される。また米国USAIDはコロンボ事務所に多くのスタッフを配置し、事務所長の権限は非常に大きい。
なお、今回視察した有償協力案件のうち、日本のマスコミ等に取り上げられ批判の対象となった「サマナラウェア水力発電ダム」の漏水問題(案件概要は付属資料5参照)については、スリランカ側は自国の問題であることを明確に認識している。国際専門家パネルによる勧告を受けて採用されたウェットブランケット方式注3による漏水対策工事が、有償資金協力により近く開始される予定である。
注3:漏水の発生している部分に土砂を集中投下することにより、漏水を停止する改修工法。
同ダム建設の資金提供(英国との協調融資)、建設工事と施工監理を担当した日本としては、今後とも安全性を厳しくチェックしていく必要があると考えられる。
IV 実施上の問題点の改善策
今回の対スリランカ援助実施体制評価の全体的評価としては、実施上の大きな問題はなく、日本のODAが期待された効果を発現していると結論づけられる。しかし、援助の効率性と効果に関係する、いくつかの問題点を指摘することができる。これらは実施体制上の深刻な問題点とは言えないが、対応策を検討し改善することによって、より適正かつ効果的・効率的な援助を実施するための参考となるよう、以下に示した。
1 スリランカ側の実施体制に関する問題
1)開発計画内容の明確化と具体化
スリランカ政府は公共投資5カ年計画(PIP)によって、国全体の開発目標を示している。PIPは毎年改訂され、今後5年間の開発目標、開発投資額と外国援助の割合がセクター毎に示されているが、各セクター内の個別開発案件とその優先順位までは示されていない。一般的には、国家開発計画に準じてセクター毎の開発マスタープランが策定され、マスタープランの中で個別案件が確認され、その優先順位が示されることにより、個別案件の開発における位置づけが明確にされる。しかし、スリランカの場合は各省でのマスタープランの策定は概して不十分であり、分野によっては、関係省庁がマスタープランの策定自体をJICAはじめ外国の技術協力に委ねている場合もある。
開発の主体はあくまで被援助国側である。したがってスリランカ政府としては、公共投資5カ年計画など開発の基本になる政策の中に、個別開発案件の優先順位、開発達成スケジュールなどを明示し、援助国側に対し、援助要請の内容とその背景およびそのための被援助国側での具体的措置等を、明らかにすることが必要である。
2)援助案件実施の遅れ
実施の遅れの主因として、関係者は、スリランカ側の調達手続きを指摘する。前政権の体制では実施機関あるいは担当省が決定権をもち、調達は遅滞なく行われていたようであるが、決定過程の不透明性が問題とされていた。そこで現政権は、調達にからむ汚職を防止し、公正をはかるため技術審査委員会(TEC)および次官クラスで構成するCATB(Cabinet Appointed Tender Board)を設置し審査を行うとともに、また一定以上の金額の契約については閣議の了承を必要とすることとした。このような厳格な手続きの結果、審査段階で調達手続き上の問題が指摘され、入札のやり直しに至ったり、閣議了承による契約に変更が生じ、改めて閣議了承が必要となったりすることなどにより、実施が大幅に遅延するケースも生じている。また、遅延をもたらす他の要因としては土地収用の不手際(住民問題)も指摘されている。高速道路の当初予定ルートを断念せざるを得なくなった案件もある。
これらの問題は日本のODAの中では、とりわけ円借款案件に顕著であるが、同様の問題は世界銀行、ADBの案件においても生じており、実施が何年も遅れたという深刻なケースも発生している。このような背景からADBが技術協力により、入札制度の改善にのり出しており、世銀、OECFもこれに協力している。
スリランカ国内の政治および行政システムに起因するこの問題は、外国側から介入しにくい点を含んではいるものの、ドナー間の連絡と協調により不合理な事情による遅延に対し注意を喚起することができると考えられる。特にトップ・ドナーである日本が、業務の効率的実施、あるいは資金の効率的活用という観点から改善を促すことは効果的である。これに加え、日本が中心となって他のドナーと協調することができれば、更に一層、効果的な改善が期待される。
3)中間管理職の育成
プロジェクト方式技術協力などの案件で、協力期間が終了し日本人専門家がいなくなると活動が低下するという問題が、日本大使館関係者から指摘された。その大きな要因の一つとして、カウンターパートが離れるという問題がある。スリランカだけで発生している問題ではないが、カウンターパート・スタッフが日本で研修を受け技術を習得することにより、かえってその組織から離れてしまうことが懸念されている。
なお、日本への受入研修においても、スリランカからの研修員が日本国内で行方不明になる事件が多く発生している。日本国内での不法就労が目的と考えられているが、スリランカ国内におけるキャリアへのインセンティブの不足の現けともみられる。
この問題(ブレイン・ドレイン)は、スリランカの官庁組織の制度のなかで、年功序列的昇進制度が有能な技術者の昇進を阻み、かえって人材の有効利用という観点からはマイナス効果をもらたしていることとも関連している。この点について、世界銀行現地事務所では民営化による組織の合理化と人的資源開発の必要性を指摘している。
一般にスリランカは教育レベルが高いと認識されているが、高い識字率にもかかわらず、生産的、知的労働力としての教育訓練は十分でない。一方、富裕層の家庭では子弟を米国、英国、オーストラリアなどへ海外留学させているが、それら子弟がそのまま海外にとどまることも多く、国の開発や発展に貢献し得る人材が有効に活用されないという深刻な問題も抱えている。
スリランカの政府組織において、若く有能なスタッフの能力がより発揮されるような制度を検討するとともに、今後の日本のODAにおいても人材育成の支援に力を入れ、協力終了案件の自立発展性を確保するため工夫を行うことも必要であろう。
4)援助機材の通関手続きの簡素化
技術協力に伴う無償供与機材がコロンボ港に置かれたまま、通関に2ケ月かかったというケースが鋳造技術向上センター(プロ技)で発生している。政府間の合意により、援助機材への関税はかからないことになっている。しかし、スリランカの制度では、実施機関である工業開発委員会(IDB)が、機材の輸入関税相当分の金額を実施機関側のカウンターパート予算として計上し、形式上支払っている。このための手続きに時間がかかり、機材のサイトへの到着が遅れ、既に赴任している専門家の技術協力業務の開始に影響を及ぼした。
同様に、無償機材の輸入手続きの遅れの問題は、ペラデニア大学歯学部整備計画(無償案件)でも、工業規格の準拠証明、関税手続きが原因となって発生している。このような問題は既存のスリランカの機材輸入制度のなかでは今後も発生し得る問題と考えられる。大蔵計画省による制度改善などの検討が必要である。
2 日本側の実施体制に関する問題
1)開発の新しいテーマへの取り組みの強化
スリランカ経済の発展に伴い、援助のニーズに変化が生じてきており、これに適切に対応することが必要である。新たなテーマとしては、民活導入、環境保全、貧困対策、地域開発などがスリランカ側から示されている。真にニーズに適ったプロジェクト形成されるようにするため、援助供与国側である日本としても必要な場合には適切な援助を行えるよう更に努力していくことが必要である。
また、スリランカにおいては通信、電力、水道などの分野で民営化が進められているが、援助機関によって民営化推進への意見が多少異なる。世界銀行、米国(USAID)は民営化を推進する立場をとっており、例えば電力セクターについては既存の電力公社(CEB)の効率を問題視しており、外国の民間資本の参入によって一部の発電事業を民営化するべきとの主張をしている。一方、日本側は政府の役割についての十分な検討を行うことなく一律的に民営化あるいはインフラ開発への民間資本の参入を進めることに対しては慎重な立場をとっている。この問題については日本側の考え方をまとめ、世界銀行、米国など他の援助機関と意見を調整し、スリランカの開発に取り組む上での共通認識を深め、より効果の高い援助の実施を期す必要があると考えられる。
公共事業体の民営化あるいはインフラ整備への民間企業の活用は、最近アジアをはじめ各地域で実施されつつあり、インフラ開発のひとつの流れとなってきており、日本も民活インフラ事業に対する支援策として円借款および技術協力スキーム等の活用を図ろうとしている。開発の方法論と政策が絡んだこのような各国の開発援助テーマについては、より本格的な調査研究と検討が、日本の政府、援助機関、大学および民間の関係者の間で広く知見を求めて行われるべきであろう。
2)援助形態間の連携と他のドナーとの連携
JICAの開発調査から円借款への展開は電力、港湾、農業関連などの分野で実績があり、一貫して日本が援助しているという印象を与えている。また、最近の事例では、円借款による都市排水と河川の水辺環境改善案件に関連し、強制移転住民の定着地におけるコミュニティーの組織化に青年海外協力対チームが協力している。また、新規案件の採択検討にあたっては現地のJICAとOECFとの間で情報交換が行われており、案件形成段階からの調整努力がなされている。日本の援助を実施する両機関の調整強化は、スリランカ側にとって歓迎されることである。
他の援助機関との連携については、積極的に進める必要があるが、他国の技術援助で調査・設計された案件を円借款案件として採択するにあたっては、追加調査などにより、事業の中立性を含めて慎重に検討する必要がある。なお、世銀との連携でJICAで調査を行った南部の灌漑案件では、組織改革が進んでいないなどの政策的理由で世銀融資に至らないことになった件もある。
3)草の根無償協力の充実
今回の調査で視察した草の根無償案件である排水対策では、現地NGOの的確な指導により、少ないコストで貧困住民の衛生改善に役立つ事業が実施されていた。スリランカ政府もこの件をモデル・ケースとしてとりあげている。
大規模なインフラ案件に比較し、草の根無償援助は、非常に小規模であるが、迅速かつ直接的に被援助国側国民に裨益する効果を持つものであり、その費用対効果は極めて高いと思われ、今後その充実が期待される。しかし、一方では、現地のNGOをはじめとする実施主体組織に関する情報と現地事情など申請案件審査の拠り所となる情報の収集、そして実施状況の把握と実施後の評価など、援助金額に比べ煩雑で手間のかかる事業でもある。日本大使館では一名の担当者が他の日常業務との兼任でこの任にあたっており、今後草の根無償の拡大を図るのであれば、現地の実施・フォローアップ体制について検討する必要がある。
おわりに-援助実施体制評価を踏まえての付言的コメント
今回のスリランカ援助実施体制評価調査の全体を通じて、日本のODAの実施状況は良好であるとの認識されたが、このことは、納税者である日本国民にはあまり良く知られていないと思われた。本調査報告のおわりに、今回の調査結果を踏まえ、いくつかのコメントを記しておきたい。
1 評価活動の重要性
ODAは国内の公共事業と異なり、国外で行われているこから、一般の国民の目に触れないというハンディーを背負っている事業である。また、受益者が、外国の人々であるということもその効果が理解されにくい原因となっている。このような点からも評価活動の重要性を指摘することができる。
また、日本のODAのこれまでの量的な拡大に対し、その質的改善の必要性が指摘されている。この観点からも、評価活動が重要性を増してきていると考えられる。
評価には、適切な評価基準の設定などによる公正さの確保とともに、評価結果の公開などが大切である。しかも、評価の内容が国民に理解しやすいことが必要である。
経済協力案件については、外務省や実施機関による評価のほか、会計検査員の実地検査や、総務庁による監査なども行われている(付属資料2参照)。これらの活動は各々の機関の視点から行われるものであるが、その調査結果が、全体としてODAの質的改善に寄与するものとなり、かつ国民の理解に役立つものとなる配慮が、常に必要と考えられる。
2 ODAデータ・ベースの構築
コンピュータによる情報の管理・集計・分類が可能になってきたため、膨大な事業となったODAについても一括して情報を集中し、いつでも引き出せるようにすることが可能である。現在の体制ではODA事業は外務省を中心に19の省庁にまたがっており、これら省庁や実施機関であるJICA、OECFが有す各データ・ベースは、統合されて初めて全体像が説明できるものである。
ODAの各案件および全体像が一カ所で即座にわかるようなデータ・ベースは的確な評価活動の実施のために不可欠である。また、これにより国会審議への対応、国民からの照会、マスコミへの対応などに関し、より的確な措置が可能となる。
3 ODA推進のための新しい視点
スリランカでの現地調査の結果は、本報告に述べたとおり、日本のスリランカの経済・社会開発に、ODAは極めて大きな役割を果たしているということである。しかし、そのことが巨額な援助を負担している日本国民には伝わりにくい。スリランカ国内における日本の援助の新聞報道は、頻繁に行われているのに対し(JICAの資料によると、1996年10月~12月の3カ月間で22件)、日本国内では、1996年中におけるスリランカのODAに関する新聞報道記事は主要3紙合計で3件(円借款2件、研修1件)、各紙ともわずか1件であり、いずれも事実を簡単に報じるにとどまっている。
日本のODAはこれまで一貫して量的拡大を続け、1991年以来日本は世界一の援助国である。1997年度予算では約1兆2千億円にのぼる税金が投入されていることを考慮に入れると、国民(納税者)の理解を促進することが何よらも必要である。しかし、一般に、特定のODA案件やODA全般の問題点については新聞、雑誌などを通じて詳しく報じられがちであることから、一般国民はODAについてネガティヴなイメージを抱きやすい。
これに関し、実行可能な具体策としては、インターネットなどのメディアも活用した日常的な広報活動の他、次のようなことが考えられる。
1)日本のマスコミを対象としたプレス・ツアーを外務省(大使館)が主催する。
2)観光で来訪する日本人に対し、ODAサイト・スタディー・ツアーを提供する。
3)スリランカの要人が日本を訪問した折に、日本のODAがもたらしている自国国民の喜びを、日本国民に対し直接伝える。
ODAは政府レベルで決定され実施されているが、受益者は相手国政府ではなく、相手国国民であり、また援助を負担しているのは、日本政府ではなく、日本国民である。このことに鑑みれば、相手国の国民が日本の援助によって受ける喜びを、日本国民が共有(シェアー)することが、ODAを推進するための本当の基盤となるものと思われる。
日本側の政府関係者のみならず、相手国政府の関係者も、そのことを常に念頭に置き、適切な配慮あるいは措置を行っていくことが必要であると思われる。

