2. エジプト
(現地調査期間1997年2月20日~3月5日)

〈団員構成〉
■石田 進 国際大学大学院国際関係学研究科教授教授
■岡松 孝男 昭和大学小児外科教授
■畑中 美樹 国際経済研究所首席研究員
■夏目 高男 外務省中近東アフリカ局中近東第1課地域調整官
■川口 哲郎 外務省経済協力局評価室首席事務官
■唐澤 拓夫 外務省経済協力局評価室事務官
はじめに
(1) エジプト国別評価の目的
本国別評価は、エジプトに対する日本の援助が、全体としてエジプトの開発や発展にどのような援助を与えているかを中心にマクロ的視点から評価を行い、その結果、得られた教訓を日本・エジプト間の各種政策対話等の場を通じて将来の日本の対エジプト援助政策に反映させることを目的として実施された。
(2) 評価の視点及び手法
本調査においては、日本の援助実績が多く、現在、日本の対エジプト援助の重点分野として位置づけられている経済インフラ、保健医療、農業の3分野を中心に、以下の手順に従って総合的な評価を行った。
1 事前調査
現地調査に先立って、以下の項目について国内において関連資料の収集・整理・分析を行った。
1)日本の援助政策・援助重点分野の変遷
2)エジプトの国歌開発計画の変遷
3)日本の開発援助実績
4)他のドナーの援助動向
2 現地調査
1)現地日本側関係者、エジプト側関係者、他のドナー関係者へのインタビュー調査
2)統計等、関連資料の収集
3)主要プロジェクトの視察

1.日本の援助の実績
(1) 日本の援助の重点分野
日本は、エジプトが、i)中東地域の大国であり、中東地域の平和と安定の維持に指導的役割を果たしていること、ii)市場指向型経済の導入に努力していること、iii)民主的議会制の運用等、民主化を進める一方、政治的安定を維持していること、iv)日本との関係が緊密であること、v)高い人口増加率、貧困問題を抱えており、援助需要が大きいことなどから、中東地域における援助の重点国の一つとして位置づけている。
日本の対エジプト援助は、1992年に2月に派遣された経済協力総合調査団等におけるエジプト側との政策対話を踏まえ、現在のところ以下の5部門を重点分野としている。
1)農業部門:食糧自給率向上のための支援として、農業生産の拡大、農産物の保管・流通面の改善
2)教育・訓練部門:経済・社会基盤の基礎となる人材の育成強化として、初等・中等教育と職業訓練を通じた人造り
3)工業部門:長期産業政策及び民間投資の促進として、経済インフラ整備、メンテナンス技術の普及等
4)医療部門:低所得層に直接碑益する地方における基礎医療の質的改善のための協力として、看護婦の養成、人口、家族計画等
5)環境・衛生部門:上下水道等の生活環境及び公衆衛生の改善
(2) 援助形態別実績
日本は、有償資金協力では、エジプトの大規模な開発需要に応えるべく、スエズ運河の拡張に対する協力をはじめとする運輸・交通分野、エネルギー分野、農業分野のほか、工業、水供給分野など、広範囲にわたり協力を行ってきた。1988年度以降については、円借款に係る延滞問題等のためプロジェクト案件が一旦途絶えているものの、湾岸危機に際しての中東周辺国に対する経済的支援の一環として1990年度及び1991年度に合計821億円の緊急商品借款を供与した。1991年7月より、パリ・クラブにおける合意を受けての実質的な債務削減のために行なっていなかった新規円借款については、1996年10月以降、その供与再開を検討している。
無償資金協力では、累次の食糧増産援助をはじめとする食糧・農業分野、保健・医療分野、水供給分野等の基礎生活分野を中心に、運輸・交通分野等幅広い分野に対して援助を実施しており、複数年にわたる比較的大規模な協力案件も多い。
技術協力では、農業、保健・医療、工業などの広範囲の分野に、プロジェクト方式技術協力、開発調査等を中心に実施している。「カイロ大学小児病院」、「カイロ大学看護学部」など、無償資金協力と連携したプロジェクト方式技術協力も見られる。また、アフリカ・中東諸国からの研修員がエジプトで研修を行う第三国研修(エジプト側による呼称は三角協力)を、看護教育、稲作、熔接技術、地震観測センター、達設機械、精米処理技術の各コースについて実施しているほか、94年度からはパレスチナ人を対象としたコースも開始されている。
1995年度までの日本の対エジプト援助の累計実績は、有償資金協力(支出純額)は19億1,107万ドル、無償資金協力は7億1,300万ドル、技術協力は2億5,292万ドルを記録している(表1)。この実績は中近東地域内ではどの形態の援助においても第1位である。
| 暦年 | 贈与 | 有償資金協力 | 合計 | ||
| 無償資金協力 | 技術協力 | 計 | |||
| ~1990 | 274.95(19) | 138.75(10) | 413.71(29) | 1,026.24(71) | 1,439.95(100) |
| 1991 | 23.99( 4) | 17.05( 3) | 41.04( 7) | 578.53(93) | 619.57(100) |
| 1992 | 44.16(40) | 24.46(22) | 68.62(62) | 41.97(38) | 110.59(100) |
| 1993 | 99.20(36) | 25.40( 9) | 124.60(45) | 150.55(55) | 275.14(100) |
| 1994 | 129.51(69) | 20.85(11) | 150.36(80) | 38.63(20) | 188.99(100) |
| 1995 | 141.19(58) | 26.41(11) | 167.60(69) | 75.15(31) | 242.75(100) |
| 累計 | 713.00(25) | 252.92( 9) | 965.93(34) | 1,911.07(66) | 2,876.97(100) |
注:()内は、ODA合計に占める各形態の割合(%)
出所:外務省経済協力局編『日本の政府開発援助ODA白書』下巻
(3) DAC主要国に占める日本の援助
DAC主要国からの対エジプト二国間援助と日本のそれとの比較を表2に示す。エジプトは1979年にアラブ諸国の中で初めてイスラエルと平和条約を結んで中東和平の先鞭をつけたものの、アラブ諸国の反発によりアラブ連盟の加盟停止、アラブ産油国からの援助打ち切りなどの制裁を受けたため、以後は米国をはじめDAC主要国からの二国間援助が対エジプト援助の大部分を占めるようになった。1990年から1994年までの5年間の対エジプト二国間援助の実績で見る限り、日本は年毎に変動はあるものの常に上位5カ国の中に顔を出している。
| 暦年 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 合計額 |
| 1990 | 米国(58.2) | ドイツ(17.6) | フランス (7.1) | 日本 (5.0) | イタリア (4.4) | 1,970 |
| 1991 | 米国(48.1) | 日本(26.9) | ドイツ (8.0) | フランス (7.1) | イタリア (3.5) | 2,304 |
| 1992 | 米国(55.4) | ドイツ(23.8) | フランス (8.9) | イタリア (4.6) | 日本 (3.7) | 3,001 |
| 1993 | 米国(53.9) | 日本(15.8) | フランス(15.0) | イタリア (8.3) | ドイツ (6.4) | 1,742 |
| 1994 | 米国(29.6) | イタリア(26.7) | フランス(17.7) | ドイツ (12.6) | 日本 (8.2) | 2,311 |
注:()内は、対エジプト二国間援助合計に占める各国の援助額の割合(%)
出所:外務省経済協力局編『日本の政府開発援助ODA白書』下巻
2.日本の対エジプト援助に対する全体的評価
(1) エジプトの開発計画に対する日本の援助
日本の対エジプト援助について、エジプトの開発計画における優先順位と比較しながら整理すると、概要は表3のようになる。
| エジプト優先順位 | 有償 | 無償 | 小計 | |
| 1978~82年度 | i)運輸・通信 | 287.38 | -- | 287.38 (19.3%) |
| ii)電力・公共施設 | 230.22 | 1.0 | 231.22 (15.5%) | |
| iii)農業* | 101.40 | 42.78 | 144.18 ( 9.7%) | |
| 合計 | 1,319.75 | 168.65 | 1,488.40(100.0%) | |
| 1983~87年度 | i)運輸・通信 | 73.50 | -- | 73.50 ( 5.0%) |
| ii)電力・公共施設 | 407.61 | -- | 407.61 (27.8%) | |
| iii)農業* | 254.00 | 73.09 | 327.09 (22.3%) | |
| 合計 | 1,230.21 | 235.68 | 1,465.89(100.0%) | |
| 1988~92年度** | i)運輸・通信 | -- | -- | -- |
| ii)電力・公共施設 | -- | 57.65 | 57.65 ( 1.8%) | |
| iii)農業* | -- | 65.74 | 65.74 ( 2.0%) | |
| 合計 | 3,019.35*** | 245.10 | 3,264.45(100.0%) | |
| 1993~95年度 | i)運輸・通信 | -- | -- | -- |
| ii)電力・公共施設 | -- | -- | -- | |
| iii)農業* | -- | 64.08 | 64.08 (27.6%) | |
| 合計 | -- | 231.86 | 231.86(100.0%) |
注: * 灌漑・排水を含む
**全投資額(即ち、公共投資のみではない)に占める優先順位を掲載している
*** うち、2,225 ・11億円は債務繰り延べ、669.34億円は商品借款
出所:外務省経済協力局編『日本の政府開発援助ODA白書』下巻
日本のエジプト援助は、1978~82年度ではエジプトで優先順位の高い3分野への援助が日本援助の約45%、また、1983~87年では同比率が約55%と、概ね先方の開発優先順位に即したものとなっている。但し、1988~92年度、1993~97年度では、エジプト向けの有償資金協力が停止していることから、優先順位の高い電力・公共施設や住宅建設への支援が皆無となっている。もっとも、1988~92年度でも、債務繰り延べや商品借款を主な内容とする有償資金協力を除いた無償資金協力のみで考えると、エジプトの開発優先3分野への日本援助中の比率が50%に達している。
このように、日本の対エジプト援助は、同国の経済開発計画の基本目標に概ね沿ったものであり、1992年2月に派遣した経済協力総合調査団に代表されるエジプト側との継続的な政策対話を踏まえ、同国経済の基本的ニーズに適切に応えてきたと言える。
(2) 日本の援助の効果と課題
有償資金協力はスエズ運河の拡張やデキーラ一貫製鉄所など大型の国家的プロジェクトに供与される場合が多い。これらの大型プロジェクトの成果は顕著で、エジプトの経済発展と財政事情の改善に大きく貢献していることは明らかである。今後新規の円借款案件を検討するに当たっては、エジプト側はプロジェクトの返済能力を重視し、慎重に対応しようとしている。日本側もそのプロジェクトがエジプト経済に与えうる効果の大きさに配慮するとともに、そのプロジェクトの返済可能性をより厳しく審査すべきであろう。
保健医療部門、農業部門やその他の部門に対する無償資金協力及び技術協力を主とする援助は、エジプト側のニーズに正しく対応して、基本的には大きな効果を挙げている。しかし、同時に、これらのプロジェクトについては技術的に今後改善を加える余地もあると思われる。例えば、農業部門の援助プロジェクトとして重要な農業機械化プロジェクトにおいて供与される高度な農業機械や、医療プロジェクトで供与される精密な医療機器は、操作や修理に必要な基礎的な訓練とともにスペアパーツ一式なども供与されるのが一般的ではある。しかし、スペアパーツの品切れを地元では補給しえないことや複雑な修理作業を現地の人ではこなせないなどの原因で、供与された機械や機器類が遊休化している事例が見られた。
高度な農業機械や精密な医療機器を使いこなし、それらを現地の技術で保守、修理して技術体系全体として現地に定着させることまでも援助の内容として視野に入れるならば、援助の内容は個々の農業部門や医療部門などの範囲を超え、工業部門での援助の性格をも兼ね備えざるを得なくなる。このような部門間の関連にもっと日本側もエジプト側も関心と配慮を払うべきではなかろうか。
エジプトは幾多の経済的困難を抱えているものの、低開発国というよりもテイクオフ過程を完了しつつあり、かなりの程度まで工業化した国であるというのが実状である。そのような国に対する援助は、単に欠落しているところを高度の機械や機器類を供与して補うという内容ではなく、エジプト側が供与された機械や機器類を使いこなし、必要なスペアパーツを自給して保守、修理をやり遂げて、同じような援助を繰り返し受けなくても良いように自立していくのを支援することに重点を置くのが望ましい。
日本の対エジプト援助を効率性・適正度等の観点から見た場合、エジプトの援助受入能力、或いは計画遂行能力等の限界などの点から、必ずしも全ての援助プロジェクトがうまくいっているわけではない。日本の対エジプト援助において見られる問題点は、各分野の援助要請に於いて、エジプト側が、「エジプトの持つ援助受入能力や技術レベルを超えるような機器等の援助や、実現可能性や実行可能性に疑問なしとしない計画を前提とした援助」を求めがちであるということである。このため、日本側としては、エジプト側のこうした傾向を十分認識した上で、エジプトの能力、資質を十分に吟味したり、或いは計画の妥当性を慎重に検討する体制・仕組みを事前に構築しておく必要がある。
エジプト側は今後の開発計画での重要目標のひとつの柱として、シナイ半島総合開発(総額約230億ドル)、上エジプト総合開発(総額約900億ドル)からなる超国家プロジェクトの実行を挙げている。当然、これら大規模プロジェクト絡みでの援助を日本に要請してくることが予想される。しかし、これらの計画はまだ曖昧な部分が多く、日本側としては、エジプト側の政策の進捗を注視しながら対応を考えていく必要があろう。
日本としては、地味ではあるが、将来において同国社会経済の足腰がしっかりするような分野、即ち、貧困者・弱者救済や人的資源の活用、生活環境・公衆衛生の改善など、国民生活の向上への協力を通じてエジプト経済の活性化につながるプロジェクトについて、積極的に支援をしていく必要があろう。
エジプト側の日本の援助に対する評価は、一般的に極めて高いものであった。円借款の返済負担が為替レートの高騰によって過重になったという苦情を除き、この評価調査においてエジプト側から批判や苦言はほとんど聞かれなかった。また、円借款の新規供与が1991年7月から1996年まで停止されたことが、エジプトの開発政策上、どの程度の支障をもたらしたかと懸念されたが、エジプト側関係者から、深刻な影響を受けたとの発言は聞かれなかった。訪れた援助プロジェクトの現場では、どこでも日本の援助に対する感謝の言葉が述べられ、同時に更に援助を継続して欲しい旨の強い要望が表明された。日本の対エジプト援助・協力は大きな効果を挙げ、エジプトにおける経済発展と生活水準の向上などに大いに貢献していると評価されよう。
3.マクロ経済・経済インフラ部門
(1) 概況
エジプトは、1974年10月の門戸開放政策の採択以降、1)インフラストラクチャの建設・整備、2)生産部門の強化の2点を基本目標として開発を進めている。前者については、産業活動の円滑化及び国民生活の質的向上を目指して、電力・運輸・通信分野が重視され、後者では、それまでの輸入代替工業化から輸出促進工業化へと戦略転換が図られた。
これら2つの基本目標を達成するための大きな流れとしては、当初はインフラ整備に相対的に力が注がれ、その進捗に伴い、次第に生産部門の強化・拡充が重視されるようになった。しかしながら、1980年代中頃から生産部門の強化が計画通りに進展しない中で、門戸開放政策の結果として経済的に大きく成功する階層が誕生する一方で、人口の急増やインフレの継続などから経済状況を悪化させる貧困層が拡大するなど社会的歪みが問題となってきた。このため、開発計画においてもサービス部門依存型経済からの脱却や、所得分配の公平化が新たに打ち出されることとなった。
その後、対外債務問題の悪化を背景に、紆余曲折を経ながらも、経済構造・調整改革の実施を条件に、IMFからの融資獲得やパリ・クラブでの債務繰延べを実現した。1993年度からの開発計画では、民間部門の役割の拡大や市場メカニズムの確立を基礎とした生産部門の強化及びインフラ部門の整備を目標としている。
(2) 日本の対エジプト経済協力に対する評価
エジプトの開発計画における優先部門を過去20年にわたり具体的に見ると、常に運輸・通信及び電力・公共施設の整備が最上位を占めており、日本のエジプトに対する援助においても、基本的にこれらの部門への援助を中心に展開されてきた。
ムバラク政権下のエジプトでは、1982年以降1996年央までの期間に、援助国・国際機関から提供された開発資金のうち1,620億LE超(現行為替レートで660億ドル超)をインフラ部門の整備・拡充に割り当てているが、日本からのスエズ運河の諸整備やその他の運輸・通信、或いは全般的な発電能力の拡充、さらには上下水道の整備での援助はこの中で大きな役割を果たすとともに、エジプトの経済・産業活動の活性化及び国民生活の向上・改善に確実につながっており、大いに効果があったと言える。
さらに、エジプトの基礎的インフラストラクチャーである電力部門は、過去15年で著しく改善されており、エジプト側の諸外国の中でも先方ニーズに合致した日本の援助への評価と期待は非常に高い。ショブラ火力発電所やアシュート火力発電所等の日本の援助、並びに他の援助国・機関からの支援を受けて、発電設備能力は1982年の5,030メガワットから1996年には12,468メガワットへと3倍弱の水準に増加し、この間のピークロードの発電量も年平均11%で拡大している。現在では、同国国民一人当たりの電力消費量は875メガワットにまで上昇している。
また、エジプトの主要な外貨収入源の一つであるスエズ運河の浚渫・改修についての日本の援助は、明らかに、エジプトの投資・貿易の機会増大に寄与している。浚渫技術などの日本からの技術移転も、これまでの間に十分に行われていると判断される。しかし、スエズ運河の更なる拡張、汝漢等の将来計画については、陸路輸送、原油のパイプライン輸送等、競合関係となる他の輸送手段との経済性の検討が必要となるであろう。v日本のインフラストラクチャー整備分野における協力は、全体としては妥当なものであり、大きな効果を上げていると評価し得るが、個々のプロジェクト単位で見ると、当初の計画に比べて十分な効果を発現するに至っていないプロジェクトもみられる。
例えば、電力部門の場合、将来の需要予測がプロジェクトの規模を決定する大きな要因であるが、当初計画の時点で、将来の需要予測のよりどころとしていた周辺地域での新規工場の設立や新興住宅地の建設などの関連事業計画の遅延又は停滞によって、実際には需要が当初計画通りに伸びず、その結果、電力施設の設備稼働率が低い状態のままなのである。また、仮に、関連事業がすべて顕在化したものとして設備稼働率を計算したとしても、その数値は十分とは言えない水準であったりする。
エジプト側の関連事業が当初計画通りに実施されていないことは遺憾ではあるが、それと同時に、エジプト側から示された関連事業計画の実現可能性について、プロジェクト審査時にどの程度厳密に調査されたのか、ということについても疑問なしとしない。
日本側としては、このように、エジプト側が実現可能性や実行可能性が必ずしも確かでない計画を限定として援助を求めてくる傾向があることを十分認識し、計画の妥当性を慎重に検討することが重要である。この点から、今後、エジプト側が進めようとしているシナイ半島総合開発や上エジプト総合開発という超国家的プロジェクトに対しては、慎重に吟味することが必要であろう。
また、エジプト政府では、民間部門が経済成長の機関車役であることを認識しており、1991年の経済改革プログラムの導入以降、民間部門の活動を支える分野への投資に焦点を当ててきている。特に、インフラストラクチャー部門については、改革プログラムの開始以来、最優先順位を与えているため、今後は民間部門のインフラ建設を促進するかたちでの支援が求められよう。
4.保健医療セクター
(1) 概況
エジプトは、現在経済的にも社会医療福祉の上でも地域格差の解消に努力している。特に近年では、上ナイル地方の地域格差解消に重点を置き、保健省で、同地方の医療福祉の向上に努めている。
エジプト全体としての疾病傾向は、依然として開発途上国型(感染症、消化器、呼吸器系疾患、周産期疾患が多い)である。特に地方にその傾向が串著に見られることから、保健省は地方自治体政府と協力して地方医療施設の改善に力を尽くしているが、大部分が輸入に依存している医療機器については依然として整備が進まず、遅滞している。
一方、カイロ、アレキサンドリアなど都市部では所得面での階級格差が広がりつつあり、低所得階級の企衆衛生思想の普及、公立大学病院を中心とした医療設備の拡充、医師、看護婦をはじめ医療従事者の育成強化政策が打ち出されつつある。日本はこのような背景のなかで、エジプトの保健医療分野への数々の援助を行ってきた。
エジプトに対する日本の保健医療分野における主な援助案件は以下の通りである。
1 プロジェクト方式技術協力
カイロ大学小児病院(以下CUPH)、カイロ大学看護学部(以下HIN)、家族計画・母子保健
2 無償資金協力
アインシャムス大学放射線部門改善計画、救急医療機材整備計画、カイロ大学小児病院、カイロ大学看護学部、ルクソール市及びケナ県病院医療機材整備計画
(2) 日本の対エジプト援助の評価
1 機材供与案件における問題点
病院、施設等への医療機材の援助について、技術援助を伴わない場合は、現地の経済状態、電力事情、病院あるいは施設のスタッフの教育レベルについての十分な事前調査が必要となる。どこの国においても、医師は最新の医療機器を用いて診療し、患者に最新かつ高レベルの医療を提供したいと願うものであり、医療機器の援助要請に際しては、医療機器保守管理技師の技術レベル、あるいは実際にそれらの機器を操作運用する中堅医師、看護婦等の病院スタッフの能力を十分に踏まえない要請がなされがちである。したがって事前調査においては、この点を充分に考慮した調査がなされなければならない。
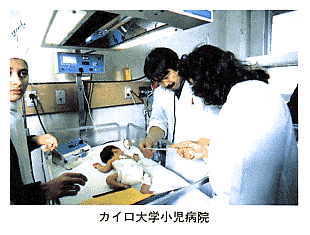
過去のエジプトに対する医療協力、特に技術協力を伴わない機材供与の場合、現場の技術、技能レベルと必ずしも一致していないと思われる機器が供与されたため、それらの機器が有効に使われずに破損しているケースが認められた。このケースでも、供与される機材は高級品とはせず標準的レベルのものを調達するなどの配慮はなされていた。しかし、医療機器の使用法についての技術、技能レベルを見極める作業は極めて禎雑かつ、容易でないことが多い。とりわけ、現代の日本に生活している人には考えも及ばない些細なことがらが、開発途上国においては供与機器を利用する上で重大な支障となることがある。以下にいくつかの例を挙げる。
手術用の手洗い装置などの蛇口について、少しでも水が漏れていると極限まで栓を閉めようとする習慣があるため、パッキンなどの部品が摩滅し、蛇口、水道栓が容易にねじ切れてしまう。
精密電子装置の多い集中治療室や手術場では、水を使った掃除は厳禁であることは、開発途上国でも病院管理者、医師は理解している。しかし、若い医師、看護婦、掃除人には理解していない者も多く、特に掃除人はほとんど理解していないことが多い。その結果、精密機械を水洗いすることすらある。
自動輸液装置、自動注射器などについても、操作法の知識のあるのは一部の上級医師のみである。しかし、それらの医師は常に病室にいることはなく、日常業務は看護婦など、全くその知識のないものが行っていることが多い。このような事情は各病院で異なるため、事前調査では判明しにくい。
CTなど大型の画像診断装置では、画像を判断し診断することができる医師はいる。しかし、その医師が適切な画像を得るための指示を技師に与えることはできないことが多く、また技師が画像を判断することもない。この点を理解せずに、医師あるいは担当機関の要請に応じてこれら大型の診断装置を供与した場合、画像撮影はできても画像判断は不可能で、医師は間違った診断を行いそれに気づかないということも発生しうる。そうなると「診断率の向上」という効果は皆無となってしまう可能性もある。
エジプトの平均的医療レベルの判断に甘さがあったため、要請したエジプト側、日本側双方で満足のいく効果を得られなかった部分があったのではないかと考えられる。
2 技術協力の役割
CUPH、HINに対する技術協力では、個々の専門分野に対する協力と総合的な管理運営に対する協力を行っている。当初日本はこのような技術協力のやり方に慣れておらず、臨床専門分野の個々の対応に追われてきた感があった。細切れの技術移転は結局長続きせず、カウンターパートの転職によりまたもとに戻ってしまうことが多かった。CUPHの第3期プロジェクトでは、対象を循環器疾患の診断、治療成績の向上に絞り、検査部門、臨床部門の派遣専門家も主としてこの技術の専門家が予定されている。
このように協力の対象を十分に絞り込むことによって日本の専門家の選定や依頼が比較的容易になり、カウンターパートの養成も行いやすくなったことは確かであろう。しかし、日本ではこの種の技術協力に対し、残念ながら、組織的にはまだ十分な理解を得られているとは言い難く、専門家として派遣される個人の好意に頼らざるを得ない場合が多い。
3 今後の課題
エジプトにおいては、近年、少なくともカイロ、アレキサンドリアなどでは公衆衛生思想も向上しつつあり、病院、保健所などの施設も整いつつある。しかし地方都市においては大きく立ち遅れているのが現状である。その立ち遅れは、上級医師、看護婦など医療従事者の不足が最も大きな原因であり、このために医療機器の援助を行っても十分な効果を発揮できない。
今後の日本のエジプトに対する医療援助は、医療格差の解消とその水準の向上に向けられるべきであろう。そのためには地方都市における教育病院の整備、スタッフ育成がなされなければならない。スタッフ育成には、現存のCUPH、HINなどの活動とリンクさせていくことが有効であろう。一方、地方都市の教育病院の整備は、日本としてはせいぜい2病院くらいに絞り、そこに重点的に技術協力を伴う医療機器の供与を続けていくことが効果的と思われる。同時に、教育病院を中心とした一般市民に対する公衆衛生思想の普及という観点を考えると、乳児健診、胸部疾患や循環器疾患の集団検診などの支援が加えられていくことが望まれる。
5.農業部門
(1) 概況
日本はエジプトの農業部門に対して1968年から1994年にかけての27年間に、農業・水産の各分野にわたり、各種形態からなる援助プロジェクトを実施し、その合計金額は約545.5億円となる(表4)。この農業援助額を形態別に見ると、ほぼ半分までがアドレア地区の土地改良やアスワン州の砂糖きび生産改良計画などからなる有償資金協力のプロジェクトによって占められている。米作機械化センター計画などの農業機械化関連のプロジェクト、精米技術訓練センター拡充計画や一連の食糧増産援助などからなる無償資金協力プロジェクトがそれに次いで、これら両援助形態を合わせれば95%強となる。開発調査、プロジェクト方式技術協力やその他が僅かずつを占めている。
表4 日本の対エジプト農業援助実績額(1968~94年)の形態別内訳
| 形態 | 金額 | % |
| 開発調査 | 12.3 | 2.3 |
| プロ技* | 11.4 | 2.1 |
| 無償資金協力 | 243.9 | 44.7 |
| 有償資金協力 | 276.4 | 50.7 |
| その他** | 1.5 | 0.2 |
| 計 | 545.5 | 100.0 |
注:* プロジェクト方式技術協力
**単独機材供与、研究協力およびミニプロジェクト
出所:JICA国別情報ファイル
農業援助プロジェクトをいくつかの種類に大別し、その内訳を示したものが表5である。この表で見る限りでは、土地改良プロジェクトが24.9%と最も大きな割合を占めている。土地改良プロジェクトは、有償資金協力による2件のみであるが、土地改良は現在のエジプト農業にとって最も重要な農地の基盤整備に関わる事業で、その性格上、1件当たり多額の費用を要するため、日本の対エジプト農業援助額の中では大きな割合を占めることになる。その農業生産増大や農民生活水準の向上に与える効果は大きく、かつ持続的であることは確かである。次いで金額的に大きな割合を占めているのが農業機械化関係のプロジェクトであって、無償資金協力による米作機械化センター計画や有償資金協力による砂糖きび生産改善計画などがある。
エジプトに対しては、食糧増産援助と呼ばれる無償資金協力が1981年以降ほとんど毎年、その金額も多い年で11億円、少ない年で4.5億円が供与され、表5で見るように総額では89億円、16.3%を占める。この援助の内容は、食糧増産を目的として肥料、農薬または農業機械類を無償供与することである。農業機械類は、既存の農業機械化関連プロジェクトのフォローアップの一環などとして供与されることもある。供与される肥料、農薬または農業機械類は、ある程度の食糧増産効果を挙げていることは確かであろうけれども、特定のプロジェクトに集約されていないため、それらの効果やありうべき問題点は把握し難く、従って評価の対象にし難い。
精米・米貯蔵関係プロジェクトは、無償資金協力による精米技術訓練センター拡充計画や米貯蔵センター改善計画など、食糧や輸出農産物として重要な米の商品価値を高める加工、貯蔵に関わる援助で、大きな効果をもたらしているであろうことが期待出来る。
表5 日本の対エジプト農業援助実績額(1968~94年)のプロジェクト種類別内訳
| プロジェクトの種類 | 金額 | % |
| 農業機械化関係 | 120.9 | 22.2 |
| 灌漑関係 | 17.0 | 3.1 |
| 食糧増産援助 | 89.0 | 16.3 |
| 水産関係* | 33.9 | 6.2 |
| 土地改良 | 135.7 | 24.9 |
| 精米・米貯蔵関係 | 48.8 | 8.9 |
| その他** | 100.2 | 18.4 |
| 計 | 545.5 | 100.0 |
注:* アタカ漁港再整備計画を含む。
** 食糧援助、研究協力、開発調査、優良種子、
食肉冷蔵および単独機材供与など。
出所:JICA国別情報ファイル
水産関係のプロジェクトは無償資金協力によるアタカ漁港再整備計画やハイダム湖における内水面漁業の振興に関わる漁業管理センター計画などである。特にハイダム湖漁業管理センター計画は、エジプトで従来ほとんどなかった淡水魚類の増養殖をめぐる試験・研究機関から構成される。
潅漑関係のプロジェクトには、無償資金協力による上エジプト潅漑施設改修計画やバハル・ヨセフ潅漑用水路整備センターなどがある。上エジプト潅漑施設改修センターは、具体的には潅漑用のポンプの更新を内容とする援助で、農業機械化の一環でもある。圃場整備のためにトラクターなどの導入による農業機械化との対比がプロジェクト評価のポンプとなる。
(2) 日本の対エジプト経済協力に対する評価
エジプト経済に占める農業部門の比重は極めて大きく、農業部門を改善することはエジプトの農民の生活水準の向上に役立つばかりでなく、エジプト経済全体を健全化することに大いに貢献する。このため、日本が対エジプト援助において農業部門を重点援助部門に数えているいることは正当なことである。農業部門における日本の援助は、形態別および種類別の内訳やその割合なども概ね妥当であると言えよう。
農業部門に対する日本の援助は、エジプト当局にとって資金的にも技術的にも困発な土地改良、基本的な潅漑・排水路の整備、漁港や農産物の加工・貯蔵設備の整備など農業の基盤整備関係のプロジェクトを比較的重視し、商業ベースに乗りやすい機械化や漁業の操業などに関わるものは、試験・研究機関やパイロント的な内容のプロジェクトおよび技術・職業訓練のプロジェクトに限定するよう心がけることが望ましい。試験・研究の水準を超えて普及しそうなプロジェクトには民間の活力を活かし、商業ベースでの展開に任せるべきであろう。また、この種のプロジェクトに有償資金協力を供与する場合には、プロジェクトの経済性や返済可能性を厳格に検討すべきであろう。
農業・潅漑の機械化については、エジプト現地の能力では、日本製の高度な農業機械の保守・整備、修理が行き届かず、特にスペアパーツの不足から稼動しないで遊休化、老朽化している機械が見られる案件もある。エジプト側の技術力、スペアパーツなどの国産能力を一歩一歩高めることを心がけ、技術訓練を重視することが肝要である。必要なスペアパーツ一式とスペアパーツ加工・製作のための工作機械類が当初からエジプト側に供与され、導入されているにも拘わらず、使用頻度の高いスペアパーツはまもなく欠乏し、エジプト現地でのスペアパーツの製作も、うまくいっていない。
エジプト側のスペアパーツ国産能力、修理技術力などを大きく超える高度の機械類を供与して、その結果、スペアパーツなどの供給や機器の更新でいたずらにエジプトの対外依存度を高めることにならないよう、日本、エジプト双方が十分に配慮することが望ましい。エジプト側は、高度で精密な機械類の導入を高望みせず、着実にマスターできるものから国産能力を身につけていく努力を重視すべきであろう。また、日本側も、エジプト側のそのような努力を支援していくべきであろう。エジプトは経済発展と工業化のかなりすすんだ国であって、もう一歩押し上げることによって大きく技術力を発展させ得る国であることが認識されなければならない。

