第1章 国別評価
1.ラオス
(現地調査期間1996年11月24日~12月6日)
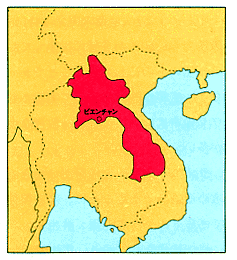
〈団員構成〉
■斉藤 優 中央大学経済学部教授
■深井 善雄 元JICA専門家
■昌谷 泉 海外コンサルティング企業協会副主任研究員
■安部 忠宏 外務省経済協力局評価室長
■唐澤 拓夫 外務省経済協力局評価室事務官
1.ラオスの国家開発の基礎構造
開発援助を正確に評価するためには、まずは援助受取国の国家開発の基礎構造を正確に把握し、それを基に発生した開発ニーズと、それを具体化した援助プロジェクトとの関連を分析する必要がある。国家開発の基礎構造と開発ニーズは、通常、マクロ的には国家開発計画の中で密接に関連づけられ、それを具体的に展開する方向で援助プログラムが形成される。国家開発の基礎構造や開発ニーズを無視した援助プログラムは正当な国民的指示は受けられないだろうし、成功させることも困難であろう。
ラオスの国家開発の基礎構造を、援助評価に関わる範囲で素描する。ラオスの社会経済構造をみると、ラオスは人口的には小国、発展段階的には最貧国(LLDC)、内陸山岳経済、などの諸特徴を持つ。人口密度は日本の約17分の1にすぎず、都市化率も低く、広く分散した山岳小農村社会が大半を占める。政治体制的には、1953年10月にフランスから独立したが、やがて東西冷戦の影響を受けてインドシナ紛争に巻き込まれ、対立抗争を経て、1975年に革命を起こして「ラオス人民民主共和国」となり、社会主義路線を採択した。東西冷戦体制の崩壊が近づくにつれて、1986年に解放と市場経済の導入に道を開いた。この間、外国援助に頼らなければならない状況は続き、ラオスに対する援助は、主として革命前はアメリカ合衆国に、革命後は旧ソ連に、移行経済過程に入ると日本及び主要先進国、国際機関へと援助供与構成は変化してきた。
ラオスの国家開発の基本方向は、他の開発途上国と同じように、産業化と近代化を中心とするものであった。ここでの産業化とは、工業化よりも広範な概念であって、社会的分業を担い、経済の重要部門になる産業にしていくことであり、農業を含む1次産業部門にも当てはめることができる。ラオスの国家開発の構造と産業構造を見ると、農業を中心とする1次産業の開発は特に重要である。国内総生産の半分以上を農業に依存し、労働力の約60%が農業に従事している。近代化とは、より進歩的、より合理的、より高い価値のものにしていくことであって、社会開発や政治開発、文化開発、インフラ整備など、広範な活動を通して実現される。また、産業化にもインフラが重要であり、インフラの中には道路や通信、教育などのように、国が小さくても巨額の投資が必要なものが多い。
ラオス経済は、天然資源に大きく依存し、国際分業においても比較優位を天然資源に求める経済であるために、経済開発は天然資源と関係したものが多い。山岳と国際河川であるメコン川の利用・共生が、ラオス開発のカギの1つである。農民の大半がいまだに焼き畑耕作をしており、電力輸出用のダム建設プロジェクトの提案も目白押しである。それだけに、開発の際に天然資源の利用のみならず、自然の恵みを与えてくれる環境への影響に十分な注意を払わなければならない。つまり、ラオスにとって、国家開発の基本方向として、「持続可能な開発」は特に重要な意味を持つ。
ラオスの国家開発にとって不利な面を持つものとして、内陸山岳国ゆえの自然的制約、人口小国ゆえの小市場、人材・技術者・資本などの開発資源の不足などが挙げられる。内陸国であるために、全貿易額の40%以上を隣国タイに依存し、残りの多くもベトナム、中国に依存している。これまでのところ、移行経済と対外開放をすればするほど、バーツ経済圏に組み込まれていく状況にある。
2.ラオスの国家開発メカニズムと外国援助
一般に、国際開発援助は、援助受取国の開発ニーズ(Nr)と開発資源(Rr)の関係と、援助供与側の援助ニーズ(Nd)と援助資源(Rd)の関係から、両者の話し合いを通して実現していくものであり、その成果は両者の評価基準によって判断される。評価基準は客観的であればあるほど、その評価基準が両者に共有できるものであればあるほど、判断における食い違いは少なくなる。判断における食い違いを少なくするために、両者のニーズ(N)・資源(R)関係について国際関係からの分析が必要である。
日本は、これまで、基本的には援助受取国の要請に応えて援助するという要請主義を採ってきたので(Nr→Nd)、その要請が正しい国家開発ニーズからなされ、それに正しく応えている限り、両国間で矛盾や衝突が起きることはない。もちろんラオスにおける開発援助も要請主義を原則にしてきた。
国家開発と援助の関係を、主として両者のN・R関係の国際関係から追跡する。国家開発計画には、その国の、その時期の国家開発ニーズ(Nr)と必要資源の配分(Rr)が統合的に書き込まれている。したがって、それぞれの時期の日本の開発援助プロジェクトとラオスの国家開発計画とを照合させることによって、日本の開発援助がラオスの国家開発に適合的なものであったかどうかの判断ができる。
日本がラオスに援助を始めて30年を越える。初期の援助と、ラオスが社会主義建設を目指した頃、経済開放化と市場経済原理の導入へと移行した新経済メカニズム(NEM)の時代、政治経済が激変した1990年代の援助とは内容が大きく変わっている。そこで、ラオスの国家発展の時期をこれら4つに分けて、それぞれの時期のラオスと日本のN・R関係を対比させながら、日本の援助の変遷を追ってみる。
マクロ的評価では、まずラオスの国家発展のパフォーマンスを検討し、これに援助がどのように作用し、貢献してきたかを分析する。経済開発援助は貿易や海外直接投資にも影響することがある。近年のラオス経済は高成長と言える成果を持続しているが、これは、この時期よりずっと以前の、例えばナムグム・ダムや国道主幹線の開発などのインフラ整備が有効に作用したからであろう。外国援助が急増し始めた1980年代後半でも、ラオスでは電力・木材・コーヒーが3大輸出品であった(1989年の統計で輸出総額の71.4%)。それが1995年には、木材(25.4%)、製品(22.5%)、衣類(22.0%)、電力(6.9%)、金再輸出(6.3%)へと、輸出の工業化・多様化が進んだ。
このように、当初の援助が後になって大きく効いてくる場合もある。また近年では、日本の援助はトップ・ドナーの地位にあるのに、日本からの海外直接投資は15位と低く、ラオス政府からの投資要請が強い。けれども日本のインフラ建設援助や技術協力が、他国からの海外直接投資の導入に大きく貢献している面は考えられる。
近年のラオス経済の高成長は産業化と近代化を中心とするものであった。産業化は工業化を含めた産業多様化と貿易成長を促進し、他方でインフラ開発、社会開発、政治的安定などを含む近代化が産業化を促進しする方向で補足的に作用したからであろう。近代化や産業化には、外国援助が相当程度で貢献したと考えられる。近年では、ラオス政府はGDPの約2割の外国援助を利用している。国家開発に外国援助を利用できる割合が大きいが、このことは同時に援助への依存も深まっていることを意味する。対外債務を91年と95年で比較すると、対GDP比率では32.8%から39.6%へ、デット・サービス・レイシオでは、輸出が増大してきたため11.2%から4.9%になっている。一般に、LLDC諸国ではラオスより悪い状態の国がほとんどである。
近年におけるラオスの経済開発のマクロ的パフォーマンスは、表1にみられるように、高成長を維持している。95年にはインフレ率が高くなっているなどの問題もあるが、全般的に言って、LLDCでありながら、かなり良い成績を挙げていると考えられる。
経済成長に外国援助がどの程度の貢献をしたかを計量的に正確に算出することは、データや分析方法の問題もあり困難である。しかし、個々の開発援助プロジェクトをできるだけ正確に評価して、経済成長にプラスに作用したか、マイナスに働いたかを判断することは可能であろう。
| 主要指標 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|
実質GDP成長率(%) 1人当たり名目GDP インフレ率(年末) 貨幣流通量(年末、10億キープ) 貨幣流通量増加率(年末、%) 為替レート(年末、1米ドルに対する) 純外貨流入量(百万米ドル) 外国援助受取額(百万米ドル) 政府歳出(10億キープ) 政府歳入(10億キープ) 財政赤字(除無償援助、10億キープ) 外貨準備高(年末、百万米ドル) 輸入額(百万米ドル) 輸出額(百万米ドル) |
6.7 200 17.7 46.9 14.4 695 55.8 175 143.4 61.0 -82.4 64.8 202 79 |
4.0 216 10.4 51.3 9.4 711 9.6 132.6 151.1 74.7 -76.4 57.2 215 97 |
7.0 250 6.0 76.5 49.1 715 56.2 134.0 192.1 93.5 -98.6 81.2 265 133 |
5.9 290 9.0 125.8 64.4 716 111.5 181.3 170.5 113.3 -72.9 150.9 432 240 |
8.1 335 6.7 166.0 32.0 718 106.6 188.7 266.7 143.6 -123.1 158.2 564 300 |
7.0 350 25.7 193.3 16.4 920 203.3 232.5 294.0 165.7 -128.3 191.1 587 348 |
出所:在ラオス日本大使館 (ラオス政府提供資料を基に作成)
(1) 75年以前の日本の援助
インドシナは、フランスの植民地から独立した後も革命のための紛争、それに東西代理戦争的な役割を背負わされながら、長期間にわたって戦乱に悩まされてきた。ラオスは60年間続いたフランス植民地から1953年に独立し、その後、1975年に王政から共産主義国家樹立を目指した革命政権に変わった。この間、東西援助競争を主導していたアメリカ合衆国は積極的に援助した。
この時期のラオスの経済社会開発5ケ年計画の主要な柱は、
イ)ビエンチャン地区を中心にした農業開発の展開
ロ)インフラの整備・向上
ハ)工業化(利益率の高い消費財工業を中心に)
であった。一方、日本の本格的な援助は、1966年に無償資金協力で行われたナムグム河開発基金協定からであり、この期間に行われた主要なものは、
イ)インフラ開発(ナムグム・ダム、空港整備、上下水道開発など)
ロ)社会開発(マラリア撲滅計画、ルアンプラバン病院、タゴン医療センターなど)
ハ)農業・食料援助(食料援助、タゴン農場開発など)
などがある。ほとんどの日本の援助プロジェクトがラオスの国家開発計画に示された開発ニーズと直接・間接に適合するものであったと判断できよう。また、多くの援助プロジェクトが終了した後も、その成果を踏み台にして、新しい後継援助プロジェクトが生み出されている。例えば、ナムグム・ダムは発電機の補修、技術研修などの事業へ、1969年のビエンチャン国際空港滑走路延長事業は、1995年からの改修計画へとつながっている。
1971年に完成したナムグム・ダムは、その後のダム建設に重要な学習と教訓を与えている。このダムに関して、その環境面の問題が無かったわけではないが、ラオスの国民生活の向上、産業化、近代化に必要なエネルギーの確保、電力輸出による外貨獲得などによる便益が、いろいろな面からこのようなコストよりもはるかに大きいと判断して、ラオス政府はこのダムを建設したのである。ラオス側ではナムグム・ダムを高く評価しており、その建設経験と学習を他の分野の開発にも活用している。ラオスの多くの人達が、長期にわたってナムグム・ダムの建設・運用に協力してきた日本の貢献を認識している。
ナムグム・ダムはラオスへの日本の援助の評価の際によく取り上げられるが、同様に日本のODAによって1973年に建設された上水道システムの紹介は少ない。上水道システムの建設・改善への日本の援助はその後も続けられ、現在ではビエンチャン市の人口の約71%がこの恩恵を被っている。
この他、長期にわたって技術協力がなされているものの1つに養蚕業がある。養蚕業はラオスにとって重要産業の1つであり、1968年に現地調査が行われて以来、今でも続けられている。
(2) 1975年からの社会主義革命政権における日本の援助
1975年にラオスは革命によって社会主義政権に変わり、西側主要諸国と外交関係を再構築するまでは、主として旧ソ連、東欧諸国、ベトナムなどの当時の社会主義諸国から援助を受けた。旧ソ連の援助は、コメコン・タイプの協力関係であって、物々交換型の貿易の赤字を貸し付けたり、生活必需品に重点が置かれていた。旧ソ連の援助は多いときにはラオスに対する援助総額の約7割を占めていた。1976~90年までの旧ソ連からの累積貸し付けは7億1,500万ルーブル、累積贈与は4,800万ルーブルであった。これらを利用して経済計画が図られたが、期待したほどの効果は得られなかったようである。

1975年に3ケ年計画、さらに社会主義経済の完成を目指して第1次5ケ年計画(1981~85年)が作成され、実施された。第1次5ケ年計画の主な内容は、
イ)農業開発と食糧の自給
ロ)交通等のインフラの整備
ハ)国家による通貨・物価の管理
ニ)教育水準の向上
などであった。日本は、この時期にも援助を続けてきた。この時期の主な日本の援助を見ると、
イ)インフラ整備(道路・輸送網、上水道など)
ロ)社会開発(教育機材供与など)
ハ)農業開発・食糧増産(タゴン農場、都市近郊農業など)
ニ)高等電子技術学校開設、製薬工場と技術移転
などである。ラオスの国家開発計画と日本の援助を対照させてみると、大まかな項目では国家開発ニーズに適合した援助であったと判断して良いであろう。
ラオスは、道路開発には現在でも多くの援助国を利用している。しかし、道路が開発されても、運輸システムの整備に投資しなければ大きな開発効果は期待できない。日本は1978年にラオスのバス公社に無償資金協力でバス29台を供与して、ラオスの公共輸送システムの整備に貢献した。この援助は、その後1988年にビエンチャン都市交通網整備計画によって更に拡大した規模で引き継がれ、さらに、この計画に必要な機材供与・技術協力も続けられ、現在では利益をあげるまでに発展したという。
教育・技術移転において大きな成果を挙げ、ラオス側に高く評価されている援助の中に高等電子技術学校がある。この学校は、1977年に日本の援助によって建設された。教育用機材の供与、長期専門家の派遣などにより、この学校では数多くの上級技能者を育成してきた。1995年には新校舎に建て替えられ、著しく近代化された。本校は、近々大学に昇格することになっている。
この他、この期間の興味ある援助の1つに、製薬技術開発センター建設計画がある。医療基盤の貧弱さと医薬品供給の不足・外国依存に悩まされてきたラオスにとって、ラオスの実情に適合した国内製剤と国産原料による製薬の生産開発を行うのに必要な設備を備えた「製薬技術センター」設立の援助を受ける意義は大きかったであろう。工場稼働の技術移転はほぼ完全に済んでおり、帳簿上もかなりの成果を挙げているようであるが、経営能力を向上すればさらに発展できると思われる。
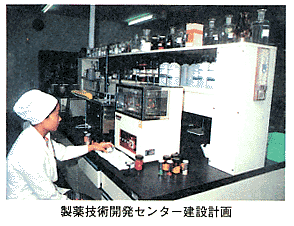
(3) 新経済メカニズム(NEM)開始時における日本の援助
ラオスは、1986年に新経済メカニズム(NEM)を採用することによって、それまでの社会主義政策を大きく変更していった。NEMの基本的な方針は、改革によって経済開放化と市場経済原理の導入であり、それは、ラオス経済を中央計画経済から市場指向的経済に転換するのに役立った。この頃には、既に旧ソ連援助の増大は期待できず、東側の国際分業も行き詰まっていた。NEMは、旧ソ連崩壊前に、一足早めに移行経済をタイムリーかつ効果的に推進したもので、成功的であったと判断して良いであろう。
NEMの主要改革項目は、
イ)銀行制度の改革
ロ)税制改革
ハ)貿易自由化、外国投資法の制定と外国企業の誘致
ニ)物価の自由市場価格化
ホ)国営企業の独立採算性、さらに民営化
などであった。ラオスでは、NEMに基づいて第2次5ケ年計画(1986~90年)が作成され、その主な内容は、
イ)食糧の安定供給
ロ)森林資源の開発と保護
ハ)鉱工業の育成
ニ)インフラ(交通・輸送、郵便など)
ホ)物品の流通ネットワークの整備
ヘ)国家財政の強化
ト)教育水準の向上
チ)外国との経済・文化交流の推進
リ)平均経済成長率を10%とする
などであった。これらの国家開発ニーズに対して、この時期の日本の援助の内容の主たるものは、
イ)インフラ関連(都市近代化、都市交通など)
ロ)社会開発関連(教育など)
ハ)農業開発・食糧増産援助
ニ)草の根無償援助
ホ)援助の多角化と増大傾向
であった。ラオスの国家開発ニーズと日本の援助を対比させてみると、やはり大体において適合していると判断して良いであろう。技術協力において重要な役割を果たす専門家の派遣実績をみると、1978~85年の間に6人であったのが、1986~90年の間には41人に増え、指導科目も多様化している。
この期間に、主要プロジェクトの数や種類が増加してきたこと、そして草の根無償援助のような新しいタイプの援助が出てきたことに注目すべきであろう。
また、この時期には、首都郊外総合農業開発、都市近代化などで新しい前進が見られた。首都郊外総合農業開発は、1)首都圏の慢性的な食糧不足の緩和、2)畑作の振興、3)農村インフラの整備と農村開発、4)米、野菜の輸入代替生産による外貨節約・国際収支改善、などのために1990~93年の間に22億円の無償資金協力を実施したものである。周辺地域への技術普及、施設の維持管理など、まだまだ改善の余地はあるにせよ、作付け面積と単位収穫量は上昇しており、事業成果を挙げている。
都市近代化には、電気通信インフラの整備は欠かせない。電気通信部門に対する外国援助競争もこの頃から始まっている。日本は、1990年に専門家の派遣と無償資金協力により、デジタル交換機及び関連付帯設備を提供している。アジアにおける情報化社会の浸透の中で、ラオスのような人口小国に対しても、情報化先進国による海外市場獲得競争は厳しい。
この時期に草の根無償援助が始まった意義は大きい。草の根無償援助は少額ではあるが、開発NGOなどの開発プロジェクトを支援するものである。1989年には総額約9万ドルがビエンチャン職業訓練センター、マホソット病院眼科病棟建設など3件に供与され、翌年には4件に増えた。現地調査で主な草の根無償援助のプロジェクト・サイトの視察を行ったが、いずれも相当の効果を挙げていた。
(4) 1991年の憲法制定以降の日本の援助
旧ソ連の崩壊によって、ラオスは1991年以降は西側先進諸国と国際機関からの援助に大きく依存するようになった。ラオスは依然として海外援助に大きく依存しながらも、産業化・近代化に努力し、市場経済化・民営化と対外経済関係における輸出の増大などによって国民経済の高成長を維持している。実質経済成長率は約7%で成長しており、製造業、建設業、観光業などが高成長した。この期間は経済パフォーマンスは良好である。
この時期のラオスの国家開発計画は、第3次5ケ年計画(1991~95年)によって代表される。この計画の主要内容を簡単に示すと、
イ)市場経済移行のための経済改革の実行
ロ)公共部門の効率化と民営化
ハ)社会資本と人的資本の開発
ニ)自然資源の有効活用と環境保護
などが挙げられる。
この期間のラオスに対する外国援助は、二国間援助が総額の約半分、その中で、1991年以降は日本が最大の援助国になっている。この期間の日本の援助のうち主要、或いは新しい援助プロジェクトを見てみると、
イ)農村開発(都市近郊農業開発計画、サバナケート農業総合開発計画など)
ロ)インフラ整備(道路、輸送、テレビ局など)
ハ)社会開発(病院・医療など)
ニ)環境保全、森林保全など
ホ)草の根無償援助の活用と増大
などが挙げられる。これら日本の援助の内容とラオスの国家開発計画を比較すると、この期間でもやはりラオスの開発ニーズに大体において適合したものと判断して良いであろう。ラオスは、この時期から新しい開発組織の形成に前進が見られ、また、海外援助機関もラオスを注目するようになって、新しい開発ニーズ、新しい開発プロポーザルが増大してきた。
例えば、1996年から始まった森林保全・復旧計画は、森林荒廃の原因になっている焼き畑や無秩序な伐採を抑え、荒廃した森林を復旧するために、ラオス政府が森林保全・復旧の技術とシステムの構築について日本の援助を求めてきたものである。この計画においては、住民参加を基本とし、住民との対話を重視していることが注目される。ラオスから木材輸入をしている日本にとっても適切な援助プロジェクトの1つであろう。
この時期からは連携援助が重視されてきた。国際機関との連携の例としては、プライマリー・ヘルス・ケア活動、予防接種普及活動、感染症対策の強化のための活動基盤の確立を目的とした日本・WHO公衆衛生プロジェクトがその1つである。二国間ベースでは、タイとの連携協力もある。
近代的社会インフラの開発協力として、1993年に無償資金協力で国立テレビ局(LNTV)に新しいテレビ放送局を建設した。LNTVが設備不足、予算不足、人材不足に悩んでいたために大いに役立ったが、同じ悩みが今でも続いていることも確かである。
また、この時期には、草の根無償援助の活用・増大が図られ、中でも地方の小学校建設は、地域住民に直接感謝されている。小学校といっても、(自立発展性を考慮して)建設費の約2割を地域の人達が調達し残額を日本が無償援助するもので、日本にとって金額は小規模でもラオス側にとっては大きな効果を持つ。

3.国際機関及び主要援助国の評価
近年におけるラオスに対する外国援助は、表2にみられるように、援助の増大傾向、二国間援助のシェアが増えてきたこと、日本がトップドナーを維持していること、などである。主な援助分野を援助主体別にみると、表3にあるように、
二国間援助:輸送、人的資源開発、地域開発、農林漁業、コミュニケーション
多国間援助:輸送、農林漁業、エネルギー、経済管理、社会開発
NGO援助:保健、地域開発、人的資源開発、農林漁業、人道援助
となっている。
多数の援助国、援助機関、援助団体がそれぞれの援助方針に基づいて援助活動をしている。援助資源を節約し効果をより向上させるためには、ラオス側とこれら援助ドナー側の話し合いと調整が必要になってくる。対ラオス援助のために、UNDPを議長として、適当な時期にラオス援助円卓会議が開催され、その他の関連国連機関、世界銀行、アジア開発銀行などの国際機関と日本、スウェーデン、オーストラリア、フランス、ドイツなどの援助国がラオス政府と共に対ラオス援助の基本方針についての意見交換や、援助機関間の調整・情報交換などが行われている。
UNDPは、ラオス政府と援助国・援助機関との間の調整役として重要な役割を果たしており、適当な時期にラオス国別援助計画も策定する。UNDPの第5回ラオス国別援助計画(1992~96年)では、以下の3つの分野に重点が置かれている。
イ)物理的インフラの開発
ロ)人的資源開発
ハ)NEMの支援
UNDPでは、この第5回ラオス国別援助計画は成功したと自己評価している。この計画期間中に多くの開発プロジェクトが実施され、それらがラオスの開発マネジメント能力の向上に累積的なインパクトを与えてきたと判断している。開発のマスタープランの作成指導もその1例である。中でも強調しているのは、UNDPが開発にとって決定的に重要な2つの資源、つまり、1つは外国投資、もう1つは外国援助を管理し調整する制度・機関を創設し、強化するのを支援してきたことである。前者は外貨法であり、後者は外国援助原則である。UNDPの援助手段の中心は人的資源開発であり、オン・ザ・ジョブ・トレーニングとフェローシップの利用による技術協力・技術移転である。
|
年 援助側 |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | ||||||
| 援助側 | % | 援助側 | % | 援助側 | % | 援助側 | % | 援助側 | % | 援助側 | % | |
|
二国間援助 オーストラリア 日本 ドイツ スウェーデン フランス |
58,850 5,207 6,914 3,799 10,733 3,255 |
36.6 3.2 4.3 2.4 6.7 2.0 |
70,200 6,390 20,813 13,259 14,909 6,928 |
39.4 3.6 11.7 7.4 8.4 3.9 |
71,901 10,505 22,524 3,013 22,217 7,314 |
43.0 6.3 13.5 1.8 13.3 4.4 |
106,705 12,753 36,544 14,329 17,095 11,271 |
46.9 5.6 16.1 6.3 7.5 5.0 |
118,411 11,897 45,003 11,806 13,336 9,387 |
50.7 5.1 19.3 5.1 5.7 4.0 |
147,666 14,286 59,875 24,471 13,136 12,368 |
48.8 4.7 19.8 8.1 4.3 4.1 |
|
多国間援助 ADB IDA(IBRD) IMF UNDP |
96,501 43,946 31,220 0 12,346 |
60.1 27.3 19.4 0.0 7.7 |
100,991 59,116 14,100 11,250 9,553 |
56.7 33.2 7.9 6.3 5.4 |
88,768 16,080 38,170 8,000 11,803 |
53.1 9.6 22.8 4.8 7.1 |
112,315 39,124 37,979 14,060 9,159 |
49.3 17.2 16.7 6.2 4.0 |
101,643 28,459 26,791 16,878 7,363 |
43.5 12.2 11.5 7.2 3.1 |
134,589 64,271 27,102 17,708 8,225 |
44.5 21.2 9.0 5.9 2.7 |
|
EU NGO |
2,436 2,902 |
1.5 1.8 |
2,429 4,482 |
1.4 2.5 |
792 5,794 |
0.5 3.5 |
2,638 5,944 |
1.2 2.5 |
4,511 9,198 |
1.9 3.9 |
8,558 11,648 |
2.8 3.9 |
| 合計 | 160,689 | 100.0 | 178,102 | 100.0 | 167,225 | 100.0 | 227,602 | 100.0 | 233,763 | 100.0 | 302,461 | 100.0 |
|
援助主体 援助分野 |
二国間援助 | 多国間援助 | EU | NGO | 総計 | |||||||
| UNDP | その他 | 小計 | ||||||||||
| ドル | % | ドル | % | ドル | % | ドル | % | ドル | % | ドル | % | |
|
農林漁業 地域開発 コミュニケーション 開発行政 災害予防 国内商業取引 経済管理 エネルギー 保健 人的資源開発 人道援助・救済 工業 天然資源 社会開発 輸送 |
15,569 18,617 14,976 14,357 1,617 229 1,270 2,324 4,061 22,665 6,223 3 3,147 5,769 36,839 |
5.15 6.16 4.95 4.75 0.53 0.08 0.42 0.77 1.34 7.49 2.06 0.00 1.04 1.91 12.18 |
2,631 409 280 1,295 51 420 69 208 169 0 0 288 1,651 745 |
22,626 481 4,745 675 0 0 18,560 20,871 4,453 3,617 3,987 372 1 13,520 32,078 |
25,626 890 5,025 1,970 51 0 18,980 20,940 4,661 3,786 3,987 372 289 15,171 32,841 |
8.47 0.29 1.66 0.65 0.02 0.00 6.28 6.92 1.54 1.25 1.32 0.12 0.10 5.02 10.86 |
723 2,964 851 0 0 628 0 0 1,848 0 0 1,544 0 |
1,600 2,547 0 444 30 0 40 0 2,683 2,001 1,527 15 0 761 0 |
1,600 2,547 0 444 30 0 40 0 2,683 2,001 1,527 15 0 761 0 |
0.53 0.84 0.00 0.15 0.01 0.00 0.01 0.00 0.89 0.66 0.50 0.00 0.00 0.25 0.00 |
43,518 25,018 20,001 16,771 2,549 229 20,290 23,892 11,405 28,452 13,585 390 3,436 23,245 69,680 |
14.39 8.27 6.61 5.54 0.84 0.08 6.71 7.90 3.77 9.41 4.49 0.13 1.14 7.69 23.04 |
| 総計 | 147,666 | >48.82 | 8,225 | *126,364 | 134,589 | 44.50 | 8,558 | 2.83 | 11,648 | 3.85 | 302,461 | 100.00 |
出所:UNDP, Development Cooperation, Lao People's Democratic Republic, 1996 Report, Oct. 1996.
*注1)総多国間援助のその他の総計は各項目における金額の合計と一致していないがこれについての注記はUNDPのレポートにはない。
UNDPはこれまでの援助経験からの最も重要な教訓として、援助効果をさらに高めるためには、技術協力の焦点を戦略的部門に集中すべきであったと述べている。そして、関連指標やターゲットに最大のインパクトを与えるための相互作用を有効に利用するために、今後はもっと高度のプログラム・アプローチが必要になるという。
UNDPが示すこれからの援助戦略と課題領域は、
イ)持続的開発と長期的成功を確保するために、開発の国家的自主性を持たせる
ロ)外国援助に関する援助調整
ハ)開発資源の調達・流動性と最適利用
ニ)プログラム・アプローチ
ホ)国連機関間の協力
ヘ)ジェンダー考慮
などである。
国連機関には、UNDPの他にいろいろな専門機関がある。例えば、ユニセフはラオスで教育プログラムを中心に援助活動をしており、中でも初等教育とインフォーマル教育を重視している。この他、ジェンダーとWID(途上国の女性支援)のプログラム、マラリア対策用薬品・医療プログラムにも取り組んでいるが、予算が少ないことの悩みを抱えている。
世界銀行は、ラオスのマクロ経済が概ね順調に成長し始めた1989年から構造調整融資を開始した。ラオスは高い経済パフォーマンスを続けており、NEMに沿って各種の経済改革・租税制度改革、移行経済過程の促進などに努力が払われ、相当の評価が与えられている。1989年に始まった民営化政策は、1997年までに戦略的重要企業は残して、90%の企業の民営化を達成目標にしている。
近年の国連・国際機関の援助の重点は、NEMの支援、インフラの開発、人的資源開発であるという。二国間援助においても重点援助分野が各国で考慮されており、戦略的な展開が図られつつある。たとえ重点分野が同じでも手法ややり方が異なる場合は多い。
小規模なものでは農村開発のプロジェクト数が増加していくであろう。大型案件に関しては、現在ダム開発と道路・運輸開発のプロポーザルが多く持ち込まれている。ダムに関係する電力部門のラオス政府の政策として、
イ)多数の国際機関・国からの資金協力を得ながら電力開発
ロ)全国供給網の整備とラオス電力公社の事業能力の拡大
ハ)電力輸出所得の増大
ニ)水力発電開発が最大限利用できる可能性の考慮
ホ)電力開発に外国民間資金の導入を考慮(BOT方式)
などが挙げられている。ダム開発のプロポーザルが多く提出されているからといって、ラオス政府が環境破壊などのネガティブな面を無視しているわけではなく、このことは関係当局の説明にもあった。
主要援助国の中で、スウェーデンはラオスに熱心に援助してきた。スウェーデンの主な援助対象部門は、森林部門、道路部門、保健部門であるが、近年では環境部門にも注目し、人権問題を重視している。スウェーデンはラオスに対する主要援助国であり、これまでの成果に自信を持っており、今後の援助活動にも積極的である。
オーストラリアは、初期には農業部門中心であったが、NEM導入後は、援助対象部門を多様化してきている。教育部門や運輸・通信などのインフラ部門の比重を増大させており、オーストラリアによる友好橋建設援助は、関係諸国に大きくアピールして評価された。
以上のように、ラオスにおける援助は、その結果が良く、小国、LLDCであるがゆえに援助のプロフェッショナル性が特に問われ、成果が大国より早く現れることもあって、援助機関・国の間の援助競争が激化してきた感がある。例えば、道路建設には国際機関、主要援助国のほとんどが区間毎に援助してきた。たくさんの援助プロジェクトがラオスに持ち込まれており、一部では消化不良を起こしかねない。
援助受取国であるラオスについて、援助側の各機関・各国の意見によると、ラオスの各省庁が援助プロジェクトを何でも抱えたがる、郡レベルでは消化能力が小さく、低いガバナンス能力、人材不足、開発ニーズに関しては、村レベルでは食糧など生活物資が、県以上のレベルになると道路その他のインフラが重視されるという。
ラオス政府も参加する援助機関・国間のドナー会議では、プロジェクトの調整・連携、情報交換がなされる。例えば、森林保全援助には日本を含めて多くの援助機関・国が参加しており、必要に応じてドナー会議が開催されているが、農業・農村開発や森林保全の援助においては、回転基金方式の適用に関心が持たれている。回転基金やルーラル・クレジットが議論されたドナー会議に出席した日本人専門家の報告によると、
イ)スウェーデンが援助した焼き畑対策プロジェクトの回転基金の経験では、農民の返済率は50~60%に止まること
ロ)「借りる」だけでなく、「預ける」ことの重要性を教育する必要があること
ハ)金銭的な面では女性が果たす役割が重要であること
ニ)ルーラル・クレジットによって家畜飼育が増大し、かえって森林破壊を招く恐れがあること
ホ)インフレ率を考慮した利息にすべきかどうか
などが議論されたという。
これからの対ラオス援助プロジェクトにおいて、いずれの援助機関・国・NGOも指摘するのが所得創出的視点の重要性、自立発展的システムの重視、援助の量から質への転換などである。
4.外国援助における日本の役割
(1) 外国援助の中での日本の援助の役割
ラオスの国家開発において外国援助が相当の役割を果たしてきたことは、これまで見てきたような、この30年間の発展史的分析や国連・国際援助機関の評価報告から読みとれる。しかし、その役割が顕著に実感できるようになったのは、ラオス自身がNEMによる変身を実行して、先進諸国・国際機関からの援助の増大に努力した80年代後半からである。
既に述べたように、日本は、対ラオス外国援助において、1991年以来、二国間援助ではトップドナーの地位を維持している。大まかに見ると、援助総額の約半分が二国間援助であり、その中で日本のシェアは1991年の約12%から1995年の約20%に増大した。援助額やシェアが大きくなってくると、国際機関や他の援助国からも注目されるようになり、またラオスと日本の外交関係・国際関係が密になってくるのは当然のことであろう。ドナー会議における協力・調整・情報交換においても、やはり援助資源をより多く提供できる日本への関心は大きい。公衆衛生プロジェクトのようなWHOとの援助協調など、共同援助相手としても期待される部分が多くなってきた。
通常、欧米の援助国の場合、小規模・草の根援助の中心的な担い手は開発NGOである。日本では、近年、開発NGOが増加してきたとはいえ、比較的にまだ少ない。日本で、この分野を主に担当してきたのが青年海外協力隊であった。1974年~96年の間に、90数名の青年海外協力隊員がラオスで活動してきた。欧米の先進諸国の開発NGOと異なる点は、青年海外協力隊が政府系援助機関からの派遣であり、ラオス政府から要請された職種の技術に習熟していることが派遣前から確認されていることである。今回の評価調査で隊員が派遣されているラオスの関係機関を訪問したところ、ほとんどの機関の責任者が感謝の意を表した。
近年、日本が草の根無償援助やNGO事業補助金事業を始めてから、日本の開発NGOを予算的に支援できるようになって、多少とも日本の開発NGOの活動がしやすくなったようである。ラオスでも外国の開発NGOの連絡機構が組織され、活動面での協力、経験的教訓の共有、情報交流などが行われている。このような中で、日本の開発NGOに対する認識も高まってきているという。当然、ラオスの人達の間でも日本の開発NGOの活動は評価を高めつつあるようである。
(2) 日本の援助の特徴
通常、ある国の対外援助の特徴を評価の視点から見る場合、その国の援助原則や援助方法、成果の相対的な比較、援助受入国との関係などを考慮して判断する。例えば日本に関しては、ODA5原則や要請ベースの援助方式、地域的にアジアの比重が大きい、などがよく挙げられる。
ラオスの国家開発の基礎構造から、対ラオス援助が社会開発と農村開発、借款よりも贈与が中心に、インフラ、ダム建設以外は小規模プロジェクトが多くなるのは当然であろう。
ラオスに対する日本の援助の特徴は、第1に援助の継続性である。1966年にナムグム河開発基金に資金援助して以来、社会主義政権になった後も一貫して援助を絶やさず、援助を続けてきたことである。30年を超える日本の援助の継続性をラオス側でも評価しており、日本・ラオス間の外交関係にもこのことの反映が感じられる。
第2は日本は援助を増大させて1991年以降はトップ・ドナーになっていることである。日本の援助が要請ベースであることを考えると、それだけ日本に対する要請が増大してきたことを意味する。
第3は、日本の援助における近年の変化でもあるが、援助の多様化と連携化である。援助額の増大につれて援助分野が多様化されてきた。初期にはインフラと農業開発・食糧援助に重点が置かれていたが、それぞれの分野内での多様化と社会開発や農村開発、さらには環境保全、文化開発なども加わり、また技術協力面でも量的増大と多様化が進んでいる。技術協力についてみると、ラオスに限らず大体に言えることであるが、欧米の先進諸国が被援助国側のトップの養成に重点を置くのに対して、日本の場合は、言語の関係もあるかもしれないが、相対的に実際に役立つ現場の技能者の養成を重視してきた。連携化については国連・国際機関との連携、タイとの連携援助、政府系と民間・NGOとの連携などが増えてきた。
連携は、重複の無駄を廃し、補完関係のメリットを利用できるようなものでなければならない。例えば、政府系とNGOとの連携では、政府系は小規模ながらNGOの資金不足を補い、NGOは政府系ではできない援助をする。ある日本のNGOでは、村落開発プロジェクトを実施する際に、協力の対象とする村の選択基準として、1)地理的に隔離された貧困村であること、2)構造的な後進性を抱えていること、3)主体性を持ち、自前の開発資源をも出すこと、4)開発の経験交流に参加すること、5)他の援助機関が入っていないこと、6)大型開発に関係している村は選択しないこと、などを挙げている。
(3) 日本の援助の新しい展開
日本の援助全体の傾向の中で、重要になってきたのが量から質への転換である。援助能力は量的なものと質的なものに依存する。量的な対応も必要であろうが、成果、インパクト、経済性などを厳しく問い、質的向上の努力が求められる。
国家開発計画は世界のメガトレンドをも考慮に入れて作成される。国家開発計画に対応させながら立案される個々の援助プロジェクトの中には、新しいトレンドや関連諸国の影響を受けた新しいプロジェクトが現れてくる。例えば、環境問題に対応する環境保全プロジェクトや情報化社会の波及による新しい電気通信プロジェクトなどが増えつつある。
日本の援助の増大による多角化・連携化の方向に沿って、一国的立場ではなく、援助主体間・部門間・地域間の連携援助のメリットを追求する方法が工夫されつつある。既に述べたドナー国間の連携援助の他に、社会開発・経済開発・文化開発・人的資源などの部門間の連携援助、さらには大メコン圏開発協力のようなインドシナ全域に対する地域的協力などが挙げられる。この他、NGOの国際的連携も効果を発揮しつつある。例えは、焼き畑農村プロジェクトに関する国際的なNGOの経験・意見・情報交流の場として、日本のNGOも参加しているフォーラムが存在する。
5.マクロ・レベルの総合的評価
マクロ・レベルの総合的評価をするに当たって、1)妥当性、2)効率性、3)波及効果(インパクト)4)自立発展性という評価基準から考えてみる。
(1) 日本の対ラオス援助の妥当性
援助の妥当性を、援助をめぐるニーズ(N)・資源(R)関係、援助過程での手続きという2つの視点から検討する。ラオスでは、国家開発の基礎構造と国家開発計画から、国家開発のN・R関係が明確に示される。したがってラオスの国家開発計画を見れば、どんな開発ニーズが、どんな順位で重要であったのかが確認できる。また、それらの開発ニーズに対して、日本からどれだけの援助資源が供与されてきたかは日本側の援助統計を見ればわかる。
2章では、日本が援助を開始した時点からラオスの国家開発の歴史的経緯を4つの時期に区分して、それぞれの時期のラオスの国家開発計画と日本の主要な援助プロジェクトを対照させながら、両者のN・R関係の一致性を検討した。その結果、日本の主要援助プロジェクトは大体においてラオスの国家開発計画と整合し、支援するものであった。国家が近代化を図っていく場合に、ラオスのような小国であっても、道路の幅も人口密度に比例させて日本の17分の1で良いと言うわけにはいかない。これまでの国家開発計画の中でインフラ建設は常に重要項目であったし、外国援助の重要性が大きかったものである。
援助過程における手続面から見ると、日本の援助は基本的には要請ベースで行われており、援助の押しつけ、援助受取国の開発ニーズを無視したような援助プロジェクトにならないように配慮されている。ラオス政府が正しい援助要請をしている限り、日本側の援助主体が適切に対応している限り、妥当性を欠くような援助は行われないはずである。日本・ラオス間のインフラ建設協力において、ナムグム・ダムは象徴的なプロジェクトの1つである。環境面など若干の問題は残したかもしれないが、多方面にわたるプラスの累積効果は多大のものであろう。
(2) 日本の対ラオス援助の効率性
これまでの日本の援助の中には、個々の援助プロジェクト単位で見れば、満足な成果を挙げたものもあれば、そこまで達しなかったものもあろう。いろいろな分野の援助プロジェクトを総合的に正確に判断するのは容易ではない。計量的な貢献度の計算はデータ的に無理であるため、日本の援助がそれぞれの時期のラオスの国家開発パフォーマンスや困難な国家的問題の解決に貢献できたかどうか、日本の援助とラオスの開発パフォーマンス・問題解決が同調的であったかどうかで判断する。
日本の援助の個々の援助プロジェクトの大半は、実施過程において若干の問題があったとしても、大体において所期の目的を達成していると言えよう。ラオスの国家開発パフォーマンスが顕著に高くなってくるのは、既に述べたように1980年代後半に入ってNEM採用後である。経済開発パフォーマンスは、この時期大いに改善し、日本援助もこれと同調的に軌を一にして増大していった。
しかし、このような高い経済開発パフォーマンスが実現できたのも、それ以前の道路開発や電力開発、上水道開発などのインフラ開発が功を奏したからであろう。30年前のナムグム・ダム開発があった場合と、無かった場合を比較すると、問題は抱えながらもその累積効果と波及効果の大きさが理解されよう。
社会開発に関しても、1989年と1995年を比較すると、平均寿命では49歳から51歳へ伸び、失明率は1%から0.5 %に減少した。小学校の純就学率も70%から73%に上昇しているなど、着実に社会開発が進んでいることは確実である。日本の援助においても開発開発部門は重点部門の1つになっている。貢献度を正確に計量計算することは困難であるが、貢献してきたことは確かである。
個別プロジェクトでは、効率性は、一般に、援助供与主体と援助受入主体の協力関係・条件やプロジェクト・マネジメントなどに大きく依存する。規模の大きな援助プロジェクトでは改善の余地はあろう。小規模な援助プロジェクトでは、開発NGOを支援することによって援助分野を拡大できたし、即応性が大きくなり、全体としての援助効率性を高めたと言えよう。
全体的に見て、他国と比較して、内陸山岳国・最貧国などの諸条件から若干の不利な点があること、近年では高い開発パフォーマンスを挙げていることなどを考慮して、改善の余地はあるにしても、良い援助効率であると判断して良いであろう。
(3) 日本の対ラオス援助のインパクト
国家開発の範疇には経済開発、社会開発、文化開発、政治開発、環境開発・保全などが含まれる。そして、各開発部門は密接な相互作用関係を持つ。例えば、道路・運輸、電気通信などのインフラ建設援助は経済開発のみならず社会開発、文化開発、政治開発などいろいろな部門にインパクトを与えてきた。また、経済開発と環境問題とは、ラオスにおいても密接な関係があり、両者が矛盾しないような持続可能な開発が求められている。
社会インフラの整備への支援は、国家的統合と国際関係の浸透・増大へと導く。特に縦貫国道(13号線)、横断国道(7、8、9号線など)、空港の建設は、経済・政治・文化などの国家的統合に大いに役立ったと同時に、貿易・国際交流・対外関係の重要性を増大させていった。
さらに、日本の援助の増大につれて、日本・ラオス間の国際交流・外交関係が、徐々にではあるが、増えてきたことは確かである。例えば、長期的には貿易・投資の経済交流、両国間の要人の相互訪問などが挙げられる。
日本の援助の基本的方針の1つとして、「国造りは人造りから」という考え方がある。人材開発は経済開発、社会開発、文化開発、政治開発など、ほとんどのものの基本に関係するものである。もちろん、この基本方針は対ラオス援助においても適用されてきたと考えられる。大規模プロジェクトの度に多くの技能者が育ってきており、日本人専門家のカウンターパートの中には日本で研修を受けた経験のある人達も多い。これらのプロジェクトや関係者からの技術移転の効果は小さくないと考えられる。都市化率が高く、コミュニケーション・インフラが発達し、技術移転の対象が集中している国と違って、ラオスのように、いずれの発達も遅れた分散居住社会では、技術移転の速度は遅くなりがちである。
(4) 日本の対ラオス援助の自立発展性
援助の基本的考え方は、自助努力を支援することである。自助努力には自立・主体性、技術移転、マネジメント能力などが求められる。
マクロ的に見ると、対ラオス援助の自立発展性は、大半のLLDC諸国と同じように、援助依存度が極めて高く、満足できる状態ではない。自立発展性が向上しなければ、援助従属化の傾向が心配される。近年は、国家開発パフォーマンスが良くなっているため、この水準を落とさなければ、時間はかかっても自立発展性の向上が期待できよう。自立発展性を高めていくためには、自助努力をしながら主体性を強化していく必要がある。ラオスは第6回党大会(1996年3月)において、2020年までにLLDCから脱却する目標を決議した。援助依存の高成長が長続きしないことを考慮すると、結局、マクロ指標で見た援助依存度を引き下げるほどの高成長を、長期的に持続していく必要がある。
ラオス側で外国援助を利用するのに必要な、自助努力に見合う開発プロジェクト実現資源の調達に苦労しているケースが目立つ。確かに、自助努力分の資源の十分な調達が遅れて、開発プロジェクトの実施に支障を来した件数が少なくなかった。
開発プロジェクトの自立発展性は、マクロ的には制度・体制が大きく関係してくる。ラオスはNEMの採用以来、解放・改革を熱心に推進しつつあるが、例えば水道料金、医療費、受信料、電気代などの算出、誰が支払うのか、などにいろいろな問題を抱えている。これらを含むマネジメント・システムが有効に働くようにしないと、自立発展性は図れない。この他、マネジメント・システムの問題の前に、制度的な問題を抱えた援助プロジェクトも見られた。森林保全プロジェクトにおける回転基金のように、いろいろな工夫がなされているが、このような工夫が有効に働き定着していくには、制度造りと時間が必要であろう。
今後とも自立発展性の向上には日本・ラオス間の協力と工夫によって努力することが必要であろう。
6.総括
ラオスの関係省庁の要人の意見はいずれも、日本の援助が国家開発に役立っており、今後とも日本の援助に期待しているという内容のものであった。この種のインタビューでは、ほとんどの国が感謝の意を表してくれるものであるが、大型プロジェクトが関係している官庁では、その官庁予算と比較すると日本の援助は大きな比重になるので、特別な意味が感じられた。また、援助を受けたラオス側実施機関の責任者からは、日本からの援助が大いに役立っており、今後も継続、増大を期待しているとの評価に加えて、具体的な援助要請計画を持っている機関が多かった。
個別援助プロジェクト毎に見ると、若干の問題がないわけではないが、それらの開発プロジェクトは大体において評価基準をクリアしているものと判断できる。
対ラオス援助では、人口、社会構造、文化、自然環境、国の規模・発展段階などからいって、大規模プロジェクトの他に、地域の特性に適合した小規模プロジェクトも比較的に大きな成果を挙げている。小規模プロジェクトの分野では青年海外協力隊活動や開発NGOなどが積極的な貢献をしている。
近年の日本の援助の増大・多角化・連携化の中で、新しいタイプのプロジェクトの形成が試みられている。国際間・部門間・規模間・主体間の連携もその1つであり、成果を挙げているものもある。
援助プロジェクトの形成において、特に1)自助努力の重要性、2)より効果的な新しいタイプの援助の追求、3)開発と環境の調和を図る持続可能な開発、及びそのテクノロジーの追求の重要性、が高まっている。
近年、インドシナが国際政治・開発援助の視点から世界の注目を浴びており、その中でもラオスは、LLDCで援助の需要が大きいこと、小国ゆえに援助効率が高く出ることの他、社会システムにおいても多くの問題を抱えていることなどから、国際機関、各国の援助機関、援助専門家、開発NGOなどの関心を大いに引いており、援助能力が国際競争的に問われる状況にある。
これまでの分析の結果、計量分析や評価手法に問題を含んでいるにせよ、日本の30年にわたる対ラオス援助は、ラオスの国家開発にある程度の貢献はしてきたと考えられるし、ラオス側にもこのように評価している人達が多い。

