3.4 ザンビア
3.4.1 ザンビアにおけるGIIの実施状況
ザンビアは、1997年に新たにGII重点国に加えられた国であり、GII重点国の中でも日米連携の促進にかなり比重が置かれた国の一つである31。本報告書の中では、日米連携について別途章を設けている(USAIDのコンサルタントが執筆担当)ため、ザンビアにおける日米連携については、その章を参照されたい。ただし、プロジェクト自体が日本の主要案件と考えられるものについては日米連携によるコンポーネントを含む案件も本節で取り扱った。
(1)人口直接分野(リプロダクティブ・ヘルス分野)への協力の特徴
ザンビアでは、GII対象期間の人口直接分野の日本の主要な協力は、UNFPAとのマルチ・バイ案件である「人口家族計画特別機材供与」(2000年実施)のみである。
(2)人口間接分野への協力の特徴32
人口間接分野の協力の内、保健医療分野の主要案件は、技術協力プロジェクト33の「感染症対策プロジェクト34」と「ルサカ市プライマリー・ヘルス・ケア(PHC)プロジェクト」、無償資金協力による「大学教育病院小児科改善計画」や「ルサカ市基礎医療機材整備計画」である。ワクチンやEPI分野の子どもの健康改善を目ざす分野への支援を含めて感染症対策として案件の数が多かったことが分かる。スキーム別の案件数を見ると、無償の機材供与案件がもっとも多く9件であった。次いで、無償資金協力が4件と多く、プロジェクト方式技術協力は3件(現在は2件)であった(表3.22)。
表3.22 人口間接分野の主要協力案件(1994-1999)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出所:JICA、「人口・エイズ分野実績 1993-1999」、無償資金協力については、外務省経済協力局、『我が国の政府開発援助の実施状況に関する年次報告』(94年度版-99年度版)より作成。 |
「感染症プロジェクト」と「感染症対策プロジェクト」(本プロジェクトは、2001年3月より「エイズおよび結核対策プロジェクト」として実施されている。終了は2006年。)は、トップ・レファラル施設である国立の大学教育病院(University Teaching Hospital)におけるウイルス検査室への技術協力プロジェクトであった。1989年~2000年35までの間は、同検査室におけるポリオウイルス、結核菌、インフルエンザウイルスの検査機能の向上を「感染症プロジェクト」と「感染症対策プロジェクト」の2件が支援した。このプロジェクトは、2001年3月より「エイズおよび結核対策プロジェクト」としてHIV/AIDSおよび結核に対象疾患をしぼって技術協力を開始した(2001年3月時点からは、エイズ分野への支援として分類される)。さらに同病院の小児科施設が無償資金協力で改善された。
もう一つの「ルサカ市プライマリー・ヘルス・ケアプロジェクト」(1997年~2002年)は、対照的に保健医療サービスの末端のレベルを支援している。このプロジェクトは、不法居住地域(未計画居住地域という)における住民参加型のプライマリー・ヘルス・ケアの推進を支援している。活動は、環境衛生等の保健教育、小児成長モニタリング等の啓蒙活動、患者紹介転送制度の構築、学校保健教育の実践である。
その他には、蚊帳や抗マラリア剤、車輌、検査用機材の供与を行った「マラリア総合対策」(子どもの健康無償資金協力、1998年)と、EPIのワクチンやコールド・チェーン用資材を供与が行われた。
ザンビア政府がワクチンやコールド・チェーン用資材を100%ドナーに頼っているように、GII期間中、日本はUNICEFとともに、主要ドナーの一つとなっている。(図3.16)。日本は、1995年から2001年の間に、年間全支援の内、最高で27.4%(金額換算、1996年)を支援した実績があるが、JICAザンビア事務所ではザンビアの予防接種事業の自立発展性を考慮して、支援を漸減しており、2001年の支援は7.7%にとどまった(表3.23)。
図3.16 EPI用ワクチンとその他資機材のドナーによる供給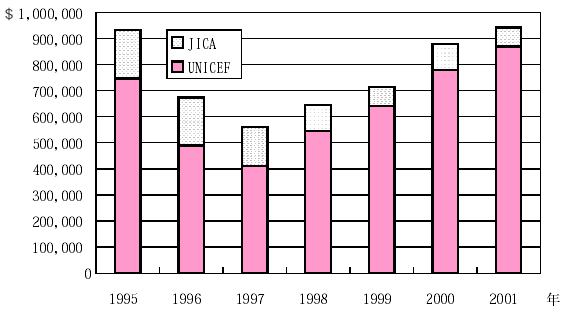 |
| 出所:UNICEFザンビア事務所作成の資料より作成 |
| 表3.23 日本の供与によるEPI用ワクチンとその他資機材の全費用に占める割合 (金額換算)
|
||||||||||||||
| 出所:UNICEFザンビア事務所作成の資料。 |
人口間接分野のサブ・プログラム別では、草の根無償資金協力を除いては、「基礎的な保健医療」への協力案件数が多かった。「基礎的な保健医療」への協力案件は主に機材供与で実施されたことが分かる。「初等教育」と「女性の職業訓練・女子教育」に対しては、案件数がそれぞれ1件と2件で、前者に対しては無償資金協力、後者に対しては機材供与による協力が実施された(図3.17)。
図3.17 スキーム別人口間接分野の協力実施件数(1994-1999)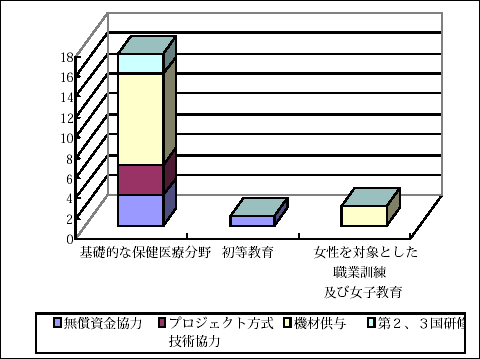 |
| 出所:JICA、「人口・エイズ分野実績 1993-1999」、無償資金協力については、外務省経済協力局、『我が国の政府開発援助の実施状況に関する年次報告』(94年度版-99年度版)より作成。 |
スキーム別の協力金額の割合を見ると、無償資金協力の4件による実施が63%と大きく、プロジェクト方式技術協力の3件による実施が32%、機材供与の9件(内7件が基礎的保健医療分野、2件が女性を対象とした職業訓練及び女子教育)による実施が5%と続いている(図3.18)。
図3.18 スキーム別金額実績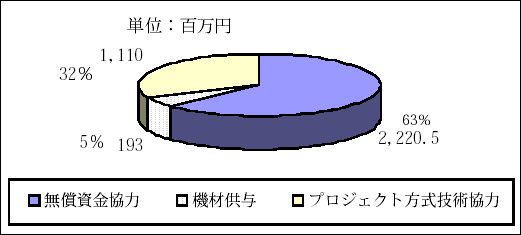 |
| 出所:JICA、「人口・エイズ分野実績 1993-1999」、無償資金協力については、外務省経済協力局、『我が国の政府開発援助の実施状況に関する年次報告』(94年度版-99年度版)より作成。 |
案件実施数を経年的に見ると、ザンビアが重点国となった1997年以降、年間案件実施数が増えている。サブ・プログラムの「基礎的保健医療」には毎年協力が実施された(図3.19)。
図3.19 人口間接分野サブ・プログラム別案件実施件数(1994-1999)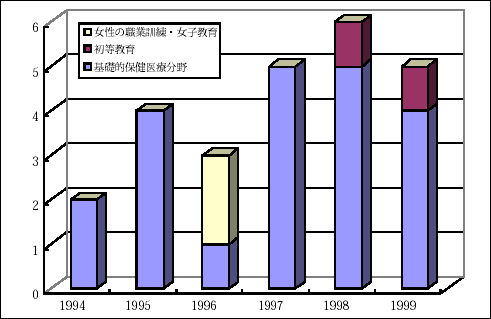 |
| 出所:JICA、「人口・エイズ分野実績 1993-1999」、無償資金協力については、外務省経済協力局、『我が国の政府開発援助の実施状況に関する年次報告』(94年度版-99年度版)より作成。 |
(3)エイズ分野
日本の協力は、NGOに対する開発福祉支援事業(1999年度)が主要な案件であり、感染予防の分野である。その他に、草の根無償資金協力によりNGOによるエイズのケア分野(「エイズ孤児」対策)を中心に支援が行われた。開発福祉支援事業では、ワールド・ビジョン・ザンビアによる感染率の特に高い国境地帯等におけるハイリスク・グループに対するエイズ予防教育プロジェクトに対する支援が実施中である(2000年3月開始、2003年2月終了予定、このプロジェクトは日米連携プロジェクトである36)(表3.24)。
表3.24 エイズ分野の主要協力案件(1994-1999)
|
|||||||||
| *本案件はエイズ及び基礎的な保健医療分野にカウントしている。
出所:JICA、「人口・エイズ分野実績 1993-1999」、無償資金協力については、外務省経済協力局、『我が国の政府開発援助の実施状況に関する年次報告』(94年度版-99年度版)より作成。 |
(4)スキームの有機的な連携
「ルサカ市プライマリー・ヘルス・ケアプロジェクト」においては、日本の無償資金協力によって給水施設が整備されていたことを基礎として同プロジェクトが保健教育を実施した。開発福祉支援事業によるWorld Vision Zambiaのエイズ分野のプロジェクトには、草の根無償資金協力により車輌等が提供された。子どもの健康無償資金協力により供与された蚊帳のソーシャル・マーケティングを行っているNGOであるソサエティー・フォー・ファミリー・ヘルスには草の根無償資金協力による機材供与が実施され、JOCVが派遣されている(日米連携案件であり、このNGOはUSAIDから支援を受けている)。
3.4.2 GII認知度
1998年の日米合同プロジェクト形成調査団派遣と、その後の企画調査員のJICAザンビア事務所への派遣を通じて、GIIはバイとマルチのドナーに認知されていた。特に企画調整員による他ドナーとの積極的な情報交換により、GIIの認知度は高まった。
3.4.3 他開発パートナーとの連携
1999年にJICAザンビア事務所に対して、案件形成とドナー調整を担当する企画調査員が派遣され、各種ドナー会合37および個別ドナーとの協議を積極的に実施した。今回訪問した全てのドナー機関(複数の国連機関、二国間ドナー)は、この企画調査員、あるいは他の日本大使館/JICA職員と情報交換の機会を持ったことがあった。このため、日本との情報交換は頻繁に行われ、連携案件も実施された。ザンビアでは、SWAPが進展しており、ドナー調整の必要性は、日本側関係者によく認識されていた。
(1)UNICEFとの連携
UNICEFとのマルチ・バイ連携(麻疹とBCGのワクチン供与、開始1989年)においては、その予防接種のノウハウを活用した援助が実施可能となった。HIV/AIDS分野においても、日本がUNAIDSに拠出した資金をUNICEFが母子感染予防プログラムで活用したという形での連携がある。他国で問題になった国連機関との連携の実施にかかる金銭面および時間面でのコスト(事務や意思決定手続きや連携に関するインセンティブの違い等から生じる)も連携を通じて高まった効率性を減ずるものではなく、問題にはなっていなかった。
(2)USAIDとの連携
日米の両国は、ザンビアにおいて日米連携(日本はGIIとして、アメリカはコモンアジェンダとして)を重点的に行うべく、1998年に日米合同プロジェクト形成調査団を同国に派遣し、それ以降の連携対象分野として以下の3分野を検討、合意した。この後、日米の情報交換と実際の連携は拡充した。なお、詳細については、本GII評価調査においてUSAIDおよびそのコンサルタントが日米連携の評価調査を担当して、第4章を執筆しているので参照されたい。
連携対象分野:
| 1) | HIV/AIDS対策及びリプロダクティブ・ヘルス(コミニュティー・レベルの活動、ハイリスク・グループへの対策、「包括的リプロダクティブ・ヘルス計画」への支援) |
| 2) | 子どもの健康(EPI及びポリオ、学校保健、飲料水等) |
| 3) | システムの強化(人口・健康指標調査、健康関連情報管理システム等) |
(3)その他ドナーとの連携
UNFPAとの間では、マルチ・バイ連携による難民支援として情報・教育・コミュニケーション教材と医療資機材の供与が実施された(スキーム:人口家族計画特別機材供与)。日本は、その他に、UNDP、USAID、DANIDA、UNFPAとの連携により人口保健調査への支援を、UNDPに日本が設置した「人造り基金」を通じて支援している38。
なお、保健省と保健分野のドナーが合同で実施した「保健改革評価調査」("Joint Identification and Formulation Mission for Zambia 2000" )に対して、我が国ノンプロ無償の見返り資金が使用されたことを附記する。
「エイズ及び結核対策プロジェクト」では、ジョイセフや国際家族計画連盟(International Planned Parenthood Federation (IPPF))との連携がある。
(4)NGOとの連携
現地NGOとの連携は、エイズ分野での開発福祉支援事業(ワールド・ビジョン・ザンビアによる「HIVハイリスク・グループ啓蒙活動」)や草の根無償資金協力、また、人口間接分野での現地NGO(蚊帳のソーシャルマーケティング等を行っているソサエティー・フォー・ファミリー・ヘルス)へのJOCV派遣を通じて大きく進展した。
人口間接分野では、プロジェクト方式技術協力の「ルサカ市プライマリー・ヘルスケア・プロジェクト」において、日本のNGOであるアジア医師連絡協議会(Association of Medical Doctors of Asia=AMDA)と「徳島で国際協力を考える会」及びAMDA ザンビアと連携があった39。「エイズ及び結核対策プロジェクト」では、ジョイセフやIPPFとの連携がある。
日本の会計年度に準拠した精算のタイミングが、複数のドナーから資金支援を得ているNGOにとっては、年に精算時期が2回あることとなり、事務負担の増加となっている例があった。一方でNGO側に日本のシステム(会計処理方法等)に対する理解と協力をNGOから得るために、日本側が多くの労力(現地レベル)を費やした。
3.4.4 評価結果(妥当性、効率性、効果、自立発展性)
(1)妥当性
ザンビアでは、1991年に保健セクター改革40が開始された。SWAPがすでに導入され、過去に高次レベルの病院に偏重していた資源投入を住民に近いヘルス・サービスに転換し、支払い可能で効果の高い必須サービス・パッケージの提供をDALYs41に基づいて進めている。1996年の保健省データによれば、主要疾患は、マラリア、急性呼吸器感染症、HIV/AIDS、下痢症、周産期に起因する疾患・障害、結核、栄養障害であった42。これに対して必須サービス・パッケージには、基礎的な治療と予防活動、家族計画、栄養改善が含まれている43。
コモン・バスケット型の協力の一つとしてディストリクトに対するディストリクトバスケット・ファンドが1994年より稼働中である。その運営は良好44で、2000年時点で参加しているドナー機関の数は10機関に上る。保健予算全体をカバーするバスケット・ファンドの設立が目指されている45。
a.人口直接分野
人口直接分野への協力はプロジェクトが1件と件数が少ないためプログラムとしての評価はしない。
b.人口間接分野
日本の人口間接分野に対する協力は、ザンビア政府の保健分野の開発課題と保健セクター改革に対して、全体としては妥当性があった。日本の協力は、健康負担の大きい疾病を対象とした点(プロジェクト方式技術協力の「感染症対策プロジェクト」による結核菌検査室の機能向上、無償資金協力によるマラリア対策)、そして、必須サービス・パッケージの提供推進と一部が重なるアプローチ(「ルサカ市プライマリーヘルスケアプロジェクト」)をとったという点から妥当性がある46。
日本とUNICEFとのマルチ・バイ連携案件(ワクチン供与等)も、UNICEFがザンビア政府とともに作成したカントリー・プログラムを日本が支援したと理解でき、妥当性が高かった。「ルサカ市プライマリー・ヘルス・ケアプロジェクト」が、ディストリクトの保健行政を所轄するディストリクト・ヘルス・マネージメント・チームをカウンターパートとした、活動の一部として能力強化を図ったことは、保健セクター改革の中でディストリクトへの分権化が推進されている点で妥当性が高い。
日本の援助スキーム面から妥当性を検討すると、ほとんどの他ドナーの支援はコモン・ファンドへ移行する傾向にあることから、日本の援助は、コモンファンドへの参加に制約があり、その妥当性は高いレベルにあるとは言えない。なお、現地レベルでは、セクター改革やSWAPの進展に伴い、JICA業務がセクター改革やSWAPの枠組みの中で位置づけられるように配慮を行っている。
c.エイズ分野
ザンビアでは、1984年に国内初のエイズ患者が発見されて以来、HIV感染とエイズの発症が拡大した(図3.20参照)。
図3.20 ザンビアにおけるHIV感染とAIDSの拡大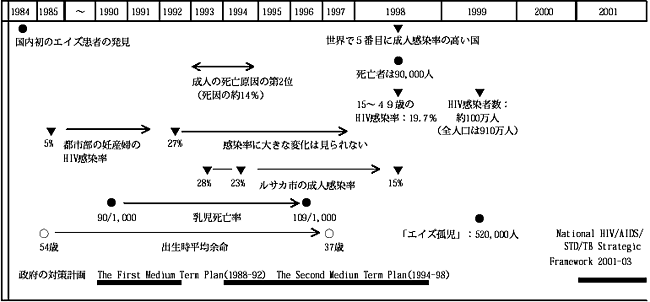 |
| 出所:HIV/AIDS/STD/TB Council, "Strategic Framework 2001 -2003", P.4, 15, UNAIDS, WHO, "Zambia Epidemiological Fact Sheets on HIV/AIDS and sexually transmitted infections 2000 Update(revised)", Ministry of Health/Central Board of Health, "HIV/AIDS in Zambia: Background Projections Impacts Intervention", 1999, P.15, 17, 国際協力事業団医療協力部、『ザンビア国 エイズおよび結核対策プロジェクト短期調査報告書』、平成12年12月、P.15より作成。 |
1993年、1994年の段階で、エイズは成人の死亡原因の第2位(死因の約14%)となった。1998年には、死亡者は9万人と推測された。1999年のHIV感染者数は、約100万人(全人口は約910万人)となり、1999年末の時点では、世界で5番目に成人感染率の高い国であった47。エイズの流行により出生時平均余命は、1980年代半ばの54年から1998年の37年へと大幅に低下した48。両親もしくは片方の親を失った「エイズ孤児」は、1999年には52万人に上った49。このような大きな健康負担となったHIV/AIDSは、健康問題にとどまらず、ザンビアの経済50、社会に負の影響をもたらしている。
一方、ルサカ市内の若年人口(15~19歳)の間では、感染率が1993年には28% であったものが、1994年には23%、1998年には15%と減少した。これは、エイズ予防教育が効果を発揮し、若年層に行動変容が起きたものと見られているが、さらなる検証が必要である51。
GII期間中の政府のエイズ対策計画は、「第2次中期計画」 (1994 - 1998)(MTP II)と「ザンビア国家HIV/AIDS, 性感染症、結核戦略枠組 2001-2003」である(表3.25)。最初の計画であ「第1次中期計画」 (1988 - 1992)の期間に15~49歳の人口集団の感染率は約18%に達し、この計画に対する反省52を基に、MTP IIが策定された。MTP II では、エイズとSTD、結核の対策プログラムが統合され、マルチ・セクターによる取組として、すべての政府省庁と民間セクター、市民社会、エイズ患者がプログラムに参加し、エイズ対策に一層の努力が注がれた53。現在の政府対策としては、「ザンビア国家HIV/AIDS, 性感染症、結核戦略枠組 2001-2003」があり、前の対策計画の枠組みを引き継ぎ、HIV/AIDSの予防と影響の緩和に対するマルチ・セクターによる取組みを採用している。各種介入により、1)エイズ/STDの感染防止、 2)HIV/AIDSによる社会経済的なインパクトの軽減、3)政府の最高レベルも含めたすべてのレベルでの国内外の資源の導入、を目指している54。
表3.25 GII期間のザンビアにおけるHIV/AIDS対策プログラムの重点
|
|||||
| 出所:HIV/AIDS/STD/TB Council, "Strategic Framework 2001 -2003", P.15-18より作成。 |
上記のこれまでのザンビアのHIV/AIDSによる健康負担と政府対策の展開に対して、日本のGIIによる協力の妥当性を検討すると、主要な協力の開始時期(1998年以降)がMTP IIの時期と一致しており、ザンビア政府自体がHIV/AIDS対策に一層注力を開始した時期でもある。また、日本の協力の内容は、ザンビア政府が重点を置いた予防分野であり、かつ、その中でも特に重要視された要素(表3.25の「1)HIV/AIDSの予防」の内容を参照)に対する活動であった。このため、日本の協力はザンビアのHIV/AIDS対策の課題と政府の政策に対して妥当性が高かったと言える。
(2)効率性
a.人口直接分野
人口直接分野への協力はプロジェクトが1件と件数が少ないためプログラムとしての評価はしない。
b.人口間接分野
人口間接分野の協力は全体として、一定の効率性を確保できた。理由としては、日本のNGOおよび現地NGOとの連携やUNICEFとのマルチ・バイ連携から、NGOやUNICEFのノウハウを生かした援助の実施につながり、効率性が高まったことが挙げられる。NGOとの主要な連携としては、1)「ルサカ市プライマリー・ヘルス・ケアプロジェクト」における日本のNGOおよび現地NGOとの連携、2)子どもの健康無償資金協力により供与された蚊帳のソーシャル・マーケティングを行っているソサエティー・フォー・ファミリー・ヘルスとの連携がある。
また、スキームの有機的連携も効率性の向上に貢献した。「ルサカ市プライマリー・ヘルス・ケアプロジェクト」においては、日本の無償資金協力によって給水施設が整備されていたことを基礎として同プロジェクトが保健教育を実施したため、効率性が高まった。ワールド・ビジョン・ザンビアのエイズ分野のプロジェクトには、草の根無償資金協力により車輌が提供された。ソサエティー・フォー・ファミリー・ヘルスは、無償資金協力により供与された蚊帳をソーシャル・マーケティングしているが、このNGOに対して草の根無償資金協力により機材供与が実施され、JOCVが派遣されている。
費用対効果については、2件のプロジェクト方式技術協力は人口間接分野に占める投入額の割合が大きい(1995~99年までの同分野に対する投入の約32%、金額は約11億円)点から費用対効果の検証が求められる。現時点では、合計金額の支出内訳および他ドナーの同様プロジェクトの金額と支出内訳の詳細なデータがないため最終的な結論づけは難しいが、効率性は十分に高いとは言えない可能性がある。その理由としては、以下の点が指摘できる。「感染症対策プロジェクト」は実質的には1980年代からの継続案件であるためODAの総投入規模は相当大きいものとなる55が、その費用対効果はウイルス検査室機能向上で測ることに留めるべきか議論の余地がある56。「ルサカ市PHCプロジェクト」では、実施している個別介入自体は費用対効果が高いと一般的に認識されているが、人口が4万8,000人(1996年、JICA資料より)という1地域に集中的な投入(日本人の人件費も含む)が行われており57、全体的な投入と成果の比較で見れば効率性が高いとは言えない可能性もあり、さらなる検証が望まれる。
c. HIV/AIDS分野
日本の協力は、ザンビアにおけるHIV/AIDSによる各種問題の深刻化と、それに伴う政府対策が転換した時期に実施され、時宜を得ていた。また、GIIのプロジェクト形成ミッションが1998年12月に派遣され、その後、短期間でHIV/AIDS分野での協力が拡大した点からは、プログラムとして見た場合に実施が効率的に行われたと言える。
日本の協力は、おおむねNGOの活動を通じてコミニュティ・レベルに対して実施されたが、エイズ分野(予防、ケア)ではコミニュティ・レベルの活動が重要であるため、効率性が高かった。また、日本の予防分野の協力において、ハイリスク・グループや血液の供給分野を活動の対象としたことは効率的予防を実現させた。NGOとの連携は、エイズ分野への協力に関する日本自体のノウハウが限定的であっても、日本が協力実施することを可能とした。
(3)効果
a.人口直接分野
上記のように、ザンビアにおいては人口直接分野への日本の協力が1件のみ(マルチ・バイ案件の消耗品供与)であるため、それによる国全体のリプロダクティブ・ヘルスの改善に対する効果は検討していない。
b.人口間接分野協力
人口間接分野の協力は、GIIの「包括的アプローチ」では、リプロダクティブ・ヘルスの改善にも貢献するという論理展開になっている。このため、ザンビアがGIIの重点国に指定された1997年以降GII期間終了までの間に、ザンビアでのリプロダクティブ・ヘルス関連の主要で入手可能であった基礎的指標の変化を表3.26に示した。
表3.26 1997年のザンビアでのリプロダクティブ・ヘルス分野の基礎指標の変化
|
|||||||||||||||
| 注:出産前検診の受診率や訓練を受けた人材による分娩介助の割合は入手できなかった。
出所:UNICEF, 「世界子供白書」、1998年版、1999年版、2000年版、2001年版。 |
表3.26から妊産婦死亡率および乳児死亡率には、1997年以降の4年間に変化がないことが分かる。最大の理由としては、これらの指標の変化を検証するにしては、対象期間が短すぎるためである。通常、これらの指標に変化が生じるには長い期間を要する。経済や教育の状況の変化により人々の健康の状態も変化することは知られるところであるが、何故、変化がなかったのかを明らかにするためにはより詳細な調査が必要である。妊産婦死亡率は一般的に改善されるまでに多くの時間を要すると理解されているため、この4年間を中心に前後の期間にわたりさらに長期的に検証すれば変化が出ていることが考えられる。また、乳児死亡率に改善が見られない理由としては、HIV/AIDSのネガティブな影響が推定される。
また、日本の協力が健康の改善にどれだけ貢献したかを測るためには、詳細な調査が必要となるが、GII評価調査においては、期間等の制約から詳細な調査は実施できなかった。
しかしながら、可能な範囲による検証から、日本の人口間接分野協力は、国レベルに対してある程度のポジティブな効果を与えた。その理由としては、以下が挙げられる。
「感染症対策プロジェクト」(1995-2000年)では、ウイルス検査室の機能強化を支援してきた。ウイルス検査室のポリオウイルスとインフルエンザウイルス検査に対してWHOから認証が得られた。結核検査室では抗酸菌培養と薬剤感受性試験の実施が可能となった。今後は、この中央のトップレベルでの効果をどのように全国的に波及させ58、ザンビア国民の健康の改善に寄与させていくかが課題となる。
日本のEPI分野への協力は国家レベルに対する直接的支援であり、国レベルへの満足できる程度のインパクトがあった。日本はBCGのワクチン供与を実施したが、日本の供与が実施された期間(1989年以降)、BCGのカバー率は常に85%を越えていた。近年さらに向上が見られ、1999年の87%から2000年には99%となった。一方、日本による麻疹のワクチン供与支援があったものの、麻疹の予防接種カバー率は近年下降が見られる。1996年に93%であったものが、1997年には78%に、1998年と1999年にはそれぞれ73%、72%へと下降している59。この原因としては、政府の継続的な資金不足により、ディストリクトレベルでEPI対策資金が不足するため、対策に必要な資機材の確保や人材育成が十分に出来ないことにあるとUNICEFでは見ている60。
他方、ザンビアにおける初等教育や女性支援も含めた人口間接分野の全体の協力が、人口直接分野にどの程度インパクトを与えたのかについては、時間的、データ的な制約から検証できなかった61。また、ザンビアにおける1997年から2001年までの4年間の初等教育や女性支援に関する状況の変化を検証するための指標は、入手できなかった。
c.エイズ分野
無償資金協力による「安全な血液供給」のための機材供与案件は、確実なHIV感染予防につながり、国レベルでの効果を上げたと言える。しかし、その他のプロジェクトは開始後まだ間もないため、エイズ分野の協力全体をプログラムとして見た場合の効果を評価することは尚早であるが、日本が開発福祉支援事業で支援しているワールド・ビジョン・ザンビアの活動は表3.27の通り活発化している。
表3.27 ワールド・ビジョン・ザンビアの活動実績
|
||||||||||||
| 出所:GII評価調査団のアンケートに対する回答より作成。 |
(4)自立発展性
a.人口直接分野
人口直接分野への協力はプロジェクトが1件と件数が少ないため、プログラムとしては評価しない。
b.人口間接分野
「感染症対策プロジェクト」において供与されてきた機材の維持管理が財政面で困難となると考えられる。「ルサカ市プライマリー・ヘルス・ケアプロジェクト」では1つの地域に対して集中的投入(人材面、予算面)が行われたため、同様の内容のプロジェクトの実施は日本のODAなしでは難しい。これらの点から、人口間接分野のプログラムの自立発展性が十分に確保されているとは言えない62。しかし、技術面の自立発展性は、プロジェクト方式技術協力の2件のプロジェクトともに高い(検査室への技術移転、住民参加の推進方法等の各種ノウハウの行政における蓄積等)。
c.エイズ分野
日本の協力によって供与された物品のほとんどが消耗品であることから、供与品についての自立発展性は論じることができない。また、NGOとの連携案件は、開始後間もないため自立発展性を論じる段階にない。
3.4.5 今後の協力のあり方
(1)保健連携専門の担当職員(企画調査員もしくは専門家)を配置することは、緊急課題である。他ドナー、特に米国は保健分野の専門家を複数配置しているため、日本との連携事業を行う際にも日本よりも多くのリソースを動員することが可能である。このため、事業の進展において、日本との実務処理の能力とスピードに差が出て、連携に影響することもある。コモン・バスケットへの資金投入の制約のある日本としては、専門担当職員を通じてコモン・バスケットに参加しているドナーも含めた援助協調に関する情報を引き続き収集し、かつ、日本の援助について具体的な情報(スキーム紹介のパンフレット等の広報的なレベルではなく)を発信し、援助の効率、効果の改善に資する連携を実施すべきである。
(2)今後、コモン・バスケットの追加的設置の可能性もあることから63、ドナーによるこのシステムへの移行がさらに進展し、それが保健省およびディストリクト保健委員会にとってさらに主流化した場合に、日本が保健省およびディストリクト保健委員会とどのように連携していくべきか、さらに、今後いつまで「セクターの開発戦略に沿った協力を実施すれば、コモン・バスケットへ投入は行わなくともいい」という論理に依拠した援助実施がどの程度可能か十分に検討する必要がある(そのためにも保健セクターの援助調整担当の職員の派遣は不可欠である)。
(3)ザンビアが保健セクター改革として分権化を推進している中で、分権化後に市民サービスの決定や提供の主体となるディストリクトレベルに日本の協力の効果を波及させることが課題である。
31 1998年には日米合同プロジェクト形成調査団が派遣され、その後の日米連携の枠組みが合意された。1999年には同調査団からの提言を受けて、日米連携の促進と援助協調を担当する企画調査員がJICAザンビア事務所に派遣された。
32 2000年度には、プロジェクト方式技術協力の「エイズおよび結核対策プロジェクト」が開始されているが、本項での分析の対象はデータの関係上、1999年度までとなっている。
33 GII期間中には、3件のプロジェクト方式技術協力が実施された。
34 本プロジェクトは、2001年3月より「エイズおよび結核対策プロジェクト」(2006年終了)として実施されている。
35 1980年に開始された同検査室への技術協力プロジェクトを出発点としている。
36 このプロジェクトは、USAIDのグローバル/リージョナル・レベルのプロジェクトにも組み込まれている。
37 課題別ワーキンググループ(HIV, マラリア、EPI、学校保健)の会合は、1カ月に1回程度開催されおり、各ガイドラインの策定や援助調整を行っている。ザンビア側とドナー側の双方が参加している。
38 GIIの実績として算入されているか不明。
39 同プロジェクトは、マイアミ大学、ネブラスカ大学とも連携がある。
40 1996年の保健セクター改革では、保健省は政策立案機関として、保健医療サービスの提供は保健省監督下の中央保健審議会(Central Board of Health)が所轄することとなった。
41 Disability Adjusted Life Years。「障害を調整した人生年数」、詳細については、世界銀行、『世界開発報告 1993』を参照。
42 Ministry of Health, "National Health Strategic Plan 2001-2005", P.20.
43 World Bank, "Report No. PID1084".
44 豊吉直美、『企画調査報告書(ザンビア共和国・保健医療)』、2001年12月。
45 目標達成までの移行期間における支援手段として従来のプロジェクト型支援、技術協力支援、資機材供与が認められている。豊吉直美、『企画調査報告書(ザンビア共和国・保健医療)』、2001年12月。
46しかし、必須サービス・パッケージの提供の全体的戦略とは高い妥当性があったわけではない。「ルサカ市PHCプロジェクト」では、人口が約4万8,000人(ジョージ地区、1996年時点)の地域に対してODAによる集中的投入によるサービス提供が行われており、財政難の中でザンビアのディストリクトが必須ヘルス・サービスの提供を推進するというヘルスセクター改革とは資源分配方針に関して違いが大きい。
47 国際協力事業団医療協力部、『ザンビア国 エイズおよび結核対策プロジェクト短期調査報告書』、平成12年12月、P.15。
48 HIV/AIDS/STD/TB Council, "Strategic Framework 2001 -2003", P.4.
49 同上。
50エイズとエイズ関連の合併症の発症は、1997年には20歳~49歳という働きざかりの人口集団に多い。Ministry of Health/Central Board of Health, "HIV/AIDS in Zambia: Background Projections Impacts Intervention", 1999, P.17.
51 Ministry of Health/Central Board of Health, "HIV/AIDS in Zambia: Background Projections Impacts Intervention", 1999, P.15.
52 対策計画では、8つの重点分野を選定した(1)結核・ハンセン病、2)IEC、3)カウンセリング、4)検査体制支援、5)疫学・研究、6)STDと臨床ケア、7)プログラム管理、8)家庭におけるケア)が、医療の領域では納まらないHIV/AIDSに対しては不充分であり、保健以外のセクターも含めたマルチ・セクターの取組と調整が必要であったと分析された。National HIV/AIDS/STD/TB Coundil, "Strategic Framework 2001 -2003", P.15.
53 HIV/AIDS/STD/TB Council, "Strategic Framework 2001 -2003", P.15.
54 HIV/AIDS/STD/TB Council, "Strategic Framework 2001 -2003", P.15.
55 1995年から1999年までの投入に限ってみると、この間は「感染症プロジェクトII」の最終年と「感染症対策プロジェクト」の3年間で約6億1千万円である。
56 理由は、末端の医療サービスレベルにおいては需要の多い、簡単な技術で安価で実施可能な検査が量的/質的に十分ではない現状があり、また、国際保健協力においては、相手国の健康問題改善にもっとも効果的で費用対効果の優れた介入を行うべきという基本的認識があるためである。なお、検査機能に対する投入である場合は、検査数の増加、検査の精度の向上から成果を測ることも可能である。
57 1997年から1999年の3年間のこのプロジェクトの投入金額は、約4億8千万円である。UNICEFのプログラムである"Water, sanitation & health education" (1997年~2001 年)は、5年間の投入金額が約927万ドルで、1年あたり約185 万ドルとなり、3年間では約555万ドルである。UNICEFがこのプロジェクトとは異なる省庁をカウンターパートとしていることや、プロジェクト期間の後半になると他ドナーとの連携しているため最終的な裨益人口のうちどこまでがUNICEFの資金のみでカバーされているか判明していないために、UNICEFのプロジェクトとの単純な比較はできない。UNICEFのプロジェクトでは期間終了の1年前の2000年には対象地域の内、10のディストリクト(ディストリクトの数はザンビア全体では72ある、よって10/72がカバーされた)において90%の手動ポンプが適正に稼動し、当初200 か所であった家庭用トイレが22,000か所となった。
58 プロジェクト実施中に検査室の検査技師以外に対してもワークショップが複数回開催された。これらのワークショップが全国レベルへの普及のためのメカニズムを備えていたとは言い難い。
59 UNICEFザンビア事務所の資料。
60 同上。
61 人口間接分野のプロジェクトの専門家とカウンターパートの中には、間接分野から直接分野へのインパクトはなかったという見解の人もいる。
62 同プロジェクトには、現地NGOであるAMDA ZAMBIAとの連携があるため、このNGOが活動のノウハウを獲得して、今後も活動を実施させていく可能性もあるが、活動資金の確保の問題が明確ではないため、自立発展性については未知数である。
63 GII評価調査団によるDANIDAの専門家へのインタビューから。

