3.3 バングラデシュ
3.3.1 GIIの実施状況
(1)人口直接(リプロダクティブ・ヘルス)分野への協力の特徴7
表3.8に人口直接分野の主要プロジェクトを示した。プロジェクト方式技術協力「リプロダクティブ・ヘルス人材育成プロジェクト」(1999年開始)をコアとして、無償資金協力(左記のプロジェクト方式技術協力の実施場所となっている「母子保健研修所」の建設等)、NGOとの連携(現地NGOに対する開発福祉支援事業、本邦NGOに対する開発パートナー事業)、JOCV等の各種スキームの有機的組み合わせによる協力を実施してきた。これによって、中央レベルからコミニュィ・レベルまで日本の協力によってカバーすることが可能となっている。
プロジェクト方式技術協力の開始以前には、JOCVのグループ派遣による「フロントライン母子保健活動計画」が実施されており、JOCV隊員(看護婦、保健婦、助産婦)が郡の保健局、もしくは家族計画局に配属され妊産婦検診の推進、思春期保健教育等の活動をフィールド・レベルで実施していた。これを通じてJICAの協力はコミュニュティ・レベルにも届いていた。
草の根無償資金協力では、母子保健と家族計画を組み合わせたタイプによる診療所への支援が多かった。これらは、リプロダクティブ・ヘルス全体への支援として分類した。
表3.8 人口直接分野の主要案件(1994-1999)
|
||||||||||||||||||||||||
| *本案件は直接/間接分野両方にカウントしている。
注:本表作成に使用したデータには、バングラデシュに対する人口直接案件は1994、1995年は含まれていない。 出所:JICA、「人口・エイズ分野実績 1993~1999年」、JICA、www.jica.go.jp |
サブ・プログラム目標別に見ると、「安全な妊娠出産」に対する支援が大きく、それに対する支援のスキームでは、機材供与が多いことが分かる(図3.12)。
図3.12 スキーム別人口直接分野の協力実施件数(1994-2001)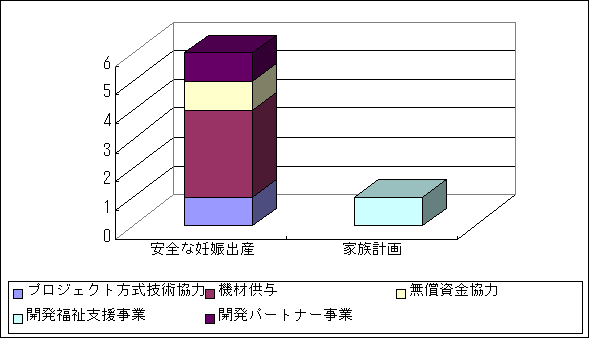 |
| 出所:JICA外務省経済協力局調査計画「我が国の感染症対策協力」 |
安全な妊娠出産分野の支援はGII期間の後半になって開始され、実績合計では、もう1つのサブ・プログラムの家族計画分野の合計よりも圧倒的に大きいことが分かる(表3.9)。特に1998年は、JOCVのフロントライン計画に対する機材供与と母子保健研修センターの施設改善のための無償資金協力が実施されたため、金額が大きく伸びている(表3.9)。2000年度になると、安全な妊娠出産分野において、新たに開発パートナーシップ事業が開始されたため、その分の金額が増加している。
表3.9人口直接分野主要案件のサブ・プログラム目標別金額 単位千円
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出所:JICA、「人口・エイズ分野実績 1993~1999年」。無償資金協力金額は、外務省、『我が国の政府開発援助の実施状況 1999年度に関する年次報告』。 |
(2)人口間接分野への協力の特徴
表3.10に人口間接分野の1993年から1999年の主要案件を示した。主要案件は、機材供与によるEPIのワクチン供与やポリオ根絶計画支援などの案件(UNICEFとの連携案件を含む)や、農村婦人研修所建設計画等である。研修案件(「リウマチ熱・溶連菌感染・心疾患抑制」)案件を除いて、スキームは、全てが機材供与案件となっている点が特徴的である。なお、表3.10には含まれていないが、ポリオ根絶計画支援としてのJOCVの派遣(1999年に4名、2000年に1名、派遣期間2年間)が行われ、コミニュティ・レベルでの接種率の拡大を図った。
草の根無償資金協力も多く実施され、GIIに直接的に関連する案件として分類される案件数は18件に上る。サブ・プログラム目標で分類すると、「基礎的保健医療分野」への支援がもっとも多く、16件となり、「女性を対象とした職業訓練および女子教育」分野への支援が1件、リプロダクティブ・ヘルス分野と女性の職業訓練の両方にわたる支援が1件となっている。草の根無償資金協力は全体として75件あるため、上記以外にもGIIと分類できる案件の存在する可能性もあるが、正確なデータはない。
表3.10 人口間接分野の主要案件(1994-1999)
|
|||||||||||||||||||||||||||
| *本案件は人口直接/間接分野両方にカウントしている。
出所:JICA、「人口・エイズ分野実績1993~1999 年」、無償資金協力については、外務省、『我が国の政府開発援助の実施状況(1999 年度)に関する年次報告』 |
草の根無償資金協力案件以外をサブ・プログラムで分類すると、人口間接分野の内、実施案件数が多かったのは、「子どもの健康」分野(5件)であり、次いで「基礎的な保健医療」分野(3件)であった。「女性を対象とした職業訓練および女子教育」分野は、1案件のみしか実施されなかった。「子どもの健康」分野における支援内容としては、機材供与がもっとも多く、それは、麻疹のワクチン供与など予防接種分野での支援である。
これを金額面から経年的に示したのが、図3.13である。「子どもの健康」分野の案件は、金額面でも人口間接分野の協力において大きな割合を占めている。「基礎的な保健医療」分野は、1996年と1997年に実施されたが、その後実施されていない。「女性を対象とした職業訓練および女子教育」の1案件が実施されたのは1998年であり、同年の人口間接協力全体金額のわずかを占めるに留まった。
図3.13 サブ・プログラム目標別の協力実績(1996-1999)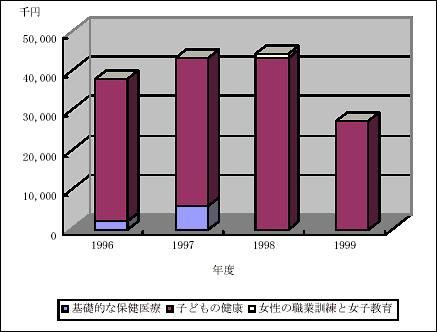 |
初等教育分野では、NGOに対する草の根無償資金協力とグラミン銀行に対する有償資金協力が実施された。
(3)エイズ分野への協力の特徴
バングラデシュにおいては、HIV/AIDSにかかる健康問題が未だ顕在化していないため8、日本が本格的な支援を開始するに至っていない。2000年からNGOへの草の根無償資金協力を開始し、現在までに2件の実績がある。
(4)各種スキームの組み合わせ
JOCVがグループ派遣されて、リプロダクティブ・ヘルス分野の活動(人口直接)、ポリオ、EPI分野(人口間接)での活動を実施してきた。これらの分野においては、JOCVのコミュニティ・レベルで活動が展開できるというメリットが生かせる。特に、ポリオやEPIのような住民の活動参加が重要な分野では、隊員が現地語を話し、村で生活している点は、住民の参加促進に大きく貢献した。この点は、保健省および他ドナーから高く評価されている9。
3.3.2 GIIの認知度
GIIは、日本の援助関連機関(大使館、JICA、JIBIC)では認知されている。JICAのプロジェクトに派遣されている専門家の間では、担当プロジェクトがGIIに分類されているか否かについて認知度が低い。
1999年度に日米合同プロジェクト形成調査団が派遣されたため、政府およびドナー機関を訪問したため、当時から在職していた担当者であれば、GIIを認知していた。しかし、担当者がその時点以降に替わっている機関においては認知されていなかった。
一方、国連機関では、本部からの通知や日本が開催した「感染症対策沖縄国際会議」を通じてIDIを認知していた。
3.3.3 他開発パートナーとの連携
プロジェクト・レベルでの他ドナーとの連携は、JICAプロジェクト方式技術協力の「リプロダクティブヘルス人材開発プロジェクト」で非常に活発に実施されている。UNICEFやUSAID等の援助機関以外に、バングラデシュにおける最大のNGOであるBRAC10とも、同プロジェクトの研修にBRACの診療所のスタッフの参加を通じて連携している11。
(1)バングラデシュ政府保健省
GIIの実施期間中に全体としては、バングラデシュ政府(保健省、援助調整窓口機関12)と日本側の関係機関(日本大使館、JICA)との対話や協議が増加したということはなかった。しかし、GII最終年度において、日米合同プロジェクト形成調査団がバングラデシュに派遣され、大蔵省対外調整部13に対して、GII自体と今後の日本の同分野でのバングラデシュへの協力方針を説明した。また、それをきっかけに現地の日本側関係者が積極的に協議の場を持ち、日本側とバングラデシュ政府との対話が進展した。
(2)UNICEFとの連携
バングラデシュにおける日本とUNICEFの連携(ポリオ根絶キャンペーン、EPI等)は、非常に活発14であり、連携によるポジティブな結果も得られ、GII全体の中で他ドナーとの連携の「ベスト・プラクティス」に含めることができる(第5章、5.4を参照)。UNICEFダッカ事務所としては、日本との連携が、栄養分野(日本はヨード欠乏症対策分野において、すでにUNICEFと連携を開始している)、バングラデシュで緊急の健康問題となっている地下水ヒ素問題15、基礎教育分野においても拡大することを期待している。
(3)USAIDとの連携
バングラデシュに対しては、1995年に人口・エイズ分野に関する「日米合同プロジェクト形成調査団」が派遣された。2000年2月にも、人口・エイズ分野の人口・保健分野への国際協力における日米協調の方向性を探ぐるために、「日米合同プロ形調査(第二次16)」が派遣された。調査の結果、「日米合同プロ形調査」では、現地レベルでの連携をさらに強化し、双方のプログラムの有機的な連携をはかることが合意された。
さらに、日米および現地の国際機関事務所との協議の結果、以下の6分野において日米が適当な案件実施17の可能性を検討していくことが決定された。この後、日米の情報交換と連携をはかる動きが一定期間熱心に続けられた。詳細については、本GII評価調査においてUSAID およびそのコンサルタントが日米連携の評価調査を担当して、第4章を執筆しているので参照されたい。
案件実施可能性を日米が検討することとなった分野:
| 1) | ポリオ根絶キャンペーン |
| 2) | EPI |
| 3) | リプロダクティブ・ヘルス |
| 4) | HIV/AIDS |
| 5) | 微量栄養素 |
| 6) | 国際下痢症疾患研究センター (International Center for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh (ICDDR,B)18)への支援 |
(4)その他ドナーとの連携
バングラデシュの保健セクターにおいては、SWAPが1997年から進展しており、SWAPに基づいたバングラディッシュ政府の保健・人口セクタープラン(Health and Population Sector Plan:HPSP)が1998年より実施された19。この動きの推進に積極的なドナーは、DFID20や北欧諸国のドナーである。これらのドナーは、SWAP自体がドナー調整を基礎とするアプローチであるため、HPSPの実施(モニタリングや評価も含め)の各局面において、定期的/非定期的、公式/非公式な協議を通じて密接な連携を実施している。HPSPに関する協議としては、ドナーのみの協議とドナーと政府による協議がある。
日本大使館およびJICAバングラデシュ事務所は、現時点ではプール・ファンディングへの参加が困難である等の理由によりSWAPには積極的に関与していない。USAIDもプール・ファンディングへの参加が困難であるためにSWAPには参加していないが、HPSP関連の協議には参加して、内容をUSAIDダッカ事務所の事業に反映させるべく積極的な情報収集を行っている。なお、SWAPに積極的に関与しているドナーからは、関与していないドナーに対してもSWAPの進展状況、モニタリングや中間評価に関して電子メールによる情報発信が行われている。
(5)国連機関との連携
プロジェクト・レベルでは、「リプロダクティブ・ヘルス人材開発プロジェクト」とUNFPAとの間での情報交換を中心として実施されている。「マルチ・バイ」による日本との連携は実施されていなかった。
バングラデシュにおいて日本のHIV/AIDSへの取組みは、同分野への協力内容の項で述べた理由により未だ限定的であるため、HIV/AIDS分野での他ドナーとの連携は実現していなかった。
(6)NGOとの連携
NGOとの連携は、JICAの開発福祉支援事業と開発パートナー事業、また日本大使館による草の根無償資金協力において実現された。JICAの開発福祉支援事業では「地域住民参加型家族計画プロジェクト」(NGO:バングラデシュ家族計画協会)、開発パートナー事業では「リプロダクティブ・ヘルス地域展開プロジェクト」(NGO:ジョイセフ)が実施された。草の根無償資金協力については、本節3.3.1の(1)、(2)、(3)を参照されたい。
3.3.4 評価結果(妥当性、効率性、効果、自立発展性)
バングラデシュにおいては、HIV/AIDSにかかる健康問題が未だ顕在化していないため、日本が本格的な支援を開始するには至っていないことから、エイズ分野の協力については限定的な評価に留めた。
(1)妥当性
a.人口直接分野
バングラデシュにおける人口直接分野、すなわちリプロダクティブ・ヘルス分野のニーズはGII全期間を通じて非常に高く、これに対する日本の取組みは妥当性が非常に高い。特に、GII期間終了近くに開始されたプロジェクト方式技術協力(実施中)は、バングラデシュの母子保健政策との妥当性が高い。表3.11に、GII期間中のバングラデシュの国家開発計画のリプロダクティブ・ヘルス分野に関連する目標、戦略概要を紹介する。
表3.11 GII期間中のリプロダクティブ・ヘルス分野に関連する目標、戦略概要
|
||||
| 出所:バングラデシュ「第4次5カ年計画」、「第5次5カ年計画」、HPSPより本調査団作成。 |
プロジェクト方式技術協力の「リプロダクティブ・ヘルス人材開発プロジェクト」は、以下の点からバングラデシュの保健開発政策に対しても妥当性が非常に高く、女性のリプロダクティブ・ヘルスに大きく貢献することが期待できる。このため、このプロジェクトは、日本のリプロダクティブ・ヘルス分野の協力の核と位置づけることができる。
- 母子保健研修センターが同分野の人材育成のコアの機関である
- 育成対象者が地域レベルで活動する人材である
- HPSPにおける人材育成を視野に入れた活動を展開している
b.人口間接分野
バングラデシュでのEPIやポリオ根絶キャンペーン分野のニーズは非常に高く、特にポリオ根絶の日本の大規模な協力は、保健開発政策に非常に妥当性が高い。世界的レベルでのポリオ根絶への最後の一押し(2001年時点でポリオの野生株は80%がバングラデシュ、インド、パキスタンに集中している)という点から、日本の協力は、世界的にも時宜を得たものと言える。日本は、1995年から1999年までの間のNIDの総コストの48%を負担した。同期間のその他のバイのドナー機関の負担は、USAID(イミュニゼーション・アンド・アザー・チャイルド・ヘルスというNGOを通じて)3%22、DFIDが2 %に留まっている。対象期間の日本の無償資金協力によるNIDに対する貢献を表3.12に示した。第六回のNIDでは経口ポリオ・ワクチンの必要量の95%23を日本が供与している。
表3.12 NIDに対する日本の無償資金協力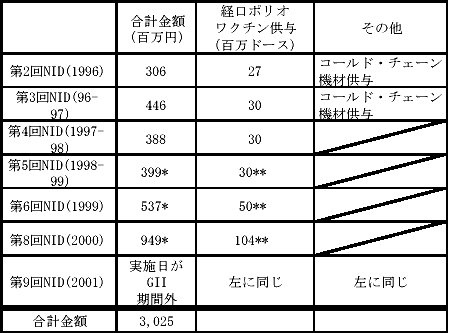 |
|
*UNICEFに対する補助資金として **その他にトレーニングとアドボカシーを支援 出所:UNICEFバングラデシュ事務所、"Japan-UNICEF Join Learning Mission",April 2001より本調査団作成。 |
貧困削減や女性のエンパワーメントが重要度の高い開発課題であるバングラデシュにおいて、日本がグラミン銀行への支援(有償資金協力)や農村女性のための各種研修施設の建設(無償資金協力/草の根無償資金協力)、初等教育施設建設と教員養成(草の根無償資金協力、NGO事業補助金)などに対する支援を実施してきたことは、開発課題に対して非常に妥当性が高い。
(2)効率性
a.人口直接分野
リプロダクティブ・ヘルス分野では、施設整備や人材開発のプロジェクト方式技術協力を実施、かつ、ESP関連の協力案件をNGOを通じて展開するという、サービス改善に関する部分に集中的な投入が見られ、同分野への課題解決のためのプログラムとして効率性が高かったと言える(図3.14)。
図3.14 人口直接分野の主要案件展開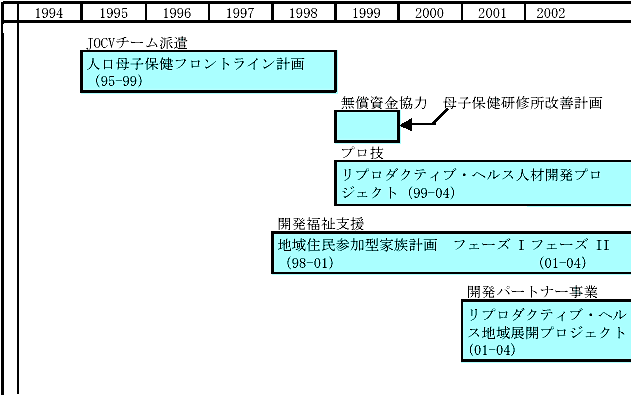 |
| 出所:本調査団作成 |
b.人口間接分野
EPIやPolio ポリオ根絶キャンペーン分野への協力は主にUNICEFとの綿密な連携を通じて実施され、これらの分野でUNICEFの持つノウハウの活用があったことで、効率性は非常に高かった。
(3)効果
a.人口直接分野
GII期間のバングラデシュでのリプロダクティブ・ヘルス分野の基礎指標の変化は表3.13に示したように、改善が見られる。これらの改善は、保健セクターにおけるバングラデシュ政府の各種の投入(サービス実施、施設改善、人材育成等)およびドナーやNGOによる投入、受益者である住民自身の投入が複合的に効果をもたらしたことで実現したものである。また、経済や教育の状況が改善すると人々の健康も改善することは知られるところである。
健康の改善に資したと考えられる各種ファクターが存在する内、日本の協力が健康の改善にどれだけ貢献したかを測るためには詳細の調査が必要となるが、GII評価調査においては、期間等の制約から詳細な調査は実施できなかった。
表3.13 GII期間のバングラデシュでのリプロダクティブ・ヘルス分野の基礎指標の変化
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出所:UNICEF、世界子供白書、2000年版、2001年版。UNFPA,世界人口白書、1995年版、 1996 年版、1997年版 |
表3.14 GII期間のバングラデシュのTFRの変化
|
||||||||||||
| 出所: John Cleland, James F. Phillips, Sajeda Amin and G.M. Kamal, The Determinats of Reproductive Change in Bangladesh: Success in a Changing Environment、P.10、UNFPA、世界人口白書、1995年版、 1996 年版、1997年版。 |
日本の人口直接分野の協力は、全体として、
| 1) | HPSPの最重要分野であるリプロダクティブ・ヘルス分野での協力である、 |
| 2) | その分野の中でも重要である人材育成へ投入を行っている、 |
| 3) | プロジェクト・レベルでドナー調整しつつ実施している、 |
| 4) | 集中的(時期的、金額的)な投入が行われている、 |
| 5) | プロジェクトが国レベルに対してインパクトを与え得るメカニズムや意義を備えている。 |
この判断の基礎の一例として、日本の主要プロジェクトである「リプロダクティブ・ヘルス人材開発プロジェクト」が、バングラデシュ政府のリプロダクティブ・ヘルス分野の人材育成のコア機関に対してインプットを行っており、同プロジェクトから国全体の人材育成分野への高い波及効果が期待できる。同プロジェクトは、開始(1998年)からの期間が短いが、実施期間中にプロジェクト目標を達成する見込みが、かなり高い。理由として、活動の順調な進捗状況と、保健省からの同プロジェクトに対する有能な人材面での投入、そして日本人専門家による継続的な技術指導が指摘できる。2000年6月から2001年3月までの10カ月間に研修は、39グループを対象に実施され、研修受講者は合計で530名に上る(医者が23名、医者以外の看護婦や家族福祉訪問員等の医療従事者が235名、TBAや栄養士などの非医療従事者が272名)。研修の効果は、受講生に対する研修後のテスト結果から定量的に明らかになっている24。活動の進捗を示す例として、研修の実績を本節末の表3.15に示した。また、同プロジェクトは、母子保健研修センターの臨床サービスの向上も目指しており、この点に関するデータを表3.16、表3.17に示した。
表3.16 「リプロダクティブ・ヘルス人材開発プロジェクト」による母子保健研修センターの臨床サービスの向上 I
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出所:「リプロダクティブ・ヘルス人材開発プロジェクト」提供資料より作成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表3.17 「リプロダクティブ・ヘルス人材開発プロジェクト」による母子保健研修センターの臨床サービスの向上 II
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出所:「リプロダクティブ・ヘルス人材開発プロジェクト」提供資料より作成。 |
保健省保健局人材開発部と家族計画局基礎医療部は、同プロジェクトによる母子保健研修所の機能強化の高い意義を認め、母子保健研修センター以外のリプロダクティブ・ヘルス分野の研修機関とのネットワーク強化に期待をしている。
NGOとの連携案件である開発福祉支援事業のプロジェクト(「地域住民参加型家族計画」、詳細については本報告書の第6章「NGOとの連携」を参照)においても、フェーズ1において現地NGOが作成した17のESP研修モジュールが政府の研修モジュールとして採用された。これは、研修モジュールの質の高さを示し、本プロジェクトがバングラデシュ全体の研修にも意義のあるインパクトをもたらしたと言える。現在、プロジェクトはフェーズ2に入っており、今期間においても国レベルにインパクトを与えることが期待できる。
b.人口間接分野
日本によるEPIやポリオ根絶分野への協力が行われた期間において、ポリオの症例が1995年から2000年までの間に95%減り、予防接種のカバー率の向上(図3.15)も見られた。日本の協力規模が大きいことから、これらの成果に大きく貢献したと言える。また、これらの協力は、マスメディアの報道等を通じてバングラデシュにおける日本の協力の可視性やプレゼンスを高めるという効果もあった。
図3.15 予防接種のカバー率の向上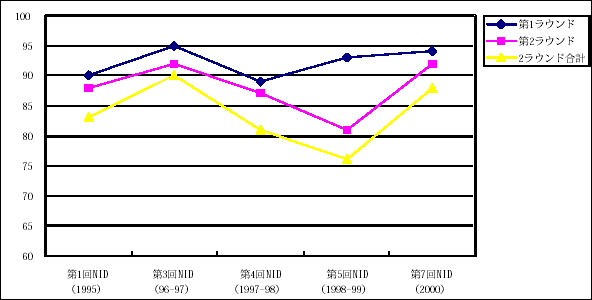 |
| 出所:UNICEFバングラデシュ事務所提供資料より作成。 |
人口間接分野のサブ・プログラムである「初等教育」と「女性を対象とした職業訓練および女子教育」についてGII対象期間の変化を見るために、女性の成人識字率と初等教育の純就学率(就学当該年齢で就学する子どもの数の就学当該年齢人口に対する割合)を表3.18に示した。
表3.18 人口間接分野の初等教育の整備と女性のエンパワーメント関連指標の変化
|
||||||||||||||||||
| *:本データは、世界子供白書1999年版より抽出しているが、同書では注として指定の年次以外のもの、標準的な定義によらないもの、あるいは国内の一部地域のものであると説明している。
出所:世界子供白書、1999年版、2001年版。 |
||||||||||||||||||
表3.18の数値の変化で分かるように、女性の初等教育の整備と女性のエンパワーメント関連指標は改善してきている。日本はGII対象期間において、NGOによる小学校建設や女性に対する識字教室の実施等に対する支援を行っている。また、農村女性に対する職業面での研修所に対する支援を実施している。しかし、これらの各支援が総体として国全体の状況にどのようなインパクトを与えたのかは、今回の現地調査では充分な資料が得られなかった。
c.エイズ分野
「バングラデシュHIV/AIDS・STD連盟」による「HIV/AIDS予防・治療支援計画」プロジェクトは、このNGOがHIV/AIDS分野で活動するNGOのネットワーク的な機能を果たしており、このNGOへのネットワークに属するNGOへの波及効果が期待できるため、重要性が高い。
GII分野(人口直接、人口間接分野の保健医療に関係する分野、エイズ分野)の日本からの支援全般をバングラデシュ保健省は高く評価をしており、今後の支援の拡大を期待している。
(4)自立発展性
a.人口直接分野
「リプロダクティブ・ヘルス人材開発プロジェクト」において、人材は順調に育成されおり25、技術面での自立発展性は確保される可能性が高い。
同プロジェクトは、バングラデシュ政府のリプロダクティブ・ヘルス分野人材育成機関もカウンターパートにしており、その機関の研修事業の実施能力向上のための投入も行っているため、プロジェクトが順調に進捗すれば、リプロダクティブ・ヘルス分野での政府による人材育成事業実施の自立発展性も確保される可能性が高い。
無償資金協力で建設された母子保健研修所の運営資金をバングラデシュ政府側が確保し続けることができるか、また日本から供与した機材の維持管理を継続できるのかについて、日本側が今後も充分な注意を払い、必要な措置の検討を行うことが重要である。
b.人口間接分野
日本による供与品の内、消耗品であるワクチンを除いて、コールドチェーンに要する機材は、バングラデシュ政府の管理下に置かれ、維持管理の責任はバングラデシュ政府が有する。しかし、UNICEFの政府に対する支援があるため、供与機材は今後も活用され、維持管理されていく可能性が高い。
3.3.5 NGOとの連携(開発パートナーシップ事業1案件のみにかかる評価)
バングラデシュにおいて、NGOとの連携は、JICAの1) 開発福祉支援事業(現地NGO支援)、2) 開発パートナーシップ事業(本邦NGO支援)、3) 草の根無償資金協力によって実現している。本報告書においてNGOとの連携に関する評価は、本評価調査団に参加したNGO代表が担当した(本報告書6章を参照)。しかし、バングラデシュにおける開発パートナーシップ事業の実施NGOは、財団法人家族計画国際協力財団(ジョイセフ)であり、ジョイセフからは職員がNGO代表として本評価調査団に参加しているため、NGO連携に対する評価の内、開発パートナーシップ事業の検証は、本節において行うものである26。しかし、ジョイセフのプロジェクトを「プロジェクトとして評価する」ものではなく、同プロジェクトに関する考察からバングラデシュでのNGO連携に関して普遍性が高いと想定される事項のみを抽出することを目的とする。表3.19にプロジェクト概要を示した。
表3.19 開発パートナーシップ事業によるNGOプロジェクトの概要
|
||||||||||||
| 出所:GII評価調査団からのアンケート回答、JICA資料より。 | ||||||||||||
プロジェクトの特徴は、以下の点である。
| 1) | プロジェクトでは、リプロダクティブ・ヘルス/家族計画サービスの利用増加のための健康教育や診療活動のみならず、その基礎となる女性のエンパワーメントを重視した識字教育や収入創出活動等を組み入れて、包括的な活動を実施している。 |
| 2) | 日本の援助の有機的連携が行われている。JICAの開発パートナーシップ事業で支援されているNGOプロジェクトの活動拠点である女性多目的研修センター27は、日本大使館による草の根無償資金協力(1997年度)により建設された28。このプロジェクトには、JOCVがTOT(トレナーズ・トレーニング)を行うことを目的として1998年から派遣されている29。また、プロジェクト方式技術協力「リプロダクティブ・ヘルス人材開発プロジェクト」の専門家からアドバイスを受けている。 |
| 3) | 住民の参加が、各局面で実現している。ESP供給のために保健ワーカーは、担当する村の出身者である。地域レベル(村が複数集まった単位)には、プロジェクトと住民との連携を確保するため、女性も含めた住民のリーダーから構成される運営委員会と諮問委員会を設置している。 |
| 4) | 現地NGOや現地人スタッフを活用している。このため、日本人が長期滞在していない。 |
| 5) | ジョイセフには、この地域での活動経験がすでにあった。 |
| 表3.20 開発パートナーシップ事業 (「リプロダクティブ・ヘルス地域展開プロジェクト」)評価に関する考察30
|
||||||||
| *この背景には、ジョイセフと協力している現地NGOであるFPABがバングラデシュにおいてはリプロダクティブ・ヘルス分野のパイオニア機関である(設立1953年)ことがある。FPABは、コミュニティ・レベルにおけるリプロダクティブ・ヘルス分野のサービス供給に関してノウハウを持っており、それをジョイセフのプロジェクトにおいても活用することできた。 |
以上の検証の結果から、本開発パートナー事業の評価項目上にプラスに貢献している、または貢献していくであろう(プロジェクトは2001年3月に開始された)ファクターを抽出し、評価項目に対する貢献度を示した。(表3.21)
表3.21 本開発パートナー事業の評価項目上に貢献している/いくファクター
|
|||||||||||||||||||||||||
| (◎かなり貢献する、○貢献する)
出所:本評価調査団作成。 |
表3.21の貢献度は以下の見解に基づく。
| 1) | 現地の事情に詳しく、活動経験のある日本のNGOとの連携 日本のNGOであるジョイセフが、現地の事情(コミニュティ・レベルも含めた)にも詳しく、かつ、現地で活動経験があることは、プロジェクトの妥当性、効率性、効果にプラスに寄与するであろう。 |
| 2) | 現地NGOとの連携 本プロジェクトにおいてジョイセフが、現地NGOであるFPABと連携することから、効率性(プロジェクトの順調な進捗、投入と成果と比較面での効率性)が向上する可能性が高い。また、現地NGOの持つノウハウによって、プロジェクトがより効果を上げやすいであろうことも指摘できる。現地NGOがプロジェクトでの連携を通じて能力を向上させると、プロジェクトの自立発展の可能性も高まる。 |
| 3) | 現地人スタッフの活用 現地人スタッフの活用は、現地NGOとの連携と同様な面での効率性の向上に貢献すると考えられる。現地人スタッフの活用によって、日本人を長期滞在させる必要がなくなった場合は、滞在費を節約できる。 現地人スタッフが業務を通じて、将来の開発プロジェクトにおいても活用可能な各種能力を伸ばせた場合は、現地のリソースの向上(質的、量的側面)が期待できる。プロジェクトの自立発展の可能性も高まる。 |
| 4) | 住民の参加 住民の参加は、プロジェクトの効率性を高め、効果を上げる可能性を持つ。また、プロジェクトの自立発展の可能性も高まる。 |
3.3.6 今後の協力のあり方
(1)SWAPが進展していることから、今後のIDIの効果的運用という側面からも専門性を備えた人材の早急なJICA事務所への配置と、同人材のセクター(保健セクター)・レベルのドナー会議への参加が望まれる。
(2)バングラデシュは、国の経済規模に比較して援助受入れ金額が大きく、ドナーの数と援助形態も多い。また、各種ドナー会合が保健医療分野以外でも活発に開催されている。このような環境下で、大規模ドナーの一つである日本は、各種ドナー会合への出席や貢献が強く求められている(これに対して大使館とJICAは積極的に協力して会合への「日本の出席」を確保しようとしている)。バングラデシュではNGO活動が非常に活発であり、バングラデシュ大使館にあがってくる「草の根無償」の申請書は、現在年間300件程度である。これらの状況と日本にとってのバングラデシュへの援助の重要性から判断して、日本の援助効果のさらなる改善のためには、日本大使館およびJICA事務所の経済協力担当者の人員増加が望まれる。
(3)国別援助計画、国別援助実施計画(2001年7月作成)に沿った的を絞った協力(戦略性の高い)が今後も実施されることが、援助効果を上げるために望ましい。
(4)SWAPが進展する中、今後は、保健省との窓口となる日本サイドの担当者の明確化が望ましいと保健省では考えていることから、日本側の役割分担を明確に保健省側に示し、理解を得る。
| 表3.15 「リプロダクティブ・ヘルス人材開発プロジェクト」による研修実績 (2000年7月~2001年3月、9カ月間)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (*1):Obstetrical & Gynecological Society of Bangladesh (*2):Human Development & Research Organization
(*3):Bangladesh Breastfeeding Foundation (*4):Concerned Women for Family Development (*5):RADDAは略語ではなくNGOの正式名称 出所:「リプロダクティブ・ヘルス人材開発プロジェクト」提供資料より本評価調査団作成。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 本項で示した案件以外に、バングラデシュ国にも所属している国際機関である国際下痢性疾患研究センターに対して、日本はGII開始以前から現在にいたるまで長期的な支援を行い、支援ドナーとして上位に位置している。日本からの支援は、例外的な年を除いて他の国際機関への拠出と同様な手続き(外務省経済協力局国際機構課扱い)で拠出されている。本機関は、研究機関としての臨床部門も備えており、周辺住民にサービスを提供しているが、基本的には国際研究機関である点から本節では検証しない。
8 バングラデシュにおいては、ハイ・リスクグループにおけるHIV感染率さえも周辺国に比較して非常に低いため、政府と援助機関が本格的にHIV/AIDS対策に取組むに至っていないというのが、複数の援助機関関係者の見解である。しかし、STD罹患者の数が多い、ハイ・リスク行動が実施されているなどHIV感染の拡大の下地となる要素が存在しているため、政策レベルでの早期の本格的取組みが一部援助機関からは望まれている。
9 GII調査団の保健省およびドナー機関に対するインタビューより。
10正式名称は、以前はBangladesh Rural Advancement Committeeであったが、現在はBRACが正式名称である。
12 JICAのプロジェクトにおいて訓練を受けるのは、通常、主に政府機関の人材である。
12 日本大使館が主に協議を行う相手は、援助調整窓口機関であるバングラデシュ政府大蔵省Economic Relations Division(ERD)であり、JICA事務所ではプロジェクト・レベルの協議となるためプロジェクトのカウンターパートである保健省の特定部署となる。
13 JICAのプロジェクト方式技術協力と草の根無償資金協力を日本からのODAとしてカウントしていない。これは、日本のプロジェクト方式技術協力では、確定予算をバングラデシュに示さないためであり、また、草の根無償資金協力の支援対象がNGOだけとなっているためである。
14 2001年度だけでもUNICEFダッカ事務所の職員は、比較的正式な協議だけでもJICAバングラデシュ事務所員と8回、日本大使館の職員(草の根無償資金協力担当者)と5回、JICAの日本人専門家とは2回行っており、この他にも面会の協議、電話、電子メールによる連絡を頻繁にとっている(今回評価調査のアンケート回答より)。
15 JICAの開発パートナー事業でヒ素対策プロジェクトが実施されていることもあり、ヒ素対策分野でも内容調整や進捗確認の情報交換が実施されてきた。「日本・UNICEF合同学習調査」が実施される予定。
16 本調査実施以前の1999年11月から12月にかけても、「日米合同プロ形調査」団が派遣されたが、バングラデシュでのゼネストの影響により参加予定の複数の調査団メンバーが参加できなくなったため、2000年2月に再度調査団が派遣された。したがって、前者の調査が「第一次」調査であり、後者の調査が「第二次」調査となっている。
17 ここでの実施とは、6分野において日米それぞれが案件を実施することであり、1つのプロジェクトを一緒に行う共同実施は意味しない。日米の並行的な案件の実施を通じて、6分野の開発課題の改善を効果的に進めることをめざすものである。
18 アメリカが1960年に設立したSEATO(South East Asian Treaty Organization)コレラ研究所を母体として、1979年に発足した国際研究機関。日本からのICDDR,Bに対する資金拠出は、1990年代後半のほとんどは、他ドナーに比較して圧倒的に大きい金額を拠出しているアメリカに次いで第2位であった。
19 なお、SWAPは、現在もっとも積極的に関与しているバイのドナーの1つであるDFIDの見解によれば、順調に進展しており、その理由は、バングラデシュにおいて、1)SWAP推進に対する同国政府の継続的な政治的意思、2)保健省責任者の強いコミットメント、3)円滑なドナー調整、4)ドナーによる技術面での支援の存在するためとのことである(本評価調査団によるヒアリング)。
20 DFIDはSWAPを推進するために、バングラデシュにおけるDFID実施によるプロジェクトを廃止して、プロジェクトは全てNGOによる実施のプロジェクトを支援する形態とした。また、保健セクター担当者として、SWAP専門担当者を3名配置している。
21 GII評価調査団のインタビューとアンケートに対する回答。
22 アメリカのCenter for Disease Control は9%を負担している。
23 国際協力事業団アジア第二部、『バングラデシュ日米合同プロジェクト形成調査(第一次)(人口・保健分野)、調査報告書』、平成12年1月、P3。
24 「リプロダクティブ・ヘルス人材開発プロジェクト」提供の資料。
25プロジェクト提供の資料から、研修が研修生の知識レベルを高めたことが定量的に確認できた。また研修生の研修に対する満足度も高いことが判明した。
26 NGO代表として本評価調査団に参加しているジョイセフ職員は、本節における自組織の活動の評価は行っていない。
27 各種活動のための場所の他に、診療室、分娩室等、保健施設としての設備も備えている。
28 同センターは、開発パートナーシップ事業で支援を受けているジョイセフが、プロジェクトにおいてパートナーするバングラデシュ家族計画協会(FPAB)の所有物で、この現地NGOが草の根無償資金を獲得した。FPAB自体も、1998年からJICAの開発福祉支援事業の支援によるプロジェクトを実施し、現在プロジェクトはフェーズ2を実施中である。
29 JOCVがNGOに派遣された最初のケースである。
30 現地調査の時間が限られていたため、情報が限定的とならざるを得なかった。

