3.2 タイ
3.2.1 GIIの実施状況
(1)HIV/AIDS分野プロジェクトの特徴
タイは、GIIが対象とする3分野(人口直接、人口間接、HIV/AIDS)のうち、HIV/AIDS分野の重点国として位置づけられている。我が国は、GII開始後、1996年までは「エイズ予防対策プロジェクト(プロジェクト方式技術協力)」を実施し、国立衛生研究所(NIH)を拠点に研究協力を実施するとともに、プロジェクト後半では、啓発教育、公衆衛生活動の強化支援を行った。1998年以降は、事業の目標をより明確化するため、プロジェクト方式技術協力を研究協力とコミュニティー活動の2つに分け、国立衛生研究所(NIH)でのワクチン開発にかかる研究を中心とした「国立衛生研究所機能向上プロジェクト」と、コミュニティー・ベースのアプローチによる感染予防と患者へのケアを視野に入れた「エイズ予防地域ケアネットワークプロジェクト」を実施している。JICA支援によるプロジェクト方式技術協力を行う一方で、草の根無償資金協力や開発福祉支援事業を実施し、NGOとの連携を通して、特に患者とその家族へのケアの分野へも支援を行っている。
表3.6 我が国のHIV/AIDS分野の協力(1994-2000)
|
||||||||||||||||||||||||
| 出所:JICA人口・エイズ分野実績、我が国の政府開発援助 下巻2000年度版 |
図3.8 形態別協力案件数 |
| 出所:JICA人口・エイズ分野実績、我が国の政府開発援助 下巻 2000年度版 |
図3.9で示される通り、GII開始以降、我が国のタイのHIV/AIDS分野への協力件数は、草の根無償資金協力、プロジェクト方式技術協力を中心に、年々、増加している。実績額も、プロジェクト方式技術協力が一旦終了した1996年を除いて、毎年増加傾向を示している(図3.10)。2001年現在、タイで実施中のプロジェクト方式技術協力案件に占めるHIV/AIDS分野は14件中2件、保健医療協力では、プロジェクト方式技術協力4件中2件がHIV/AIDS分野であり、我が国のタイへの協力の中で、HIV/AIDSは重点分野の1つであることが伺える。
図3.9 我が国のタイでのHIV/AIDS分野の協力件数(1994-2000)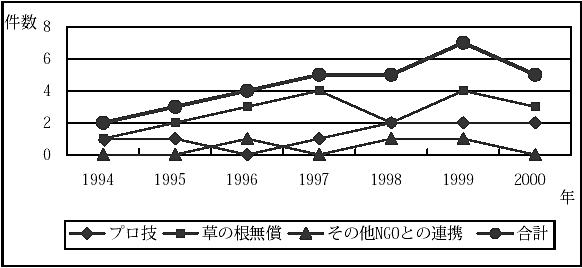 |
| 出所:JICA人口・エイズ分野実績、我が国の政府開発援助 下巻 2000年度版 |
図3.10 我が国のタイへのエイズ分野の協力実績額(94-00)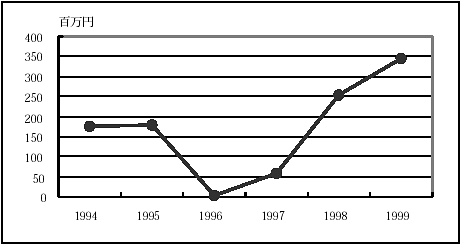 |
| 出所:JICA人口・エイズ分野実績、我が国の政府開発援助 下巻 2000年度版 |
HIV/AIDS分野の協力は、大きく、(1)HIV感染予防、(2)エイズ患者とその家族のケア、(3)研究開発・人材育成、の3つのサブ・プログラムに分類することができる(添付資料プログラム・ツリー参照)。我が国のタイへのHIV協力をサブ・プログラム別にみると、コミュニティ・レベルでの活動が中心となる「エイズ患者へのケア」は、草の根無償資金協力等、NGOを通した支援による協力が多く、検査技術の向上や、研究活動等、科学的専門性を求められる「研究開発」は、プロジェクト方式技術協力による支援が中心となっている(図3.11及びプログラム・ツリー参照)。また、「HIV感染予防」においても、母子感染予防や啓発教育をプロジェクト方式技術協力で行う一方、公的介入では到達が困難とされているリスク・グループを対象とした予防については、NGOとの連携で支援を実施している。一方、現在実施中のプロジェクト方式技術協力「エイズ予防・地域ケアネットワークプロジェクト」は、HIV感染予防、エイズ患者のケア、検査技術の向上と、1つのプロジェクトでHIV/AIDSにかかる包括的要素を包含していることが特徴的である。
図3.11 サブ・プログラム別協力件数(1994-2000)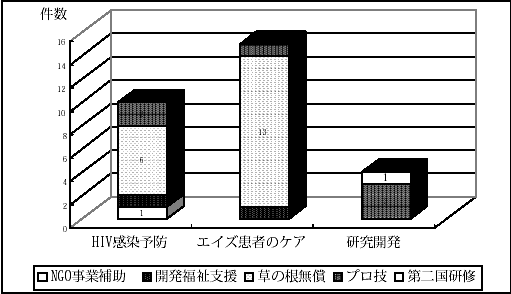 |
| 出所:JICA人口・エイズ分野実績、我が国の政府開発援助 下巻 2000年度版 |
3.2.2 GIIの認知度
タイでは、在外公館及びJICAの保健協力案件担当者は、「GII」について認知していた。また、タイは、GIIの3分野(人口直接、人口間接、HIV/AIDS)のうち、エイズ分野のみの対象国となっているため、インドネシアでみられたような、「どのプロジェクトがGIIのどの分野に分類されているのか」といった混同はみられなかった。
タイにおけるHIV/AIDS分野の協力が、案件数、実績額ともに増加しているのは、GIIのような政策レベルのイニシアティブに起因するというよりはむしろ、タイのHIV感染の現状とニーズによるものと認識されている。GIIやIDIなどの政策レベルで発表されるイニシアティブの意義について、現場担当者からは「政策としてのイニシアティブと、案件及び現場とをいかに連携させていくか」「イニシアティブの勢い(Momentum)の継続性をどのように確保するか」が今後の課題として指摘された。
3.2.3 他の開発パートナーとの連携
(1)NGOとの連携
上述の通り、タイにおける我が国のHIV/AIDS協力は、プロジェクト方式技術協力と、草の根無償資金協力、開発福祉支援、等、NGOとの連携、と異なるスキームの組み合わせで実施されており、コミュニティ・レベルのケアやハイリスク・グループを対象とした介入等、公的機関を通した協力だけでは不十分な部分をNGOとの連携で補完している。
草の根無償資金協力の最近の例として、日本のNGOの現地法人であるシェア・タイランドやワールドビジョン・タイへの支援が挙げられる。シェア・タイランドは、コミュニティーによる予防啓発活動とHIV感染者及びその家族へのケアを実施しており、コミュニティーに根差した包括的なHIV/AIDS対策の形成を目指し、地域住民の人々と、県病院及び県保健局との連携を図りつつ活動を行っている。ワールドビジョン・タイは、南タイ・ラノン県、ミャンマーとの国境沿いを活動の対象地域としている。近年、この地域でミャンマーからの不法滞在者が多く、これに起因しこの地域でHIV感染者が急増している背景から、行政、草の根無償資金協力、ワールドビジョンが連携し、HIV/AIDS対策にかかる保健所設置を支援している。
タイ北部パヤオ県で実施中の技術協力「タイ・エイズ予防・地域ケアネットワークプロジェクト」では、開発福祉支援事業との連携が行われた。98年から99年にかけて、同事業対象地域で、JICAは、ラックス・タイ財団(NGO)との開発福祉支援事業を実施し、HIV感染者及びエイズ患者に対するケアと、予防教育に地域ぐるみで取り組むための基盤整備等への支援を行った。この開発福祉支援事業のもとで母子垂直感染予防薬であるAZTパッケージが購入されたが、これらのAZTパッケージの配付を、技術協力の活動の中で実施した。
2000年、我が国は、人口・リプロダクティブ・ヘルス分野での最大の国際NGOである国際人口家族計画連盟(IPPF、本部イギリス)に、「HIV/AIDS信託基金」を設置し、100万ドルの拠出を決定した。この基金により、タイ家族計画協会(PPAT)は2001年2月、アジア、アフリカ諸国から20名の参加者を招聘し、HIV/AIDSに関するアドボカシー・トレーニングを実施した。
(2)諸外国の研究機関との協力
「国立衛生研究所(NIH)機能向上プロジェクト」では、我が国の無償資金協力により建設された「国立衛生研究所(NIH)」において、エイズと新興・再興感染症に関する研究実施能力を強化する目的で活動が行われており、本案件を通して、さまざまなレベルでの研究協力が進んでいる。例として、日本の研究者とタイの研究者の共同研究の促進や、プロジェクトで実施中のコホート研究に関するオックスフォード大学、米国疾病防疫センター(Centers for Disease Control and Prevention (CDC))、など諸外国の研究機関との協力、などが挙げられる。また、今後、ケニアでプロジェクト方式技術協力(「感染症研究対策プロジェクト」)が実施されたケニア中央医学研究所(KEMRI)とタイNIHとの共同研究が予定されている。
(3)「ケア・パッケージ・モデル」づくりにおける各種パートナーとの連携
プロジェクト方式技術協力「エイズ予防・地域ケアネットワーク」では、主要な活動の1つである「ケア・パッケージ・モデル」づくりを、WHO等、他の開発パートナーとの調整と連携を図りつつ実施している。昨年から、タイ保健省感染症対策局は、エイズ・ケア・パッケージ・モデルづくりをWHOとの合同プロジェクトと位置づけ、ワーキング・グループを発足させた。同ワーキング・グループの参加機関は、JICAプロジェクト、タイ保健省感染症対策局リジョン10、WHO、チェンマイ県衛生局、パヤオ県衛生局、チェンライ県衛生局、米国CDC、保健省エイズ課、である。連携を通して、中央とのパイプづくり、プロジェクト方式技術協力の活動の広報、他機関とのコスト・シェアリング、などが進む反面、各機関の思惑の違い、アプローチの違いによる調整の困難な点も生じている。
(4)その他
1997年以降、日本政府と社団法人国際厚生事業団(JICWELS)は、UNAIDSと連携し、毎年、タイでエイズワークショップを開催している。
3.2.4 評価結果(妥当性、効率性、効果、その他)
(1) 妥当性
上記でみてきた通り、タイにおける日本のHIV/AIDS分野の協力は、当初、プロジェクト方式技術協力による研究協力及び予防・啓発活動が実施されていたが、徐々にコミュニティ・レベルでの活動も行うようになり、1998年以降は、研究所での活動、コミュニティ・レベルでの活動と、目的が異なる2つの活動をそれぞれ個々のプロジェクトに分け実施している。また、近年、草の根無償資金協力や開発福祉支援事業など、NGOへの支援を通したコミュニティ・レベルでの患者とその家族のケアへの協力が増加している。
タイのエイズ感染者第1号は1984年に発見された。初期の感染者は注射薬物常習者が中心であったが、その後、性交渉による感染が増加し、現在は、異性間性交渉による感染が、感染経路として最も多い。1996年までの累積感染者数は100万人と推計され、2000年7月現在、エイズ患者数(報告数)は、累計で149,266名と推計されている。また、1989年には0%だった検査通院中の妊婦の罹患率が1995年には2.3%に増加しており、感染が、ハイリスク・グループ(注射薬物常用者や性産業従事者等)から一般へ拡大しつつある様子が伺える。また、減少傾向にあった結核患者数が、ここ数年若干増加しており、HIV/AIDSの蔓延が主たる原因とみられている。
タイ政府によるHIV/AIDSへの取組みは、感染者が急増しはじめた1980年代後半より本格的に着手された。当初は、医学的アプローチによる取組みが中心だったが、感染拡大に伴い、エイズの社会的側面への配慮の重要性が認識されるようになった。1992年には、エイズ問題は医療分野のみに留まらず、社会経済問題でもあるとの認識から、首相府の国家経済開発委員会と保健省感染症総局(CDC)エイズ課が中心となり、「エイズ予防・管理国家計画」を策定した。1994年にはHIV/AIDSワーキンググループによる統計調査の見直しが行われ、その結果が「エイズ予防・管理実施計画」に反映された(表3.7参照)。1997年からは、エイズ予防・管理国家計画が「第八次国家経済社会開発五カ年計画」の一部となり、ここでは、特に一般感染の拡大に対する社会的配慮が重視されている。感染予防に関し、タイ政府は、売春宿でのコンドームの配付を中心に対策を実施し、一定の成果をあげたが、経済危機以降、エイズ対策予算が大幅に削減され、今後の対策を懸念する声もあがっている。
表3.7 タイ政府によるエイズ対策の基本方針の推移と我が国のエイズ分野の協力
|
||||||||||||||||
| 出所:国際協力事業団基礎調査部「タイ王国・エイズ分野プロジェクト形成調査結果資料(内部検討資料)平成9年1月」からの情報よりGII評価調査団作成 |
前述の通り、我が国のタイでのHIV/AIDS分野の協力は、当初研究協力を中心に行われていたが、90年代後半から、プロジェクト方式技術協力でもコミュニティ・レベルでの予防活動が行われるようになり、また、NGOへの支援を通した患者とその家族のケアへの協力も増加している。我が国のタイでのHIV/AIDS分野の協力をプログラムとしてみると、プロジェクト方式技術協力とNGOへの支援を通した協力(草の根無償資金協力、開発福祉支援事業)が相互補完し、予防、ケア、研究・人材育成と、包括的な協力を構成している(プログラム・ツリー参照)。タイ政府のHIV/AIDSへの取組みも、90年代に入り、徐々にHIV/AIDSの社会へのインパクトに配慮した対策が方針として打ち出され、また、感染と患者の発生の進度に伴い、予防とともに患者とその家族へのケアに対しても対策が行われるようになっている。我が国の協力の方向性は、このようなタイ政府の方針に整合している。近年タイにおいてHIV/AIDSの感染が一般にも拡大する傾向にあり、患者とその家族へのケアへのニーズが高まっており、我が国の協力が、プロジェクト方式技術協力と草の根無償資金協力及び開発福祉支援を中心に、地域による感染者とその家族へのケアの分野にも協力の重点を置いていることは時宜に適した妥当な協力といえる。
(2) 効率性
a.各種スキームの組合せによる相互補完性
先にもみてきた通り、タイでの我が国のHIV/AIDS対策協力のプログラムは、プロジェクト方式技術協力と草の根無償資金協力及び開発福祉支援事業を組み合わせ、コミュニティ・レベルでのケアやハイリスク・グループを対象とした対策など、行政だけでは不十分な部分をNGOへの支援を通した協力で補完する構成となっており、立場や機能の異なる機関がそれぞれの比較優位性に基づき協力することにより、効率性の高い協力プログラムを構成している。
また、北部タイでは、同一地域を活動対象とする開発福祉支援事業(「北部タイにおけるコミュニティ組織を通したエイズ予防とケア」)とプロジェクト方式技術協力(「エイズ予防・地域ケアネットワーク」)が、母子感染予防対策で連携し、開発福祉支援事業のもとで購入されたAzidothymidine(核酸素逆転写酵素阻害剤)パッケージ161組をプロジェクト方式技術協力を通して配付した。同じ活動目標を掲げる複数の案件が、それぞれに可能な役割や機能で相互に補完しあい連携することは、活動の重複を避け、特定の目標の達成を促す効率的な協力といえる。
b.プロジェクト方式技術協力の目的の明確化
93年から96年にかけて実施された「エイズ予防対策プロジェクト」では、研究協力ならびにエイズ教育、公衆衛生活動の強化支援を実施した。1998年以降は、研究協力と地域レベルでの活動は目指す方向性が異なることから、これまで1つの技術協力案件で実施されてきたHIV/AIDS協力を、2つの技術協力案件(「国立衛生研究所(NIH)機能向上プロジェクト」、「エイズ予防・地域ケアネットワークプロジェクト」)に分け、協力を実施している。1つの案件が複数の案件目標を包含するのではなく、案件目標を1つに絞り、明確化することにより、案件の活動目標も一層明確になり、目標達成にむけた効率的な協力のロジックを組み立てることが可能となる。
c.短期派遣専門家の選定
現在実施中の技術協力「エイズ予防・地域ケアネットワークプロジェクト」のカウンターパートから、異なる短期専門家の派遣が多いことが、我が国の協力の課題として指摘された。日本人専門家がプロジェクトに短期間派遣される場合、対象地域の問題の背景や詳しい社会状況など、現状を正確に把握しないまま帰国してしまうケースが少なからず生じているという。日本人専門家は、長期に日本の職場を離れられないなど、専門家を派遣する日本社会の構造的な問題については、今後、優れた専門家確保のために積極的に取り組んでいかなければならない課題である。一方、例えば、同じ専門家を短期ではあるが継続して派遣する、現地の専門家を雇用する等、短期専門家派遣にかかるいくつかのオプションを検討してみることも重要であろう。専門家の派遣には当然ながらコストが発生する。費用、派遣期間、目標の達成の3つの要素に着目し、費用効率性の高い短期専門家派遣の方法を改めて検討することが求められる。
(3)効果
a.タイにおけるエイズの現状と我が国の協力との関連性
タイ政府は、1990年代、性産業従事者へのコンドームの普及に積極的に取組み、性産業従事者とその顧客の感染については一定の成果をあげ、新規感染率を低下させた。しかし、過去の感染の結果、また感染の潜伏期間が長いため、これまでに約30万人がエイズで死亡し、感染者は約100万人に及ぶ。2000年には、約5万5,000人がエイズを発症し、約同数が死亡すると推計されており、感染率は低下しているものの、感染者は今後も増加しつづけると予想されている5。
また、タイでは、新規感染者の構成が変化しつつある。10年前は、ほとんどの感染者が成人で、約80%が性産業従事者とその顧客であったのが、2000年には、新規感染者2万9,000人中約4,000人が子供であると推計されている。また、成人の新規感染者のうち、約半数が、夫やセックス・パートナーとの性交渉により感染した女性で、次いで注射薬物常用者、性産業従事者とその顧客と推計されており6、HIV/AIDS感染が一般人口にも拡大する傾向がみられ、タイでのHIV/AIDS感染は、今後も継続して取組みが必要とされる重要課題である。
我が国の協力は、1990年代前半は研究協力に重点が置かれており、90年代半ばから徐々に地域レベルの活動を実施するようになり、90年代後半からは、研究協力と地域レベルの活動が同時並行で行われている。研究協力の直接的な目的が、一次医療レベルの予防ではなく、投薬、薬剤耐性、日和見感染症治療、ワクチン開発、等であることを考えると、研究協力のインパクトの範囲は、ある程度限定されたものとなる。地域レベルの活動を行う「エイズ予防・地域ケアネットワークプロジェクト」では、予防とケアを包含した、地域内で取り組むエイズ対策のモデルづくりを行っており、ここで策定された対策モデルをプロジェクト対象地域以外の県へも適用することにより、広範への貢献が期待されるが、本案件を含む我が国の地域レベルの協力は開始からわずか数年が経過したのみであり、現段階でこれら地域レベルの協力が、タイのHIV感染率、患者発生率、母子感染予防等に及ぼすインパクトについて言及するには時期尚早といえる。
b.共同研究の促進への効果
研究協力を実施することにより、その波及効果として他の開発パートナーや、対象国を越えた連携や協力が可能となる。タイでのNIHを通した我が国の協力においても、タイと我が国の共同研究の促進、オックスフォード大学や米国CDCなど、他の先進国の研究機関との研究協力の促進、他の途上国からの研究者の受入と研修が行われ、タイという国の枠組みを越えた、研究者の連携促進に貢献している。また、今後、ケニアで実施された我が国の研究協力のカウンターパート機関とNIHとの共同研究が予定されているなど、他国での我が国の開発協力との連携、経験のシェアも可能となっている。
c.我が国の専門家の育成への効果
タイは、公的機関、NGO共に、他のアジア諸国に先んじてHIV/AIDS対策の経験が豊富であり、我が国の専門家がタイの経験から学ぶことも多い。現在実施中の「エイズ予防・地域ケアネットワークプロジェクト」では、HIV/AIDS感染者を対象としたデイケアセンターの成功要因を分析するなど、派遣専門家が積極的にタイのコミュニティ・レベルのHIV/AIDS活動から学ぶよう努めている。地域の活動から学んだことを体系的にまとめ、我が国のHIV/AIDS協力のアプローチづくりに役立てることができれば、重要な効果といえる。また、このようなプロセスを通じて、我が国の専門家の人材育成に貢献している。
d.効果の可視性
我が国の協力はインプットの大きさに比し、効果や貢献の可視性が低いことが、案件のカウンターパートから指摘された。例えば、無償資金協力による機材供与を行った場合、それらの機材を使用する(あるいはそれらを使用可能にする)プロジェクトを実施しなければ、対象国の人々に対する我が国の協力の「顔」が見えてこない。実際、NIHでは、我が国の無償資金協力により多くの機材供与を受けているが、それらを使用する我が国からの技術協力や研究協力が少なく、結局、他ドナー(例えば米国CDC等)がそれらの機材を使用したプロジェクトを実施し、協力の「結果」が他ドナーに帰してしまう場合が過去に多々あったという。機材供与は、技術協力と共に実施するほうがその「効果」が見えやすく、今後、この点に留意した無償資金協力を実施することも重要と考えられる。
(4)その他
a.研究所プロジェクトにおける自立発展性
NIHでの研究協力について、関係者とのインタビューの中で、我が国の協力案件終了後、案件実施期間中と同様の研究活動及び機能維持の可能性については、これを疑問視する声もあった。理由として、設備や機材(日本からのインプット)の維持管理費が十分に確保されないこと、現在実施中のコホート研究にコストがかかることが挙げられた。
3.2.5 今後の協力のあり方
(1)南南協力実施の可能性
タイは、近隣諸国に先んじてHIV/AIDS対策の経験を有し、コンドーム普及による感染予防では一定の成果を挙げていることから、今後は、第三国研修を積極的に実施するなど、南南協力の拠点として我が国の協力を展開することも、妥当性が高いものと考えられる。
(2)HIV/AIDS協力のプログラム化
現在、我が国のタイへのHIV/AIDS協力は、プロジェクトごとに案件目標はあるものの、プログラムとして個々の協力を捉えてはおらず、このためプログラムとしての協力目標が明確にされていない。また、各案件の目標も測定可能なものばかりではない。我が国の協力がタイのHIV/AIDS分野の状況の改善にどの程度貢献するのか、協力の効果について明らかにするためには、地域、分野でみれば点または面として実施されている協力案件を立体的なプログラムとして捉え、プログラム目標を明確にしておくこと、つまり、我が国が個々の案件から成る協力を通して、何を達成したいのか、について明らかにし、可能な範囲で測定値を設けておくことが重要である。
(3)研究協力における自立発展性の確保
機材供与やインフラ整備が多く含まれる研究所をベースとした案件は、供与・整備されたインフラをどのように運営し、維持・管理していくかが、案件の成否を決めるといっても過言ではない。このため研究協力案件を計画、実施する際には、案件終了後の組織、人的、経済的持続可能性に配慮し、供与される機材の選定、運営・管理技術の導入、運営・管理にかかる人材育成を行う等、長期的視点から自立発展性に配慮した案件づくりが重要である。
(4)研究活動の支援における目的と対象の明確化
研究協力における研究活動は長期間にわたる場合が多いため、ODAとして研究を支援する目的と対象範囲を明確にしておくことが重要である。ODA案件としてカバーする部分を明確にし、それ以外の部分は、日本国内の研究機関に橋渡しする等、他機関との連携やコスト・シェアリングを図ることも検討すべきオプションといえる。
5 World Bank. Thailand's Response to AIDS: Building on Success, Confronting the Future.
6 同上

