第3章 GIIによる協力の妥当性、効率性、効果、協力の成功例: 現地調査によるケース・スタディ
3.1 インドネシア
3.1.1 GIIの実施状況
(1) 人口直接(リプロダクティブ・ヘルス)分野への協力の特徴
インドネシアでの人口直接分野の協力は、1989年から94年まで実施された「家族計画・母子保健プロジェクト」と、1998年から5年間の予定で実施されている「母と子の健康手帳プロジェクト」と、2つのプロジェクト方式技術協力(プロジェクト方式技術協力)を中心に、安全な妊娠・出産に重点をおいた協力が行われている1。特に、母子手帳の普及は、「家族計画・母子保健プロジェクト」で試行され、1995年から97年に派遣された母子保健専門家に活動が引き継がれ、1996年から2003年にかけてUNFPAとのマルチ・バイ協力(人口機材特別供与)による母子手帳印刷への支援が実施されるなど、継続的に協力が行われている。1998年からは新しいプロジェクト方式技術協力「母と子の健康手帳プロジェクト」が開始され、インドネシアの母子手帳の全国展開を支援している。
表3.1 人口直接分野の主要協力案件(1989-1999)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出所:JICA「人口・エイズ分野実績1993~1999年」、外務省『我が国の政府開発援助の実施状況に関する年次報告』(94年度版~99年度版)より作成 |
人口直接分野の協力は、(1)安全な妊娠・出産、(2)家族計画の普及、(3)モニタリング・サーベイ、の3つのサブ・プログラムに分類することができる。図3.1で示される通り、GIIが発表された1994年以降、我が国のインドネシアにおける人口直接分野の協力をサブ・プログラム別にみると、2件の技術協力(「家族計画・母子保健プロジェクト」、「母と子の健康手帳プロジェクト」)を中心に、「安全な妊娠・出産」分野への協力に重点が置かれていることがわかる。また、技術協力の他にも、人口機材特別供与が母子保健手帳の普及を支援し、人口直接分野の草の根無償資金協力も、その大半が「安全な妊娠・出産」を目的としたプロジェクトを支援している(表3.1)。
図3.1 スキーム別人口直接分野の協力実施件数(1994-1999)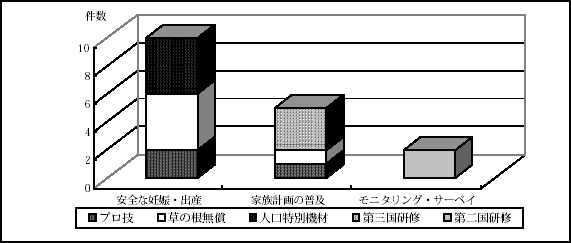 |
| 出所:JICA人口・エイズ分野実績、我が国の政府開発援助 下巻 2000年度版 |
サブ・プログラム別に協力を時系列でみると、人口直接分野で「安全な妊娠・出産」への協力の実績額が急激に増加したのは、1997年以降であることがわかる(図3.2、3.3)。
図3.2 サブ・プログラム目標別協力案件数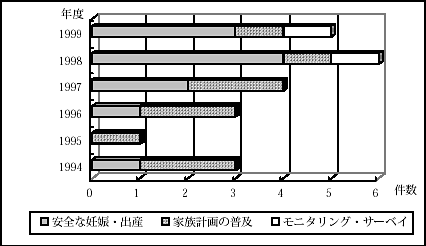 |
| 出所:JICA人口・エイズ分野実績、我が国の政府開発援助 下巻 2000年度版 |
図3.3 サブ・プログラム目標別の協力実績額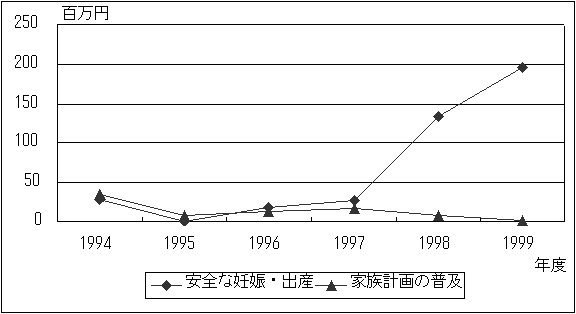 |
| 出所:JICA人口・エイズ分野実績、我が国の政府開発援助 下巻 2000年度版 |
インドネシアは、1970年以降、国家家族計画委員会(BKKBN)を中心に全国規模で家族計画プログラムを推進し、出生率、人口増加率の低下に一定の成功を納めた経験を持つ。このため、人口直接分野のサブ・プログラムの1つ「家族計画」の分野では、我が国は、インドネシアを「南南協力」の拠点とし、第三国研修を実施してきた。
一方、1997年以降、アジア経済危機による政府の著しい財政難が原因で、BKKBNの避妊具・避妊薬の購入予算が大幅に減少した。インドネシア政府は、経済危機の影響で自律的に家族計画を実行できない夫婦に対し、経口避妊薬を無料配布するため「家族計画プログラム」を策定し、国際社会に支援を要請した。
(2)人口間接分野への協力の特徴
人口間接分野(基礎的な保健医療、初等教育、女性の職業訓練・女子教育)での協力は、「基礎的な保健医療」への協力件数が最も多く、GII実施期間中の主要案件だけでも、技術協力4件、無償資金協力8件、有償資金協力4件を数える。また、草の根無償資金協力が12件、開発福祉支援が2件実施されており、この分野でのNGOとの連携も促進された。
一方、「基礎的な保健医療」以外のサブ・プログラム「女性の職業訓練・女子教育」及び「初等教育」分野の協力件数は少ない(図3.4)。
図3.4 サブ・プログラム別協力件数(1994-1999)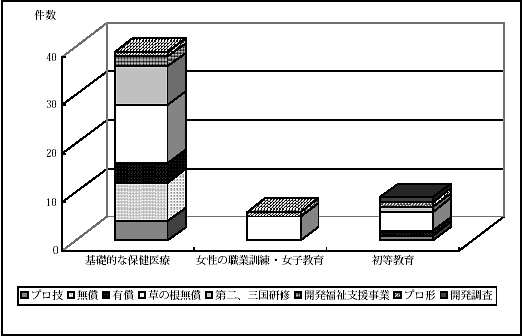 |
| 出所:JICA「人口・エイズ分野実績、我が国の政府開発援助」下巻2000年度 |
「基礎的な保健医療」への協力案件のうち、主要案件数が最も多かったのが、地域保健サービスの改善や、プライマリ・ヘルスケアの拡充を含む「公衆衛生」への協力であり、次いで、機材供与や病院の修復などにあたる「施設改善」への協力が多かった(図3.5)。
図3.5 基礎的な保健医療分野への協力の内訳(1994-1999)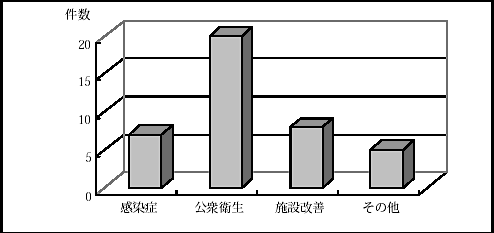 |
| 出所:JICA人口・エイズ分野実績、我が国の政府開発援助 下巻 2000年度 |
「公衆衛生」への協力件数は、1998年以降増加し、「施設改善」への協力件数を大幅に上回るようになった。近年、インドネシアでの我が国の保健医療協力は、「サービス」の改善や「システム」の拡充など、ソフトコンポーネントへの協力が増加している傾向が伺える。有償資金協力案件においても、1980年代は医療器材供与関連が大半だったが、1995年以降、保健分野の円借款案件に、トレーニング等のソフトコンポーネントが含まれるようになってきた2。
図3.6 基礎的な保健医療分野への協力の経年変化(1994-1999)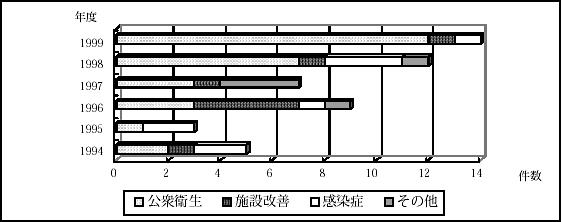 |
| 出所:JICA人口・エイズ分野実績、我が国の政府開発援助 下巻 2000年度版 |
(3) HIV/AIDS分野への協力の特徴
インドネシアでは、我が国のエイズ分野への協力は非常に少ない。エイズ分野の主要協力案件7件中、4件は草の根無償資金協力によるNGOへの支援であり、その他は有償資金協力、医療特別機材供与、第三国研修が各1件となっている(表3.2)。エイズ分野の有償資金協力案件(「スラウェシ地域保健医療強化計画」)は、血液供給システムの整備と強化を通して、妊産婦死亡率の低減、エイズやC型肝炎等の感染症の予防を図るなど、地域保健医療水準を向上させることを目的としており、エイズ対策に活動の目的を特化したものではない。エイズ分野の協力は「予防・啓発」「患者及びその家族のケア」「研究開発・技術向上」と、3つのサブ・プログラムに分類されるが、インドネシアでの我が国のエイズ分野の協力は「予防・啓発」への支援が比較的多い(図3.7)。
表3.2 インドネシアでのエイズ分野の主要案件(1994-1999)
|
|||||||||||||||
| 出所:JICA「人口・エイズ分野実績1993~1999年」、外務省『我が国の政府開発援助の実施状況に関する年次報告』(94年度版~99年度版)より作成 |
図3.7 中間目標サブ目標レベル協力案件数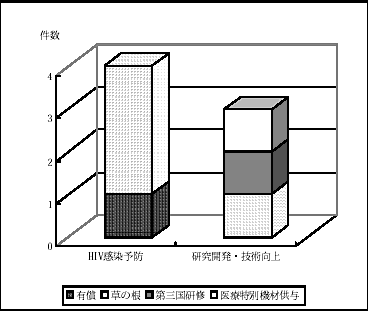 |
| 出所:「JICA人口・エイズ分野実績、我が国の政府開発援助」下巻 2000年度版 |
3.1.2 GIIの認知度
インタビュー調査の結果、我が国の大使館及び援助実施機関(国際協力事業団、国際協力銀行)の保健案件担当者は、「GII」とその内容について認知しているが、担当しているどの案件が「GII」に分類されているかについて、明確には把握していなかった。プロジェクト方式技術協力案件の派遣専門家も、「GII」について聞き知ってはいるが、担当プロジェクトがGIIに分類されているか否かについての認知度は低い。政策レベルで打ち出されたイニシアティブと、実際に協力案件を動かす現場との乖離が推察される。
インドネシア政府の保健省担当者(HIV/AIDS担当)、プロジェクト方式技術協力案件のカウンターパートの間では、「GII」は全く認知されておらず、国際機関(UNICEF、UNFPA)についても同様であった。政策レベルで発表されるイニシアティブが、我が国の協力の方向性を示すものであることから、イニシアティブを打ち出した後の対外広報活動の重要性を示唆する結果となった。
尚、国際機関職員及びカウンターパートの間では、「沖縄感染症対策イニシアティブ(IDI)」については、2000年12月に会議を開催した経緯から、記憶に新しく、比較的認知度が高かった。
3.1.3 他開発パートナーとの連携
(1)UNFPAとのマルチ・バイ協力による人口特別機材供与
我が国は、UNFPAとのマルチ・バイ協力による人口特別機材供与を通して、インドネシアの母子手帳の全国展開を支援している。インドネシアの母子手帳は、技術協力「母子保健・家族計画プロジェクト(1989~1994)」とインドネシア保健省との連携により中部ジャワ州で開発され、1994年、パイロット地域の人口15万人を対象に試行が開始された。インドネシア政府は母子手帳の母と子の健康増進にかかる有益性を認め、1997年には、中部ジャワ州全県及び全市(人口300万人)に加え、他の4つの州で母子手帳の配付を開始した。我が国は、1997年から2004年までの予定で、UNFPAとのマルチ・バイ協力により、年間約2000万円の人口特別機材供与を出資し、主として母子手帳の印刷を支援している。この協力により、2000年度は、約80万冊の母子手帳および母子手帳ガイドブックを印刷し、対象8州ならびに保健省中央へ配付した。
(2)「母と子の健康手帳プロジェクト」を通した他の開発パートナーとの連携
技術協力「母と子の健康手帳プロジェクト」は、インドネシア保健省が統括している「母子手帳プログラム」の一部である。同プログラムが母子手帳の全国展開を目指しているため、JICAプロジェクトの対象地域以外で、母子保健分野で活動する他の開発パートナー(NGO、国際機関、二国間ドナー、等)との調整が重要であり、カウンターパートであるインドネシア保健省のイニシアティブで連携が進んでいる。例えば、同プログラムに対し、世界銀行は1995年、ADBは1999年、UNICEFは2000年から、母子手帳印刷費やトレーニング費用を拠出しており、JICAプロジェクトは、導入期のセミナーや、一部トレーニングを、これらの機関と連携して実施している。2000年現在、インドネシア26州のうち16州(このうち3州はごく限られた地域のみ)で母子手帳が使用され、対象妊産婦は145万人にのぼるが、このうち我が国が負担している母子手帳は約80万冊、残りは他ドナー、NGO、または地方自治体が、それぞれの予算で印刷している。
表3.3 母子手帳の印刷における他の開発パートナーとの連携状況
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *印はいずれも2001年から実施予定
◎はJICA「母と子の健康手帳プロジェクト」対象地域を含む州 WV: ワールド・ヴィジョン(USAIDからの資金) ADRA: アドベンティスト・ディベロップメント・アンド・リリーフエージェンシー PCI: プロジェクト・コンサーン・インターナショナル NTB: ヌサ・テンガラ・バラット NTT: ヌサ・テンガラ・ティムール 出所:JICA.プロジェクト方式技術協力案件概要表「インドネシア母と子の健康手帳プロジェクト」 |
3.1.4 評価結果(妥当性、効率性、効果、協力の成功例)
(1)妥当性
a.当該国GII分野の開発課題/開発政策/受益者のニーズに対する妥当性
前述の通り、GII発表以降、インドネシアでの人口直接(リプロダクティブ・ヘルス)分野での我が国の協力は、母子手帳の普及を中心に、安全な妊娠・出産の分野に重点が置かれてきた。また、人口間接分野で、基礎的な保健医療、特に地域保健サービスの整備(公衆衛生)に重点を置いた協力が行われ、地域の保健医療インフラを整備することにより、リプロダクティブ・ヘルス分野での目標達成に貢献するというプログラムを形成している。
インドネシアでは、妊産婦死亡率が高く、1994年は出生10万人あたり390人と、東南アジアでは最も高い値を記録した。妊産婦の主な死因として、妊娠中の出血、流産の合併症、産褥熱等が挙げられている。また、乳幼児死亡率も高く、1995年は、出生千あたり55人と、これも東南アジア地域で最も高く、隣国フィリピンの約2倍であった。乳幼児の主な死因として、急性呼吸器系感染症、新生児仮死、分娩障害、感染症、下痢症、等が挙げられている。
このような状況を背景に、インドネシア政府は、第六次保健計画(1994~1999)の中で、重点課題として(1)保健サービスの質的向上と公平な分配、(2)コミュニティにおける栄養状態の改善、(3)コミュニティおよび民間部門の参加促進、(4)プログラム管理の改善、を挙げ、これらを通した(1)乳幼児・妊産婦死亡率の低下、(2)乳幼児と妊娠可能年齢の女性及び妊産婦の栄養改善、を重要課題として強調している。特に妊産婦死亡率については大幅な改善が目標とされ、第五次保健計画終了時(1993年)の出生10万あたり425を、第六次保健計画終了時までに225まで引き下げることを目標値として掲げた。
このような現状及びインドネシア政府の保健医療分野の方針に鑑み、安全な妊娠・出産と、母と子の健康増進に重点を置いた我が国の人口直接(リプロダクティブ・ヘルス)分野の協力は、その方向性において妥当であったと考えられる。1999年、インドネシア政府は、今後10年間の保健・医療に関する政策方針として「ヘルシー・インドネシア2010」を発表し、従来の「治療」「リハビリテーション」といった「受け身的」な保健医療政策を「疾病予防、健康増進」へと転換していく基本方針を打ち出した。前項でみてきたように、人口間接分野での我が国の協力は、1998年以降、地域保健サービスの改善や、プライマリー・ヘルス・ケアへの協力が増加しており、近年のインドネシア政府の方針と整合している。
家族計画分野では、1970年代以降、インドネシア国家家族計画委員会(BKKBN)の主導で、全国レベルで対策が行われ、一定の成果をあげたことから、我が国はインドネシアを同分野の「南南協力」の拠点と位置付け、第三国研修を行ってきた。しかし一方で、1997年以降は、経済危機の影響により、BKKBNの避妊具・避妊薬の購入予算が大幅に減少し、国の支援を必要とする家庭への避妊具・避妊薬の無料提供が困難となっている。
HIV/AIDS分野については、インドネシア政府が、近年漸く、エイズ対策戦略の必要性を認識しつつある状況であり、我が国はこの分野ではこれまであまり多くの協力は行ってこなかった。GII発表以降、インドネシアのHIV/AIDS分野における主要な協力として挙げられるのが、血液供給システムの強化を目的に行われている有償資金協力案件「スラウェシ地域保健医療強化計画」である。しかし、インドネシアでのHIV感染は、異性間交渉によるものが半数以上を占め、輸血による感染は、1.6%に過ぎない3。インドネシアのエイズ患者及びHIV感染者数は、保健省統計では1727人(2001年1月)と発表されているが、国際的には5万2000人以上のHIV感染者が存在すると推計されている。現状を正確に把握し、サーベイランスや検査技術の向上、予防に関する啓発活動等、実状とニーズに則した、より優先順位の高い分野への協力を目指し、インドネシアにおける我が国のHIV/AIDS協力のプログラムを作ることが重要である。
(2)効率性
a.案件のスケジュール通りの進捗と技術専門家派遣
今回、現地調査で訪問した案件4はいずれも、比較的計画通りに案件が進捗していた。案件のカウンターパート機関に、活動が予定通りに進んでいる理由について尋ねたところ、技術協力の派遣専門家がプロジェクトサイトに常駐し、カウンターパート機関と日々コミュニケーションをとっていることが挙げられた。技術協力と専門家派遣については、その経済効率性に関し、近年さまざまな意見が議論されているが、案件の効率的な実施(予定に則した進捗)に関するカウンターパートからのこのような指摘は、一考に値する。但し、技術協力の派遣専門家が、案件の進捗を計画通りにマネジメントできるか否かは、個々人の資質によるところが大きい。全ての案件について、技術専門家による効率的な案件の実施を行うためには、協力実施機関によるモニタリングのシステム作りやマニュアル化が必要となる。
b.母と子の健康手帳の普及~プロジェクト方式技術協力、スキームの組み合わせによる継続的支援
母と子の健康手帳の普及については、上記で何度も述べてきたように、1994年まで行われていたプロジェクト方式技術協力でその開発と試行が実施され、その後、母子保健分野の派遣専門家に引き継がれ、インドネシアの保健省が国家プログラムとして母子手帳の普及を開始した後は、UNFPAとのマルチ・バイ協力による人口特別機材供与で母子手帳の印刷を支援し、また、1998年から開始されたプロジェクト方式技術協力「母と子の健康手帳プロジェクト」で技術支援を行う等、母子手帳の普及を通した母と子の健康の向上という1つの目標のもとに90年代半ばから継続して、成果を着実に積み上げていく努力がみられた。このように、特定の目標に対し、いくつかの協力のスキームを組み合わせ、一定期間継続して協力を行ったことは、プログラム目標達成の観点から効率性が高められたと考えられる。
c.草の根無償資金協力とその他の我が国の協力との連携
在インドネシア日本大使館の担当者とのヒアリングによると、草の根無償資金協力の新規案件の選定にあたっては、既存の我が国の協力案件と被供与団体の関連性や相互補完性への配慮に努めているとのことであった。既存の協力案件との、分野、タイミング、地理的補完性に配慮し、戦略的に草の根無償資金協力を投入していくことは、プログラム目標の達成という視点から効率的な協力のアプローチといえる。
(3)効果
これまでみてきた通り、我が国のインドネシアでのGII関連分野における協力は、安全な妊娠・出産への支援を中心に行われており、プログラム目標として、インドネシアの母と子の健康増進が中核に据えられていた。このプログラム目標の達成度を測る主要な指標として、各関連案件では、妊産婦死亡率と乳児死亡率の低下を掲げている。
これらの指標について、GII発表以前と以後を比較すると、乳幼児死亡率、妊産婦死亡率共に低下傾向にある(表3.4)。一方、近隣諸国と比較すると、インドネシアの基礎保健指標は必ずしも良い値とはいえない。特に妊産婦死亡率については、第六次保健計画における目標値(出生10万あたり225)の達成には及んでいない。
表3.4 インドネシアの基礎保健指標
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出所:Central Bureau of Statistics, Government of Indonesia |
表3.5 第六次保健計画における主要保健指標目標値
|
|||||||||||||||||||||
| 出所:国際協力事業団医療協力部『国別医療協力ファイル:インドネシア』平成9年3月 |
前述の通り、妊産婦死亡率や乳幼児死亡率が、安全な妊娠・出産及び母子保健分野の協力の目標達成を図る指標の一部としてあげられる一方、これらの指標は、保健分野の介入のみで容易に変化する指標ではなく、経済、社会のさまざまな変数に影響を受ける。このため安全な妊娠・出産及び母子保健分野での我が国の協力のインパクトを測るには、母親の知識向上、生活の変化、ハイリスク妊婦のリファラルケース等、関連のある種々の指標について、量的、質的に詳細調査を実施する必要がある。今回のGII評価では、時間的制約及び調査のTORに鑑み、これらのインパクト評価については調査を実施していない。従って、これらの指標の経年変化と我が国の協力の相関関係についてここで明言することはできない。
しかし、我が国が支援する母子手帳の普及は、国家プログラムとして全州導入を目指し、プロジェクト方式技術協力を通して、プロジェクト対象地域内外での研修活動やワークショップの開催、他の開発パートナーとの連携、国際シンポジウムの開催等、広範な地域での活動を展開しており、パイロット地域を越えた全国レベルへの貢献に努めている。また、さきにも触れたように、安全な妊娠・出産と母子保健分野に対し、我が国は1990年代後半に集中的な投入を行っている。インドネシアの乳児死亡率や妊産婦死亡率が、近隣諸国に比しさらなる改善の余地はあるものの、徐々に低下していることに対し、我が国のこれまでの協力が何らかのかたちで貢献しているものと推察することは可能と考えられる。
(4)協力の成功例
我が国がインドネシア保健省との協力で、開発、普及を支援してきた母子手帳は、パイロット地域で試行された活動が、インドネシア全国レベルへの普及という、広範囲への適用が可能となった点で、日本の協力の「成功例」の1つといえる。
本協力の成功要因として、次の点が指摘されている。
| 1) | 「母子保健手帳」が、目に見える、わかりやすい、子供の成長モニタリングの媒体であった。 |
| 2) | 母子の健康の向上という案件目標が国、地域の優先順位に整合していた。 |
母子保健手帳による母と子の健康管理の手法が我が国で成熟期にあったため、技術移転をスムーズに行うことが可能であった。
プロジェクト方式技術協力の後の専門家派遣や人口機材特別供与による支援等、我が国のコミットメントが十分であった。
さらに、プロジェクト方式技術協力の実施にあたっては、パイロット地域の選定とカウンターパートのキャパシティーについても、充分な配慮がなされている。現在実施されているプロジェクト方式技術協力の対象地域は、リプロダクティブエイジの女性の識字率が80%と、比較的高く、パイロット地域として、限られたプロジェクト実施期間中に効果が見込まれる地域を選定している。また、地方自治体と中央保健省のカウンターパートの能力が高く、母子手帳普及の推進活動、関連援助機関の調整等、カウンターパートがイニシアティブをとって実施しており、被援助国のオーナーシップの確保が可能となっている。
一方、本件協力の「効果」については、指標や、効果測定のための調査方法について未だ議論されているところであり、本件を日本の協力の「成功例」として明確に位置づけていくためにも、今後、質的、量的指標を併せた案件の効果についてモニタリング・評価を実施していく必要がある。効果の測定及びインパクト調査の必要性については、今回の現地調査中、本案件に派遣中の専門家及びカウンターパート機関からも指摘があった。また、保健医療サービスの地方分権化が進むなか、母子保健手帳の印刷費確保が重要となっており、回転資金制度の導入等、自立的かつ持続可能な活動実施の仕組みづくりが今後の課題といえる。現在実施中の技術協力では、既に2地域で、試験的に母子保健手帳の印刷に回転資金制度が導入されている。
3.1.5 今後の協力のあり方
(1)自立型保健医療体制の確立
インドネシアでは、国家予算に占める保健医療費の割合が2.6%に過ぎず、保健医療施設、設備、医薬品を外国の援助に依存することが多く、簡易な医療機材のメンテナンスも自国のみではままならないケースが多い。1997~98年の経済危機の際は、医薬品や検査試薬の不足により保健医療サービスの質が低下し、社会的弱者が保健医療サービスへのアクセスを遮断される事態となった。この経験から、経済危機による公的セクターの保健医療支出の減少等、外部要因に左右されない、持続的な保健医療サービスの提供を目的とした自立型保健医療体制の確立が今後の課題であり、我が国の協力も、この点に配慮した協力のプログラムづくりが求められる。
(2)特定の目標に向けた継続的投入
インドネシアにおいて、我が国は、母子保健の向上を目指し、プロジェクト方式技術協力、専門家派遣、国際機関とのマルチ・バイ協力、等、種々のスキームを組み合わせ、継続的に協力を実施してきた。このように特定の目標に対し、いくつかの協力のスキームを組み合わせ、一定期間継続して協力を行うことは、プログラム目標達成の観点から効率性の高い協力のアプローチと考えられる。
(3)プログラム戦略と草の根無償資金協力
インドネシアでは、草の根無償資金協力案件の選定に際して、我が国の当該分野のその他の協力との関連性を重視していた。プログラム戦略を明確にし、これにもとづく優先分野と重点に沿って、草の根無償資金協力案件を選定すれば、草の根無償資金協力と他のスキームとの有機的な連携が可能となる。プログラム戦略にもとづいて、どのような分野に草の根無償資金協力案件を投入していくかを明らかにしておくことは、効率的なプログラム目標達成のために重要である。
1 GIIでは、「人口分野」を「リプロダクティブヘルス」の幅広い概念で捉え、人口直接分野には、女性の周産期の健康の向上を支援する意味で「母子保健」及び「安全な妊娠・出産」が含まれている。
2 GII評価団の現地調査でのインタビュー(国際協力銀行 現地駐在事務所 担当者)からの情報による。
3 国際協力事業団.平成9年『国別協力医療ファイル:インドネシア』
4 今回、インドネシアの現地調査では「母と子の健康手帳プロジェクト」及び「南スラウェシ地域保健強化プロジェクト」と、2つのプロジェクト方式技術協力案件を訪問した。

