地球温暖化対策関連ODA評価
調査報告書
第5章 総合評価
5-3 インパクト
(1) 期待されるインパクトの評価
対策分野ごとに期待されるアウトカムをロジカル・フレームワークにより整理すると、温暖化対策ODA全体から期待されるインパクトについては、以下のように記述できる。
我が国の温暖化対策ODAは、先に説明したように副次的、間接的温暖化対策が多いために、地球温暖化対策以外でのインパクトが大きい。特に、産業分野での取組が多い削減対策では、エネルギーの安定供給、産業振興への貢献、公共交通インフラの整備など、被援助国の持続可能な開発に直接寄与するインパクトが多く期待される。また、地域環境への好影響も期待される。
また、吸収源分野の事業では、元来、砂漠化対策や生物多様性保全を目的とした植林や森林保全などを目的とした事業となるため、それら分野でのインパクトが多く期待される。
適応分野では、削減・吸収源と比べて、さらに地球温暖化対策としてのアウトカムとそれ以外のアウトカムの垣根があいまいであり、多くの一般的な持続可能な開発のための援助が適応事業としても分類される。先に見たように、適応事業はそのほとんどが、気候変動に対する脆弱性の高い国々を対象としているため、これらの事業によって回避される経済的損失についても、かなりの規模にのぼると考えて差し支えない。
温暖化対策ODAが、地球温暖化対策については「副次的」な目的となっている事業がほとんどを占めることから考えれば、地球環境無償ガイドラインや環境アセスメントなど、既に導入されている環境配慮手法が適切に運用されていると仮定すれば、環境面での負のインパクトは、最小限に抑えられるように事業が計画されていると考えることができる。また、貧困対策や女性の参加・受益の確保、社会的弱者への配慮、民主的ガバナンスなど、社会的なインパクトについても、同様に考えることができる。
総合的に評価すれば、京都イニシアティブは持続可能な開発を支援する事業のうち、地球温暖化対策効果のあるものをリストアップしている側面があることから、逆にこれらの事業による正負の社会的、環境的インパクトは、望ましい結果となるような手当てが既に打たれているといえる。
図表 温暖化対策ODAの中心である京都イニシアティブのロジカル・フレームワーク
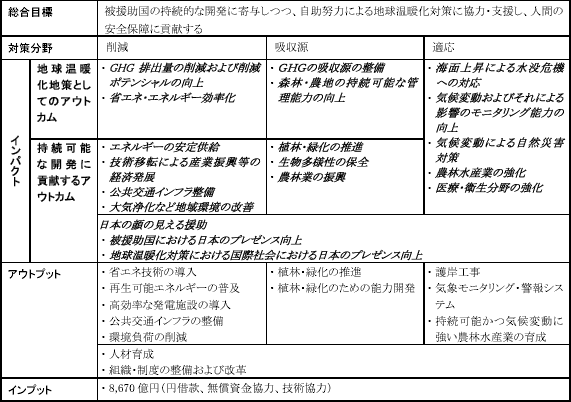 |
| 出所) 野村総合研究所作成 |
(2) 「顔の見える援助」の視点からの評価
日本国政府にとって、ODAが重要な外交手段の一つである以上、ODAにより実施された案件が、被援助国政府・産業界・国民によって認知されることは重要である。特に、機材供与型の無償資金協力の場合は、技術協力と異なり、「日本の考え方や経験、技術を伝える機会」は、それ程多くないため、能動的な広報活動に留意する必要がある。
このような発想に基づき、ODA認知度に係るヒアリング調査の結果に基づき、温暖化対策ODAの評価を行った結果を以下に示す。
<ODA認知度に係るヒアリング調査の結果>
温暖化対策ODA案件が、「日本政府のODAにより実施されたもの」ということが、どれだけ認知されているかにつき、現地ヒアリング/視察調査を実施し、いくつかの回答を得た。主な回答は、以下の通りである。
1) 中国政府国家環境保護総局におけるヒアリング結果
・ 日本のODAは、金額規模が大きいものの、対外的広報が不十分であり、一般的に中国国民による認知の度合いは低い。アジア的なやり方と言えるかもしれない。
2) 湖北省林業庁におけるヒアリング結果
・ 「漢江上流水土保持機材」が日本のODA事業により実施されたということは、現地の住民や役人も全て承知している。
3) 在中国日本国大使館におけるヒアリング結果
・ 草の根無償1件でも、数億円の無償資金協力案件1件でも、メディアに取り上げられる際には、同じような情報量となる場合がある。より一層、中国国民への広報が行き届くような工夫が必要である。
・ 大使館としては、折ある毎に現地メディアを呼ぶなどして、広報活動には留意している。
4) グレシック火力発電所の視察結果
・ 運転指令室や配電盤にはODAマークが貼り付けられていたが、「グレシック火力発電所が日本の円借款により建設され、日本の無償資金協力によりリハビリされたものである」ということは、分かり難かった。
<総括評価>
今回の現地調査は非常に短期間であり、直接、現地住民の声を聞くことはできず、二次的な情報の収集に留まるものであることを前提制約とした上で、上述の結果より、以下のようなことが言える。
・ 全般的に、被援助国における日本のODAの広報活動を、より強化すべきである。但し、被援助国政府との歴史的関係等にも配慮する必要はある。
・ 供与機材に対するODAロゴの使用は、定着しつつあるようであった。広報効果を高めるためには、現地大使館等の一層の活動に期待したい。既に定着している竣工式等へのメディアの招待に加え、一般国民の目に触れる機会の少ない案件、完成以降数年を経過した施設等についても一層の広報が必要であり、ブランタス河での開発40周年のプレイアップや、草の根無償で実施している有識者への書簡の送付など、様々な機会を捉えて広報を展開していくことが必要である。

