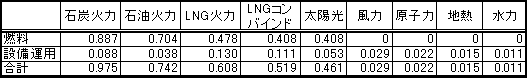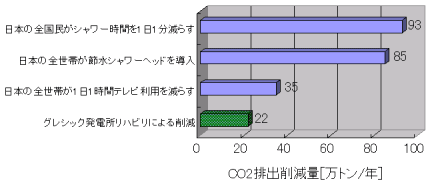地球温暖化対策関連ODA評価
調査報告書
第5章 総合評価
5-2 有効性
(1) GHG排出削減・吸収への日本の温暖化対策ODAの貢献度
京都イニシアティブは、持続可能な開発を目的とする「副次的」事業と、温暖化対策としての成果の発現に時間を要し、かつ成果の確認が困難な「人づくり」事業が中心であることから、直接的に地球温暖化対策に寄与する事業は多くない。この事実は、地球温暖化対策の観点からは、有効性が十分に担保されていないとも考えられるが、温暖化対策ODAの総額は、(条件等が違うために単純比較はできないものの)他国の温暖化対策ODAの規模と比較しても飛びぬけており、その規模の大きさから全体としては地球温暖化対策として有効な成果を上げるているものと期待される。但し、明確に温暖化対策への貢献度が測定・評価できる体制になっていない点は、今後の改善点といえる。
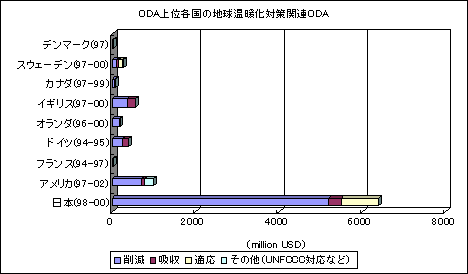 |
| 出所)各国のUNFCCC国別報告書および各国統計。日本のデータは、外務省のCOP6再開会合向け資料 注)各国のデータは、年度・期間、温暖化対策ODAの定義に違いがあることに注意。 |
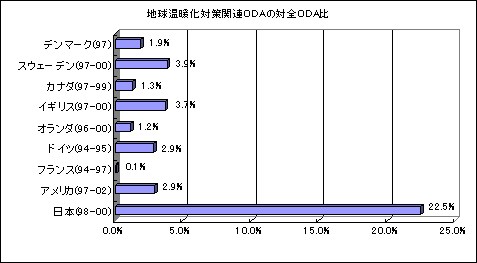 |
| 出所)各国UNFCCC国別報告書およびDACデータ |
(2) UNFCCCへの参加支援
技術協力ODAには温暖化対策そのものの知識や、UNFCCCへの報告に際して必要な人材を育成する案件があり(例えば、地球温暖化防止技術、地球温暖化対策コース等)、その対象国は東アジア、東南アジア、中南米、アフリカ諸国と広く対象範囲を設けている点で評価できる。
適応が必要となる島嶼国、人口が急増するアフリカ諸国、エネルギー効率改善の余地がある中央アジアや東欧への技術協力はまだニーズがあり、期待されるところである。
詳細はこちらをご覧下さい(PDF)
(3) 我が国の技術/経験の活用の評価
技術協力、無償資金協力、そして"タイド"の有償資金協力に限定して考えた場合、我が国の技術/経験を十分に活用しつつ、有効な協力を実施していく必要がある。
地球温暖化対策と関わりの深い、エネルギー分野と植林分野において、特色ある事例や現地調査の結果等を踏まえ、我が国の技術/経験を活用した協力が実施されているかを検証/評価した結果は、以下の通りである。
<エネルギー分野について>
1) 最適電源開発のための電力セクター調査
特に、途上国においては、「電力が絶対的に不足している状況にあること」、「初期投資の大きい新エネルギーは成立し難いこと」等の理由により、新たな電力供給を行う際に、大規模火力といったような従来型の伝統的な電源が選択されがちである。地球規模の視野で考えた場合、この中に、「いかに"地球温暖化対策の視点"を適正な度合いで反映させていくか」、すなわち「GHGの排出量の少ない新エネルギー等の電源の選択を促進していくか」が、重要なポイントとなる。
日本国政府が、2000年度に開発調査にて実施した「最適電源開発のための電力セクター調査」は、国・地域における電源のベストミックスを提案する、政策支援型の技術支援である。このような技術協力は、我が国のノウハウを生かしつつ、被援助国の電源開発計画の中に「地球温暖化対策の視点」を織り込むために非常に有効な手法といえ、評価できる。今後も、このようなタイプの技術協力を重点的に実施していくべきであろう。
2) 新エネルギー分野の技術移転
コストや技術等の制約要因から、先進国の新エネルギー技術を、そのまま途上国に移転することは困難である。このため、(今回評価の対象外であるが)NEDOを通じて経済産業省が実施しているエネルギー分野のモデル事業も、省エネルギー分野が中心であり、新エネルギー分野の事業は限定的である。
今後、地球環境無償案件の形成を促進するためには、まずは、メーカー等を中心として、途上国向けの新エネルギー分野の技術開発を進めていく必要があるといえる。
3) 工場等における省エネルギー推進に係る政策支援
途上国においては、エネルギー供給価格が低く設定されていることが多く、省エネルギー施設の導入によるエネルギーコスト削減効果が、導入コストに比して小さくなりがちである。従って、途上国政府は、企業に省エネルギー施設を導入する経済インセンティブを与える必要がある。
JBICが1999年度に実施した、「フィリピン国産業公害防止支援政策金融事業」や、「タイ国電力消費効率促進事業(1993年度案件のため、今回評価の対象外)は、途上国政府を経由して、途上国民間企業の省エネルギー施設導入を促進する事業である。これらの事業は、途上国における地球温暖化対策を、日本における経験を生かしつつ、政策の面から支援する有効な手法であり、評価できる。
<植林分野について(林木育種分野のケースより)>
植林事業においては、「適地適木」が非常に重要である。日本においては、この発想に基づき、1957年以来の40年以上の間、国家的事業として、林木育種事業を展開してきた。林野庁林木育種センター(現独立行政法人林木育種センター)を中心として、有用な種子の開発に取組、研究成果を蓄積してきた。また、併せて、ジーンバンク事業など、遺伝資源の保全にも取り組んできたという経緯がある。
今回、現地調査の対象とした「中国日中協力林木育種科学技術センター」事業においては、上述の日本の技術を応用する形式にて協力を実施しており、我が国技術を活用しつつ有効な支援を行っているという観点から評価できる。また、中国南部地方の地理・気候条件に合うような種子の開発に取り組んでいることから、適正技術の観点からも評価できる。
現地調査におけるヒアリング調査の結果からも、「同プロジェクトは、第一フェーズの成果を踏まえて慎重に組立てられたものであり、適正な技術開発が行われている」ということを確認した。
|
温暖化対策ODAの有効性ケース・スタディー =CO2排出削減量の算出事例=
電力中央研究所によると、日本の電源別CO2排出量は、以下の通りとなっている。この値は、日本の施設の平均値であり、これをそのままインドネシアのグレシック発電所に当てはめても、実際の削減量を算出することはできない。しかし、得られるデータの制約から、ここでは、この数値を利用して、グレシック発電所リハビリ事業において、石油火力電源をLNG火力電源に転換することによるCO2排出削減量を算出する。 図表:日本の電源別CO2排出量(単位:kg-CO2/kWh)
さらに、これを1年分に換算すると、次のようになる。
|