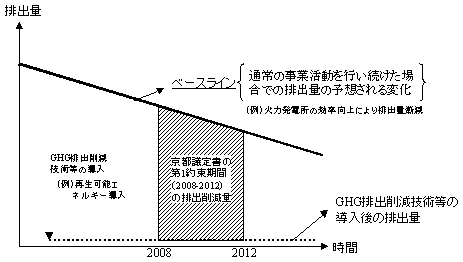地球温暖化対策関連ODA評価
調査報告書
第5章 総合評価
5-1 妥当性
(1) 地球温暖化対策分野の評価
1997年に日本政府が発表した京都イニシアティブは、日本の温暖化対策ODAに唯一の政策的枠組を与えるものといえる。京都イニシアティブは、最優遇条件による円借款も含めると98年以降の3年間で、約8,670億円の資金的・技術的支援を実施してきており、この分野では世界的にも圧倒的な支援規模であるといえ、国際的にも大いに評価されるべきプログラムといえる。
先に見たように京都イニシアティブは、人間の安全保障、被援助国の自助努力、および持続可能な開発への貢献を目的として、1) 人づくりへの協力、2) 最優遇条件(金利0.75%、償還期間40年)による円借款、3) 我が国の技術・経験(ノウハウ)の活用・移転を3本柱として地球温暖化対策への取組を打ち出している。これら3本柱では、削減・吸収・適応の各地球温暖化対策分野を全て対象としており、幅広く地球温暖化対策に取り組んでいるとともに、人づくりからインフラ整備、そして技術移転まで、その方法論においても幅広く取り組んでいる。
このように、京都イニシアティブを中心とする我が国の温暖化対策ODAは、地球温暖化対策として必要な分野を網羅しているといえ、その幅広い取組の方向性は高く評価される。但し、適応事業については、件数・金額的には、一定水準にあるものの、事業内容については今後検討の余地があるといえる(次章で詳述)。
図表 温暖化関連ODA全体の分布(再掲)
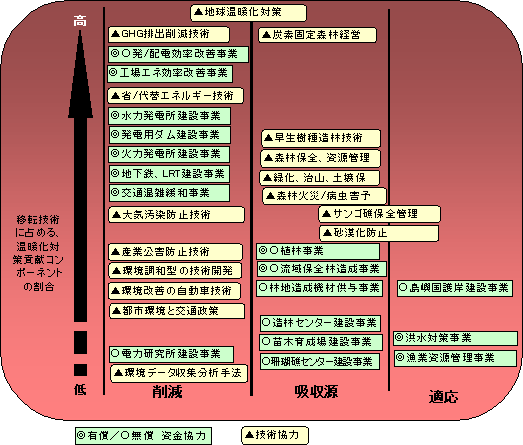 *個々の案件の条件等により、縦軸方向の上下は入れ替わることあり |
| 出所)外務省経済協力局およびJICA環境女性課資料より野村総合研究所作成 |
(2) 各事業の温暖化対策としての妥当性
本来、プログラム・アプローチとは、その企画・立案段階からより上位レベルでのインパクトを目指して、全体フレームの中で戦略的にプロジェクトが開発・実施・管理されるべきものであり、プログラム・レベルでの評価も当然このようなフレームワークの中で実施されなければ、その意味をなさない。
この観点から本調査の評価対象である温暖化対策ODAを見ると、97年6月の国連環境開発特別総会(UNGASS)および97年12月に京都で開かれた第3回国連気候変動枠組条約締結国会議(COP3)を受けて、途上国における地球温暖化対策を支援する「京都イニシアティブ」として展開されているものであり、その実施体制は多岐に渡るものの、地球温暖化対策という共通目標に向けたプログラム・アプローチが取られているといえる。
しかしながら、人づくりへの協力、最優遇条件による円借款、技術・経験の活用・移転という京都イニシアティブの元で実施されている各種プロジェクトが、実際にプログラム・アプローチの中で、案件発掘、計画、実施されているかどうかについては不透明な部分があるといえる。
その一方で、地球温暖化対策自体が、多くのステークホルダーを含み、地球温暖化対策はもちろん、被援助国の経済成長や人材育成、ドナー国の利益など多目的的な取組であり、プログラム・レベルでのアプローチがより求められる分野といえる。
京都イニシアティブの下にリストされている事業の多くは、京都イニシアティブ策定前から既に実施あるいは案件形成がされていたものであり、これらの事業が結果的に地球温暖化対策に貢献することはあっても、案件形成当初から地球温暖化対策を目的としておらず、地球温暖化対策効果は副次的な効果であるといえる。これらの事業については、事後的に地球温暖化対策としての効果の評価を試みることはできるが、当初から地球温暖化対策を目的としていないために達成度や有効性を評価することはできない。
また、京都イニシアティブ発表以降に案件形成・実施されている事業についても、そのほとんどが地球温暖化対策は副次的に位置付けられており、地球温暖化対策としての達成度や有効性を評価することは非常に困難となっている。
一方で、円借款による事業の中には、渋滞緩和のための都市大量交通システム(地下鉄、モノレール等)や天然ガス発電など、ベースライン的考え方ではGHG排出削減になるものの、実際には排出量増につながる可能性の高い事業も含まれている。このような、温暖化対策にはなりうるが実際にはGHG排出増につながる事業については、ベースライン算定(P.66枠内参照)のための厳格な基準を設けるなど、確実に温暖化対策となるようなしくみの導入を検討する必要がある。
アメリカ、カナダ、ドイツなどの他の附属書I国による温暖化対策ODAは、その規模は京都イニシアティブに遠く及ばないものの、具体的事業は温暖化対策を第一義的な目的としているものもあり、より妥当性は高いといえる。今後は、案件形成段階から地球温暖化対策としての配慮を織り込んでいく方策の検討が求められる。
|
||||||||||||||||||
| 出所)各国資料より野村総合研究所作成 |
|
GHG排出削減・吸収量算定におけるベースラインの考え方 GHGの排出削減プロジェクトにおけるGHGの排出または除去を測定する際の比較となるシナリオを「ベースライン」と呼ぶ。その定義・方法論については、京都議定書に関する交渉においてこれまでに具体的に決定されているものではなく、また、既存の研究成果においても様々に定義されているが、通常、プロジェクトタイプの京都メカニズムによる事業活動がない場合に生ずる(であろう)排出量をベースライン排出量とする場合が多い。
これまでにUNFCCCに報告されているAIJプロジェクトにおいては、主に以下のような考え方に基づいてベースラインを設定している。 図表 AIJにおけるベースライン設定
世界銀行PCFでは、JI/CDM市場の創生期においては、さまざまなベースライン算定手法の可能性を追求することが重要であるとし、あえてベースライン算定手法の標準化や一本化は行わないとしているが、基本的にはプロジェクト・ベース(セクター・ベースに対して)での算定に取り組むとしている。その中でも、既に世銀内の従来の事業評価で実績のある「投資分析手法(最も経済的リターンの高いシナリオを選択)」、または「コントロール・グループ分析手法(PCF事業実施前または実施地域外で最も普及しているシナリオを選択)」を適用するとしている。 オランダが実施する炭素クレジット調達事業であるCarboncredits.nlでは、ガイドラインの中でプロジェクト条件によって4つの手法を推薦しており、具体的に分析すべき項目(=Key Factor:人口や経済データはもちろん、導入が計画・予測される関連法・政策、エネルギー価格予測、天候なども分析項目として含まれている)も定めている。 図表 Carboncredits.nlにおけるベースライン算定方法
|
(3) 対象国分布の妥当性
温暖化対策ODAの対象国に関し、将来のGHG排出量を示唆するデータと、これまで日本のODAにより実施してきた、削減、吸収、適応対策事業を、地理的な分布の観点から比較した。併せて、ODAの基本戦略である"アジア重視"も考慮しつつ、日本の温暖化対策ODAが、適所で実施されてきたかどうかに関し、妥当性を評価した。
第3章において、無償/有償資金協力の案件件数と合計額、技術協力の合計額を示したが、無償/有償案件については件数、金額ともに中国、インドネシア、インド等アジア地域が際だって多い。これはODA大綱においても明言されている通り、アジア重視の政策を反映している。技術協力はアジア以外に中南米も多く、アフリカ諸国も対象国となっている。
対象国の温暖化への関与度を、予想人口伸び率とGDP成長率(第2章参照)とで測ると、直近10年のGDP年平均増加率は、中国、インド、東南アジア諸国が特に著しく高い値を示しており、人口増加率の予測では、アフリカの増加が際だって高く、東南アジア諸国、中南米諸国も比較的高い。
GHGの排出源を、産業部門、民生部門、運輸部門の主に3部門に分けて考えた場合、特に産業部門については、第2章で示した産業用エネルギー消費の変化率が著しい地域が、最も排出削減対策ODAの対象として妥当な地域といえる。
現在のアジア地域に重点政策を基本方針とし、その枠内で温暖化対策ODAを進めるならば、アジア地域の中での、特に削減、吸収、適応をそれぞれ進める余地のある国を対象とする案件形成を推進していく必要があろう。
1) 削減関連の温暖化対策を行う余地
対象国の削減関連の温暖化対策を行う余地を、エネルギー消費当たりGDP(15ページ参照)で測ると、GDP産出に必要なエネルギー消費量の高い国(エネルギー消費当たりGDPの低い国)は、コスト面でも技術面でも削減が比較的容易と考えられ、費用効果的に有利に排出削減対策を実施することができる。単位エネルギー消費量当たりのGDPは、ロシア、中央アジア、アフリカにおいて低い値となっている。
一方、無償/有償資金協力案件で、副次的に削減効果のある案件(金額ベース)は第3章に示した通りであるが、案件数は中国、フィリピン、インドネシアに多く、ほぼエネルギー効率の実情(すなわち削減効率の高い国・地域)と合致しているといえる。
2) 吸収源関連の温暖化対策を行う余地
対象国の吸収源関連の温暖化対策を行う余地をここでは森林面積減少率で測る(17ページ参照)。森林面積減少率の高い国では、水土保全、生態系保全案件による副次的吸収対策が比較的容易に実施できると考えられる。直近10年の森林面積減少率は南米諸国、アフリカ諸国が著しく減少している。
一方、無償/有償資金協力案件で、副次的に吸収効果のある案件(金額ベース)は第3章に示した通りである。インドネシアは依然減少傾向にあり、今後も継続的な支援が必要である。
3) 適応関連の温暖化対策を行う余地
IPCC、特に温暖化の影響を扱う第2作業部会では一貫して適応を議題に取り上げ、その必要性や重要性を確認しているが、具体的な適応策や技術についての知見が十分得られているとはいえない。また、その環境への影響範囲は、生物多様性、水資源、農業と食糧安全保障、森林、林業、漁業、海洋、人間の居住環境、健康等多岐に渡り、副次的効果も明らかには分かりにくい。
国立環境研究所地球環境研究センターでは、アジア地域の国々(バングラデシュ、中国、インド、タイ、ヴィエトナム)、南太平洋島嶼国(フィジー、キリバス、サモア、トンガ、ツバル)の海面上昇による脆弱性評価をまとめており(海面上昇データブック, 国立環境研究所地球環境研究センター, 2000)、それぞれの地域で海面上昇による著しい影響が報告されている。
地球温暖化対策の観点から考えた場合、今後は、科学的見地から地球温暖化に係る脆弱性が高いと位置付けられた海岸地域や小島嶼国に対し、適応事業への支援を拡大していくことが重要であろう。
(4) 被援助国の持続可能な開発への貢献
京都イニシアティブにおいては、地球温暖化問題を「その国の産業構造、ライフスタイルに根ざした問題であり、各 国の主体的な取組が肝要であるが、地球的視野から考えれば、温暖化問題解決のため先進国が積極的に途上国の取組に対して協力することが必要である」と位置づけている。これまでのGHGが主に先進国から排出されてきたとはいえ、2010年以降に途上国のGHGが先進国を上回るとのIPCC予測があることも考慮すれば、被援助国における削減対策への協力は、非常に重要な取組といえる。UNFCCC締約国会議(COP)においても、地球温暖化は「共通だが差異のある責任」を附属書I国(主に先進工業国)と非附属書I国(発展途上国)間で共有していることで合意しており、地球温暖化対策に寄与しつつも、非附属書I国の持続可能な開発を支援していくことは、日本を含めた先進工業国の責任であるともいえる。
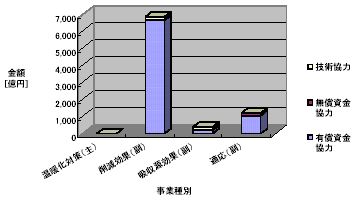 |
| 出所)外務省およびJICA資料より野村総合研究所作成 |
日本の温暖化対策ODAを地球温暖化対策分野別および形態別にみると、円借款による削減事業が大半を占めている。京都イニシアティブでは、最優遇条件による円借款を途上国支援の柱としているが、具体的には、1) 省エネルギー、2) 新・再生可能エネルギー、3)森林の保全・造成、4) 大気汚染対策を主な対象として想定しており、これらは全て被援助国の持続可能な開発に寄与するものと期待される(有償事業リストを参照のこと)。特に、これらの事業は全て持続可能な開発を第一目的としたものであり(逆に地球温暖化対策効果は副次的といえる)、被援助国の持続可能な開発に寄与しつつGHG削減にも寄与するものである。
(5) 被援助国政府の政策との整合性の評価
ここでは、中国とインドネシアを事例として、「エネルギー分野の政策」、「植林分野の政策」のそれぞれを対象とし、日本国の温暖化対策ODAが、これらの政策との整合性を十分に保ちつつ実施されているかにつき、検証・評価を行った。結果は、以下の通りである。
1) 被援助国のエネルギー分野の政策との整合性(インドネシア国の事例)
・ 外務省所管のエネルギー分野ODAは、要請主義を前提として実施しているため、案件選定の段階から、先方政府の政策を反映する選定が行われる。従って、整合性は十分に保たれているといえる。
・ インドネシア国政府のエネルギー分野の所管官庁である鉱山・エネルギー省におけるヒアリング調査の結果、「日本のエネルギー分野のODAは、インドネシア国のエネルギー政策と十分に整合性を持ち、実施されている。」という回答を得た。従って、整合性は十分に保たれていると評価できる。
・ 「第6次および第7次国家電力開発計画」における、エネルギー開発戦略の優先政策は、1)エネルギー源の多様化、2)エネルギー効率の向上、3)環境に配慮した新エネルギー開発の促進等である。日本のODA案件は、以下の事例に示されるように、インドネシア国エネルギー分野の政策を、技術、資金の両面から効果的に支援していると評価できる。
- 「最適電源開発のための電力セクター調査(開発調査2000年度)」により全体政策を支援
- 通貨危機以降、民活導入が頓挫し、効率の悪い発電施設の施設更新のための資金調達が滞り、上述2)の実現が危ぶまれる状況にあるインドネシア国に対し、「グレシック火力発電所(リハビリ無償1998年度)」の供与を行い、政策実現に貢献した。
- 「再生可能エネルギー利用地方エネルギー供給計画(開発調査2000年度)」、「鉱工業プロジェクトアフターケア調査:インドネシア太陽光(開発調査2000年度)」、「地熱技術および開発に係る専門家派遣(1999年度)」、「地熱エネルギーに係る研修への研修員受入(1999年度)」等の技術協力により、上述優先政策1)および3)の実現に貢献してきた。
2) 被援助国の植林分野の政策との整合性(中国の事例)
・ 中国政府は、「国家5ヵ年計画」を基本とし、かなり充実した計画や政策を策定している。「国家5ヵ年計画」の植林・緑化分野においても、1)天然林資源の保護、2)退耕環林、3)三北長江中上流防護林、4)環北京防砂、5)野生動植物保護基地、6)重点地区早生多産林の6大重点項目に従い、植林・緑化事業を推進している。日本のODA技術協力案件も、この重点項目に合致する案件を実施してきており、中国政府の政策に整合する形で進められてきたと評価できる。
・ 日本のODA有償資金協力案件においては、特に、上述重点項目の中の2)および3)に合致するような案件を重点的に採択してきている。従って、中国政府の政策との整合性は十分に保たれていると評価できる。
・ 中国政府の植林・緑化分野の所管省庁である林業局におけるヒアリング調査の結果、「日本の植林分野のODA技術協力は、中国の他地域への拡大を意図したモデル事業として実施してきており、中国の植林政策の目標達成に多いに貢献しているといえる。」との回答を得た。従って、整合性は十分に保たれており、かつ政策実現の要となるような案件を実施していると評価できる。
3) 総括評価
以上の2国における事例からは、日本の温暖化対策ODAが、被援助国政府の政策と整合性を保ちながら進められてきていると評価できる。
これは、第1章3-1でも述べた通り、「日本の外務省ODA案件が、被援助国政府からの要請を基本としていること」に加え、現地大使館が、JICAおよびJBICなどの案件実施機関の関係者とも協力しつつ、先方政府関係省庁との政策対話を密に実施している結果といえる。但し、被援助国側での温暖化問題に対する認識・優先度の低さから、温暖化対策ODA事業としての明示された要請が出されることは、あまりないという状況になっている。
(6) ドナー間調整について
地球温暖化問題は、グローバルな問題であり、かつ先進国(附属書I国)全体が責任を共有する問題でもある。また、CDMの本格化を見据えた動きもあり、先進国各国がそれぞれの思惑を持って、多くの途上国で温暖化対策ODAを展開している。しかしながら、各国が温暖化対策ODA政策を策定する際に、ドナー間での調整は行われていない。UNFCCC締約国会議においても、各国の取組等は発表されているが、ドナー間での調整にまでは至っていない。我が国は、特に米国とは地球温暖化問題でのハイレベル協議を設置しており、今後途上国支援においての活発な意見交換と調整が期待される。
現地調査を行ったインドネシアと中国の事例から被援助国におけるこの分野での調整についてみると、両国とも基本的には従来のドナー国調整の場を活用している形になっている。但し、地球温暖化対策は、被援助国の複数の省庁に散らばっている場合が多く(環境省、産業省、農林省など)、その対策分野ごとの調整が行われる場合はあっても、地球温暖化対策全体の調整の場は、設置されていないようである。これは、被援助国側において窓口が一本化できていない場合が多いためといえ、ドナー国側としてはCDMの本格化を見据えた各国独自の動きもあり、調整へのインセンティブが働きにくいとも考えられる。
そんな中で、中国では、世界銀行中国事務所が中心となって、各ドナー国・機関がCDM分野で何をしているかを整理しようとする動きが見られる。今後は、特にアジア各国において、この分野でのODA
シェアの高い日本が、積極的に調整のイニシアティブを取っていくことが期待される。