地球温暖化対策関連ODA評価
調査報告書
第4章 評価方法
4-3 評価項目
本調査においては、経済協力開発機構(OECD)の開発援助委員会(DAC)が1991 年に発表した「DAC評価5項目」のうち、(1)妥当性(Relevance)、(2)有効性(Effectiveness)、(3)インパクト(Impact)、 (4)持続性(Sustainability)の4項目を評価の柱とした。この中で、地球温暖化の視点を中心に、ISDの視点および納税者の視点も含めた形で総合的に温暖化対策ODAを評価した。
なお、「DAC評価5項目」のうちの「効率性(Efficiency)」については、温暖化対策ODAが、「本来温暖化対策を目的とした事業でないことから温暖化へのインパクトを測る手段が組み込まれていない」ために温暖化への直接的なインパクト(すなわち排出削減量あるいは吸収量)測定が困難なため、本調査での評価項目からは除くこととした。
(1) 妥当性 (Relevance)
ここでは、我が国の温暖化対策ODA政策全体の妥当性を他国の温暖化対策ODA政策との比較および必要性との整合性などから、枠組み全体を評価した。また、事業自体の温暖化対策事業としての妥当性、対象国分布の妥当性についても評価した。
一方で、被援助国の持続可能な開発への貢献度や被援助国政府の政策との整合性、さらには被援助国におけるドナー間調整など、持続可能な開発の視点からみた妥当性についても評価している。
(2) 有効性 (Effectiveness)
本来「DAC評価5項目」では、期待される成果が得られたかどうかについてを「有効性」の項目で評価するものとしている。しかしながら、既に述べたように、本調査で対象としている温暖化対策ODA事業のほとんどは、本来、持続可能な開発への貢献を目的に案件形成・計画されているものであり、温暖化防止への貢献を事業の目的として明確に位置付けているケースは多くない。このことから「地球温暖化の視点から期待される成果」を得られたかについては評価できない。
本調査では、GHG排出削減・吸収への温暖化対策ODAを通した日本の貢献度について評価するとともに、その際の我が国の技術やノウハウがどの程度活用されているかを分析することとした。
(3) インパクト
温暖化対策ODAの実施によって、被援助国において期待される(あるいは予想される)正負のインパクト(=社会的変化)についてを、特に温暖化対策の分野別に分析する。本調査では、1998年以降の事業が主な対象となっており、まだ開始されたばかりの段階にあったり、計画中の事業も少なくないことから、実際のインパクトを評価することはできない。
ここでは、温暖化対策ODA政策全体において期待される成果・インパクト等をロジカル・フレームワークとして対策分野別に整理し、どのような期待(予想される)インパクトがあるかという視点から分析・評価することとした。
また、我が国の納税者への間接的なインパクトという視点から、温暖化分野での我が国のODAが、どの程度被援助国および国際社会に認知されているか、すなわち「顔のみえる援助」となっているかについて評価した。
(4) 持続性
持続性項目は、ODAの実施によって発生する成果・便益を、いかに活動終了後も持続されるかを評価するものである。本調査では、被援助国での地球温暖化対策の長期的継続性への支援として、具体的には、温暖化対策ODA事業採択/内容決定の際の「維持・管理費用」への配慮、およびキャパシティー・ビルディング・プログラムについて分析・評価することとする。
図 評価グリッド
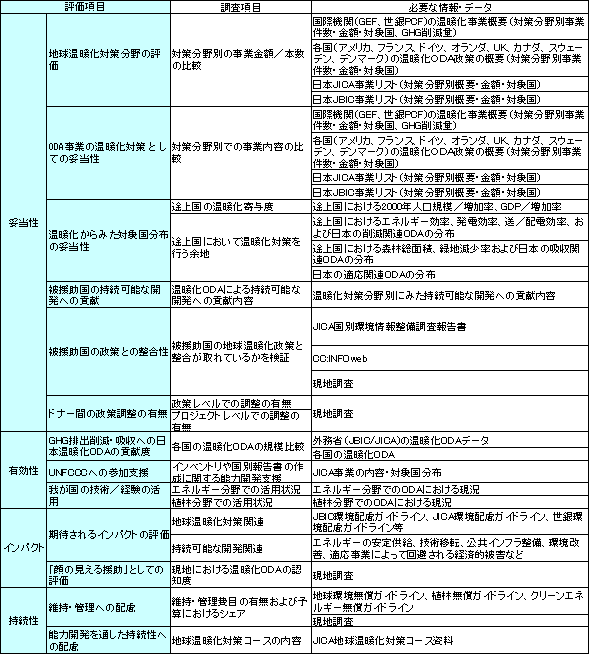 |
| 出所)NRI野村総合研究所作成 |

