地球温暖化対策関連ODA評価
調査報告書
第3章 我が国の地球温暖化対策関連ODAの概要
3-2 日本国政府外務省ODAの実施状況
(1) 分析方法
1) 対象データ
- 有償/無償資金協力:地球温暖化対策関連事業の1998~2000年度実績データ。
- 技術協力:JICA企画部環境女性課が、年度毎に集計している、JICA実施の環境分野における技術協力実績データの1998~2000年度分。
2) 分析手法
- 地球温暖化対策案件の抽出(有償/無償資金協力案件):基本的に上述1)の対象データを利用。
- 地球温暖化対策案件の抽出(技術協力案件):上述1)の対象データの中から、地球温暖化対策に貢献する可能性が低いと思われる、次の分野に該当する案件を除外することにより、地球温暖化対策案件と見なせるデータを集成した。なお、「技術協力は、カバー領域が非常に広範であり、この中から適応分野を抽出するのは困難であること」、「抽出前の元データが環境分野の技術協力案件であり、適応分野に分類可能な案件が抜け落ちている可能性があること」等の制約から、今回の分析においては、適応対策を抽出しないこととした。
上下水道、地下水開発、地方給水、都市排水、水環境管理、廃棄物管理、産業廃棄物処理、有害金属汚染対策、環境負荷物質の分析技術、野生生物保護、生態調査、昆虫学、海洋保全、魚類防疫、気象・水文観測、環境影響評価、農業・農村開発、農薬モニタリング、公園管理、環境行政、環境教育、火山学、地震・耐震工学、砂防、災害調査・復旧、防災行政、リスク評価技術、海洋石油開発に係る安全/環境管理
3) 分析項目
- 地球温暖化対策を第一目的とする技術協力案件が、技術協力全体に占める割合
- 有償/無償資金協力、技術協力の各体系における、温暖化対策ODA案件の、対策分野別/形態別の実施状況
- 有償/無償資金協力、技術協力の各体系における、温暖化対策ODA案件の、対策分野別の国別分布状況
- 有償/無償資金協力、技術協力の各体系における、地球温暖化対策への貢献度に応じた実施案件の分布状況
- 温暖化対策ODA案件の、形態別の総支援額の経年変化
- 温暖化対策ODA案件の、対策分野別の総支援額の経年変化
4) 分析上の制約
- 京都イニシアティブ発表以降(3年度分)のデータのみを対象としているため、対象件数が少ない。
- ほとんどの案件が、地球温暖化対策を第一目的と位置付けて実施したものではなく、結果的に地球温暖化対策に貢献している「副次的」案件である。各案件の地球温暖化対策への貢献度は、明示的なデータとして存在しないため、案件概要等の情報に基づき判断した。具体的な判断基準は、前述2)に示した通りであるが、この基準は本報告書での暫定的な設定に過ぎず、今後、議論を深めるべき課題である。
- 本来、技術協力の概要を示すデータとしては、"当該技術協力により育成された能力"などを表現するデータを用いるべきである。しかし、技術協力の形態が多様であり、例えば「1件の開発調査を通じてどのような量のキャパシティビルディングが行われたか」というような、元データもしくは変換係数が存在しないことから、金額を用いての表現に留めた。
(2) 地球温暖化対策を第一目的とする技術協力案件が技術協力全体に占める割合
「GHGの排出は何らかの経済社会活動に付随するものであること」、「炭素固定を主目的とする植林は、未だ調査研究が行われている実験段階にあること」等の理由により、地球温暖化対策を第一目的とする二国間資金協力は、少なくとも、現時点では存在しない。
一方、技術協力については、地球温暖化対策に係る政策策定等の能力を養成する研修等が、既に実施されてきている。ここでは、そのような地球温暖化対策を主目的とする技術協力を、1998-2000年度に実施の温暖化対策ODA案件と位置付けた事業の中から抽出し、その技術協力全体における位置付けを明らかにする。
以下の5つの技術協力案件が該当案件である。これらの地球温暖化対策を主目的とする技術協力の実施予算額の合計が、技術協力予算総計に占める割合は、約1%である。
図表 地球温暖化対策を主目的とする技術協力案件リスト
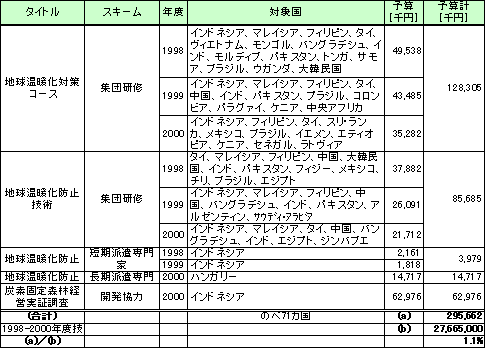 |
| 出所)JICA環境女性課集成の環境分野技術協力案件リスト1998-2000年度より野村総合研究所作成 |
(3) 地球温暖化対策関連ODA案件の対策分野別/形態別の実施状況
1998-2000年度に実施された温暖化対策ODAを、対策分野別に分類し、それぞれの事業金額を示したものは、以下の図の通りである。また、協力形態別に、その対策分野別の内訳を示したものは、以下の図の通りである。
対策分野別の金額規模では、削減効果が群を抜いて多くなっているが、これは、電力エネルギー分野への有償資金協力案件が数多く存在することによるものである。
協力形態別における、対策分野別の内訳で見ると、無償資金協力全体における適応案件の割合が、有償資金協力のそれに比して大きいことが分かる。
図表 温暖化対策ODAの対策分野別の案件実施状況
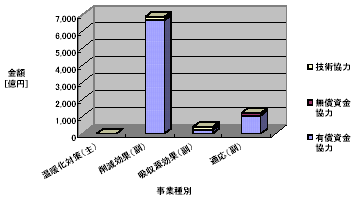 |
| 出所)外務省経済協力局およびJICA環境女性課資料より野村総合研究所作成 |
図表 温暖化対策ODAの形態別の案件実施状況
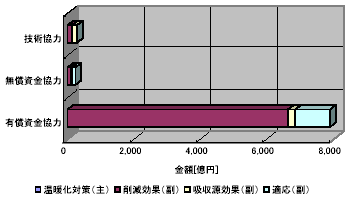 |
| 出所)外務省経済協力局およびJICA環境女性課資料より野村総合研究所作成 |
(4) 地球温暖化対策関連ODA案件の対策分野別の国別実施状況
以下の図は、1998-2000年度に実施された温暖化対策ODA案件に関し、形態別の事業予算合計金額の大きさを、国別にランク分けして示したものである。無償/有償資金協力の案件件数は、ODA大綱の方針通り、アジア地域、特に中国、インドネシアが際だって多い。金額についても同様(次頁参照)
詳細はこちらをご覧下さい(PDF)
金額規模の大きさが日本からの距離に反比例しているような傾向が見られることは、東、東南アジアを、ODA一般の戦略的重点対象国として位置付けていることと関連付けて考えることが出来るだろう。
詳細はこちらをご覧下さい(PDF)
地球温暖化対策を主目的とする技術協力につき、事業予算合計額を国別に示すと、次の図のようになる。
東・東南アジアや、中南米諸国など、途上国の中でも比較的工業化の進んだ国を対象として実施してきていることが分かる。
詳細はこちらをご覧下さい(PDF)
削減対策に係る技術協力につき、事業予算合計額を国別に示すと、次の図のようになる。
東・東南アジアや中南米諸国に加えて、東欧諸国を対象とした技術協力も数多く実施されていることが分かる。一定程度の工業化が進んだ国を主な対象として実施しているためと推測できる。
詳細はこちらをご覧下さい(PDF)
削減対策に係る資金協力につき、事業予算合計額を国別に示すと、次の図のようになる。
少数の国に集中しているように見えるが、これは、今回対象とした資金協力ODAの案件数が少ないことによる。少ない案件数ながらも、排出削減ポテンシャルの高い東・東南アジアの国々(中国、タイ、フィリピン、マレイシア等)に、削減対策に係る大きな金額の資金協力が実施されていることが分かる。
詳細はこちらをご覧下さい(PDF)
吸収源対策に係る資金協力につき、事業予算合計額を国別に示すと、次の図のようになる。
特に、中国において、植林分野の有償資金協力が大規模に実施されており、これを受けて、トータルの予算合計額の大きさでは、中国が群を抜いていることが分かる。また、それ以外の国については、森林減少率の高い国や、もともと広大な森林面積を持っている国が、吸収源対策ODA案件の対象となっていることが分かる。
詳細はこちらをご覧下さい(PDF)
適応対策に係る資金協力につき、事業予算合計額を国別に示すと、次の図のようになる。
適応対策の具体的内容は、治水事業や洪水対策事業がほとんどであるため、そのようなニーズの高い国や地域に、案件が分布していることが分かる。
特に、フィリピン国における適応対策ODA予算額が群を抜いているが、これは、同国を対象として、洪水対策に係る有償資金協力が、複数実施されていることによる。
詳細はこちらをご覧下さい(PDF)
(5) 地球温暖化対策への貢献度に応じた実施案件の分布状況
1) 有償資金協力案件の地球温暖化対策への貢献度に応じた分布
1998-2000年度に実施された有償資金協力の温暖化対策ODA案件を、対策分野を横軸に、事業全体に占める温暖化対策貢献コンポーネントの割合を縦軸にとり、概念的に示したものは、以下の図である。
有償資金協力においては、GHGの排出削減分野にて、多くの事業を実施していることが分かる。これは、そもそも有償資金協力が、経済開発と関わりが深い分野にて実施されることから、経済活動に伴う排出削減事業が結果的に多く実現した当然の帰結といえる。
吸収源対策分野では、吸収手法として主に植物による二酸化炭素吸収しかないため、事業種数としては少数となっているが、一件あたりの規模が大きい場合が多く、吸収源として比較的大きなインパクトを持つ分野といえる。
適応対策分野では、洪水対策事業を中心に、複数の事業が実施されている。
図表 有償資金協力:地球温暖化対策への貢献度に応じた実施案件の分布
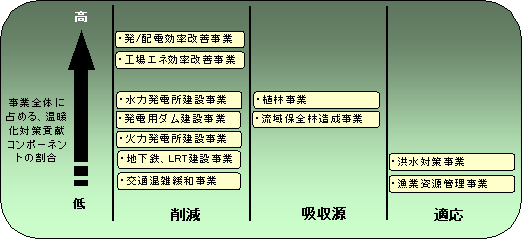 *個々の案件の条件等により、縦軸方向の上下は入れ替わることあり |
| 出所)外務省経済協力局およびJICA環境女性課資料より野村総合研究所作成 |
| 注: この図は、カバーしている分野の視覚イメージ化を目的としたものであり、案件数を反映していない点や、縦軸の方向性が厳密なものでない点等の制約を持つ点に留意が必要である。図中の縦軸の方向性については、考え方として、当該事業がなかった場合と実施した場合における、温室効果ガスの削減または吸収の便益が事業実施による社会便益の合計に占める割合を目安とする。但し、データ(GHG削減/吸収量、各種便益の貨幣価値換算係数)制約から具体的数値を用いて貢献度を算出することは不可能であったため、事業毎の一般的或いは典型的な想定に基づく目安である。 また、表中の事業名称は、具体的な個別案件名称と一対応になっているわけではなく、"事業種"の名称である。以降の、無償資金協力、技術協力に係る図も同様である。 |
||||||
2) 無償資金協力案件の地球温暖化対策への貢献度に応じた分布
1998-2000年度に実施された無償資金協力の温暖化対策ODA案件を、対策分野を横軸に、事業全体に占める温暖化対策貢献コンポーネントの割合を縦軸にとり、概念的に示したものは、以下の図である。
無償資金協力においては、特に吸収源対策の分野で、さまざまな内容の事業を実施している。これら案件は、中国やインドネシア等の数カ国にほぼ集中していることから、各事業間での相乗効果も期待できると考えられる。
削減対策分野では、リハビリ無償による発電効率改善事業等を少数ながら実施している。間接的な効果に留まる案件ではあるものの、電力分野の研究開発を遂行するための施設建設事業も削減対策として分類した。
適応対策分野では、「モルディブ国護岸建設事業」のみを実施している。この事業は、長期にわたり継続的に実施してきた案件である。適応事業の中でも、海水面上昇により島嶼国が被る影響は特に深刻なものと予想されており、この案件は非常に意義深い事業であると言えるだろう。
図表 無償資金協力:地球温暖化対策への貢献度に応じた実施案件の分布
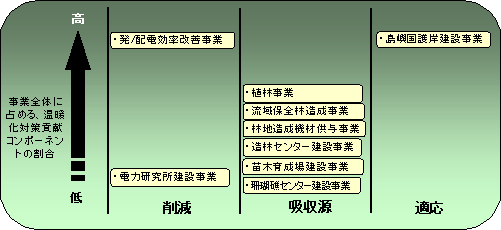 *個々の案件の条件等により、縦軸方向の上下は入れ替わることあり |
| 出所)外務省経済協力局およびJICA環境女性課資料より野村総合研究所作成 |
3) 技術協力案件の地球温暖化対策への貢献度に応じた分布
1998-2000年度に実施された、技術協力の温暖化対策ODA案件を、対策分野を横軸に、移転技術に占める温暖化対策貢献コンポーネントの割合を縦軸にとり、概念的に示したものは、以下の図である。なお、図中の★印は、地球温暖化対策を主目的とする技術協力を示している。
技術協力は、きめ細やかな協力であり、内容や具体的な協力形態(専門家派遣、研修、プロ技、開発調査等)も多岐にわたり、データ件数もかなり多い。従って、以下の図は、元データから、かなり簡略化された形で、技術協力の全体像を表現している。なお、「1.(2)分析手法」で既述したように、今回の分析においては、適応対策分野の案件抽出を行っていないため、この欄が空欄となっている。
削減対策分野と吸収源対策分野のそれぞれにおいて、多岐にわたるキャパシティ・ビルディングを実施していることが分かる。
図表 技術協力:地球温暖化対策への貢献度に応じた実施案件の分布
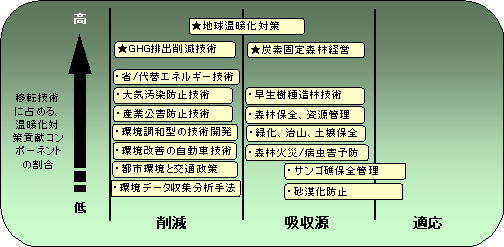 *個々の案件の条件等により、縦軸方向の上下は入れ替わることあり |
| 出所)外務省経済協力局およびJICA環境女性課資料より野村総合研究所作成 |
4) 地球温暖化対策関連ODA全体の地球温暖化対策への貢献度に応じた分布
以上、有償資金協力、無償資金協力、技術協力のスキーム毎に、事業の分布状況を概観してきたが、これらを、一枚の図に集成すると、以下の通りとなる。
ただし、前掲の図の縦軸に着目すると明らかな通り、キャパシティ・ビルディングを目的とする技術協力と、設備/施設の建設により直接的に地球温暖化に貢献する資金協力事業とでは、縦軸を共通化することは困難である。下図は、この限界を認識した上で、全体を概観するために、敢えて一つに集成したものである。従って、縦軸方向のミクロな上下関係に囚われ過ぎることなく解釈する必要がある。
図表 温暖化関連ODA全体の分布
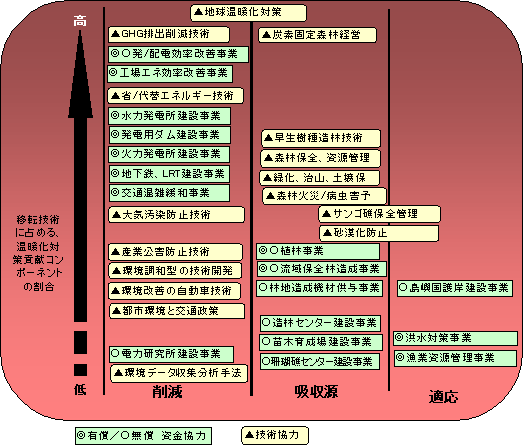 *個々の案件の条件等により、縦軸方向の上下は入れ替わることあり |
| 出所)外務省経済協力局およびJICA環境女性課資料より野村総合研究所作成 |
(6) 地球温暖化対策関連ODA案件の形態別の総支援額の経年変化
温暖化対策ODA案件の形態別(有償資金協力、無償資金協力、技術協力)の1998-2000年度間の経年変化を以下に示す。
特に、有償資金協力の増加傾向が、全体支援額の増加傾向の主要因になっていることが分かる。また、その他の無償資金協力と技術協力については、特に増加傾向にないことが分かる。
図表 温暖化対策ODA案件の形態別の総支援額の経年変化
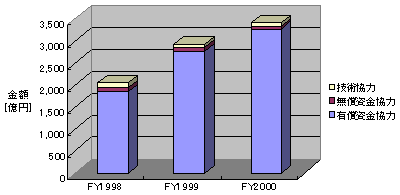 |
| 出所)外務省経済協力局およびJICA環境女性課資料より野村総合研究所作成 |
(7) 地球温暖化対策関連ODA案件の対策分野別の総支援額の経年変化
温暖化対策ODA案件の1998-2000年度間の対策分野別(主温暖化対策、削減、吸収源、適応)の総支援額の経年変化を、以下に示す。
主温暖化対策を除く全ての対策分野において、増加傾向にあることが分かる。中でも、1999年度から2000年度にかけての、削減対策分野での支援額の伸び率が大きいことが分かる。これは、2000年度に、削減対策分野の有償資金協力が多く採択されたことに因る。
図表 温暖化対策ODA案件の対策分野別の総支援額の経年変化
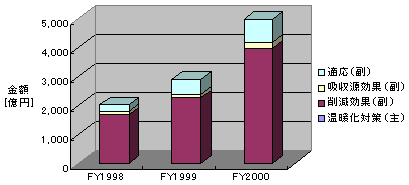 |
| 出所)外務省経済協力局およびJICA環境女性課資料より野村総合研究所作成 |

