地球温暖化対策関連ODA評価
調査報告書
第2章 国際的な地球温暖化対策に関する途上国支援の現状と傾向
2-2 他国・国際機関の地球温暖化対策の現状
UNFCCCでは、地球温暖化に関して先進国と途上国間での「共通だが差異のある責任」を明確にしており、条約の附属書I国(先進国)各国は、国内でのGHG削減・吸収対策とともに、途上国における削減・吸収および適応への援助に取り組んでいる。ここでは、国際機関(世界銀行と地球環境ファシリティー(GEF))およびOECD国際援助委員会(DAC)によるODA額上位国(米、仏、ドイツ、オランダ、英国、カナダ、スウェーデン、デンマーク)による温暖化対策に関する途上国支援の現状、さらに、これまでに実施されたAIJの概要について分析した。
(1) 概況
先進国各国は、それぞれ温暖化対策に関する途上国援助を実施しているが、「GEFを中心とした国際機関を通した支援に重心」を置いている国と「二国間援助でも独自に援助を展開」している国に大別される。前者としては、フランスやデンマークが揚げられ、温暖化関連援助の大半がGEFへの拠出という形で実施されている。
一方、日本をはじめとする他のODA大国の多くは、独自の戦略や政策を基に、GEFへの拠出に加えて二国間援助を実施しており、各国によってその規模はもちろん、考え方、対象国、対象分野などは大きく異なっている。その中でも、日本の温暖化対策関連の二国間援助(ODA)は円借款も含めれば、額、対策分野、対象地域分布からみても他を圧倒している(次章に詳述)。アメリカ、カナダ、ドイツなどによる地球温暖化対策関連ODA(以後、温暖化対策ODA)は、その規模は京都イニシアティブを中心とする日本の温暖化対策ODAには及ばないものの、具体的事業は温暖化対策を第一義的な目的としているケースが見られる。
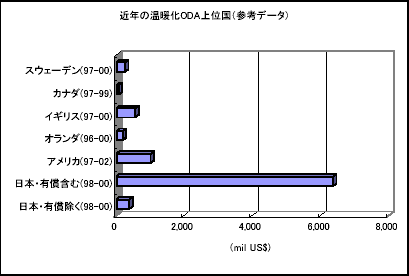 |
| 注) 各国によって温暖化対策ODAの定義、データ年度、援助スキーム等が異なるため直接比較はできないことに留意のこと。 出所)各国の国別報告書、温暖化対策行動計画等より野村総合研究所作成 |
(2) 国際機関を通した地球温暖化対策支援
途上国の地球温暖化対策への取組を支援している国際機関は、GEF、世界銀行、国連開発計画(UNDP)、国連環境計画(UNEP)、アジア開発銀行、国連食料農業機関(FAO)、国連産業開発機関(UNIDO)など多岐に渡っている。ここではUNFCCCのための資金メカニズムとして指定されているGEFと、途上国でのGHG削減の先進的な取組であるプロトタイプ炭素基金(PCF)を実施する世界銀行の温暖化対策プログラムについて概説する。
1) 地球環境ファシリティー(GEF)
GEFは、1989年のG7アルシュ・サミットおよび1992年の国連環境開発会議(地球サミット)での議論を受けて、1994年に創設された国際的な地球環境問題のための資金メカニズムであり、途上国における地球環境の保全・改善のための無償資金を世界銀行、UNDP、UNEP、そして各地域開発銀行を通じて供与している。
活動分野は、4つに重点が定められており、中でも気候変動に関しては、UNFCCCのための資金メカニズムに位置付けられ、これまでに全体の32%の資金が投入されている。
1998年からの増資においては、36ヶ国が約27.5億ドルの資金拠出に同意している。GEFのドナー上位国と累積拠出額は以下の通りであり、日本はシェア22%の最大ドナー国となっている。
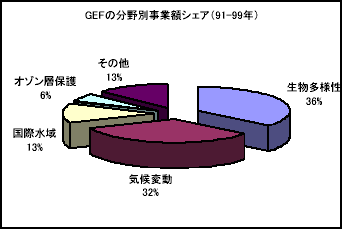 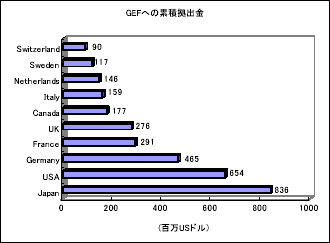
|
| 出所)GEFホームページ |
GEFでは、「地球環境上の利益」の確保に必要な費用に資金を供給しており、持続可能な開発を推進する支援資金に対して「追加的」または「補完的」に地球環境保護に必要な費用(Incremental Cost)を提供している。気候変動分野でみれば、まさに温暖化対策として必要な部分に資金供給がなされているといえる。具体的プロジェクトとしては、途上国のUNFCCCへの参加支援(GHGインベントリや国別報告書の作成)、省エネルギーと効率化に対する障害(法・制度的、行政的、市場的な障害)の除去、再生可能エネルギーの開発支援などが揚げられる。
GEFの実施機関のひとつである国連開発計画(UNDP)の温暖化対策を分野別にみると、91%が削減分野に投入されており、吸収源と適応はごくわずかに過ぎないことが分かる。吸収源に関しては、UNFCCCでの取扱いに議論があったことが反映しており、適応については直接「地球環境上の利益」に寄与しないとの考え方から、これまではごくわずか(適応については、脆弱性評価など)しか実施されてこなかった。
今後は、マラケシュ合意に盛り込まれた3つの基金(特別気候変動基金、最貧国基金、京都議定書適応基金)の実施機関としての可能性もあり、温暖化対策での途上国支援においては、ますますGEFの重要性が高まると考えられる。
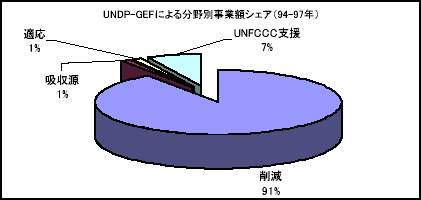
|
| 出所)UNDP-GEFホームページ |
2) 世界銀行 - プロトタイプ炭素基金(PCF)
プロトタイプ炭素基金(PCF)は、CO2削減プロジェクトとそこから発生する削減クレジットが京都議定書の目標に貢献し、かつ削減コストの低減につながることをデモンストレーションすることを目的に、2000年1月に世界銀行が設立した基金である。
PCF出資者としては、6カ国政府に加えて17社の民間企業も参加しており、ホスト国としては39カ国が参加している。基金の総額は1.45億USドルであり、活動終了予定の2012年までに25~30件のプロジェクトの実施を想定している。PCFを通じては、GHGの排出削減に寄与するとともに、共同実施(Joint Implementation: JI)・クリーン開発メカニズム(Clean Development Mechanism: CDM)に関心のある国・民間企業・その他団体等に政策・制度・ノウハウを身に付ける機会を提供し、かつ世界銀行と民間企業の協働による環境対策のための新たな資金調達方法の模索が期待されている。
|
||||||||||
| 出所)PCFホームページおよびPCF2001年次報告書より野村総合研究所作成 |
これまでの計画・実施された事業は、地域的には中南米にやや偏っているが(47%)、PCF担当者によれば、これは中南米諸国が早期からCDMに関心を持ち、積極的に取組を進めてきた結果である。
2002年度からは、PCFを支援する目的で、ホスト国の能力開発を行う「PCFplus」プログラムが、PCFとは別資金でカナダ、スウェーデン、フィンランドの拠出によって開始されている。
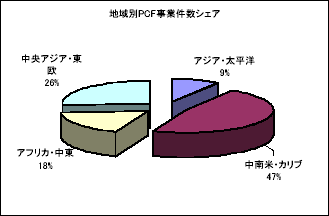 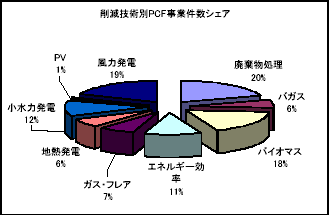
|
| 出所)PCF2001年次報告書より野村総合研究所作成 |
3) 世界銀行 - 国家戦略策定プログラム(National Strategy Studies Program: NSS)
国家戦略策定プログラム(NSS)は、1997年にスイス政府と世界銀行が共同で始めたAIJ・JI・CDMのホスト国の能力開発を支援するプログラムであり、これまでに8カ国が調査を完了して「国家戦略」を策定している。現在は、ドイツ、オーストラリア、フィンランド、カナダもプログラムに参加し、資金・技術・人材で貢献している。
主な調査内容としては、ホスト国のGHG排出量の現状と予測、ホスト国が実施し得る温暖化対策の分析、GHG削減量の予測と削減費用の分析、可能性のあるプロジェクトの抽出、削減プロジェクトによる市場形成や融資機会についての分析などとなっている。
|
||||||
| 出所)世界銀行NSSホームページより野村総合研究所作成 | ||||||
(3) 他国による地球温暖化対策関連支援
1) アメリカ
ブッシュ政権による京都議定書からの離脱を受け、2002年2月に「米国気候変動戦略:新アプローチ(U.S. Climate Change Strategy: A New Approach)」が発表された。その中で途上国に対する援助としては、1)途上国における気候観測システムへの投資、2)森林保全のための債務環境スワップ、3)GEFを通じた貢献、4)米国際開発庁(USAID)を通した削減・吸収分野での支援の4つが柱として位置付けられている。
また、1998-2002年には、USAIDが、5ヵ年総額10億USドルにのぼる「気候変動イニシアティブ(USAID Climate Change Initiative)」を実施しており、削減を中心とした支援に取り組んできている。
AIJについては、共同実施イニシアティブ(US Initiative on Joint Implementation)を1993年10月に発表しており、これまでにエネルギー関連および土地利用関連のプロジェクト25件を11カ国で実施してきている。
<米気候変動戦略>
ブッシュ政権の気候変動戦略では、国際協力は国内的な取組を補完するものと位置付けており、途上国の気候観測システム、債務環境スワップ、GEF、USAIDを通した途上国支援が、日本との共同R&Dなどと並んで、国際協力の柱となっている。
| ・ | 途上国の気候観測システムへの投資としては、2,500万ドルの拠出が予定されており、他の先進国にも途上国での気候観測への投資を呼びかけている。 |
| ・ | 森林保全のための債務環境スワップは、債務国が森林(特に熱帯雨林)を保護することを条件に債務を帳消しとするもので、2003年度として4,000万ドルの予算が議会に要請されている。これまでに、ベリーズ、エルサルバドル、バングラデシュ、タイの各国と債務環境スワップで合意している。 |
| ・ | ブッシュ政権は、GEFへの拠出金として1.78億ドルを2003年度予算として要請しており、これは前年度比7,700万ドルの増加となる。 |
| ・ | 2003年度のUSAIDによる温暖化対策関連予算として、1.55億ドルを議会に要請しており、特に米国のエネルギー技術の移転によるGHG排出削減と吸収源での支援を主要な目的としている。 |
<USAID気候変動イニシアティブ>
1997年にクリントン前大統領によって5ヵ年で総額10億ドルの同計画が発表された。この中で、地球温暖化問題は、USAIDの重点課題のひとつ位置付けられており、二国間援助では、適応よりも温暖化の緩和、すなわち削減と吸収源での重点的な取組を基本方針としている。
| ・ | 重点分野としては、省エネルギー、発電でのエネルギー効率改善、送配電効率の改善、再生可能エネルギーの開発、エネルギー部門の改革・再編・民営化、エネルギー関連法・政策改革、大気浄化、メタン削減、森林プロジェクト、農業管理(N2O、メタンの削減)があげられている。 |
| ・ | メキシコ、ブラジル、インド、インドネシア、フィリピン、ロシア、ウクライナ、ポーランド、カザフスタン、中央アフリカの各国が重点対象国に指定されているが、その他の国であっても事業は実施されており、全体的には、各地域に分散させた対象国分布となっている。 |
| ・ | 特にUNFCCCへの参加に資する能力開発として、国別研究プログラム(Country Studies Program)が実施されており、途上国および経済移行国の国別報告書(特にインベントリ)作成の義務を支援している。これまでに55カ国を支援。 |
| ・ | 国家行動計画策定支援プログラム(Support for National Action Plans)により、43カ国(審査中を含む)の地球温暖化防止国家行動計画の策定を支援している。 |
 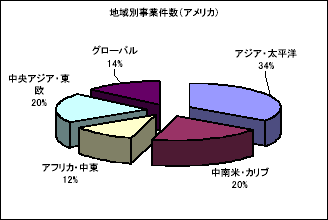
|
| 出所) "Climate Change Initiative 1998-2002" (USAID) |
| 【出所】 | ・U.S. Climate Change Strategy: A New Approach (2002年2月発表) ・USAID Climate Change Initiative (1998-2000) ・UNFCCC第2次国別報告書 (1997年7月提出) ・国務省ヒアリング |
2) フランス
フランスは、温暖化対策のための基金やプログラムは特に設けておらず、基本的にはGEFへの拠出(1994年より合計2.91億USドル)を通じて温暖化対策での途上国支援を実施しているといえる。
二国間援助としては、GEFの設立に合わせて、地球環境問題に関わる途上国援助機関であるフランスGEF(FFEM)を1994年に設立しており、GEFと同様の考え方に沿って地球環境に関する途上国支援を行っている。FFEMでは、主にフランス語圏アフリカ諸国を中心に援助しており、第3次国別報告書によれば、1998年には72百万USドルを温暖化関連で支援している。対策分野としては、削減に重点を置いており、全体の88%に上る。
また、FFEM事務局は、フランスによるAIJプロジェクトも担当しており、農村域電力化、建物でのエネルギー効率改善、産業でのエネルギー効率化、地熱発電などのプロジェクトを、アフリカ、アジア、中東および東欧で実施している。
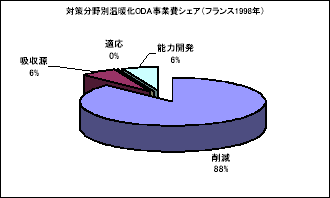 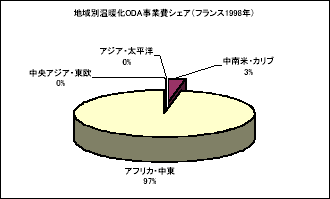
|
| 出所)第3次国別報告書および「National Programme for Tackling Climate Change 2000-2010」より野村総合研究所作成 |
| 【出所】 | ・National Programme for Tackling Climate Change 2000-2010 (2000年) ・UNFCCC第3次国別報告書 (2001年11月提出) |
3) ドイツ
1997年にUNFCCCに提出された第2次国別報告書によれば、ドイツは1994-95年の2年間で、約4.1億USドルを温暖化対策ODAとして、途上国に支援している。基本方針としては、温暖化対策は被援助国の国家政策・開発計画に沿ったもの、すなわち持続可能な開発に寄与するものを実施しており、エネルギー関連、運輸・交通、産業、農業、林業・植林が重点分野として位置付けられている。また、環境管理手法、環境情報管理、経済的手法の導入などの能力開発にも力点が置かれているのが特徴といえる。
ドイツの技術協力機関であるDeutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ)では、「途上国のUNFCCC参加・実行を支援するためのプログラム」が実施されており、1993-2001年までの7年間で総額1,650万マルクを支援している。重点分野としては、エネルギー、運輸、産業、廃棄物処理を指定しており、GHG排出量の多い途上国が主な対象国と位置付けている。また、CDMのプロモーション、案件発掘、ホスト国のCDM能力開発にも寄与することを明確に位置付けているのが特徴的といえる。
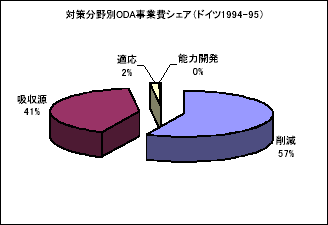 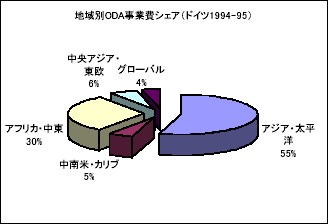
|
| 出所)第2次国別報告書より野村総合研究所作成 |
| 【出所】 | ・Germany's National Climate Protection Programme (2000年10月) ・UNFCCC第2次国別報告書 (1997年4月提出) ・GTZ Measures to Implement the UNFCCC |
4) オランダ
第3次国別報告書によれば、オランダは、1997-2000年の4年間で、総額約2.1億ユーロを「気候プログラム(Climate Programme)」として途上国での温暖化対策を支援している。気候プログラムでは、エネルギー部門を主な対象と位置付けており、再生可能エネルギー開発などを通じたGHG排出削減と貧困撲滅を目指している。
能力開発事業としては、気候変動対策・政策の立案・実行のための組織・整備にも力を入れている。また、オランダは排出削減目標達成のための重要な手段としてCDMを位置付けており、気候プログラムを通じてホスト国のCDM事業受け入れ準備に係る能力開発にも注力している。
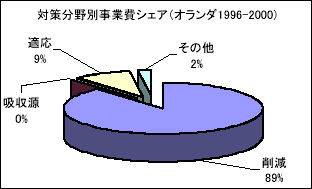 |
| 出所)第2次国別報告書より野村総合研究所作成 |
<Carboncredits.nl(ERUPT /CERUPT)プログラム>
Carboncredits.nlは、京都メカニズムを利用した炭素クレジットを国際調達するための事業であり、ERUPT(Emission Reduction Unit Procurement Tender)はJI事業、CERUPT(Certified Emissions Reduction Unit Procurement Tender)はCDM事業により発生する削減クレジットをオランダ政府が入札によって調達する制度となっている。調達資金は、ODAとは別枠となっており、それぞれ経済省、環境省の独自予算となっている模様である。
オランダは、京都議定書における削減目標(-6%)の半分を、京都メカニズムを通じて達成するとの方針を打ち出しており、Carboncredits.nlを通じて削減クレジットを得る計画としている。なお、Carboncredits.nlを通して国内での削減目標が緩和されているとの考え方から、同国では民間企業によるJI/CDM事業は認めていない。
図表 オランダのCarboncredits.nlの仕組み
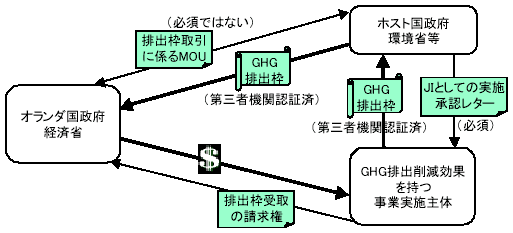 |
| 出所)Carboncredits.nlホームページより野村総合研究所作成 |
図表 オランダのCarboncredits.nlの概要
|
|||||||||||||||||||||||
| 出所)Carboncredits.nlホームページより野村総合研究所作成 | |||||||||||||||||||||||
| 【出所】 | ・オランダ政策実行計画(1999年6月) ・UNFCCC第3次国別報告書(2001年11月提出) ・Carboncredits.nlホームページ ・経済省ヒアリング |
5) イギリス
イギリスは、第2次ODA白書(Second White Paper on International Development - Eliminating World Poverty: Making Globalisation Work for the Poor)で、地球温暖化問題を重要な課題として位置付けており、GEFへの拠出金の充実を含めた温暖化対策での途上国支援の強化を打ち出している。
また同国は、Climate Change Challenge Fundを通じて、1997-2000年の4年間で222事業(総額3.48億ポンド)を実施しており、エネルギー効率化、森林による吸収源、そして脆弱性評価調査を含む能力開発事業を中心とした適応事業を通じて途上国の温暖化対策を援助している。
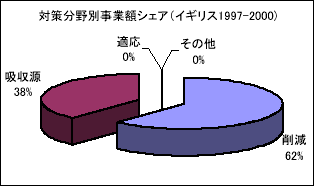 |
| 注)適応に関するデータは未入手 出所)第3次国別報告書より野村総合研究所作成 |
| 【出所】 | ・Climate Change - The UK Programme (2000年) ・Second White Paper on International Development - Eliminating World Poverty: Making Globalisation Work for the Poor ・UNFCCC第3次国別報告書 (2001年10月提出) |
6) カナダ
カナダは、地球温暖化対策関連での途上国支援としては、世界銀行のプロトタイプ炭素基金(PCF)への出資(1,500万加ドル)や国内企業の海外投資(JIおよびCDM)を支援する早期技術的対策プログラム(Technology Early Actions Measures=TEAM:3年間で6,000万加ドル)を通しての間接的な支援のほかに、ODAによる各種事業、さらにODA資金とは別枠での地球温暖化対策を直接対象としたカナダ気候変動開発基金(Canada Climate Change Development Fund=CCDF:1億加ドル)がある。
<CIDAを通した途上国援助>
ODAによる事業は、カナダ国際開発庁(Canada International Developent Agency: CIDA)を通じて実施されており、同国のODA戦略の中で6つの重点分野への支援(基礎生活分野、ジェンダー、インフラ・サービス、人権とグッド・ガバナンス、民間セクター開発、環境)の中で温暖化対策が取り組まれている。
| ・ | 1997-1999年の3年間で総額11.2億加ドルが、温暖化対策関連分野で援助された |
| ・ | 削減が71%と多くなっているが、吸収減、適応についてもそれぞれ16%と12%となっている |
| ・ | 能力開発については、CCCDF(後述)で取り組んでいるものと考えられる |
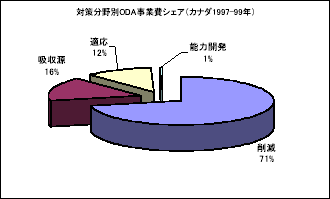 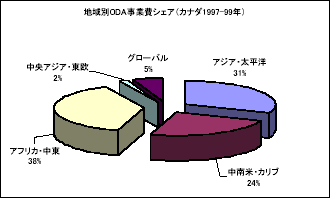
|
| 出所)UNFCCC国別報告書より野村総合研究所作成 |
<カナダ気候変動開発基金(CCCDF)>
CCCDFは、CIDAを通して途上国への地球温暖化対策に資する環境配慮型技術(Environmentally Sound Technology)の移転や能力開発を主な支援内容としており、途上国の持続的発展に寄与しつつGHGの排出量削減や吸収、途上国の地球温暖化への適応、国際的な地球温暖化対策への途上国の貢献を支援することを目的としている。また、これらの支援を通じて、カナダが低コストでのGHG排出量削減・吸収を実現することも大きな目的となっており、途上国のCDMやJIの受け入れ能力の開発や向上にも取り組んでいる。但し、CCCDFを通じて、カナダの排出削減クレジットを得ることは想定していない。CCCDFでは、二国間援助のほか、世界銀行や他国際機関の信託基金への資金供与等も行っている。
図表 CCCDFの対策分野と対象国
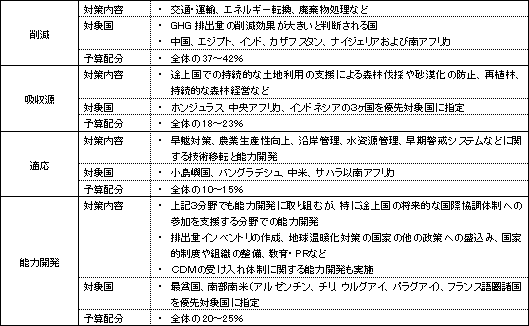 |
| 出所)"Canada Climate Change Development Fund" より野村総合研究所作成 |
実際に実施された事業(36件)の対策分野を件数別でみると、バランスよく配分されていることが分かる。また、地域別で対象国分布をみると、アジア太平洋が52%となっており、重点が置かれている。
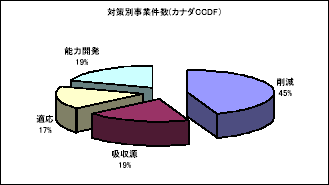 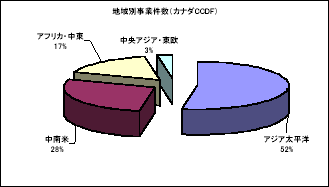
|
| 出所)"Canada Climate Change Development Fund" より野村総合研究所作成 |
| 【出所】 | ・Canada's National Implementation Strategy on Climate Change (2000年10月) ・Canada Climate Change Development Fund(2000年) ・UNFCCC第3次国別報告書(2002年2月提出) |
7) スウェーデン
第3次国別報告書によれば、スウェーデンは、1998-2000年の3年間で、約2.6億USドルの温暖化対策ODAをスウェーデン国際開発庁(SIDA)を通じて実施している。
SIDAは、途上国での貧困撲滅を大目標としており、温暖化対策関連事業もこの方針に基づいて実施されており、対象国は南部アフリカやアジアが中心となっている。1998年には、SIDAの実施事業による温暖化対策への貢献についての調査研究がなされたが、直接的に温暖化対策に資する事業はほとんどないとの結果が報告されている。
対策分野としては、削減、吸収源、適応、そして一般的な環境対策などを対象としており、非常にバランスが取れている。
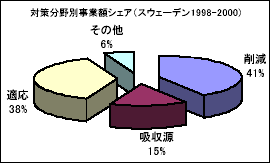 |
| 出所)第3次国別報告書 より野村総合研究所作成 |
【出所】 ・UNFCCC第3次国別報告書(2001年11月提出)
8) デンマーク
デンマークの温暖化対策戦略である「Status and Perspectives for Denmark's Climate Policy(2000年3月)」では、途上国への援助を重要な取組のひとつとして位置付けており、途上国による国際的な温暖化対策への参加を支援するものであるとしている。但し、ODAは、途上国の持続可能な開発に貢献するのが基本であり、「(GHG排出量の低い)最貧国へのODA資金が、GHG排出量の多い中進国に振り替えられてはならない」としている。デンマーク国際開発庁(DANIDA)を通じたODAは、約20カ国の最貧国が対象に指定されている。
第2次国別報告書によれば、温暖化関連の二国間援助としては、1997年に3,060万USドルを支援しており、タイ、マレーシア、南アフリカでのエネルギー分野および植林・森林経営分野に援助している。デンマークの温暖化対策ODAの特徴としては、吸収源関連事業が多いことがあげられる。
デンマークは、温暖化関連の国際協力のほとんどをUNFCCC、UNEP、世界銀行、GEF等を通じて実施している。
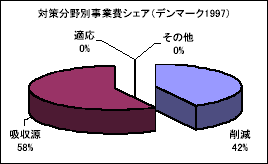 |
| 出所)第2次国別報告書 より野村総合研究所作成 |
| 【出所】 | ・Climate 2012: Status and Perspectives for Denmark's Climate Policy (2000年3月) ・UNFCCC第2次国別報告書 |
(4) AIJの現況
共同実施活動(Activities Implemented Jointly: AIJ)は、1995年に開催されたUNFCCC第1回締約国会議において決定された制度で、二国間でGHG削減・吸収事業を共同で実施し、その削減クレジットを両国で配分する制度である。JIおよびCDMのパイロット・フェーズとして位置付けられており、現在までにUNFCCC事務局に登録されたAIJプロジェクトは155件にのぼる。
プロジェクト内容は、削減では省エネルギー・再生可能エネルギー開発・燃料転換・漏洩ガス回収、吸収源では、植林・森林管理・農業などの分野で実施されており、合計で約7千万t-CO2(年当たり270万t-CO2)のGHG削減または吸収が見込まれている。
ホスト国は42カ国リストされており、東欧・中央アジア地域が件数ベースで55%となっており、偏りが見られる。一方、ドナー国は11カ国であり、スウェーデンが53件(34%)、米国が44件(27%)、オランダが24件(15%)と積極的に取り組んでいる。日本は、UNFCCC事務局に登録されている事業としては、タイ、ヴィエトナム、中国(3件)で5件実施しており、省エネルギー事業が4件、漏洩ガス回収事業が1件となっている。
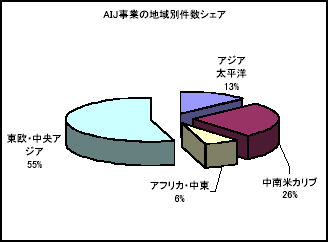 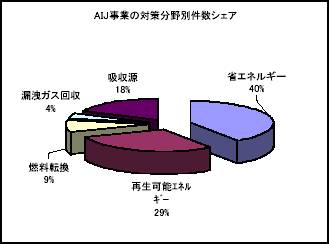
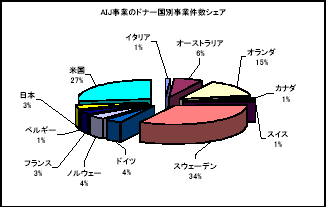
|
| 出所)UNFCCCのAIJホームページ より野村総合研究所作成 |

