第6章 重点分野別の援助実績
6.3 投資促進・輸出振興のための基盤整備
「投資促進・輸出振興のために基盤整備」においては、経済インフラに関わるセクターに限らず直接的に投資と輸出に関係する産業育成分野も分析評価の対象とした。経済インフラについては構成するサブセクター毎に現状と課題を考察し、我が国援助の取組みについて分析と評価を行った。
6.3.1 産業育成分野の現状と課題
(1)バングラデシュ国の工業および産業育成政策
バングラデシュ国は工業化の推進という点で遅れをとった国である。1971年の独立前、比較的単純な加工を要する産業(ジュート、繊維、製糖、セメント、軽工業および小規模の肥料、鉄鋼製造)をベースとして出発した。独立後は、経済的自立の達成を掲げて、輸入代替指向および国内需要重視の産業育成戦略を採用した。近年に至るまで、バングラデシュ国の工業化は政府主導、公共部門管理により進められ、工業セクターにおける公共投資の多くは、化学肥料産業の生産能力増加と重化学工業の育成に充当された。
しかし、ドナー機関も支援した上記の開発戦略は、国内需要規模が低購買力のため小さいこと、および国営企業の経営が非効率であったことより、輸入代替や国内需要充足という当初目標の達成には貢献したものの、効率性の面で問題を残した。このため1980年代後半より、バングラデシュ政府は民間参入による工業化、輸出振興および海外直接投資(FDI)促進を重視し始め、ドナー機関の意向もあり構造調整と市場経済化に向けた環境創出に取組みを開始した。輸出産業の振興に向けては、競争力のある製造業の育成を最重視している。
1999年に策定された産業政策では、外国を含む民間投資がほぼ全ての産業に対して可能となり、民営化対象の国営企業を選定され、一部は実施に移されるか政府により再構築されている。また、工業化における政府の役割を規制から奨励へと転換させ、国営企業や公益機関の効率化と特定の戦略的業種の育成のみに限定している。
産業政策ではバングラデシュ国の産業開発ビジョンを「10年以内に製造業が少なくともGDPの25%を占め。労働者の20%を雇用する」と設定した。バングラデシュ国が比較優位を有する産業としては、「スキルの向上と生産性の向上を伴った労働集約的製品の生産」にあるとしている。
(2)分野の課題とパフォーマンス
バングラデシュ国の産業育成上の開発課題として、第5次5ヵ年開発計画では次の課題が掲げられた。これら課題に対応するため、5カ年開発計画期間中で、民間資本投資の約27%が充当される想定にある。一方政府の方針を踏まえ、公的部門資本支出はわずか約1.4%が充当されるのみである。
| 民間セクターの成長 | 地場産業と中小企業支援 | |
|
民間セクターの発展より牽引される工業化 産業政策の実施促進と規制等歪みの除去 起業家の育成 |
地場技術と資源を活用した産業の育成と発展 労働集約型小規模企業の育成および発展 |
|
| 国営企業と公益事業の改革 | その他 | |
| 公的産業セクターの効率運営 国営企業の民営化プロセスの促進と加速化 |
技術データベースとR&D(基礎科学)機関の整備 生産的かつ健全な労使関係の構築 地域間バランスの取れた工業化促進戦略の策定 弱体産業の再活性化(責任と義務の明確化) |
|
| 輸出振興 | ||
|
比較優位のある輸出産業の育成および発展 農産加工業の発展と多様化 市場と製品の多様化 効率的な輸入代替および輸出指向型産業の育成 製品品質管理による国際品質基準への適合 |
そして、開発計画では推進産業として1)繊維・アパレル、2)皮革、3)ソフトウェアおよびデータ加工、4)電子、5)農産加工、6)漁業、7)軽工業、8)化学およびガス関連、9)繊維関連、10)チェック生地、11)ホテル・観光産業を挙げ、民間セクターの参入を期待している。
世銀やADBなど国際援助機関は、民間セクターの成長への重要な課題として金融セクターの健全化(金融および資本市場の強化)、外国投資受入れ制度の環境改善、法および司法制度の改革を挙げている。これらは、工業セクターの範囲に含まれる課題ではないが、国際機関では工業セクター成長の要件として位置付け、取組んでいる。
産業および製造業の1990年以降のシェアと年平均成長率は以下のとおりである。GDP全体の平均成長率よりも優れた成長率を誇っているものの、シェアでみれば先述の政策目標である25%とは未だ乖離がある。更に近年の動向はシェアおよび成長率共に低下傾向である。雇用の吸収力に至っては、過去10年間低下傾向にあると考えられている。労働者数の20%の雇用が期待されたセクターとして、期待とは逆の貢献をする現状となっている。
|
表6-3-1 産業/製造業セクターのGDPシェアと年平均成長率、雇用者数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国営企業の公益事業の改革については、国営企業などの赤字額が多いことと、製品への過剰な補助金支出の観点から重要である。1990年に入り、民営化や効率化事業を部分的に進めた結果、国営企業などの赤字体質は改善傾向にあった。しかし不安定な要素が多く、近年は再び悪化傾向にある。これは石油など国際市場価格の高騰が要因である。民営化や大規模なリストラクチャリング事業の動きを見守る国営企業は、操業と雇用の不確実性に見舞われており、効率的運営への関心を喪失させ、本来望まれるアクションが取れないでいるとの報告もなされている。
|
表6-3-2 国営企業の赤字の推移
|
バングラデシュ国の工業および製造業成長の源泉は、国内需要規模が小さいこともあり外国からの投資促進と輸出振興である。しかし、FDIと輸出振興に資する工業の育成は、繊維産業を除き未だ成果が実っていない。繊維・アパレルを除いた、消費財、繊維産業の関連投入財、高付加価値耐用財、生産財全て、充分な発展と生産性の向上をみていない。バングラデシュ国政府は、これら課題に応えるため、工業団地・輸出加工区の設立を積極的に支援した。しかし、政府自身認識しているように、これら施設は充分に活用されておらず、政策目標である労働集約型産業の発展と産業の地域分散も進んでいないのが現状である。
|
表6-3-3 主要製造業サブセクターの生産量指数 (1988/89=100)
|
上表より既製服(アパレル)産業の生産量が突出して伸びていることが判る。非金属、紙・パルプなどは顕著な増産傾向にあるが、他は1990代後半に入り停滞および減産傾向にある。輸出面においても関連するニット製造を含めると繊維産業の貢献度が非常に高い。名目の総輸出額自体は急激な増加を示している。但し、依然輸入超過の状況にあること、繊維産業への偏重、名目数値であることを考慮すると、必ずしも工業セクターの発展が順調とは言えない。
|
表6-3-4 主要輸出品目の推移-総輸出額比
|
|
表6-3-5 輸出総額の推移 (単位:百万タカ)
|
工業セクターのもう一つの主目標である外国直接投資の促進状況を見ると、順調に推移していたのが近年低下傾向にあることが判る。これはアジア経済危機が主要因として考えられる。なお、FDIを件数ベースでみると繊維産業が30%近くを占めている。投資面でもバングラデシュ国における繊維産業の役割の大きさが伺える。なお、投資庁(BOI)によると、実際の投資額は外国と国内投資どちらも登録実績の約30%程度であり、海外からの投資流入並びに国内の資本稼働状況ともに低い状態であることに変わりない。登録数と実際に行われる投資実績との乖離は、経済インフラのボトルネックおよび公益サービスの供給不足が原因であると報告されている。
|
表6-3-6 外国直接投資額の推移(単位:百万US$、登録ベース)
|
バングラデシュ国の工業セクターは、既存産業の近代化への遅れとかつて保護されていた国内需要の自由化による喪失に見舞われている。90年代の前半から始まった貿易制度の自由化による国内市場の変化への対応と調整が遅れている。自由化政策による産業構造の転換期であり、市場経済化への初歩的段階にあると言える。
また、低い賃金水準と豊富な労働力を有している一方で、技術革新に必要な基礎能力、現代的なマネジメント能力に乏しく、長期かつ余剰な資本が極端に不足しているとの指摘がある。政府が掲げている奨励業種も希望的な観測と他国の先例への追従によるものも含まれ、一層の重点化が必要と言われている。2005年にはMFAの失効に伴い、貴重な外貨収入の源泉であり、かつ強い雇用吸収力と他産業へのリンケージを有する繊維・アパレル産業が失速すると予測されている。
バングラデシュ国に求められるのは、先述した課題への迅速な対応、とりわけ競争力、優位性、ポテンシャルに基づいた重点産業の絞り込み、輸出産業の多様化、国営および公益企業の改革であり、民間セクターの成長を加速させるため、健全な金融および資本市場の育成、各種制度の見直しを伴う投資やビジネス環境の整備、法および司法制度の改革、インフラの整備が求められる。
6.3.2 我が国のバングラデシュ国産業育成への取組みと貢献
農業に代わる新たな経済の牽引力となるべき工業および製造業はGDPの約25%弱を占めるに過ぎず、成長率も近年鈍化している。工業および製造業の迅速な成長を確保することが今後の経済成長にとって重要であり、国内市場は未だ貧困により購買力が制約されているため、産業の成長には国際競争力を有する輸出産品の開発育成が極めて重要である。このことから、我が国が国別援助計画上、投資促進、輸出振興を重点課題としたことは妥当であり、育成すべき産業の特定、制度金融機関の育成もにらんだ産業支援策を打ち出したのは適切な方向を見据えたものと評価できる。
(1)援助の実績
過去約10年間の我が国のバングラデシュ国における産業育成への取組みは、下表のとおりである。我が国は、主に肥料工場の建設および改修事業に重点を置いてきたことが判る。但し、これら重化学工業への支援は、必ずしも投資促進、輸出振興および工業の深化と成長を主眼に取組まれてきたものではないことを留意する必要がある。重化学工業への重点支援は、農業投入物の増産を通じた農業生産性の増加が上位の目標であった。本邦および第3国研修事業では、投資促進、中小企業育成および診断、民営化促進に係る研修業務が提供されている。また、投資促進に対する技術支援にて専門家派遣もなされている。
| 民間セクターの成長 | |
| 国営企業と公益事業の改革 | |
| 公的産業セクターの効率運営 | チッタゴン尿素肥料工場建設事業(有償) ジャムナ肥料工場建設事業(有償) ゴラサール肥料工場改修事業(有償) チッタゴン苛性ソーダプラント修復事業(有償) ジュートパルプ製紙工場建設計画調査(開調) |
| 国営企業の民営化プロセスの促進と加速化 | 本邦研修 |
| 輸出振興 | |
| 比較優位のある輸出産業の育成および発展 | |
| 農産加工業の発展と多様化 | |
| 市場と製品の多様化 | |
| 効率的な輸入代替および輸出指向型産業の育成 | |
| 製品品質管理による国際品質基準への適合 | 第3国研修 |
| 地場産業と中小企業支援 | |
| 地場技術と資源を活用した産業の育成と発展 | 本邦研修事業 |
| 労働集約型小規模企業の育成および発展 | 本邦研修事業 |
| その他 | |
| 技術データベースとR&D(基礎科学)機関の整備 | |
| 生産的かつ健全な労使関係の構築 | 第3国研修 |
| 地域間バランスの取れた工業化促進戦略の策定 | チッタゴン地域工業開発計画調査(開調) |
| 弱体産業の再活性化(責任と義務の明確化) | |
(2)我が国援助のセクターへの貢献
ゴラサール肥料工場改修事業(有償)

|
更に重要な点は、我が国の肥料工場への集中的支援が、USAIDによる農業投入物流通市場の改革支援と相乗的効果を生み出したことである。単に肥料の増産を行っても、その流通市場が歪められ、充分機能しない限り、消費者による効率的な肥料の利用は妨げられる。肥料セクターを考える場合、肥料の流通および価格政策は無視できない。かつては政府系公社の独占事業であった農業投入物流通事業をUSAIDの支援により改革が進められ、現在では、工場出荷時の政府による一括買上げと買上げ価格の政府管理以外、消費者までの流通市場は自由化されている。
当該分野では、1)肥料工業支援をとおしたバングラデシュ国の政策目標が明確であったこと、2)政府に事業成果実現への強いコミットメントがあったこと、3)企業ベース支援のため実施機関に事業の円滑遂行に向けた適切な動機付けが働いたことなど、バングラデシュ国の他セクターに見受けられる維持管理の資金的裏付けの不足、事業実施能力の不足が事業成果に支障を来すほどの問題ではなかった。近年は、原材料調達の問題、環境汚染問題、政府による買上げ価格の抑制により、事業効果の発現に悪化の傾向が見られるが、支援開始以来1990年代半ばまでは、我が国が支援した肥料工場のパフォーマンスは良好であった。
このように我が国の重化学工業向けの資金支援は、良好な環境のもとその目標に沿った成果が適切に達成され、バングラデシュ国主要課題の一つであった米の自給自足達成にも間接的に貢献した。
(3)援助実施上の問題点
肥料工場への資金的支援は、確実に農業生産性の増加に貢献したが、それが真に経済合理性のある選択肢であったかは重要な視点である。1990年代半ばまでは、バングラデシュ国肥料工業は比較的健全な財務状況にあると評価されていたが、政策的に低く抑えられた原料(天然ガス)価格によるところが大きかった。つまり資源の合理的配分を促した支援ではなかった。また肥料事業は、天然ガスの安定調達や設備機器の適切なメインテナンスが事業成否の鍵となり、天然ガスセクターの動向や事業実施機関の財務健全性が大きく事業成果に影響する。我が国が支援した肥料工場でも近年これらの問題(ガス価格の適正化と買上げ価格の抑制)が事業運営に悪影響を及ぼしている。
但し、これら問題は政府が他セクターの政策より誘導する管理価格が要因であり、政府による生産量の調整も常態化していたため、肥料事業に民間事業者の参入、資金活用を導入するには相応しい事業環境ではなかったことは事実である。これらのリスクを民間事業者では請け負えないため、我が国の支援を始め、公的な外国援助資金の注入が必要であったと考えられる。
食糧自給が実現され、肥料工業発展の黎明期を終えた現在は、国営管理と価格統制の妥当性は失われつつあり、より効率的な政策目標の達成が求められる。民営化の動向はバングラデシュ国でも不可避の状況にある。従って、重化学工業への支援は、緊急的なもの、国営企業の改革支援、および制度改革を見据えた海外投融資的な性格を持つ支援に限定されるべきであろう。これはその他多くの業種の国営企業向け支援においても考慮されるべきことである。
また、重化学工業支援が唯一の産業育成上の支援策であったことを鑑み、振り返るべき視点もある。まず、重化学工業自体は、天然ガスの利用促進以外、他工業とのリンケージが比較的希薄である。つまり農業や天然ガス以外の経済的波及効果が薄いと言われており、新たな産業の育成、投資促進、輸出振興への寄与を期待するものではなかった。但し、バングラデシュ国は農業国であり、かつ肥料の輸入国であったことが支援の背景であったことは事実であり、この背景に沿った支援の効果、貢献度合いは先述のとおり満足のゆくものであった。
工業セクターの開発動向で触れたとおり、バングラデシュ国においては繊維産業以外活発に輸出および投資促進に貢献している製造業が不足している。これ以外過去10年あまりのバングラデシュ国製造業および産業セクターの発展状況はGDPにおけるシェアおよび雇用吸収力で視ても芳しいものではなかった。その繊維産業は、2005年にはMFAの失効に伴い、失速すると予測されている。
我が国は投資促進、輸出振興を上位課題として掲げているが、課題解決における戦略は明らかに経済インフラの整備に偏重していた。チッタゴン地域の工業開発計画調査(93~95年)以外、有望産業の育成、投資および輸出の振興に向けた計画の策定業務、ツーステップ・ローンによる金融支援など産業セクターへのより直接的な支援が近年見受けられない。
バングラデシュの産業構造と発展水準を考慮すれば、地場産業やコテージ産業振興に向けた技術支援とこれに連携する小口金融支援も重要である。近年バングラデシュ国NGOの当該分野への参入が活発であるが、その産業構造と発展水準を考慮すると、輸出振興の観点から有望な産業を抽出し、支援を拡充するのは困難であったものと思料される。同様に民間セクターの育成や成長、および国営企業の民営化促進という課題についても、主に世銀、ADBおよび他ドナーの支援分野であった。
6.3.3 経済インフラ整備の現状と課題
バングラデシュ国開発計画書では、経済インフラのカテゴリーを道路、空港、港湾、鉄道、電力、通信と分類し、それぞれのサブセクターに開発課題を与え開発予算を配分している。経済インフラ整備や公益サービス供給に共通してみられる問題点は、絶対量の不足、サービス供給の質的低下と非効率性、維持管理(予算や資金不足)、アクセスの地域間不均衡である。
(1)道路(陸上交通)
バングラデシュ国の交通需要は、独立以来旅客と貨物輸送需要の両方において、非常に大きく増大した。90年代以前は輸送需要の伸びはGDPの平均成長率よりも高かった。近年は、必ずしも高い成長率を示していないが、依然増加基調にある。輸送モード別では、道路輸送へのシフトが顕著であり、現在バングラデシュ国で最も重要な輸送モードとなっている。道路輸送はこのうち貨物輸送の60%、旅客輸送の75%を担うに至っている。輸送需要の伸びは今後更に成長すると予測されており、道路輸送への負荷が高まるものと予測されている。要因はバングラデシュ国東西地域を結合したジャムナ橋の完成、市場経済化の進展である。
|
表6-3-7 道路輸送(貨物輸送)量とシェアの推移(単位:百万トン)
|
バングラデシュ国の道路網は、国道、地方道路、タナ接続道路(Feeder-A)、成長センター接続道路(Feeder-B)、ユニオン接続道路(RD-1)、村落道路(RD-2又はVillage road)で構成される。国道、地方道路、Feeder-Aは運輸通信省道路局(RHD)が、その他は地方政府・地域開発・組合省地方政府土木局(LGED)が建設、維持管理主体である。RHD道路に接続するジャムナ橋など長大橋は、ジャムナ多目的橋梁庁(JMBA)により管理される。
これまで全ての道路は政府支出により建設され、維持管理されている。今後の陸上輸送需要の増大に向けて、バングラデシュ政府は多大な資金負担を回避するため、道路セクターへの民間の参画、民間資金の活用を政策目標に掲げている。民間参入を促進するため、政策枠組みや法制度の確立が求められている。道路セクターの課題は以下のとおりである。
| 道路ネットワークの整備・拡充・質的向上 | 民間の参入と民間資金活用の促進 | |
| 5幹線道路の国際規格レベルでの整備 統合およびバランスの取れた幹線道路網の構築 ダッカ東部バイパスと主要橋梁の完成 既存幹線道路網の非結合部分の整備 |
インフラ整備への民間部門参画を促す環境の整備(法的枠組みとインセンティブ供与パッケージの整備) 料金徴収の導入による国内資源活用の促進 |
|
| 実施機関の強化 | 交通安全 | |
| 組織強化(計画・実施・維持管理に向けた人材と設備面) | 交通事故の減少および道路安全管理体制の強化 ダッカ市等主要都市での歩道橋の建設 |
これら課題に具体的に応えるため、開発計画では以下の数値目標を掲げている。
- 毎年最低500kmの幹線道路の舗装
- 毎年200kmの接続道路の建設
また、早期の完成が望まれる主要橋梁として、アシュガンジのバリハブ橋、パドマ橋、クルナのルプシャ鉄道兼用橋が特定されている。
道路網の整備状況は以下のとおりである。90年代に入り地方道とFeeder-Aなど地方村落と地方都市間を結ぶ道路網の整備が進んでいることが判る。しかし舗装率については、その他末端の村落道路を含めても平均して50%近い舗装率を誇る他の南西アジア諸国と比較すると、随分遅れている状況にある。このため、農村開発分野における村落地域道路の整備との調整を図りながら、農村地域と主要幹線を繋ぐフィーダ道路の維持管理と質的向上(舗装)に取組むことが望まれる。
|
表6-3-8 道路総延長と舗装状況 (単位:km)
|
主要幹線道路などの整備に対して、現在までのところ民間セクターの参画は実現されていない。RHDでは現在3幹線の維持管理について民間セクターの参入を検討しているところであるが、民間の活用を円滑にする法的枠組みやインセンティブ供与の仕組み造りは未だ整備されていないのが現状である。
近年、都市部の交通渋滞が課題としてクローズアップされており、ダッカ東部バイパスの整備を始め対策も講じられている。しかし、道路セクターのみで対処できる課題ではなく、他の交通モードとの連携のうえ、包括的に都市交通改善に対策を講じる必要性に迫られている。
(2)空港
バングラデシュ国は面積が小さいこと、水上交通が発達していることもあり、航空輸送の役割は国内輸送需要の面から小さい。現在バングラデシュ国には、人口規模の割に2つの国際空港を含めて8つの空港しかない。空港セクターの開発課題は以下のとおりである。
| 空港施設の整備・拡充・質的向上 | |
| ダッカ・トリサル・チッタゴン・オスマニ国際空港の建設・改修 既存空港滑走路の拡張・改修 |
旅客・貨物需要対応のための旅客ターミナル施設拡充 ダッカ空港の第2滑走路の建設 国内航空サービス拡充に向けた新規国内空港の整備 |
空港セクターの課題は施設整備(フィジカル・デベロップメント)ベースの目標であるが、バングラデシュ国民の所得水準が向上し、航空移動が現在より魅力的な手段と認識されない限り、空港施設の役割は大きくならないであろう。但し、空港施設の整備には先行投資としての位置付けもあり係る状況から全国的な整備が進められている。
|
表6-3-9 空港利用乗客数および貨物量(単位:'000およびトン)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空港施設が扱う輸送量の推移は上表のとおりである。輸送量は旅客と貨物とも増加基調にある。但し、空港施設整備と併せて航空旅客および貨物輸送需要の一層の掘起しも求められる。そのためには、民間航空会社の国際線参入など航空輸送サービスの拡充と改善も必要である。
(3)港湾および内陸水運
港湾および水運セクターは、バングラデシュ国国内の人的および物資移動に重要な貢献をしているのみならず、2大港湾であるチッタゴンおよびモングラ港を通じて輸出入物資の窓口として、輸出の振興および促進に間接的に貢献している。港湾および水運セクターの開発課題は以下のとおりである。
| 港湾施設の整備・拡充・質的向上 | 港湾および水運機関の能力向上と民営化 | |
|
河川港、内水コンテナ港および倉庫施設の拡充整備 バックアップ設備を含めた新規コンテナ港の建設とコンテナ処理設備の調達 ドックヤード施設の最適利用の促進 チッタゴンの深海港整備に係る調査の実施 港湾運営(コンテナ)業務の効率化と質的向上 |
港湾・海運関係者向けの教育訓練の充実化と施設拡張および近代化 港湾業務の民営化促進に向けた制度の整備 |
|
| 水運ネットワークの整備・拡充 | その他 | |
| 農村部の汽艇用着岸施設の整備 離島向け海運サービスの拡充と着岸施設の整備 |
海運安全管理体制の構築 カントリーボート・サービスの機械化による改善 船舶用エンジンおよび部品の輸入関税緩和 |
下表は、チッタゴンおよびモングラ港の物資処理状況の推移である。船舶の港湾滞在日数は、堅調に改善していることが伺えるが、一方で寄港船舶数、輸出入量の伸びが停滞又は低下傾向にある。海上輸出入の約77%がチッタゴン港で扱われており、残りはモングラ港で扱われている。従って、チッタゴン港の輸出入物資処理能力の如何がバングラデシュ国の輸出振興および経済活動に大きく影響する。
|
表6-3-10 チッタゴンおよびモングラ港の物資処理状況
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チッタゴン港は遠浅の港である。その為港湾施設より大型船への物資運搬に運搬船を利用する必要があり、物資の処理能力に制約を与えていると認識されている。そして、この物資処理能力面での制約が、輸出促進に多大な制約を与えていると考えられる。第5次5ヵ年開発計画でも依然チッタゴン港の処理能力には改善と事業効率化の余地があると報告している。
主要ドナーであるADBは港湾セクターに対し、上記課題のなかでもとりわけ港湾事業の効率化を目的とした各種の制度改革を重要課題として着目している。商業ベースでの運営、民間セクターの参入、港湾事業の自主性を促進し得る政策提言を行い、政府側に改革への着手を求めている。
(4)電力およびエネルギー
電力不足はバングラデシュ国の経済成長と貧困の削減にとって重要な問題である。現在、僅か15%程度の人口が電力供給へのアクセスを有する程度である。電力供給事業の実施機関は、一部を除き低効率でありおよび高いシステムロスの問題を抱えている。電力およびエネルギー(天然ガス)セクターの開発課題は以下のとおりである。
| 電力供給施設の整備 | 民間セクターの活用 | |
| 既存施設の最大活用と発電能力の追加 送配電網の拡充 北西部における電力不足の解消 農村部への電力供給の拡充 |
電源開発への民間セクターの参画 | |
| サービスの改善 | その他 | |
| 信頼的かつ支障のない電力の供給 効率的システム運用による電力供給単価の低下 システム・ロスの低下 |
バイオマス・エネルギーなど再生可能エネルギーの利用促進 | |
| キャパシティ・ビルディング | ||
| 料金の改訂および良好な財務管理による責任機関の補助金依存からの脱却 実施機関の管理体制と技術能力の改善 |
バングラデシュ国電力供給事業は、都市部の発送配電を管轄する電力庁(BPDB)、一部地域の送電のみを管掌するバングラデシュ送電会社(PGCB)、ダッカ首都圏の配電を管掌するダッカ市配電公社(DESA)、農村部の電化事業を管掌する農村電化庁(REB)および農村電化向け発電事業会社である農村電力会社(RPC)により運営されている。DESAは管轄地域の一部の配電事業を更に新たな会社(DESCO)に委託している。なお、いくつかの民間事業者が発電事業に参入している。
下表はバングラデシュ国の発電量と消費量の推移である。発電容量の予備率から判断する限り、近年需要と供給が逼迫していることが判る。90年代を通じて政府は計画のとおり発電施設拡充(発電可能容量の増加)を果たせなかったことによる。これは、電力セクター改革の遅れに起因する資本的支出の資金協力が滞ったことと、実施機関の事業実施能力の不足が要因であると指摘されている。需給の逼迫は、消費量の成長率が発電量の成長率を大きく上回っていることからも伺える。電化家庭の割合が低いことも含め、発電施設の改修や増設を通じた供給体制の整備拡充は、依然重要課題とされている。
|
表6-3-11 バングラデシュ国全体の発電量と消費量の推移
|
需要家数については、BPDBの需要家数の伸びが90年代後半に入り鈍化している。これはBPDBの事業実施効率性と供給および顧客サービスの質の問題である。一方、REBは事業運営面とサービス面で比較的評価の高い機関であり、急激に需要家数を伸ばしている。電化組合の形成を通じた運営管理で料金徴収率も高く、上記開発課題に沿った電力事業運営が行われている。但し、一人当り電力消費量は依然低い水準にあり、電力セクターは今後も強い需要成長に対応する必要がある。
|
表6-3-12 需要家数と一人当りの消費量の推移 (単位:千人およびkWh)
|
需要への適切な対応と併せて重要な課題は、電力事業の効率化とサービスの質的改善である。BPDBは度重なる停電や電圧低下に見舞われ、大幅な改善はなされたものの依然高いシステムロスを記録し、料金徴収率の低さと相まって財務状況の悪化を招いている。この点で、ADBを始めドナー機関は、事業運営体制の効率化と歪みを排除した料金体系への見直しを含めて迅速なセクター改革を求めている。DESAも同様に非効率な事業運営と高いシステムロスという問題を抱え、停電時間などサービス内容にも改善の余地が大いにあると報告されている。
|
表6-3-13 システム・ロスおよび停電日数の推移 (単位:%)
備考:停電時間は年間値、BPDBのもの。 |
世銀やADBは我が国同様、電力セクターに対する主要ドナーであり、近年セクターの構造改革や政策の改善に重点を置いた支援を行っている。具体的には、電力およびガス料金の見直し(経済的水準への値上げ)、独占的構造のアンバンドリング(機能分割)化、配電事業の地域分割化、民間セクターの参入(配電運営管理、発電事業)などを提言している。
発電事業では既に数社の民間事業者が電力供給を行っている。発電容量の拡充では、民間セクターの果たした役割は大きく、2000年以降5年間で、既存容量の45%に当る1,400
MWがBOT/BOO方式で供給される。配電事業においても顧客向けサービス、検針・請求・料金徴収を含めた運営管理に民間セクターの参画が一部地域で導入されている。
(エネルギー:天然ガス)
発電用の主要燃料である天然ガスは、バングラデシュ国が豊富に抱える天然資源の一つであり、一方で貴重な外貨の獲得および節約手段でもある。但しエネルギー消費全体で視れば、薪など伝統的な燃料が約55%を占める。
しかし、天然ガスは森林保護などの観点からも、更にエネルギー源としての貢献が求められている資源である。工業および商業用エネルギーの供給源としては、天然ガスは現在70%を占めている、1980年時点の35%と比べて大幅に増加した。天然ガス・セクターの開発課題としては、以下が認識されている。
|
具体的に、政府は年平均10%のガス生産増を想定している。このため、既存のガス供給施設の改修と拡張、確認埋蔵量の増加に向けたガス田探査の実施が求められている。天然ガス・セクターでは、探査および生産事業に対する民間セクターの参入促進に向けた政策と環境の整備が進み、国際石油会社(IOCs)など民間事業者は既に活発な調査および生産供給活動を行っている。
ADBは天然ガス開発における民間セクターの役割を重視し、直接投資による支援からより民間セクターを呼び込むためのセクター改革と制度強化支援へのシフトを表明している。
|
表6-3-14 天然ガスの生産および消費量の推移
|
天然ガスの生産および消費量の推移は上表のとおりである。生産量は1997年度まで目標の年平均10%成長を達成できなかったが、1998年度は達成した。天然ガス開発には多くの不確実性が伴うため、安定的な供給可能量の確保は困難である。しかし、ガス供給インフラの整備や改修に投資を向け、送ガス容量の増加を図ることも可能であると指摘されている。
(5)通信
バングラデシュ国の開発計画において、通信セクターは比較的高い優先度を与えられている。情報伝達の機能が経済成長や貧困緩和に及ぼす影響を重要視していること、そして独立後の電話サービスの供給状況があまり芳しくないためである。2001年6月現在で、100人当りの固定電話台数は、0.87台(民間事業者分を含む)であり、近隣アジア諸国(インド:3.2、スリランカ:4.1、パキスタン:2.3台)に比べても非常に低い水準である。なお、政府は2002年度までに、100人当り1台を達成するとした計画目標を設定している。
通信サービスへの投資を拡大するため、政府は民間投資を呼び込む政策を掲げている。民間セクターによる通信サービスは、現在のところ農村での電話事業、携帯電話事業、ポケット・ベル事業などで見受けられる。固定電話事業については活発な民間参入が行われていないのが現状である。通信セクターの開発課題は以下のとおりである。
| 電話通信サービスの拡充および質的向上 | 民間セクターの活用促進および通信事業の効率化 | |
| 電話サービスのユニバーザル化 固定電話保有率(100人当り1台)の実現 国際通信回線と付属施設の拡充 EPZおよび工業団地地区に所属する全産業への電話接続の確保 電話通信サービスの質の向上 ソフトウェア輸出、情報産業に必要な通信網の整備 |
公共と民間部門の競争促進 民間部門の役割の増加 通信セクターへの外国直接投資の促進 通信規制委員会の機能強化 |
バングラデシュ国政府による通信事業は、電信電話庁(BTTB)、農村電話事業を行う民間事業者、その他携帯電話事業者などにより運営されている。BTTBはドナー機関より、その事業効率性の低さ、顧客サービスの悪化(積滞件数が2000年度現在で約20万件、平均の積滞期間は3~4年と言われている)、サービスの質の低さ、および腐敗体質を指摘されており、早急なセクターおよび実施機関の改革が求められている。
|
表6-3-15 電話サービスの質に関する指数(BTTB分)の推移
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定電話数の推移でセクターの開発状況を視る限り満足のできるものではない。一方、民間セクターの通信セクターにおける貢献度を示す公式な指標はないが、2002年1月には携帯電話サービス事業の最大手であるGrameen Phoneの契約携帯電話数が50万台を突破するなど、政府のリソースのみでは通信需要に対応できなくなっていることが現実化している。しかしながら、携帯電話を含めその他通信手段と民間セクターに如何なる位置付けと役割を通信網整備計画において求めているのかが明確にされていない。
|
表6-3-16 通信セクターの開発(全国規模)の推移
|
BTTBもサービスの質の向上を図り、将来の需要増加に対応する目的で、電話回線のデジタル化、回線交換機の自動化、国際回線交換機の拡充に取組んでいる。しかし、技術的な改善に限らず、民間への固定電話通信事業権の部分移譲を含め政策改善を通じ、民間資本と技術を活用しながら迅速にサービス拡充に取組む必要がある。
なお、通信関係の技術革新は非常に速いスピードで進んでいる。バングラデシュ国でも例えば電信サービスの役割は低下しており、一方でインターネットを始めとする大規模情報容量伝達手段の普及が進んでいる。新技術の導入や展開についても政府の果たす役割を必要最低限公益的な性格を持つ施設の拡充や市場環境や制度の整備に留め、民間セクターを大いに活用する方針が必要であろう。情報技術産業の育成と発展の基礎としても重要である。
6.3.4 我が国の経済インフラ整備への取組みと貢献
我が国の援助計画においても表明されている「投資促進、輸出振興に向けた経済インフラ整備」は、次の点で妥当性を有する。
- 経済インフラ整備は極めて低い水準で推移してきており、絶対量が不足していたこと
- 貧困緩和に向けた戦略として所得機会、資源、情報、人的ネットワークへのアクセス確保およびその改善が必要であったこと
- 経済成長の一要因である輸出や外国直接投資の振興には、電力/エネルギー、運輸、通信、港湾、空港などの経済インフラの整備と安定したサービス供給は不可欠であり、外国企業が見るバングラデシュ国の優位性や魅力を低賃金労働力以外にも創出する必要があったこと
なお、我が国援助計画では、ダッカ~チッタゴン、ダッカ~クルナ地域を成長センターとし、インフラ整備投資の重点充当先として掲げている。これはバングラデシュ国の主要課題である投資促進、輸出振興の観点からみても、ダッカおよびチッタゴン両地域はEPZおよび国際空港の保有地域であり、チッタゴンおよびクルナはバングラデシュ国の二大国際港湾に隣接する地域であることから妥当な判断であると言える。
(1)援助の実績と我が国援助のセクターへの貢献
(A)道路(橋梁)セクター
過去約10年間の我が国のバングラデシュ国道路・橋梁セクターへの取組みは、下表のとおりである。我が国は、主に橋梁整備に重点を置いており、運輸交通セクター全体でも橋梁整備が中心的な分野であり、かつ比重が高い。国家規模の橋梁建設のみならず、幹線道路結合のための橋梁建設、農村道路の橋梁建設にも支援を行っている。一方、バングラデシュ国幹線道路の建設、維持管理主体であるRHDには継続的に専門家が派遣され、維持管理体制の強化に係る技術協力を行っている。研修事業では、都市交通計画を中心とした内容の研修が提供されている。
| 道路ネットワークの整備・拡充・質的向上 | |
| 5幹線道路の国際規格レベルでの整備 | |
| 統合およびバランスの取れた幹線道路網の構築 | 村落道路橋整備計画(無償) |
| ダッカ東部バイパスと主要橋梁の完成 |
メグナ/メグナ・グムティ橋建設計画(無償) ジャムナ多目的橋建設事業(有償) パクシー橋建設事業およびE/S(有償) ルプシャ橋建設事業(開調・有償) |
| 既存幹線道路網の非結合部分の整備 |
地方道路簡易橋建設計画(無償) ジャムナ橋アクセス道路事業(有償) ダッカ・チッタゴン間幹線道路中小橋梁建設計画(無償) |
| 監督機関の強化 | |
| 組織強化(計画・実施・維持管理に向けた人材と設備面) | 専門家派遣および第3国研修 |
| 民間の参入と民間資金活用の促進 | |
| 交通安全 | |
道路橋梁分野への支援は、資金協力について言えば、産業、電力セクターに並ぶ我が国の主要支援分野である。世銀、ADBおよび他ドナー機関とは、道路セクターについて各機関の担当分野に関する分担がなされており、世銀やADBが幹線道路事業やフィーダ道路建設事業に注力する一方、我が国は橋梁建設への支援にほぼ特化している。ドナー間で効率的に最終的な政策目標に向かって協力が図られている事例となっている。
いうまでもなく、バングラデシュ国における橋梁整備の意義は計り知れないものである。次図のとおり国土は長大河川や小河川により四方分断され、ダッカ、チッタゴン、クルナの主要都市地域がそれぞれ孤立して位置し、北西部はとくに切り離された形で開発が遅れていた。
係る状況下、過去10年間あまり我が国は同じく次図に示す橋梁施設の建設を通じ、国家の物理的統合と物流、人的移動上のボトルネック解消に向けて支援を行ってきた。なお、我が国がこれまでに支援した橋梁整備事業は、先述の戦略上重点地域に対応するものであったこと、ジャムナ橋、メグナ・メグナグムティ橋、パクシー橋の3橋梁整備により、ダッカ~チッタゴン~クルナのバングラデシュ国3大都市が陸路で結ばれ、基盤道路網が確立されたことが判る。
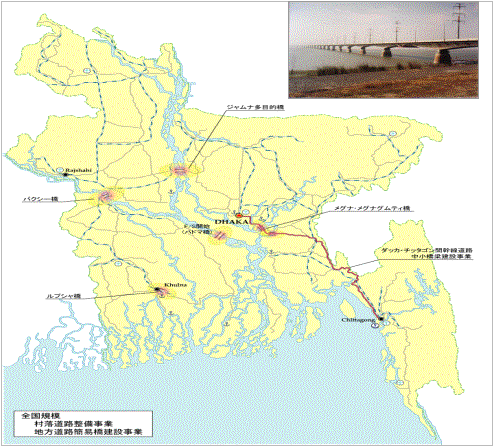
図6-3-1 我が国が支援した道路・橋梁整備事業の位置
国家的建設事業ではない、小規模橋梁整備事業についても、一定規模の洪水の度分断される道路を半永久的に結合するなど、住民の社会経済活動に係るリスクや取引および時間費用の軽減に貢献している。
バングラデシュ国の道路セクターが貧困緩和と経済成長のために果たすべき役割は、所得機会、資源、情報、人的ネットワークへの国民のアクセス確保およびその改善である。国民のアクセスビリティが改善している証として、輸送需要の安定した伸びが挙げられる。90年代に入り、陸上輸送需要の伸びは約3%の平均成長率で推移している。
この伸びを持続的に成長させるため、橋梁は主要幹線道路の高規格化、拡充整備と相まってボトルネックの解消と輸送キャパシティの拡大に貢献してきた。また我が国が橋梁整備支援を行った地域を個別的にみていくと、それぞれ以下の効果が確認されている。事後評価が完了していないその他橋梁整備事業にも同様の効果が期待できるものと考える。
| ジャムナ多目的橋 | 定量的効果
| ||||||||||||
| メグナ・メグナグムティ橋 | 定量的効果
| ||||||||||||
| ダッカ・チッタゴン間幹線道路 中小橋梁建設計画 |
上記メグナ・メグナグムティ橋の効果と同様と考えられる。当該区間はバングラデシュ国陸上輸送量の約30%が集中する最重要幹線である。 |
上表からも個別的にではあるが、国民のアクセスビリティ改善に橋梁整備事業が貢献していることが判る。
(B)空港セクター
|
チッタゴン国際 空港開発事業(有償) 
|
|
||||||||||||
セクター開発動向にて示したとおり、チッタゴン空港の貨物および旅客取扱い量は増加している。しかし、施設の稼働率は未だ充分ではない。チッタゴン空港には、現在チッタゴン~ダッカ間のフライトが毎日、コックスバザールへのフライトが週4日利用可能な他、国際線は当初計画と異なり、カルカッタ~チッタゴン間が週1便利用可能であるのみである。
なお、先述のとおり空港整備は先行投資的な性格が強いものであり、本事業は輸出振興、投資促進の目標に沿った海外とのゲートウェイ整備に相応しいものであるため、事業の妥当性に疑問は無い。しかし乗り入れ航空会社による需要の掘り起しが必要である。
また、チッタゴン空港整備が支援される前のバングラデシュ国の空路ゲートウェイはダッカのみであった。度重なる洪水や自然災害に見舞われる同国では、ダッカ空港が非常時の場合の物資輸送基地または旅客機の一時着陸場所としてチッタゴン国際空港を代替空港として利用できるようになった。整備前はインドのカルカッタ空港がその役割を担っていたことを考えるとバングラデシュ国の国益にも繋がるものと思料される。
(C)港湾/水運セクター
我が国の港湾/水運セクターへの取組みは、下表のとおりである。港湾ではバングラデシュ国の主要河川港の一つであるダッカ港開発事業に係るエンジニアリング・サービス(E/S)を支援した。港湾および水運セクターは、ADBを中心にほかドナーの継続的プレゼンスが確認されるセクターである。先述のとおりADBは下記課題のなかでもとりわけ港湾事業の運営効率化を目的とした組織制度および政策の改革に注力している。
| 港湾施設の整備・拡充・質的向上 | |
| 河川港、内水コンテナ港および倉庫施設の拡充整備 | |
| バックアップ設備を含めた新規コンテナ港の建設とコンテナ処理設備の調達 | ダッカ港開発事業E/S(有償) |
| ドックヤード施設の最適利用の促進 | |
| チッタゴンの深海港整備に係る調査の実施 | |
| 港湾運営(コンテナ)業務の効率化と質的向上 | ダッカ港コンテナ・ターミナル整備計画(開調) |
| 水運ネットワークの整備・拡充 | |
| 港湾および水運機関の能力向上と民営化 | 専門家派遣および本邦および第3国研修事業 |
我が国は上記E/Sの他、専門家派遣、本邦および第3国研修を通じ、港湾事業管理、運営近代化、船舶安全実務、航路標識に係る技術協力や研修を行っている。
港湾および水運セクターは、非効率な事業運営、度重なる労使のトラブルが指摘されており、港湾の荷役処理能力におけるボトルネックが、輸出振興と海外企業進出の障害になっているとの報告もある。海洋国である我が国は、港湾事業運営や港湾行政、船舶の運航管理などに関する経験や技術を充分蓄積している。我が国の経験を基にした総合的な技術協力支援によるセクター改善も一案であろう。
(D)電力/エネルギー・セクター
電力セクターは我が国の経済インフラ整備支援において最も重点を置いたセクターの一つであった。過去約10年間の我が国のバングラデシュ国電力セクターへの取組みは、下表のとおりである。その他経済インフラ・セクターと比較して、セクターの開発課題に満遍なく支援が提供されていることが特徴的である。この点からも電力セクター全体が我が国の重点的支援分野であることを裏付けている。
そのうち、新規発電施設の建設および既存発電施設の改修による発電容量の拡充が最も比重を占めている。また、専門家派遣や本邦および第3国研修事業を通じて、電力供給計画、発電設備の維持管理体制強化、本邦研修事業 電力セクター支援、火力発電技術、電力設備の効率的運用に係る技術協力が提供されており、これら技術協力の一部が資金協力と連携のうえ実施されているセクターでもある。
| 電力供給施設の整備 | |
| 既存施設の最大活用と発電能力の追加 | ガスタービン発電プラント建設事業(有償) シレット・コンバインド・サイクル発電所建設事業(有償) ハリプール発電所修復・拡張事業(有償) 発電船改修事業(有償) |
| 送配電網の拡充 | 配電網整備事業(有償) |
| 北西部における電力不足の解消 | |
| 農村部への電力供給の拡充 | 農村電化事業フェーズIV-CおよびV-A)(有償) 配電網拡充および効率化事業(有償) |
| サービスの改善 | |
| 信頼的かつ支障のない電力の供給 | |
| 効率的システム運用による電力供給単価の低下 | |
| システム・ロスの低下 | エネルギー部門構造調整借款(有償) 配電網拡充および効率化事業(有償) |
| キャパシティ・ビルディング | |
| 料金の改訂および良好な財務管理による責任機関の補助金依存からの脱却 | エネルギー部門構造調整借款(有償) |
| 実施機関の管理体制と技術能力の改善 | 専門家派遣および本邦および第3国研修事業 |
| 民間セクターの活用 | |
| その他(バイオマス・エネルギーなど再生可能エネルギーの利用促進) | |
(都市部への電力供給)
我が国の電力セクターへの支援により、計5カ所の発電所(うち2隻の発電船を含む)が建設され、その設備容量は1999年度時点で全国発電容量の約14%を占めるに至った。発電容量のシェアでみれば、我が国の貢献が多大なものであることが判るが、問題は実施機関側の運用状況と結果としてのサービス供給状況であった。需給バランス(容量ベース)は90年代を通じて非常に逼迫しており、度重なる停電に見舞われている。
逼迫した需給状況と度重なる停電は、結果的に需要家数の伸びを鈍化させている。実施機関のカスタマー・サービス(新規接続申請の受付、メインテナンスなど)のパフォーマンスと相まって、需要家数の増加は更に抑制され、最終的にバングラデシュ国一人当りの電力使用量を極めて低い水準に留めている。そして、我が国が電力セクターへの支援を通じて期待した効果は国民の電力サービスへのアクセスの拡大と利用増加による社会経済活動の活性化であった。
以上の問題は我が国支援にその原因が着せられるものではない。しかし、我が国が支援した5つの発電所のうち、3つが後に改修事業の対象となった事実を無視することはできない。改修融資に至った経緯は、火災など予期せぬ事象も含まれているが、リハビリ用の資金協力は本来で有れば最低限の維持管理支出で済むはずの財政負担を拡大させ、後に振り向けるべき資本投資に充当するのを妨げることに繋がる。
|
システムロス削減 パイロット事業(有償) 
|
我が国も係る環境の変化を受け、システム・ロス削減、ハリプール発電所修復・拡張事業にみられるソフト・コンポーネント支援の導入など実施機関のパフォーマンス改善に向けた取組みを併せた資本整備協力を始めており、望ましい方向にあると考えられる。
|
ハリプール発電所修復・拡張事業では、BPDBから分離した形でハリプール発電所事業ユニット(Strategic Business Unit:SBU)を設立し、調達、人事、運営面でBPDBより権限移譲を図り、独自の運営・維持管理計画の策定、サプライヤーとの直接的なスペアパーツなどの購買活動、新たなマネジメント委員会の設立、更にBPDBとの電力購買契約の締結を行うに至っている。
また発電所従業員の評価体系を構築し、他の介入無く人事運営を行っている。さらに9職務分野のQCサークルが形成され、5S運動の導入、ISO取得も行われた。結果的に同発電所の運営状況は極めて良好に転換し、従業員の動機付けや自尊心醸成にも貢献したと報告されている。特徴的なことは、このSBU立上げと初期運営支援に専門家派遣と研修業務の技術協力が連携し、発電所運営に関するソフト面支援がより強化されたことである。 |
バングラデシュ政府の報告では、SBUに対する支援を世銀、ADBおよびKfWらが進める電力セクター構造改革支援(独占的構造のアンバンドリング化、配電事業の地域分割化、民間セクターの参入)に対峙する改革支援手法として高く評価している。しかし、最終需要家向け電力料金の見直し(経済的水準への値上げ)、受益者負担の徹底、BPDB本体の構造的な財務状況は依然解決できる問題ではないため、更なるセクター改革の推進は必要不可欠であると認識される。
(農村部の電化)
農村電化事業を管轄するREBは事業運営面とサービス面で比較的評価の高い機関であり、急激に需要家数を伸ばしている。電化組合の形成を通じた運営管理を行い、料金徴収より独立採算ベースの運営を行う点が特徴である。REBはこれら組合に配電網整備に係る初期投資資金の支援を行い、電化組合は徴収料金により維持管理費を賄いながらREBからの資金支援に対する返済を行う。
電化組合とREBの間では、パフォーマンス・ターゲット・アグリーメント(PTA)が結ばれ、組合の配電ロス、料金回収、負荷率の改善などに対する目標値を毎年設定する。組合がこれら目標値を達成した際は、組合管理者や職員などへの給与増(逆もある)という形でインセンティブが働くシステムを構築している。このように健全な環境が整備されたうえで、REBは良好なパフォーマンスを示している。
料金徴収率は1999年度にて97%、システム・ロスは1998年度にて18%台を記録しており、どちらもBPDBとDESAより優れた数値を記録している。現在REBはDESAやBPDBが農村部にて有する変電および配電設備の引継ぎを行っており、顧客もREBに移譲されている。
我が国は1977年にUSAIDが策定した農村電化マスタープランの実施に協力する形で、継続的な資金協力を行っている。電化が部分的にてでもなされたタナ(郡に当る)は、全国486タナのうち424タナに上り、家庭需要家数は2001年11月現在で307万戸に及ぶ。設立された電化組合数は同じく67(1カ所当りの人口は約60万人)に及ぶ。うち我が国は、5つの組合設立および約40万戸の家庭電化に貢献し、世銀、USAIDに次ぐ3番目のドナーである。
農村電化の上位目標は、農村における社会経済活動を活発化させ、所得機会を増加させ、貧困の緩和に資することである。また、適切な家族計画の遂行にも貢献すると言われている。REBでは農村電化事業の社会経済インパクト調査を実施しており、電化が典型的な農村社会および経済に及ぼした変化と効果を評価している。評価結果によると以下の変化や効果が確認されている。
経済的な効果
社会的な効果
|
インパクト評価は、REBによる電化地域500世帯と未電化地域200世帯を対象としたサンプル調査であるが、評価結果で得られた傾向はバングラデシュ国全体の農村電化事業がもたらした一般的な効果や変化として考えられる。我が国が支援した農村電化事業の対象地域でも同様である。但し留意すべきことは、教育、保健衛生、市場機能、アクセス道路など、電化以外の要因が組合わさって電化の恩恵を増幅させている点である。電化と併せた統合的なBHNの充足が重要であり、はじめて変化がもたらされる環境が整備されると指摘されている。
(エネルギー:天然ガス)
天然ガス・セクターでは、世銀、ADB、USAIDなどのドナーによる支援が活発であり、天然ガス田の試探掘や採掘より、パイプラインおよび配管網建設、精製所の近代化、ガス・セクターの改革支援まで幅広く支援を提供している。我が国の当該セクターにおけるプレゼンスは小さいが、「自国天然ガス活用による石油代替促進」の課題に対し、1980年にバクラバード天然ガス開発事業(有償)に資金協力を行い、1994年には、チッタゴン地域で想定された供給不足に緊急対応する目的で、バクラバード天然ガス開発事業 II(同ガス田既存抗井の改修と新規抗井の掘削と抗井仕上げ)について資金協力を行っている。
(E)通信セクター
我が国の通信セクターにおける支援実績は以下のとおりである。電話通信網および通信容量の拡充、通信サービスの向上に対応した資金協力に焦点が当てられており、通信技術の変化への対応や最新技術の習得のため、研修事業による技術協力が提供されている。
| 電話通信サービスの拡充および質的向上 | |
| 固定電話保有率(100人当り1台)の実現 | 電気通信網拡充事業(有償) 大ダッカ圏電話網整備事業(有償) |
| 国際通信回線と付属施設の拡充 | 本邦研修 |
| EPZおよび工業団地地区に所属する全産業への電話接続の確保 | |
| 電話通信サービスの質の向上 | 電気通信網拡充事業(有償) 大ダッカ圏電話網整備事業(有償) 本邦研修 |
| ソフトウェア輸出、情報産業に必要な通信網の整備 | 第3国研修 |
| 民間セクターの活用促進および通信事業の効率化 | |
我が国は1990年前後にかけて都市部の電話/テレックス通信網およびダッカ首都圏における電話網整備事業を2フェーズに分け継続支援し、結果的に首都ダッカにおける43%の電話回線が我が国資金協力によって整備された。我が国の通信網整備支援により整備された通信容量は極めて短期間に消化され、バングラデシュ国のボトルネック解消、経済活動の活性化や円滑化に果たした効果は確認される。
但し、電話通信容量の整備量が潜在需要に追いつかない状況(積滞件数の存在)は、過去10年以上に亘って続いており、積滞件数は更に増加傾向にある。我が国の支援後、充分な余剰容量を保てる期間は生じていない。通話時の障害発生数についても大きな改善を示していない。
電話普及率については、我が国の支援期間の前後で、全国レベルで100人当り0.19台(1987年度)より0.22台(1992年度)に増加した。しかし、現時点で政府目標値である2002年までに100人当り1台の達成は固定電話のみでは困難であり、民間事業者が行っている携帯電話台数を含めれば到達している可能性がある。固定電話通信へのアクセス不足(一部の携帯事業のみ固定電話との通信が可能である)や通信信頼性の薄さは、経済活動の支障となっているものと考えられ、とりわけFAXなど視覚通信需要には支障があるものと思料される。
現時点では、我が国が公的資金によりバングラデシュ国の通信セクターを支援する分野は通信網の幹線部分など大規模な設備投資を要する部分、セクター改革および制度改革支援に限定されるものと考えられる。通信セクターで適用される技術の変化や革新の速度は、公的援助のスピードになじまない点も指摘される。携帯電話を始め民間通信事業者が積極的に市場参入しており、都市部固定電話事業を独占しているBTTBもその非効率性と低いサービスの質より、民間資金および民間の事業運営ノウハウの部分的な活用が求められている。
(2)援助実施上の問題点
バングラデシュ国の経済インフラ各セクターの実施事業にて多く視られる実施上の問題として以下が挙げられる。
運営、維持管理に係る予算措置と能力の不足
施設完成後の運営・維持管理費用を利用者から徴収する料金にて充当するもの、政府の経常予算から充当されるものを問わず、バングラデシュ国経済インフラ施設の維持管理に係る予算不足は主要な問題点として認識されている。
電力セクターでは、利用者料金が採算可能な料金設定より低めに設定されている。REBが管理する地域電化組合を除き、実施機関が財務上自立して事業運営を継続することは出来ない状況にある。政府補助金により実施機関の赤字が一部補填されているが、稼働中および老朽化した発送配電設備を経済的耐用期間で随時更新するに充分ではない。当初の資本的投資は、その規模から支援は依然必要であるが、メインテナンス費用はもちろんのこと後の耐用期間に応じた更新費用も、実施機関が内部留保により資金手当できることが望ましい。
経済合理的な料金への見直しの必要性を掲げる一方、実施機関は社会政策的に電力を供給する責務を負わされている。世銀などは、料金体系を見直し、分割化、民活化を推進して、経済自立性を追求する電力事業者の集合体へ変革させるよう構造改革を支援している。
我が国は改革の進捗に留意し支援内容を慎重に吟味しており、プロジェクト・レベルでも出来る限り事業運営能力の問題について言及するため、ソフト面を強化している。この点は他セクターでの支援においても習うべき点である。電力を公益財と位置付け社会政策的にその整備・供給を優先すべきか、ドナー方針に沿うべきか意見を積極的に表明すべきであると思料される。
同じく重点を置いてきた橋梁整備支援でも、メインテナンスに係る必要資金を確保できていない事例がある。メグナ・メグナグムティ橋では、料金所を委託運営する民間業者が国庫に納める金額に対し、一旦国庫収入とされた後、政府が各橋梁に対し配分するメインテナンス資金が非常に少額であり充分な資金を確保するに至っていない。維持管理の量的および質的な不足は、そのまま事業効果の発現状況に影響する。
道路および橋梁の維持管理体制の構築と予算措置は、支援開始前に必要不可欠な条件として確認し、料金徴収による維持管理が困難であれば、実施機関として必要な措置を講じるよう申し入れが望まれる。一方でバングラデシュ国の財政事情を踏まえ、よりメインテナンス・フリーに近い構造物とする、農村道路や橋梁では近隣住民の定期的な土木作業などで対応できるよう留意するなどの配慮が望まれる。
また、電力セクターの援助では実施機関側による技術的に適切な維持管理が成されていないことで、設備運用に支障を来した事例があった。通信セクターでは、回線施設自体は整備拡充されたものの、通話の障害発生率などサービスの質的向上がみられない事例がある。全般的に施設面の整備というハード面には関心を示すが、ソフト面の改善(質の良い公共サービスを提供するための仕組み-組織と制度-づくり)に対する意識が全般的に希薄であると指摘されている。
事業実施の準備段階に係る能力の不足
バングラデシュ政府の腐敗体質、有能な人材の不足、入札関連情報の漏洩や政治介入により調達、工事段階において適切かつ迅速な処理が行われないため、実施期間が大幅に遅延する場合がある。事業実施に当って必要となる関係機関との調整能力が不足している。
過度の依存体質
バングラデシュ国は援助に依存した国であることに違いないが、個別事業毎にもドナーやコンサルタントへの様々な依存が見受けられる。ドナーやコンサルタントが働きかけを起さない限り、事業が前進しない事例が多い。
社会や環境面への影響
我が国が過去10年あまりの間に支援した大規模なインフラ整備事業に、社会環境(住民移転を伴うもの)や自然環境への悪影響が指摘されたものはなかった。但し、今後も適切な対処と配慮が求められる。
習うべき好例として、ジャムナ多目的橋では、世銀の指針による住民移転行動計画を策定し、住民移転に係る新たな法律の整備、大規模な移転地整備、移転先での移転住民に対する生計向上支援、職業訓練、衛生普及活動が実施された。移転住民以外にも間接的に事業による環境変化に影響される住民も含めて対策が講じられた。係る配慮と対策の実施は、近隣住民や受益者からの真のサポートを得るうえで、かつ事業の持続性を確保するうえでも不可欠なものである。
以上述べた課題や成功の要因に帰着するものは、バングラデシュ政府のガバナンス能力、実施事業に対するオーナーシップの有無である。近年、世銀や欧州国ドナーはとりわけバングラデシュ国のガバナンスの改善とオーナーシップの醸成に関心を示している。
6.3.5 教訓と提言
食糧自給が実現され、肥料工業発展の黎明期を終えた現在は、国営管理と価格統制の妥当性は失われつつあり、今後国営企業向けへの支援は、緊急的なもの、改革支援、または制度改革を見据えたマネジメント・サポート的なものに限定されるべきである。
新たな輸出産業の多様化と育成、投資・輸出の振興策策定に関する支援が望まれる。バングラデシュ国では産業育成に向けた長期信用市場が未だ機能しておらず、円借款によるツーステップ・ローンの適用に向けた制度金融機関の育成も検討価値があろう。インフォーマルからフォーマル化への転換に向け、バングラデシュ国NGOによる中小企業金融を通じた支援が始動されている。当該分野に対する、資金協力も検討に値する。
経済インフラ分野において事業運営パフォーマンスが比較的良好であると評価されるREBおよびハリプール発電所は、自ら次の点が事業成功の主要因であると述べている。それらは、
- 実施機関の組織や人事面での他者からの介入を排除すること
- 事業方針に曖昧さがないこと(電化地域の一方的な拡充より、組合の財務的自立性が優先される)
- 関係職員らに昇給と減給のインセンティブが働いていること
- 計画策定、組織と制度の整備、事業の実施展開、モニタリング、評価までドナー(USAID、ハリプールの場合は我が国)が継続して支援を行っていること、であった。
先述した実施上の課題と併せて、今後経済インフラ整備への支援を行う際、これら要因の有無を把握し、適用または改善の可能性を検討することが望ましい。
経済インフラ分野においては、ガバナンスの弱さとオーナーシップの欠如が事業の円滑な実施や成果発現の障害となる事例が多い。バングラデシュ国がこのテーマに誠実に取組んでいる証として、政府の政策内容、法制度、組織体制、公共サービス提供に係るパフォーマンスの改革、改善にこれを求め、支援供与のコンディショナリティーとするドナーも存在する。
しかし、我が国は要請主義と相手国の自助努力重視を継続する以上、バングラデシュ政府の自尊心と慣習を阻害しない独自の方策を以って、インフラ整備支援に当る必要があると思料される。この点から今後以下の方策を協議のうえ講じていくことが望まれる。
- 従来以上にソフト面(組織や制度)での改善を促しうるコンポーネントをパッケージ化し供与する。ここで資金協力と技術協力スキームとの連携を一層充実させ、専門家派遣、研修事業、プロ技協など技術協力の一定部分を戦略的に資金援助が集中する重点分野、セクターに配分する(ハリプール発電所拡充事業がモデルとなろう)。
- ソフト面の改善コンポーネントの提供では、対象セクターの改革や政策の方向性と他ドナー機関が得た教訓や経験を踏まえ、充分に到達可能な目標を検討のうえ設定し、成果重視型の技術協力を展開する。
- かかる取組みをモデル化し継続的に改良と見直しを重ねながら、対象実施機関内の他地域、他部門、および他のインフラ・セクターや実施機関に展開を図る。
但し、ソフト・コンポーネントを組み合わせたプログラム的なアプローチでも、全体的なセクター・パフォーマンスの改善には限界がある場合も思料される。この場合は、世銀や他主要ドナーが行っているセクター改革支援構造調整融資などの進捗に歩調を合わせたうえでインフラ整備支援を行うなど、他ドナーとの協調やバングラデシュ政府への変革努力を促す必要がある。
さらに、経済インフラ分野では、民営化および民活化の動向に沿いながら支援内容を検討することが重要となる。これは電力/エネルギー、港湾、通信セクターにおいてとりわけ重要となる検討事項である。バングラデシュ政府や他ドナー機関とのセクター改革議論や調整会議に参加し、「誰が最も効率的にセクターの開発課題に応え、政府はどんな役割を果たし改革を進めるべきか」を検討する必要がある。
セクター改革の方向性次第では、我が国の支援内容も限られたものになることは止むを得ない。しかし、一方で我が国の経験を踏まえた上、独自のセクター開発課題への対応方策への理解と関心を求めることも必要である。


