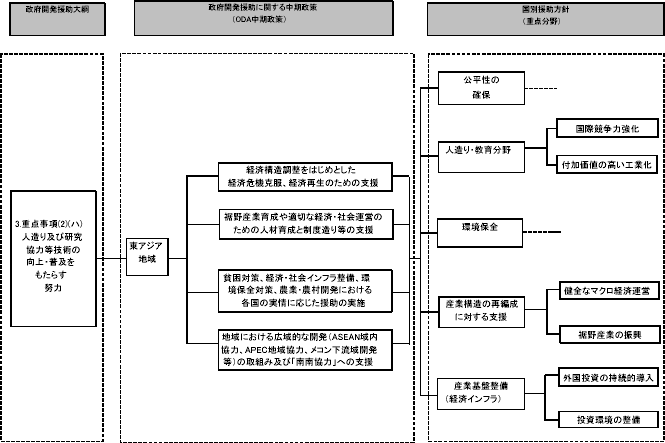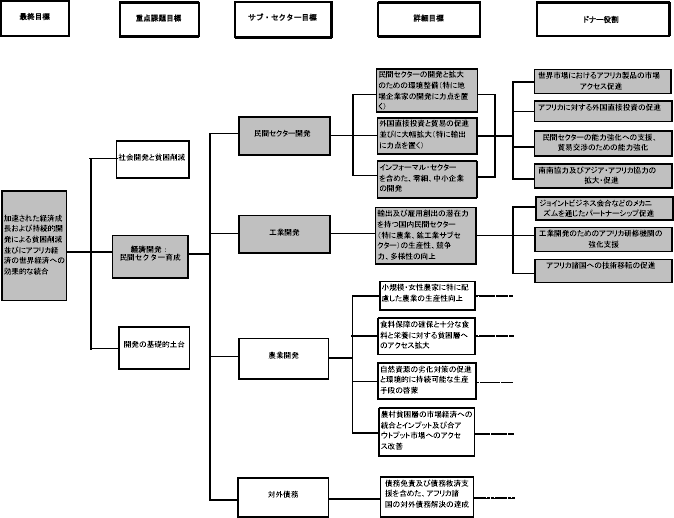|
(3)広域的な開発への取組み及び「南南協力」への支援に照らしたプログラムの目的の整合性
インドネシア政府は、TICADプロセスを通じた対アフリカ開発支援で日本政府と共催で「第1回アジア・アフリカフォーラム」*7をバンドンで開催し、「アジア・アフリカ協力のバンドン枠組み」を採択して以来、南南協力支援を実施してきた。その後JICAの協力を得て、第三国研修(対南アフリカ共和国)、AICAD調査団の受け入れ*8、インドネシアの農科大学にアフリカの研究者を5年間継続して招聘する支援を実施している。この他、アセアン域内協力として立ち上げられたCLMV協力会合*9への参加並びに日本、インドネシア、カンボジアの協力による対カンボジア研修の実施等の事例を挙げることができる。また、ブルネイの資金協力と日本政府の機材供与支援を経て設立された南南技術協力センター(NAM CSSTC)を拠点として、対アフリカ開発支援のプログラムが企画され、その具体化が進められている。
上述したインドネシアによる地域協力や、アジア・アフリカ協力への取組みは、アジアの地域協力あるいはアジア・アフリカ協力の活動に繋がる活動であり、我が国のプログラムの目的は、こうしたインドネシアによる広域的な開発や「南南協力」への支援に照らして、整合性を備えていたと思われる。
5-2-2 プログラムのプロセスについての評価
プロセスの実態については、アフリカの研修員受入と専門家派遣のプロセスの実態と大きな相違は認められないため、ここでは重複を避けるためプロセスの実態の記述を割愛した。但し、対アフリカ協力と比べ、インドネシアの経済発展段階の先進性や政府機構の整備、法制度の精緻の度合い等の背景から、我が国の貿易・投資分野協力に対する要請が極めて高く、協力分野が多岐にわたっている。例えば、我が国は、「貿易投資促進」、「投資促進政策」、「投資環境整備」、「輸出戦略」、「貿易保険」、「貿易金融」、「輸出市場戦略」、「国際貿易実務」、「物流」、「商社設立」、「国際商契約」等の研修テーマ、指導科目に基づいた研修員受入並びに専門家派遣を行っている。
(1)研修員受入のプロセスの検証
研修コース策定の適切性
案件策定のプロセス自体は対アフリカ協力の場合と相違はないが、対インドネシア貿易・投資分野協力においては、受益国政府並びに我が国関係省庁の関心が高いため協力案件にも多くの要望が寄せられている(外務省技術協力課聴き取り調査)。
割当国選定の適切性
割当国の選定に際しては、在外要望調査に基づき、関係者(受益国、在外公館、外務省本省、JICA在外事務所)間で、援助政策方針、目標、援助戦略等について協議を行なうが、どの程度協議を行ったかという問いに対して、JICA在外事務所からは、「年度毎の統一要望調査による協議を行い、また本邦からの調査団派遣により適宜実施している」との回答を得、在外公館の回答では、「月ベースで協議を行った」という回答を得た。
また、研修員の割当国の選定について、「インドネシアの国家開発計画(PROPENAS)等における貿易・投資ニーズを参照したか」という問いに関しては、在外公館とJICA在外事務所は共に「大いに考慮した」と回答している。また、他ドナーの援助活動との補完性と整合性に関しても、「大いに考慮した」、「ある程度考慮した」とそれぞれ回答を得ており、割当国選定について適切性が確認された。
研修員選考の適切性
研修員派遣機関は、研修員候補者の選考を、「従事している職務とその将来的ニーズとの関係性」を基準に行ったと回答している(貿易研修センター)。研修員派遣機関における組織内部的な選考の効率性については、研修員派遣機関(貿易研修センター、投資調整庁)の大部分の研修員OBは、「効率的であった」と回答している。しかし、投資調整庁の研修員OBから「非効率的」であったとの回答も見られる。その理由と具体的な障害として、「研修コース開設に関する情報が不透明であり、参加者の手元に届くのに時間がかかるため、意思決定するにはあまりにも時間が短すぎる」、「候補者選考に際しインタビューの機会を設けること」等のコメントが寄せられている。
研修運営の適切性
研修運営については、大多数の研修員OBが日本における研修運営の効率性や良好な研修環境を高く評価し、研修運営の適切性を確認した。但し、貿易研修センター研修員OBのコメントとして、「日本側は、インドネシアのニーズを必ずしも効率的に把握してない」、「遠隔地や後発地域にインドネシアの潜在的な研修コース受講への需要があるので、地方政府に直接協力ができないか」といったコメントを基に、ニーズ充足という観点から研修運営に関する改善点を指摘する要望も認められた。また、「もっと研修実施期間を短くし、基礎的な実務科目をカリキュラムに入れるべきではないか」とするコメントも寄せられている。
フォローアップの適切性
研修終了後、帰国してからのフォローアップ支援について、投資調整庁の研修員OBは「十分受けた」と回答している。一方、フォローアップを「受けなかった」との回答を寄せた投資調整庁の研修員OBも見られ、ばらつきが見られる。「受けなかった」とする貿易研修センター研修員OBが多数を占めるが、これは日本側からの直接的な情報提供等と理解しているためで、業務遂行に関しては常駐する長期・短期の専門家から助言・指導を受け、研修講師となった研修員OBが派遣専門家の研修コースに参加し、本来携わる業務に関する科目について知識の習得に努める等のフォローアップが行なわれている(貿易研修センターへの専門家)。
フォローアップ支援ニーズに関するコメントとして「研修コースに関する情報」(投資調整庁/研修員OB)、「日本の投資家、対インドネシア直接投資に関心を持つ投資家のリスト、日本で需要が高いインドネシア製品やサービスに関する情報」(投資調整庁/研修員OB)が必要であると回答している。
(2)専門家派遣のプロセスの検証
案件採否並びに実施案件形成の適切性
専門家派遣の案件採否については、統一要望調査を受けてから、在外公館、関係省庁等関係者を交えた協議がプロセスの最初の段階として位置付けられる。外務省経済協力局技術協力課によれば、専門家派遣の要請を受けて、受益国の貿易・投資分野ニーズについてもある程度検討されていることが確認された。また、受益国のニーズについては、アフリカの場合と同様、本省よりも在外公館の方がより多くの情報を持っているとの認識から、現地からの情報に依拠していることも確認された。案件選定から方針決定まで毎週ベースで協議を行なったとの回答も寄せられている(在外公館)。
また、専門家受入機関が受入ニーズについて、組織内で同僚や上司を交え議論を行ったか否かに関しては、貿易研修センター、コンベンション・ビューローから「活発に議論した」との回答を得ており、派遣要請側としても真剣に対処していたことが確認された。
専門家確保の適切性
専門家の選定については、案件採択後、外務省本省、在外公館、関係省庁、JICA本部の間で協議が行なわれ、受益国のニーズに合った候補者を選定する。JICA国内事業部によれば、「候補者が省庁推薦である場合、その推薦を受けJICAの責任で専門性・適格性を判断している」としている。また、貿易・投資分野協力における専門家は、民間企業や貿易投資関連の団体等における貿易投資実務の経験者が多いため、派遣専門家への応募も日本の貿易投資関連の企業・団体等からの紹介や推薦に基づく場合が多いことが確認された。
事前研修の適切性
事前研修に関するアンケート調査によれば、「ODAに関する研修は民間出身の専門家にとって大いに役立った」という理由で、事前研修を高く評価しているが、加えて、開発途上国援助・支援の国際的流れや中心的課題についての講義を希望している(投資調整庁ヘの専門家)。その一方で、赴任国の専門分野や事情についてもっと時間を割いて欲しいとの要望も出された(貿易研修センター、投資調整庁ヘの専門家)。初めて専門家が派遣された場合では、専門分野の時間割りは殆どなかったとの回答も見られる(コンベンション・ビューローヘの専門家)。
以上の専門家のコメントから、事前研修において専門家個々に対する極めの細かい研修内容の改善への期待がうかがえるが、事前研修の適切性については充分確認できた。
業務実施環境の適切性
専門家並びに専門家OBに対する聴き取り調査やアンケートによれば、インドネシアに関する豊富な情報が存在し、また継続的な協力が多いため、業務実施環境については概ね良好との回答が寄せられた(貿易研修センターヘの専門家、投資調整庁ヘの専門家)。逆に、初めて専門家を受け入れた場合では、受入機関側に専門分野についての知見がなく受入機関に対するオリエンテーションに多くの時間を割いたとしている(コンベンション・ビューローへの専門家)。少なくとも継続的な専門家派遣については充分適切性が確認された。
中間報告の適切性
中間報告に関しては、アフリカの場合とほぼ同様に、専門家が赴任後に作成する「業務実施方針書」に基づく途中経過報告の性格を有し、ほぼ四半期毎に作成され、JICA在外事務所へ提出されている。インドネシアでは、この報告書に基づき派遣専門家とJICA在外事務所との意思疎通が行われており、派遣専門家の業務の効果的・効率的な遂行の確認、改善・提言、派遣期間の検討等にも役立てられていることが確認された。(投資調整庁への専門家)。
最終報告の適切性
派遣専門家は、業務終了にあたり「総合報告書」を作成し、JICA在外事務所へ提出することが義務付けられている。外務省経済協力局技術協力課への聴き取り調査では、この総合報告書をJICA勉強会や専門家報告会等を通して入手し、次年度以降の協力を検討する際の資料として十分活用されていることが確認された。同様に受入機関にも提出されている(投資調整庁への専門家OB)。
5-2-3 プログラムの結果についての評価
(1)プログラムを通じた人材育成の有効性
インドネシア貿易研修センター運営支援を通じた、インドネシア人の幹部職員の研修運営能力の付与、インドネシア人研修講師育成を人材育成の有効性の1つとみなすことができる。貿易研修センターでは、同センター運営にかかる幹部職員の育成から、研修・教育事業に携わる講師の養成まで派遣専門家の助言・指導のもと「専門知識の付与並びにその知識の運用能力の向上」を果たし、研修員OBが講師として独立して授業実施が可能になった。受講者は開発課題で揚げる民間事業経営者や輸出担当者であり、研修・教育実施場所も地方展開を見せており着実な効果の広がりを検証した。
その他、アンケートの回答によれば、「貿易・投資促進における日本の人材育成協力でもっとも効果的な点は何か」という質問に対して「生産性向上と競争力強化」(インドネシア貿易研修センター/研修員OB)という回答を得た。投資調整庁研修員OBは、研修カリキュラムで強い印象を受けた点として、「寛容な態度や経済的思考を持っていること」、「理論的・実践的側面での日本の協力」、「マーケティング部門での協力」というコメントを寄せている。
(2)受益国における技術移転のインパクト
派遣専門家の回答によれば、赴任した政府機関の職員に対して、講義やセミナーを積極的に行なっていることが確認された(貿易研修センター、投資調整庁、コンベンション・ビューローへの専門家)。
貿易・投資分野協力を通した民間部門への技術移転については、JICA在外事務所は「十分行われている」という認識を示している。その理由として「インドネシア貿易研修センターにおいては、輸出促進に係る民間事業者向け研修が実施されている」という点を挙げている。研修コースで修得した知識の民間部門への伝達状況とその方法に関しては、具体的には、民間を対象とした研修、フォーラム、ワークショップ等の機会を通して研修で得た知識が民間部門へ移転されている状況が分かった。
専門家による協力では、投資促進のための情報や、日系企業に対する投資法制度に関する情報提供を通じ、我が国からの対インドネシア直接投資の促進等の面で、インパクトをもたらしていることが判明した。また、インドネシア国内での起業家の発掘による、国内投資の促進にも協力が進められている(投資調整庁への専門家)。
5-2-4 インドネシアに対する貿易・投資分野協力の総合評価
(1)プログラムの目的
インドネシアに対する貿易・投資分野協力は、インドネシア貿易研修センターの運営支援を通じた人材育成、知的支援の他、投資調整庁による国内外の投資促進が中心である。これまでの我が国のインドネシアに対する貿易・投資分野協力プログラムの目的は、ODA大綱、ODA
中期政策、さらに対インドネシア国別援助方針に示された我が国の援助政策体系に照らして妥当なものであったと言える。
受益国であるインドネシアの開発ニーズに照らした場合も、貿易・投資分野における人材育成という側面において、整合性を備えた協力であったと言える。特に、人材育成を主眼としたインドネシア貿易研修センターの運営に対する支援は、我が国の援助方針に照らして、極めて妥当性のある協力であったと言える。
また、インドネシアによる地域への開発努力や「南南協力」の取組みに照らした場合、我が国のインドネシアに対する貿易・投資分野プログラムの目的は、整合性を備えていると思われる。
(2)プログラムのプロセス
プロセスの検証では、インドネシアに対する貿易・投資分野での研修員受入と専門家派遣の実施プロセスについて、概ね適切性が検証された。但し、研修員受入の候補者選考の効率性に関しては、改善点も若干指摘されたが、受益国政府機関内の組織運用上の問題といえる。
一方、専門家派遣のプロセスでは、案件採否並びに実施案件形成に関して、適切性が検証された。また、中間報告書、総合報告書に関しては、JICA在外事務所との意思疎通や、次期専門家派遣への情報のフィードバックという点において適切なプロセスであったことが認められた。
(3)プログラムの結果
プログラムを通じた人材育成に関して、インドネシアの貿易研修センターでは、同センター運営にかかる幹部職員の育成から、研修・教育事業に携わる講師の養成まで派遣専門家の助言・指導のもと「専門知識の付与並びにその知識の運用能力の向上」を果たし、研修員OBが講師として独立して授業実施が可能になった。受講者は開発課題で揚げる地場の民間事業経営者や輸出担当者であり、研修・教育実施場所も地方展開をみせており有効性の着実な拡大が確認された。
また、プログラムを通じて受益国における民間部門へ技術移転のインパクトがもたらされたことも確認された。例えば、投資調整庁への派遣専門家は、地方の起業家発掘のため、投資調整庁地方部局(BKPMD)と協力し、数多くのセミナーや説明会を開催している。インドネシア語の投資促進のためのホームページにおいて、英語・日本語版のページを立ち上げ、投資促進関連機関、BKPMDをネットワークで結ぶことにより、投資機会の情報提供に貢献していることも確認された。
|
Box 5:インドネシア貿易研修センター(IETC)中間評価(概要)
経緯:
インドネシア貿易研修センター支援は、1985年の「日本・インドネシア技術協力年次協議における協力要請」から始まり、1986年「コンタクト調査団派遣」、1987年「事前調査団派遣」、「長期調査員派遣」を経て、1988年「実施協議調査団派遣」、「IETC事業実施協議調査団報告書」が作成された。プロジェクト技術協力方式として1989年からフェーズ1(1989~94年)、同フォローアップ(1994年~95年)を経て、本格的な研修・教育事業を軌道にのせるフェーズ2(1997年~2001年)終了時においてインドネシア側から評価の要請が出され、JICA本部で当該案件を採択し「中間評価」をインドネシアのコンサルタントに依頼して実施した。同報告書はJICA並びにインドネシア商工省、輸出振興庁に提出された。
評価結果の概要:
| 1. |
調査方法:卒業生140名をランダム抽出し、面談・アンケート質問票への回答の集計・分析 |
| 2. |
回答者の分析:回答者の分布―ジャカルタ、ボゴール、タンゲラン、ブカシからの参加。67%が学卒者。120社の内訳(外資系は6%、外資との合弁は6%、残り全てインドネシア資本)業種(ゴム、木工、繊維、農産品、その他) |
| 3. |
輸出の状況:67%の会社は輸出業に携わっている。その内半数は、売上げに占める輸出比率は25%。 |
| 4. |
研修参加の動機付け:半数以上は知識の修得・改善、24人は輸出増加を期待、18人は知識の自社への応用を期待。 |
| 5. |
カリキュラム:「輸出市場」のプログラムには大多数の参加者の関心が高い。また、「品質管理やビジネス・コミュニケーション」も人気のあるプログラムである。また、数人は「インターネット市場」プログラムに参加し、その内約4割は促進手段としてITを利用している。「企業経営」プログラムは、実務の支援にならず、人材不足を補完するものではない。 |
| 6. |
参加頻度:19%の会社は定期的に社員をIETC研修に派遣、他の半数以上は3~6月毎に派遣。 |
| 7. |
コメント:回答者の75%は、研修終了後、研修でえた知識を応用しており、多大のインパクトを受けたと回答。但し、応用の難しさ、理論と実務の乖離があり、IETCのプログラムは基礎的、一般的にすぎるとの回答もあり。 |
|
| *3 |
JICA年報2002年「東南アジア地域―重点課題と取り組み」:アセアンはかっては日本からの支援を一方的に受けていたが、現在は、第三国研修、第三国専門家派遣などを通じて、近隣諸国のみならずアフリカ等に対する南南協力を実施し、日本はこの推進を支援している。 |
| *4 |
我が国のインドネシアへの援助方針は、「インドネシア国別援助方針」によって定められている。国別援助方針よりも踏み込んで援助計画を定めた「国別援助計画」は未だ策定されていない。 |
| *5 |
なお、インドネシアは世界銀行、IMFの支援を経て、2002年に暫定貧困削減戦略ペーパー(I-PRSP)の策定に着手し、同ペーパーにおいて貿易・投資分野に関する政策や戦略を示しているが、その基礎となる計画等はGBHNやPROPENAS等に基づくとしている。 |
| *6 |
「PROPENAS」(National Development Program)2000~2004, BAPPENAS, 2000 |
| *7 |
1993年に開催された第1回アフリカ開発会議の翌年、TICADプロセスのフォローアップとして、日本政府並びにインドネシア政府の共催により、第1回アジア・アフリカフォーラム(AAF I)が開催された。AAF Iの「アジア・アフリカ協力のバンドン枠組」では、人的資源・制度開発、農業セクターの生産性向上、金融開発が提言分野として盛り込まれた。 |
| *8 |
AICAD: African Institute for Capacity Development(ケニア、タンザニア、ウガンダ3ヶ国が日本政府の支援をえて、ケニアに設立したアフリカ人造りの拠点でインドネシア側とは相互交流や調査団の往復を通して具体的な事業の策定中である(JICA在外事務所聴き取り調査)。 |
| *9 |
CLMV協力会合は、カンボジア(Cambodia)、ラオス(Lao)、ミャンマー(Myammer)、ヴィエトナム(Vietnam)の開発支援を行うための、我が国とアセアン諸国を交えた国際開発会合である。 |
|