1.4 国際機関との合同評価
国際機関との合同評価は、他のドナー国・国際機関と、双方の主要援助受取国におけるそれぞれの援助プロジェクトを対象に、共同で作業を行う評価です。評価視点の多角化、評価手法の向上などの視点から有益であり、OECD(経済協力開発機構)のDAC(開発援助委員会)の場で、実施が推奨されています。
|
1.Dfid:マラウイ・「前期初等学校プロジェクト(英国国際開発省プロジェクト)」(1999年度) 評価調査団: 牟田 博光 東京工業大学教授 ロバ-ト・デロウイン 外務省 田中 由美子 国際協力事業団 田中 千聖 国際協力事業団 武藤 小枝里 国際協力事業団 現地調査実施期間:1999年7月12~23日 |
■プロジェクトの目的
コミュニティ主体(住民参加型)の前期初等教育(小学校1年生から4年生まで)を改善するプロジェクトである。コミュニティ主体により実施・運営が可能で、かつ費用対効果の高いモデルの開発、ならびに、コミュニティ主体の学校運営を支援できる教育文化省のキャパシティビルディング、および両者のパートナーシップの構築を目的としている。
■評価結果
- (1)妥当性
学校施設建設にとどまらず、総合的、包括的な援助を行うことによって、教育の確実な質的向上をめざしている。マラウイの教育現状を踏まえ、女子児童の就学や成績・達成度の向上を図れるよう配慮している。 -
(2)目標達成度
建設計画フェーズI(1996~98)では10郡で30校、フェーズII(1998~99)では11郡で31校、フェーズIII(1998~2000)では11郡で35校を建設済/建設中である。 -
(3)効果
就学率の向上、質の改善に関するデ-タについては収集中である。フェ-ズIV(2000~01)ではチラズル郡でスクール・マッピングを実施予定である。 -
(4)効率性
学校施設建設や教材・教具購入において、コストの削減や維持管理費の捻出等についても配慮が見られる。フェーズI-IIIを経るにしたがって材質や工法を工夫し、同等の品質を保ちながら、建設単価を減少させる努力をしている。フェーズIIIの2教室1ブロックの建設単価は104米ドル/平方メートルにまで低下させている。 -
(5)自立発展性
先進国の基準から考えれば、建物の建設コストは最小限に抑えられているが、簡単な木枠に泥を塗っただけの付近の民家に比べれば、はるかに高価である。さらに、教育の質を維持するために学校開設に合わせて準備された豊富な教材も数年で消耗せざるを得ない。これらの学校を運営する維持費は住民の所得に比して高価である。現状では政府、ドナ-の支援無しには住民の自助努力だけでは施設・設備、教材の供給を維持できないのが実状である。
■提言
親の所得を高めるような他の社会開発プロジェクトなどの支援を得ずに、教育プロジェクトだけを実施することの限界を示している。プロジェクト期間が終って、英国が完全に手を引いた後の自助努力の状態については、関係者にさめた見方が多い。自助努力は被援助国の意識の問題であると同時に、それを可能にする経済的体力の問題でもある。経済水準に応じた援助のあり方、目標設定を考えなくてはならない。
|
2.タイ・「東北タイ大規模苗畑センター」及び「東北タイ造林普及計画」 (国連食糧農業機関(FAO)との合同評価)(1999年度) 評価調査団: 小林 英治 富士大学教授(現在下関市立大学教授) 加藤 正勝 FAO企画・予算・評価部評価課長 ダルモ・スパルモ FAOアジア太平洋事務所森林官 現地調査実施期間:2000年2月19日~28日 |
■プロジェクトの目的
東北タイでは森林の伐採が急速に進み、環境および住民の生活に悪影響が出てきた。このような状態を改善するために、政府は1988年より東北タイ緑化計画を策定するなどの 取組みを実施してきた。こうした流れを受けて、本件は植林を通じて当地域の環境の保全および貧困軽減を含む住民の生活向上を目的として実施された。
■評価結果
- (1)予定された4カ所の大規模苗畑センターが建設され、造林のための苗木の生産および配布に役立った。センターで生産された各種苗木のうち、合計8,940万本が燃料に使う木が不足している2,410村に配布された(達成率約9割)。
- (2)タイからの研修員受入れおよび専門家派遣が予定通り実行され、苗畑造成・植林・訓練技術などの移転が行われた。住民たちの訓練を行うために143のコースが準備され、約6千人(うち女性1,380人)が受講した。造林普及活動のために展示林が造成され、各種パンフレット類が作成・配布された。
- (3)造林普及活動により、東北タイ全体の約1割の村、特に燃料に当てる木が不足している村の41%が恩恵を受けた。経済的・社会的効果を判断するには時期尚早であるが、住民の造林活動の活発化や植林からの収入などに造林普及活動を通じた効果が出始めている。
■提言
- (1)今後住民参加によるコミュニティ・フォレストリー(村落林業)を通じて緑化活動を進めることが重要であり、住民の動機付け、訓練、造林普及活動などに一層取り組まねばならない。
- (2)特に造林普及活動は本計画中の弱点であり、タイ政府は造林普及活動を重点的に展開するために、予算・人員の措置をとる必要がある。
- (3)配布後の苗木のモニタリングを十分に行うことが必要である。
- (4)現地実施機関であるタイ王立森林局は造林活動を効果的に進めるために、他の政府機関やNGO等との連携を強化する必要がある。
- (5)苗木配布を一部有料化することで回収された費用を活用し、苗木の質およびサービスの向上させるとともに、センターの自立的発展を促すことが重要である。
■■外務省からの一言■■
本プロジェクトは、無償資金協力・プロジェクト方式技術協力・青年海外協力隊・NGO等が、それぞれの得意分野で有機的に連携し、数量で評価可能な実績を残した優良プロジェクトの一つと評価しています。植林の推進において国際パルプやキャッサバ市況の影響を受けたことや、植林樹種(ユーカリと郷土樹種)の問題があったものの、東北タイ地方において、4つのセンターの地域を中心に確実に効果が現れ始めています。
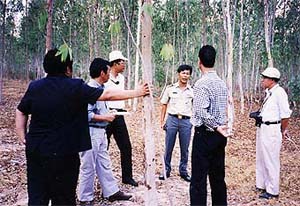
ユーカリ林の視察

