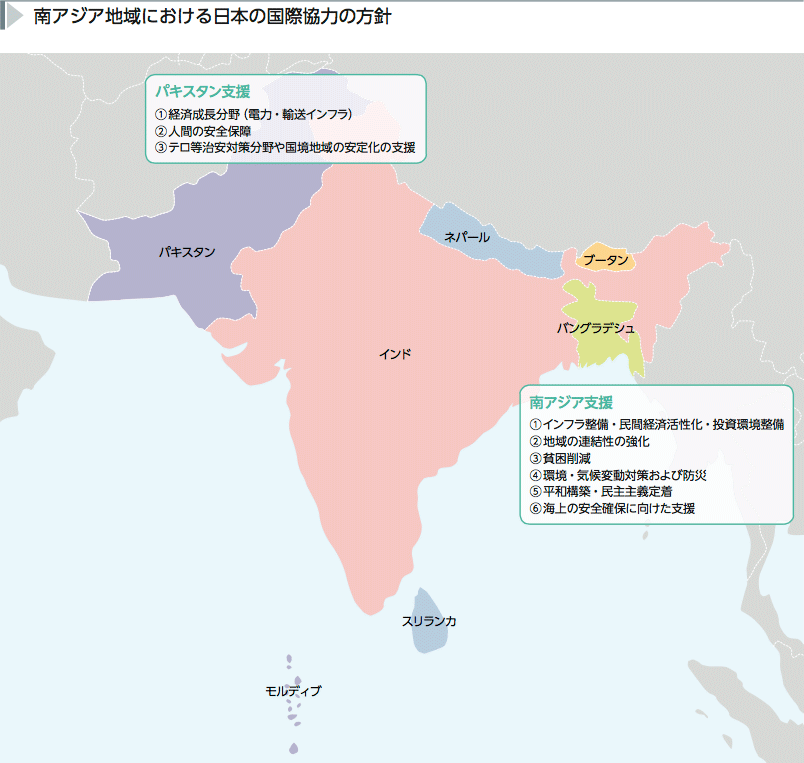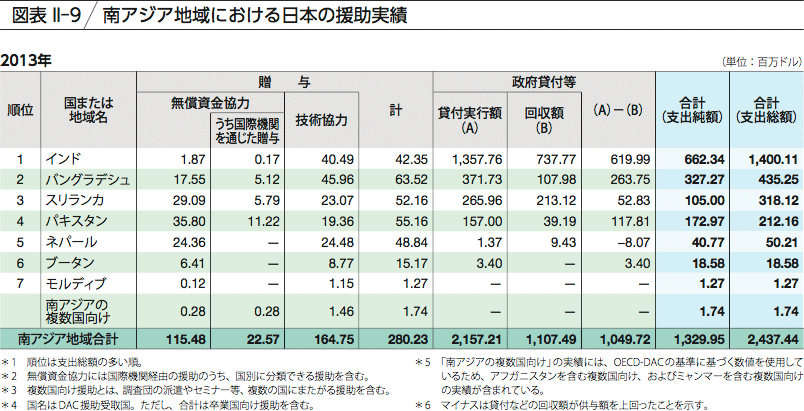2.南アジア地域
南アジア地域には、世界最大の民主主義国家であるインドをはじめとして、大きな経済的潜在力を有する国があり、国際社会における存在感を強めています。地理的には、東アジア地域と中東地域を結ぶ陸上・海上の交通路に位置し、日本にとって戦略的に重要であるほか、地球環境問題への対応という観点からも重要な地域です。また、テロおよび過激主義に対する国際的取組における役割といった観点からも、日本を含む国際社会にとって関心の高い地域です。
一方、南アジア地域には、道路、鉄道、港湾など基礎インフラの欠如、人口の増大、初等教育を受けていない児童の割合の高さ、水・衛生施設や保健・医療制度の未整備、不十分な母子保健、感染症、そして法の支配の未確立など取り組むべき課題が依然多く残されています。特に貧困の削減は大きな問題であり、この地域に住んでいる16億人に近い人口のうち約5億人が貧困層ともいわれ、世界でも貧しい地域の一つです。ミレニアム開発目標(MDGs)達成を目指す上でもアフリカに次いで重要な地域となっています。(注4)
日本は、南アジア地域の有する経済的な潜在力を活かすとともに、拡大しつつある貧富の格差をやわらげるため、経済社会インフラ整備の支援を重点的に行っています。
< 日本の取組 >

日本はBay of Bengal Industrial Growth Belt(BIG-B)構想を掲げ、今後のバングラデシュのテイクオフを支援する。バングラデシュ側からは「このときを長らく待っていた!」と感謝が述べられた(写真:佐々原秀史/在バングラデシュ日本大使館)

インドのデリー・メトロは総事業費の半分以上が日本の円借款によって賄われた。今では毎日200万人以上もの人々に利用される市民の足として定着している

アフガニスタン国境沿いからパキスタンの首都イスラマバード郊外に移住してきた避難民。幼い弟の面倒を見る少女(写真:新井さつき/在パキスタン日本大使館)
南アジア地域の中心的存在であるインドとは、「特別戦略的グローバル・パートナーシップ」に基づいて、デリー・ムンバイ間産業大動脈構想(DMIC)の中核となる貨物専用鉄道(DFC)建設計画などの経済協力をはじめ、政治・安全保障、経済、学術交流など幅広い分野で協力を進めています。インドは日本の円借款の最大の受取国であり、日本はインドにおいて電力や運輸などの経済インフラの整備等を支援しています。2014年9月のモディ首相訪日時の日印首脳会談において、今後5年以内に、日本の対インド直接投資とインド進出日系企業数の倍増という日印両国の共通目標を実現するために、インド側がビジネス環境のさらなる改善に向けて努力するのに合わせ、日本側からは、インドに対し今後5年間でODAを含む3.5兆円規模の官民投融資を実現するとの意図を表明しています。また、農村環境の整備など貧困削減に向けて社会分野での開発も進めています。
近年、発展が目覚ましく、日本企業の進出も増加しているバングラデシュとは、2014年3月の岸田外務大臣のバングラデシュ訪問、5月のハシナ首相の訪日および9月の安倍総理大臣のバングラデシュ訪問という一連の要人往来の中で、5月に「包括的パートナーシップ」が立ち上げられました。また、その際、2014年よりおおむね4年から5年を目途に、バングラデシュに対し、最大6,000億円の支援を実施する意図を表明しました。このような二国間関係強化の中で、①バングラデシュの経済インフラの開発、②投資環境の改善、および③連結性の向上を3本柱とする「ベンガル湾産業成長地帯(BIG-B)」構想を中心に、政策対話を強化し、経済協力を進めています。
2014年9月に安倍総理大臣が日本の総理大臣として24年ぶりに訪問したスリランカに対しては、両国間の海洋分野での協力を強化していくこと、ならびに、スリランカの国民和解の実現および2020年までの貧困からの脱却、中進国入りに向けた同国の取組を支援していくことを表明しています。幅広い分野で深化・拡大しつつある二国間関係を踏まえ、今後もスリランカの一層の経済発展とともに、進出している日系企業の活動環境の改善にも寄与する運輸・電力基盤などのインフラ整備の協力を行っていきます。また、同国の紛争の歴史や開発の現状を踏まえ、後発開発地域を対象に生計向上や農業分野を中心とした産業育成など、国民和解に役立つ協力および災害対策への支援を継続していきます。
パキスタンは、テロ撲滅に向けた国際社会の取組において重要な役割を担っており、アフガニスタンの安定にとり、パキスタンの協力は極めて重要です。これまで日本は、2009年4月に世界銀行と共に東京で開催したパキスタン支援国会合の際に表明した10億ドルの支援を実施したほか、テロ対策や防災等についても支援を実施しています。2013年6月に発足したシャリフ新政権は、経済・財政の立て直しや治安の改善を最優先課題として取り組んでおり、2013年9月、IMF理事会は、パキスタンに対する新規IMFプログラム(3年間、66.4億ドル)を承認しました。日本としてもパキスタンの改革努力を後押しするため、2014年6月には50億円の電力セクター改革プログラムローンを供与するなど、電力等の経済社会基盤(インフラ)整備および人間の安全保障の面で支援しています。
- 注4: 2014年のMDGsレポートによれば、1日約1.25ドル未満で生活する人の割合は30%(2010年)で、これはサブサハラ・アフリカに次いで高い数字である。
●バングラデシュ
自然災害に対応した公共建築物の建設・改修能力向上プロジェクト
技術協力プロジェクト(2011年3月~実施中)

構造実験試験体の損壊状況について説明するOYOインターナショナルの井上明専門家(写真:JICA)
サイクロンや洪水などが頻繁に発生するバングラデシュでは、地震災害のリスクも高いといわれています。しかし近年、大きな地震が発生していないため、耐震建築物はほとんどなく、マグニチュード6.5~7の地震が起こると、現存する建物の7割が倒壊するともいわれています。特に地震時に重要な機能を担う病院や消防署、学校、政府庁舎といった公共施設の耐震化は差し迫った課題です。
そこで、地震対策の分野で世界でもトップレベルにある日本の技術と経験を活かして、政府機関職員の耐震設計・施工能力や耐震改修に係る技術を向上させるための協力を実施しています。このプロジェクトでは、全国に5,000棟以上ある公共建築物の現況を把握するとともに、建築技術者の技術の習得や設計・施工の品質管理の確立、地震に強い建築方法の開発などに取り組んでいます。このプロジェクトは、バングラデシュの公共建築物の耐震化推進につながる支援といえます。
一方で、2013年4月、自然災害ではありませんが、ダッカ市内の9階建てのビルが突然崩れ落ち、入居していた縫製工場の労働者ら多数が命を落とす事故が起こりました。縫製産業は、同国の輸出額の約8割を占め、女性を中心に400万人が従事している重要な産業であり、その生産施設の安全性の強化は緊急の課題です。そこで日本政府は直ちに、このプロジェクトとタイアップして、縫製工場の耐震診断をして耐震補強工事や建て替え工事を行うための長期低金利融資を供与し、縫製工場の労働環境の安全性を高めるためのプログラムを立ち上げました。技術協力で能力強化を行った政府機関職員が縫製工場の耐震診断や改修設計を行い、さらに融資を通じて実際に建物に耐震対策を講じることにより、安全性の向上につながることが期待されます。(2014年8月時点)