国際協力の現場から 11
紛争が続く地で避難民の自立と地元住民との融和を支援
~アフリカ・スーダンでNGOが菜園づくり・井戸掘りに協力~
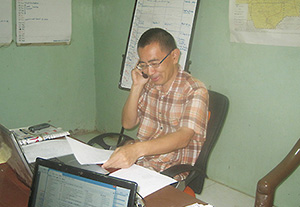
首都ハルツームにあるNGO事務所での今井さん。現地のスタッフと緊密に連絡をとりながら、支援を進めている(写真:JVC)
1956年の独立以来、長く続いてきたスーダン南北内戦は、2011年の南部独立によってようやく終結を見ました。しかし、その後もスーダンの一部では治安が安定せず、ダルフール、南コルドファンなどでは、今も200万人以上の国内避難民を抱えています。
国際協力NGO・日本国際ボランティアセンター(JVC)は、スーダンの南コルドファン州で2010年から避難民に対する支援活動を行ってきました。スーダン現地代表を務めている今井高樹(いまいたかき)さんは、安全上の理由で現在首都ハルツームを拠点としています。そして700km離れたカドグリ事務所のスーダン人スタッフ3名と連絡を取り合いながら南コルドファンでの活動を続けています。
カドグリは、「ヌバ山地」と呼ばれる丘陵地帯に囲まれ、丘陵地の裾野に沿って農村・牧畜地域が広がる土地です。住民たちは一年の半分を占める雨季に畑を耕し、残り半分の乾季には炭焼きや薪(たきぎ)拾いを行ったり、市内に働きに出て生計を立てています。
「戦闘地域からカドグリに逃れてきた避難民は約4万人。当初、私たちは避難民に対して食料などの人道支援を行っていました。やがて、活動を通じて避難民の生活状況を把握していくうちに、カドグリの地元住民に土地の一部を提供してもらい、避難民の生計確保のための菜園づくりができないかと考えるようになりました。避難民たちが同じ村の出身者や親戚(しんせき)を頼ってカドグリに避難していることもあって、地元住民側に受け入れようとする姿勢があったことが大きな助けになったと思います。」と今井さんはいいます。
とはいえ、土地の所有者はあくまでも地元住民なので、菜園づくりの用地をどこにすべきかは、地元住民と避難民双方のリーダーの間で話し合ってもらう必要がありました。「私たちの役割は、両者の関係を良くするための場所づくりだと認識しています。私たちは、その機会を提供しますが、話し合いそのものについては基本的に彼らに任せています。そうしたやり方を根気強く続けていると、自然に地域住民の中から、井戸掘りなどの地域の問題を話し合う場に、避難民グループを招いたりする動きが出てくるのです。」
話し合いの結果、一部の土地が避難民の畑に充てられることになり、2012年からは食料支援を取りやめ、避難民の自立支援のための雨季の耕作支援に切り替えました。さらに、避難民にとって、雨の降らない乾季の生計手段の確保が重要だということが分かり、2013年からは日本NGO連携無償資金協力※1の支援によって乾季の菜園づくりと井戸掘削(くっさく)・補修による小規模灌漑(かんがい)支援を開始しました。避難民たちは、簡単な研修を受け、モロヘイヤ、オクラ、ルッコラなどの野菜を作り、食料として利用し、さらに市場で売って収入源にすることを目標としました。収穫した野菜を家庭で調理し、子どもに食べさせたというある避難民が「これで毎日、朝起きたときに食べ物のことを心配する必要がなくなった。良かった。」としみじみ語ってくれたそうです。プロジェクトは様々な不安に苛まれてきた避難民たちに大きな安心を与えることができました。

紛争被災民の耕作再開を支援するため、種子を配布しているJVCのスタッフ(写真:JVC)
活動を進めるに当たって、避難民と地域住民の自発性と自立心が重要だったと今井さんはいいます。「放置されていた井戸の修理を住民たちが頼みに来たことがありました。こちらは、住民たちの側に自ら点検・補修する意思や計画があるように見えなかったので、要望に対してすぐにうんといわずに、様子を見続けました。すると、住民同士が少額を分担し合って井戸の補修をしたり、『大事な井戸は自分たちで管理しなくては』と井戸管理委員会を作って井戸の維持運営の準備を始めたのです。これにはこちらも驚きました。また、最初こちらから種や農具を支給して始まった菜園づくりでしたが、収穫が終わり、次の種蒔(ま)きの時期になっても、避難民たちは私たちのところに種をもらいに来るのではなく、自分たちで市場に行って新たに種を買って蒔いていました。スーダンの人々は、自分たちでできることは自分たちで、という意識がとても強いのです。」与えられた支援をいつのまにか自分たちで引き受けて、自ら動かしていこうとする南コルドファンの人たち。そんな彼らの姿を見るとき、今井さんはプロジェクトの成果を実感するといいます。
「生活再建を進める事業については、避難民と地域住民が協力しながら、一年を通じて安定的に生計手段を確保できるようになった段階が『出口』(外部からの支援の終了)だと考えています。間もなく、いくつかの集落ではこの段階に到達できると期待しています。」地元住民と良い関係の中で、避難民が自立的な生活を築けるよう今井さんは今日も奮闘を続けています。
※1 日本のNGOが開発途上国・地域で行う経済社会開発事業および緊急人道支援事業に対して外務省が資金協力を行う制度。これを受けたNGOが活動実績を積むことで、国際的活動を広げるという意味でNGOの能力強化も目的としている。
