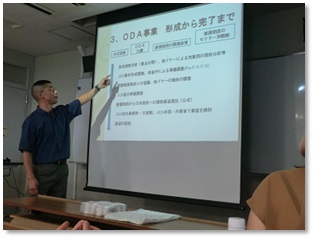第236回ODA出前講座 開催報告
~大阪大学~
2014年6月16日(月曜日),大阪大学に外務省国際協力局国別開発協力第1課の本田真一事務官を講師として派遣しました。今回の出前講座では,同大学人間科学部の3,4年生及び人間科学研究科修士1年生の27名を対象に「ODAの実態~霞ヶ関から現場まで~」というテーマで講義を行いました。
講義概要:「ODAの実態 ~霞ヶ関から現場まで~」
◆参加者からの感想(抜粋)◆
◆一般的なデータや定義,資料ではなく,実際に活動されたから分かるステークホルダーの考え方や実施プロセスの具体的な説明を聞けてとても興味深かったです。また,ODAを実施するにあたって人類学的な研究も必要であるというお話は一番意外でした。ODA=慈善事業,ボランティア,というイメージしか無かったのですが,ODAをやるにあたっては資金が必要で,「役に立つから」という理由だけでは動けないこともあるのだと分かりました。
◆現場,現実に即してお話いただいたので,途上国への援助は良い事であるとか,すべきことであるといった理想ではなく,リアルな現実を知ることができました。予算に限りがある中で,実際の援助と評価のバランスをどうとっていくのかという点が興味深かったです。最も効果的な方法と,各ステークホルダーに配慮した方法が異なることは多いでしょうし,そういったバランス感覚を保つのが大変なのではないかと思いました。
◆「援助」というよりも,「公共事業」であり,普通の企業のように利益というものを意識しているところに新たな視点を持った。
誰のための援助なのか?という批判はODAに対してあると思う。ODAは国益があるから,ある程度の見返りを期待して行われるものだとしたら,100%の純粋な援助というのは難しいのかと感じる。
誰のための援助なのか?という批判はODAに対してあると思う。ODAは国益があるから,ある程度の見返りを期待して行われるものだとしたら,100%の純粋な援助というのは難しいのかと感じる。
◆ODAのスキームが理解できた。ODAが多面的なものであること,単なる公共事業ではないというところがおもしろいなと思った。当事者観念を変えていくことが大変であるというところも興味深い。ODAの事業は事業の内容以外の部分での壁があることが分かった。言葉の壁や考え方の壁や時間の壁。それらをどう越えていくかで内容の成功に大きく関わってくるのだと分かった。
◆ODAは“開発援助”という名がついているのに,なぜステークホルダーの人たちは自分の利益を第1優先にしてしまうかという疑問がありましたが,今回のお話を聞いてODAの様々な側面を知り,少し理解できたような気がします。ODAがそもそも何なのか,また自分がそれに関わっていきたいときにどういった取り組み方があり,それぞれがどういった目的を持っているのかを知ることができました。様々なアクターがいる上に,皆異なる目的や価値観を持っているので,その人たち全員が合意して一つの方向を向いて進んでいくのは難しいことなのだと改めて実感することもできました。
◆ODA特に印象的だったのは,ただ“困っている人を援助すべき”と言うのは簡単だけれども,どう実現するのか,利益面も考える事が不可欠だと強調されていたことです。マクロとミクロ,両方の視点から考えることの必要性が分かりました。