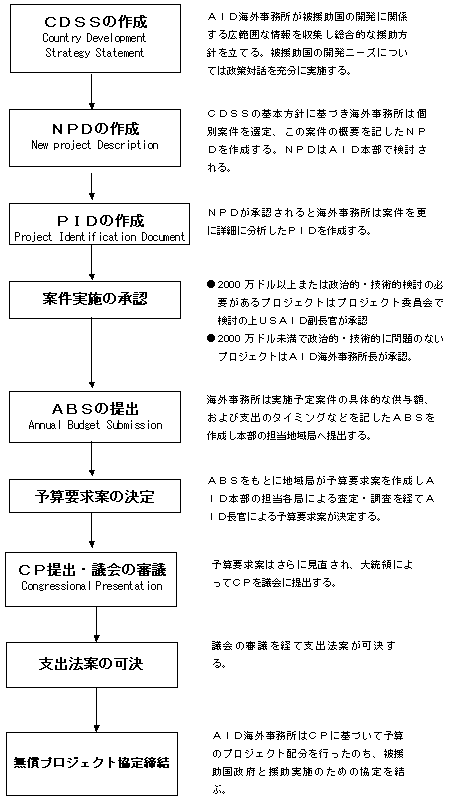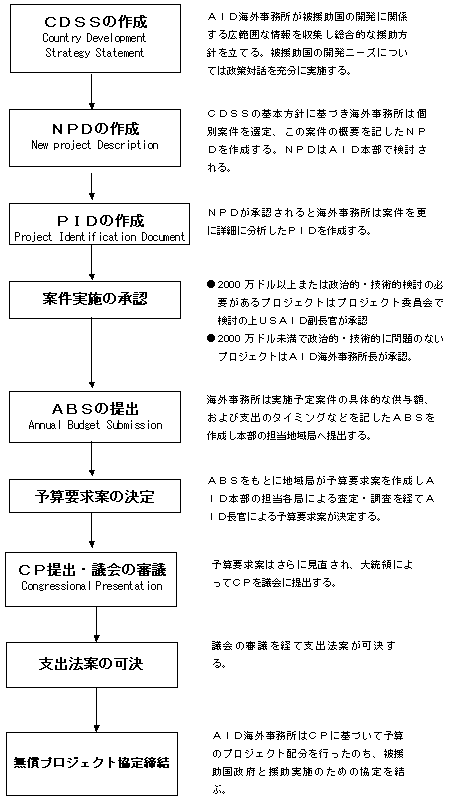「ODA総合戦略会議」傘下の「国別援助計画」の
策定に関する所見
(資料4)
| [1] | 国別援助計画策定のあり方
「第2次ODA改革懇談会」報告(平成14年3月末日)は、「現行の国別援助計画はわが国として取り組むべき重点分野を十分に絞り込んだものとはいえない」と国別援助計画の重点化を提言している。 それによると、第1に「ODA総合戦略会議」が地域・分野の専門家の知見を吸収し、国内関係諸機関とのネットワークを強化しながら国別重点分野を絞り込むとし、第2に、絞り込みに当たっては途上国側のニーズを十分に考慮し、主要な国際機関・援助国の国別援助戦略を研究し、わが国の比較優位分野を選択する、とある。 ODA予算の効率的、効果的な運用のためにも、「国別援助計画」策定委員会は「選択と集中」を実行すべく、ODA資金の分野別、形態別配分の重点化をきめる必要がある。このことは、上記提言のなかでこう述べている。 「国別援助計画の大胆な重点化を図る必要があるが、その際は、日本が技術力やノウハウの優位性を発揮できる分野に十分配慮し、日本の特徴や利点を生かすよう努めねばならない」。このことは従来の要請主義的な原則から"オファー方式"の導入を意味しているといえる。 |
| [2] | 「国別援助計画」にもとづく援助交渉とその推進がこれからの開発戦略の核心的部分になることが予想されるが、日本の場合、国別援助計画の策定による交渉が米国AIDのCountry Development Strategy Statement の内容に比べ劣っているといわれてきた(松井謙・東京国際大学教授、「国際開発ジャーナルOpinion」 1990/6)。
|
| [3] | USAIDのCountry Development Strategy Statement (CDSS) AIDは援助実施に際しては、CDSSの作成などの案件発掘の初期段階から相手国と十分な政策対話を行っているが、援助を実施する側が進めている構造調整、市場経済化などの開発政策を被援助国に選択するように、かなり強く勧めている。 この観点からは援助国主導の援助であるということができる。しかしながら、アメリカとしても被援助国の要請は、遅くとも最終的に案件の実施を事務的に決定する際には公式な要請を入手することにしている。 CDSSの内容に踏み込むと、第1に、当該被援助国への「USAIDの援助戦略」を明示する。たとえば、市場経済化を支援する一環として、経済の生産性向上を成長戦略として定めると、その基本方針を定め、生産性を増加させる分野を決める。たとえば、(1)農業と民間企業、(2)生産性改善に必要なサービス・インフラストラクチャー、(3)地方の開発、(4)教育と訓練など。 第2に、政策協議プロセスの支援。 第3に、主要分野における生産性向上に対する支援を決める。たとえば、農業分野、インフラ分野、上下水道分野。 第4に、民間ボランティア組織と連携する計画立案をする。 |
第I章 アメリカの援助と無償資金協力(89年)
図1―(8) アメリカの援助案件の発掘から実施までのプロセス